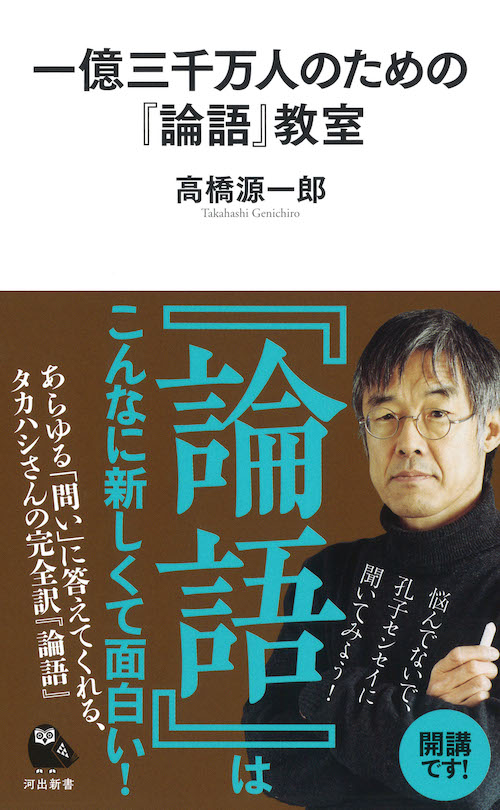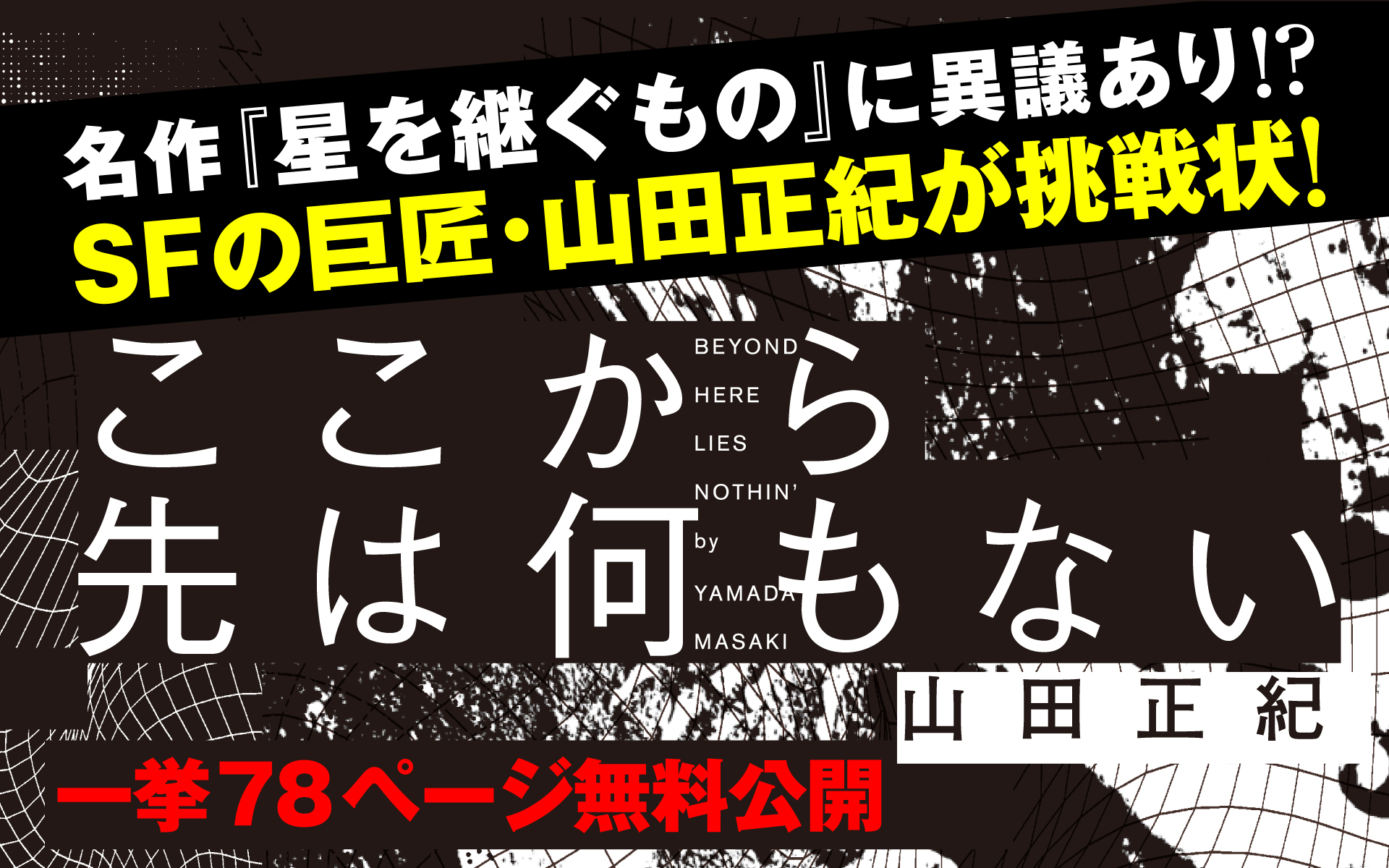文庫 - 日本文学
『論語』はこんなにも感動的だった! 物語でわかる論語の世界 『論語物語』より「 伯牛疾あり 」
下村湖人
2020.11.10
『次郎物語』の著者として知られる下村湖人は、生涯をかけて『論語』を学び続ける中で、『論語』にある孔子の言葉を、短い物語に仕立てました。そうして出来上がった『論語物語』(河出文庫)には、熱心な教育学者でもあった下村湖人と、孔子による弟子への人間味あふれた熱情が組合わさり、歴史に残る「座右の書」が生まれたのです。
今回は『論語物語』(河出文庫)刊行に際しまして、この感動的な物語を現代の皆様にお届けすべく、収録された28話の中から、5話を連続で公開します。
続きは、文字が大きく読みやすい河出文庫版でお楽しみください。
* * *
伯牛疾あり
冉伯牛の病気は、いよいよ癩病の徴候をあらわして来た。顔も、手も、表面がかさかさになり、全体にむくみあがって、むらさき色がかった肉が、皮膚の下から、今にも渋柿のようにくずれ出そうである。
このごろは、訪ねてくれる友人もほとんど無い。彼自身でも、人に顔を見られたくはないので、その方が気は楽だが、一方では、やるせのない淋しさが、秋の水のように心の底にしみて来る。そして、その淋しさの奥には、人間に対する呪詛が、いつもどす黒く渦を巻いているのである。
ことに、天気のよい日など、病室の窓から、あまりにも美しい日光が、燦々と木の葉にふりそそいでいるのを見ると、天地ことごとくが、自分に対して無慈悲なように思えてならない。
(澄みきった日光の下で、生きながら腐爛して行く人間の肉体! 何という自然の悪意だろう。こんな悪意にみちた自然の中で、人間の心だけが、素直に育って行こう道理がない。)
彼はすぐそんなことを考えて、眼を暗い部屋の隅に転ずるのである。
しかし、自分の病気の正体を知った当座のおどろきにくらべると、これでも、彼の心は平静にかえった方である。その当座は、悲しいとか、怨めしいとかいうのをとおり越して、何の判断力もなく、まるでからくり人形のように、家の中をうろつきまわったものである。自殺しようとしたことも、幾度となくあった。しかもそれは、あとで考えると、全く無意識的な発作に過ぎなかったようである。
かように、ほとんど絶望そのものになりきっていた彼が、ともかくも、悲しんだり、怨んだりするだけの人間らしさを取りもどしたのは、まったく孔子のお蔭である。
孔子は、おりおり彼をたずねて来ては、慰めたり、叱ったり、いろいろの教訓を与えたりした。しかし、もっとも多く孔子が口にしたのは、一緒に諸国を遍歴して嘗めた労苦のおもい出、とりわけ、陳蔡の野に飢えたおりのことであった。伯牛にとっては、こうした過去の物語が、何にもましてなつかしかった。単なる慰藉や、叱責や、教訓などでは、どうにもならなかった彼も、一緒に旅に出て難儀をしたころのことが、しみじみと孔子自身の口から談られるのを聴いていると、次第に人心地がつき、生への執着が、水滴のように彼の心の中に滴りはじめるのだった。
それと同時に、彼の理性もそろそろと甦って来た。そして、このごろでは、どうしたら悲みや怨みに打ち克つことが出来るのか、どうしたら自分の悪疾を気にしないで、以前のとおり落ちついた心で道に精進することが出来るのか、また、どうしたら生死を超越することが出来るのか、そうしたことに心を悩ますまでになったのである。
(自分は、徳行においては、顔淵、閔子騫、仲弓などとならび称せられ、自分でも、内心それを得意にしていたものだが、今から考えると、自分の徳行なんか、まるで寄木細工見たいなものに過ぎなかった。その証拠には、一寸した障碍にぶっつかると、すぐばらばらに壊されてしまうのだ。病気や運命に負けるような徳行が、何の徳行だ。──
(それにつけても思い出すのは、陳蔡の野でみんなが苦しんだ時に、先生の云われた言葉だ。
「君子も固より窮することがある。だが、小人と異るところは、窮しても濫れないことだ。」(「陳蔡の野」参照)
と。そうだ、どんな場合にも濫れない人であってこそ、真に徳行の人ということが出来るのだ。しかし、その力はどこから出て来るのか。──
(また、いつだったか、先生は、
「大軍の主将といえども、生擒にされないことはない。しかし、微々たる田夫野人でも、その操守を奪い取ることは出来ない。」
と云われた。何というすばらしい言葉だろう。病気ぐらいでとりみだしている自分の心が恥かしい。しかし、その堅固な操守の根本の力となるものは何だ。自分にはそれがわからないのだ。自分はこれまで、そうした根本的なものを掴むことを怠って、ただ先生や先輩の言動だけを、形式的に真似ていたに過ぎなかったのではなかったか。──)
こうした反省をつづけている間の彼は、さほど不幸ではなかった。考えの解決はつかなくても、やはり彼の心には、人間らしいある明るさがあった。少くとも、その間だけは、腐爛して行く自分の肉体を忘れることが出来た。しかし、からだを動かした拍子に、痛みで皮膚の感覚が、眼をさますと、彼はすぐ自分の手を見つめた。それから、その手をそっと顔にあてて、指先で、用心ぶかく眉や鼻のあたりを探った。そして、そのあとで彼の心を支配するものは、いつも戦慄と、萎縮と、猜疑と、呪詛とであった。
どうしたわけか、今日はとりわけ朝から彼の心が落ちつかない。友人たちに対する邪推が、それからそれへと深まって行く。
(みんなが寄りつかないのは、きっと自分の病気を恐がっているからだ。そのくせ、病人の気持を察して、などと、いかにも思いやりのあるようなことを、おたがいに云いあっているのだろう。あいつらには、先生のいつも仰しゃる「恕」とか、「己の欲せざるところを人に施してはならない」とかいうことが、恐らく、こんな時にだけ役に立つのだ。)
そんな皮肉な考えが、自然に彼の頭に浮んで来る。そして、そのあげくには、孔子だって、本音を洗って見たら、どんなものだか知れたものではない、といったようなことまで考える。
(そういえば、先生も、もうそろそろ一カ月ちかくも顔を見せられない。考えて見ると、自分の顔全体が変にくずれ出したのは、この前お会いしたころからのことだ。いよいよ先生も逃げ腰だな。──
「冬になって見ると、どれがほんとうの常盤樹だかわかる。ふだんは、どの木も一様に青い色をしているが。」
などと、よく先生は鹿爪らしい顔をして云っておられたものだが、さて先生ご自身は、果してその常盤樹といえるかな。聖人と云われるほどの人の正体も、今度という今度は、はっきりわかるわけだ。それも、自分がこんな病気になったお蔭かも知れない。)
伯牛は、眉も睫毛もない、むくんだ顔を、気味わるくゆがめて、皮肉な笑いをもらしたが、笑ったあとで、たまらなく不愉快な気 気持になった。何だか、孔子という人間一人の化の皮をはぐために、自分が犠牲にでもなっているような気がしてならなかったのである。
(孔子一人のために、これまでも、われわれはどれほど苦しんで来たことだろう。それに、こんな病気にまでなって、その正体を見究めなければならないのか。孔子という人間は、それほど人に犠牲を要求する価値のある人間なのか。)
彼は、そんな飛んでもないことまで考えて、まるで気でも狂ったようになっていた。
「先生がお見舞い下さいました。」
と、その時、だしぬけに召使いが戸口に立って云った。
伯牛はぎくりとした。そして、悪夢からさめたあとのように、しばらく天井を凝視した。それから、急にあわてて、一たんは臥床の上に起きあがったが、すぐまた横になって、頭からすっぽりと夜着をかぶってしまった。夜着は肩のあたりでかすかにふるえていた。
「こちらにお通しいたしましても、よろしゅうございましょうか。」
召使いは、一歩臥床に近づきながら云った。
返事がない。
召使いは、しばらく首をかしげて思案していたが、独りで何かうなずきながら、そのまま部屋を出て、しずかに戸をしめた。
五六分が過ぎた。その間伯牛は、夜着の下でふるえつづけていた。すると、だしぬけに窓の外から孔子の声がきこえた。
「伯牛、わしは強いてお前の顔を見ようとは云わぬ。せめて声だけでも聞きたいと思って、久々でやって来たのじゃ。」
「…………」
「このごろ工合はどうじゃ。やはりすぐれないかの。だが、心だけは安らかに持つがいい。心が安らかでないのは、君子の恥じゃ。」
「先生、お……お……お許しを願います。」
伯牛は、むせぶように夜着の中から云った。
「いや、そのままで結構じゃ。お前の気持は、わしにもよくわかる。人に不快な思いをさせまいとするその気持は、正しいとさえ云えるのじゃ。しかし、……」
と、孔子は一寸間をおいて、
「万一にも、お前がその病気を恥じて、顔をかくしているとすると、それは正しいとは云えない。お前の病気は天命じゃ。天命は天命のままに受取って、しずかに忍従するところに道がある。しかも、それこそ大きな道じゃ。そして、その道を歩む者のみが、真に、知仁勇の徳を完成して、惑いも、憂いも、懼れもない心境を開拓することが出来るのじゃ。」
伯牛は嗚咽した。その声は、窓のそとに立っている孔子の耳にも、はっきり聞えた。
「伯牛、手をお出し。」
孔子は、そう云って、自分の右手を、窓からぐっと突き入れた。彼の顔は、窓枠の上にかくれて、内側からはちっとも見えない。
伯牛の、象の皮膚のようにざらざらした手が、怯えるように、夜着の中からそろそろとのぞき出た。孔子の手は、いつの間にか、それをしっかりと握っていた。
夜着の中からは、ふたたび絶え入るような嗚咽の声がきこえた。
「伯牛、おたがいに世を終るのも、そう遠くはあるまい。くれぐれも心を安らかに持ちたいものじゃ。」
孔子は、そう云って、伯牛の手を放すと、しずかに歩をうつして門外に出た。そして、いくたびか従者をかえりみて嘆息した。
「天命じゃ。天命じゃ。しかし、あれほどの人物が、こんな病気にかかるとは、何というむごたらしいことだろう。」
伯牛が、雨にぬれた毒茸のような顔を、そっと夜着から出したのは、それから小半時もたってからのことであった。彼は、全身ににじんだ汗を、用心深く拭きとりながら、臥床の上に坐った。悔恨の心の底に、何か知ら、すがすがしいものが流れているのを、彼は感じていた。
「朝に道を聞けば夕に死んでも悔いない。」といった、嘗ての孔子の意義ふかい言葉が、しみじみと思い出された。
(永遠は現在の一瞬にある。刻下に道に生きる心こそ、生死を乗りこえて永遠に生きる心なのだ。)
彼はそう思った。
(天命、──そうだ。一切は天命だ。病める者も、健やかなる者も、おしなべて一つの大いなる天命に抱かれて生きている。天は全一だ。天の心には自他の区別はない。況んや悪意をやだ。天はただその歩むべき道をひたすらに歩むのだ。そして、この天命を深く噛みしめる者のみが、刻下に道に生きることが出来るのだ。)
彼は、孔子の心を、今こそはっきりと知ることが出来た。そして、さっき孔子に握りしめられた自分の手を、いつまでもいつまでも、見つめていた。
彼の心は無限に静かで、明るかった。彼にはもう、自分の肉体の醜さを恥じる気持など、微塵も残っていなかった。彼は、いつ死んでもいいような気にすらなって、恍惚として褥の上に坐っていた。
* * *

下村湖人『論語物語』(河出文庫)*11月6日発売!
*文庫版には該当箇所の原文も掲載されております。
また本文中、今日の観点から見て差別的と受け取られかねない表現がありますが、作品発表時の時代的背景を考慮し、原文通りといたしました。