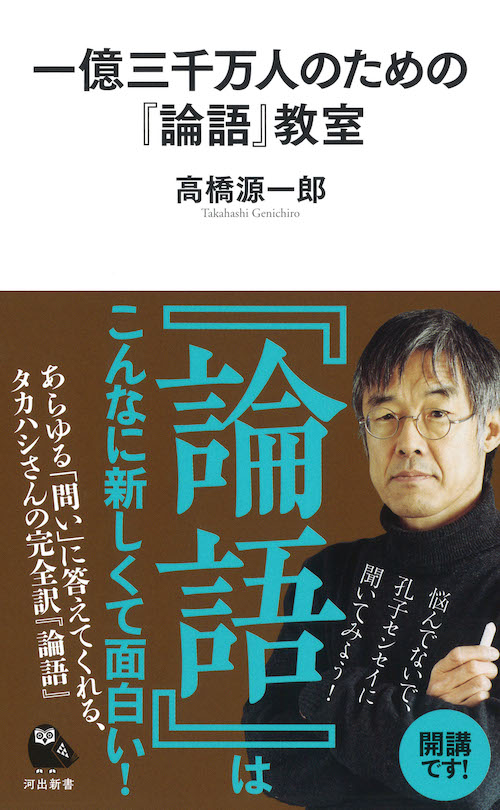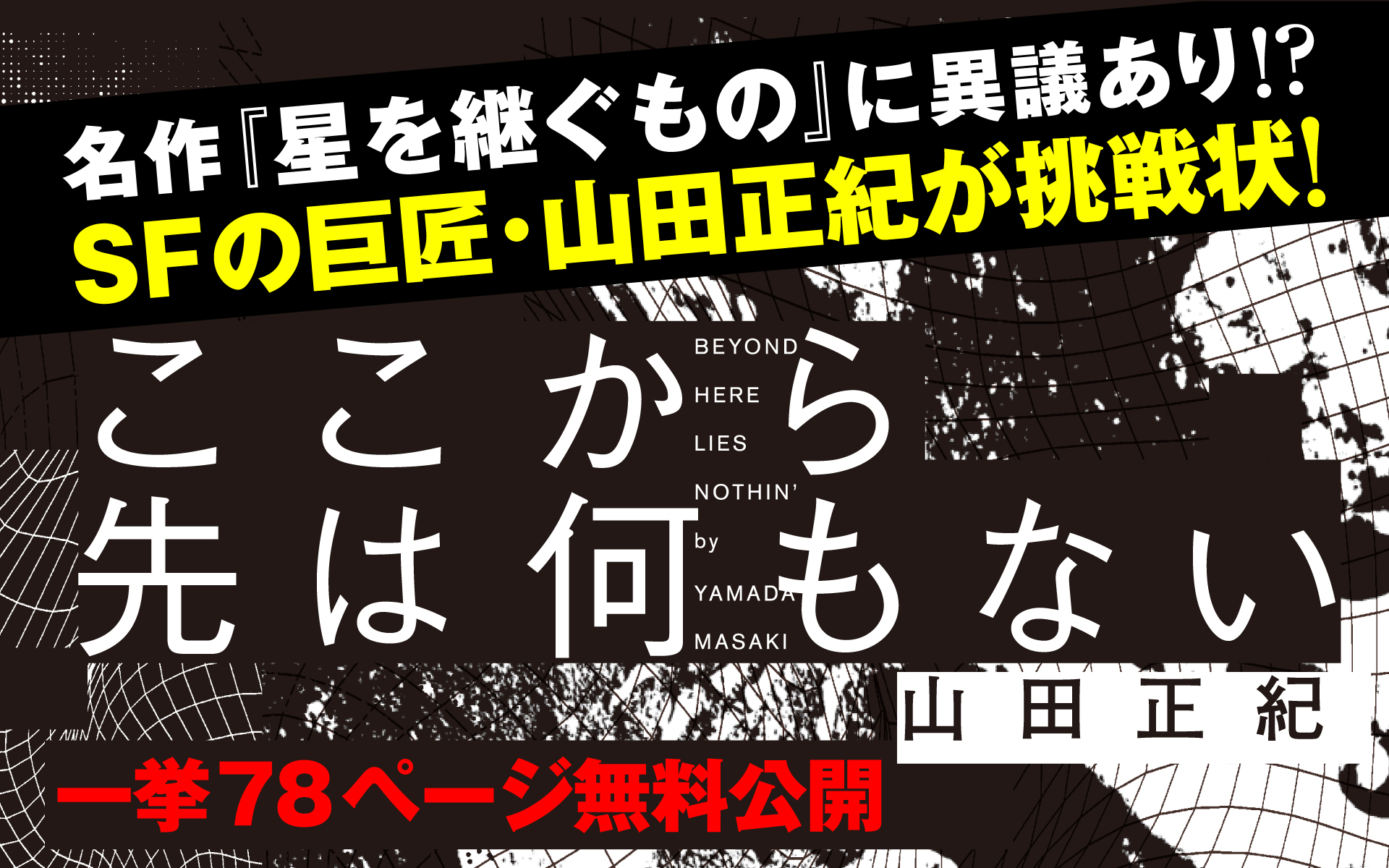文庫 - 日本文学
これなら『論語』がよくわかる! とにかく最高な『論語』入門! 物語でわかる論語の世界② 『論語物語』より「自らを限る者」」
下村湖人
2020.11.18

『次郎物語』の著者として知られる下村湖人は、生涯をかけて『論語』を学び続ける中で、『論語』にある孔子の言葉を、短い物語に仕立てました。そうして出来上がった『論語物語』(河出文庫)には、熱心な教育学者でもあった下村湖人と、孔子による弟子への人間味あふれた熱情が組合わさり、歴史に残る「座右の書」が生まれたのです。
今回は『論語物語』(河出文庫)刊行に際しまして、この感動的な物語を現代の皆様にお届けすべく、収録された28話の中から、5話を公開します。
続きは、文字が大きく読みやすい河出文庫版でお楽しみください。
* * *
自らを限る者
「冉求はこのごろどうしたのじゃ。さっぱり元気がないようじゃが。」
孔子にそう云われるほど、実際冉求はこの一二カ月弱りきった顔をしている。別に身体に故障があるのではない。ただひどく気分が引き立たないのである。
彼が孔子の門にはいったのは、表面はとにかく、内心では、いい仕官の口を得たいためであった。仕官をするには、一とおり詩書礼楽に通じていなければならない。そして、その方面にかけての第一人者は、何と云っても孔子である。孔子の門にさえはいって居れば、ともかく一人前の人間に仕立ててもらえるだろうし、それは仕官の手蔓だって、きっと得やすいにちがいない。そう思って、彼はせっせと勉強しつづけていたのである。
ところが、しばらく教えをうけているうちに、彼は一つの疑問にぶッつかった。それは孔子の学問が、最初自分の考えていたのとちがって、何だか実用に適しないように思えることであった。なるほど孔子は、いつも理論よりも実行を尊ばれる。それはよくわかる。よくわかるが、その実行というのが、非常に世間放れのしたもので、忠実にそれを守っていたら、実生活の敗北者になりそうなことばかりである。客観性を持たない真理は、要するに空想に過ぎないのではないか。自分は美しい空想を求めて入門したのではない。もっと生活に即した、実現性のある教えがほしい。
それに、こんな夢のようなことばかり教わって、ぐずぐずしていたのでは、仕官の機会がいつ来るのか、わかったものではない。そう云えば、孔子は、われわれ門人のために、仕官について、ちっとも積極的に働いてくれてはいないようだ。「自分にそれだけの力さえあれば、何も世間に名前の知れないのを心配することはない。」などとよく云われるが、今の時代にずいぶん迂遠な話だ。むやみと押売りするわけにも行くまいが、ちっとはわれわれの気持を察して、何とかわれわれの評判が立つようにして貰いたいものだ。
とにかく今のままでは面白くない。顔回など、馬鹿正直に孔子の一言一行を学んで、喜んでいるようだが、あんなに身体が弱くて、どうせ忙しい政治家などになれない人は、あんな風にでもして、自ら慰めるより仕方があるまい。だが、われわれと顔回とを同一視して、彼の真似さえしていれば、それでいいような風に云われるのは、少々心得がたい。なるほど顔回は、あんな風だから、個人的な徳行の点では、優れているのかも知れない。しかし、政治には、子路のような蛮勇も要れば、子路のような華やかさも要る。そう誰も彼も同じ調子で行くものではない。個性を無視して、何の教育だ、何の道だ。
彼は、そんな不平を抱いて、永いこと過ごして来た。そして、幾度となく、いろんな理窟をこねまわして、孔子にぶッつかって見た。しかし、ぶッつかって見ると、いつも造作なく孔子にやりこめられてしまった。やりこめられたというよりは、軽々と抱き上げられて、ぽんとやさしく頭をうたれたような気がするのだった。そのたびごとに彼は拍子ぬけがした。そして、そのあとには変にさびしい気持が、彼の心を支配するのだった。
日がたつにつれて、彼は、孔子があまりによく門人たちの心を知っているのに驚いた。彼自身、どれほどうまく言葉を繕って見ても、孔子はいつも先廻りして、彼の前に立ちふさがっていた。個性を無視するどころではない、一人々々の病気をよく知りぬいていて、まるで魔術のように急所を押さえてしまう。しかもその急所の押さえかたは決してその場その場の思いつきではない。孔子の心のどこかに、一つの精妙な機械が据えつけてあって、そこから時と場合とに応じて、自由自在にいろんな手が飛び出して来るように思える。「道はただ一つだ。」とは、よく聞かされた言葉だが、恐らくそれが孔子の掴んでいる道なのだろう。しかし、その正体はわからない。それは「仁」だというものもある。「忠恕」だというものもある。言葉では何とでも云えるだろうが、その心持を実感的に味うことは容易でない。しかも、それこそ孔子が、生きた日々の事象を取りさばいて行く力なのだ。決してそれは、自分が以前に考えていたような美しい空想ではない。十分な客観性をもった、血の出るような実生活上の真理なのだ。そして、それを掴むことこそ、真の学問なのだ。
彼はだんだんとそんなことに気がつき出した。同時に彼の態度も次第に変って来て、仕官などはもうどうでもいいことのように思われ出した。そして、そういう心で門人たちを見ると、なるほど顔回はその中でも一頭地をぬいている。閔子騫や、冉伯牛や、仲弓もなかなか立派である。宰我や子貢は何だか生意気に見える。子夏と子游とは少しうすっぺらだ。子路は穴だらけの野心家のように思える。そして自分は、と彼は自ら省みて、いつも一種の膚寒さを感ずるのであった。
子路に似て政治を好みながら、子路ほどの剛健さと醇朴さを持たない彼は、とかく小策を弄したり、言いわけをしたりすることが多かった。門人仲間では謙遜家のように評されているが、それは負惜しみや、ずるさから出る、表面だけの謙遜であることを、彼自身よく知っていた。彼は自分の腹の底に、卑怯な、小ざかしい鼬のような動物が巣喰っていて、いつも自分を裏切って、孔子の心に背かしているような気がしてならなかった。
(俺は道を求めている。この事に間違いはないはずだ。)
彼はたしかにそう信じている。しかし同時に、彼の心のどこかで彼が道を逃げたがっていることも、間違いのない事実であった。そして、
(駄目だ。俺は孔子の道とは、もともと縁のない人間だったのだ。)
彼は、このごろ、しみじみとそう思うようになった。そして、いくたびか孔子の門に別れを告げようかと考えたこともあった。しかし、思いきってそれも出来なかった。こうして、ぐずぐずしている間に、彼の腹の中の鼬はいよいよ彼に、表面をかざるための小策を弄さした。そして、小策を弄したあとの淋しさは、そのたびごとに、いよいよ深くなって行くばかりであった。
こうして彼の顔色は、孔子の眼にもつくほどに、血の気を失って来たのである。
彼は、とうとうある日、ただ一人で孔子に面会を求めた。心の中を何もかもさらけ出して、孔子の教えを乞うつもりだったのである。ところが、孔子の室にはいると、例の腹の中の鼬が、つい、ものを云ってしまった。
「私は、先生のお教えになることに強いあこがれを持っています。ただ、私の力の足りないのが残念でなりません。」
彼は云ってしまって、自分ながら自分の言葉にちっとも痛切なところがないのに驚いた。
(何のために自分はわざわざ一人で先生に面会を求めたのだ。こんな平凡な事を云うくらいなら、いつだってよかったはずだ。先生もさだめしおかしな奴だと思われるだろう。)
そう思って、恐る恐る彼は孔子の顔を見た。
孔子は、しかし、思ったよりも遥かに緊張した顔をしていた。そして、しばらく冉求をじっと見つめていたが、
「苦しいかね。」
と、いかにも同情するような声で云った。
冉求の鼬は、その声をきくと急に頭をひっこめた。そしてその代りに、しみじみとした感じが、彼の胸一ぱいに流れた。彼は、母の胸に顔をくッつけているような気になって、思う存分甘えて見たいとすら思った。
「ええ、苦しいんです。なぜ私は素直な心になり得ないのでしょう。いつまでもこんな風では、先生のお教えをうけても、結局駄目ではないかと存じます。」
「お前の心持はよくわかる。しかし、苦しむのは、苦しまないのよりは却っていい事なのじゃ。お前は、自分で苦しむようになったことを、一つの進歩だと思って、感謝していい、何も絶望することはない。」
「でも先生、私には、真実の道を掴むだけの素質がないのです。本来駄目に出来ている男なのです。私は卑怯者です。偽り者です。そして……」
と、冉求は急にある束縛から解放されたように、やたらに、自分をけなしはじめた。
「お黙りなさい。」
と、その時凜然とした孔子の声が響いた。
「お前は、自分で自分の欠点を並べたてて、自分の気休めにするつもりなのか。そんな事をする隙があったら、なぜもっと苦しんで見ないのじゃ。お前は、本来自分にその力がないということを、弁解がましく云っているが、ほんとうに力があるか無いかは努力して見た上でなければわかるものではない。力のない者は中途で斃れる。斃れてはじめて力の足りなかったことが証明されるのじゃ。斃れもしないうちから、自分の力の足りないことを予定するのは、天に対する冒瀆じゃ。何が悪だといっても、まだ試しても見ない自分の力を否定するほどの悪はない。それは生命そのものの否定を意味するからじゃ。しかし……」
と、孔子は少し声をおとして、
「お前は、まだ心からお前自身の力を否定しているのではない。お前はそんなことを云って、わしに弁解をすると共に、お前自身に弁解をしているのじゃ。それがいけない。それがお前の一番の欠点じゃ。」
冉求は、自分では引っこめたつもりでいた鼬の頭が孔子の眼には、ちっとも隠されていなかったことに気がついて、少からず狼狽した。
孔子は、しかし、静かに言葉をつづけた。
「それというのも、お前の求道心が、まだ本当には燃え上っていないからじゃ。本当に求道心が燃えて居れば、自他に阿る心を焼きつくして、素朴な心にかえることが出来る。素朴な心こそは、仁に近づく最善の道なのだ。元来、仁というものは、そんなに遠方にあるものではない。遠方にあると思うのは、心に無用の飾りをつけて、それに隔てられているからじゃ。つまり、求める心が、まだ真剣でないから、というより仕方がない。どうじゃ、そうは思わないのか。」
冉求は、うやうやしく頭を下げた。
「とにかく、自分で自分の力を限るようなことを云うのは、自分の恥になっても、弁護にはならない。それ、よくそこいらの若い者たちが歌っている歌に、
ゆすらうめの木
花咲きゃまねく、
ひらりひらりと
色よくまねく。
まねきゃこの胸
こがれるばかり、
道が遠くて
行かりゃせぬ。
というのがある。あれなども、人間の生命力を信ずる者にとっては全く物足りない歌じゃ。なあに、道が遠いことなんかあるものか。道が遠いといってへこむのは、まだ思いようが足りないからじゃ。はっ、はっ、はっ。」
孔子は、いかにも愉快そうに、大きく笑った。
冉求は、このごろにない朗らかな顔をして室を出たが、その足どりには新しい力がこもっていた。
* * *

下村湖人『論語物語』(河出文庫)*好評発売中!
*文庫版には該当箇所の原文も掲載されております。
また本文中、今日の観点から見て差別的と受け取られかねない表現がありますが、作品発表時の時代的背景を考慮し、原文通りといたしました。