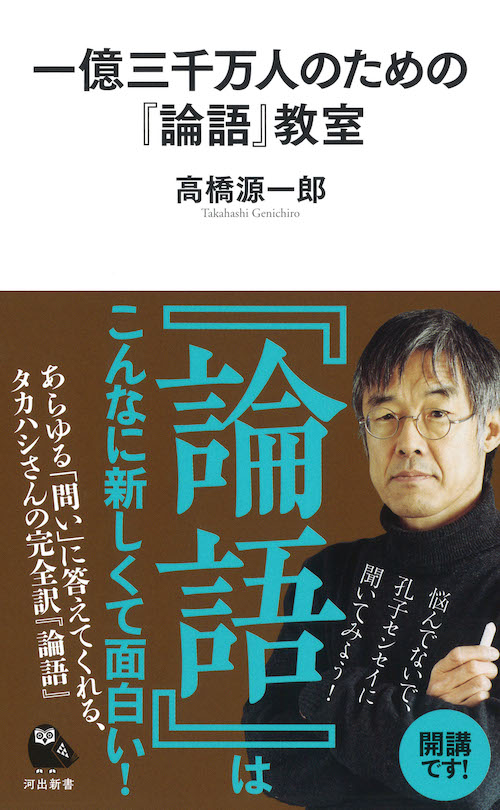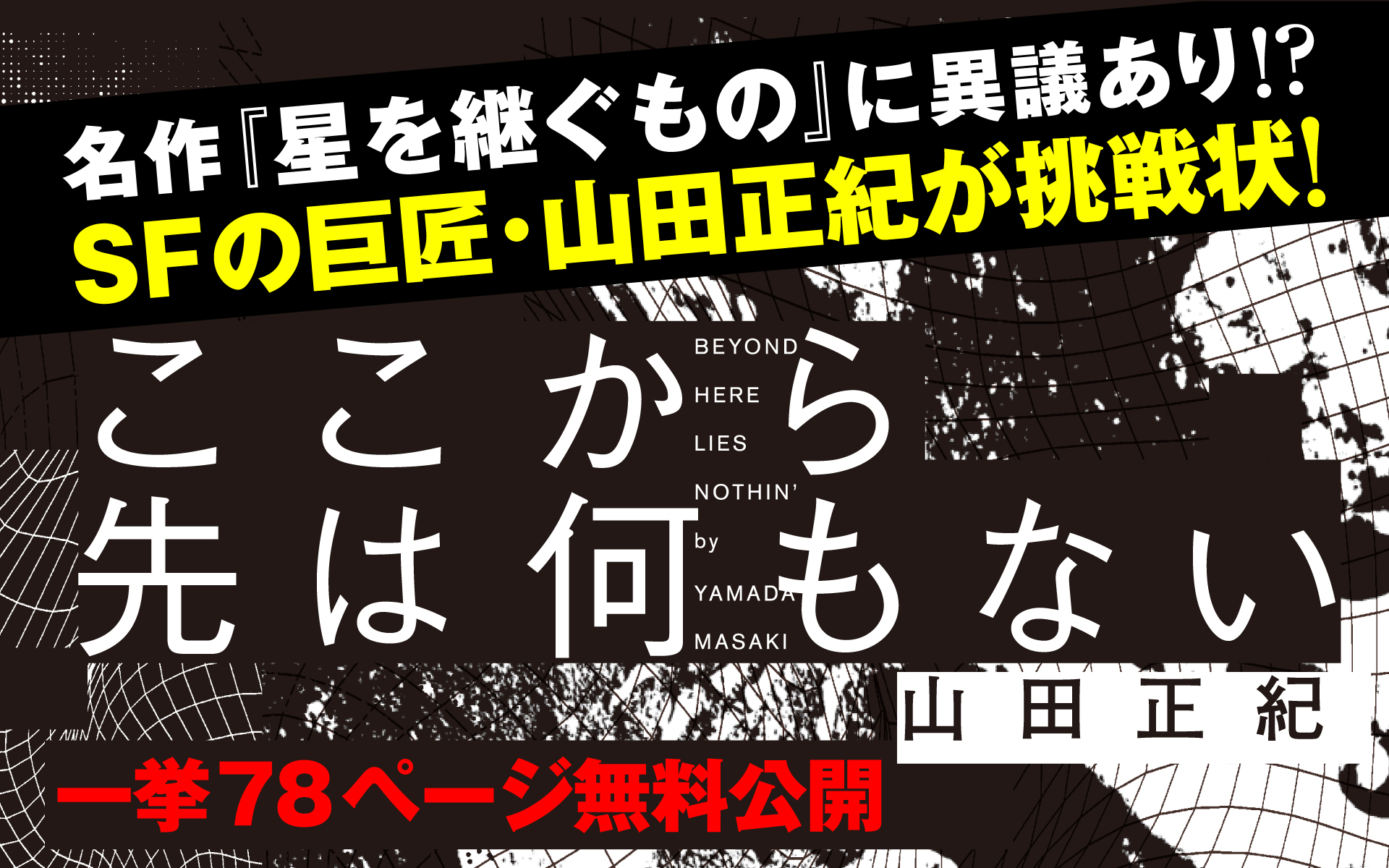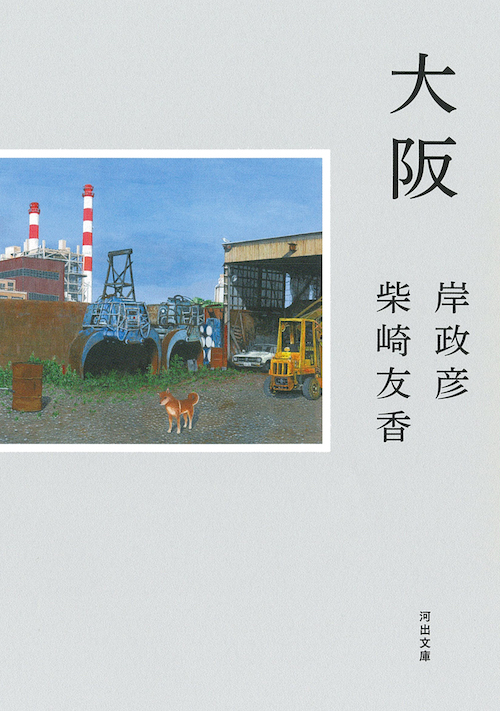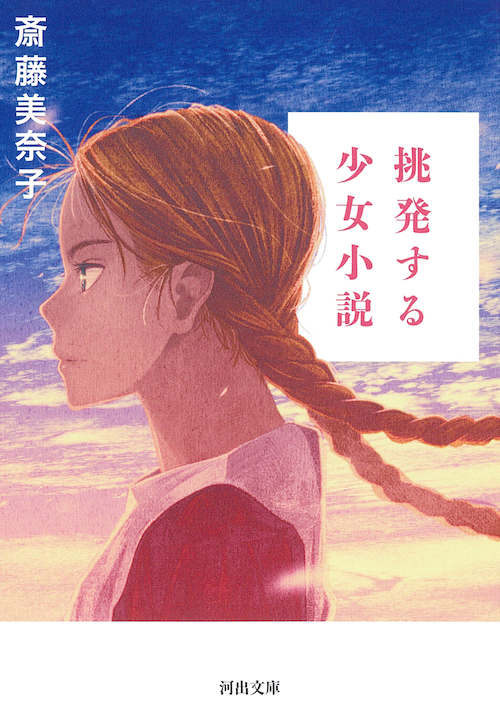文庫 - 日本文学
ここに、感動できる『論語』の名作があった! 物語でわかる論語の世界③ 『論語物語』より「大廟に入りて」
下村湖人
2020.11.19

『次郎物語』の著者として知られる下村湖人は、生涯をかけて『論語』を学び続ける中で、『論語』にある孔子の言葉を、短い物語に仕立てました。そうして出来上がった『論語物語』(河出文庫)には、熱心な教育学者でもあった下村湖人と、孔子による弟子への人間味あふれた熱情が組合わさり、歴史に残る「座右の書」が生まれたのです。
今回は『論語物語』(河出文庫)刊行に際しまして、この感動的な物語を現代の皆様にお届けすべく、収録された28話の中から、5話を公開します。
続きは、文字が大きく読みやすい河出文庫版でお楽しみください。
* * *
大廟に入りて
魯では、その年、大廟の祭典を行うのに人手が足りなかった。もっとあからさまに云うと、祭典の儀式に最も明るかった人が病気なので、臨時にその代りをつとめる人が、是非必要だったのである。
大廟には、魯の始祖周公旦が祭ってある。その祭典が、国として最も重要な祭典であることは、云うまでもない。従って、儀式の面倒なことも、この上なしである。よほど礼に明るい人でないと、下ッぱの役目でも勤まりそうにない。況んや、もっとも大切な役目を、大廟の奉仕には直接経験のない人に勤めさせようというのだから、その人選がなかなかむずかしい。あれかこれかと詮議の末、やっと白羽の矢が孔子に立てられた。
孔子は、当時まだ三十六七歳にしかならなかったが、すでに多くの門人もあり、その学徳は国の内外に聞えていた。ことに、礼についての彼の造詣は、推薦者の言によると、天下にならぶ者がなかった。それだけに、彼に対する期待も大きかったが、なにぶん、年が若いというので、一部では、彼を危ながっているものもないではなかった。ことに、永らく大廟に奉仕している人たちの間には、変な猜み心から、いろいろの取沙汰が行われていた。
さて、いよいよ祭典の準備がはじまって、孔子もはじめて大廟に入ることになったが、その日は、彼に好意を持つ者も、持たない者も、たえず彼に視線を注いで、その一挙一動を見まもっていた。
ところで、彼等の驚いたことには、孔子は先ず祭官たちに、祭器の名称や、その用途を訊ねた。そして、一日じゅう、それからそれへと、その取扱いかたや、儀式の場合の坐作進退のこまごましたことなどを、根掘り葉掘り訊ねるのであった。
「何という見当ちがいでしょう。これでは、まるで五つ六つの子供を雇い入れたのも同じではありませんか。」
「評判なんて、あてにならないものですね。」
「ふん。どうせ山師でしょう。仕官も出来ないくせに、門人ばかり集めて、いかにも学者ぶっているところを見ても、ろくな人間でないことは、はじめからわかっていますよ。」
「ご尤もです。第一、私共のように、永年こうして奉仕していても、なかなか覚えられないほどの儀式が、あの田舎者の若造に、そうやすやすとのみこめるわけがありませんからね。そんなことぐらい、その筋でもわかりそうなものですが……。」
「当局の非常識にも、全く呆れてしまいますね。」
「いずれ非常識の酬いが来るでしょう。しかし、今度ばかりはわれわれに責任がありませんから、どんなしくじりがあっても、安心ですよ。」
「そう云えばそうですね。しかし、本人の大胆さには驚くではありませんか。あれでやっぱり本気なんでしょうか。」
「さあ、それは本人に聞いて見ないとわかりますまい。しかし、無神経なことはたしかですよ。あんなつまらんことを一々訊ねて、恥かしそうにもしていませんからね。」
「恥かしいどころか、それが当りまえだといったような顔をしていますよ。」
「ああ真面目くさって訊かれたんでは、茶化すわけにも行きませんし、困りましたよ。」
「何しろ、おたがいもいい面の皮でさあ。教えてやった揚句に、その下役に使われるなんて。」
「いや、年はとりたくないものです。」
「それにしても、あんな青二才を、鄹の片田舎から引っぱり出して来て、礼の大家だなんて云い出したのは、一たい誰でしょう。人を馬鹿にするにもほどがあるではありませんか。」
「今更、そんなことを詮議立てして見たところで始まりますまい。それよりか、礼の大先生の現代式祭典のやり方でも覚えこんで、われわれも、もっと出世をする工夫をした方が利巧でしょう。」
「いや、なるほど。そう事がきまれば文句なしです。はッはッはッ。」
孔子の姿が見えないところでは、あちらでも、こちらでも、そうした失望やら、嘲笑やら、憤慨やらの声がきこえた。孔子は、それを知ってか、知らないでか、一とおり質問を終ると、みんなに丁寧に挨拶をして、その日は一旦退出した。
心配したのは孔子の推薦者であった。彼とても、孔子の力量を実際に試して見たわけではなく、世評と、孔子の門人たちの言葉を信頼していたに過ぎなかった。で、彼は、大廟内の噂を耳にすると、すぐ子路のところに駆けつけた。事柄が事柄だけに、直接孔子に会うのも憚られたし、それに、こんな場合、何もかもぶちまけて相談の出来そうなのは、孔子の門人のなかでは子路が一番だ、と思ったからである。
子路は、一とおり話をきくと、大声を出して笑った。
「ご安心なさい。貴方のご迷惑になるようなことは断じてありません。……しかし、先生も先生だ。そんな児戯に類するようなことをして、皆さんにご心配をおかけしなくてもよさそうなものだ。……どうです、これからご一緒に先生のお宅にお伴しましょう。私にも少し文句があるんです。ぶちまけてお話をして、先生のお考えも承ろうではありませんか。そしたら貴方もいよいよご安心でしょう。」
で、早速二人は孔子の門をくぐった。
子路は、孔子の顔を見るなり、お辞儀もそこそこに、来意を告げた。そして例の大声を張りあげて、詰問でもするように云った。
「僕は、先生のその流儀が、どうも腑に落ちないのです。こんな時こそ、先生は堂々と、ご自分のお力をお示しになるべきではありませんか。だのに、わざわざ、田舎者だの、青二才だのと云われるようなことを、どうしてなさるのです。」
「私の力を示すというと?」
孔子は顔色一つ動かさないで云った。
「むろん、先生の学問のお力です。」
「学問というと、何の学問かな。」
「それは今度の場合は礼でしょう。」
「礼なら、今日ほど私の全心を打込んだところを、皆さんに見ていただいたことはない。」
「すると、先生の方からいろいろお訊ねになったというのは、嘘なんですか。」
「嘘ではない。何もかも皆さんに教えていただいたのだ。」
「何だか、さっぱりわけが解りませんね。」
「子路、お前は、一体、礼を何だと心得ている。」
「それは先生にふだん教えていただいているとおり……。」
「坐作進退の作法だというのか。」
「そうだと思います。ちがいましょうか。」
「むろんそれも礼だ。それが法に叶わなくては礼にはならぬ。しかし礼の精神は?」
「先生に承ったところによりますと、敬しむことにあります。」
「そうだ。で、お前は、今日私がその敬しみを忘れていた、とでも云うのかね。」
子路の舌は、急に化石したように、硬ばってしまった。孔子はつづけて云った。
「かりそめにも大廟に奉仕するからには、敬しんだ上にも敬しまなくてはならない。私は、先輩に対する敬意を欠きたくなかったし、それに従来の仕来りについて、一応のおたずねもして見たかったのだ。それをお前までが問題にしようとは夢にも思わなかった。しかし……」
と、彼は一二秒ほど眼をとじたあとで、
「私にも十分反省の余地があるようだ。元来、礼は敬しみに始まって、調和に終らなければならない。然るに、今日私が皆さんにお訊ねした結果、皆さんのお気持を害したとすると、私のどこかに、礼に叶わないところがあったのかも知れない。この点については、私もなお篤と考えて見たいと思っている。」
子路はますます固くなった。孔子の推薦者は、さっきから二人の話を落ちつかない風で聴いていたが、孔子の言葉が終ると、急に立上って、挨拶もそこそこに辞し去った。
孔子は、子路と二人ぎりになってからも、眼をつぶってしばらく考えこんでいたが、ふと何か思い当ったように云い出した。
「子路、お前は、何よりも剣が好きだ、と云ったことがあるね。」
「はい。」
「学問が何の役に立つか、と云ったこともあるね。」
「はい。」
「だが、今では、学問の大切なことは、十分わかっているだろう。」
「それは申すまでもございません。」
「ところでお前には、まだ学問をするほんとうの心構えが出来ていない。」
「と申しますと?」
「現に今日もお前は、よく考えもしないで、私の方に飛びこんで来たのではないかね。」
「申しわけありません。」
「学問に大切なことは、学ぶことと考えることだ。学んだだけで考えないと、道理の中心が掴めない。だからいつも行き当りばったりだ。丁度真暗な室で、柱をなでたり、戸をなでたりするようなもので、個々の事柄を全体の中に統一して見ることが出来ないのだ。むろん考えただけで学ばないのもいけない。自分の主観だけに捉われて、先人の教えを無視するのは、丁度一本橋を渡るように危いことだ。向うまで行きつかないうちに、いつ水の中に落ちこむか知れたものではない。事柄によっては、いくら考えても何の役にも立たない事さえあるのだ。いつだったか、私は、食うことも寝ることも忘れて一昼夜も考えこんだことがあるが、何一つ得るところがなかった。そんな時、古聖人の残された言葉に接すると、一遍に道理がわかるのだ。とにかくどちらも軽んじてはいけない。学びつつ考え、考えつつ学ぶ、これが学問の要諦だ。ところでお前は、そのどちらもまだ十分でない。それも、結局、お前に敬しむ心がないからではないかね。」
孔子の言葉は、容易に終りそうにない。
「道は一つだ。心に敬しみさえあれば、物事を軽率に判断することもなかろうし、わかりもしない事をわかったように見せかけることもないだろう。」
「別に、わからない事をわかったように見せかけたつもりはありませんが……」
子路は、少し不服そうに、言葉をはさんだ。
「そうか、そう自分では信じているのか。」
「少くとも、今日の事では……」
「ふむ。するとお前は、お前自身何を考え、何をやっているのかさえ、よくはわかっていないようだな。」
孔子もまだ若かった。彼の言葉には、かなりの辛辣さがあった。
「お前がさっきの人をつれて、ここにやって来た時には、お前は何もかも知りぬいた人のような顔をしていたのだ。礼のことも、そして私が今日大廟でどんな心でいたかも。」
「それは全く私の誤解でした。」
「誤解? なるほど人間には誤解というものがある。そして、もしそれが敬しみに敬しんだ上での誤解であるならば、許されてもいい。しかし、万一にも、自分を誇示したい念が急なために生じた誤解であるとすると、それは最早や誤解でなくて虚偽だ。自分自身に対する不信だ。生命の真の願いを自ら暗ますものだ。そしてそれが人間をして無知ならしめる最大の原因だ。お前には、まだここの道理がよくのみこめていない。だから人一倍無知を恥じていながら、却って知が進まないのだ。自分は真に何を知っているのか、また何を知らないのか、それらをつつましい心で十分に反省して、知っていることを知っているとし、知らないことを知らないとする、そうした自他を偽らない至純な気持になってこそ、知は進むのだ。要するに、知は他人に示すためのものではない。それは自分の生命を向上せしむる力なのだ。そしてまことの知は、ただ遜る者のみに与えられる。このことをいつまでも忘れないでいて貰いたい。」
孔子の顔は、そこで急にやさしくなった。そしてうなだれている子路を、いかにも労わるような眼で見やりながら、
「それさえ覚えていて貰えば、わしはもうお前に何も云うことはない。お前はその勇気──自他ともに許しているその勇気を、これからは、お前自身の心の中の敵に向けさえすればいいのだ。遜る勇気、敬勇気、──どうだ、子路、何とも云えない、いい響きをもった言葉ではないか。この言葉をくりかえしているだけでも、わしは、私の眼の前に、深い、明るい、しかも力強い世界が現われて来るような気がしてならないのだ。」
子路の睫毛には、その時、かすかに光るものが宿っていた。 孔子は、子路が帰ったあと、永いこと黙想にふけった。そして、翌日からの大廟における彼は、従来の儀式の誤った点を正し、欠けたところを補い、終日謹厳そのもののような姿をして、祭官たちを指揮していた。
* * *

下村湖人『論語物語』(河出文庫)*好評発売中!
*文庫版には該当箇所の原文も掲載されております。
また本文中、今日の観点から見て差別的と受け取られかねない表現がありますが、作品発表時の時代的背景を考慮し、原文通りといたしました。