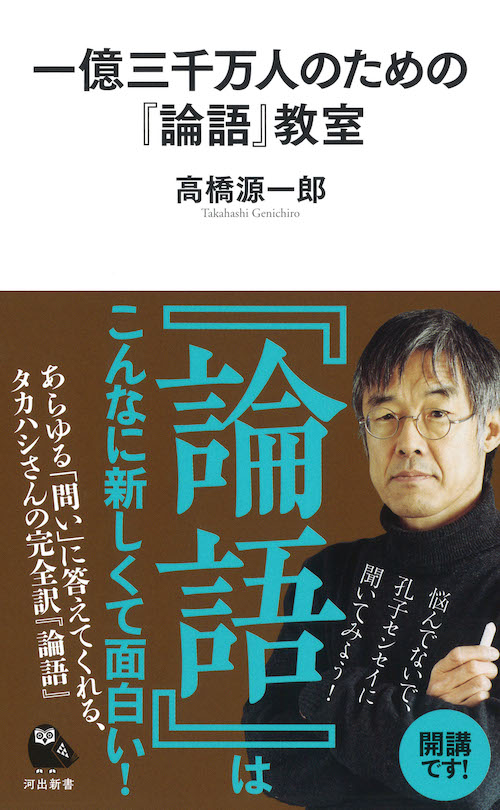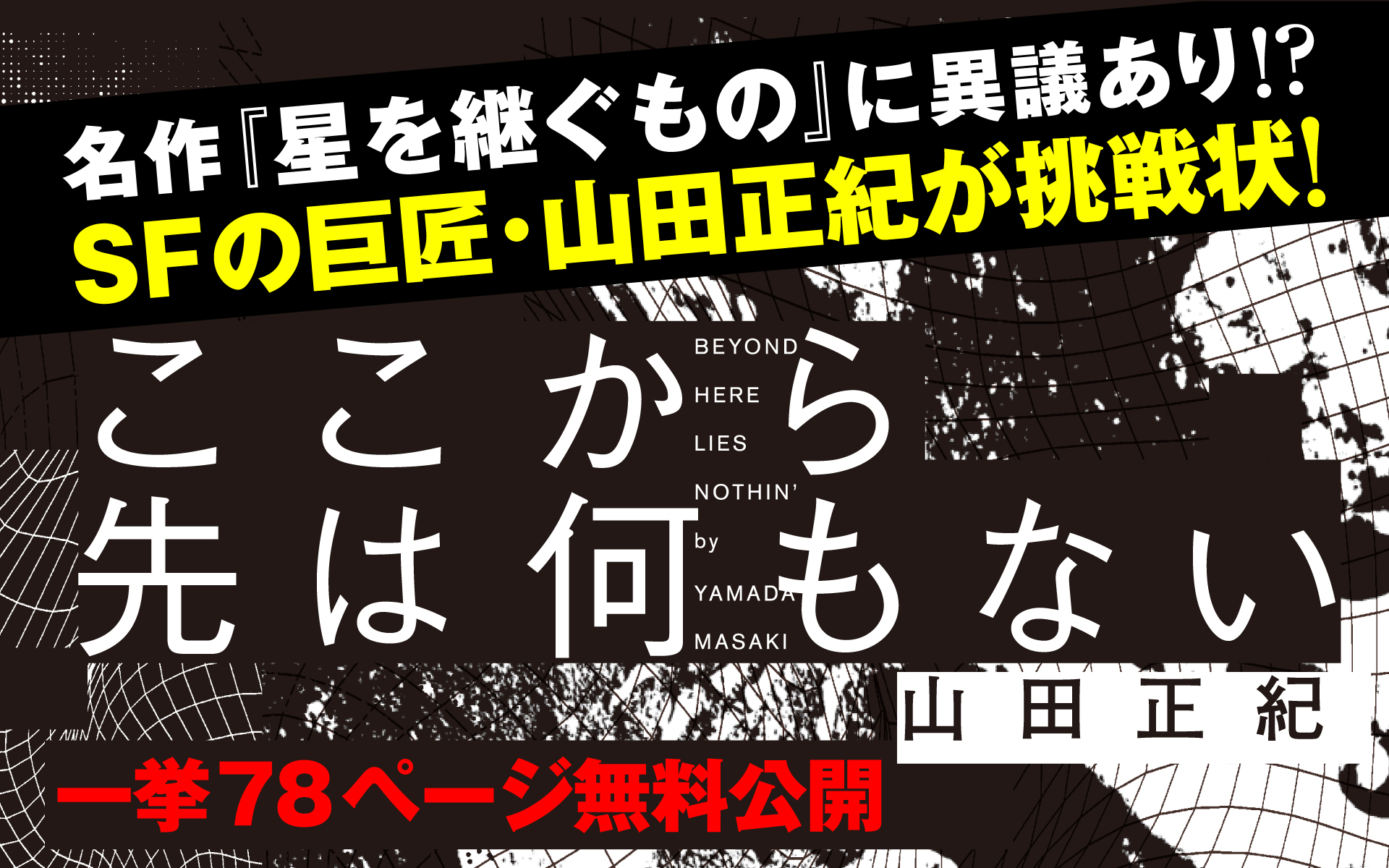文庫 - 日本文学
『論語』はこんなにも感動的だった! 物語でわかる論語の世界④ 『論語物語』より「匡の変」
下村湖人
2020.11.20

『次郎物語』の著者として知られる下村湖人は、生涯をかけて『論語』を学び続ける中で、『論語』にある孔子の言葉を、短い物語に仕立てました。そうして出来上がった『論語物語』(河出文庫)には、熱心な教育学者でもあった下村湖人と、孔子による弟子への人間味あふれた熱情が組合わさり、歴史に残る「座右の書」が生まれたのです。
今回は『論語物語』(河出文庫)刊行に際しまして、この感動的な物語を現代の皆様にお届けすべく、収録された28話の中から、5話を公開します。
続きは、文字が大きく読みやすい河出文庫版でお楽しみください。
* * *
匡の変
「そうです、今思うと、このまえ陽虎の供をして来た時には、あそこからはいったのでした。」
顔刻は、御者台から策をあげて、くずれ落ちた城壁の一角を指しながら、孔子に云った。
孔子の一行は、衛を去って陳に行く途中、今しも匡の城門にさしかかったところである。──匡は国境に近い衛の一邑である。
「あの時は、陽虎もずいぶん乱暴を働いたそうじゃな。」
孔子は、車の窓からあたりの景色を眺めながら、感慨深そうにいった。──陽虎というのは、魯の大夫季氏の家臣であったが、陰謀を企てて失敗し、国外に逃れ、匡に侵入して暴虐を働いた男である。
「ええ、全く無茶でした。掠奪はするし、婦女子は拘禁するしで、今でもさぞ匡の人たちは怨んでいることでしょう。」
「お前も、その怨まれている一人じゃな。」
「お恥かしい次第です。しかし、あの時はどうにも出来なかったのです。供をするのを拒みでもしたら、それこそ命がなかったのですから。」
「で、お前も一緒になって、何か乱暴をやったのか。」
「とんでもない事です。乱暴をやらなかったことだけはお信じ下さい。私が陽虎のところを逃げ出したことでも、それはおわかり下さるでしょう。」
そんなことを話しながら、間もなく一行は城門を入って、予定の宿舎についた。
しばらくは何事もなかった。ところが、夕飯をすまして一同がやっと寛ろぎかけたころ、門外が急にざわつき出した。二三の門人たちが、不思議に思ってかけ出して見ると、いつの間にか、塀の周囲は、武装した兵士ですっかり取囲まれていた。
「どうしたのです。」
門人の一人が、おずおず門のすぐわきに立っている兵士に訊ねた。
兵士はぎろりと眼を光らしたきり、返事をしなかった。そして、他の兵士に何かひそひそと耳うちした。耳うちされた兵士は、二三度うなずくと、すぐどこかに走って行ってしまった。
門人たちは、うす気味悪く思いながらも、しばらくあたりの様子を見ていた。すると、さっき耳うちされた兵士が、隊長らしい、いかつい顔をした髥男と一緒にもどって来た。
「命令があるまでは、この家から一人たりとも門外に出すのではないぞ。よいか。」
いかつい顔が、近くにいる兵士たちを睨めまわしながら云った。ついでに彼は、孔子の門人たちの顔を、一人一人、穴のあくほど見つめた。
門人たちはまだわけが解らなかった。しかし、自分たちに関係のないことではないらしい、ということだけは、おぼろげながら推察が出来た。で、彼等は急いで門内にはいって、みんなにその様子を報告した。
「なあに、われわれに関係したことではあるまい。或は何かの間違いかも知れないが。……とにかく、みんな静かにおやすみ。用があれば、今に何とか先方から云って来るであろう。」
孔子は、事もなげにそう云って、自分の室に引きとった。
みんなは、しかし、落ちつかなかった。ことに顔刻は、不安そうな顔をして、何度も窓から外をのぞいた。
「よし僕が真相をしらべて来る。」
子路がたまりかねて、剣をがちゃつかせながら、一人で門外に飛び出した。
間もなく彼は帰って来たが、かなり興奮していた。
「馬鹿馬鹿しい。あいつらは、先生を陽虎と間違えているんだ。」
「なに、陽虎と?」
門人たちは、みんな呆気に取られた。
「そうだ。今日車の中に、たしかに陽虎が乗っているのを見たというんだ。」
「驚いたね。」
「しかし、無理もない点がある。何しろ、先生のお顔は、われわれが見ても、どうかしたはずみには、陽虎そっくりに見えるんだから。」
「それにしても、少しひどいよ。お供の様子を見ただけでも、大抵わかりそうなものじゃないか。」
「ところがそのお供にも、大きな責任があるんだ。」
「何だ、われわれにか。」
「いや、みんなというわけではない。実は顔刻が御者台にいたのが間違いのもとさ。」
「なるほど。また陽虎の供をして来たと思ったんだな。それに先生のお顔が陽虎そっくりと来ているんでは、疑われるのも無理はない。」
顔刻は、気ぬけがしたような顔をして、みんなの話をきいていた。
「しかし、孔子の一行だということを話したら、すぐわかってくれそうなものじゃないか。」
「ところが、そう簡単に行きそうにないんだ。何しろこの土地では陽虎に深い怨みがあるし、うっかり欺されて逃がしてしまったら、住民が承知しないというんだ。」
「でも、先生に顔を出していただいたら、まさか飽くまでも陽虎だとはいうまい。」
「それがあてにならないんだ。何でも、この土地で陽虎の顔を一番よく知っている簡子という男が、先生を陽虎だと言い張っているらしいのでね。」
「では、どうすればいいんだ。ぐずぐずしていると、今に乱入して来るかも知れないぞ。」
「いや、そんな乱暴は滅多にはやるまい。ほんとうの孔子の一行に、無礼があってはならないということは、よくわかっているので、今は大事をとっているところらしい。」
「それにしても、邑内に先生のお顔を知っている者が、一人ぐらいはいそうなものだね。」
「それがいると問題はないのだが、困ったことには、顔刻や陽虎の顔は知っていても、先生にお目にかかった者が一人もいないというんだ。」
「で、結局どうしようというのかね。」
「孔子の一行だということがはっきりするまでは、このまま閉じこめて置く考えらしい。」
「おやおや。で、一たい、いつまで待てばいいんだ。」
「少くも調査に三四日はかかるだろうと云っていた。早速方々に人を出しているそうだ。」
「馬鹿馬鹿しい。そんなのんきな話があるものか。」
「仕方がない。これも天命だろうさ。しかし、あまり永びくようであれば、こちらにも決心がある、と、そう云っておいた。」
「うむ、それはよかった。」
「ところで先生はもうお寝みかね。」
「まだだと思うが……」
「とにかく、先生にも一応事情をお話しておこう。」
子路はそう云って孔子の室に行った。
門人たちは、子路が去ると、急に黙りこんで顔を見合せた。塀の外からは、おりおり兵士たちの叫び声や、佩剣の音が聞えて来た。顔刻はその音を聞くたびに、眼玉をきょろつかせて、みんなの顔を見まわした。
子路は再びはいって来て云った。
「先生は、こちらからあまり突ッつくようなことをしないで、静かに待っている方がいい、と仰しゃる。ただ先生が心配していられるのは、顔淵のことだ。」
顔淵は、一行におくれて、その夜晩く匡につくことになっていたのである。
「そうそう。顔淵のことはついうっかりしていた。もうそろそろ着くころだが、事情を知らないで、うかうかとわれわれの宿を探しでもすると、変なことになるかも知れないね。」
「用心深い男だから、滅多なことはあるまいと思うが……」
「それにしても、まさかこんな事があろうとは、夢にも思っていないだろうからね。」
「何とか方法を講じなくてもいいのか。」
「方法って、どうするんだ。」
「誰かこっそり城門の近くまで行って……」
「そんなことが出来るものか、こう厳重に取囲まれていたんでは。」
「いっそわれわれの方から、先方の隊長に懇談して見るのも一方法だね。」
「さあ、それも却って藪蛇になるかも知れない。」
門人たちは、口々にそんなことを云って、ざわめき出した。
それまで、一言も発しないで、腕組をしながら考えこんでいた閔子騫が、この時はじめて口を出した。
「顔淵はわれわれより智慧がある。先生もきっと、顔淵のためにわれわれが細工をすることを好まれないだろう。」
冉伯牛と仲弓の二人も、最初から沈黙を守っていたが、閔子騫の言葉が終ると、いかにもそうだと云うように、深くうなずいた。すると子路が云った。
「実は先生の御意見もそのとおりだ。心配はしていられるが、こちらで細工をするより、本人に任した方がかえって安全だ、と仰しゃるんだ。」
みんなは、孔子が顔淵を信ずることの非常に篤いのを知っていた。彼等のある者は、孔子が嘗て、
「顔淵は終日話していても、ただ私の言うことを聴いているだけで、一見愚かなように見えるが、そうではない。彼は黙々たる自己建設者だ。どんな境地に処しても常に自分の道を発見して誤らない人間だ。彼は決して愚かではない。」
と云ったことを思い起した。で、誰も孔子の意に反してまで、顔淵のために手段を講じようとは云い出さなかった。
「すると、今夜は結局何もしないで、このまま寝るより仕方がないのか。」
「何だか落ちつかないね。」
「僕は寝たって眠れそうにないよ。」
みんなはそうした不安な気持を語りあいながら、それからもしばらく起きていた。しかし、いつまで起きていても仕方がないので、門外の様子に気を配りながら、やっとめいめいの床についた。
眠れない一夜が明けた。兵士たちの足音は夜どおしきこえた。そして顔淵はついに姿を見せなかった。
ところで、包囲は翌日も、翌々日も解けなかった。門人たちの不安は、刻々につのって行くばかりであった。孔子をはじめ、五六の高弟たちは、さすがに落ちついているような風を見せてはいたが、顔淵の消息が、皆目わからないのには、彼等もすっかり弱りきった。時として、孔子の口からさえ、ため息に似たものが、かすかに洩れることがあった。それをきくと、門人たちはいよいよたまらなかった。
子路は少し気短かになって来た。孔子は絶えず彼の様子に気をつけて、出来るだけ彼の気持を落ちつけるように努めた。そのために、彼はしばしば楽器を奏で、歌を唄い、子路に合唱を命じたりした。
四日目の夜更けであった。孔子と子路とが門人たちに囲まれて、例によって歌を唄っているところへ、ひょっくり顔淵が戸口に姿を現わした。さすがの孔子も、歌を唄い終るまで我慢が出来なくて、飛びつくように、彼の方に走って行った。
「おお、よく無事でいてくれた。わしはもうお前が死んだのではないかと思っていた。」
顔淵は、眼に一ぱい涙をためて答えた。
「先生がまだ生きていられるのに、私だけがどうして先に死なれましょう。」
みんなもその時は総立ちになっていたが、二人の言葉をきくと、画のようにしいんとなって、動かなかった。
「まあお坐り。」
孔子は、手をとるようにして顔淵に席を与えた。そして、この三日間、どこにどうしていたか、また、どうして囲みを破って無事に家の中にはいることが出来たかを訊ねた。顔淵は答えた。
「あの晩城門をはいると、すぐ大体の様子がわかりましたので、そ知らぬ顔をして、別に宿をとることにしました。そして、先生の一行が衛から陳に行く途中、ここを通られたはずだということを、この四日間、出来るだけ住民に吹聴しました。そのうちに、こちらのお宿から絃歌の音が聞え出したのです。その時は何とも云えない感じでした。住民の中にも、その音をきいて、これは陽虎ではない。陽虎にあんなすぐれた音楽が出来ようはずがない、などと云う者も出て来たようです。で、私もいくぶん安心しまして、思いきって隊長に事情を話し、中に入れてもらうように交渉しますと、案外たやすく承知してくれました。尤も、中にはいる分には構わないが、一旦はいったら、二度と出られないかも知れない、などとおどかされましたが……」
門人たちは、安心とも不安ともつかないような顔をして、たがいに目を見合せた。
孔子は、久方ぶりに晴やかな笑顔をして云った。
「これで一行の顔もそろった。今後どうなろうと、みんな一緒だと思えば気が楽じゃ。今夜はゆっくり休ましてもらおうか。」
孔子がそう云って立上ろうとした時であった。門のあたりで、急に罵り合う声が聞えた。
「陽虎だ! 何といったって陽虎にちがいないんだ。」
「万一孔子の一行だったらどうする。」
「万一も糞もあるもんか。俺たちの家財も娘も台なしにしやがった陽虎じゃないか。あいつの顔は、この俺の眼に焼きついているんだ。」
「そりゃそうかも知れない。しかし、もうあと一日だ。せっかく今まで我慢したんだから、明日まで待ってくれ。」
「明日まで待ったら、間違いなく俺たちに引渡すか。」
「そりゃ隊長の命令次第さ。」
「それ見ろ。そんなあいまいなことで、俺たちをごまかそうたって、駄目だ。」
「ごまかすんじゃない。今調査中なんだ。明日までには、きっとはっきりするんだ。」
「ふん、何が調査だ。あいつらの音楽にたぶらかされて、隊長自身が、孔子の一行にちがいない、などと云い出すような調査は、糞喰えだ。」
「何も音楽だけで決めようというのではない。世間の噂でも、孔子がここを通られることは、たしからしいのだ。」
「それも、二三日前から、変な奴がここいらをうろついて、云いふらしたことなんだろう。」
「そればかりでもないさ。」
「じゃあ、どんな証拠があるんだ。」
「証拠は隊長のところにある。」
「そうれ、知るまい。自分で知らなきゃあ、すっこんでいろ。俺たちは俺たちの考えで勝手にするんだ。……おい、みんな来い。」
「待てッたら。」
「畜生、なぐったな。」
「命令だ!」
「何を!」
小競合が始まったらしい。つづいて群集の喊声、兵士たちのそれを制止する叫び声、どたばたと走りまわる足音、佩剣の響き、物を抛げる音などが、騒がしく入りみだれた。
門人たちは、孔子を取巻いて、硬直したように突っ立った。誰の顔も真青だった。中には、がちがち躯をふるわせている者もあった。
孔子は、一寸眼をつぶって思案していたが、しずかに眼を開くと、門人たちの顔を一巡見まわした。
「恐れることはない。みんなお掛け。」
彼はそう云って席についた。門人たちも、腰をおろすにはおろしたが、その多くは上半身を浮かしたままであった。
孔子は、厳かな、しかもゆったりした口調で話し出した。
「文王が歿くなられて後、古聖人の道を継承しているのは、このわしじゃ。わしはそう信じる。そして、これはまさしく天意じゃ。永遠に道を伝えんとする天意のあらわれじゃ。もし道を亡ぼすのが天意であるなら、何で、後世に生れたわしなどが、詩書礼楽に親しむことがあろう。天はきっとわしを守って下さる。いや、わしのこの大きな使命を守って下さる。天意によって道を守り育てているこのわしを、匡の人たちが一たいどうしようというのじゃ。みんな安心するがよい。」
半ば腰を浮かしていた門人たちは、やっとめいめいの席に落ちついた。
「それに──」と、孔子はつづけた。
「人間というものは、心の底を叩けば、必ず道を求め、徳を慕うているものじゃ。だから徳には決して孤立ということがない。どんなに淋しくても、徳を守りつづけて行くうちには、誰かはきっとこれに感応して手を握ろうとする。匡の人たちも、やはり同じ人間じゃ。現に、陽虎を悪んでも、この孔子を悪んでは居らぬ。心配することはない。ただ天を信じ、己を信じて、正しく生きてさえ行けば、道は自然に開けて来るものじゃ。」
門外の騒ぎは容易に治まらなかった。しかし、それに引きかえて、室内は、誰一人息をする者もないほど、静まりかえっていた。
孔子は、話を終ると、もう一度みんなの顔を念入りに見まわして、しきりに一人でうなずいた。そして、最後に、隅っこに小さくなって坐っている顔刻を見つけると、彼は急に笑顔になって云った。
「ほう、顔刻もまだ無事で結構じゃ。」
顔刻はいよいよ小さくなった。
「では、子路──」
と、孔子は、やはりにこにこしながら、子路を顧みた。
「また一緒に文王の楽でも始めようか。」
子路は、今まで汗が出るほど握りしめていた剣を、鞘ごと自分の前に突っ立てて、右手でそれを叩きながら、調子をとりはじめた。
二人の喉からは、やがて朗々たる歌声が流れ出した。他の門人たちは、しばらくそれに耳をすましていたが、間もなくそれに合せて、ある者は唄い、ある者は剣を叩いた。
門外の騒音と、屋内の旋律とは、かなり永い間、星空の下にもみ合っていたが、騒音は次第に旋律に圧せられて、小半時もたつと、匡の人々は、子守唄でも聞きながら、深い眠りに落ちて行くかのようであった。
翌日は、隊長をはじめ、匡の役人たちが五六名、礼を厚うして孔子に面会を求めた。
誰よりも生きかえったようになったのは、顔刻であった。しかし彼は、その日の出発に際して、どうしても孔子の車の御者台に乗ろうとはしなかった。
* * *

下村湖人『論語物語』(河出文庫)*大好評発売中!
*文庫版には該当箇所の原文も掲載されております。
また本文中、今日の観点から見て差別的と受け取られかねない表現がありますが、作品発表時の時代的背景を考慮し、原文通りといたしました。