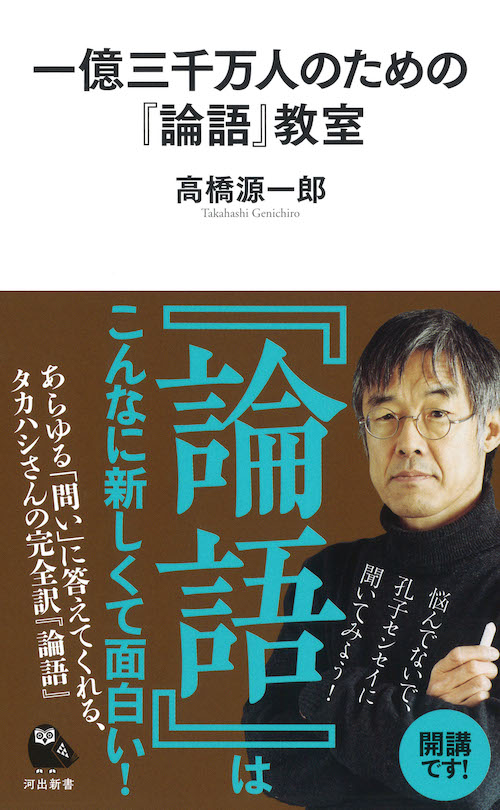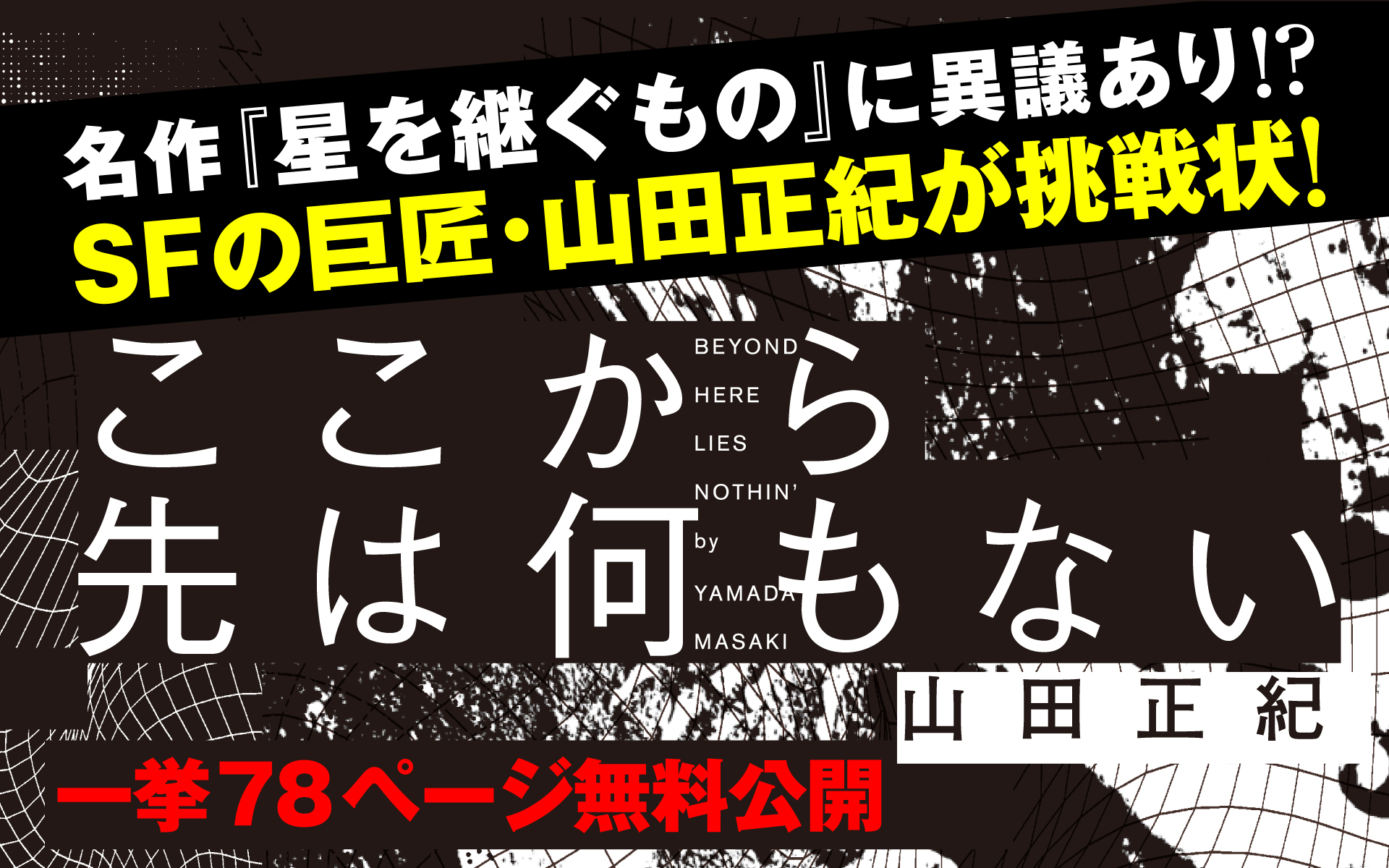文庫 - 日本文学
『論語』はこんなにも感動的だった! 物語でわかる論語の世界⑤ 『論語物語』より「渡場」
下村湖人
2020.11.25

『次郎物語』の著者として知られる下村湖人は、生涯をかけて『論語』を学び続ける中で、『論語』にある孔子の言葉を、短い物語に仕立てました。そうして出来上がった『論語物語』(河出文庫)には、熱心な教育学者でもあった下村湖人と、孔子による弟子への人間味あふれた熱情が組合わさり、歴史に残る「座右の書」が生まれたのです。
今回は『論語物語』(河出文庫)刊行に際しまして、この感動的な物語を現代の皆様にお届けすべく、収録された28話の中から、5話を公開します。
続きは、文字が大きく読みやすい河出文庫版でお楽しみください。
* * *
渡場
春はまだ寒かった。傾きかけた日が、おりおりかげって、野づらは明るくなったり、暗くなったりしていた。
葉公に見切りをつけて、楚から蔡に引きかえす孔子の心は、いくぶん淋しかった。彼は車にゆられながら、眼をとじては、じっと考えに沈んだ。手綱を執っている子路は、もう小半時近くも黙りこくっている。ほかの弟子たちもずいぶん疲れたらしく、三四町(約三〇〇~四〇〇メートル)もおくれて、黄色い土埃の中を、とぼとぼと足を引きずっている。
「しばらく休むことにしたら、どうじゃ。」
孔子は、思い出したように車の中から顔をつき出して、一行の様子を眺めながら、子路に云った。
「はあ──」
子路は生返事をした。そして車は相変らず、かたりことりと軋りつづけた。
「みんなもだいぶ疲れているようではないか。」
と、孔子は軽く子路をたしなめるような口調で云った。
「もうすぐ渡場だと思います。」
子路は面倒臭そうな顔をして、ぶっきらぼうに答えた。孔子もそれっきり黙ってしまった。
それから十五六分も経ったころ、子路は急に自分でぴたりと車をとめた。孔子は、渡場に着いたのかと思って、顔を出して見たが、そうではなかった。路が二つに岐れている。子路は手綱を握ったまま腕を組んで、じっと前方を見つめている。
「どうしたのじゃ。……休むのか。」
孔子は半身を車から乗り出して云った。
「渡場に行く路はどちらだか、考えているところです。」
孔子は微笑した。そして武骨な子路の後姿を黙って見ていた。しかし、子路はいつまで経っても、木像のように動かなかった。
「考えたら路がわかるかね。」
孔子はふとそんな皮肉を云った。このごろ、子路に対してだけは、おりおりこうした皮肉が、軽く彼の口を滑るのである。
子路の顔には、しかし、いつものとおりの反応が現われなかった。彼はやはり前方を睨んだまま、反抗するように答えた。
「わかります、わかると思います。」
孔子はもう微笑しなかった。彼は、子路が心に何か迷いを持っている時、いつも自分に無愛想になる癖を、よく知っていた。
(子路は、渡場に行く路のことだけを考えているのではない。)
孔子はそう思った。そして、子路が何を迷っているかも、ほぼ見当がついた。
(子路としては無理もない。彼は、淋しく旅をつづけるには、弟子たちの中でも一番不似合な男なのだ。)
しかし、孔子は口に出しては何とも云わなかった。彼は、憐むような眼をしばらく子路の横顔に注いでいたが、やがて眼を転じて、路の附近を見まわした。左手に墓らしい小高い丘があって、すぐその手前に、二人の農夫がせっせと土をいじっている。路から一町(約一〇〇メートル)とは隔っていない。
彼は急ににこにこしながら子路に云った。
「考えているより、訊ねた方が早くはないかね。ほら、あそこに人がいる。」
「はあ──」
子路は、やっと孔子の方を振りむいた。彼は孔子に何を云われたのか、はっきりしなかったかのように、きょとんとした顔をしている。
「すぐ行って、渡場を訊ねておいで。手綱はわしが握っている。」
「恐れ入ります。」
子路は、いかにも狼狽えたように、何度も頭を下げた。そして、孔子の手に手綱を渡すと、大急ぎで二人の農夫のところに走り出した。その後姿が何となく可笑しかった。孔子はしかし笑わなかった。彼は、胸の底に何かしみじみとしたものを感じながら、子路から眼を放さなかった。
「おうい。」
と、子路は、まだ七八間(約十三~十四メートル)も手前に突っ立って、大声で農夫を呼んだ。
農夫は、しかし、顔をあげなかった。子路は仕方なしに、更に二三間(約四~五メートル)進んで声をかけた。しかし二人共振りむいて見ようともしない。
車の中からこの光景を見ていた孔子は、ただの百姓ではないらしいと思った。そして子路の無作法な様子が少し気がかりになって来た。
(もし例の隠士だと、子路は少し手こずるかも知れない。)
彼はそう思った。が同時に、子路との間に取交わされる問答を想像して、これは一寸面白そうだ、とも思った。子路がどんな顔をして帰って来るのか、心配なような、待遠しいような気持になって、彼は相変らず子路の様子を眺めていた。
子路の方では、農夫たちがまるで彼の声など耳にも入らぬような風なので、ひどく癪に障っていた。彼は、それでも、仕方なしに二人のすぐそばまでやって来た。そして呶鳴りつけるような声で云った。
「おい、これほど呼んでいるのに聞えないのか。」
背のひょろ長い方の農夫が、顔をあげて、じろりと子路を見た。そして変に嘲るような笑いを洩したかと思うと、またすぐ下を向いてしまった。三四寸(約九~十二センチ)髥を垂らした、五十恰好の、どこかに気品のある顔である。それは長沮という隠士であった。
子路は、この時はじめて、これはしまった、と思った。で、少し照れながら、急に丁寧に云った。
「いや、これは失礼。……実は渡場に行く路がわからなかったものですから……」
すると、また長沮が顔をあげて子路を見た。今度はあまり皮肉な顔はしていなかった。しかし、返事をする代りに、道路の方を見遣って、そこに孔子の車を見つけると、もう一度胡散臭そうに子路の顔を見た。
「渡場の方に行きたいのですが……」
と、子路は少し小腰をかがめながら、ふたたび訊ねた。
「あれは誰ですかい。あの車の上で手綱をとっているのは。」
子路は、自分の問いには答えないで、すましきって、そんな事をあべこべに訊ね出した相手の横着さに、腹が立ったが、つとめて丁寧に答えた。
「あれは孔丘という方です。」
「孔丘というと、魯の孔丘のことですかい。」
「そうです。」
「じゃあ、渡場ぐらい知っていそうなものだ。年がら年中、方々うろついている男だもの。」
そう云って、長沮は、すぐ腰をこごめて鍬を動かしはじめた。そして、それっきり子路が何を云っても、唖のように黙ってしまった。
子路は呆気にとられた。
この間、もう一人の農夫──これは桀溺というずんぐりとした男だった──は、あたりに何が起っているのか、まるで知らないかのような風をして、耕された土に、せっせと種を蒔いていた。子路は、長沮に比べると、この方が少しは人が善さそうだと思った。で、その方に近づいて行って、もう一度渡場に行く路を訊ねた。
「何、渡場じゃと……」
桀溺は顔も上げないで答えた。
「ええ、渡場に行くんですが、右に行ったものでしょうか、それとも左に……」
「右でも左でも、自分の好きな方に行くさ。」
「どちらからでも同じでしょうか。」
「同じじゃない。」
桀溺は、そう云ってひょいと顔をあげた。赧ら顔で、眼が小さくて、髥はちょっぴりしか生えていない。長沮より年は三つ四つ下らしい。
「同じじゃないよ。」
彼はもう一度そう云って、にっこり笑った。小さな眼が肉に埋もれてしまって、大きな皺のように見える。
子路は何が何やら解らなかった。彼は怒ることも笑うことも出来なかった。すると桀溺は、急に笑いやめて、まじまじと子路の顔を見ながら云った。
「お前さんは一たい誰だね。」
「仲由という者です。」
子路は素直に自分の名を告げた。
「仲由? そして何かい、やっぱり魯の孔丘の仲間だというわけかね。」
「そうです、門人の一人です。」
「ふふふ──」
桀溺はだしぬけに笑い出した。それは菎蒻玉が振動して、その割目から湯気を吹き出すような笑い方だった。
子路は、孔子の門人だと答えたのを笑われたので、さすがにきっとなった。しかし、相手は子路の様子などまるで気にもとめていないかのように、そっぽを向きながら云った。
「孔丘のお仲間じゃ、渡場がわからないのも無理はない。気の毒なことじゃ。」
子路はとうとう我慢しきれなくなって、腕まくりし出した。
「おッと仲由さんとやら、それがいけない。そう腕まくりをして見たところで、物事はかたがつくものではない。それよりか、お前さんは一たい今の世の中をどう考えていなさる?」
子路は、折角まくり上げた両腕を、だらりとさげて、眼をぱちくりさせた。
「何処も此処も、どろどろの沼みたいになっているのが、今の世の中じゃないかね。え、仲由さん。」
「そうです。たしかにそうです、だから……」
「だから渡場を探していると、お云いかね。そりゃもう、ようわかっとる。だが、どの渡場も気に入らないのが、お前さんの先生ではないかね。」
子路は、相手が孔子を冷かしそうになったので、また両腕に力を入れた。しかし、彼は心の中で、相手の云うことに何かしら共鳴を感じた。うまいことを云う男だな、と思った。そして、内々自分が孔子に対して抱いている不平を、この男の口をとおして聞いて見たいような衝動に駆られた。彼は力みながら相手の顔を見つめた。
「沼に船を浮べては見たいが、泥水のとばっちりをかぶるのは嫌だ、と云うんじゃ、お前さんの先生も、少々虫がよすぎはしまいかね。今時、何処をうろついたって、満足な渡船なんか、見つかりゃしないよ。わかるかね、仲由さん。どうせ今の世の中が泥水の洪水見たいなものだとわかったら、なるだけ洪水の来ない山の手に避けているのが一等だよ。洪水だ、洪水だ、とわめき立てて、自分で泥水のそばまで行っちゃ、逃げまわっているなんて、そもそも可笑しな話さ。だい一、見っともないじゃないかね。」
子路は、半ば感心したような、半ば憤慨したような、変な顔をして突っ立っていた。
「おや、そのお顔はどうなすったい。孔丘の仲間だけあって、お前さんも、よっぽど悟りの悪い人間らしいね。そう世の中に未練があっては、話がしにくいが、しかし五十歩百歩ということもある。あの殿様もいやだ、この殿様もいやだというところを、ちょいと一つ飛びこして、この世の中全体に、見切りをつけて見る気には成れないものかね。気楽に高見の見物が出来て、そりゃいいものだぜ。わッはッはッ。」
「しかし……」
と、子路は非常に真剣な顔をして、何か云おうとした。だが、桀溺はもうその時には、その円い尻をくるりと子路の方に向けて、せっせと種を蒔いていた。そして、それっきり、子路が何と云おうと一言も返事をしなかった。
子路は、なぜか、もう腹が立たなかった。彼は、これまでにも、何度か隠士に出会ったことがあったが、今日ほど愚弄されたことはなかった。肝心の渡場は教えて貰えないし、おまけに孔子も自分も、まるで台なしにくさされてしまったので、ふだんの彼なら、黙っては引下れないところであった。しかし、今日の彼は、妙にしんみりとなってしまったのである。
隠士たちの物を茶化すような態度には、彼も流石に好意が持てなかった。しかし、彼等がいかにも自由で、平安で、徹底しているらしいのに、彼は強く心を打たれた。孔子の持たない、ある高いものを彼等は持っているのだ、とさえ彼には思えたのである。
彼は黙って踵をかえした。
彼は歩を移しながら孔子の車を見た。そしてその中にしょんぼりと坐っている孔子を想像した時、彼の眼がしらが急に熱くなった。彼は存分に孔子を詰りたいような気持にさえなった。そして一散に車のところに走りつけた。
おくれていた門人たちは、すでに車の周囲に集って、何かしきりに孔子と話していた。彼等は子路が走って来るのを見ると、話をやめて一斉に子路の方に顔を向けた。子路は、しかし、彼等の誰の顔も見なかった。彼は乱暴に彼等を押しのけて、いきなり車の窓枠に両手をかけた。
孔子は微笑しながら、
「どうしたのじゃ、えらく隙どったではないか。」
子路は、しかし、口が利けなかった。彼は何度も拳で荒っぽく眼をこすって、ただ息をはずませていた。
「隠士らしかったね。」
孔子は、子路の心を落ちつかせるように、ゆったりと云った。
「そうです。隠士でした。偉い隠士でした。」
子路は爆発するような声でそう云って、孔子の顔をまともに見た。
孔子の顔は静かで晴やかだった。それは子路が全く予期しない顔だった。彼はもっとみじめな顔を車の中に見出すはずだったのである。彼はあてがはずれたような気がした。
「ほう、それはよかった。そしてどんな話をして来たかね。」
孔子にそう云われて、子路はすっかり出鼻を挫かれてしまった。存分に自分の意見を交えて、孔子の反省を求めるつもりでいたのだが、もうそれどころではなかった。やっと事実を報告するのが、彼には精一杯だった。
孔子は眼をとじ、門人たちは眼を見張って、子路の話を聴いた。一通り話がすむと、門人たちは、云い合したように顔を見合せた。それから、いかにも不安そうな眼つきをして、めいめいに、そっと孔子の顔を覗いた。
孔子はやはり眼をとじたまま、しばらく考えに沈んでいたようであったが、深い吐息を一つもらすと、子路の方を向いて云った。
「それで、渡場に行く道は、どちらにするかね。」
子路はぎくりとした。荘厳な殿堂の中で、神聖な審問を受けているような気がして、棒のように突っ立った。
「わしは人間の歩く道を歩きたい。人間と一緒でないと、わしの気が落ちつかないのじゃ。」
と、孔子は子路から他の門人たちに視線を転じながら云った。
「山野に放吟し、鳥獣を友とするのも、なるほど一つの生き方であるかも知れない。しかし、わしには真似の出来ないことじゃ。わしには、それが卑怯者か、徹底した利己主義者の進む道のように思えてならないのじゃ。わしはただ、あたりまえの人間の道を、あたりまえに歩いて見たい。つまり、人間同志で苦しむだけ苦しんで見たい、というのがわしの心からの願いじゃ。そこにわしの喜びもあれば、安心もある。子路の話では、隠士たちは、こう濁った世の中には未練がない、と云っているそうじゃが、わしに云わせると、濁った世の中であればこそ、その中で苦しんで見たいのじゃ。正しい道が行われている世の中なら、今頃はわしも、こうあくせくと旅をつづけていはしまい。」
門人たちは、静まりかえって、孔子の言葉に耳を傾けた。子路の眼には、いつの間にか涙が一ぱいたまっていた。彼は、その眼を幾たびかしばたたいて、孔子の顔をまじまじとうちまもった。暮近い光の中に、人生の苦難を抱きしめて澄み切っている聖者の姿を、彼は今こそはっきりと見ることが出来たのである。
「先生、私は先生に対して勿体ないことを考えておりました。」
子路は、顔をまともに孔子に向けたまま、ぼろぼろと涙をこぼした。
孔子は、それに答える代りに、車の窓から手綱を子路に渡した。そしてみんなを顧みながら、朗らかに云った。
「子路の好きな方に行ってもらおう。間違っていたら、もう一度引きかえすまでのことじゃ。」
みんなが思わず笑い出した。子路も赤い眼をしながら笑った。
丁度その時、二人の隠士は、鍬を杖にして、一心にこちらを眺めていた。子路には、それが恰も二つの案山子のように思えてならなかった。彼は嬉しいような、淋しいような気分になって、孔子の車を動かしはじめた。
どこかで鴉が嘲るように鳴いた。
* * *

下村湖人『論語物語』(河出文庫)*大好評発売中!
*文庫版には該当箇所の原文も掲載されております。
また本文中、今日の観点から見て差別的と受け取られかねない表現がありますが、作品発表時の時代的背景を考慮し、原文通りといたしました。