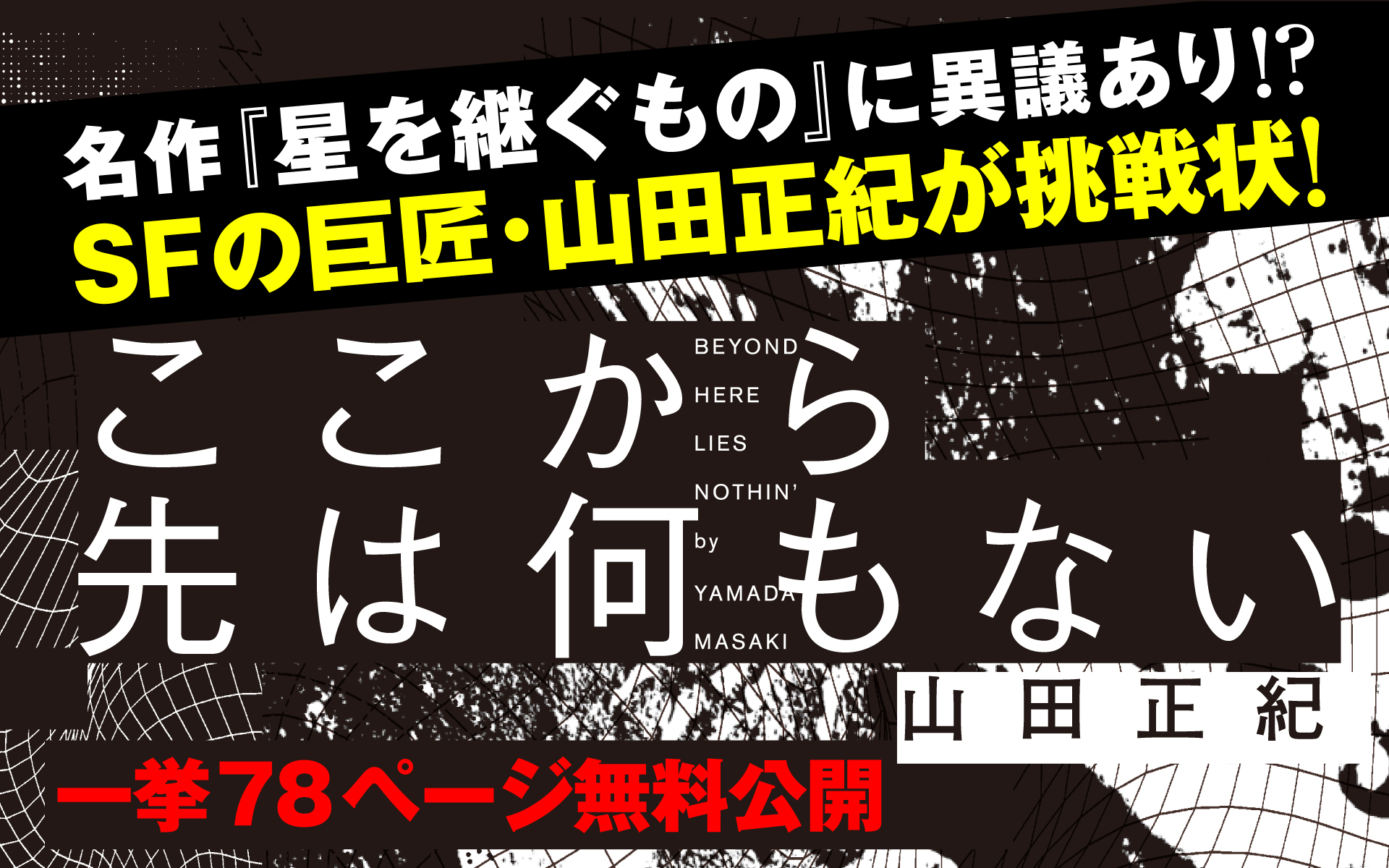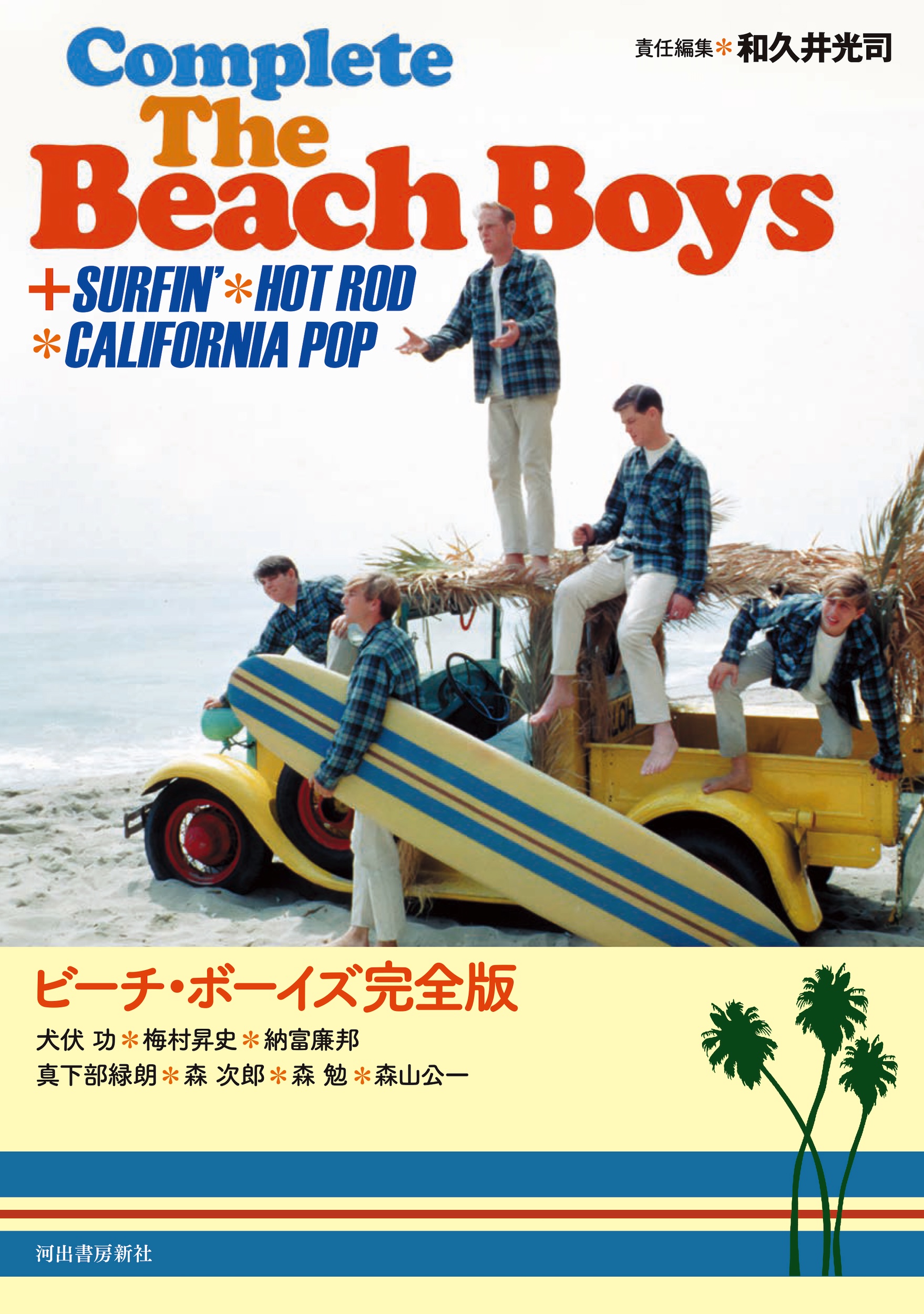文庫 - 日本文学
有吉佐和子『一の糸』待望の復刊が評判。酒井順子さんによる解説「赤姫の一生」を無料公開!
酒井順子
2022.08.08
有吉佐和子ファン、文楽ファン、書店さんから「復刊ありがとう!」の声を多くいただいている『一の糸』(河出文庫)。凄まじいまでに芸道を追求する男とそれを支える女の大正から昭和の戦後まで、波瀾万丈の人生を描く有吉佐和子の代表作の一つです。酒井順子さんによる解説「赤姫の一生」を無料公開します。

「紀の川」「華岡青洲の妻」「恍惚の人」「複合汚染」「非色」……驚くほど多ジャンルの小説を書き続けた有吉佐和子。そのなかでとりわけ濃密な描写で際立つのが、古典芸能ものではないでしょうか。
有吉は学生時代に「演劇界」への投稿から文筆をスタートし、歌舞伎、人形浄瑠璃、日本舞踊等々とものすごい勢いで古典芸能をわがものにしていき、20代で早くも人形浄瑠璃の新作台本まで手掛けるまでのめり込んでいるので、古典芸能の世界を描くのはひと際筆が乗ったに違いありません。
本書は造り酒屋の箱入り娘である茜と、その惚れた芸を究める文楽の天才三味線弾きで美貌の男の二人の波瀾万丈の人生を描きます。また同時に太夫と三味線弾きという、芸のうえでのいわば“夫婦”関係も濃密に描かれ、有吉ファン、文楽ファンにはこたえられない作品です。有吉作品を愛読され、文楽通でも知られるエッセイストの酒井順子さんに本書に魅力を語っていただきます。
(以下、酒井順子 解説 河出文庫『一の糸』巻末解説より転載)
解説 赤姫の一生
文字通り、三本の糸が張られた楽器である、三味線。右手で撥を、左手で棹を持ち、三味線の胴の部分を太腿に置いて構えた時、一番上になる糸が、「一の糸」である。
三本の糸の中でも最も太く、そして最も低く重厚な音を出す、一の糸。本書の主人公である茜が、父親に連れられて文楽公演に行った時、三味線の一の糸の音を聴いて衝撃を受けたことから、この物語は動き出す。「三味線弾きの心から直に観客の誰をも憚らず茜の躰にしみ通るように」響いたその音に、彼女の心は掴まれるのだ。
眼病のため目が見えない状態にあった茜は、常よりも聴覚への依存度が高くなっていたところで耳にした三味線の音に、惚れた。そしてそんな茜の姿に接した読者もまた、三味線弾きの露沢清太郎に、そしてこの物語に惚れることになる。
文楽を観に行った時、芸との衝撃的な出会いを果たしたという話を、しばしば耳にする。舞台上で役を演じるのは生身の人間ではなく、人形。物言わぬ人形の代わりにストーリーを語るのは、大夫。人間が演じる芝居を観る時とは異なり、観客はいつしか浄瑠璃を自身の中に取り込み、また自身が人形の中に入り込むことによって、精神の原初的部分が揺さぶられる感覚を抱くのだ。
有吉佐和子も、そのような経験を積んできた人なのではないかと、私は思う。有吉佐和子は、大学時代に歌舞伎研究会に所属し、歌舞伎専門誌『演劇界』への寄稿を始めた、著者。一九五六年、二十五歳の時には、地唄の大検校とその娘について描いた『地唄』が芥川賞候補となり、文壇に本格デビューを果たした。
同時期には人形浄瑠璃の新作台本や新作浄瑠璃を書く等、若き日の有吉佐和子は、伝統芸能との関わりの中で、その才能をほとばしらせている。やがて様々なジャンルの小説を書くようになっていくが、伝統芸能は有吉佐和子にとって、創作のベースとなっていたのではないか。
一九六五(昭和四十)年、著者三十四歳の時に刊行された本作は、三味線弾きの妻となった主人公・茜の一代記である。露沢清太郎の三味線に心を掴まれた茜はその後、紆余曲折を経た後に、彼の妻となった。
第一部にはその紆余曲折ぶりが記されているが、清太郎恋しさのあまり、茜が一人で大垣まで行って一夜を共にする様子は、文楽に出てくるある種の女性達と重ね合わせることができよう。
一度恋を知ったが最後、後先を考えずに突っ走っていく娘が、文楽にはしばしば登場する。茜の目が治ってから初めて見た文楽である「本朝廿四孝」に出てくる八重垣姫も、その一人。彼女は許嫁に危機を知らせるべく、氷結した諏訪湖の上を、まさに突っ走っていく。「本朝廿四孝」を見ながら茜は、八重垣姫と我が身とを重ね合わせて、号泣するのだった。
『一の糸』は、八重垣姫にもその後の人生がある、ということを示す物語である。現実を見れば、恋に突っ走るという、芝居の山場のような場面で人生が終わるわけではない。ヒロインはいずれは走ることを止め、その後は山やら谷やらを、地道に歩み続けなくてはならないのだ。
清太郎が妻子を持っていることを知った後の茜は、苦労を重ねる。父の死と家の没落、そして母の奮起と、人生は波瀾万丈の展開に。
清太郎改め徳兵衛と結婚してからも、苦労は絶えない。夫婦となってみると徳兵衛は気難しく、女の影も見え隠れする。先妻の子供達は容易に懐かないばかりか、日本は戦争に突入し、食べるものにも事欠く毎日に。
「本朝廿四孝」で言うならば、十種香の段、奥庭狐火の段の「その後」が、第二部以降には記されている。赤く豪奢な衣装を身につけた苦労知らずの〝赤姫〟のような茜に、その衣装を脱がなくてはならない時が来たのだ。
苦労を続けながらも、しかし茜は徳兵衛と別れることはない。一の糸と同様に、妻もまた替えがきかない存在なのだと気付いた茜は、妻という立場への自信を、次第に深めていくのだった。
茜・徳兵衛の夫婦と並んで描かれるのは、芸の上での夫婦とも言うことができる、徳兵衛・宇壺大夫の姿である。芸における相性はぴったりであるにもかかわらず、宇壺大夫からプライドを傷つけられた徳兵衛は、宇壺大夫と別れるばかりか文楽からも離れてしまうのであり、その孤独はやがて、彼の命を蝕むのだった。
徳兵衛・宇壺の別離の時期は、文楽界の分裂騒動とも重なっている。本作に記される会社側と組合側の分裂事件は実話であり、十四年にわたって分裂時代が続いた後、財団法人文楽協会の発足によって、一九六三年に両者は一つにまとまった。翌年から雑誌連載が始まった本作は、戦中・戦後の文楽の激動期についての記録的作品という側面も持っていよう。
別れぬ人達。別れる人達。そして別れても、元に戻る人達。この本に登場する人々は、それぞれが互いを愛しながらも、不器用な表現をぶつけ合うことしかできない。徳兵衛が宇壺大夫への怨讐をようやく乗り越えることができたのも、自らの死の直前だった……。
そんな徳兵衛を支える茜の中には、常に最初に聴いた一の糸の音が響いていたのだろう。大垣まで突っ走った茜は奔放な女に見えるが、しかし彼女は徳兵衛しか知らぬ一途な女として生きていく。少女時代の激しい恋情は、長い坂道のような夫婦生活を最後まで上り切るための、助走だったのだ。
結婚によって赤姫の衣装を脱いだ茜だが、相手を思い続けるという赤姫の精神は、年月が経っても、彼女の中から消えることはなかった。有吉佐和子は、その色褪せない赤色から主人公の名をつけたのではないかと、本を閉じた後に、ふと思う。