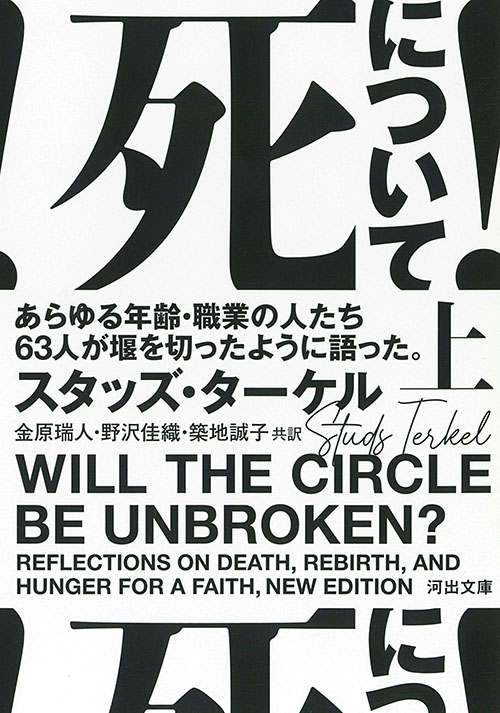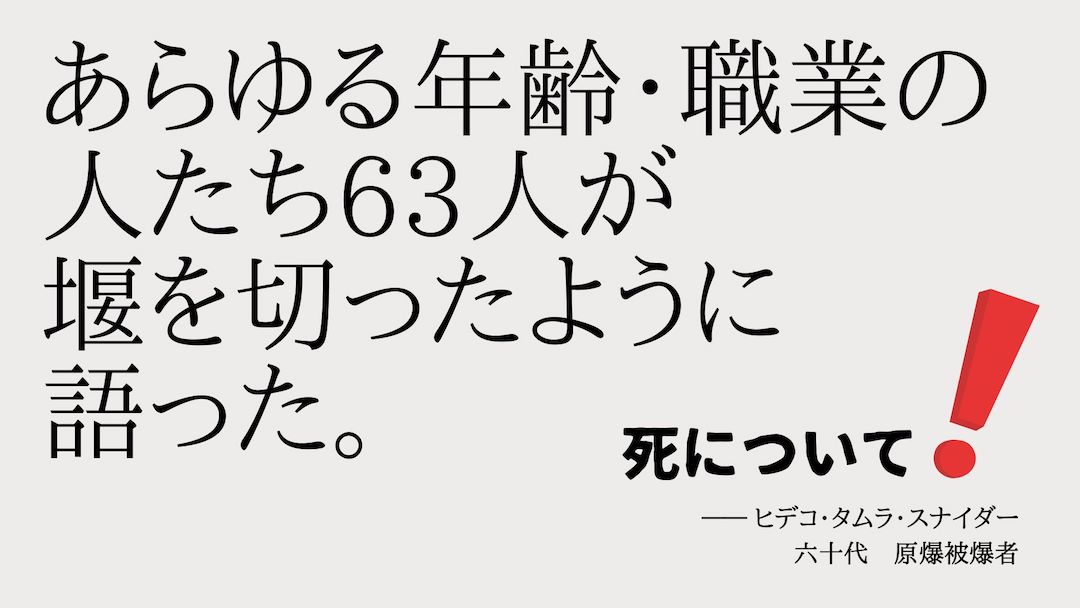
文庫 - 人文書
エノラ・ゲイはまだ上空にいる――原爆被爆者が語る『死について!』伝説的インタビュー集から先行公開
スタッズ・ターケル
2022.08.06
ピューリッツァー賞作家にしてインタビューの名手スタッズ・ターケル(『仕事!』『「よい戦争」』ほか)の名著『死について!』(金原瑞人,野沢佳織,築地誠子 共訳)の復刊が決定。看護師・葬儀屋・元麻薬常用者・外科医・戦争退役軍人などあらゆる年齢・職業の63人が「死」について語る大型インタビュー集です(2022年11月河出文庫より上下分冊で刊行予定:上巻書誌ページ/下巻書誌ページ)。
上巻収録作より、広島の原爆被爆者であるヒデコ・タムラ・スナイダーの語りを先行公開します。
※年齢はターケルによるインタビュー時のものです。
※著者による注は本文中に[ ] で、訳者による注は末尾に( )で示しています。
===
被爆者は、恐ろしい死と恐ろしい生を耐えねばならなかった。
そんなことは、もう二度とあってはいけないのです。
ヒデコ・タムラ・スナイダー
六十代 原爆被爆者
シカゴ大学付属病院で、精神科のソーシャルワーカーをしている。広島の被爆者のひとりとして、その瞬間をつづった回想録『ある晴れた日に(One Sunny Day)』を執筆した。
最近はみんな、ヒロシマのことをあまり考えなくなった気がするんです。毎年、カレンダーの八月六日に印をつけてもらえれば、広島に原爆が投下されたことを思い出して、それが人類にとってどんなことを意味するか、考える機会になると思うのですが。ヒロシマの問題は、死の問題すべてにつながっていますからね。
一九四五年の八月六日はよく晴れた日で、わたしにとって最高に幸せな日になるはずでした。両親に頼みこんで、学童疎開をしていた遠くの村から広島の実家に呼びもどしてもらったばかりで、さあ、これからはお父さんお母さんと一緒に暮らせる、と思っていたんです。学童疎開というと、(アメリカでは)まずイギリスの子供たちを連想しますが、日本の子供たちも疎開させられていたということは、ほとんど知られていません。どちらも小さな島国だから、事情は似ていたのに……。わたしの祖父は、その二年ほどまえに亡くなっていましたが、実業家で、大きな屋敷を持っていました。そこにわたしたち親子三人と、父の兄の一家が住んでいたのです。広島の市街地から一、二キロ離れたところで、屋敷にはとてもとても美しい庭がありました。けれどもあの日、幸福でのどかで美しい朝が一瞬にして消え去って……ありとあらゆるものが破壊しつくされました。炎と、灼熱と、倒壊の世界でした……。その日、母は仕事で街の中心に出かけていました。わたしにとって兄同然だったいとこも、同じように街の中心にいました。父は仕事で広島港に出かけていて、爆心地から三、四キロ離れたところにいました。わたしは、家の自分の部屋にいました。初め、敵機が二、三機飛来するという警報が出たんですが、しばらくすると「警戒警報解除」の放送がありました。だから、外にいた人たちは、シャツを脱いだ人も大勢いたんです。とてもよく晴れた日で、きれいな青空が広がっていました。
わたしは十歳で、もうじき十一歳になろうとしていました。前日の夜に疎開先からもどったばかりで、ずっと読書に飢えていたので、いとこが貸してくれた本を読みふけっていました。たしか、お侍の決闘の話か何かで――男の子の読み物でしたけれど。その日はお腹の具合が少し悪かったので、母がおかゆを作って置いていってくれたのを覚えています。突然、あたりがピカッと光ったのとほぼ同時に、ドッガァーンというものすごい音がとどろきました。それまできいたこともないような、すごい音でした。それから、ゴォーッという爆風がきて、家が地震のようにぐらぐら揺れて、つぶれるんじゃないかと思っていると、いろんなものが飛んできました。それが果てしなく続くように思えて、あたりは真っ暗で、ただただあらゆるものが落ちてきては身体にぶつかるのを感じていました。その底知れない闇のなかで、子供心に生まれて初めて、「わたし、死ぬんだ」とつぶやいたのを覚えています。そう口に出してしまうと、なぜか不思議と穏やかな気持ちになって、完全にパニックに陥ることはありませんでした。でも、熱風と破壊はとどまるところを知らず、いつまでもいつまでも続いて、もう永遠に終わらないように思えました。「そうか、これが戦争で死ぬってことなんだ。わたしはもうじき死ぬんだ」という言葉が頭に浮かんで。だから、ようやくすべてが終わったとき、わたしほどびっくりした人間はいなかったと思います。すべてが静かになって、自分がまだ生きていること、息をしていることに気づいたときは……ええ、ほんとうに驚きました。
家から出るのは、とても大変でした。身体が思うように動かなくて。それでもなんとか外に出てみると、あたりの景色は一変していました。初めは、何か大きな爆弾に直撃されたと思っていたので、庭の真ん中に大きな穴が空いているだろうと思ったのですが、そんな穴はありませんでした。そこで、屋敷の外に出てみました。屋敷はお城のように盛り土をした上に建っていたのですが、道に出ると、けがをした人やつぶれてしまった家がたくさんみえました。家のなかは、瓦礫の山でした。最初に目に入ったのは、地面に倒れているふたりの女の人で、血だらけになって、助けを求めていました。家のなかから、なんとか外に出ようとしている人もいました。全身すすだらけで、髪はぼさぼさで……。そのあと、けがや火傷をした人を大勢目にしました。
だれもが、一種のショック状態にあったんだと思います。当時の日本人はみな、忍耐を美徳とする文化のなかで育てられていました。痛いから、怖いからといって大声で叫んだりしてはいけない――それは恥ずべき行為である、と教えられていたのです。だから、みんなじっと耐えて、どんなことも切り抜けようと思っていました。痛みに声をあげたりしてはいけない、と。なかにはこらえきれなくて声をもらす人もいましたが、ほとんどの人はとても静かにしていました。そして息も絶え絶えに、小声で「助けて……」とつぶやいていたんです。でも、それだけにかえって、思い出すと胸が痛みます。ほんとうはすごく苦しかったのです。わたし自身は、ショックで凍りついたようになっていました。いまは戦争中で、これも戦争による破壊のひとつなんだということはわかったものの、実際に何が起こったのかまるでわからずにいたのです。表に出てからも、ひっきりなしに爆発音がきこえていました。おそらく軍の基地で、弾薬が爆発していたんでしょう。三十秒に一度ぐらい爆発がありました。街全体から煙が上がって、家から出てくる人たちはひどい状態でした。
わたしにできることは、日頃母から教えられていたとおりにすることでした。母は焼夷弾が落とされて炎に囲まれるのを恐れて、いつもわたしに「川のほうへ逃げなさい」と教えていました。太田川には支流が七つもあって、街のあちこちに川が流れていたんです。わたしは太田川をめざしました。すると、すでに川に飛びこんで溺れかけている人がたくさんいました。火傷がひどくて瀕死の状態だけどまだ生きていて、なんとか火傷の痛みを和らげようとしていたのです。母が街のどこにいるのか、わたしは知りませんでした。もし知っていたら、いまこうしてあなたと話してはいないでしょう。あとでわかったのですが、母は街の中心近くの家にいて、建物の下敷きになって焼け死んだのです。居場所を知っていたら、わたしもきっとそこへ行って、一緒に焼け死んでいたに違いありません。けれども、居場所を知らないわたしは、母をみつけ出すことができませんでした。
その次の日から、みんな散り散りになった身内をさがし始めました。たいていの人は、家族がどこにいるのかわからず、救援所に行くしかありませんでした。救援所といってもにわかづくりのもので、お寺の境内や本堂の床に大勢のけが人がごろごろと寝かされているだけです。人、人、人……そのなかを歩いていくのは、とてもつらかった。わたしは母の名前を呼んで、「お願い、返事をして」といいましたが、答えが返ってくることはなく、ただざわめきのようなものがきこえるだけでした。ひどいショック状態で、無意識に感情を閉め出していたけれど、懸命に母をさがし出そうとしました。でも、たまらない気持ちでした。お母さんがみつからない、お母さんがみつからない、どうすればいいの、と。お母さんに会いたいけれど、ここに寝かされている人たちのような状態なら会いたくない。だけど、お母さんが大好きだということ、一緒にいたいということは伝えたい……そんな思いで、半ば奇跡が起こるのを期待して、母に教わった歌を、わたしが歌うと母が喜んでくれた歌を口ずさみ始めました。(少し嬉しそうに)そして心のなかで、「どうか神様、この歌をお母さんのところに届けて、慰めてあげてください。お母さんをみつけられないわたしのかわりに」と祈っていたんです。そのときです、感情がもどってきて、わっと泣きだしたのは。泣いて泣いて、泣き続けました。けれども、これはすべての被爆者が、原爆から生き残ったすべての人が経験したことです。死んでいった人たちを助けられず、苦しみをともにできなかったことへの無力感。なにしろどんな爆弾が落とされたのか、知るよしもなかったのですから。また、爆弾によって直接火傷やけがを負わなくても、あとから苦しみだして死んでいった人たちが大勢います。放射線のせいです。どれだけ強力な放射線を浴びたことか……。放射線は骨髄や脳のなかまで透過していって、胎児にも影響を与え、奇形児が生まれました。けれども原爆が投下された当時は、自分を、互いをどうしたら助けられるのか、まるでわかりませんでした。原爆による死は大量殺戮で、尊厳などまるでありません。わたしたちは無力そのものでした。その場に居合わせた人だけでなく、多くの人を苦しめたのです。目にみえないものが、人間を、DNAを、植物を破壊したのです。
以前に、四つ葉のクローバーをさしあげましたね。あれと同じものが、太田川の土手一面に生えていたんです。クローバーの形も変わってしまって――葉が五枚あるものや六枚あるものが、そこらじゅうに生えていました。わたしはそれを摘みました。クローバーのDNAが変わってしまったのは、間違いありません。爆心地にいなかった人でも、黒い雨[広島と長崎で原爆が投下されたあと、焼けた物質の灰と放射性降下物を含んだ黒い雨が降った]に当たると肌にくっついてなかなか取れなかったものです。もっとも当時は、それがなんなのかわかりませんでしたが。わたしたちはみんなそういうものを、生物学的な影響だけでなく精神的な影響をも、背負って生きてきたのです。長いこと、原爆の記憶が心から離れなくて、苦しみました。若い頃はずっとそうでしたし、四十代、五十代になってもそれは続きました。けれども、この病院にきて尊厳死をみるようになって、少しずつ変わってきたのです。精神科で大勢の人を相手に経験を積んできて、死を理解するという難しい課題に取り組んだことが、転機になったのです。
わたしも一時は、原爆症のせいで生死の境をさまよいました。高熱が何日も続いて、意識が混濁していたのです。何か月ものあいだ、床を離れることができませんでした。どうやって回復したか、ですか? すごく時間がかかりました。いちばん悪かったときには、もう望みはないとまでいわれたそうです。そこへ、父の妹が生きているスッポンを二、三匹持ってきてくれました。そのおばは、スッポンの生き血を飲めば命が助かると信じていたのです。おばは父と一緒に苦労してスッポンの首を切り落とし、したたる血をガラス瓶に受けて、わたしに飲ませてくれました。それから、スッポンの肉でスープも作って、食べさせてくれました。当時は食糧難でみんな飢えていましたから、おそらくそのたんぱく質がよかったのでしょう、わたしの熱は下がり始めました。けれども、その次の年は学校に通えませんでした。仲のいい同級生で、わたしと同じ八月五日に疎開先から広島へもどった子がいましたが、その子は原爆で吹き飛ばされて死にました。彼女とは同じ村の、それも同じお寺に疎開していました。
兄同然だったいとこは、原爆の熱線で身体の表面が溶けて死にました。被爆したあと数時間は息があったのですが、服と皮膚はほとんど焼け焦げてなくなってしまっていたと、みていた人が話してくれました。ズボンに鉛の留め具がついていて、その一部だけは残ったけれど、あとはすべて燃えてしまったそうです。
母といとこのことを考えると、ふたりがどんな最期を迎えたかを思うと、胸に何かがこう……恐怖と悲しみがない混ぜになったような感情が湧き起こります。あのときあの場所にいて生きのびた人はみな、そういう痛みを、罪の意識をひきずっているのです。愛する人たちを失った悲しみ、その場に一緒にいられなかった悲しみ、無力だったことへの悲しみ。何が起こったのかもわからず、なんの警告も受けず、心構えもできていなかったのですから。母親も、いとこも大好きでした。何かしてあげたかったし、たとえ何もできなくても、そこに一緒にいて、「大好きよ。痛いのに何もしてあげられなくてごめん。でも、ここにいるから……」といってあげたかったのです。けれどもわたしたちは、アスピリンをあげることすらできなかった……当時はアスピリンなんてありませんでしたから、こんなことをいってもしかたないけれど。
そう、水さえもあげられなかったんです。日本の風習では、だれかが臨終を迎えると、必ず綿か何かに水を含ませて、唇を湿してあげるのに。あのとき身体を焼かれた人たちも、水をくださいと訴えていた。でも、あげられなかった。「水を飲むと死んでしまう。だから与えてはいけない」といわれて。そして自分は生きのびたけれど、あの人たちは死んでいった。みんな、「だれだれが死んだ。だれだれも死んだ」といって歩いていました。そんなときにうちの祖母がいったんです。「ちょっと、これじゃ死んだ人はみんないい人で、生き残ってるあたしたちは悪人みたいじゃないの」って。たしかにいわれてみるとそうでした。生き残ったことを、後ろめたく感じていましたから。
おじは祖父の工場にいて、建物の下敷きになったのですが、ガラスで深い傷を負ったところがひどく腫れてしまい、やがて脳ががんにおかされて死にました。わたしにスッポンを持ってきてくれたおばは、爆心地にはいなかったのですが、そのおじととても仲がよかったから、嘆き悲しんで死んでいきました。そのおばの姉にあたるもうひとりのおばは、お風呂に入ったあとで死にました。祖母は長いこと腹痛に悩まされたあげく、やはり死にました。父は六十代の初めまで生きのびましたが、あるときわたしに、「毎日ひどく疲れて、難儀だ」という手紙を送ってよこしました。その数日後のことです。日本から電話をもらって、父が死んだことを知ったのは。被爆者の多くは、「ぶらぶら病」と呼ばれる症状に悩まされました。いつもすぐに疲れてしまうんです。疲れやすいだけでなく、被爆者はがんにもかかりやすいのです。また、被爆者の女性が、異常に頭の小さい小頭症の赤ん坊を出産したというケースもあって、独身女性は被爆者であることを隠していました。当時は見合い結婚が主流でしたからね。被爆者で障害児を産む可能性があるということは、就職も結婚も難しいということでした。そして、得体の知れない病気にかかる危険が高いということでもありました。
(アメリカ軍による)占領時代、日本のマスコミは原爆症についてわかったことを発表できずにいました。その問題に関しては、いかなる出版物も出してはいけないことになっていたのです。ですから、どんな病気なのか、治療法はあるのか、ほんとうのところはだれもわからずにいました。そのうえ、日本が初めて戦争に負けたという事実。あの恐ろしい戦争で、国民はものすごく苦しみました。だからだれも、戦争のことは思い出したがらなかったのです。
けれども、もちろん、それは昨日のことのようにわたしの心に焼きついています。たっぷり心にしみこんだ記憶と恐怖とを、消し去るすべなどありません。
長いこと、恐怖に追い立てられるようにして生きてきました。なぜなら、わたしは死=大量殺戮というふうに結びつけて考えていたからです。そこには、死んでいく者に敬意が払われる余地などありません。原爆の記念碑や平和公園が作られて――それはいいことだけれど、わたしはこの目で原爆をみて、生き抜いてきたのです。だまされはしません。いいですか、原爆が恐ろしい事実であることに変わりはないのです。でも、そろそろ話を進めて、いまでは死に対する感じ方が変わったというお話をしましょう。
わたしは偶然に、まるで運命の手に導かれるようにして、いまの仕事に就きました。この病院で働くようになって最初に担当した瀕死の患者さんは、臓器移植を受けた方でした。一九八七年のことです。うちの子供たちが、シカゴ大学の敷地内にあるラブ・スクール[シカゴ大学の敷地内にある、評判の高い私立学校]に進学したので、わたしは仕事をさがしていました。「キャンパスで働きたいのです」と希望したところ、この病院で働けることになり、最初に与えられた仕事が肝臓移植を受けた患者さんのケアでした。殺菌消毒された白衣を着て集中治療室に入ると、ちょうど移植手術を受けたばかりのその患者さんが、手術室から運ばれてきたところでした。それはとても難しい、生死にかかわる手術でした。みると、患者さんはありとあらゆる生命維持装置につながれています。わかりますか? そのとき思ったんです。なんてすばらしいんだろう。この女性の命を救うために、あらゆる手段が講じられている。彼女の生命に敬意が払われている。あのとき広島で、救いの手をさしのべられることなく土や床の上で死んでいった人たち、薬も食べ物も水も与えてもらえなかった人たちとは大違いだわ、と。わたしは、こんなふうに人の命が大切に扱われているのをみて、ほんとうに元気がわいてきたのです。わたしにとって、生命を救うお手伝いができるのは、じつにありがたいことでした。広島では瀕死の被爆者たちを助けることができず、無力感と後悔にさいなまれていましたが、ここでは人の命を救うために積極的な努力が行なわれているのです。
それからです。長いこと押さえこもうとしてきた感情を、少しずつ取りもどしていったのは。まだ、正面から見据えることはできませんでした――とても恐ろしくて。でも、さまざまな形で人間の命を救おうとする試みがあるのだと気づいてからは、死についていろいろと考えられるようになりました。
もちろん、一夜にして成し得たわけではありません。エリザベス・キューブラー・ロス(1)、ミルトン・エリクソン(2)、ケン・モーゼズといった人たちの力を借りて、記憶と向き合っていったのです。死について考えると、底なしの悲しみを感じないではいられませんでした。打ち砕かれた夢や、母があまりに突然死んでしまったためにちゃんと答えてもらえなかった問いや、何年も何年ものあいだ心のなかに潜んでいた思いなどを、かなりありのままに表現できるようになりました。それでも、どうしてもわかってもらえない部分はあります。日本人であるわたしは、個人的な感情を表現するのがとても苦手だからです。
わたしにいろんなことを教えてくれたのは、じつのところ、担当した患者さんたちでした。たとえば、赤ちゃんや小さい子供のいる女性の患者さんは、この子たちを残して死ねないという思いがとても強くて、強烈な悲しみに襲われます。その姿をみていると、わたしにはほんの一瞬ですが、母が死ぬ間際にどう感じていたか、わかる気がしました。「わたしは死ねない。あの子を置いては死ねない」と思っていたに違いありません。自分だけでなく母も悲しかったことに気づくのは、とてもいいことでした。親を亡くすのはつらいことですが、子を残して死んでいく親のほうがもっとつらいでしょう。
ここで出会った患者さんひとりひとりが、自分の人生にわたしを迎え入れて、心の奥にある気持ちや考えを分かち合ってくれました。わたしは、そのひとつひとつを追体験させてもらったのです。おかげで、もう千人もの人生を生きたような気がしていて、そのすべてがわたしの心を豊かにしてくれました。患者さんたちから学んだことは、尊厳を持って死ぬことがいかに大切か、ということです。大量殺戮の場合、心の準備をするひまがありません。それは苦しみ以外の何ものでもありません。死ぬということは、自分とつながっているものすべてにお別れをいうことです。そのなかには物も含まれますが、もっと大切なのは人でしょう。残される者は死んでいくひとりの人とお別れをするだけですが、死んでいく人はこの世のあらゆるものにお別れをいうのです。
ヴェルディの初期のオペラ『ナブッコ』は、旧約聖書のバビロン捕囚を題材にしていて、ユダヤ人のコーラスが出てくるのですが、わたしはそれを初めてきいたときに大好きになりました。のちに歌詞の意味を知って、強制労働させられたユダヤ人が故郷を恋こがれて歌う歌だとわかると、さらに深い共感を持ちました。わたしの心の奥にも、同じ思いがあるからです。「わかるわ、その気持ち。わたしも故郷が恋しいもの」と思いました。けれども、気持ちが落ち着いてから考えてみると、じつはわたしが恋しく思っているのは、再建されて無秩序に広がっている大都会の広島ではなくて、祖父の屋敷の庭であり、自分自身の家なのだとわかりました。わたしがほしいのは、お母さんのいる家、現実にはもう存在しない家なのです。死とは、故郷に帰ることです。わたしたちは意識のどこかに、産道を下って世に出たときのことを記憶しています。その記憶のテープレコーダーが回りだすのは、ずっとあとになってからかもしれませんが、おそらく細胞は記憶しているのです。わたしはその故郷に帰るのです。今までの記憶を越えて。ですから、死とは、この世界から消え去ることであると同時に、どこか別の場所に移動して、姿かたちを変えることだと思っています。
十代の頃、すっかり気落ちしてどうしていいかわからず、川の土手に座っていたことがあります。奇形のクローバーを摘んだのもこのときで、日暮れ近くに川がとうとうと水をたたえて流れていくのをみていました。茜色に染まっていた穏やかな川面が、しだいに夕闇に包まれていくとき、色づいた水面が風を受けて静かに踊っているようにみえました。そのとき、ほんの一瞬ですが、天にでもいるような穏やかな気持ちになれたのです。最悪の時だったにもかかわらず。それと同じで、自分がいおうとしていることをわかってもらえたときは、天にも昇る心地になります。意思の疎通ができて、気持ちを分かち合えることこそ、このうえない幸せなのです。
わたしの場合、故郷の話をすると、どうしても死と結びついてしまいます。それでも、子供たちが十代後半になったとき、広島へ連れていきました。人生の重要な一時期を過ごした場所を、みせたいと思って。それまでは故郷に帰るたび、どうしようもなく気が滅入って悲しくなったものでしたが、そのときはちょっと違う経験をしました。当時を生々しく思い出すようなものはみたくなくて、まだ一度も平和記念資料館に入ったことはなかったのですが、子供たちにはぜひみせたかったので連れていきました。そこで、あるものを初めて目にしました。中央の円形大広間の大きなスクリーンに、実物大のエノラ・ゲイ(広島に原爆を投下したB29爆撃機)が白黒で映し出されていたのです。原爆が投下される直前の、ほんの一瞬の様子を映しているのです。わたしは思わず、両手を前に突き出して、エノラ・ゲイの動きを止めようとしていました。そして思い出したのです。原爆が投下されるまえは、みんな飢えてはいたものの、どんなに無邪気で元気だったかを。すると、涙がこみあげてきました。泣いて泣いて、しゃくりあげるほど泣いて、「やめて、お願い、やめて」とつぶやいていました。かなわぬ願いだと、エノラ・ゲイは動き続けるのだとわかっていながら……。
やがて、はっと思いあたりました。ある意味で、エノラ・ゲイはまだ上空にいるのだと。いつか核兵器を使って戦争をするかもしれないとわたしたちが思っているかぎり、そこにとどまり続けるのだと。だって、人類の歴史のなかで、持っているのに使わなかった兵器などないのですから。それで、思ったのです。わたしは最後の息を引き取るまで、ヒロシマの経験を訴え続けていかねばならないと。なぜなら、人類に対して核兵器が使用されたのは、ヒロシマが史上初めてだったのだから。そして、原爆を投下されたのも、投下したのも、同じ人類なのだから。どうか、八月六日を忘れずに、ヒロシマの日としてカレンダーに記してください。そして、生と死はとても密接につながっていること、命はかけがえのないものであることをわかってほしいのです。命あればこそ、愛し愛され、敬い、尊び、話し、歌い、祝うことができるのです。最後に息を引き取るそのときまで。(ささやくように)被爆者は、恐ろしい死と恐ろしい生を耐えねばならなかった。そんなことは、もう二度とあってはいけないのです。
(1)スイス生まれのアメリカの精神科医(1926-2004)。主著に、ターミナルケアのバイブルといわれる『死ぬ瞬間』(鈴木晶訳、中公文庫、改版2020年)等がある。
(2)心理療法家(1901-1980)。「催眠の魔術師」と呼ばれた。著書には『ミルトン・エリクソンの催眠の現実』(共著、横井勝美訳、金剛出版、2016年)等がある。彼の催眠療法についての研究書は多数邦訳されている。
===
こちらの語りと、他、刑事・救急救命士・牧師・作家・ラジオパーソナリティーなど残る62人の語りは2022年11月上旬刊行予定 『死について! あらゆる年齢・職業の人たち63人が堰を切ったように語った。』に収録予定です。