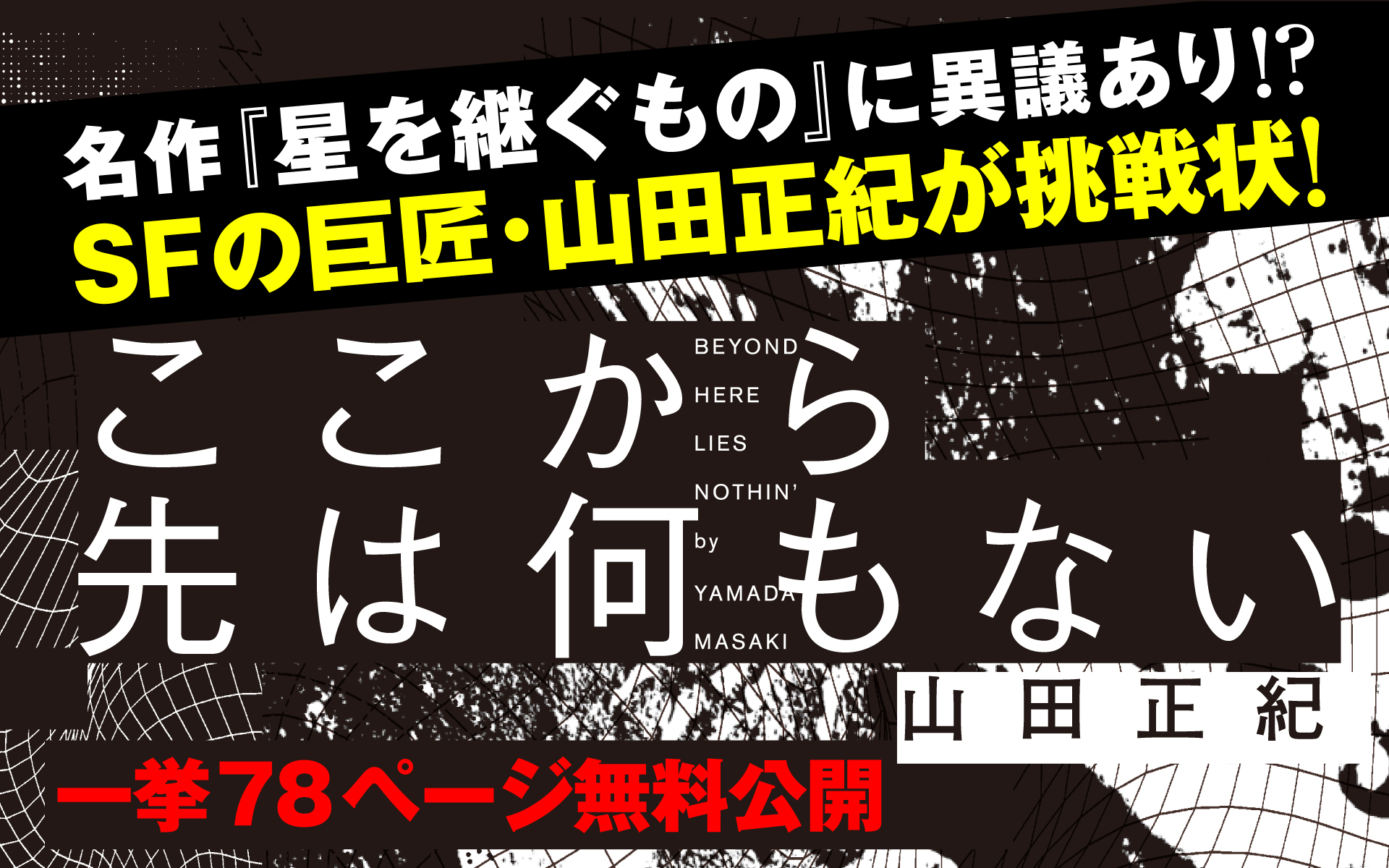文庫 - 日本文学
【読み放題フェア開催中】羽田圭介『隠し事』ほか電子書籍全48作品が読み放題!
【解説】陣野俊史
2016.04.13
PR:【電子書籍の読み放題フェア開催中/ブックパス】
ただ今ブックパスでは、創業130周年記念・河出書房新社フェア開催中!
「映像化作品特集」「芥川賞作家特集」「必読!文芸作品」「長野まゆみ特集」の4つのテーマで、全48作品が今なら読み放題でお楽しみいただけます。
—————————————————————————-
『隠し事』
羽田圭介
【解説】陣野俊史
そして情報は漏れつづける
この小説は『文藝』二〇一一年冬号に掲載された。単行本は、二〇一二年一月に刊行されている。二〇一一年冬号ということは、この年の秋には人の目に触れる状態だったことになり、とすれば、それ以前、つまり二〇一一年の上半期くらいの時間に書かれたのでは、と推測する。もっと前に書かれた可能性も高いのだが……。むろんこの年は、東日本大震災の年で、文字通り、日本の社会は大揺れに揺れていた。その中で、彼女の携帯電話(以下、「ケータイ」と呼ぶ)にこれだけ執着する若い男の小説を書くというのは、ある意味、強い集中力を必要としたのではないかと思う。みんなが同じ方向を向いているときに、あえてそちらを見ない、というか。
それと、文庫になるとわからなくなることがあって、この小説の単行本についていた帯に、あるデータがグラフ化されていた。「モバゲーリサーチ調べの公開データをもとに図表作成」と但し書きがあって、「恋人(夫や妻を含む)の携帯電話、黙って見たことはある?」という問いに対する答えだ。「ある」男性(20代〜30代)48パーセント、女性(20代〜30代)72パーセント……。この数字をみて、何かを感じ取れ、というほうが無理なのかもしれないし、ええっ、そんなにみんな恋人のケータイを覗いているの? と半信半疑になる人もいるだろう。やや気になるのは、主人公の恋人「茉莉」が使っている「ピンクゴールド」のケータイが、普通に読む限りにおいて、パツンと畳み込むタイプの、例のガラケーに思えることだ。著者が書いている時点(これは推測でしかないが)が、二〇一一年の上半期だったとすれば、すでにアップルのiPhoneは日本でも販売されているわけで、どうしてこの小説の根幹にあるケータイはガラケーであって、スマホじゃないのか、というところも気にはなるのだ。
アップル社のiPhone4sが二〇一一年十月発売で、このスマホが世界じゅうでバカ売れして以後、圧倒的な勢いでスマホがわれわれの日常に浸食してきたという説を信じるならば、この小説の書かれたタイミングが、スマホの一般化の直前だったということはあるだろう。だから「茉莉」と「僕」のケータイはガラケーなのだ、と一応は言えるのかもしれない。それはそれでガラケー最後の小説として、貴重な文化史的証言の小説のようにも思うのだが、いや、それより何より、私がどうしてこれほどスマホとガラケーの差異にこだわるかといえば、ガラケーとスマホではセキュリティの面で格段に差があるように思うから。スマホだと指紋認証や暗証番号といったセキュリティ確保のためのハードルが高いように思う。ガラケーなら(茉莉のケータイを毎晩チェックし続ける主人公みたいに)簡単にメールを開いたり住所録をチェックしたりできるのかもしれないが、なんてったって、いまはスマホの時代。ひょっとして、こんなに簡単にケータイのコンテンツにアクセスできるのは、小説として隔世の感を読者に与えてしまうんじゃないのか──と、余計な、しかし、どうにもぬぐいがたい心配を抱いてしまうのだ。
そこで、非常勤で教えている大学の、あるクラスでアンケートをしてみた。対象者は約50名。都内の某有名私大。文学部の三年生と四年生。サンプル数が少ないのはご容赦ねがいたい(急なアンケートだったもので)。他人のケータイなど見ません、と(憤然として?)答えた人が、2割。友達の話ですけれどという前提で、何らかの形で覗き見る、あるいはチェックすると回答した人が、8割。ふーん、意外に多いなぁ。知りたいのは、セキュリティはどうやって突破しているかということ。指紋認証は? 恋人のスマホに、自分の指紋を登録させているのだそうだ(まあ、指紋の登録を拒否すればそれだけ怪しいというオチにはなるのだろう)。暗証番号が設定してあっても、彼氏ないし彼女が暗証番号を打ちこんでいる姿を横目にしながら暗記するらしい(これはありがち)。つまり、スマホのセキュリティもさして高くはない。親密な関係になればなるほど、セキュリティは確保できない。「茉莉」と「僕」みたいに……。それにしても、学生のアンケートで最も震えたのが次の言葉だった。「今は、恋人のメールとか着信履歴とか見れるアプリがあるらしいですよ。怖。」
ホント、怖い世の中である。
小説の解説らしく、文学の話をしよう。
付き合って七年の若い男女が、互いに隠し事をしないで(あるいは、そう思い込んで)同棲してきて、ふとしたきっかけで男が女の行動に疑いを持ち、猜疑心にかられて、女のケータイを細部まで吟味し(彼女のケータイの「電源アダプター差し込み口についている細かな線傷」を思いだし、家の充電器ではそんな傷がつくはずがないと考え、「やはりホテルか」と彼女の浮気を確信するくだりは、妙な説得力を持っている……)、と思いきや、女のほうがすでに男のケータイに「転送設定」をほどこしていて、男のケータイのメールは、女の指定した転送先のPCにダダ漏れしていた……。と書くと、ごく親密なカップル間の関係性を描いただけの小説のように捉えられるかもしれないが、そうではない。
この二人の間には、隠しごとを隠しておくべき場所がない。ケータイもしかり。すべての情報は漏れつづけている。
このとき、小説の進むべき道は二つ、ある。
ひとつは、隠しごとを隠しておける場所を作ることである。「僕」は、フランセス・A・イエイツの『記憶術』を繙くのだ。このくだり、読んでいて大笑いした。あの、イギリスのネオ・プラトニズム研究者の分厚い書物(邦訳はあります)を参照して、頭の中に神殿を築く。そこに出来た空間に記憶したいモノを配置していく……。この記憶の仕方は「場所法」と呼ばれているのだが、これが単に衒学趣味で小説に導入されているのではなく、隠しごとを隠しておくべき場所として、記憶術が有効活用されているのだから、羽田のマニアックぶりに脱帽したことを正直に告白しておこう。
もうひとつの小説の進むべき道はこうだ。漏れつづけている情報など、どれほど漏れてもいい。そんな情報によって把捉できるのは、些末なことにすぎない。つまり、情報として窃視している事柄の無意味さを物語の中で宣言する道である。
茉莉は、最後にこう言うではないか……。「ねえ……私のケータイを見て、私のことがわかった?」
「僕」は答えない。二人の部屋の外では雨が降っていて、その音が大きくなるだけだ。いい場面だけれど、修羅場でもある。もし「僕」が茉莉のことが「わかった」と答えれば、茉莉は、ケータイごときでわかるはずがないと冷笑するだろうし、「わからない」と答えていれば、じゃ、どうしてケータイを窃視し続けたのか、となじるだろう。どちらに転んでも、茉莉の勝ち。そんなことはわかっているから「僕」は答えない。答えないことで、ケータイから漏れている情報が、おそらくは無意味なのだが判断を宙吊りにしておく、という態度に自分をスライドさせている。でもこの態度も一時的なものにすぎず、結局、ケータイ以外に元カレたちと「真の関係」をどこかで保っているじゃないか、との疑心暗鬼が頭をもたげるのだ。男は、揺れる。
このあたりの、揺れる男心が、羽田の真骨頂なのだと思うが(これは、芥川賞受賞作『スクラップ・アンド・ビルド』まで一貫して流れている)、一方で、若い女は存外ドライなので、結局、「僕」を、ケータイを盗み見る情けない男として断罪することになるだろう。覚悟すべし。そういえば、前述した大学生のアンケートの回答にこんなのがあった。「友達の彼氏はケータイを必ず見るそうです。気持ち悪いので別れるようにすすめようと思います」。