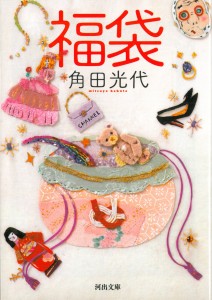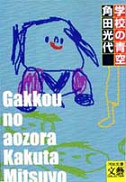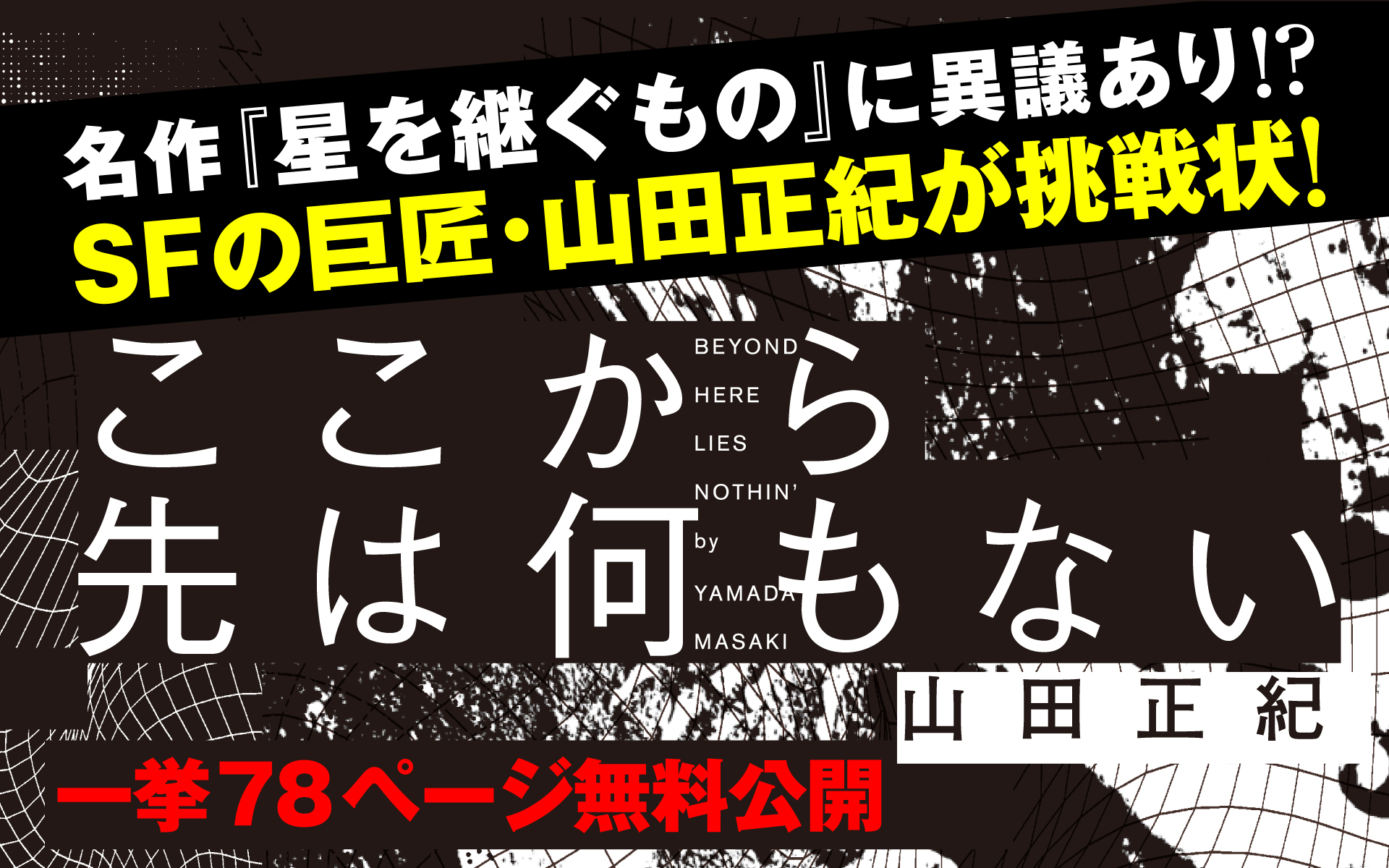文庫 - 日本文学
【読み放題フェア開催中】角田光代『福袋』ほか必読の全48作品
【解説】栗田有起
2016.04.20
ただ今ブックパスでは、創業130周年記念・河出書房新社フェア開催中!
「映像化作品特集」「芥川賞作家特集」「必読!文芸作品」「長野まゆみ特集」の4つのテーマで、全48作品が今なら読み放題でお楽しみいただけます。
—————————————————————————-
『福袋』
角田光代
【解説】栗田有起
愛のまんまんなか
街なかで走る角田さんを見かけたことがある。
彼女は週に20キロ近く走っているそうである。視界のはしに彼女が現れたとたん、はっと目を奪われた。ジョギングするひとは珍しくないが、彼女の姿には特別な何かがあった。見えなくなるまで追い、まぶたに残像が焼きついて消えなかった。いいもの見たなあ、と思った。どこにでもありそうなのに、特別なこと。まさに角田さんの書く小説だ、そう思った。
八篇の短編に登場する人物は私たちの隣人といっていいだろう。どこかですれちがってもおかしくないほど、私たちの日常に近いところで暮らしている。ごくおだやかに日々を営む彼らが、ある日特別な出来事に見舞われる。そのあと、それまでとおなじようには生きられないという意味で、その出来事は重大な意味を持つ。
『カリソメ』に登場する夫婦は離婚間近、夫が妻以外の女性と恋に落ちたせいである。出ていった夫宛てに同窓会の知らせが届き、妻は彼の代理として会に出席する。大学の同級生が評する彼は、妻のまったく知らない人物であった。自分が結婚していたのは「仮」の男だったのか。
『犬』の主人公は、生まれてはじめて女性と同棲する。彼らの新居に一匹の犬が出現し、それによって彼女の人となりが露わになってゆく。人と深くかかわることの真実を知る主人公は「現実と自分が乖離してしまったような淡い離脱感」をおぼえる。
どちらもこわい話だ。自分と別れてくれという夫の同窓会に出席する妻、想像するだけで身のうちがちくちくする。一匹の犬に執着する恋人も空恐ろしいし、犬を失った彼女にたいして主人公が心のなかで放つ言葉も衝撃的だ。と同時に、読んでいるこちらの、ひとにはいえない黒い好奇心が満たされる快感もひそかにあったりする。「だれかとともに暮らすということは、(中略)不気味なことなのかも」と『犬』の主人公が思うその不気味さを、私たちも抱えているのである。
角田さんの小説には本当のことしか書かれていない。本当のことを知るのはときにこわい。けれども知らずにはいられない。だとしたら、こわさに耐えられるくらいに私たちは強くならなくてはいけない。角田さんのこわい小説を読んでいると、いつもそう思わされる。
走らない私には、20キロの距離を走るというのはものすごく大変なことに思える。つらくないですかとかつて角田さんに聞いたことがあった。仲間とマラソン大会に出場もするというのだから、よほど走ることが好きなのにちがいない。笑顔で否定されるだろうと思ったのだが、彼女はすぐさま「苦しいよ〜」と答えた。眉根をよせて、いかにもつらそうな表情を浮かべながら。
だったらどうして走りつづけるのだろう、と嫌なことからすぐに逃げ出すへなちょこの私は考えてしまう。つらくて苦しいのに、なぜ? しかしこの質問を、書くことに置きかえてみたらどうだろう。角田さんは毎日のように締め切りが、それもいくつも重なってある。小説はもちろんのこと、エッセイ、書評、旅へ出かけてルポルタージュを書く。誰に読ませるつもりのない日記までも書いているという。
それだけ書くのだから、よほど書くことが好きにちがいない、とは、さすがに考えない。おなじく小説を書くものとして、毎日毎日、楽しくてしょうがないわ〜と仕事をするはずがないと思う。でも仕事はやめない。書かなくてはならないからだ。誰に命令されたわけではない。自分のために書くのである。走ることもおなじなのだろう。走らなくてはならないから走る。自分のために、走る。
愛することも似ているのかもしれない。あるいは、生きることにも。
『イギー・ポップを聴いていますか』の主人公は家の近くに置かれた紙袋を拾う。中身はビデオテープ。主人公は次々とテープを再生してみる。どんな人物が持ち主だったのか、テープの内容で推測していくのだが、最後の一本で事情は明らかになる。持ち主の心情を想像するうちに、主人公はみずからの夫婦関係について思いいたる。
「ぼくらは愛のはじまりでも終わりでもない、ちょうどまんまんなかにいる、と唐突に気づく。金太郎飴の、あの退屈な、金太郎の顔がちょうど歪んだあたり。」
苦しくつらいことから逃れるのが優先されるのなら、誰もひとを愛したりはしない。愛するのには力がいるし、勇気がいる。人生をかけた大ごとだ。言葉にすると大袈裟だが事実なのだからしょうがない。
人生をかけた大ごともしかし、日々のなかにあれば通勤や家事や雑用みたいに当たり前の顔をしている。ついつい、「退屈」を感じてしまったりする。
私たちに必要な強さは、日常の「退屈」という重たさ、わずらわしさに耐えうるものでもあるのだろう。
八篇に登場する、私たちによく似た人物たちも日常にまみれ、その重みにあえいでいるように見える。けれども、彼らはそこから逃げはしない。逃げたという自覚を持ったとしても、やはりみずからの持ち場にとどまる。そうするしかないから、というあきらめがあったとしても、それでも。
「ひょっとしたら私たちはだれも、福袋を持たされてこの世に出てくるのではないか。福袋には、生まれ落ちて以降味わうことになるすべてが入っている。希望も絶望も、よろこびも苦悩も、笑い声もおさえた泣き声も、愛する気持ちも憎む気持ちもぜんぶ入っている。」(『福袋』)
角田さんの小説は人生を手ばなしに肯定しない、否定もしない。あるがままの人生が描かれている。だから、やりきれない感情が湧き、にがい後味が舌に痛いこともままある。なぜなら生きることはつねに「まんまんなかにいる」ことで、途中にいるということはつまり、善し悪し、幸不幸、の判断をつけられないということだから。
私たちは福袋の中身を選べない。捨てることもできない。「それはただそこにある。自分だけに持たされたものとしてそこにある。」私たちにできるのは、味わうことだけだ。すべてを自分だけのものとして、一生かけて慈しみ、ひたすら愛でるのだ。そのうちにあるとき突然、ちらりと美しいものが現れる。その美しいものが放つ光はきっとこの身をあたたかく照らす。どんな結末でも、角田さんの小説はいつもそう信じさせてくれる。