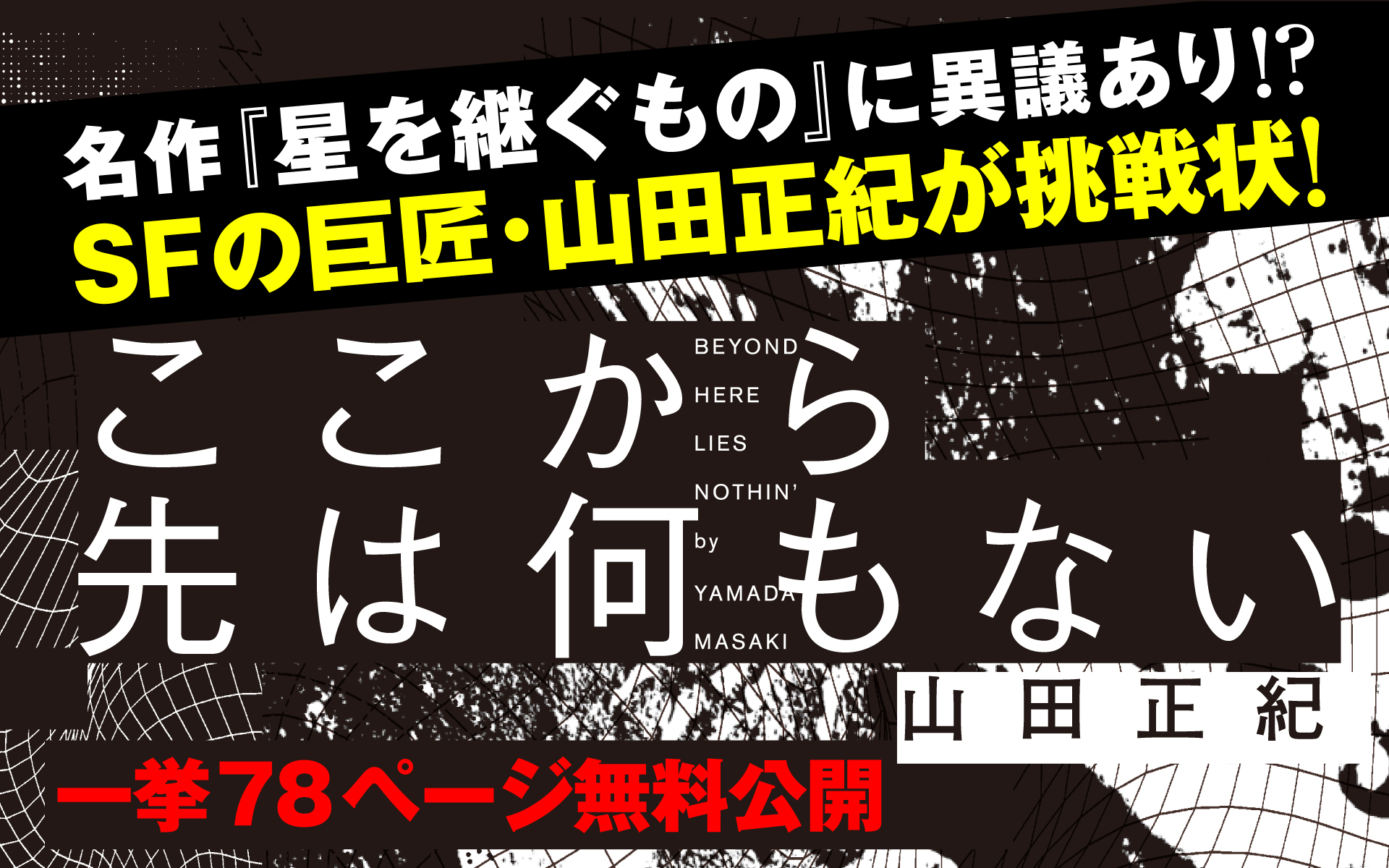文庫 - 日本文学
ついに37万部突破!全米図書賞受賞『JR上野駅公園口』試し読み
柳美里
2021.02.10
JR上野駅公園口
冒頭試し読み
柳美里
また、あの音が聞こえる。
あの音──。
聞いている。
でも、感じているのか、思っているのか、わからない。
内側にいるのか、外側にいるのかも、わからない。
いつ、いつか、だれ、誰だったのかも、わからない。
それは肝心なこと?
肝心だったこと?
誰、なのか──?
人生は、最初のページをめくったら、次のページがあって、次々めくっていくうちに、やがて最後のページに辿り着く一冊の本のようなものだと思っていたが、人生は、本の中の物語とはまるで違っていた。文字が並び、ページに番号は振ってあっても、筋がない。終わりはあっても、終わらない。
残る──。
朽ちた家を取り壊した空地に残った庭木のように……
萎れた花を抜き取った花瓶に残った水のように……
残った。
ここに残っているのは、なに?
疲れ、の感覚は、ある。
いつも、疲れていた。
疲れていない時はなかった。
人生に追われて生きていた時も、人生から逃れて生きてしまった時も──。
はっきりと生きることなく、ただ生きていた気がする。
でも、終わった。
ゆっくりと、いつものように見る。
同じではないが似ている風景──。
この単調な風景のどこかに、痛みが在る。
この、似たような時間の中に、痛む瞬間が在る。
見てみる。
たくさんの人が居る。
みな、一人一人違う。
一人一人、違う頭を持ち、違う顔を持ち、違う体を持ち、違う心を持っている。
それは、わかっている。
でも、離れて見ると、同じか、似ているようにしか見えない。
一人一人の顔は、小さな水溜まりのようにしか見えない。
初めて上野駅のプラットホームに降り立った時の自分の姿を、山手線内回りの到着を待つ人々の中に探してみる。
鏡や硝子や写真に映る容姿を見て、自信を持ったことはなかった。とりわけ不細工ではなかったと思うが、誰かに見詰められるような容姿であったためしは一度もなかった。
容姿よりも、無口なことと無能なことが苦しかったし、それよりも、不運なことが堪え難かった。
運がなかった。
また、あの音が聞こえる。あの音だけ、血が通っているような──、鮮やかな色の付いた流れのような音──、あの時は、あの音の他には何も聞こえなくなって、あの音が頭蓋の内側を駆け巡って、頭の中に蜂の巣があって何百という蜂が一斉に頭から飛び出そうとしているかのように騒がしく熱く痛くなって、なんにも考えられなくなって、瞼が雨に打たれているかのようにぴくぴく震えて、拳を握り締めて、全身の筋肉を縮めて──。
ずたずたに引き裂かれたけれど、音は死ななかった。
捕まえて閉じ込めることもできなければ、遠くに連れ去ることもできない、あの音──。
耳を塞ぐこともできなければ、立ち去ることもできない。
あの時からずっと、あの音の側に居る。
居る──?
「まもなく2番線に池袋・新宿方面行きの電車が参ります、危ないですから黄色い線までお下がりください」
プォォォン、ゴォー、ゴトゴト、ゴトゴトゴト、ゴト、ゴト、ゴットン、ゴットン、ゴ、トン、ゴ……トン、ブーン、ルゥー、ブシュウーキキ、キキ、キィ、キ……キ……キ……ゴトッ……シュー、ルルル、コト……
*
JR上野駅公園口の改札を出て、横断歩道を渡ったところにある公孫樹の木の植え込みの囲いには、いつもホームレスたちが座っている。
あそこに座っていた時は、親を早くに亡くした一人っ子のような心持ちになったものだが、福島県相馬郡の八沢村から出たことがない両親は二人とも九十歳を超える天寿を全うしたし、昭和八年生まれの自分につづいて、ほぼ二年置きに、長女のはる子、次女のふき子、次男の英男、三女のなお子、四女のみち子、三男の勝男、四男の正男と下に七人もいて、末の正男とは十四歳も違ったから、弟というよりは子どもみたいなものだった。
けれど、時は過ぎた。
ここに、一人で、座っていた、歳を取り──。
束の間の浅い眠りの中で疲れた鼾をかいて、時折目を覚ますと、公孫樹の木の葉が描く網のような影模様が揺れて、あてどなく彷徨っている気がした、ここに居るのに、もう何年もこの公園に居るのに──。
「もう、いい」
眠っているように見えた男の口からはっきりと言葉が飛び出し、口や鼻の穴から白いけむりがそっと立ち上った。右手の中指と人差指に挟まった煙草の火は、もうじき指を焦がしそうだ。長年の汗や垢で元の色が判らないほど変色はしているが、ツイードの鳥打ち帽、格子縞の上着、茶色い革のブーツは外国の狩人みたいな出で立ちだ。
山下通りの坂道を鶯谷の方に向かって走る車──、信号が青になり、視覚障害者用信号機の誘導音が、ピヨッ、ピヨピヨッと流れると、上野駅公園口改札から出てきた人が横断歩道を渡ってくる。
男は体を前に傾がせたまま、横断歩道を渡ってくる身綺麗な格好をした家のある人たちの姿を眺める、視線の止まり木を探すように──、そして、まるでそうする力しか残っていないかのような震える手で煙草を、白髪の方が多い髭だらけの口元まで持ち上げて吸い、長々と溜め息を吐いて考え事を打ち切り、老いた指を広げて煙草を落とし、色褪せたブーツの爪先で吸殻の火を踏み消した。
足の間に拾い集めたアルミ缶の入った90リットル半透明ごみ収集袋を置き、透明なビニール傘を杖のように握り締めて寝ている別の男……
白髪を輪ゴムで団子頭にしている女は、隣に置いた臙脂色のリュックサックの上に重ねた両腕を枕にして突っ伏している。
顔ぶれは変わったし、数も減った。
バブル崩壊後は数が増え、公園内の遊歩道と施設以外の場所はブルーシートの「コヤ」で埋め尽くされ、地面や芝生が見えなくなるほどだったのに──。
天皇家の方々が博物館や美術館を観覧する前に行われる特別清掃「山狩り」の度に、テントを畳まされ、公園の外へ追い出され、日が暮れて元の場所に戻ると、「芝生養生中につき立ち入らないでください」という看板が立てられ、コヤを建てられる場所は狭められていった。
上野恩賜公園のホームレスは、東北出身者が多い。
北国の玄関口──、高度経済成長期に、常磐線や東北本線の夜行列車に乗って、出稼ぎや集団就職でやってきた東北の若者たちが、最初に降り立った地が上野駅で、盆暮れに帰郷する時に担げるだけの荷物を担いで汽車に乗り込んだのも上野駅だった。
五十年の歳月が流れて、親兄弟が亡くなり、帰るべき生家がなくなって、この公園で一日一日を過ごしているホームレス……
公孫樹の木の植え込みのコンクリートの囲いに座っているホームレスたちは、寝ているか、食べているかのどちらかだ。
紺色の野球帽を目深に被り、国防色のシャツを着て、黒いズボンの膝にコンビニ弁当を置いて食べている男……
食べものに困るということはなかった。
上野には老舗のレストランがいくつもある。暗黙の了解で、閉店後、裏口の扉には鍵をかけない店が多かった。中に入ると、生ゴミとは別の棚に売れ残った惣菜をきれいな袋に分けて入れておいてくれていた。コンビニエンスストアも、店の裏にあるゴミ捨て場に、賞味期限切れの弁当やサンドイッチや菓子パンがまとめて置いてあって、回収車が取りにくるまでの間に行けば、欲しいだけもらうことができた。陽気がいい時分はその日のうちに食べないといけないけれど、寒い時は何日かコヤに置いておいても、ガスコンロで温めて食べれば大丈夫だった。
毎週水曜と日曜の夜は、東京文化会館からカレーライスの支給があったし、金曜日は「地の果てエルサレム教会」、土曜日には「神の愛の宣教者会」の炊き出しがあった。「愛宣教会」はマザー・テレサで、「エルサレム教会」は韓国系だった。「悔い改めよ、天の御国は近づいた」という幟旗、ギターで讃美歌の弾き語りをする髪の長い若い娘、大鍋をおたまで搔き混ぜるちりちりパーマのおばさん──、新宿や池袋や浅草から遠出してきているホームレスもいたから、多い時は五百人ぐらいの長い列ができた。讃美歌と説教が終わると、食事が配られる。キムチ炒めとハムとチーズとソーセージが入った丼飯、納豆ご飯に焼きそば、食パンとコーヒー……主をほめよ、主をほめよ、主の御名をほめよ、ハレルヤハレルヤ……
「食べたい」
「えー食べたい?」
「食べたくない」
「じゃあ、ママ食べちゃお」
「えー、えへへ」
桜の花びらのような薄紅色の半袖ワンピースを着た五歳ぐらいの女の子が顔を斜めにして、豹柄ワンピースで体の線を浮き上がらせている水商売勤めらしい母親の顔を見上げながら歩く。
コツコツとヒールの音を響かせて、紺色のスーツを着た若い女が母と娘を追い抜いていく。
突然、大粒の雨が、今を盛りと繁らせている桜の葉という葉をはたき、タイルを模した白い舗装道路に点々と黒い跡を付けていく。人々は鞄から取り出した折り畳み傘を広げる、赤、黒、ピンクの水玉、白い縁取りがある紺──。
雨が降っても、人の流れは止まらない。
二つ並んだ傘の中で、同じような黒っぽいスラックスにだぼっとしたシャツを着た老女が話をしながら歩いていく。
「朝から二十二度ぐらいなんじゃない?」
「そうねぇ」
「寒いというか、涼しいというか、凍えちゃいそうよねぇ」
「すごーい、すずしーい」
「リュウジが、向こうのお義母さんの料理を褒め過ぎで」
「えー、ヤな感じねぇ」
「お義母さんに料理を教われって」
「いやぁねぇ、雨」
「梅雨だから、あと一ヶ月ぐらいは仕方ないわよ」
「今、アジサイどうなの?」
「ないわよ」
「コナラは?」
「コナラの時期じゃないしねぇ」
「この辺、ちょっと建物が変わったんじゃない? スタバなんてなかったでしょ?」
「洒落た感じになったわよね」
ここは、桜並木──。
毎年四月十日前後は、花見客で賑わう。
桜が咲いている間は「エサ取り」の必要はない。
花見客が捨てていった食べ残しを食べ、吞み残しを吞めばいいし、敷物にしていたビニールシートで、一年間使って皺が寄り雨漏りがするようになったコヤの屋根や壁を新調することができる。
今日は月曜日、動物園は休み──。
上野動物園に、娘と息子を連れてきたことはない。
東京に出稼ぎに来たのは昭和三十八年の暮れ、洋子が五歳、浩一はまだ三歳だった。
上野にパンダがやってきたのは、それから九年後、二人とも中学生になっていて動物園に行きたがる年齢は過ぎてしまっていた。
動物園に限らず、遊園地にも海水浴にも山登りにも行かなかったし、入学式にも卒業式にも授業参観にも運動会にも行ったことはなかった、ただの一度も──。
親や弟妹や妻や子どもらが待つ福島の八沢村に帰るのは、盆暮れの二回だけだった。
一度だけ、盆休みの前に何日か早く帰れた年に、ちょうどお祭りか何かがあって、原町に子どもらを連れて遊びにいった。
鹿島駅から常磐線に乗ってひと駅──、真夏で、暑くて、とにかく眠かった。体と心のどちらともが強い眠気に揺さぶられ、子どもらのはしゃぎ声も、自分の生返事も、霞のようにぼんやりしていたが、列車は空と山と田圃と畑ばかりの風景を切り裂き、トンネルを越えて加速した。青と緑、二つの色だけになった窓硝子に、四つの手をヤモリのように広げて額と唇を付けていた子どもらの甘酸っぱい汗の臭いを鼻腔いっぱい吸い込んで、ほんの何分かのあいだ頭をこくりこくりと前に倒した。
原ノ町駅で降りると、改札の駅員さんが、雲雀ヶ原でヘリコプターに一回ナンボかで乗せてくれるみたいですよ、と言うので、右手に洋子、左手に浩一──、二人の手を繫いで浜街道を歩いていった。
滅多に帰らない父親に懐かず、甘えたりねだったりすることをしない浩一が「お父ちゃん、乗りたい」と繫いでいた手をぎゅっと握り締めた。はっきりと顔が浮かぶ。言いづらいことを言いかけて、気後れして何度も口を閉じ、しまいには怒ったように真っ赤になった浩一の顔──、だが、金がなかった。あの頃で三千円ぐらいだったから、今だったら三万円以上……大金だった……
代わりに、当時十五円だった松永牛乳のアイスまんじゅうを買ってやると、洋子はすぐに機嫌を直したが、浩一は父親に背を向けて泣き出し、しゃくりあげて肩で息を刻み、金持ちの家の男の子を乗せて飛び立つヘリコプターを見上げては、拳で涙を拭っていた。
あの日の空は一枚の青い布地のように晴れ渡っていた。乗せてやりたかったのに、金がなくて、乗せてやることができなかった──、悔いが残った。その悔いは、十年後のあの日に、矢となって心を射抜き、今も突き刺さったまま、抜けることはない──。
切り傷のように真っ赤な「上野動物園 ZOO」の文字も、「こども遊園地」の看板や柵の上で両手を広げている赤、青、黄色の服を着た小人たちの指も、動いてはいない。
でも、一本の葦のように震え、話せる限りは話そうと思うのに、どうしたらいいかわからず、出口を求めて、出口こそ見たいものなのに、闇も降りないし、光も射さない……終わったのに、終わらない……絶え間ない不安……悲しみ……淋しさ……
風がサーッと木々を渡り、サラサラサラッという葉擦れと共に水滴が振り落とされたが、雨はもう降っていないようだ。
白抜きで「パンダ焼」とある色褪せたピンクのひさし、紅白の小さな提灯が揺れている桜木亭には脚立が出してあり、赤い前掛けをした女が掃き掃除をしている。
桜木亭の前の木のベンチには二人の老女が座っている。右の、白いカーディガンを羽織った老女が、「一応写真持ってきたわよ、見る?」と黄色い布バッグの中から、小さなアルバムを取り出した。広げて見せたのは、三十人ばかりの老齢の男女が三列に並んで写っている集合写真だった。
左の、白カーディガンの老女より頭一つ大きい黒カーディガンの老女は、肩に掛けたままの革バッグから老眼鏡を取り出し、写真の上に人差指の先で伸ばしたバネのような円を描きはじめた。
「これあのほら、ヤマザキ先生の奥様でしょ? ヤマザキ先生も見えたのね」
「いつも必ずお二人で見えるの。昔から、おしどり夫婦ですものね」
「この人、生徒会長の……」
「シミズさん」
「これはあれ、トモちゃん」
「笑顔に面影があるわよね」
「これ、あなた。素晴らしいわぁ、女優さんみたいじゃなぁい」
「まぁ、何をおっしゃいますかぁ」
二人の老女が寄り添って一つになった影の中で、一羽の鳩が探るように練り歩いている。
二人の老女の頭上では、二羽の烏が警告するような鋭い声で鳴き交わしている。
「このタケウチさんの隣、ヤマモトさんでしょ? 骨董品店のね……この人はソノダヨシコさん……」
「この方、ユミちゃんよ」
「あぁ、ユミちゃん。ユウコさんのお通夜でお目にかかったわよね」
「何十年ぶりかだったのに、お互いすぐにわかった」
「この人、事務のぉ、事務のぉ……」
「イイヤマさん」
「そう、イイヤマさん」
「その隣が……」
「あの、あれでしょ? ヒロミさん?」
「そうそうそう、ヒロミさん」
「これ、ムッちゃん」
「ムッちゃんも歳とらないわねぇ」
「シノハラさんだ」
「いつもお着物お召しになってるわね」
「きれいだわよね」
「フミちゃん、タケちゃん、チーちゃん、この方はクラタさん。この方だけクラスが違ったの」
「あら、気付かなかった」
「クラタさんは、川崎にお住まいなんだけど、近所で徘徊している方がいてお困りだって。越後湯沢の宿で、夜みなさんお休みになったのに、この方だけ起きていてね、お茶を飲みながら話して、みんな布団に入っているのにね、話が終わらないのよ」
「あら困ったわね」
「困りましたともぉ。クラタさんのご近所で、どなたかの旦那さんが徘徊して、家の庭に立っていたとかで」
「それは、困るわね。ご近所だと、警察に通報するわけにもいかないしね」
写真を持ち歩いたことはなかった。でも、いつも、過ぎた人、過ぎた場所、過ぎた時間は、目の前に在った。いつも、未来に後退りながら、過去だけを見て生きていた。
懐かしさや郷愁などという甘いものではなく、今はいつも居た堪れず、未来はいつも恐ろしかったから、気が付けばいつも、過ぎてしまえばどこにも行かない過去の時間に浸っていたのだが、時間は終わってしまったのか、一時停止しているのか、いつか巻き戻してまた始められるのか、永遠に時間から締め出されたままなのか、わからない……わからない……わからない……
家族が一緒に暮らしていた頃は、写真を撮ったことはなかった。
ものごころ付いた頃には戦争が始まっていて、食糧難で、腹ばかり空かせていた。
七、八年遅く生まれたお陰で、戦争には行かずに済んだ。
同じ部落には十七歳で志願して兵隊になった者もあったし、徴兵検査に合格しないように醬油を一升吞んだり、目や耳が悪いふりをして徴兵を逃れた者もあった。
終戦の時は、十二歳だった。
戦争に敗けて悲しい、惨めだということよりも、食っていくこと、食わせることを考えなければならなかった。子どもなんて一人食わせていくのも大変なのに、下に七人も弟妹がいた。当時の浜通りには、東京電力の原子力発電所や東北電力の火力発電所なんてものはなかったし、日立電子やデルモンテの工場もなかった。大きな農家は農業だけで食べていけるけれど、我が家の田圃はほんの微々たるものだったから、国民学校を卒業してすぐに、いわきの小名浜漁港に出稼ぎに行って住み込みで働いた。
住み込みといっても、寮やアパートの用意はなく、大型漁船の中で寝泊まりする生活が始まった。
四月から九月にかけてはカツオ、九月から十一月にかけてはサンマ──、サバ、イワシ、マグロ、カレイなども獲れた。
船の暮らしで困ったのは、虱だった。服を着替える度に虱が落ちるわ、縫い目にザーッと虱が付いているわ、少し暖かくなると背中でもぞもぞ動くのがわかるわで、虱にはとにかく悩まされた。
小名浜の出稼ぎは二年目で終わりにした。
親父が北右田の浜でホッキ貝を採りはじめたので、その手伝いをすることになった。
木製の小さな舟で海に出て、アサリ採りに使う鉄製の馬鍬を底に沈めて、ワイヤーなんてなかったからロープで、手で引っ張っては足で押さえ、引っ張っては押さえて、親父と二人で毎日毎日ホッキ貝を引き上げた。
ホッキ貝は、同じ部落の人も、他の部落の人も皆が採って、貝に繁殖する間を与えず採りつづけたせいで、四、五年で採り尽くしてしまった。
長男の浩一が生まれた年に、八沢村から北海道に出稼ぎに行った叔父さんのツテを頼って、北海道の霧多布の隣の浜中という漁村に、昆布の刈り採りの出稼ぎに行くことにした。
五月の連休に田植えをやって、肥料やりや草取りを野馬追までに終えて──、相馬では、畑仕事でも家の改修でも借金の返済でもなんでも「野馬追までに」と言い、野馬追勘定という言葉があるくらい、野馬追を一年の節目にしている。
野馬追は七月の二十三、二十四、二十五の三日間開催される。
一日目は、宵祭り。相馬・宇多郷の中村神社から総大将が出陣し、鹿島の北郷本陣で総大将お迎え。宇多郷と北郷の騎馬武者は揃って出陣し、太田神社からは原町・中ノ郷の騎馬武者、小高神社からは小高郷の騎馬武者、浪江・双葉・大熊の標葉郷からも騎馬武者が出陣する。
二日目は、本祭り。法螺貝と陣太鼓の音を合図に五百騎の騎馬武者が一斉に進軍して、雲雀ヶ原で甲冑競馬と神旗争奪戦を行う。
三日目は、野馬懸。小高神社で、白鉢巻に白装束の御小人が素手で荒馬を捕らえ、その馬を奉納する神事。
馬を借りるとか鎧兜を揃えるだとかで何百万もかかるという話で、貧乏人には縁がない祭だったが、五、六歳の頃、親父と一緒に鹿島の副大将の家に行って、肩車をしてもらって出陣式の様子を見たことがある。
「出立は十二時半」
「十二時半、しかと賜りました。伝令直ちに帰陣し、その旨お伝え申し上げます。以上」
「ご苦労。北郷侍にあってはお流れを頂戴してもらいたい」
「お流れ頂戴します。なお、宇多郷本陣での騎馬のご無礼、何卒ご容赦願います。これにて伝令直ちに帰陣致します」
「お役目ご苦労。道中気をつけて参られよ」
「相馬流れ山ナーエ ナーエ ッサーイ
習いたきゃござれナーエ エーッサイ
五月中の申ナーエ ナーエ ッサーイ
アレサ御野馬追いナーエ エーッサイ」
武者たちはそれぞれの馬に跨り、青々とした田圃の畦道を進んでいく──、風にはためく旗印が一つ一つ違うのが面白くて、「あ! あの旗はムカデだ!」「蛇がからまってるよ!」「あっちの旗は馬が逆立ちしてる!」と親父の頭上で大声を上げて旗を指差していた。
北海道へ出稼ぎに行くのには汽車で二昼夜かかった。鹿島から常磐線に乗って仙台に行き、仙台から東北本線で青森に行き、青函連絡船に乗って函館に着いたら、朝になっていた。
函館から函館本線に乗って、十勝山脈と狩勝峠を越えなければならないのだが、機関車二台で引っ張っても急勾配でなかなか前に進まず、列車から降りて外で小便をしても追い着くぐらいのスピードしか出なかった。
南米チリでマグニチュード九・五、震度六の大地震があった年だった。霧多布でも津波で亡くなった人が十一人あったという。電柱の上の方に毛布みたいなものが絡み付いているのを見て驚き、ひと足先に住み込んでいた叔父さんに「あんなどごまで、津波来たんだが? ほんとだが?」と訊ねたら、「ほんとだ。六メートルぐれえあったって言うど。霧多布は昭和二十七年の十勝沖地震ん時も、おっきな津波来て、ほの津波で北海道本島から切り離さっち、島になったんだど。もともと陸つづきだったどごさ橋を架けてたんだげんちょ、今度の津波で橋ごど流さっちゃんだど」と言って、二人で身を硬くして海の前に立った。
海は一面昆布だらけだった。昆布は長いのだと十五メートルぐらいはあるから、竿の先にくっつけてあるシバで引っ掛けて船に寄せて、手で引き抜いていった。浜に戻ると、今度は馬車で昆布を揚げて一本ずつ浜に干していく。浜が昆布で真っ黒になるまで干して並べて、干して並べて──。
それを二ヶ月やって、十月初めには稲刈りに帰る、そんな暮らしを三年ぐらいつづけた。
腰を痛めて農作業も覚束なくなった親父と、勝男と正男は進学を希望しているし、洋子と浩一もこれからまだまだ金がかかるからと話し合い、東京に出稼ぎに行こうと腹を決めた。
東京オリンピックの前の年、昭和三十八年十二月二十七日、暮れも押し迫った寒い朝、まだ暗いうちに家を出て鹿島駅に行き、五時三十三分の常磐線の始発列車に乗った。上野駅に着いたのは昼過ぎだった。数え切れないほどのトンネルを抜けたために、蒸気機関車のけむりで真っ黒に煤けた顔が恥ずかしくて、プラットホームを歩きながら列車の窓に何度も顔を映し、帽子のつばを上げたり下げたりしたのを覚えている。
世田谷の太子堂にある谷川体育株式会社の寮に入った。プレハブの寮で、一人六畳で、便所と風呂は共同だった。朝と晩は、煮炊きできる同僚が飯と味噌汁と簡単なおかずを作ってくれた。重労働だったから、丼二杯は食べないと体が持たなかった。
弁当は、弁当缶なんて気の利いたものはなかったし、あったとしても、そんなものを買う金はなかったから、朝飯の後に丼に飯を詰めて、皿で蓋をして、風呂敷でぎゅっと結えて、電車に乗って現場に向かった。おかずは、休憩が一時間あったから、現場近くの商店街でコロッケとかメンチカツを買って食べた。
仕事の内容は、東京オリンピックで使う陸上競技場や野球場やテニスコートやバレーコートなどの体育施設の土木工事。土木といっても、ブルドーザーやショベルカーなどの重機なんていうものは見たこともなかったし、出稼ぎ労働者には操縦できなかったから、ツルハシやスコップで土を掘って、リヤカーで土を運んで、全て人力。東北の農家出身が多かった。みんな「土方仕事は畑さ耕すのとおんなじだべ」と笑っていた。五時で仕事が退けると、連れ立って吞みに行っていたが、幸か不幸か、自分は下戸だった。それでも何度か、「今日はおらのおごりだ!」と誘われて断り切れず、付き合ってはみたものの、どんなに無理をしてもコップ一杯のビールが限界だったので、次第に誘われなくなっていった。
日当千円、地元で同じ時間働いて得られる賃金の三、四倍だった。残業は二割五分増しだったから、喜んで毎晩残業をして、日曜祝日も働きに出た。
月給は十五日締めだった。毎月二万円だかそれくらいは仕送りしていた。当時の教員の月給と同じぐらいだったから、今にすると二十万円ぐらいにはなっていたと思う。
「仕事が薄いなぁ」
と言って、ポキンと楓の枝を折ったホームレスのジージャンには覚えがある。漂白剤を零したのか、背中の白い染みが北海道の形によく似ていたから、間違いない。あれは、自分が着ていたジージャンだ。布ゴミの日に広小路のゴミ収集所で拾って、春先の肌寒い日には重宝していた……コヤの天井に吊るしておいたが、きっと誰かが持ち去ったんだろう……姿を消した後に……
「これだけ景気が悪いと、小さいところとか大きいところに行っても鼻糞みたいな扱いだよ」
と、鳥の巣のような白髪頭と重ね着した襤褸のスカートを揺らした老女はハイライトに火をつけて、けむりを吸い込んだ。
この顔は、知っている……老いた顔に似合わない滑らかな額……知っている……おはよう、と挨拶をしたこともある……立ち話をしたこともあったはずだ……
「三、四十人のところがいちばん悪いね、いちばん中途半端」
「この前、小田急線に乗ってさ」
「小田急線なんてハイカラなとこ行くのか?」
「死んだシゲちゃんの飯場があったじゃないか」
「シゲちゃん? 死んだのか?」
「死んじゃったんだよ、シゲちゃん、コヤで冷たくなってたんだよ」
「死ぬよ、そりゃ、いい歳だろうが」
老女の目が、突然どんよりと沈み込んだので、慰めてやりたかったが、肩に手を置くことも、悔やみの言葉を声にすることもできなかった。
シゲちゃんのことは、知っている。シゲちゃんはインテリだった。いつも拾った新聞や雑誌や本を読んでいた。きっと頭を使う仕事をしていたのだと思う。
いつだったかコヤに子猫を投げ入れられて、アルミ缶を売った金で動物病院で去勢手術をして、エミールと名付けて可愛がっていた。「山狩り」の時にはリヤカーに乗せて移動し、雨の日はビニール傘を差し掛けてやるほどだった。
江戸の人々に時を知らせるために作られ、朝夕六時と正午の三回、寛永寺の僧侶によって打ち鳴らされる「時の鐘」の向かいの丘に、大仏のお顔のお堂があることを教えてくれたのも、シゲちゃんだった。
「大仏のお首はですね、大地震で三回、火事で一回、合わせて四回も落ちていて、誠にお労しい限りです。最初に落ちたのは一六四七年で、そのままにしておくのはお気の毒だということで、大仏再興のために江戸中を托鉢して回った僧侶があったそうなのですけれども、誰も寄進する者がなくてですね、日が沈む頃に帰りかけると、一人の物乞いが近付いてきたんだそうです。その物乞いが鉄鉢に一文銭を投げ入れ、それがきっかけでご寄進が集まり、二丈二尺の大仏ができあがったと伝えられています。しかし、約二百年後の火災でまた落ち、元通りになったと思ったら十年後の安政の大地震でまた落首、また復首──、戊辰の役、上野の戦では無事だったのに、大正十二年の関東大震災で完全に倒壊してしまった、ということです」
何事も教師のような語り口で話す不思議な人だったが、案外ほんとうに教師だったのかもしれない。
その時、シゲちゃんに、自分は、無線塔のことを話した。浜通りでは、原町といえば無線塔というほど有名で、昭和五十七年に解体されるまでは原町のシンボルだった。無線塔は大正十年に完成して、二年後の関東大震災の時に「本日正午横浜において大地震に次いで大火災起こり、全市ほとんど猛火の中にあり、死傷算なく、全ての交通通信・機関絶滅した」と打電し、それが全世界に報道された、と──。
それを聞くと、シゲちゃんは、
「不忍池の水が役立ったと言われていますが、関東大震災の時、上野公園は焼けませんでした。周りはかなり焼けて、公園の正面にあった松坂屋は全焼。火事から逃れた避難民は、上野周辺だけではなく日本橋、京橋方面からも殺到して、田舎へ帰ろうと家財一式を大八車に積んでやってきたので、上野駅構内や線路にも人があふれて列車も動かせない状態だったそうです。行方不明者が多かったから、西郷さんの銅像の台座には尋ね人の貼り紙がたくさん貼られました。
昭和天皇は軍服姿で、被災者がひしめく上野公園を視察され、防災上非常に重要であることを認識されました。そして大正十三年一月、今上陛下御慶事記念として東京府に下賜されて『上野恩賜公園』という名前になったのですよ」
と、芝生の上に横になって両目を閉じているのに長い尻尾の先をびくんびくんと動かしている虎猫のエミールをいとおしげに眺めた。
昭和天皇を間近に見たことがあるとは、シゲちゃんには話さなかった。
昭和二十二年八月五日午後三時三十五分、お召し列車が原ノ町駅に停まり、天皇陛下は駅前に下車されて七分間滞在された。
小名浜漁港の出稼ぎから帰ってきた直後の出来事だった。
圧迫感を覚えるような真っ青な空だった。アブラゼミの鳴き声が本陣山全体を震わせ、その鳴き声から押し出されるようにミンミンゼミが鳴きしきっていた。太陽を融かしたような陽射しがめらめらと揺らめいて、人々の白いシャツも緑の葉も、何もかも眩しくて目を開けていられなかったが、駅前に集まった二万五千人の一人として、帽子を被らず、身じろぎもしないで、天皇陛下を待っていた。
お召し列車から降りられたスーツ姿の天皇陛下が、中折れ帽のつばに手を掛けられ会釈をされた瞬間、誰かが絞るような大声で「天皇陛下、万歳!」と叫んで両手を振り上げ、一面に万歳の波が湧き起こった──。
「シゲちゃんが死んじゃうなんて、信じられるかね?」
「タバコの灰、なかなか落ちないね」
「八十五年もタバコ吸ってりゃ、うまくもなるだろうさ」
「ケッ、おまえさんは、赤ん坊ン時からタバコくわえてんのかよ」
「シゲちゃん、死んじゃったんだよ」
「シゲと浮気したのか?」
「首吊って死ねって言うんだよ!」
「薄汚いババァの癖に、なんでそうツンツンすんだよ」
「テメー! コノヤロー! 心臓食っちゃうぞ!」
「山谷のババァよりコエーや。来たッ、ダニッ!」
と、ホームレスの老人は自分の脛をはたいた。
「バカッ、アリだよ」
老女は足下に目を落とし、革靴を履いている右足と運動靴を履いている左足を眺め、運動靴の方の紐がほどけているのに気付きはしたが、屈んで結び直そうとはしなかった。
「まぁそうツンケンしないで座れ! 座れよ!」
「座るとこなんか、ありゃしないじゃないか」
「まぁ、座れ」
男は、植え込みのコンクリート枠に腰掛けて、ポケットの中から紙切れを取り出した。
「これ五千円くらいになるよ。当たったら、半分やるよ」
女は男の隣に座り、馬券の文字をぶつぶつと読んだ。
「とぅいんくる、だいさんじゅうごかい、ていおうしょう、じゅういちれえす、うまさんれんたん、いち、じゅうに、さん、ごひゃくえん、いち、おおえらいじん、きむらけん、じゅうに、みらくるれじぇんど、うちだひろゆき、さん、とおせんごらいあす、はしもとなおや」
女が吸い尽くして、革靴の右足の方に投げ捨てた煙草の吸殻からは、まだけむりが立ち上っている。男と女の足下で列を作っている蟻は、蟻から蟻へと連なって、樹の幹の上へ上へと這い上っているが、蟻の巣があるのは樹の上ではない──、上野恩賜公園の樹には、病院や役所や図書館の傘立ての鍵のようなプラスチックの丸い札が付けられていて、この樹は青のA620──、ざらざらとした樹皮の感覚を思い出してみる、蟻が皮膚を這う感覚も──、蟻の巣があるのは、樹の上ではない。蟻は樹から下りていく。蟻は連なって、白い鳩の糞が点在しているアスファルトのなだらかな坂道を下りていき、青いビニールシートで覆われたコヤが集められた一角へと入っていく。その一角は樹が描かれた鉄製のパネルで囲われ、パネル上部の金網は白い雲がプリントされた青いビニールシートで覆い隠されている。
コヤの中からラジオの国会中継が漏れている。
「昨年の三月の事故を踏まえて、複雑な感情を持っていらっしゃる国民がたくさんいらっしゃることも承知をしておりますけれども、それを踏まえて、国論を二分するテーマについてもしっかりと責任ある判断をしなければいけないのが政府の役割だと思っておりますので、折につけそういうご説明はしていきたいという風に思います」
「サイトウヤスノリくん」
「その作られた安全基準というのが、安全神話のもとで作られた安全基準で、それを稼働させるということで、皆さんは矛盾に感じられて怒っているわけでございます。今回の再稼働はどう見たっておかしいという怒りの声ですので、是非、総理、よく考えて判断していただきたいと思います……」
どこか近くで草刈機の音が聞こえる。
刈られた草の青々しい匂いがする。
コヤの中から即席ラーメンを鍋で煮ている匂いがしてくる。
雀の群れが何かに驚き、節分の豆をばらまいたように飛び立つ。
額紫陽花が咲いている。周りの薄紫の花が中央の濃く小さい紫の花の塊を額のように縁取っている。
生きている時は、そういうものが孤独を感じさせた。
音も景色も匂いも全部混ざり合って、だんだんと薄れていき、だんだんと小さくなっていき、指を伸ばせば何もかもが消えてしまいそうにも感じられるが、触れる指がない、触れることができない、五本の指に五本の指を重ねることもできない。
存在しなければ、消滅することはできない。
「内閣総理大臣」
「色々なアンケートがあると思います。それぞれ色々なアンケートをしていることも承知でございますけれども、基本的には、被災者の皆様のためには、これは、我が政権は昨年の九月に発足をしましたけれども、震災からの復興、そして原発事故との戦い、日本経済の再生、これは最優先かつ最重大の課題として位置付けております。そして、被災者のために寄り添った政策というものは、しっかりとこれからもやっていきたいと思います」
不意に雨が落ち、コヤの天井のビニールシートを濡らす。雨が、雨の重みで落ちる。生の重みのように、時の重みのように、規則正しく、落ちる。雨が降る夜は、雨音から耳を逸らすことができず、眠ることができなかった。不眠、そして永眠──、死によって隔てられるものと、生によって隔てられるもの、生によって近付けるものと、死によって近付けるもの、雨、雨、雨、雨──。
一人息子が死んだ日も、雨が降っていた。