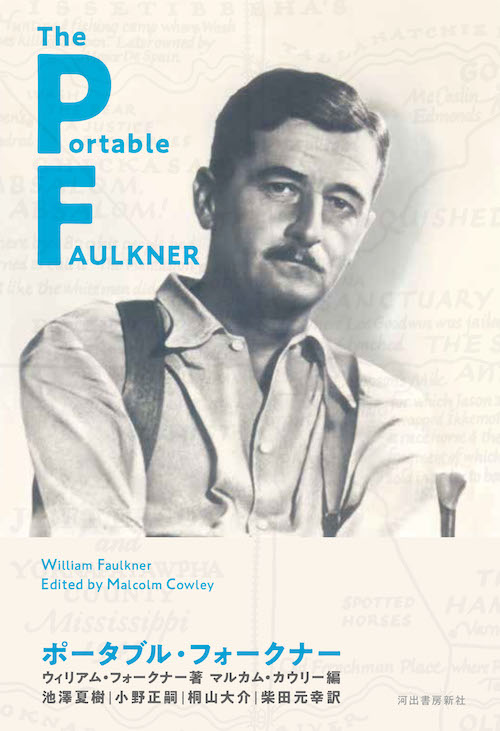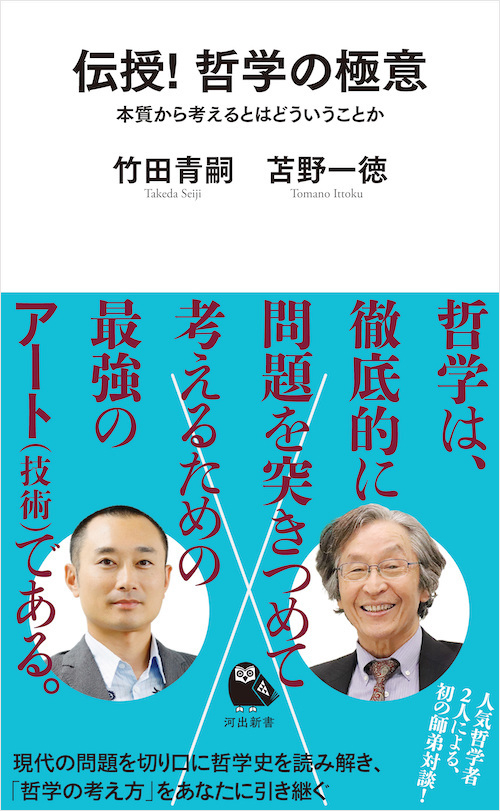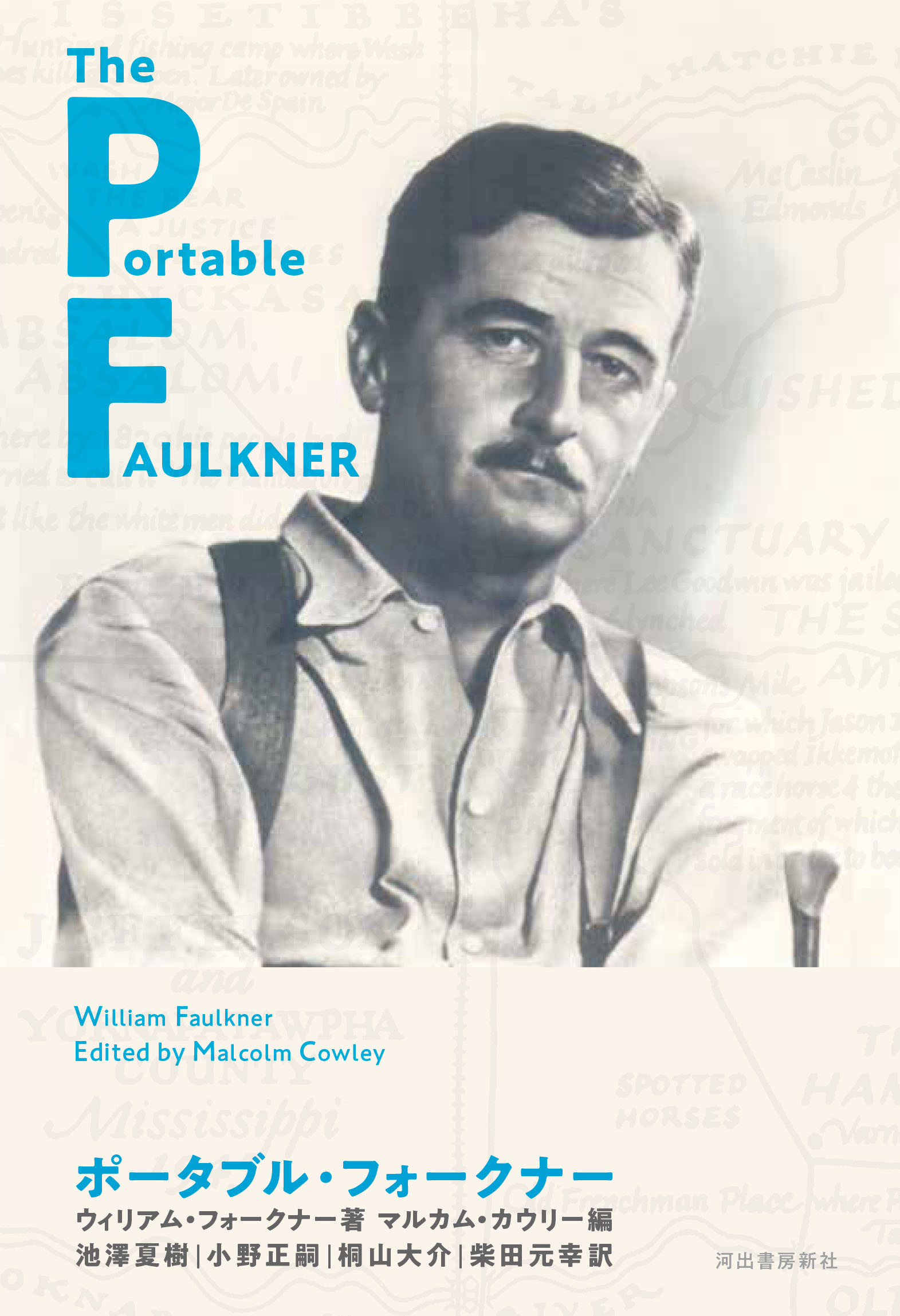
特集・コラム他 - 特設ページ
【豪華訳者陣による唯一無二の新訳!】『ポータブル・フォークナー』刊行記念、池澤夏樹×柴田元幸×小野正嗣×桐山大介による翻訳奮闘話、公開!
ウィリアム・フォークナー
2022.09.21
フォークナーをノーベル賞に導いた奇跡の選集『ポータブル・フォークナー』発売を記念して、雑誌「文藝 2022年夏季号」に掲載した豪華座談「文体の暴れ馬『ポータブル・フォークナー』翻訳奮闘話」を公開いたします。
水道橋の薔薇事件
―『ポータブル・フォークナー』の翻訳企画はどう立ち上がったんですか?
池澤 僕は個人編集をした世界文学全集(編集部注:第一期九巻にフォークナー『アブサロム、アブサロム!』を収録)と日本文学全集をつくる過程で編集・編纂が文芸活動にとって非常に重要であると、つまり創作、翻訳と並ぶ三本柱のひとつであると思うようになりました。みんな軽く見るけど、編集はさまざまな作品を批評的に読んで選んでまとめるという重要な行為なんです。そのことが頭にあって、河出書房新社の木村さんに『ポータブル・フォークナー』を丸々新訳で出せないかな、と言ったの。というのも『ポータブル・フォークナー』を編纂したマルカム・カウリーは大変いい仕事をしているんです。
フォークナーはヨクナパトーファという架空の地域を作って、そこでの人々の営みをインディアンの時代から一九五〇年代以降まで延々と書いてきた。従って彼の作品のあちらこちらを拾って並べればクロニクルになるとカウリーはひらめいたんです。それが一人の作家の優れた作品を一冊に集めるヴァイキング社の「ポータブル」シリーズにもぴったりあった。それまでフォークナーは南部の変な作家だと思われて、アメリカでもほとんど読まれていなかった。フランス人のほうが翻訳で読んでいたんじゃないかな。しかしこの一冊のおかげで彼は国内でも読者を得て、後のノーベル賞受賞にもつながった。今でも一冊として読まれていいもんだと思ったので河出の木村さんに提案したんです。そしたら、まんまと引っかかった(笑)。
―初めは柴田さんに翻訳の打診があったようですが、四人で共訳することになった経緯は?
柴田 冨山房からフォークナー全集が出ているので、絶版もありますが図書館でかき集めれば、すべての作品を邦訳で読めるわけですよね。そのなかでどう新しい価値を付け加えられるかを考えたときに、やっぱり作家と翻訳者の力をあわせて作る新訳が必要だと思った。作家はまず池澤さんがいらっしゃる。小野くんは翻訳をやっていて、かつフォークナーに通じる小説を書いているということで入ってもらわない手はないだろうと。
池澤 小野さんとフォークナーにはヴァナキュラーという共通点があると思います。マンダリン=都会的に対するヴァナキュラー=田舎的。
柴田 そうですね。前に僕がやっていた雑誌「Monkey Business」に連載してもらった「浦ばなし」などはまさにザ・ヴァナキュラーです。さらに作家と翻訳者だけでいいかというとそうではなくて、フォークナー研究の最新の動向がわかっている学者も絶対に要ると思った。それが桐山くん。誰から決まっていったかは覚えてないんだけど、順序がぐちゃぐちゃになるのはフォークナー文学の常なので(笑)。『ポータブル・フォークナー』における僕の最大の貢献は桐山くんを引き込んだことですね。解説だけでも買う価値がある。
桐山 そこからどう引き継げばいいかわからないですけど(笑)。覚えてるかぎりだと、お話いただいた時点でお三方は決まっていて、僕には研究を踏まえた訳文の確認と、カウリーが書いた文章の翻訳をお願いしたいということだったと思います。それがいつの間にかフォークナーの作品も訳すことになってました。
柴田 桐山くんはその頃まだ大学院生で翻訳の経験もなかったので、とりあえずカウリーの解説を訳してもらうことになったけど、いざ訳してもらったら翻訳がすごくいいんで、訳者の一人として入ってもらうことになったんじゃないかな。
池澤 僕は企画の提案だけして逃げようと思ってたんですよ。
一同 (笑)。
小野 僕たちは水道橋にあった「アンチヘブリンガン」というレストランで何度もミーティングをしたんですが、あるとき、池澤さんがみんなに薔薇を配ったことがあって、「ああ、絶対逃げる気だ」と思いました(笑)。ミーティングでは毎回編集の木村さんが進行表をプリントアウトしてきて、翻訳の進み具合を確認していくんです。集まるたびに柴田先生と桐山さんは訳し終えたページが増えていくんですけど、池澤さんと僕は全然進まなくて。
池澤 言い訳をすると某歴史小説作家が急に亡くなって、僕の新聞連載開始が三ヶ月早まったんです。その三ヶ月を翻訳に使うつもりでいたわけ。その連載が終わると今度はなぜか次の連載がすぐ朝日新聞で始まってしまいズルズルと遅れたのです。
小野 で、あるミーティングのときに池澤さんが迷惑かけて申し訳ないという感じで、僕たち全員に薔薇を一輪ずつ渡してくださったんです。僕はきっと別れの薔薇なんだろうと思って受け取りました(笑)。
柴田 「エミリ」じゃなくて「翻訳者に薔薇を」だよね。
バランス感覚を捨てる「勇気」
―八◯◯ページ以上ありますが、翻訳の分担はどう決めたんですか?
池澤 さっき言ったとおり、僕ははじめ翻訳する気がなかったんです。ところが、うかつに口を滑らせるっていうことがあるんだな。もともと好きだった『野生の棕櫚』の「オールド・マン」をついやるとつい言ってしまった。冨山房の全集では僕の父(福永武彦)が解説を書いていて、僕にとっては因縁のある作品なんです。それでやると言ったんだけどごめんなさい、非常に遅れて今に至りました(笑)。
小野 部ごとに担当を決めたんですが、僕に関してはあんまり長くないところがいいんじゃないかとご配慮をいただいた記憶があります。あと柴田先生が僕は「まだら馬」が好きなんじゃないかと勧めてくださって。そういう感じでそれぞれに合うものを割り当てていただいたように記憶しています。難しい作品は柴田先生がやるという話でした。
桐山 僕に割り当てていただいた作品はすごく合ったというか、入り込んで訳せました。最初は「監獄」も僕が訳す予定だったんですけど、さすがに多いということで小野さんに担当していただくことになりました。
小野 そのときのことはよく覚えてます。「小野さんはきっと好きだと思いますよ。「監獄」から翻訳するのがいいんじゃないですか?」って桐山さんから言われたんですけど、いざ訳してみたら全然わかんなくて(笑)。これは最後だなと思っていちばん後に回しました。
池澤 僕の場合をお話ししましょうか。悲惨でした(笑)。つまり歯が立たない。これまで自分も翻訳をしてきて、カート・ヴォネガットやジョン・アップダイクなら訳せた。翻訳は作者がどう考え、どういう経路を通ってその文章に至ったかを辿らなければいけないんだけど、フォークナーの場合いくらにらんでもこれがわからないんですよ。そうすると僕は半端に作家だから、文章のあいだを勝手につないでしまう。それを柴田さんに見ていただくと、通信添削で赤と青のペンがびっしり入った原稿が返ってくる。元の文章がほとんど残っていないくらい。ありがたいことでした。そのプリントは家宝として取ってあります。
それで柴田さんが手を入れてくださった箇所を全部黄色いマークでわかるように自分の文章のなかに移して(これがなかなかの重労働)、そのうえでちょいちょいちょいと自分の文体に整えました。他の人の文章であるものを日本語にするわけだから、抜け落ちるものもあるし勘違いもあるけど、それが生半可な量ではなかったと。本当に不思議な体験でした。柴田学校の生徒になれた。
小野 僕の場合、訳文を柴田先生にチェックしていただき、アメリカ南部の歴史と文化に関する細部やフォークナーの他の作品との関係を桐山さんに教えていただくという二重のチェックをしてもらい、さらに手を入れるというやり方をしています。一読してもピンとこないし、訳してもますます何が書いてあるのかわからなくなってしまうところもあって、とにかく難しかったです。
池澤 フォークナーは映画に近い場面の描写をするんだけども、その癖、実際にそこで何が起こったかがよくわからない。ひとつには一部を隠すんですよ。韜晦癖でわざと書かない。それから思いつくまま勝手放題に話が進む。ぶっ飛んだ思考過程に追いつけない。今アメリカで作家のランク付けをするしたら、と問われてフォークナーは一番をトマス・ウルフ、二番を自分にして、三番はドス・パソス、ヘミングウェイは四番目だと答えたという話があります。なぜ四番目なのか。彼は「ヘミングウェイには勇気がない」と言うわけです。読者が席を立って本棚まで行き辞書を引かなければわからないような単語を彼は使わないと。フォークナーは辞書にもないような単語をいくらでも使うわけですよ。だからやっぱり難しい。特に柴田さんが訳された「熊」、あれはすごいと思った。
柴田 フォークナーの文章は修飾が多いんですよね。じゃあどうしてそれが大変かというと日本語と英語では語順が違うからです。英語の場合は〈the man〉が最初にきて、whoのあとに「何とかかんとかした」と説明が続く。フォークナーの文章はこの〈the man〉の後にくる説明の長さが半端じゃない。もしかしたらフランス語に訳すのは、語順がほとんど一緒だからそこまで難しくないかもしれない。でも日本語で読みやすさも原文と変わらないものにしながら、リズムもなるべく再現しようと思うといろいろ工夫が必要になる。池澤さんが訳された「オールド・マン」は今言ったような傾向が顕著で、異様なんですよ。フォークナーにとっての「勇気」はこのバランス感覚を捨てるということでもあると思います。大事なものは丁寧に形容し、そうでないものはさらっと形容を済ませるのが一般的なバランス感覚だけど、「オールド・マン」ではほとんど確信犯的に正反対のことをやってますよね。
池澤 僕が最初に読んだフォークナーは筑摩書房の世界文学大系に入っている「パイロン」だったんです。そこにクロード・エドモンド・マニーというフランスの批評家が「フォークナーもしくは神学的転位」という論考を寄せているんだけど、彼女も形容詞が五つ並ぶのはひどいと書いていた(笑)。だからみんな気がついていたわけですよね。
実は笑えるフォークナー
柴田 過剰な修飾は難解さにもつながるんだけど、半分はユーモアなんですよね。今回の翻訳ではそのユーモラスな部分を伝えることを目指しました。フォークナーのユーモアは気の利いたエピソードというよりも言葉の過剰さからきている。
池澤 僕もそう思いました。マーク・トウェインやメルヴィルにも通じるアメリカ文学特有のユーモアだと思う。非常に手の込んだトール・テール(ほら話)ですよ。
小野 「まだら馬」にも田舎の人たちのお喋りの愉快さが伝わってくる感じがあります。日常のなかで言葉を遊び道具みたいに使って会話を楽しんでいる感じというか。
柴田 マーク・トウェイン的とも言える、シンプルな言葉を使った口語的な語りはヘミングウェイによってある意味ではうっとうしくもあるんだけど研ぎ澄まされて、芸術の域まで高められたわけだけど、フォークナーは対照的にマーク・トウェインに足し算するようにして別の豊かな語りをつくった。そういう大雑把な見取り図は成り立ちますね。
桐山 中期以降の長篇はとにかく一文が長いので、読める日本語にするのがまず難しいと思います。もうひとつの難しさは、先ほどの話に出た独特なユーモアです。文の長さで可笑しみが醸し出されるところもあれば、変な理屈を通すことで生まれる可笑しみもある。でもそれがあまりにも変な理屈なのでユーモアだと気づかれない場合があるんです。
柴田 『八月の光』や『アブサロム』あたりの三◯年代半ばに書かれた傑作群はユーモアとはちょっと違いますよね?
桐山 でもたとえば『アブサロム』にも常に茶化すような語りが入ってくるところがあります。「熊」でも密度の濃い文章のなかに皮肉や茶化した語りなどユーモアに通ずる要素が必ずあって、それが悲劇性をより強めている。ブーンの最後の姿も悲劇的というかすごく切ないんですよね。でもその切なさのなかにも可笑しみがある。フォークナーの作品には常にその両方があるような感じがします。逆に言うとユーモアだけの作品はそんなにないかもしれません。
池澤 シェイクスピアの『マクベス』は悲劇だけれども、第二幕第三場の門番の愚痴とか、パート単位で見ると結構ユーモラスなんですよ。それに近い気がしますね。
柴田 『野生の棕櫚』にも「野生の棕櫚」と「オールド・マン」のパートがあるわけだけど、ユーモアは圧倒的に「オールド・マン」のほうにありますよね。シェイクスピアで言えば『真夏の夜の夢』にも一方に王や貴族の話があり、もう一方に大工や鍛冶屋の話があるけど、やっぱりユーモアは大工や鍛冶屋のほうにある。
池澤 そう、「野生の棕櫚」のパートはなかなか辛い。若い二人の逃避行の必死感が切ない。さっき自分の文章を書いていて気がついたんですけど、「オールド・マン」はジョーゼフ・キャンベルが『千の顔をもつ英雄』で提唱した「七つの段階」をほとんど踏襲してるんです。ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』に応用したとされる、天命を受け、旅立って、という英雄の旅の七つの段階です。最後に主人公が刑務所に帰ることで物語が円環しハッピーエンドを迎える。フォークナーは無意識に古典的な英雄物語をなぞって大団円に繋いだんだと思う。それが最終的にあの話の明るさなんですよね。ところが「野生の棕櫚」のほうはそうはいかない。同じように刑務所で終わるけれども、悔恨のうちに終わる。そういう対比もあると思います。「野生の棕櫚」を書き始めてすぐに何か足りないと思ったフォークナーが並行して書いたのが「オールド・マン」だけど、その「何か足りない」は明るさなんじゃないかと思う。
柴田 フォークナーが二◯二二年に読まれるときに気になるのがそこですよね。つまりそういう明るさを担うのは下っ端の白人や黒人だったりするじゃないですか。その人たちをだしにして明るさをつくってるとも言えるわけで、そのことの倫理性がどう読まれるのか。
桐山 フォークナー研究も最近はコンプライアンスでやりづらくなってるところはあります。以前学会で発表したときにいわゆるNワードを発表の資料でも映さないでほしいと言われました。アメリカだとそういう配慮がされている状態です。先ほどのお話でいうと、黒人や貧乏白人がユーモアを担う部分もたしかにあるんですが、一方で物事を引いた目で見ることができる、より強い生命力を持った人たちとしても描かれています。それ自体が差別的な見方かもしれませんが、敬意を持って見ている気はします。たとえば「野生の棕櫚」と「オールド・マン」でもロマンティックな夢を持っているハリーが現実に直面して挫折していく人として描かれているのに対して、囚人は最初から現実に幻滅しています。幻滅を抱えたまま自ら刑務所に帰っていくので、ハリーよりも前向きに見える。だからこそユーモアになるんです。
モダニズムと必然性のある「めちゃくちゃ」
小野 形容にも詩的な表現が多くて、どう日本語にしたらいいのかかなり悩みました。アメリカ南部の田舎で起きていることを描くのに「ラインの乙女」だったり、ギリシャ神話だったり大げさで古典的なものを引き合いに出したりするんですよね。演劇の比喩もやたらと多い。当時の読者からも、この人何を書いてるんだろうと思われたんじゃないかという気がするんですけど、どうなんでしょう。
桐山 当時もそう思われていたと思います。ただそれもフォークナーはある程度意図してやっています。「南部」自体がつくられた概念であって、そこに舞台的なところがあるということを自覚したうえで、ユーモアを込めて大げさに書いている。形容詞については、フォークナー自身ロマン派や象徴主義が好きだったので、半ば自虐的に使っているところもあると思います。
小野 ロマン主義的や象徴主義的な詩で使われるような表現を、土埃が舞っていて方言が飛び交っているヴァナキュラーな世界を描くのに使われると、その落差にマジでやってるんだろうかって驚いちゃうんですよ(笑)。
池澤 それはモダニズムだと思う。ジェイムズ・ジョイスは『ユリシーズ』で『オデュッセイア』をダブリンという小さな町に押し込めて、六月一六日の一日の話にした。そういう土台としての古典の使い方。その点ではフォークナーのほうが、ヘミングウェイよりずっと新しいですよ。その先にガルシア = マルケスがいる。落差は明らかに意図したものですよ。
柴田 それもフォークナーの「勇気」ですよね。ちょっとアメリカ文学史のおさらいみたいになっちゃうけど、フェニモア・クーパーが猟師なんかの姿を描くときにアメリカの自然に全くそぐわない、ヨーロッパ的で仰々しいロマンティックな言葉を使ったのを、マーク・トウェインは全然リアルじゃないと批判した。その後トウェインを引き継いだヘミングウェイが文学的な言葉を使わずに削ぎ落とした文章で小説を書き、一方でフォークナーはそれと正反対のことを自覚的に過剰にすることによって、それを価値のあるものにした。
小野 でも今あんなことをしたら、編集者にやめてくださいって言われそうですよね。
柴田 モダニズムの効用ってのはそこだよ(笑)。何をやっても読者はついてきてくれるっていう前提に立てる。というか、ついてこなくてもいいという前提。フォークナーが書いていたのが、リーダーフレンドリーが前提条件ではない時代だったということは間違いなくありますね。
池澤 だって、『アブサロム、アブサロム!』というタイトル、旧約聖書のあの話をどれだけの人が知っていますか。
桐山 『響きと怒り』の出版されなかった有名な序文のなかでフォークナーは、第一章を書く前に出版社や世間との扉を閉ざして、理解されなくてもいいという決意で書いたというようなことを記しています。別のところでは、二回読んでも三回読んでもわからなければ四回読めばいい、とも言っています(笑)。
―桐山さんが翻訳された「付録」は十五年ほど前に書いた『響きと怒り』から派生した姉妹作でありながら、フォークナーは『響きと怒り』を見もせず書き上げた作品だとか。
池澤 あれだけの数の人が常に頭のなかに住んでいるのは本当にすごいと思う。人の名前なんかは間違いもするかもしれないけど、エピソードはパッパッとつながっていくわけですよ。フォークナーの本籍はヨクナパトーファにあったんじゃないかな。だから現実の生活があれほど不器用だった。アルコールもひどいし、女性たちの出入りもあってあまり幸せには見えない。でも精神の大半はヨクナパトーファに行っていたわけでしょう。でなきゃあんな分量と密度書けるわけないですよ。
小野 フォークナーはあまり書き直しをしなかったみたいに言われますよね。そのあたりは実際どうなんですか?
桐山 かなり書き直しています。直し方を見ていると、人物の一貫性というよりは書きたい出来事がまずあって、そこから人物たちが発展していくように思います。だからヨクナパトーファも確固たる世界というより、かたちを変えながら広がっていく世界という感じがします。
小野 書きたいことがちゃんとあって、それをバーッと書いてるんですね。たしかに勢いとか疾走感があって美しいんですけど、やっぱり戸惑うところもありました。普通だったら全体をもうすこし均質にならして書くんじゃないかと思うんですが、凸凹をそのまま残しているというか。これも勇気ですか?
柴田 そう思いますね。大抵の場合小説には声があって、ある種の一貫したリズムなり何なりが流れている。いやフォークナーにも一貫して流れているものはあるんだけれども均質性はそんなに追求されないというか……どう言ったらいいのかな。
池澤 自分のなかから湧いてきちゃったんだから仕方ないんだと。
柴田 めちゃくちゃと言えばめちゃくちゃなんだけど、必然性は感じるんですよね。一読者として読むとフォークナーの強い声、要は一貫したものに気持ちがいくわけだけど、訳してるとさっき小野くんが言った、一貫したもののなかにある凸凹により目がいく。それは単にセンテンス中の凸凹じゃなくて、ヨクナパトーファ・サーガ全体のなかでの凸凹さでもある。『八月の光』とか『アブサロム』という大傑作だけを読んでると、緊張感の高い文章ばかり書き続けた作家という印象を受けるんだけど、『ポータブル・フォークナー』を訳してみてアプローチも文章もバラエティーに富んでいるなと実感しましたね。
非白人作家や非欧米圏への影響
柴田 それから『八月の光』なんかを読んでると、南部の人は南北戦争以降、大事が起きなければ時間は経たないに等しいみたいな、極端な時間感覚のなかで生きている人たちのように思ってしまうわけだけど、そこにちゃんと時間の経過があるということもカウリーはこのアンソロジーで見せてくれている。
池澤 批評家の仕事としてすごいですよ。創作をしなくてもひとつの文芸の流れをつくるのが批評家だから。藤原定家らが「新古今和歌集」を編纂してその後の和歌の流れを決定づけたのと同じように、『ポータブル・フォークナー』によってフォークナーは世界に受け入れられたわけでしょう。クロノロジーで編纂したのは大変な業績で、判断力だったと思います。
柴田 桐山くんのほうが詳しいと思うけど、当時はカウリーのほうがフォークナーより世間的にずっと偉かったんですよね?
桐山 そうですね。そもそもこの企画は一度ヴァイキング社に却下されていて、その後カウリーは自分でフォークナーについての論文を三本ほど書いて発表しています。フォークナーがいかに秀でた作家なのかを世間に主張したうえで、出版企画を通したんです(笑)。
柴田 だからフォークナーに対しても、このへんが矛盾してるから書き直せみたいなことを命じることができた。
桐山 そうです。一応相談というかたちではあるんですけど、かなり細かく修正の提案を出しています。収録作にしても傑作ではなくて、ヨクナパトーファを時系列で見せるという方針に沿った作品を選んだのは英断だったと思います。普段そんなに注目されない作品でもいざ読んでみると、どれも面白いんですよね。
小野 日本にはフォークナー研究者もフォークナーが好きな作家もたくさんいるのに、そんな重要な本が今まで訳されていなかったのはなぜなんでしょう?
桐山 日本の研究では、たとえば『八月の光』や『アブサロム』といったように一作単位で論じたものは多いんですが、ヨクナパトーファ全体はそれほど注目されていない気がします。作家に与えた影響としてはそっちのほうがはるかに大きいと思うんですけど。
小野 フォークナーに影響を受けた現代のアメリカの作家というとどんな人がいるんですかね。
柴田 僕が訳している作家だとスティーヴ・エリクソンがそうですね。自分がフォークナーの末裔だとはもちろん言わないけれども、記憶と時間の絡み合いのようなことはすべてフォークナーから学んだと公言しています。
桐山 アメリカだと、ラルフ・エリスンやトニ・モリスンなどアフリカ系アメリカ人の作家、それから非欧米圏の作家など、主流の白人以外の作家により受け入れられている気がします。フォークナーの手法が描きたいものと合致するんじゃないかと思います。
小野 僕の訳したマリー・ンディアイというフランスの作家は、形容句をいくつも並べて、洗練された、でも非常に訳しにくい文体で小説を書きます。ピリオドを打たずにカンマで文をつなげていく書き方の作品もありますし、一文が一〇〇ページ以上続く作品もあります。フランスだと彼女はプルースト的な伝統に連なる作家だと言われたりするのですが、実はフォークナーの系譜にもある書き手なんじゃないかなと今回訳して思いました。非白人や非英語圏の作家がフォークナーを読んで影響を受けているのは面白いですね。
桐山 土地に根づいた記憶が重要なテーマなので、反グローバリズムとの相性がいいんでしょうね。逆にグローバリズムが進んだ主流の白人文化はそのあとポストモダニズムに行ってしまうのでフォークナー的なものには結びつきづらい。
小野 池澤さんは『百年の孤独』の単行本をバラバラに解体して研究されるぐらいガルシア = マルケスには影響を受けていらっしゃると思うんですけど、フォークナーはどうですか?
池澤 文体への影響は多分ないですね。むしろフォークナーを横目で見ながら民話の語りに変えたガルシア = マルケスに寄っていきました。それで『マシアス・ギリの失脚』でラテンアメリカ文学に少なくない大統領小説を書こうとしたんです。前にアップダイクの『クーデタ』を訳していたし。しかし書いてみると毒が足りないのね。ダークな部分が。ラテンアメリカにはカトリックがあるから、光と闇の対比が強烈なんです。フォークナーもそうだった。いちばんいい例が『アブサロム、アブサロム!』ですね。それを日本語で書こうとすると、というか僕の力で書くとぬるくなってしまう。光と闇の対比という点では、中上健次のほうがずっと勇敢だったかもしれない。これは性格だから仕方がないし、真似しようもないけど。
小野 ヘミングウェイの文体は一度解体してもちゃんと組み立て直すことのできる文体だけど、フォークナーの文体はいきなり部屋に馬が入ってきてめちゃくちゃに暴れ回って出ていった後みたいな文体だ、とどこかで読んだ記憶があります。誰の言葉か思い出せないんですが、うまいこと言うなあって。そんな文章真似できないですよね。部屋のなかに暴れ馬を放つしかないわけですから(笑)。
フォークナーは難解と言われるけれど
―皆さんの好きなフォークナー作品は?
池澤 やっぱり自分が訳した「オールド・マン」がいい。主人公は運命にさんざんいじめられながらも超律儀なわけですよ。舟と女を連れて帰るんだから。最後のほうでようやくその女と肉体関係があったということをポロリと漏らす。コミックですよね。
柴田 いや本当に「オールド・マン」が入っていてよかったなと思います。クロノロジーをつくるという観点から言えば、いちばん入る理由がない作品ですよね。それでもこれを入れようと決めたカウリーのセンスはすごい。
僕が今回強く思ったのは、フォークナーが短篇作家としてすごくいいということ。特に「死の曲芸飛行」には惹かれましたね。アメリカ人の友達は「これは反ユダヤ主義じゃないか」って言っていたけど、僕はそう思わない。むしろ敬意だと思う。
桐山 研究者のあいだでも意見が割れますね。反ユダヤ主義だという意見もあるし、それを超えたものであって積極的に評価すべきという意見もある。
小野 読みどころで言ったら、柴田先生が訳された「郡庁舎」。ピリオドがなくてセミコロンで文章をつないでいるんですよね。僕は同じ作品から取られた「監獄」を担当して普通に「、」と「。」で訳してしまったんですが、先生はセミコロンを生かしながら、かつ読めるものに訳されている。画期的な翻訳だと思います。
柴田 二葉亭四迷をはじめ明治の翻訳者たちも日本語におけるセミコロン問題に直面して、セミコロンに相当する白抜きの点〔白ごま点〕を使ってみたわけですよね。でも当時の印刷技術じゃ普通の「、」と区別がつかず、全然広まらなかった。日本語に定着しなかったことは残念でならないですよ。それはともかく「郡庁舎」はアンソロジーの第一部に入っているので、フォークナーの文体の異様さをショック療法的にまず見せたいという気持ちがあった。それで「。」の代わりに空白を使ったりして再現したわけです。小野くんが最後のほうの第八部で、「郡庁舎」の続きである「監獄」を訳してるけど、僕も「郡庁舎」が最後のほうだったら同じように訳したかはわからないですね。
小野 最初はこんな文章は見たことないから読みにくいんじゃないかと思ってたんです。でも読んだら気にならないんですよね。慣れちゃってそのまま最後まで読める。
柴田 英語の読者も違和感を持ちながら読んでいくはずですよ。こんなにセミコロンでつないでいる小説は他にないから。
小野 桐山さんが訳された「ディルシー」も素晴らしいと思いました。僕この作品すごく好きなんですよ。
桐山 「ディルシー」は『響きと怒り』の一部ですけど、これまでの翻訳では黒人の描写が他者化されすぎていると感じていました。原文ではもっと生き生きと描かれているんです。今回はそこを意識して訳しました。それから自分が訳した「アド・アストラ」には思い入れがあります。フォークナーはよく難解だと言われるんですが、決して抽象的ではないので、たとえばベケットみたいな難解さとは全く違うものだと思うんですね。特に「アド・アストラ」は日本ではあまり知られていない作品ですが、心情的に入りやすいし読みやすいのでぜひ読んでもらいたいです。
柴田 さっき南部の日常とは関係ない形容詞が出てくるという話があったけど、フォークナーはそれで話が抽象化するんじゃなくて、より生々しくなる方向に向かうんですよね。そこがジョゼフ・コンラッドとは違う。抽象的な言葉はだいたいラテン語起源なんだけど、フォークナーはラテン語を突き抜けてギリシャ語起源の言葉もよく使う。それなのに抽象的にはならないんですよね。
小野 たしかに抽象的なものが出てきても、世界自体は地面にちゃんと足がついている感じがあります。
柴田 さっきは難しいという話をしたけど、今回の我々の訳、原文以上に難しくなるようなことにはしなかったつもりです。日本で古川日出男さんがこれだけ読まれてるんだから、フォークナーも読まれるだろうって思うんだけど、乱暴か(笑)。
桐山 そもそもフォークナーを専門にしている僕にとってはある意味フォークナーがいちばんわかる作家なので、難解な作家とも思わないんです。文章は多少難しいですけど、とにかく面白い作品を書く作家だと思ってます。
柴田 いい発言だなあ(笑)。
小野 フォークナー作品って時々息を吞むような描写があって、映像みたいなんですよね。運動が文章で伝わってくる。だから映像文化に親しんでいる人たちも楽しみやすいんじゃないかなと思います。いやあでも、こんな座談会ができる日が来るとは夢にも思っていませんでした。本当にいつ訳し終わるんだろうと思っていたので。
柴田 僕も「熊」を訳してるときは、いつこの森から出られるんだろうって感じだったよ(笑)。
池澤 それにしても、みんなよく訳しましたね。結局それに尽きますよ。その上で付け加えれば、編集者は裏方だけど、この本を作った木村由美子さんの尽力も特筆に値します。映画「ベン・ハー」の戦車競走の場面、四頭の馬を鞭打って走らせる、あれが木村さんでした。
(二〇二二・二・一四)
*1 『ポータブル・フォークナー』The Portable Faulkner
ヴァイキング社から一九四六年に出版されたアンソロジー。物語内の年代順に作品を並べている点が最大の特徴。フォークナーが一つの架空の土地を舞台に物語を書き継いだことに注目を促し、当時ほとんどの作品が絶版となっていたフォークナーの評価を一躍高めた。今回の訳書は一九六七年に出版された改訂版の全訳。
*2 マルカム・カウリー Malcolm Cowley(1898-1989)
アメリカの批評家・編集者。戦前はマルクス主義に傾倒し、一九二九年から四四年まで左派雑誌『ニュー・リパブリック』の編集者を務めた。一九三四年に「失われた世代」の人々を活写したエッセイ『亡命者帰る―「失われた世代」の文学歴』を出版。一九四四年からヴァイキング社の「ポータブル・ライブラリー」シリーズの編集に携わった。
*3 ヨクナパトーファ Yoknapatawpha
フォークナーの故郷、ミシシッピ州ラファイエット郡をモデルとした架空の土地。フォークナー作品の多くはヨクナパトーファ郡を舞台とし、同じ人物が複数の作品に登場する。この形式は多くの追随者を生み出した。代表例は、「マコンド」を舞台に作品を書き継いだコロンビアの作家ガブリエル・ガルシア=マルケス。
*4 「エミリに薔薇を」 “A Rose for Emily”
一九三〇年に発表された、フォークナーの最も有名な短篇の一つ。ヨクナパトーファ郡の郡庁所在地ジェファソンに暮らす未婚女性エミリ・グリアソンをめぐるトラブルを「我々」の視点から描く。本作に薔薇の花は登場しないが、フォークナーは題名の意味を問われた際、悲劇に見舞われたエミリを哀れんで付けた題だと述べた。
*5 『野生の棕櫚』 The Wild Palms
一九三九年出版。「野生の棕櫚」と「オールド・マン」という別々の物語が交互に展開される二重小説の形式を持つ。厳密に言えばヨクナパトーファものではないが、カウリーは「オールド・マン」のみを切り出して『ポータブル・フォークナー』に収録した。「野生の棕櫚」は既婚の女性と駆け落ちする医者志望の青年の物語。
*6 「オールド・マン」 “Old Man”
一九二七年のミシシッピ川大氾濫の際に労役に駆り出され、度重なる洪水の影響で自由になる機会を得るも自らの意思で刑務所に帰っていく囚人を描く。「オールド・マン」はミシシッピ川の別称。カウリーは本作の自然描写とユーモアを高く評価し、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』(一八八四)に比した。
*7 「まだら馬」 “Spotted Horses”
一九三一年に短篇として発表されたのち、大幅に改訂されて『村』(一九四〇)に組み込まれた。『ポータブル・フォークナー』に収められているのは『村』版。ジェファソン郊外のフレンチマンズ・ベンドを舞台に、馬の競売に端を発するドタバタ劇を通じて南部の貧乏白人たちが資本主義的価値観に侵蝕されていく様を描く。
*8 「監獄(まだ完全に放棄されたわけではない―)」“The Jail (Not Even Yet Quite Relinquish―)”
『尼僧への鎮魂歌』(一九五一)第三幕の前に付されたプロローグ。監獄を一種の「視点事物」として、ジェファソンおよび南部全体の歴史が振り返られる。本作の原文では第二文以降ピリオドがなく、コロンとセミコロンで繫がれた文が延々と続き、末尾でようやく二つ目のピリオドが打たれるという異様な形式が採られている。
*9 「熊」 “The Bear”
『行け、モーセ』(一九四二)の第五章。第一~三セクションでは伝説的な熊オールド・ベン狩りが果たされるまでを、第五セクションではその後の顚末が描かれる。長篇全体を読み解く鍵ともなる第四セクションでは、曖昧な記録や伝承と個人のトラウマを含む記憶・思考が混じり合う中から主人公の祖先の罪が明かされていく。
*10 『標識塔(パイロン)』 Pylon
一九三五年に出版された長篇。ニューオーリンズをモデルとした架空の都市を舞台にし、非人間的な生活を送る曲芸飛行士たちを描く。本作はヨクナパトーファものには属さず、『ポータブル・フォークナー』にも収録されていない。後述の「死の曲芸飛行」もヨクナパトーファとの関連は薄く、テーマ面ではむしろ本作に近い。
*11 『八月の光』 Light in August
一九三二年に出版されたフォークナーの代表作の一つ。消えた恋人を探して旅する妊婦、南北戦争中に戦死した祖父の幻影に取り憑かれた牧師、白人のような見た目でありながら黒人の血が入っていると噂される殺人者の三人の物語が混在する。『ポータブル・フォークナー』収録の「パーシー・グリム」は本作終盤からの抜粋。
*12 『アブサロム、アブサロム!』 Absalom, Absalom!
一九三六年に出版された長篇。しばしばフォークナーの最高傑作と称される。南北戦争前後のジェファソン近郊でトマス・サトペンとその家族に起こった悲劇の謎を、『響きと怒り』に登場するクエンティン・コンプソンらが探究する。現在と過去が重層的に折り重なる複雑な語りを通じて南部の闇とも言うべき真相が明らかにされる。
*13 「付録――コンプソン一族」 “Appendix: The Compsons”
『ポータブル・フォークナー』が初出。『響きと怒り』最終章の抜粋である「ディルシー」を補完するために書き下ろされた。当初は数頁の小説の梗概を書くと言っていたフォークナーだが、出来上がったものはコンプソン一族の来歴を語る実質上の新作だった。小説本篇との異同も多く、カウリーを大いに困惑させることになった。
*14 『響きと怒り』 The Sound and the Fury
一九二九年に出版された長篇。当時のモダニズム文学の流れをくんだ実験的文体および時間と視点の緻密な操作により、初期フォークナーの主要テーマである南部名家の没落をその内部の人々の心理も含めて描き切った本作は、フォークナーが作家として大きく飛躍する契機となり、作家自身も本作に対する特別な愛着を表明している。
*15 「死の曲芸飛行」 “Death Drag”
一九三二年発表の短篇。フォークナーは本作を含め、第一次世界大戦で心に傷を負った男たちによる危険な飛行を題材にした物語を度々描いた。本作の主要人物ギンズファーブはユダヤ人であり、金のためなら命の危険すら顧みず、曲芸飛行の興行で身を立てている。この描写が反ユダヤ的ステレオタイプだと評されることもある。
*16 「郡庁舎(市の名前)」 “The Courthouse (A Name for the City)”
三幕構成の戯曲である『尼僧への鎮魂歌』(一九五一)では、それぞれの幕の前に散文のプロローグが付けられ、州や郡の歴史が語られる。本作は第一幕のプロローグ。一つの南京錠の紛失をめぐる騒動を通じてヨクナパトーファ郡の郡庁所在地ジェファソンが創設・命名される経緯が描かれる。コンプソン家の祖先なども登場する。
*17 「ディルシー」“Dilsey”
『響きと怒り』第四章からの抜粋。コンプソン兄弟の一人称視点から語られたそれまでの章とは打って変わって三人称の平明な文体で描かれる。崩壊していくコンプソン家を見守る召使のディルシーに焦点があてられ、作品後半では黒人教会での熱狂的なイースター礼拝の様子が描かれる。
*18 「アド・アストラ」“Ad Astra”
一九三一年に発表された短篇。第一次世界大戦の休戦協定が結ばれた日の夜、自分たちが何のために戦っていたのか、自分たちが何者なのかがわからなくなり、フランスのアミアン近郊で飲んだくれる兵士たちを描く。大戦に幻滅した結果、失意のなか享楽的な生活に溺れる若者世代、いわゆる「失われた世代」の文学に属する。
■編者紹介 マルカム・カウリー Malcolm Cowley(1898〜1989)
アメリカ・ペンシルヴァニア州出身の詩人、批評家。「ニュー・リパブリック」誌の編集などを手がけ、第二次世界大戦後はアメリカの文芸ジャーナリズムを牽引、20世紀アメリカ論壇に多大な影響を及ぼした。選集の編者としても知られ、当時一般読者にはあまり読まれていなかったフォークナーの評価を一気に高めた『ポータブル・フォークナー』編纂の業績は大きい。
■訳者紹介
池澤夏樹(いけざわ・なつき)
1945年北海道生まれ。作家、詩人。著書に『スティル・ライフ』(芥川賞)、『マシアス・ギリの失脚』『花を運ぶ妹』『静かな大地』など。訳書に『カヴァフィス全詩』など。
小野正嗣(おの・まさつぐ)
1970年大分県生まれ。作家、早稲田大学教授。著書に『にぎやかな湾に背負われた船』(三島賞)、『九年前の祈り』(芥川賞)など。訳書にM・ンディアイ『三人の逞しい女』など。
桐山大介(きりやま・だいすけ)
1983年神奈川県生まれ。アメリカ文学研究者、学習院大学准教授。専門はフォークナー、R・エリスンなどアメリカモダニズム小説。共訳書にD・ダムロッシュ『世界文学とは何か?』など。
柴田元幸(しばた・もとゆき)
1954年東京都生まれ。翻訳家、東京大学名誉教授。P・オースター、S・ミルハウザーはじめ現代アメリカ小説の翻訳多数。著書に『生半可な學者』(講談社エッセイ賞)など。