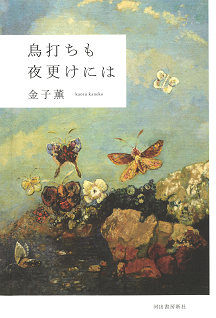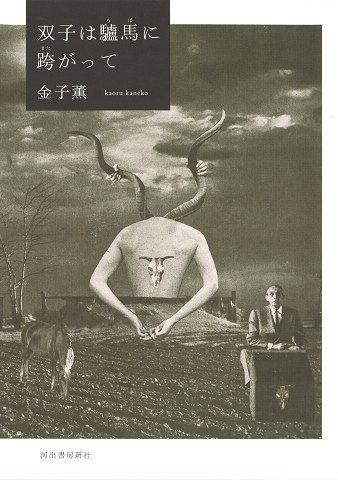ためし読み - 文藝
「文藝」冬季号掲載、金子薫「成るや成らざるや奇天の蜂」試し読み
金子薫
2022.10.06
法の届かないスラムの奇天座で、究極のドラッグ・ロロクリにより獣と化す住人たち。西尾はひとり人間のまま、ロロクリに溺れるのだが……。野間文芸新人賞作家の新境地。
===↓試し読みはこの↓へ===
成るや成らざるや奇天の蜂
金子薫
ずらりと並ぶドアから漏れる声や、廊下の彼方(かなた)から届く声が混じり合って、一つの呻き声のように反響していた。扉を薄く開き、廊下の様子を窺(うかが)う人々の顔が見える。幾つもの眼が通り過ぎていく西尾陽介を見張っている。
食事の匂いのしている部屋もあれば、大音量でテレビをつけ放しにしている部屋もある。大麻の香りを嗅いだかと思えば、その隣の部屋からは不快な臭い、おそらくは生塵(なまごみ)の発している臭気が漂ってくる。ひょっとすると室内で人間が死んでいるのかも知れない。
埃(ほこり)っぽい空気の籠もる廊下を進み、やがて西尾は、突き当たりにある非常用の扉を押し開いた。軋(きし)りを立て、淡い黄色に塗られた鉄の扉が開き、冷たい夜風が勢いよく廊下に吹き込んできた。
夜の闇に浮かび上がるように、螺旋階段が姿を現すと、西尾は恐れを胸に抱いた。外に向けて一歩を踏み出し、螺旋階段を下り始める。螺旋階段は鉄柵に囲われて高層ビルの外に露出しており、全体が錆(さ)びついている上に、手摺りの外れている箇所まで見られる。
蜂の道化プルチネッラが現れる酒場に行くため、西尾は十四階から九階に行かねばならない。〈奇天座〉は積み木遊びの如く、百以上のマンションやビルが結合し、未だ増築の続いている高層建築物の塊であり、階を移動するにはエレベーターに乗る方が遥かに早い。だがエレベーターの故障、乗り場の混雑、停電の可能性などを考慮し、西尾は日頃から階段を使うようにしていた。
売人プルチネッラも、エレベーターを使って来る者より、命を粗末に扱うかの如く螺旋階段で移動する、自分のような者にこそ、道化服を纏った姿を見せ、ロロクリを売りたいと思っているのではないか。
雨が降っていた。足を滑らせることのないよう、西尾は一歩ずつ着実に段を踏んで歩く。小雨の音のみならず、上からも下からも靴底の立てる音が聞こえてくる。他の住人も西尾と同じく、何かしらの欲望を満たすため、足を竦(すく)ませながら、ある階から別の階へ移動しているのだった。
夜間の移動に際しては、本当は各々が懐中電灯を持ち歩くべきなのだろう。麻薬やそれに類する快楽を求め、我が身を高層ビルの外部に晒(さら)して歩く〈奇天座〉の住人であるが、転がっている廃棄品に足を取られたり、寄り掛かった鉄柵ごと落下したり、そうして命を落とす者も後を絶たない。
髪や服を雨で濡らしつつ、錆びついた柵に手を滑らせ、西尾は幻覚剤を求めて下り続ける。空腹も感じてはいるが、どうせ金を使うなら、食事を愉しむよりロロクリの見せる幻に吞まれたい。
しかし仮にプルチネッラが不在であれば、自分はロロクリを入手できない。麻薬の売人は常に中毒者よりも優位に立っており、その上下関係が覆ることはない。西尾はプルチネッラの売り捌(さば)く幻覚剤に依存しているが、売人であるプルチネッラの方は、西尾が死んでしまおうと、また別の中毒者を見つけるか、薬を与えて新しい中毒者を生み出すかすればいい。
それでもロロクリが貰えるならば、何もかも瑣末(さまつ)な問題である。高さに慄(おのの)きつつも西尾の足取りは速くなる一方だった。プルチネッラを探し出して有り金をロロクリに変えるべく、夜の枯れ野の果て、山々の向こうに煌めく市街地を時に見遣り、西尾は螺旋を描いて非常階段を下降していく。
スプレーで薔薇の描かれている扉を開き、店内に入ると、常と変わらず〈花畑〉は異形の者たちで賑わっていた。黄色い嘴(くちばし)の生えている南国風の鳥の頭を被った男と、ボール紙と紙粘土などで作られた羽を背中につけた天使の女が、カウンター席に並んで掛けている。
西尾が天使の隣に腰掛けると、満席まで残り一席となった。空席は西尾の右隣に残っているが、言うまでもなく、西尾も他の客たちも、その席には蜂の道化プルチネッラが坐ることを望んでいる。
「ビールをください」
西尾の言葉にカウンターの向こうで頷くと、五十代だが年齢より若く見える店主の仰木(おおぎ)は、背後の壁に設置された棚からグラスを取り、サーバーの把手に手を掛けた。ビールを注いで反対側に把手を倒し、白い泡を載せながら彼は言った。
「今夜も普通の服ですね」
自分の着ている白一色のスウェットシャツを見て、西尾は言った。
「動物になることには、やっぱり抵抗がありまして」
仰木は声を落として言った。
「いや、西尾さんはそれでいいのです。ここが開店したばかりの頃は、仮装しているお客さんなんて店内に精々一人か二人でした。十年ほど前にロロクリが流行し始め、それからあれよあれよと、ほら、今じゃこの有り様です」
「そんな時代もあったんですね。仮装していない人が飲みに来ていたとは、なかなか信じられないです。この店では自分以外に見たことがありません。初めて飲みに来た時にはすでにロロクリがありましたから。ところで、プルチネッラが来ていないとは残念です」
グラスを西尾に手渡して仰木は言った。
「ええ、お見えになっておりません」
この酒場〈花畑〉に客足が絶えないのも、稀ながらロロクリを売りに来る道化師のお蔭であり、店主も、過去を懐かしく回顧しつつも、内心ではプルチネッラの登場を心待ちにしているのだった。ロロクリの使用が爆発的に広まり、所謂(いわゆる)一般の客は殆(ほとん)ど来なくなってしまったが、代わりに多くの常用者が屯(たむろ)するようになり、むしろ売上は増えているらしい。
「これから来ることを祈ります」
そう言って西尾は初めの一口を飲む。忽(たちま)ち緊張は緩み、プルチネッラは必ず来ると楽天的に信じられるようになった。酒を飲みながら、期待を胸に待っていれば、蜂の道化師は花畑に誘い込まれる如く姿を見せ、甘い蜜を分け与える如く幻覚剤を配ってくれる筈である。
隣にいる天使は柔和な微笑を絶やさず、背中の翼を静かに揺すり、自分自身の役、優しい天使を演じることに努めていた。しかし、手元には剥き出しの錠剤が転がっている。よく見ればロロクリとは異なる薬である。西尾の二つ隣、天使の隣の席では、南国生まれらしき鳥が、緑と赤に塗り分けられた頭部を片手で支え、もう一方の手でグラスを口元に運んでいる。
酒を飲むためにずらしていた嘴を、ぐにゃりと曲げて元の位置へと戻すと、鳥男は嗄(しゃが)れ声(ごえ)を殊更に作り、誰に言うともなく吐き捨てた。
「プルチネッラが来るかどうか、情報はないのかね。気休めになればガセネタだって歓迎したい位だが」
鳥は被り物だけでなく躰(からだ)も彩り豊かであった。翼の接合された青いトレーナーに、布団や枕から取り出したであろう無数の羽毛が、色様々に染められた上で接着されている。鳥と天使は比較的しっかりと衣装を整えており、その分、ロロクリの使用歴も他の者より長そうだった。
二人の背後では三人組の男たちがテーブルを囲んでいた。一人は芋虫、もう一人は蛹、最後の一人は翅(はね)のある蛾(ガ)のコスチュームを纏(まと)っている。相談して衣装を合わせて来店したに違いない。
虫たちは三匹とも若々しかった。二十代前半かそこらであろうか。芋虫は黄緑色の寝袋を作り替えた衣装に身を包んでいた。寝袋の丸い穴から顔と縮れた前髪が覗き、胸の辺りには手を出すための小さな穴が空いている。穴から伸びている人間の手の他に、装飾として幾対かの胸肢も生えており、今にも小枝に掴(つか)まり、ばりばりと、青い葉を食い散らかしながら這(は)っていきそうに見える。
蛹は芋虫の色違いでしかなく、茶色い寝袋から作られた衣装に、肉体をすっぽりと収め、顔と手だけを控え目に露出させていた。両隣に蛾と芋虫がいなければ、それが蛹だとは分からないかも知れない。
三人のなかで唯一、手の込んだ衣装を纏う蛾は、雀蛾(スズメガ)を模倣しているようだった。ハングライダーの翼のような形の翅を背中につけており、背凭(せもた)れとの間で押し潰してしまわぬよう、背筋をぴんと伸ばして椅子に掛けている。
観察しつつ西尾は考える。三人において主導権を握っているのは、おそらくは蛾の青年であろう。芋虫や蛹の、寝袋を利用した粗雑な衣装とは異なり、蛾のみが丁寧に衣装を用意している。ロロクリに心酔し切っているのは蛾の青年であり、他の二人は彼に調子を合わせているのではないか。
二人の女、天道虫(テントウムシ)と揚羽蝶(アゲハチョウ)が、ベランダへと出られる窓辺に置かれた、四角い木のテーブルを挟んで向き合い、それぞれパイプ椅子に坐っていた。彼女らの足元には、雄の兎が弛んだ腹を晒して仰向けに寝転がっている。やたらと写実的に作られた黒い兎の被り物を着用しているその男は、虫の女たちから向けられる冷ややかな視線には気づかず、頻繁に白眼を剥き、麻薬の熱に浮かされているのか、いまいち聞き取れぬ言葉を自らと対話するように呟いている。
人の腹を露出させてはいるが、全体として随分精巧に作られている黒兎の衣装と比べると、天道虫と揚羽蝶の衣装は、実際の昆虫よりさらに色彩が派手で、模様にもデフォルメが施されており、ロロクリの効果を増幅させる目的とは別に、洒落(しゃれ)た私服としても使われている如く見えた。
譫言(うわごと)を呟くばかりだった黒兎が、突如、甲高い声で喚きだした。
「提案があります! ここにいる皆でお金を出し合い、プルチネッラ殿に懐中時計を進呈しようじゃありませんか! ある曜日のある時間になったら、ロロクリを持って花畑に来てくださるよう、時計の贈り物を添えてお願いするのです」
揚羽蝶と天道虫が椅子から立ち上がり、黒兎を跨いでカウンターに近づいてきた。ビニール製の極彩色の翅を揺らして揚羽蝶は言った。
「時計なんか貰うよりも、いつも通り客としてロロクリを買ってくれた方が、ずっと喜ぶんじゃないの? それより、これ以上待っても来ないなら、あと一杯だけ飲んで帰っちゃおうか」
赤く塗られ、黒点の散らされている大きなプラスチックの半球を、背中におんぶする如く両手で支えつつ、天道虫も言った。
「ロロクリなら部屋に残ってるからね。今日は手に入らなくてもいいか。だけどさ、売りに来たり来なかったり、プルチネッラも適当な商売してるなあ」
仰木に空のグラスを返してから、揚羽蝶が言った。
「さっきと同じの、二つちょうだい。ロックで」
ビールを飲み干して西尾も言った。
「スコッチを水割りでお願いします」
できれば次のスコッチで閉店まで粘りたかった。ロロクリを買うための金を残しておかねばならない。欲しいのは酒でなく幻覚剤である。プルチネッラが来たとして、その時に所持金が尽きていては意味がない。
グラスを受け取り、二匹の虫の女が窓辺の席に戻っていくと、入れ替わりに黒が立ち上がり、カウンターに身を乗り出してきた。ポケットから皺くちゃになった札を出して、媚びた笑顔を作り、黒兎は天使に語りかけた。
「聞いてください。これが私の最後の金です。今夜はこれっぽっちしか持ち合わせがございません。美しい天使様、このお札と、そこらに散らばっている錠剤を、どうか交換してくださいませんか?」
アルコールを注文するのかと思いきや、プルチネッラが姿を現さないので、黒兎は天使に麻薬を売るよう持ち掛けたのだった。店主の仰木は、兎の頭を被っている男に苦々しげな表情を見せたが、プルチネッラには許している以上、店内での薬の売買を禁止する訳にはいかない。
カウンターに転がっている錠剤を鷲掴(わしづか)みにすると、黒兎には言葉を返さず、天使は席を立った。ボール紙に紙粘土を接着してある真白い羽を、西尾と鳥男にぶつけないように注意しながら、芋虫、蛹、蛾の三人が囲んでいる、丸いテーブルの方へ歩いていく。
「すでに愉しんでいる兎さんより、三匹で静かにしてるあなたたちにこそ、この薬はあげるべきでしょう。どうぞ、お好きな色を選んでください。お代は頂きませんが、早い者勝ちですよ」
そう言いながら、天使はテーブルに錠剤をぽろぽろ零(こぼ)していく。カウンターに凭れ掛かり、黒は着ぐるみから、意気消沈した、青髭(あおひげ)の目立つ顔を覗かせ、その様子を羨ましそうに見ていた。天からの恵みは小動物ではなく、昆虫のもとに降り注いだのだった。西尾も黒兎と一緒にカウンター席から眺める。
天使の施し物に逸早く手を伸ばしたのは、茶色い寝袋と一体化している蛹の青年であった。青年は錠剤を掌(てのひら)に載せて言った。
「天使さん、ありがとうございます!」
テーブルの上で錠剤を選(え)り分けながら、芋虫も言った。
「僕は緑を頂きます。葉っぱが大好物ですから。食べるのも巻いて吸うのもやっぱり緑の葉っぱが一番ですし、錠剤だってそれは変わらない筈です」
自分もお零れに与るべきか西尾が迷っていると、天使の空席を挟み、今や隣同士となった鳥男が、転げ落ちる如く椅子から下り、虫たちのテーブルに接近していった。鳥男は蛾の青年の正面の席についた。
丸テーブルに残っていた錠剤を拾い、鳥は蛾に言った。
「この一錠だけ分けてくれませんか?」
薄いプラスチック板を翅にしている蛾は、複眼と触覚をつけてある被り物のなかで笑った。
「一錠と言わず、好きに取っていいです。天使様がくれた薬でも僕は要らないから。だって、これ、ロロクリじゃないでしょう? 僕はロロクリをやるために、おかしな服を着て友達と集まってるんです。知らない薬はやりたくないし、きっとその薬じゃ変身できない。気持ちよく酩酊できたり、多少は自分が誰だか分からなくなったり、その程度の薬なら、他に幾らでもある。でも物凄い暗示が掛かって、躰がむずむずと痒くなり、気づいたら蛾になって飛んでる薬はロロクリだけだ」
ビールで錠剤を飲み下し、グラスを置いてから蛹の青年が言った。
「君はロロクリにこだわり過ぎてやしないか? 僕は正直、薬なら何だって歓迎さ。これも何か知らないけど飲んじゃった」
蛹のグラスからビールを飲み、芋虫も緑の錠剤を腹に収めて言った。
「十中八九、覚醒剤と幻覚剤の混ぜ物ってところじゃないか? 天使さん、これって飲んでも大丈夫ですか? 死んだりしないですよね?」
天使は型通りの微笑みを浮かべて言った。
「ええ、勿論(もちろん)です。ロロクリのような効果を期待してはいけませんが、その代わり、副作用も依存性もそこまで強くありません。ただし飲む量にはくれぐれも気をつけて遊んでください」
西尾は見逃さなかった。黒兎の男には施し物をせず、無視する如く芋虫たちに薬を振る舞った天使であるが、瞬間、彼女も瞬きを繰り返し、黒兎の如く白眼を剥いたのだった。天使を演じてはいるが、この女も兎と同じ穴の狢(ムジナ)であり、一皮剥けば重度の中毒者でしかない。錠剤の効果で一時的に気前よくなっているに過ぎず、醒めてから薬代を要求するかも知れない。
芋虫の青年は、黄緑色の寝袋の穴に人間の手を仕舞い、いっそう芋虫らしくなっていた。穴から手を出すと、大麻のジョイントが握られており、火はついていないにも拘わらず、西尾の席まで香りが漂ってくる如く感じられた。
気がつけば、西尾の手元のグラスは空になっていた。ロロクリ以外の薬には然(さ)して執着していない筈だが、各種の麻薬をまざまざと見せつけられて、躰は渇きを覚えていたのである。芋虫がジョイントを咥(くわ)えて着火すると、蛹と蛾も一本ずつ貰い、各々火をつけた。三匹の坐る席から煙が昇っていく様が見える。
揚羽蝶と天道虫が席を立ち、窓辺から離れ、煙の匂いを愉しむためか、残っている錠剤を探すためか、昆虫たちのテーブルに寄っていった。鳥男も芋虫から吸いかけの大麻を廻してもらい、嘴を横にずらして一服し、興奮を露わにして叫んだ。
「いやいや、何とも美しい夜じゃないかね! プルチネッラはいないが、天使さんと芋虫さんたちから素敵な品を貰ってしまった。素晴らしい! これぞ生きているってことだ! なあ、違うかね?」
よろめきながらカウンターを離れ、黒兎も鳥の後ろに立って言った。
「奇天座に感謝、そして花畑に感謝ですなあ! 仮にプルチネッラ殿がいなくても、ここは楽園だということです。さあ、さあ、誰かこのお札を薬と取り替えてくださいませ!」
仰木がカウンターから西尾の頭越しに言った。
「お客さん、お願いですから、何かお酒も頼んでください。うちを阿片窟(アヘンくつ)にするのはやめてくれませんか!」
店主の嘆願を聞き、皆がどっと笑った。この哄笑によって、〈花畑〉は密閉された阿片窟に変わってしまった。アルコールを頼む者はいなくなり、薬物の贈与、交換、売買などが、堰(せき)を切ったように盛んになりそうだった。薬が欲しくて堪らず、西尾もカウンター席を立った。
だが、彼は皆の群がるテーブルの方に進めなかった。仰木に同情した訳ではない。ジーンズに白いスウェットシャツの西尾は、異形の集まりを正面から見据えた途端、今更ながら混じることを躊躇(ちゅうちょ)したのであった。
乏しい有り金を麻薬に注ぎ込み、すべてを失い、窶(やつ)れ果てていった中毒者の末路がそこにあった。皆、派手な衣装でごまかしてはいるが、手足は枯れ木のようである。黒兎も例外でなく、腹は弛んでいても四肢は子供の如く細い。
揚羽蝶と天道虫と天使、三人の女たちも、化粧で血色よく見せているものの、頬が痩けてしまっている。鳥男は特に悲惨であり、青いトレーナーの袖には針を打ち込むための穴が空いており、紫に変色した注射痕がちらりと覗いている。
これこそが生である、などとは思いたくなかった。自我を消し去り、異なる存在に生まれ変わると言えば、幾らか聞こえはいいのかも知れないが、それは畢竟(ひっきょう)、自殺の言い換え、パロディに過ぎない。ロロクリに魅了されてはいても、自分は断じて死に魅了されている訳ではないと信じたい。陶酔を求めることが即ち死を望むことになる筈がない。私は私でありながら、この白いシャツを着たまま、不潔極まりない偽物の獣にならなくとも、ロロクリによって昂揚を得られるのだから。
幸せそうに大麻を燻(くゆ)らせつつ、それでも大麻だけでは満足できないらしく、鳥男が言った。
「プルチネッラは来ないのか? もしやあの男、今夜も来ないつもりかね? 我々がどんな気持ちで、どれだけの希望を胸に花畑に集まっているのか、少しは思い遣りを持って想像してほしいものだ。肉を求める獅子みたくロロクリに飢えていることが、あの男には分からんのか?」
プルチネッラは現れそうにない。ロロクリが手に入らないならば、部屋に帰るべき頃合いだった。ロロクリに依存しつつも衣装を纏うまでには至らず、中毒者と一緒に遊ぶことのできない西尾は、仰木にビールとスコッチ代を払い、大麻の香りに満ちた酒場を去ることにした。
続きは2022年10月7日発売 「文藝」冬季号でお楽しみください。