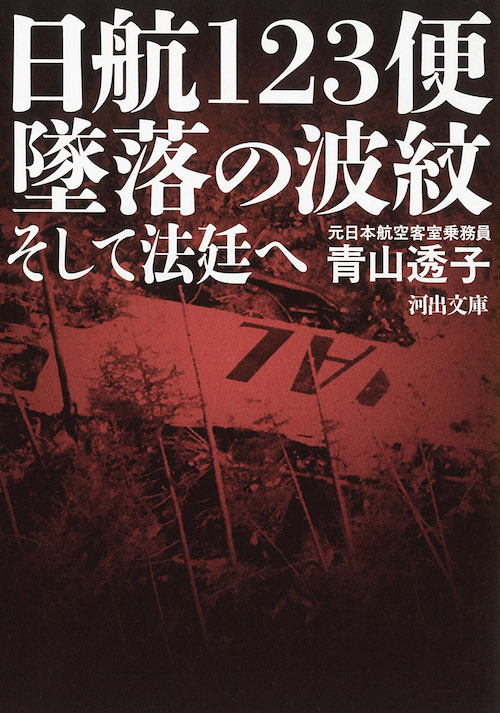ためし読み - 文藝
第59回文藝賞受賞作!安堂ホセ『ジャクソンひとり』試し読み
安堂ホセ
2022.11.25
着ていたTシャツに隠されたQRコードから過激な動画が流出し、職場で嫌疑をかけられたジャクソンは3人の男に出会う――。
痛快な知恵で生き抜く若者たちの鮮烈なる逆襲劇!
第59回文藝賞を受賞した、安堂ホセの話題作。
安堂ホセ
『ジャクソンひとり』
ココアを混ぜたような肌、ぱっちりしすぎて悪魔じみた目、黒豹みたいな手足の彼は、ベッドに磔(はりつけ)にされていた。そのビデオを見てすぐに、ジャクソンはそれが自分だと察した。その時のことは覚えていないし、似ている男なんて世界中に何人もいると思う。だけど、ここは日本で、この外見でこんなふうに扱われるのは、ジャクソンひとり。
その朝、気温が急に秋っぽくなって、ジャクソンはロンティーをかぶって出社した。いつも着ているアスレティウス社のジャージとは違って、よく知らないブランドのものだった。会社の服装規定では、競合のスポーツブランド以外なら何でも良いはずだった。
埋立地のだだっ広い敷地にそびえ立つ巨大なオフィスの隣に、その子どもみたいな小さいジムが建っていて、それがジャクソンの勤め先。アスレティウス・ジャパン本社併設の、スタッフ専用の小さなフィットネスセンターで、ジャクソンは一日中スタッフにマッサージをする。
8月末までオフシーズンだった会社のバスケットボールチームが戻ってきて、朝からスケジュールが埋まっていた。ゼンと呼ばれているフォワードの男の筋線維を指で裂く。ゼンの筋肉は驚くべき回復力だった。錆(さ)びたように縮んでいた筋肉は、指を二、三回通しただけでどんどん血を吸収し、心拍のたびに膨らんでいった。
「ジャクソンの十代の頃の夢は?」
「遊んで暮らすこと」
「スポーツ選手になりたいと思ったことは?」
「まったく」
「どうして?」
「遊びを覚えたから」
「もったいない。絶対に向いてたのに」
おまえの方が、ずっと向いてる。指で押しながら、ジャクソンはそう伝えない。ただ黙って筋肉を裂き続ける。
また会話が途切れたとゼンは思った。ジャクソンと喋(しゃべ)ると、いつもジャクソンのターンで終わる。この摑(つか)みどころのない感じ。それはゼンにとって、ジャクソンという人物そのものへの印象でもあった。
ゼンがジャクソンについて知っている情報。アフリカのどこかの国と日本とのハーフらしい。陸上やってたらしい。モデルもやってたらしい。もしかしたらゲイかもしれない。全部ジャクソン本人から聞いたんじゃなくてチームメンバーたちが噂していることだった。
もしかするとスポーツ選手になることも、モデルになることも、あるいはもっとゲイフレンドリーな職場で働くこともできたかもしれないのに、なぜいま彼がここで一日中マッサージをしているのか不思議だった。ジムのスタッフは厳密にはアスレティウス社の所属じゃないし、ゼンたち選手がここを利用するのなんて一年のうちのほんの一時期だけで、ほとんどは一般スタッフが相手。彼らはただの老化と見分けがつかないような不調を訴えて、またオフィスに戻っていく。たぶんその繰り返し。
ゲイだからマッサージの仕事で男に触りたいんじゃないかと噂するやつもいたけど、それは違うとゼンにははっきりとわかる。ジャクソンの手からは抑制を感じる。
ゼンもたまに男と寝ることがあったけど、基本的には女の子と結婚していつかは子どもを育てるつもり。ゼンにとって男相手のセックスは、SMとか3Pとかと同列の、ただのポルノのジャンルに過ぎなかった。相手に困ることはないし、特別な一人を選ぶつもりもない。
お互いに腹を割らなくても、非「純ジャパ」同士というだけで話題はそれなりにあった。60分の施術後に二人はLINEを交換し、午前中の残りの時間ジャクソンはマッサージを、ゼンはチームミーティングをして、12時にフードコートでまた顔を合わせる。
フードコートはほぼ満員で、ジャクソンはタコスとスープを注文して窓際へ急いだ。スタッフは全員アスレティウス社のウェアを着ているから、みんな何かしらの選手に見える。でも本物の選手たちは態度の大きさですぐに見分けがつく。彼らは中央のテーブルに陣取っていて、まるで何時間もそこに居座っているんじゃないかというくらいにあたりを散らかしていた。その中にゼンを見つける。二人の視線はタイミングがずれて、ゼンが見たのはジャクソンがそっぽを向くところだった。やっぱり摑みどころが見えない。ジャクソンへの印象がまた補強された。
いつのまにか晴れて、昨日までの真夏日に戻っていた。ジャクソンはロンティーを脱いでスタッフシャツに戻り、タコスをざくざく嚙(か)んでいく。タンパク質が25g入ったタコスのササミや穀物が口を渇かせた。一口ごとにスープで飲み込んで10分もかけずに完食すると、AirPodsから流れる曲を変える。ふいにゼンの背中の感触を思い出す。数時間を経た後でも、それはリアルに蘇った。
ジャクソンが席を立ったとき、ゼンはチームメンバーとのおしゃべりに気を取られていた。はじめてのデートの夜、一緒に食べた高級リゾットを数時間後のベッドにそっくりそのまま吐き出した女。昔のクラスメイトの母親が、マッチングアプリを通じて送りつけてきたヌード。チーム全員がキモがれる話題を提供しあって楽しんだ。
話はゼンのマッチングアプリの写真に移った。設定されているのは、そんなに絶景でもない山で撮った写真。
「お前、アイコンの意味わかってる?」キャプテンが嬉しそうに顔を近づけて、ゼンのスマホを指で小突いた。
「これってさ、趣味が合いそうか判断するための写真なわけじゃん。こんなとこ、連れて行かれたい女いる?」
みんなが知ってる大前提を、司会ぶった口調で説明してくるこの感じ。それに取り巻きが笑って、周りから見たら超つまんない団体だろうな、とゼンは恥ずかしくなるけど、みんなと同じように笑って応える。
他のメンバーも口々にのってきた。ほんとだ、ダサい。っていうか半目じゃん。なんで親指立ててんの? これちょっと問題だわ。今のうちに撮り直してあげよう。アメリカの大学の研究によると飲み物を持つとマッチ率が上がるらしいよ。友達と写ってると安心を覚える女性が20%増だって。いいよ、一緒に写ってあげる。絶対顔は消してね。キャプテンがカメラを構えた。はい、こっち向かないで。
ピントが合うと、カメラがゼンの背後の何かを捉えた。
〈QRコード 〝blackmixroom.org〟をwebで開く〉
誰も座っていない椅子の背に、ロンティーだけが掛けられていた。白と黒のランダムな模様の中から、ぼんやりと四角形が浮かび上がって見える。まばたきをするとまた模様に溶け込んだ。なにこれ。プリントに反応してる。ストリート系のデザインにしか見えなかった。誰が座ってたっけ? ジャクソン。へえ。なんだろ、お洒落だね。そうかな? 何のリンクかによるんじゃない? まあブランドのインスタとかでしょ。とりあえず飛んでみて。
ゼンはコーヒーを片手にポーズをとったまま、彼らのやりとりが終わるのを待っていた。キャプテンは画面を見つめたまま何も言わない。両脇のチームメイトが頭を寄せた。
ブランドムービー? にしてはちょっと。うん、ちょっとね。ゲイっぽい。彼らは軽く笑い飛ばしながら、次のカットに変わるのを待ったけど、いつまでも男がベッドに磔にされていた。なんか、行き過ぎたゲイブランディングって誰得なんだろう。これで売れるならうちの会社がとっくに手を出してる。自己満足でしかないんだよな。っていうかこの男ってさ、ジャクソン?
ゼンは反射的に腰を浮かせ、あくまでも平静な感じで言ってみた。
「ここに入る前、モデルだったらしいから、そのとき仕事したブランドとかじゃない?」
メンバーたちは未知の生物でもそこにいるみたいに、ゼンを凝視(ぎょうし)した。
「これが?」
キャプテンがスマホをテーブルの真ん中に置き、メンバーは会議をはじめる。
え、モデルってそういうモデル? モデルっていうかそれ、別の職種だから。っていうか趣味かも。趣味っていうか癖(へき)。会社に着てくるってなんの冗談? そこまで込みのプレイ? 報告したらセクハラ事案になるかな。総務の人、こんなの見たら気絶しちゃうでしょ。電流が走るようにメンバーの気持ちが一致していく。
周りのスタッフたちはみんな彼らのうるささに麻痺していた。一人ぼっちの派遣スタッフは、選手たちのシューズ特有のキキッという摩擦音に鳥肌を立てながらも食事に集中する。二人組の店舗スタッフは、ネットサーフィンを続ける。部下を連れた営業部のチーフは、自分の話がかき消されないように声を張る。大丈夫です、ちゃんと聞いてます、とアピールするように部下たちが大袈裟に頷(うなず)く。そしてその全員が、聞こえてくる言葉の断片に思った。やっぱりこいつらうざすぎる。けど今回は、ちょっと面白そう。
周囲の注意を惹きはじめた気配にメンバーもさらにヒートアップした。このイモータン・ジョーみたいなマスクは何だろう? ほんとだ、チューブ伸びてる。しかも肛門に繫(つな)がってる。これ知ってる、マンハウリングっていうプレイだよ。これはチューブじゃなくてコード。口に入ってるのがマイクで、ケツに刺さってるのがスピーカー。声を出したら体内で再生されて、体全体がスピーカーみたいになって、その苦痛でまた声が出る。その繰り返しでハードコアな轟音(ごうおん)になってく超危険なプレイ。なにそれ。最近流行ってるらしいよ。どこで? 海外。危険そう。危険だろうね。だってかなりしんどそうだもん。腹筋の歪(ゆが)み、やば。エイリアン飼ってるみたい。だめだ、傑作すぎる。どっかの誰かが大真面目にこういうこと考えてるんだと思うと、面白すぎる。俺はもはや尊敬する。自分では絶対に思いつかないし、実際にやってみるのだって、頭がおかしいか、体がバケモノなのかどっちかだよ。俺はむかつくんだけど。だってもし、これが好きでやってることだとしたら、こいつはこんな本性を隠して、毎日俺たちの体に触りまくってるんだよ。あのすかした顔で。普通のホモにはもういい加減耐性ができたけど、これは異常者の域だって。
ゼンは入口に目を泳がせる。もしジャクソンが戻ってきたとしても、態度を変えないという意志が形成されはじめていた。そしてゼン自身もあることを確信していく。自分がジャクソンに対して抱いていたのは、ある種の警戒心だったのかもしれない。
AirDropしてくんない? 自分でスキャンして。嫌だね! ハッキングされそう。はい、これとこれとこれね、間違えた、違う人に送っちゃった。まあいっか、危険周知ってことで。
いくつかのスマホが震えて、やがてフードコートのほぼ全員がビデオを見た。なにこれ、リベンジポルノ? いや、趣味らしいよ。昔の仕事らしいよ。この動き、尋常じゃない。死ぬんじゃない? やばくないの? やばくはないんじゃない、だって無事だからこうして……
他のスタッフたちよりも大きな歩幅で、ジャクソンは扉の向こうから現れ、現れたと思ったときにはもうフードコートの真ん中まで来ていた。ちょうどビデオを見ていたスタッフは、みんなすばやくミュートしていったけど、消えていくその音をジャクソンの耳はキャッチした。砂嵐の奥で男が叫んでるような、というか砂嵐そのものが男の叫びでできているような音だった。音が止むと、フードコートはさっきより静かで、ジャクソンは眉を持ちあげる。あっというまに窓際のテーブルまで到着し、トレーと包装紙、そしてロンティーを拾う。
いつもどうも。悪意たっぷりにそう投げかけてきたのは、ゼンたちのチームのキャプテンだった。いつもマッサージが丁寧で、チーム全員が感謝してる。施術が本当に丁寧で、むしろ丁寧すぎるってみんなが言っているぐらい、本当に好きで好きでやってるのが伝わってくる。
ジャクソンは口角だけで返事をして、出口へ向かう。引きとめるようにキャプテンが言った。そのお礼と言ってはなんだけど、ひとつ教えてあげると、それ、着ないほうがいいよ。
アパレルには必ず、スタッフの服をパトロールしたがる人間がいる。それで目をつけられたのかと最初は思った。
それ。キャプテンはもう一度言ってから指で何かをたぐり寄せるようなハンドサインをした。ジャクソンはふてぶてしくロンティーを放り投げてパスする。空中で、右胸に差したネームタグが太陽を反射した。
キャプテンがキャッチする。ロンティーを広げ、裏返し、背面のプリントにスマホをかざした。手品みたいにもったいぶって、心配そうに近づいてくるジャクソンをなんども盗み見た。仮面が外れる瞬間をはやく見たかった。
そしてジャクソン本人がビデオを目にする。過去のジャクソンの肉体、今朝のジャクソンの選択、キャプテンの悪意、そして自分を陥れようとする誰かの企(たくら)み。それらが狂いなく嚙み合っていくみたいで恐ろしかった。
5秒間くらいのことだった。
「悪いけどこれ、俺じゃないですよ」
あまりにも堂々と噓(うそ)をつくジャクソンに、キャプテンはむきになる。あくまで親切を装う、というプランを守ったまま、
「それはないでしょ。だってきみの服でしょ?」と返した。
「俺が買ったんじゃなくて、もらった服なんで」
「誰から?」
「さあ。モデルやってたから服なんていっぱい届くし……っていうか、答えなきゃだめなの?」
「まあ、だってある意味、公然(こうぜん)猥褻(わいせつ)じゃん? こっちからしたら」
「リベンジポルノの部類だと思うけど」
「にしてはなんか冷静だね」
「わかるように動揺しなきゃだめ?」
「はいはい、ごめんね。こっちはきみのお楽しみを見せつけられたせいで安心して過ごすこともできないけど、きみは自分が被害者だって言っててしかもそれを証明する気は全然ないから、僕たちは黙って我慢するしかないね?」
「ほぼその通りだけど、これは俺じゃなくて他人。さっきと同じこと言ってますけど」とジャクソンは鼻先で笑いを漏らした。
スタッフたちは、遠巻きに彼らの応酬を眺めながら考える。ある人はジャクソン本人説を信じた。だからジャクソンの股間にはこれと同じモノがぶら下がっているのかも? と想像して思わずジャクソンを見た。またある人は他人説を信じた。いまの返答のスピードからして、多分本当のことを言ってるはず。っていうことはジャクソンの股間にもこれとよく似たようなモノがぶら下がってるのかも? と想像して同じようにジャクソンを見てしまう。
見られると反射的に見返してしまうもので、そこにジャクソンの感情は特になかったが、眼光がぎらぎらしているから、みんな目を逸らした。まるでライトに照らされた魚みたいに、ばらばらと散っていく瞳たち。
まともに衝突してくれるだけ、むしろこいつが頼りかも。ジャクソンはキャプテンに向き直った。
「ていうかさ、どうしてこれが俺だと思うの?」
「いや、似てるからでしょ」その言葉に笑いが起こる。
「どこが?」
「見た目が」
「見た目が、って具体的にどの部分がどう似てるの?」
黒い、肌、顔が、髪、お前しか、人種、こんな人間、こういうタイプ……どの言い方も状況的にアウトだ、と喉の奥で言葉を転がしながら、キャプテンはジャクソンの頰(ほお)がだんだんと引きあがり、そして笑顔になっていくのに気がついた。
「もう一回聞くけど、どこで、俺だと、判断したの?」
「あー、はいはい。そういう感じね。ごめんごめん。俺の勘違い。もういいよ」
「なにそれ。あんたが審判だったのかよ」
ベルがランチタイム終了を知らせる。13時から予約が入っていて、ジャクソンはジムに戻ったが誰もいなかった。パソコンでスケジュールを確認すると、予約はキャンセルされていた。なんとなく予想はしていたとはいえ、ぐっと胃が重くなる。モニターを眺めていると、連続して5件のキャンセルが入って、その日の予約が全てなくなった。さらに表示を1週間単位に切り替えてみると、次々予約が消えていった、と思ったらすぐに別のオファーで埋まっていき、30分もせずに7割くらい回復した。はじめて見る名前ばかり。思わぬ支持者たちにジャクソンは感心した。客がゼロになるよりマシだけど、何かの役に立つわけじゃない。
ぶあつい唇を二本指で叩き、まぼろしの煙を吐いた。誰もいないのに、誰に向かって余裕ぶっているのかジャクソン自身も分からない。どうせしばらく誰もこないし、太腿のあいだに丸く固めていたロンティーを広げた。
モデルをやってたから服がいっぱい届く、というのは本当で、マネキン・マネージメントとの契約を解消してアスレティウス社に外部スタッフとして雇われた数ヶ月後に、その包みは自宅のメールボックスから飛び出していた。爪で包みを破り裂くと、綿100%のざらつきに触れた。白と黒のチェス盤にバグが現れたようなデザインにジャクソンはときめき、ラックに並べた。真夏日が続いて、その日まで一度も着ることはなかった。
それまで何も気づかなかったはずなのに、仕掛けを知った後だとそうとしか見えないから不思議だった。スキャンすれば反応して、確かにQRコードだった。
画面いっぱいに広がるジャクソンの肌が、ジャクソンの瞳を照らす。一瞬目をすぼめたけど、思ったより平常心で観ることができた。ジャクソンにはこの時の記憶がさっぱりない。だから不思議なことに、他人の目を借りているように無責任で、テーブルの下ではペニスに血がのぼりはじめた。集団としてのあるべき反応と、個人の本心は全く違うものだから、この興奮をマイナスしたぐらいが、標準的な他人の感想だろうとジャクソンは見当をつける。
この男、べつに何も悪くない。恥ずかしいことでもないし。まあ、人間だしね。でもかわいそう。まあでもある意味、いいキャラじゃん……ジャクソンは浮かんできたそれらの感想をお守りがわりに覚えておこうと思う。
ビデオを後半まで進めていくと、終盤に画面の外から腕が伸びてきた。日本のどこにでもいるような男の腕だった。ペニスをしごくというより、拳を腹に打ち付けるような手つきで彼は射精させられ、ビデオは終わった。
もう一度再生するまでもなく、あのホテルだ、とジャクソンはぴんとくる。何度も使ったことのあるホテルで、ベッドの下、世界地図が描かれたカーペットに見覚えがあった。埋立地にあるアスレティウス社と、ジャクソンの家のちょうど中間ぐらい、ビルに囲まれた自然公園のそばにホテル・サジタリはあった。
夕方、最後の客が帰るとマッサージ室にロックをかけ、自転車を漕ぎ、そのホテルに到着するまでに一度職質を受けた。青みがかった夕暮れのなかで、警官はライトをつけるよう促し、防犯登録を確認した。数分足止めを食らっている間に汗をかいて、アスレティウス社のシャツが体にべったりと張りついた。周囲に誰もいないことを確認してから、リュックの中に隠していたロンティーに着替えた。リュックを背負えば、後ろは隠れた。
「防犯カメラの映像は保管されていますか?」
そう聞くと、フロントの男は答えを言い淀んだ。開示を断られることは予測していたから、ジャクソンはカウンターに体重をかけて、小声でさっさと説明した。
「以前利用したものなんですが、実は、ちょっとトラブルがあって、今度警察に届けを出そうと思ってて……で、証拠が残っているか気になって」
架空の被害者を演じていたつもりなのに、それは今のジャクソンにとって事実でしかなく、そうやって自分に意識が向いた瞬間、皮膚のすぐ裏でさっと血が走る。午後から何度も起きている現象だった。
「こちらをご利用いただいたのは、いつ頃でございますか」男は不審そうに尋ね、
「1年前くらいです」と答えると、
「1年ですか」男はモニターに目を伏せて言葉を淀ませてから、「1年ですね」と言い直して、履歴を検索するためにジャクソンの名前をたずねた。映像は残されていないか、開示されるまでにかなりの交渉を必要とするだろうとジャクソンは察して、笑顔でお礼を言うと名前を告げずにホテルを出た。公園に戻って、池のほとりの公衆トイレでロンティーを脱ぎ、元のシャツに着替えた。
翌日からもジャクソンのシフトは入っていた。11時からの客は背中が痛いらしい。筋肉の硬直度をはかるために腰を刺激していくと、客は喉を鳴らした。
「これ、みんな痛がらないの?」
「めっちゃ痛がるよ」
「だよね。くそほど痛い」
「俺がやられてたら飛び上がるレベル」
「自分でやってるのに?」
「刺激に対して過剰反応するタイプの人体って、あるじゃん?」
「あー、あるかもね、そういう人体」人体、という言い回しを強調しながら客が笑う。
「そうそう。俺、結構そのタイプの人体なんだよね」
客の瞳がびっと目尻にせりあがった。しかたないよ、ジャクソンは誰かに犯されたんだから、と瞳が言っている気がした。そっか。こいつのなかでは、俺は誰かに犯されたんだ。また体が急速に熱され、冷えた。ジャクソンの奥にありもしない傷が出現したみたいだった。銀色のスピーカーを入れられたことによる炎症。金属のアミアミがそこを荒らしていった過程を、ジャクソンの体はあざやかに思い起こすことができた。覚えているのかもしれなかった。二人ともしばらく黙っていた。マッサージ室は湿っぽいムードに包まれ、残りの46分間を「しかたないジャクソン」として過ごす。
13時からは一転して「けしからんジャクソン」にさせられる。客はあのときフードコートにいた顔で、テレビのリモコンを与えると、配信サービスも繫がることに感心し、「噓とパイ投げ」というリアリティショーを選択した。
「賞金を狙う参加者たちは、お互いがインタビュアーとなって弱点を暴きあう。一般人による本気のトーク番組ごっこ」という見出しがあった。
番組のサムネイルは、いかにもアメリカのトークショー風のセットの中で、黒人男性と白人女性が向かい合っている写真だった。けれど二人はどう見てもプロの司会者やタレントではなく、女性はヨレて生地が透けかけている白いティーシャツで、男性はやけにぴっちりした花柄のワイシャツを着ていた。
ジャクソンの知らないリアリティショーだった。大勢の観客の前で片方がもう片方にインタビューし、最後にどちらに番組に残ってほしいかを投票で決めるらしい。勝てば次のバトルに進んで、負ければパイ投げ。質問には原則として答えなければならず、それは嘘でもいいけど嘘をつき続けて票数を減らす可能性も考慮する必要があり、ノーコメントの場合はショットを一杯飲む、というルールらしい。
客は途中で飽きたのかYouTubeに切り替え、飽きたはずなのにまた「噓とパイ投げ」に関するゴシップ動画を再生した。決勝まで勝ち進んだ男が、薬物パーティの常連だったという内容に、二人して意識を持っていかれる。
「けしからんことなんて、誰でもやってるじゃんね」
客はそう言ってジャクソンに目くばせをした。嫌味じゃなくて、本当にジャクソンのことを応援したいみたいだった。まあ確かに俺がこいつで、こいつが俺だったら、同じスタンスだったかも。ここまで無神経ではないけど。ジャクソンは「けしからんジャクソン」らしく、太い鼻筋に皺(しわ)を刻んで笑ってみた。客はさっと目を逸らした。また体が急速に熱され、冷えた。
マッサージにはいろんなスタッフが来たけど、どの瞳もそうやって逃げた。いくつも逃すうちに、ジャクソンはなぜか、それを指で押さえてみたくてしょうがなくなった。指圧のときの、筋肉の凝りを追いかけていくような要領で白目を指で捉えて、鍼(はり)ですっと瞳を刺してみる場面をジャクソンは想像して、血がのぼるような発作を鎮めた。
今日こそ警察に行こうと思いながら、吸い寄せられるようにあの公園に入っていた。ホテル・サジタリが木の隙間から光っているけど、素通りして公園を進む。いちばん真っ暗な生垣の近くに、不自然なほど人影が密集していた。それが全て男であることをジャクソンは知っていた。木の陰に潜み、ベンチにまたがり、植え込みの中で円陣を組んで、いたるところで男たちが触れ合っていた。自転車のライトが射し込むと、危険を察知した男たちは分散した。それが自分たちを取り締まる存在ではないと理解すると、警戒を緩めてふたたび寄り集まってくる。ジャクソンの前から次々と男たちが逃げていき、背後の闇に流れこんだ。まるでライトに照らされた魚みたいに、ばらばらと散っていく。あいつらみたいだなとフードコートのことを思い出す。ぼーっとただ自転車を操縦しているだけで、彼らは面白いように反応した。
ナイトサファリごっこが癖になって、ジャクソンは帰宅ルートに公園を選ぶようになる。あるときは一回の帰宅で何周もした。そうして彼らの反応を味わい尽くして、ある夜べつの方法を試した。あらかじめ自転車のライトを消して、チェーンが空回りする音を立てないようにゆっくりとペダルを踏み続け、植え込みのぎりぎりまで近づいてから急にスイッチをオンにすると、絶妙なポージングで絡まりあう男たちが照らされ、いっせいに弾けた。めくられたシャツの皺や絶望した表情が瞼(まぶた)に焼きつき、草を踏んで遠ざかっていく音が響いた。
翌日、ジャクソンはやっと警察署で被害届に記入を終えた。
事前に〈リベンジポルノ〉〈被害〉で検索していた。頭を抱える金髪美女のイメージ画像や、女性が被害者である前提の文章、その合間に挿入される「エッチな画像をばらまいちゃうぞ!」というセリフの描かれた昭和テイストの絵を目にするたび、あの血がのぼる感じを味わいながらも、警察での流れはなんとなく把握したので、これが何の解決にもならないだろうこともわかっていた。
被害届を受け取った職員は笑みひとつ浮かべずにジャクソンを見つめた。ジャクソンは唾を飲む。男は右手を平たくして頭にのせると、まっすぐ水平にジャクソンの方へ伸ばした。
「何センチくらい?」小さな声で男が聞く。
「はい?」
「身長」
「189とか」
男はクココ、というような音を発しながら笑うと、大げさにのけぞってみせた。
「ごめんね、あまりに大きいから、びっくりしちゃった」
「そうなんですか? 僕、30分前からあなたの前に立ってますけど」
また公園を走る。ライトを消したまま漕ぐ。肉にめり込む感覚がした瞬間にブレーキをかけると自転車は綺麗に止まり、男だけが吹き飛ぶ。公園で轢(ひ)いた三人目の男だった。男たちはいっせいに凍りついて目を凝らしたけど、ストロボモードで点灯した自転車のライトに目眩(めくらま)しされて、ジャクソンの顔は誰にも見えなかった。
ジャクソンの自転車が去っても、轢かれた男はうずくまっていた。誰かが駆け寄ると、轢かれた男は控えめに笑ってその場から走り去った。息が上がっていた。手のひらには小石のかたちの凹(へこ)みや血の滲みがあるけど、たいして痛くもない。すぐ治りそうだった。ポロシャツの裾にタイヤ痕が走っていた。手で払っても消えなかったが、洗濯すればきっと落ちるだろうと気を持ち直す。「トシさんこういうの好きそうだなと思って」という半笑いの声が蘇った。ずっと昔に大学の事務職を辞めるとき、部署を代表してそのプレゼントを選んでくれたのは、ほとんど面識のない派遣の子だった。カミングアウトしたわけでもなかったのに、いかにもゲイ受けする感じのシャツが選ばれた真意を想像すると、トシは今でも顔が熱くなる。
ゲートをくぐって、車や人々の行き交いに還っていく。自分や暗闇にいた男たちのような徘徊の気配ではなく、正しい移動の気配がした。遠くに見える歩道橋の上を若い人たちがスケボーで往復していて、それすら正しく見えた。すぐそばのガードレールの脇を通り過ぎる自転車とすれ違い、その顔がオレンジ色の街灯の下で浮かび上がる。トシは動悸がする。
男が遠ざかっていくのを黙って目で追いながら、強烈な既視感に襲われていた。黒人みたいな肌、人形みたいな目、モデルみたいな手足の彼は、トシがよく知っているジェリンという男にそっくりだった。
【続きは本書でお楽しみください!】