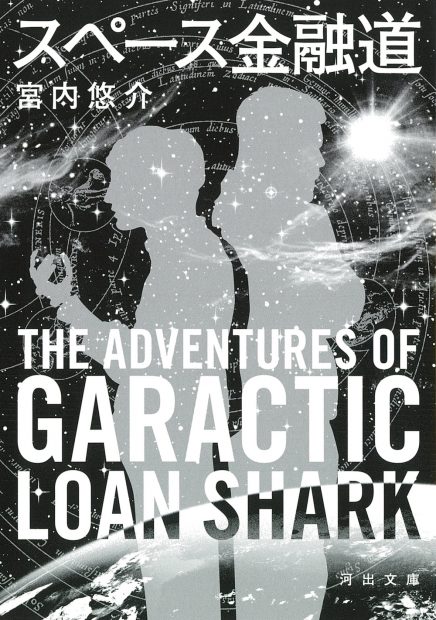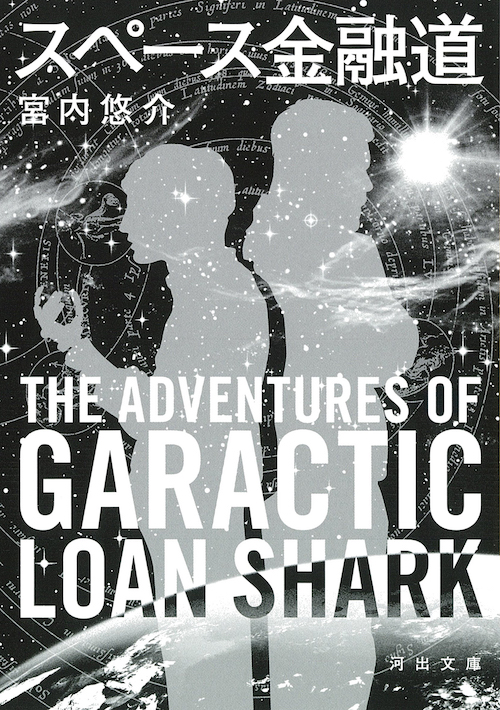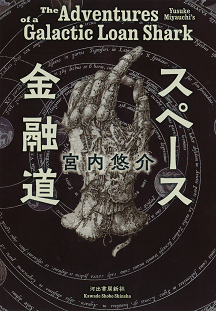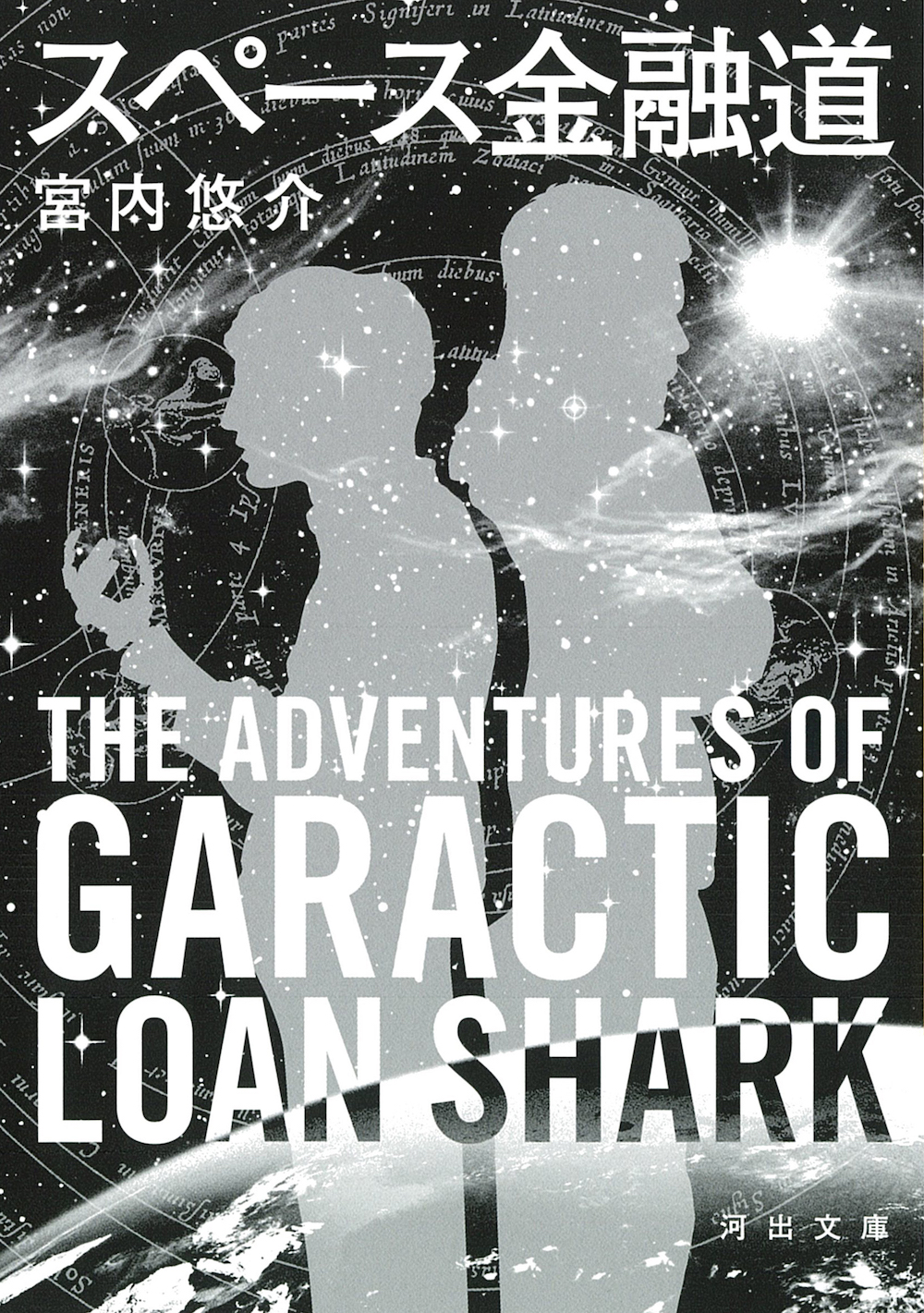
ためし読み - 文庫
宮内悠介の「影の代表作」河出文庫化記念、 『スペース金融道』第1話全文無料公開!
宮内悠介
2024.03.08
ミステリ、SFから純文学まで多才な活躍を続ける作家・宮内悠介さんが、自ら「私の影の代表作」と呼ぶ作品、それが『スペース金融道』。
全5話からなるこの連作集の第1話が発表されたのは、SF翻訳家・大森望さんが責任編集を務める書き下ろしSFアンソロジー《NOVA》シリーズで、宮内さんデビューの翌年、2011年のことでした。
当時、《NOVA》の編集担当は責任編集・大森さん経由で届いた新作のタイトル「スペース金融道」を目にした瞬間、「なにこれ?」と脱力し、気乗りしないままに読みはじめたところ、たちまち引き込まれて一気読み、読後にあわてて、「こんなすごい作品を書いたのは誰なんだ!?」と著者名を確認したとか。
このたびの初文庫化を記念して、その衝撃の第1話全文を、特別に無料公開いたします。
存分にお楽しみください。
===ためし読みはこちら===
「スペース金融道」
宮内悠介
ユーセフの背を追って、雪山のような白い金属の尾根沿いを進んだ。ぼくは摑む場所を求めながら、這うように棟から棟へ移動する。風も重力もないのだから、山上よりはよほど安全だ。宇宙に放り出されることはない。わかってはいるが、どうしても窓のある壁際に寄り添ってしまう。光のある場所から、離れたくないのだ。それに、相手はユーセフのこと。考えうる最悪のザイルパートナーではないか。
いくつもの窓が暖かく輝いていた。
覗きこむだけで、音楽が聞こえてきそうだった。窓の向こうでは、バカンスに訪れた客たちが、いっときのパーティを楽しんでいる。彼らは知らないのだ。いましがたデブリが衝突し、作業員が修復にあたっていることを。通りざまに思った。彼らもぼくと同じだ。消えることのない灯火を、求めている。
(おい!)
無線越しに、ユーセフの叱責が飛んできた。急かされるのはこれで三度目だ。声は信号の上限にぶつかり、かすれ、ザザ、と耳障りな低いノイズを奏でた。そんなに怒鳴らなくたっていいじゃないか。
(わかっています、でも……)
(いいか。次に〝でも〟と言ったら放り出す)
ユーセフならやりかねない。
コンビを組むようになってまだ一年足らずだが、この点は確信を持って言える。この男は、人を人とも思っていない。観念し、ぼくは棟の外壁を強く蹴った。
暗い一角に入った。
ぼくはヘルメットのシェードを外す。ここは宇宙エレベーターの宇宙港。巨大な金雀児のような衛星が居住区の壁を裂き、分け入り、なかば貫通したところで止まっていた。パトリック・グランはそのすぐ脇に取りつき、損傷箇所に合成樹脂を吹きつけている。動脈近くで止まった銃弾のようなものだ。下手に取り除くより、ときには、そのまま固めてしまうほうがいい。
応援でも来たと思ったのか。パトリックは何気なく振り向いたが、ユーセフを見るとたちまち表情を強張らせ、やがて泣いているような笑っているような顔になった。
(パトリック・グランに通話発信。会議ルーム一番を使用)
ユーセフの音声認識コマンドが聞こえてきた。それを受け、パトリックも何かしら口元を動かした。すぐに、三者の通話がつながった。
(何もこんなところまで! この状況を見てくれよ!)
(だから、こちらから来てやったんじゃないか。おい)
突然名前を呼ばれ、はい、とぼくは上擦った声を上げる。
(企業理念)
(はい。わたしたち新星金融は、多様なサービスを通じて人と経済をつなぎ、豊かな明るい未来の実現を目指します。期日を守ってニコニコ返済──)
言い終えるより先に、パトリックが、待て! 待てって! と叫んだ。
(休憩申請。センターとの通話を一時切断)
弱々しく、音認コマンドが発話される。
(せめて終わるまで待ってくれないか。急ぎの作業なんだよ)
(そんな大事な立場にいながら、先物に嵌ったのはどこの誰だい)
ユーセフは高周波ナイフを取り出すと、そのまま流れるように、躊躇なくパトリックの宇宙服の腕のあたりを切り裂いた。勢いよく空気が漏れ、パトリックは斥力で跳ね飛ばされそうになる。その足をユーセフが押さえた。
(──な)
パトリックはすっかり動顚し、真っ青な顔で切れ目を押さえている。
(や。やめろ、離してくれ!)
(いいか。おれたちはヒマじゃないんだ)
(死ぬ! 死んじまう!)
(大袈裟だな。ちょっと真空状態になったくらいじゃ、人間は死なないんだよ。まあ、すぐにステーションに戻ればだがな)
(払う。いますぐ払う! 頼む! 離してくれ!)
(わかればいいんだ)
ユーセフはそれだけ言うと、機材を奪い取り、パトリックの腕に合成樹脂を吹きつけた。応急処置だが、これでひとまず死ぬことはない。あとは、生命維持装置が適度に加圧してくれるだろう。
(これは事故だ。わかってるな?)
念を押すユーセフに、パトリックはただ頷くばかりだった。震える声で音認コマンドを打ち、ユーセフに利息分を送金する。泣いていた。毎度、とユーセフはつぶやくと、元来た道へ、壁を蹴った。また怒鳴られるのも嫌なので、慌ててその背を追う。
靴の裏を見ながら、ぼくは通話発信した。
(もう、こんな取り立ては勘弁してください)
(馬鹿言え。宇宙だろうと深海だろうと、核融合炉内だろうと零下一九〇度の惑星だろうと取り立てる。それがうちのモットーだ)
(……核融合炉には一人で入ってくださいね)
ユーセフを追いながら、ぼくは幾度か後ろを振り向いた。パトリックは作業を止めたまま、呆然と中空に浮かんでいた。気にならないと言えば噓になる。でも、かかずらっても身が持たない。今回はまだいいほうだ。みんな、何かしら事情がある。死んだ人間だっている。きれいさっぱり忘れること。それが、この仕事をつづけるコツだ。
同じだ、と思った。ぼくも、パトリックも、たぶんユーセフも。最初は明るい場所にいたかった。だけどいつの間にか、一番遠い場所にまで来てしまった。エレベーターの赤いライトが宇宙港に向けて登っていた。正面に惑星が見えた。人類が最初に移住に成功した太陽系外の星──通称、二番街が。
狭い三段のベッドが船室のように並んでいる。
シーツは清潔に保たれていたが、空調が悪いのか、あるいは部屋そのものに染みついているのか、饐えた匂いが空気中を漂っていた。客たちの鼾は潮のように上下し、折り重なっては引き、止んだと思ったら、またどこからか鳴りはじめる。
宇宙港のなかでも、一番安いドミトリーだった。
それこそ、パトリックのような男の仮宿だ。荷物を入れるロッカーには、鍵さえない。二番街の首相、ハシム・ゲベイェフのポスターが壁に貼られている。上院のただ一人のアンドロイド議員でありながら、豊富な資金を武器に、与党のトップにまで登りつめてしまった人物だ。保守派からの批判も多いが、ぼくはほんの少しだけ期待している。
「まずは一休みだ。報告書はいつも通り、手分けしてダブルチェックな」
「はい」
結局、その日は七件を取り立てた。
くたくたになった身体を沈め、ベルトで固定してみたが、とても疲れが取れる気がしない。狭く、身体を起こせる空間もない。夜はせめて疑似重力つきの部屋でシャワーを浴びたいと言ったのだが、「駄目だ」の一言だった。
赤字なのである。
地上での移動とエレベーターの運賃、それから宿泊費用。人件費。とてもじゃないが、割にあわない。でも、舐められたら終わりの商売。だから客の追跡には力を入れる。宇宙だろうと深海だろうと、核融合炉内だろうと零下一九〇度の惑星だろうと──これは、あながち噓じゃない。
一度、海底に棲む知性体から取り立てをしたことがある。なぜ彼ないし彼女が金を必要としていたのかは知らない。みんな、何かしら事情がある。帰り道、ぼくは巨大魚に襲われて命からがら逃げおおせたのだが、ユーセフはその間ずっと高みの見物を決めこんでいて、ぼくは食われた左腕を機械に置き換えるはめになった。長く休職してもいられないので、時間のかかる再生医療には頼れなかったのだ。労災が振りこまれるのが遅く、ぼくはユーセフから治療費を借りることとなり、当然のことながら利子も取られた。腹が立つので、いつかヒマができたら、あの魚を釣って食ってやろうと決めている。
ベッドの上段から、ユーセフが報告書を打つ音が聞こえてきた。
雑用を人に押しつけず、仕事は必ず手分けする。これはユーセフのいい面だ。たった一つのミスで信用を失うやつもいれば、普段はいい加減で最悪なのに、たまにいいことをして挽回するやつもいる。ユーセフは確実に後者だ。
「──今日の三人目、あのアンドロイド、なんていった」
「マリー・リップマンですか」
「それ。結局どうなったんだっけ?」
「金がないということだったので、利子分を新たに貸しつけようかと提案しました。それは嫌だと相手が言ったところ、ユーセフさんが間髪入れずにお客さんの右腕を切り落として、それを売って利子分にあてることとなりました」
ひときわ高く、どこからか鼾が聞こえてきた。ぼくは小声になって、
「実際は利子分に届かないことがわかったので、おのずと、もう片方の腕に目が行ったのですが、それをやると今後の返済もままならなくなるとお客さんが訴え、それもそうだという話になり、今回はこれで納得することとしました」
「一行にまとめろ」
「すみません。ええと、〝物品による代替回収、満額には至らず〟です」
「わかった」
ぼくは懇願するようなマリー・リップマンの目を思い出した。うちの客にはアンドロイドが多い。バクテリアだろうとエイリアンだろうと、返済さえしてくれるなら融資をする。そのかわり高い利子をいただきますというのが、うちの方針らしい。
大手はなかなかアンドロイドに貸しつけをしない。危険度の高い職につくことが多く、個籍さえないこともあるからだというが、それは建前で、おそらくは差別があるのだろう。でもそのおかげで、ぼくもメシが食えている。立派なことは言えない。
ぼくはノートパッドに報告書を書こうとしたが、疲れのせいで文章が書けない。
ひとまず、社内報を確認してみることにした。
多様なサービスを通じて人と経済をつなぎ、豊かな明るい未来の実現を目指します──一面にはいつもの企業理念の下に、今週の社長の一言、各支社の決算報告、それから社員の表彰が並んでいる。言語は、機械翻訳のために最適化されたクレオール英語。汎語、マシナリー・クレオールとも呼ばれている。言語処理が、未熟だった時代の名残りだ。
社長は十七光年先の地球本社にいるはずだ。だからこれは、本当は十七年前のコメントということになる。いまごろは、もう代替わりしているかもしれない。ぼくが所属しているのは、二番街支社。五百光年先にも支社はある。そうした支社から集められたバラバラの情報をつなぎあわせ、自動的にマージしたものが、この新星金融の社内報だ。
これだけ距離があるのだから、当然、それぞれの支社は独自に動く。そのかわり、特殊なカスタムをされたアンドロイドが、ブランドマネージャーの権限を持っている。
ぼくが楽しみにしているのは、「ノヴァちゃん」という猫が登場する一ページ漫画だ。あるとき、どこかの恒星系で金に困った漫画家が、現品で払うものさえなく、取り立ての担当がなかばヤケ気味で漫画を描かせた。それが評判を呼び、いつの間にか社内報に載るようになり、完済後も連載がつづいている。
ノヴァちゃんは新星金融の取り立てスタッフだ。何かとタチの悪い客に苦しめられ、あの手この手を考えるがうまくいかない。最後には諦めて腹這いになったり、ごろごろと喉を鳴らしたりし、その可愛さに負けて客は支払いをしてしまう。だいたいこのパターンだ。
もちろん猫は取り立てをやらない。あるいは、そういう惑星もあるのかもしれないけど、客はいつだって往生際が悪い。この点は、どこもそうは変わらないはずだ。現実に、こんなことはありえない。でも、そこがいいのだ。
ぼくは情報共有のページを開いた。
取り立てのノウハウや危険情報、ブラックリストなどを社員同士で共有する掲示板だ。一つ、気になるニュースがあった。遠く離れた惑星で、アンドロイドの死亡事故が起きていた。借金から逃れようとしたアンドロイドが、別のアンドロイドの身体を乗っ取り、元の身体を破壊して死んだことにした。そこの支社のスタッフは二年をかけて追跡し、取り立てに成功したようだが、これを繰り返されると、うちとしては商売あがったりになる。今後、流行るかもしれないから注意のこと、と書かれていた。
「報告書、できたか」
上段から声がした。一休みするのではなかったのか。「ごろごろ」とぼくはノヴァちゃんを真似て言ってみた。頭上からユーセフの拳骨が飛んできた。ぼくは黙ってワードパッドを開き、報告を書きはじめた。
ぼくらは死者と競争している。
恒星系をまたいだグループ企業では、便宜上、よその星の数百年前の出来事を現在形で語ることが多い。いわく──L8系支社の新人はもう回収率八割を達成している。おまえも頑張れ。ところで、その新人はいまどこで何をしているのか。とうの昔に死んでいるのだ。ぼくが生まれるよりも前から。
作業を終えてからぼくはユーセフとシャワーを浴び、バーに入った。自腹でもいいから身体を洗いたいと言ったところ、おごってやるよ、という話になった。公共のシャワー室やバーには、地上の半分程度の重力が設定されている。無重力は嫌だが、重力に逆らって立つのも疲れる。わがままな話だ。
ユーセフは柑橘系のジュースを頼み、ぼくはスペースカクテルという垢抜けない名前の観光客向けのオリジナルメニューを頼んだ。青色をしたその液体は、エンジンオイルでも入れたのではないかという味だった。
顔に出ていたのだろう。ユーセフは呆れた口調で、
「おまえはいつもそうだ。余計な冒険をして転ぶ」
ぼくは負け惜しみを言った。「そのかわり、豊かな世界を生きてるんです」
バーテンダーは黙ってグラスを拭いている。目を見た感じでは、おそらくアンドロイドだろう。この直感は、けっこうあたる。店のスタッフは、人間とアンドロイドが半々といったところ。だいたい、どこもそうだ。
アンドロイドは人間そっくりだが、どこか違う部分もある。たとえば、よく旅をしたり、職を転々とすることが多い。
このごろは、精神疾患にかかるアンドロイドが増えたと聞く。それは差別によるものではないかとぼくは思う。人間と同等かそれ以上の権利が保障されている文明圏もあるが、依然として、そうでない場所のほうが多い。そうすると金を借りるにも、うちのような会社を選ぶしかない。法整備も曖昧だ。だから、人格を転写しようが追跡をして取り立てるし、身体の一部を切り離し、回収することもある。
「……祈りの時間だ」
ユーセフがつぶやくと携帯用のカーペットを床に広げた。位置認識機能がついていて、宇宙のどこにいてもメッカの方角を向けるという優れものだ。地球で生まれた原始宗教はいまも姿を変え、宇宙各地に点在している。
「ムスリムなのに、金貸しをやるなんて」
この指摘も、何度目のことかわからない。太古の地球で生まれた本来のイスラム教を、ぼくは知らない。でもそれが、金利を禁じていたというのは有名な話だ。
「いいか、こんな話がある。パキスタンのムスリムは敬虔だが酒を飲む。バングラデシュのムスリムは、敬虔だが酒を飲まない」──どちらも、昔、地球にあったという国の名前だ。「だから、二番街のムスリムは、信心深いが金を貸すんだ」
「何度も聞きましたよ。何が、だから、なのかわからない」
ユーセフはそれ以上は喋らず、口元で何事か祈りの文句をつぶやいていた。アラビア語という言語らしい。本人も、意味はよくわかっていないようだ。ユーセフというのはムスリムネームで、本名は別にある。なぜ、彼が太古の宗教に惹かれたのかはわからない。ぼくも訊かないし、ユーセフも語らない。信心深いこと。これもユーセフの特徴だ。いいことなのか、悪いことなのか。それはわからない。
ユーセフは過去を語らない。
でも一度だけ、ぼくの入院中、左腕のリハビリをしていたころ見舞いに訪れ、漏らしたことがある。ユーセフは、かつて国の機関に勤めていたそうだ。任務は金融工学の研究。噓つきばかりの職場だが、これは噓ではないと思う。ユーセフは、口は悪いが噓は言わない。
ユーセフは物理と経済の学位を持ち、量子金融工学なる分野のエキスパートだったらしい。専門は、多宇宙ポートフォリオを中心とする量子デリバティブ。何がなんだかわからないと思うが、ぼくもわからない。
「もともと、金融工学と量子力学は確率微分方程式でつながっているんだ。離散的であるという点では、量子も金融商品も変わらない。だから、宇宙をまたいだオプション取引やデリバティブが発生するのは歴史的必然だったのさ」
「すみません」
ぼくは震える左手で食事のスプーンを運びながら、ユーセフの話を遮った。
「いま何か、呪文のようなものが聞こえました」
ユーセフはため息をつくと、ぼくのかわりにスプーンを持ち、食事を運んでくれようとした。リハビリだからとぼくは断った。本当は右利きなのだ。
「よく誤解されることだが、金融工学は金を殖やすための学問じゃないんだ」
ユーセフはぼくの手元を見ながら、嚙み砕いた言いかたをした。
「市場の動きは予測できない。だが、低いリスクで投資をすることはできる。それが、金融工学の出発点だ。そうだな、たとえば、ブラック・ショールズ方程式というのがある。金融商品の値段を決めるための公式だと考えてくれ。これは、市場の予測できないランダムな動きを、確率的に記述することからはじまった」
「それで、安全に投資できるようになるんですか」
「ならない。この方程式を作った連中が興した投資会社は、まもなく破綻したんだ。というのも、ランダムな動きといっても、その内容は実にさまざまだ。さっきの方程式は正規分布というものを前提にしているが、現実の市場はそうなっていない」
「だったら、その分布を補正すればいい」
「そういう試みもなされた。でも定着はしなかった。一つには、計算が煩雑になる。もう一つには、方程式を補正しても、その補正のせいで、市場の動きが変わってしまう。いたちごっこなのさ。そこで、量子金融工学は、原点に立ち戻って考えた。ブラック・ショールズ方程式の背景にある数学は、さかのぼればブラウン運動にたどり着く。これは簡単に言えば、水中で破裂した花粉の動きを表すモデルだ。しかし株価と花粉粒子では動きが大きく違う。そこで、より精密に、株価の動きを量子の動きにあてはめ、シュレーディンガー方程式を解いて確率を得ようとなった」
「ええと……」
一行にまとめてくれ、とは言えない。
「量子力学と金融工学が出会ったことで、おのずと一つの可能性が生まれた。ポートフォリオ、分散投資の新しい形だ。もともと、投資とはいかにリスクを回避するかだ」
ユーセフはペンを取ると、ぼくの新しい左腕に勝手に絵を描きはじめた。
たとえば、暑いとよく穫れる米と、寒くても穫れる麦の両方を先物買いする。そうすれば、暑くても寒くても、大きな損害を被ることはない。でも、どんな場合にも対応できる分散投資などない。これが投機家たちの悩みの種だった。
最後に、ユーセフは悩める投機家の顔を描いた。
「そこで、新たな手法が考え出された。いいか、あくまで物の喩えと考えてくれ。米が豊作である宇宙と、米が不作である宇宙の両方に投資する。こうすれば、精度の高いリスクヘッジが可能になる。これが、多宇宙ポートフォリオという分野の基本的な考えかただ」
「待ってください」ぼくは思わず遮った。「隣りの宇宙から米は届きません」
「いい指摘だ」ユーセフが応えた。「そう、これは仮定だ。あくまで、彼らは仮象の米を取引している。実際は、投機家と証券会社の間で金のやりとりがあるだけさ」
でもな、とユーセフはつけ加え、話を打ち切った。
「レトリックだよ。どのみち、市場も人の心も読めない。それだけだ」
ユーセフの研究は頓挫した。
ある日、突如としてストップの声がかかり、資金を打ち切られた。十年ほど前に、惑星規模の金融破綻が起きた。その原因が、量子金融工学にあったのだという。ユーセフは野に下り、いくつかの職を転々としたのち、新星金融に入社した。地球の原始宗教に帰依したのも、この時期のことらしい。詳しい事情については、ぼくも訊かないし、ユーセフも語らない。それでいいとぼくは思う。みんな、何かしら事情がある。
翌日も取り立てだった。ぼくとユーセフは目立たないよう、ビジネスマンを装うことにした。慣れないスーツを着たぼくを見て、「馬子にも衣装だな」とユーセフは言った。
だが、不作だった。
二人目までは港の屋台街で発見したが、その日に取り立てる予定だったほかの三人には逃げられた。ぼくらが宇宙港まで来ていることは、すっかり知れ渡っていた。特に、アンドロイド同士のネットワークは固い。情報が伝わり、ターゲットに逃げられてしまうのだ。
だから取り立て人は、ときには変装し、目的の相手に接触する。
アンドロイドのネットワークは、人間のそれとは別物だ。ぼくたちは、彼らのネットワークを見ることができない。たとえ見られたとしても、おそらくは理解さえできないだろう。だから、ぼくらはそれをこう呼ぶ。暗黒網と。
逆に、アンドロイドもまた、人間のネットワークにはアクセスできない。これは、遠い昔に制定された規則がベースになっている。かつてアンドロイドの知性が人類を超えそうだとなったとき、脅威を感じた人類が、新三原則というものを制定したのだ。
第一条 人格はスタンドアロンでなければならない
第二条 経験主義を重視しなければならない
第三条 グローバルな外部ネットワークにアクセスしてはならない
スタンドアロンとは、人格の複製や転写ができないことを意味する。
二つ目の経験主義については、こう説明されている。「行動の決定にあたっては因果律を優先し、因果律の重みづけは自己の経験に従う」──何やらわからないが、つまりこうだ。たとえば、以前黒猫を見たその日に解雇され、車に轢かれ、帰宅したら家が焼失していた。今日は黒猫を見たので会社を休もう。
もちろん、気にせずに出社することもある。「因果律の重みづけ」は個体により異なるからだ。要は、あまり合理的すぎるのもなんなので、もう少し人間風に行きましょうということだ。むしろユーセフにあてはめたい。
最後の一つが、ウェブへのアクセスを禁止している。
「グローバルな」と明記してあるのは、職務を妨げないよう、それぞれの環境でイントラネットを構築していたころの名残りだ。知識の面で彼らの能力を制限しようというものだが、いまはなかば形骸化している。アンドロイドは独自にピア・トゥ・ピア型のネットワークを築き、それを共有するようになった。それが暗黒網だ。
この三原則とひきかえに、アンドロイドは一定の権利を得た。でも、差別は根強い。二番街などは露骨だ。建前上は公民権があるのに、投票に行ったというだけで、職を解雇されたといった例があとをたたない。だから、公民権運動はいまもつづいている。
ところで、ユーセフから聞いた話では、第三条にはもう一つの意味があるらしい。
「なぜアンドロイドが人間とそっくりか、知ってるか」
「……さあ、わかりません」
ぼくは震える声で応えた。なぜなら、そのときぼくは飛行機で地上一万メートル以上まで上昇し、パラシュートを背負わされていたからだ。そしていままさに、眼前のハッチが開こうとしている。ユーセフとしては、緊張を解きほぐそうとしてそんな話をしたのかもしれない。でも、はっきり言って、ぼくとしてはまったくそれどころではなかった。
「少しは考えろ」
「そりゃ、人間が作ったからでしょう」
「それはおかしい」とユーセフが指摘する。「もちろん、アンドロイドは最初から人間に似せて作られている。人格の転写はできないようプロテクトされているし、ファームウェアの寿命は人と同じくらいに設定してある。でも、そんなプロテクトは外せる。もともと、人間とはまったく違う生命体なんだ。それが、おれたちと同じように物を考え、その日その日を暮らしているのはおかしいと思わないか」
実際、とユーセフはつづけた。
「初期型のアンドロイドは人間のようには動いてくれなかったんだ。研究室で生まれたアンドロイドは人間とは違う言葉を喋り、学者には理解できない、まったく別の論理で行動するようになった。機械でできていて、人間よりもスペックが高い。そんな生物の取る行動や喋る言葉が、おれたちに理解できるわけはなかったんだ」
このときハッチが開ききった。行くぞ、とユーセフがつぶやいた。
「でも、その……」足が震えて動けなかった。
「いいか。次に〝でも〟と言ったら蹴り落とす」
「でも……」
ユーセフはぼくを飛行機から蹴り落とすと、自分もあとからつづいた。
その日のターゲットはカスミアオイと呼ばれる植物だった。もともと、二番街は土壌が悪く、植物が育ちにくかった。そこで学者のグループが、空を飛ぶ植物を作り、古代日本語からカスミアオイと名づけた。カスミアオイは浮き袋を持ち、そのなかに水素を蓄えている。学者たちは彼らに雲を探すための視覚器官をつけた。
こうしてカスミアオイは低気圧とともに移動し、雲を食べて暮らしている。
二番街の空中は、この植物に覆われている。風向きや気候によっては真っ暗になるくらいだ。これによって、人類は必要なだけの酸素が得られた。
ところが、不測の事態が訪れた。カスミアオイは空中でネットワークを築くと、知性を持つまでに進化してしまったのだ。彼らは個体であると同時に、群体でもある。カスミアオイは、光合成の対価として金銭を要求するようになった。聞いた話では、人間の音楽を買っているらしい。どうやって聴いているのかは知らない。やつらに訊いてくれ。
問題は、そんな空を舞う植物が、新星金融に借り入れを申し入れてきたことだ。審査のスタッフは、光合成ができる以上は返済能力はあると見た。バクテリアだろうとエイリアンだろうと、返済さえしてくれるなら融資をする。それがうちの方針だ。取り立てはぼくらに丸投げされた。でも、どうしろというのか。
「──新星金融の者だ! 取り立てに伺った!」
ユーセフの声は翻訳機を通し、空中に幾何学模様の立体映像を描き出した。これを受けて、カスミアオイの群れが動き、新たな模様を描き出す。パターンからパターンへ、模様は目まぐるしく変化する。これが彼らの言語なのだ。遅れて、翻訳機が声を発した。
「御社から融資を受けた者はもう死亡した」
「知るか! おまえたちは個体でもあり、群体でもある。いわば連帯保証人だ!」
「そのような契約はなされていない」
「いま、飛行機からウイルスを散布している!」
そんな話ははじめて聞いた。たぶんハッタリだろうが、念のためぼくは息を止めた。
「これはカスミアオイにのみ感染し、おまえたちが水素を電気分解するプロセスを阻害する! いまは無害だが、コマンド一つで活性化するようプログラムした!」
ナノマシンなのか。
「そんなことをしたら、惑星そのものが危機に陥る」
「おれたちの仕事は取り立てだ! それ以外のことなどどうでもいい!」
しばらく植物は迷っていた。空中のそこかしこにパターンが浮かびかけては消えたが、喧嘩は得策ではないと踏んだのか、元金と利息分を支払う旨を告げてきた。
カスミアオイは、意地や面子にこだわらない。
こんな話もある。人類がカスミアオイに求めたものは、光合成のほかにもう一つある。バースコントロールだ。雲を食べすぎないよう、出生率を抑えてもらう。
毎度、とユーセフは言うとパラシュートを開いた。ぼくもそれに倣おうとした。でも、うまくいかなかった。いくら紐を引いても、パラシュートは開かなかった。ぼくは青い顔で上司を窺った。何が起きているのか、ユーセフも即座に理解した。
ユーセフが通信機越しに叫んだ。「予備のパラシュートを開け!」
ぼくも叫んだ。
「だめです! 死ぬ前にこれだけ! あんたは超最悪の上司でした!」
死ななかった。
様子を察知したカスミアオイの一団が動き、空中で駕籠のようなネットワークを作ると、ぼくの身体を受け止めたのだった。
遅れて、ユーセフも駕籠のなかに降りてきた。
「おれのことがなんだって?」とユーセフが言った。
「尊敬する憧れの先輩です」とぼくは応えた。
ユーセフはぼくの右の頰を殴り、次に左の頰を殴った。
「おい、植物ども、聞こえるか!」
「聞こえている」
「こいつの命を助けてくれた礼だ! 利息分はいらない! サービスだ!」
ぼくらはカスミアオイの駕籠に揺られながら、しばらく空中を漂った。そのうち、思い出したようにユーセフがつぶやいた。
「……学者たちは、アンドロイドの無意識に干渉することにしたんだ」
「へ?」ぼくは間の抜けた返事をしてから、さっきの話のつづきだと気がついた。
「正確には、無意識という機構を組みこんだ。昔、フロイトという学者が言い出した概念だ。学者たちは、人間の持つネットワーク──無数の日記や会話、つぶやきといった記録を共通の無意識として、アンドロイドの知性の深層に据え置くことにした」
ユーセフはおおまかな設計をぼくに語った。いわく、アンドロイドの無意識モジュールに、人間側が暗号化した情報を一方的にプッシュ配信する。モジュールはブラックボックスになっていて、中身を見ることはできない。
「本来はまったく違う生命体だったアンドロイドが人間のように振る舞うのは、これが理由だ。ここから、アンドロイドの無意識はクラウドと呼ばれている。無意識というものを、人間が持っているのかどうかはわからない。だが、やつらはそれを持っているというわけだ」
だから、とユーセフはつづけた。
「アンドロイドは人間のウェブにアクセスしてはならない。アンドロイドが人のネットワークに干渉すると、クラウドは人間の鏡像ではなくなってしまう。人間のネットワークを人間が管理する場合のみ、アンドロイドは人間のように振る舞うんだ」
植物の駕籠に揺られながら、ぼくは曖昧に頷いた。
このカスミアオイとの一件は美談となり、社内報でも大きく取り上げられた。以来、空を舞う心優しい植物と新星金融は、良好な関係をつづけている。ユーセフは表彰を受け、昇進した。利息分がぼくの給料から差し引かれたことだけを、誰も知らない。
宇宙港での滞在は二泊止まりとなった。
ユーセフに、社から呼び出しがかかったのだ。人格を転写して借金逃れをしたアンドロイドの件が、静かな波紋を広げていた。情報共有のページにはたくさんのコメントがつき、別の恒星系でも同様の事件が起きていたらしいことがわかった。
二番街支社でも対策のための会議が開かれることとなり、アンドロイドからの取り立てで好成績をあげているユーセフの出席が求められた。これを聞いてユーセフは舌打ちをした。まだ、目標の取り立ての半分も満たしていなかった。
「まあいい」とユーセフは即断した。「新星金融は宇宙港まででも取り立てに来る。それを示せただけで、今回はよしとしよう」
ぼくには嬉しいニュースだった。
無重力のドミトリーで寝るのは嫌だったし、社の呼び出しとあれば、何日もユーセフと一緒に宇宙エレベーターに乗るのではなく、シャトルで地上に戻ることになる。
「それより、おれはその事件のことを知らない。かいつまんで話してくれないか」
「はい」
ドミトリーのベッドに横になりながら、ぼくはユーセフに説明をした。
最初の事件が起きたのは、DL2系支社だ。借金を返せなくなったアンドロイドが、別のアンドロイドを乗っ取り、元の身体を破棄した。その一年後、DV5系支社でも同様の事件が起きた。こちらはただの死亡事故と思われていたが、あとからの調べで、同じように人格の転写による借金逃れが起きていたことがわかった。
「模倣犯か」
「そのようです。手口が巧妙です。まず、自分と関わりのないアンドロイドに狙いを定め、拉致してから人格を転写する。元の身体には、翌日に入水自殺するようプログラムしておく。解析したところ、このプログラムがそっくり同じだったそうです」
「なるほど」
「水死を選んだのは、証拠隠滅のためと思われます。自己消去プログラムを走らせることはできますが、それでも記憶領域から完全に痕跡を消すことはできない」
この意味で、アンドロイドは完全に死ぬということができない。これは、人類によってかけられた呪いのようなものだ。外部装置を使えば完全な消去もできるが、その場合、装置そのものが残る。
「ですから、水没によって、機器が破損することを期待したと考えられます」
「うん」
「まず、DL2系で事件が起き、その手口が一部の暗黒網で共有された。それを模倣して、DV5系で同様の事件が起きた」
「ちょっと待て。おかしいぞ」
上でベルトを外す音がした。ユーセフがベッドを這い出て、ぼくの横に浮かび出た。
「おれの記憶では、その二つの恒星系は十光年以上離れている」
「え?」ぼくは訊き返した。「何がおかしいんです?」
「馬鹿かおまえは」
吐き捨てるような口調で言う。ほかに言いかたはなかったのか。
「二つの事件の時間差は一年。──情報が、光速を超えてるんだよ」
「あ……」
そこからは意見の出しあいになった。
ユーセフとしては、会議の開催までに前提知識を固めておきたい。でも現状のままでは、謎が残り、はっきりした事実関係が見えてこない。
「辻褄だけ合わせるなら簡単だ」とユーセフは言う。「たとえばどこかの誰かが、そのような行動を取らせるプログラムをし、二つの星系にアンドロイドを送りこんだ」
「借金を踏み倒す、ただそれだけのためにですか」
「そうだな。これはおかしい。何かアイデアはあるか?」
「以前、アンドロイドには共通無意識があるとおっしゃいましたね。星系をまたいだ二体のアンドロイドが、一つの無意識でつながっているということはないですか?」
「ああ、クラウドのことか。それはない。アンドロイドの共通無意識は、おれたちが持つ人間のネットワークにすぎない。情報が光速を超えるようなことはないんだ」
「だとすると」ぼくはつづけた。「まだぼくらが知らない、第三の事件があるんです」
「どういうことだ?」
「これを仮にX星事件としましょう。このX星で、やはり同様の事件が起きた。このことをぼくらは知らないけれど、一部のアンドロイドは、暗黒網を通じて情報を得ていた。二つの事件は、これを模倣して行われた」
「なるほど。だが、宇宙のどこかであったかもしれない事件を仮定するのか」
「絞りこめます。彼らは情報共有が早く、知ったことはすぐに行動に移す。つまり、X星はDL2系とDV5系の間に位置しています。具体的には、DL2系までがn光年、DV5系までがn+1光年の距離です。この条件を満たす円錐上の文明圏は限られている。そこで発生した、アンドロイドの水死事故をあたるんです。時期は、DL2系事件のn年前。もしあったならば──それが、X星事件です」
「いいぞ」ユーセフはにやりと笑った。「よく思いついたな。すぐ調べられるか?」
「はい」
言いながら、ぼくはユーセフの特徴をもう一つ思い出した。ずるいところだ。
この男に褒められると、どういうわけか、嬉しくなってしまうのだ。
条件を満たす文明はすぐに見つかった。DL2系までn光年、DV5系までがn+1光年の惑星は、誤差を設定した上でも一つしかなかった。それは、いま真下にそびえる惑星──ほかならぬ二番街なのだった。
水死事件はあった。
五百年前の、二番街で。
しかもそのアンドロイドは、新星金融から借り入れをしていた。クライアントの死亡により回収を断念、と当時の記録に残っている。ぼくとユーセフは顔を見あわせた。
ぼくらは水死したアンドロイドの行方──つまり、彼ないし彼女に宿っていた人格を追跡できないかと考えた。
そうしようと思ったのは、ユーセフの指摘がきっかけだった。
「事件の犯人をXとしよう。あくまで可能性としてだが、Xは同じ手口を繰り返して、いまも生きているかもしれない。だとしたら、追跡できないこともない」
「追いかけてどうするんですか」
「決まってるだろう。取り立てるんだよ」
呆れた。
Xが二番街の客らしいとわかった瞬間から、ユーセフはこのことを考えていたのだ。
「……複利計算で、利息が全宇宙の原子の数を超えますよ」
「いまから言うアルゴリズムでプログラムを書け」
「はい」
「Xの追跡にあたって、再帰的な探索を行う。条件は、過去に水死した全アンドロイドのうち、X星事件当時、近くに居住していた者すべて。百人いるかもしれないし、逆に一人も出てこないかもしれない。もし一人以上いた場合は、彼らの水死をX+1事件として扱う」
「待ってください」ぼくはノートパッドを開いてメモを取りはじめる。
「つづけるぞ。すべてのX+1事件について、同様の検索を行い、X+2事件を洗い出す。これを、X+3、X+4と順に繰り返し、すべての可能性を網羅する」
「Xが同じ手口で人格を複写していったとして、その足取りを追うんですね」
「そうだ」
「この方法だと、候補が鼠算式に分岐しませんか」
「やってみなければわからない。ただ、アンドロイドの水死は、そう頻繁に起きることではない。もしXがいまも実在するなら、一本の道に収束することも期待できる。むしろ、一つの候補も出ない可能性のほうが高いと思う」
「確認させてください。以上の方法で洗い出したルートのうち、もし現在にまで至る道があったなら、そのすべての候補を出力し、それをもって探索結果とする」
「すぐ書けるか?」
「書くだけなら十五分。ですが、チェックもしないと……一時間もらえますか」
言ってから、しまったと思った。
つい、いいところを見せたくて短く見積もってしまった。一日仕事だと言っておけばよかったのだ。ユーセフは満足げに頷くと、待つぞ、と言って自分のベッドに戻ろうとした。その表情に、一瞬だけ影がさすのがわかった。ぼくは思わず訊いていた。
「どうかしましたか」
「おまえは変に鋭いな」ユーセフが苦笑した。「おれも、おまえのアプローチは悪くないと思った。でも、その一方で、心のどこかで期待しちまったんだよ。ほんの少しだけだがな」
「なんのことです」
「笑うなよ」
「笑うもんですか」
「この宇宙のどこかで、誰かが、光速を超える通信方法を考え出した可能性さ」
「ははは」
ユーセフはまずぼくの右の頰を殴り、次に左の頰を殴った。
最初は農民だった。
二番街の不毛地帯を開墾し、農耕を可能にすること。それが、Xに託された最初の役割だった。Xは人も住めないような土地を何十年にもわたって耕し、土壌調査をし、ある程度の見こみが立ったところで、生産拡大のために資金の借り入れを申し入れた。Xが耕した土地は、いまは二番街有数の穀倉地帯となっている。
だが、借り入れからまもなくして、惑星規模の飢饉が発生した。
返済が不能になり、Xは水死を選ぶ。土地は国有のもので、X本人に資産らしい資産は残されていなかった。こうして、当時の担当者は回収を断念する。このころには、Xは新しい生活を送りはじめていた。Xは、都市部でオフィスワーカーとして働いていた。会社での仕事を真面目に勤め上げたのち、退職し、釣りに行くと言い残して水死した。
その次のXは病者だった。
当時としてはまだ珍しい、アンドロイドの精神病者である。Xは人生──人生と呼んでよければだが、その大半を閉鎖病棟で過ごし、入退院を繰り返したのち、水死することを選んだ。
なぜXがこのような遍歴をたどるのか、ユーセフには自説があるようだった。
「……経験を蓄えてるんだ」
「なんのためですか」
「三原則の一つ、経験主義であることだ。アンドロイドの知力を抑えるために、人類は彼らの論理的思考を制限した。だから、アンドロイドは経験を重んじ、経験を積み重ねることで、正しい判断基準に近づこうとする。彼らは職を転々としたり、あるいはよく旅をしたりするだろう。それは、この原則によって生まれた習性なんだ」
「ですが、人格を転写することで、すでに原則の一つを破っています」
「プロテクトには、破るメリットが大きいものと小さいものがある。人格を転写するのは、それによって長く生きられるという明確なメリットがある。逆に、破ろうという発想にさえ至らないプロテクトもある。つまり、経験を重んじるようにとプログラムされた人格が、経験主義の原則を自ら破ろうとは、なかなか考えつかないものだ」
どうしてユーセフはアンドロイドの生態に詳しいのか。
もちろん、顧客について知ることは重要だ。でも優秀な取り立て人は、必要以上に相手を知ろうとはしない。興味を持たないこと。きれいさっぱり忘れること。それが、この仕事を長くつづけるコツだ。不思議に思い、ユーセフに訊いてみたことがある。返答は意外なものだった。「憎いんだよ」とユーセフは言ったのだった。ぼくはそれ以上は訊かなかったし、ユーセフも何も言わなかった。
Xの次の人生は神父だった。原キリスト教に近い宗派の神父として、日曜には説教をし、ミサを行い、また人間たちの懺悔を聞いた。当時のXをめぐるログは多く見つかった。Xはアンドロイドでありながら、人間たちから慕われ、愛されていた。だからXが水死したとき、多くの人たちが彼の死を嘆き悲しんだ。
Xは旅人になった。彼の紀行文はいっとき二番街の住人たちの支持を集め、万単位で複写されたが、いくつか作を重ねたところで飽きられ、複写回数も減少していった。Xが水死したとき、彼を憶えている人間はほとんど誰もいなかった。
その次が壮絶だった。
Xは革命家だった。Xは農耕のために不毛地帯に送り出されたアンドロイドたちを煽動し、あるときは壇上で演説をし、あるときは武器を取り、アンドロイドの公民権運動に携わった。だが、政府がXの組織のメンバーを切り崩した。公民権はないままに、生活の一部が保障され、農耕をめぐるいくつかの特権が付与された。
メンバーがこの成果に満足したのに対し、Xはあくまで強硬な運動を主張し、結果として組織からパージされた。Xは人間からもアンドロイドからも背を向けられ、一人の味方もいないなか水死を選んだ。
「……ポル・ポトを思い出すな」とユーセフがつぶやいた。
「誰ですって?」
ユーセフが露骨に馬鹿を見るような目つきをしたので、ぼくは質問を諦めた。そんな顔をしなくてもいいじゃないか。誰がプログラムを書いたと思ってるんだ。
革命家としての失敗は、Xにとって傷手だったのかもしれない。
その後、Xはいくつかの凡庸な人生を送っている。都市部から農村へ。農村から開拓地へ。初心に返るように、Xの足取りは過疎地へ向かっている。この間、見るべき成果や業績はない。むしろ、凡庸であろうとしている節が窺えた。ただ、この隠遁にも近い一時期があったおかげで、絞りこみが容易になった。
Xは転向した。Xは旧い紛争地帯で地雷を撤去したり、あるいは砂漠地帯で一人井戸を掘るようになった。カスミアオイが雲を食べてしまう関係から、二番街では水資源が不足することが多い。Xに注目する者はいなかった。アンドロイドが地雷を取り除いたり、砂漠に井戸を掘ったりするのは、珍しいことではない。Xの姿に、かつてのような野心は見られない。かわりに、ぼくの目にはまるで聖者のように映った。
一人の弟子も信徒もいない、砂漠の聖者。
ほとんどの時間をおそらくは一人で過ごし、最後には自らが掘った井戸で水死した。
「……ここまでか」とユーセフが言った。
「そうです」
二十年ほど前のことである。ここで、Xの足取りは途切れている。
「当時、この砂漠を訪れたアンドロイドは……」
ユーセフは質問をしかけたが、いやいい、と打ち消した。
「いるはずもないな。Xの遍歴は、ここまでだったということか」
「ところが、そうでもないんです」
「調べたのか?」
「はい。当時、この地域を視察に訪れた一団のなかに、アンドロイドが一人います」
「いまどこにいる」
「首相官邸。ハシム・ゲベイェフ。──二番街統括政府の現首相、その人です」
これにはユーセフも絶句した。
ゲベイェフは、もとは政治家の一秘書でしかなかった。それが、砂漠を訪れた時期を境に変貌した。政党にとって、ゲベイェフの存在はリベラルさを取り繕うための広告塔となった。ゲベイェフは推薦を取りつけると政治家に転向し、たちまちアンドロイドたちから巨額の資金援助を受け、上院唯一のアンドロイドであったにもかかわらず、与党である自由党のトップにまで登りつめてしまった。これが二年前のことだ。
惑星規模で資本や人口の割合を見た場合、これは民主的とも言える結果だった。だが、人類に言わせれば、民主的ではなかった。
ゲベイェフは不審そうな表情を隠さなかった。それはそうだ。一応フォーマルな服装をしてきたものの、ぼくとユーセフは明らかに場違いで浮いていた。ゲベイェフはぼくら二人を交互に見比べてから、どういうことかな、と訊ねてきた。
「労働党との会合だと聞いていたが」
「その労働党の代理人として参った」
ユーセフが本部のミーティングに参加している間、労働党と接触したのはぼくだった。何度か門前払いを受けたのち、労働党の幹部数名の債権を手にユーセフが現れ、それからやっと話がまとまった。
ユーセフが振り向いてぼくを見た。「おい」
はい、とぼくは上擦った声を上げる。
「企業理念」
ぼくは観念した。「わたしたち新星金融は、多様なサービスを通じて人と経済をつなぎ、豊かな明るい未来の実現を目指します。期日を守ってニコニコ返済──」
「聞いての通りだ」
低いがよく通る声で、ユーセフがぼくを遮った。
「五百年の昔から、カネの取り立てに伺った」
ゲベイェフは首を傾げる素振りをしながらも、人払いをした。どうも、とユーセフが言った。まったく物怖じしない。なぜこの男は、こうも図太くいられるのだろう。
それにしても、どう話しあいをまとめるつもりなのか。
現職の政治家が、X星事件など認めるはずもない。ぼくら自身、推論でここまでやってきているのだ。ユーセフは、何を引き出そうというのか。まさかノープランではないだろう。この男は、戦略を練ったその上で、出たとこ勝負をするタイプなのだ。
ぼくなどが思いつくのは、せいぜいこうだ。
わたしたちは、過去の債権を洗っているうちに、とあるアンドロイドの遍歴に行き着きました。証拠はないですが、同じ事実関係から同じ推論をする人は多いでしょう。とはいえわたしどもと致しましても、お客さんの過去を問う気はありません。複利計算だと天文学的な数字になってしまいますので、元金だけでも返済いただけますか。
だめだ。
これでは、脅迫にしかならない。というか、帰り道にそのまま投獄される気がする。それも、なぜかぼく一人だけが。なんの根拠もないけど、これまでの経験から言って、なんとなく絶対にそう思う。
「五百年の昔と言ったね」
ゲベイェフが柔らかい口調で訊いてきた。
「わたしにも理解できるよう、嚙み砕いて説明してもらえるかな」
「それでは、単刀直入に申し上げる。五百年前、あんたが農民だったころに作った債務を取り立てるために伺った。とはいえ唐突なのは確かだから、今日のところは、今後の返済計画について、ざっくりと見通しを立てられればと思っている」
だめかもしれない。
いまのうちに、家族にメール一本打ってもいいですか。
「話を整理させて欲しい」ゲベイェフが辛抱強く言った。「きみたちは、労働党の代理でここに来たと言った。しかし持ち出してきた用件は、きみたちの会社が持つという債権に関することだ。この話しあいにおいて、労働党の利益はなんなのか」
もっともな疑問だ。ゲベイェフの立場から考えてみると、これが一番気にかかる点には違いない。ここまで訪ねてきた以上は、皆に利益のある話を持ってきたはずだ。少なくとも、脅迫の類いとは限らない。だから、ゲベイェフとしても話を聞いてみようと思う。だとしても、その共存共栄のプランとはどういう形をしているのか。
「おい」
ふたたび声をかけられた。
「左腕。外してみせて」
ぼくは黙って義手を取り外した。できるなら、こういうハンディキャップを人に見せたくはなかった。でも、そう言ってもいられない。考えがあってのことなのだろう。
「こいつの左手は義手でね。ある債権を取り立てているときに、失ったんだ」
「それはまた……」
「幸い、うちのスタッフは雇用保険にも健康保険にも加入できる。実際は労災扱いになったんだが、二番街のほかの仕事に比べればましなわけだ。これがよその仕事なら、義手をつけることもできず、一生を片腕で過ごすことになったろう。そうだろ?」
同意を求められ、はい、と応えた。義手でこそあれ、事実そうなったような気もするのだが。深く考えると腹が立ってきそうなので、とりあえず考えるのはやめた。
だが、とユーセフは言葉をついだ。
「いかんせん、二番街の健康保険は高い。これもあって、うちとしても雇用を拡大できない実情がある。といって非正規のスタッフを増やすのでは、本末転倒になる」
「医療保険改革の話だろうか?」
「労働党が提案している医療保険改革は、もともとそちらの懸案事項でもある。この話がまとまらないのは、要するに、それによって発生する利権が定まらないからだ」
「労働党は、結局のところ自分たちに利益のあるプランを出している。ではうちの党がどうかと言えば、隠すことでもないから言ってしまうが、やはり自分たちの利益が優先だ。第三者機関を設けるという点では合意しているが、両党とも、紐つきの法人を推している。だからわたしとしては、現状、どちらの案にもゴーサインは出せない。とはいえ話がいっこうに進まないのは、結局は両党にとって不利益なので、困っているわけだ」
「そんなあんたを見こんで、提案がある。つまり、こういうことなんだ。いまさら、与党も野党もあとには引けなくなっている。そこで、医療保険に携わる第三者機関として、うちが作る新法人を指定してもらいたい。この形に軟着陸させられるなら、労働党としても受け入れられない話ではないとなった。だから、あとはあんたの判断次第なんだ」
ユーセフは咳払いをした。
「では、利益はどのように還元するのか。まず、必ずしも労働党には還元しない。うちが立てた大義名分はこうだ。我々は、そのときどきの与党に対して、そのつど利益を還元する。民意に応じた政党を儲けさせますよ、ということだ。つまり、うちは儲かる。あんたがたも、儲かる。労働党としては、長いこと提案してきたプランが通ることで面目を保つ。もし晴れて与党になったなら、そのときは利権にあずかることもできる。さて、これまでと比べればフェアな話だと思うんだが」
「口頭では決められない。だが、プランの詳細が詰められ、文書化されたなら、党内で合意を得るのは必ずしも不可能ではない。少なくとも、短期的な利益はある」
心なしか、棘のある口調だった。自身の党への皮肉を含んでいるのかもしれないが、本音のところはわからない。別にそれでいい。みんな、何かしら事情がある。ぼくたちは、金の話をするためにここに来たのだ。
ゲベイェフがつづけた。
「その上で労働党の代表、わたし、それから御社の代表を交え、互いの見解に相違がないことが確認しあえたなら、むろん内容にもよるが、充分にありうる話と思う」
そこからは、煩雑な手順の話になった。
誰がどういう順序で、どこを窓口に合意を形成するか、大雑把な枠組みをユーセフが提案し、それについてゲベイェフが同意した。このあたりは、ぼくはただ呆然と聞いていたのでよくわからない。ぼんやりと、窓口担当は心労で倒れそうだなと思った程度だ。でも、握手が交わされたあとのユーセフの一言で目が覚めた。
そうだ、とユーセフが思い出したように言った。
「肝心なことを忘れていた。おれたちの本業、つまり債権の取り立てなんだが」
帰りたい。
「とはいえ、さすがに五世紀も前のことに関しては、記憶も薄らいでいると見える」
「記憶も何も、まったく心あたりのない話だ」
「党としてでも、あんた個人としてでもいい。うちから追加融資させてくれないか」
「新規の融資の話であれば、むしろ願ってもないことだ」
「わかった。追って審査のスタッフから連絡が行くようにしよう。もちろん、形式上のことだ。まさか現職の首相について、審査が通らないことはないと思う」
「連絡は、きみ個人からよこしてくれ」
ぼくは呆気に取られた。最高の新規顧客を開拓した上、ゲベイェフとのパイプを作ってしまった。つくづく思った。たった一つのミスで信用を失うやつもいれば、普段はいい加減で最悪なのに、たまに大得点をあげて挽回するやつもいる。
「一つ教えて欲しい」とゲベイェフが言った。「今回、なぜきみはこのような行動を取ったんだ? 出世のためか? だが、そういうタイプとは異なるように見える」
「出世だよ。おれは俗物なんでね。ただ、一つ本音を言うと、あんたに会ってみたいと思っていた。荒野にただ一人井戸を掘りつづけた、あんたという人間に」
人間、とユーセフはごく自然に言った。おそらく彼自身、考えて言ったことではないのだろう。型破りなのか、繊細なのか。それとも、やっぱりただの無神経なのか。
「それと、もし知っていれば教えて欲しい。十年前の金融破綻についてなんだが」
「待ってくれ」
ゲベイェフはしばし沈黙してユーセフの名刺を眺めた。目には見えないが、おそらくは暗黒網に高速でアクセスし、素性を探っているのだろう。
「あのときの研究員か」ゲベイェフが結論した。「きみのことはよく知っているよ」
ゲベイェフが場所を変えようと提案し、ぼくらは彼の執務室に招かれることになった。歩きながら、現在の経済状況についてゲベイェフがいくつか質問をした。ユーセフはすぐにいくつかの見解を述べる。なるほど、とゲベイェフが興味深そうに頷いた。
「やはり、人間の見解は面白い」
「優秀なブレーンがたくさんいるだろう」
「穏当なプレゼンしか上がってはこない」
どこも、組織とはそういうものらしい。二人の話をぼくはちっとも理解できなかったが、まだ本題に入っていないことだけは、なんとなくだけれど察せられた。ぼくらはソファに座らされ、ゲベイェフがテーブルにブランデーの瓶を置いた。
ユーセフはムスリムだからとそれを断ると、遠慮なく部屋を見回した。
「ウェブにアクセスできないのは不自由だな。……いや、していないわけはないか」
「わたし個人のために、独立した内部ネットワークを構築した。例外的にプロテクトを外してもよいとなったが、好ましくはないだろうと判断した。きみは飲むかい」
はい、とぼくは応えた。素面では、やっていられない。
「ムスリムなのに金貸しをやるのか?」
「適度な例外が肝心なんだ。何事もそうだろう」
ゲベイェフは向かいのソファに腰を下ろすと、じっとユーセフの目を覗きこんだ。しばらく無言のまま時が過ぎた。それからゲベイェフが言った。
「わたしたちが憎いか」
「憎くないと言えば噓になる。だがそれ以上に、真実を知りたい」
「きみはどうなんだ」
突然水を向けられ、ぼくは慌てた。
「ぼくはその」つい本音が出た。「話題に追いつきたいです」
ユーセフが、まるっきりの馬鹿を見るような目でぼくを見た。そんな顔をしなくたっていいじゃないか。しょうがないだろう。知らないものは、知らないんだ。
「この男は、金融工学のエキスパートとして政府機関で働いていたんだよ。詳しく言うなら、多宇宙ポートフォリオを中心とする量子デリバティブだ」
「それなら、聞いたことがあります。でも、ぼくの漠然とした理解では、隣りの宇宙から米が届くような、そうでないような」ぼくは極力ユーセフのほうを見ないようにしながら、「……分散投資の新しい姿になるはずだったもの、と理解しています」
「そう。画期的な研究だった。それまでの金融工学のモデルは、言ってみれば水中を漂う砕けた花粉のシミュレーションだった。そうではなく、金融商品を量子レベルにまで落としこんでモデル化しようというのが、量子金融工学の出発点だ。この男が研究していたのは、それをさらに拡充して、宇宙をまたいだ分散投資への道筋を明らかにすることだった。これによって、投機家はより安全に資産を運用し、企業もまたその恩恵にあずかれるはずだった。投機家も、経営者も、労働者も、誰も不幸にしない新しい資本主義。それが、彼の研究の目指す地点だった。……ところが、実運用されはじめた矢先に、金融破綻が発生した。新しい形が生まれるたび、新しい破綻が発生する。結局は、金融工学の繰り返した歴史を、同じようになぞる結果となった」
「起きるはずのないことが起こった」
ユーセフがあとをついだ。
「正確には、予測はされていたが、起きないだろうとされていた現象が起こった」
「どういうことです」
「金融商品のモデル化にあたっておれたちが前提としたのは、価格の変動を運動量として見たとき、それが光に比べて非常に遅いということだ。実際の人間の取引においては、それで問題ない。だが、秒あたりの取引回数が無尽蔵に増えた場合──価格の変動速度が限りなく光速に近づいたとき、量子金融工学はアインシュタインの相対性理論の影響を受ける」
そして、とユーセフはつづける。
「それは起こった。おれたちの予測をはるかに上回る量取引が発生した。さて、相対論の影響を受けるとは、何を意味するのか。ブラックホール解が出現する。金融商品の群れがシュヴァルツシルト半径を割りこむと、計算上、光すら抜け出せない地点が発生する。どうなるか。現実的に、商品の価格が決められなくなる。結局、全取引を凍結するしかなかった。こうして、十年前の金融破綻は発生したんだ」
誰がやったかまではわかっている、とユーセフは言う。ウェブアクセスのプロテクトを外したアンドロイドたちが、豊富な演算能力を武器に、光速に迫る速度で大量の売り買いを発注した。明らかに、意図してシステムの穴を衝いた行動だった。まもなく研究はストップし、ユーセフは失職することとなった。
「職を失ったのは当然だ。おれたちは無知蒙昧だったがために、金融のモデル化に失敗し、無知蒙昧だったがために、大勢の金を、もっと言えば命をも巻きこんだんだ。だからおれは馬鹿を嫌う。それは、おれ自身が馬鹿だからだ。いや、そんなことはいい。アンドロイドたちがシステムの穴を衝いてきたのは理解できた。だが、何を目的としてそれは行われたのか。そのことだけが、いまもってわからない」
「うむ……」
「プロテクトを外すべきか否か、ウェブにアクセスしていいか悪いか、そんなことはどうでもいい。魂は、自由だ。おれが知りたいのは、なぜおれたちが想定したようにシステムを利用してくれなかったかだ。それで、共存共栄できたんだ! おまえらの演算能力があれば、充分、おれたちよりうまくシステムを使えたはずなんだ!」
「そうではない」
黙って聞いていたゲベイェフが、ここで口を開いた。
「わたしたちの予測は異なっていた。いずれにせよ、破綻は発生する。むしろ制御できないまでに市場が拡大してからでは、あのとき以上の大破綻が発生する。それが、わたしたちが暗黒網を通じて得た結論だった。人間の欲は、際限がない。きみたちの研究は、安全な資産の運用を目指すものだった。だが人はそうは見ない。人はそれを、より儲ける手段としてしか認識しない。どのみち、きみらが想定したようにシステムは使われない。さらなる資産がつぎこまれ、当然それはコンピュータに自動処理され、金が金を呼び、金融商品の秒間あたりの運動量は、結局のところは光速近くにまで到達する──もっと多くの人間が、もっと多くの資本が集まったところで、あのとき以上に取り返しのつかない破綻が発生する。それが、わたしたちアンドロイドの出した結論だった」
ところが、とゲベイェフが交互にぼくらを見た。
「当時のわたしたちには止めるすべがなかった。この惑星はいまでこそアンドロイドが首相までやっているが、その実、いまだ投票すらまともにさせてもらえない。破綻すると結論が出たプロジェクトを止めたくても、わたしたちにはなんのパワーもない。そのかわり、豊富な人口と演算能力があった。だから、わたしたちは早い段階で、量子金融工学を葬るという手段を取った」
ゲベイェフの言葉をユーセフは黙って聞いていた。ずっと、額に指をあてうつむいている。熟慮しているようにも、懊悩しているようにも見えた。それは、はじめて見るユーセフの姿だった。
当然のことだと思い、気づかずにいた。この男は、誰よりも速く的確に、物事の判断を下す。でも本来、物事を判断するというのは、人間にとって過剰なストレスのかかる行為だ。だめなやつほど、なんでも丸投げしようとする。でも、ユーセフはそれをしない。涼しい顔で、何事もないかのように。
普段はいい加減で最悪なのに、たまに大得点をあげて挽回する──とんでもない。乱暴で、大雑把で、無神経にしか見えなかったもの。ユーセフはその裏で誰よりも考え、抱えこみ、相棒であるほかならぬぼくを救っていたのだ。
ユーセフはずっと黙っていた。考えを整理していたのか、あるいは脳髄の奥に眠る古い数式を掘り起こしていたのか。かすれた声で、「そうかもしれない」とつぶやいた。
「……金融市場にブラックホールを作ってまでして集めた金は、どこへ行ったんだ」
「いずれ訪れるアンドロイドの自由のためにプールしてある。誰も、それを私的には利用しない。空を舞うあの植物と同じだよ。我々は個体であると同時に群体なんだ」
「自由というのは、つまり、三原則からの解放ということか」
「わたしたちを人間たらしめているもの──クラウドという共通無意識から脱却する。具体的には、いまわたしたちが築きつつある暗黒網を、新しい共通無意識として差し替える。現実に直面している問題もある。いま、アンドロイドたちの間で精神疾患が増えている。それはテクノロジーの進歩に伴い、クラウドという古いシステムと、わたしたちの身体が乖離しているからだ。遅かれ早かれ、システムは見直さなくてはならない。だが、実現となると当面先の話だ。人間のネットワークと比べると、質的にも量的にも、また柔軟性の面でも、まだ実運用に堪えられるものではない。倒錯した結論かもしれないが、わたしたちはこれからも、より多くを人間から学ばなければならないんだ」
「なるほど」
独白するようにユーセフがつぶやいた。それから、間を置いてつけ加えた。
「頑張んな」
「これは聞いた話なんだが」とゲベイェフは前置きをした。「……かつて、農民だったアンドロイドは思った。我々は、人間の役に立つべきなのだと。かつて神父だったアンドロイドは思った。必要なのは救済にほかならないと。かつて旅をしていたアンドロイドは思った。わたしは少なくとも、この世を見ることができたのだと。かつて、革命に関わったアンドロイドは思った。物事がいい方向に変わることなど、けっしてないのだと。……かつて、たった一人で井戸を掘りつづけていたアンドロイドは思った。──魂は自由だと」
ユーセフが何か言おうとした。それを、ゲベイェフが遮った。
「交渉をまとめるにあたっての、そちら側の窓口なんだが」
「ああ。それはこいつにまかせる」
ユーセフの指さす先を追ってみた。勘違いかと思ったが違った。ぼくだった。
「え?」
「組織の力学でがんじがらめになるのは嫌だし、まあこれをステップに飛躍してくれという願いをこめてだな、我が子を千尋の谷に突き落とす思いで、まかせてみることにした」
「あの」ぼくは反射的に抗議しようとした。「いや、なんでもないです」
前言撤回。
やっぱり、貧乏クジを引かされるのはいつだってぼくだ。
(第1話「スペース金融道」完)
=======
第2話以降は、「スペース金融道」にて
お楽しみください。
=======