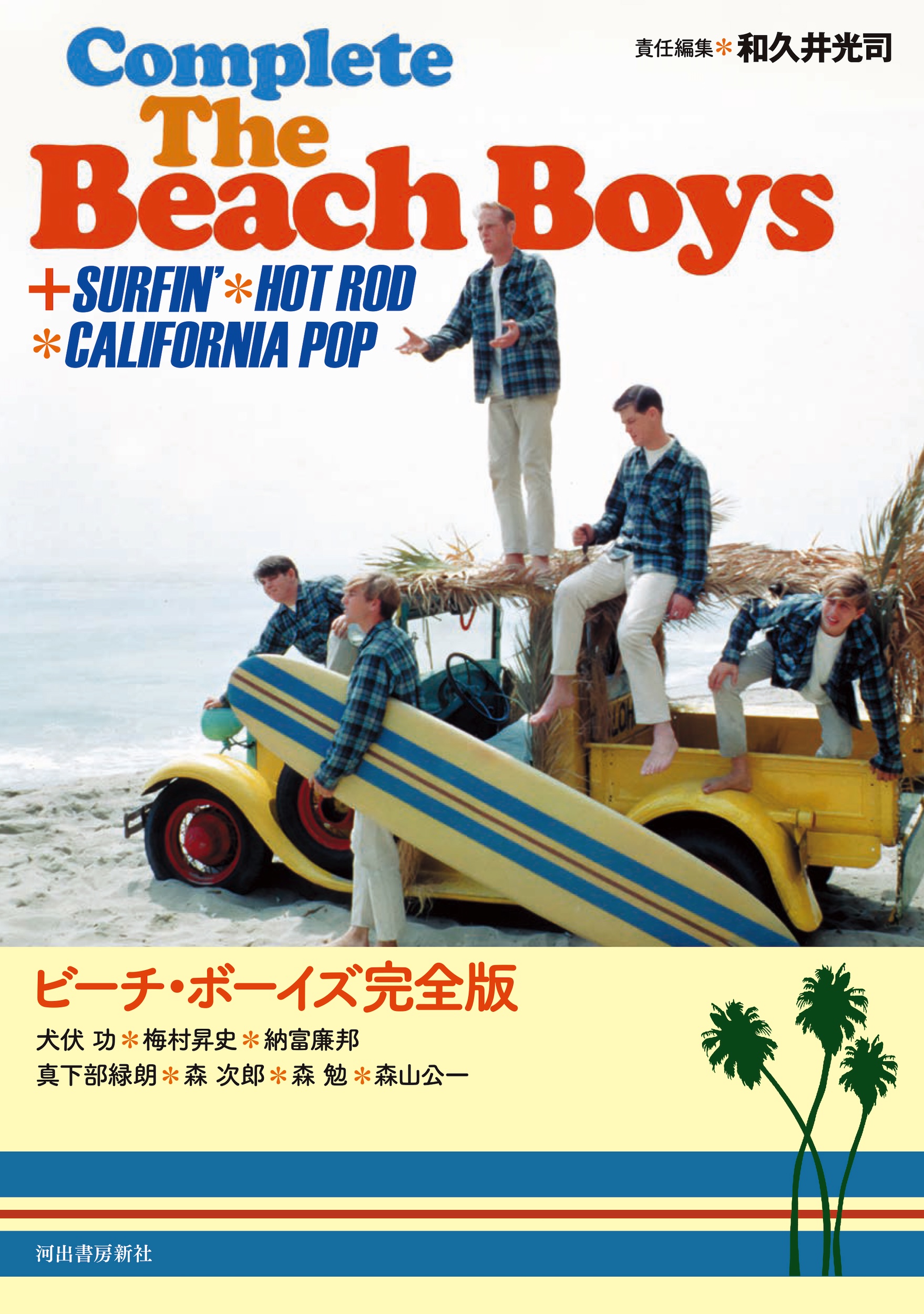ためし読み - 文庫
ガザ虐殺を問うための緊急出版 イスラエル/パレスチナでは何が起きているのか?(1) 『見ることの塩(上・下)』(河出文庫)一部ためし読み
四方田犬彦
2024.04.03
2023年10月7日、ハマスの越境作戦を契機に、イスラエル軍による大規模な復讐戦が展開しました。戦闘開始から半年が経過した今でも、日々痛ましいニュースが届けられ、第二次世界大戦以降の統治体制、宗教や民族の対立など、さまざまな要因が語られています。
この世界史的な悲劇にたいして、小社では四方田犬彦『見ることの塩』を河出文庫から緊急出版しました。本書の前半部は、2004年にイスラエルのテルアヴィヴへ、そして「壁」を越えヨルダン川西岸パレスチナへ、街を歩き、この土地に暮らす人々と対話を重ねた半年間の旅の記録です。
いま、パレスチナ/イスラエルではなにが起きているのでしょうか ―― 本書の冒頭を4回に渡って特別公開します。
===試し読みはこちら===
「見ることの塩(上・下)」
四方田犬彦
テルアヴィヴへの到着(1)
イスラエルはすでにドゴール空港を出発するときから始まっていた。
ベン・グリオン空港へと向かうエール・フランス機に乗るため、2時間前に空港に到着すると、この便に乗る乗客たちだけが隔離され、他から離れた地下のチェッキング・カウンターのところに連れていかれた。ここですべての荷物がX線で調べられた。搭乗券を受け取って控え室に向かうと、もう一度荷物の検査があった。搭乗時間となっていよいよ飛行機に乗り込むという直前に、さらに三度目の荷物検査があり、スタッフの黒人女性から荷物の内容と出自について細かな質問を受けた。すべてはセキュリティ、つまり安全のためだと説明された。この言葉はその後、イスラエルでは何かにつけ聞かされることになった。機内に危険物、爆発物が持ち込まれることに対し、イスラエル人は病的なまでに警戒心を示していた。彼女はわたしがパスポートを見せただけでは納得しなかった。そこでわたしはわざわざ鞄を開いて、招聘先の大学からの書類を提示し、自分の旅の目的について説明をしなければならなかった。いよいよイスラエルに向かうのだ。成立以来、恒常的に戦争状態にある国に向かうのだという実感がしてきた。
長い間わたしは、てっきりこの検査員はフランス側が準備したスタッフだとばかり、思いこんでいた。後になって知ったのだが、彼女はどうやらイスラエル国防軍から派遣されてきた特別担当官だった。彼女はなるほど黒い肌をしていたが、それでもユダヤ人なのであった。近年になってエチオピアから大量に渡来することになった、シバの女王の裔を自称するユダヤ人だったのである。こうしてわたしは、パリからベン・グリオン空港までの飛行に身を任せることになった。
イスラエルに行ってみたい。あの国に滞在して、そこで起きていることを目の当たりにしてみたい。わたしがこうした計画を口にしたとき、周囲の友人知人の反応はほとんどが否定的なものだった。
そんな危険な国にいって爆弾騒ぎに巻きこまれ、大怪我をしたり、爆死してしまったらどうするのだという意見が、まずあった。ユダヤ人が築きあげたシオニズム国家に滞在することは、あの国の体制を認めてしまうことではないか。帰国した後にきみは、親イスラエル派と誤解されてしまうぞ、という声もあった。映画史家としてきみは、アメリカやイタリアで映画の勉強をしてきたというのに、なんでまた学問の専攻とは何の関係もないイスラエルになど興味をもとうとするのか。そもそもあんな中近東の国に映画などあるのだろうか。そして外務省はもうかなり長い期間にわたって、日本人がこの国に渡航することを自粛するよう勧告していた。
こうした感想を聞きながら、わたしは今から26年前、まだ軍事独裁政権下の韓国に語学教師として赴こうと決意したときの、周囲の反応を思い出していた。あのときも人々は、韓国のように貧しく危険な国に行って何になるのだといった態度を、わたしに向かって隠そうとしなかった。あんな反日的な国に日本人が行って、どんな目に遇うか考えたことがあるのかと、面と向かって忠告してくれた者もいた。今となっては信じられないことだが、一度「南朝鮮」に渡ってしまうともう「北朝鮮」に渡航できなくなってしまうぞと、親切に助言してくれた者さえいた。
わたしがソウルに滞在している間に大統領が暗殺され、韓国全土にわたって非常戒厳令が発令された。大学は長く閉鎖され、集会も夜の外出も禁止された。だがわたしは個人的な次元で危険を感じたことは、一度もなかった。戒厳令のもとでも韓国人は冷静であり、落ち着いた日常生活を送っていた。わたしは日本人ということで親切にされることはあっても、脅威や恐怖とは無縁の生活を送っていた。皮肉なことにわたしがもっとも大きな違和感に襲われたのは、帰国後に不在時の日本の新聞を纏めて読んだときだった。そこには最大級に誇張された表現で、戒厳令下の異常事態の報道がなされていた。
こうした政治的、軍事的事件の情報ばかりを部分的に与えられてきた日本人が、韓国を危険な国だと認識してしまうのは、ある意味で仕方のないことである。まして70年代の日本人は、韓国でどのような映画が製作され、どのような音楽が歌われているのかも、皆目知らされていなかったのだから。帰国したわたしは映画批評家として、まず韓国映画の紹介に携わることになった。
2004年のイスラエルについても、状況はほとんど同じだった。日本のメディアにこの国が登場するとき、そこで語られるのはきまって「自爆テロ」による死傷者の数であり、イスラエル国防軍がパレスチナの西岸やガザで行なった虐殺と破壊の映像だった。イスラエル人たちが具体的にどのようなものを食べ、どのような音楽を聴き、どのような日常を送っているかを知っている者は、わたしの周囲にはいなかった。戦争はいけないことだと、誰もが口にした。だがパレスチナ人とイスラエル人の錯綜した物語について充分な知識をもっている者は皆無だったし、多くの者は正統的なユダヤ教とシオニズムが歴史的に対立してきたという事実さえ知らなかった。かくいうわたしも例外ではなく、自分が赴こうとしている国では、支配者であるユダヤ人と悲惨な犠牲者であるパレスチナ人によって、きれいな形で二項対立が構成されているものだと漠然と信じているだけで、それ以上のことは知らなかった。わたしを含めて、日本人たちはイスラエルをめぐって恐るべき無知と無関心のなかにあったのであり、それをけっして反ユダヤ主義の名のもとに一般化する気持ちはないが、そこには未知の社会に対する閉鎖的でステレオタイプな映像に満ちた認識が感じられた。この状況には、かつてわたしが韓国をめぐって周囲の日本人から受け取った言葉に、きわめて近いものが横たわっていた。
だが日本人とは別に、わたしは思いも寄らない側から、イスラエル渡航をめぐって、批判的な反応を受け取ることになった。個人的に長いつきあいのあった、ユダヤ系の友人たちからである。わたしの西欧人の友人のうち、3分の1までが何らかの意味でユダヤの血を引いている人間だった。彼らはわたしにむかって、別にそれを隠そうともしなかった。ある友人などは、「四方田さん、あなたのモノの考え方は実にユダヤ的だ。ひょっとしてご先祖にユダヤの血が混じっていることはありませんか」と冗談口を叩いて、お互いに笑い合うという仲であった。ひとたび自己否定の考え方に取り憑かれてしまったとき、人は血統や出自に関係なくユダヤ人と化してしまうものですよと説く知人もいた。だが一度わたしがイスラエルに行こうと思っていると宣言したとき、彼らの何人かは、冷ややかな感想を述べた。
あるオーストラリア人は、自分の前で二度とイスラエルという言葉を口にしないでほしい、あんな強制収容所のような国家はユダヤ人とは何の関係もないとまでいった。別のアメリカ人は、イスラエルがパレスチナ人を追放して成立したおかげで、ユダヤ人はまたしても歴史のなかで賤民の位置に引き戻されてしまったと語った。イスラエルに向かう途中で立ち寄ったパリでは古い友人から、イスラエルを面と向かって非難こそしなかったが、いつもそんな危険な場所にばかり行きたがる人をアンドレ・マルロー・コンプレックスというのよと、かなり距離を置いた感想を告げられた。ユダヤ系の西欧人にとってイスラエルを話題にすることは、きわめて微妙なことだった。そこには若い在日韓国人の前で北朝鮮の話をすることにいくぶん近いものがあるだろうかと、わたしは考えてみた。だが軽率な比較はできなかった。ある者には気楽な決断に思えたことが、別のある人間にとっては深刻で忌まわしい記憶の再現にほかならないというイデオロギー的状況が、ここでもわれわれを捉えていたのである。そしてこの状況は、わたしのイスラエルへの関心を掻き立てることになった。有体にいって、ここまで人に嫌われる国というものを、一度観ておきたいという強い気持ちに駆られたのである。
躊躇しているわたしにむかってイスラエル行を強く勧めたのは、山口淑子だった。かつて李香蘭と呼ばれたこの大女優は、1970年代初頭にイスラエルとレバノンのパレスチナ難民キャンプを訪れ、TVドキュメンタリーを遺していた。イスラエルに到着して何日も夕陽を見つめているうちに、自分が満洲国にいた頃を思い出してしまったと、彼女はわたしにいった。イスラエルを満洲に比較するという大胆な発想に、わたしは一瞬驚いたが、建国に至るまでの歴史的経緯を考えると、それはあながち荒唐無稽なだけではないように思われた。山口淑子は幼少時より、日本人が一等国民で、中国人が二等国民であるこの虚偽の帝国の現実を見知っていたのである。アラファトさんは「今度はガザで会おう」といってくれたのですよと、彼女はわたしにいった。
さらにわたしは、自分が赴こうとする場所に出自をもつ、2人の人物を個人的に知っていて、彼らから強い印象を受けていた。1人は比較文学者のエドワード・W・サイードで、1987年にコロンビア大学に滞在していたわたしは彼の授業に参加していた。サイードは教室ではもっぱらアウエルバッハやニーチェといった西欧の哲学者や文学者について語るばかりで、出自であるパレスチナのことに言及することをあえてみずからに禁じている素振が窺えた。だが彼が著わした何冊かの書物を通して、わたしはこの亡命中の碩学がいかなる個人的な代価を払って「オリエンタリズム」なる概念を築きあげることになったかを理解することができた。白血病を患ったサイードが半世紀ぶりに故郷エルサレムを訪れたさいに記したエッセイ集を、わたしは彼への深い敬意から日本語に翻訳していた。
わたしが知っていたもうひとりの人物は、イスラエルの映画監督のアモス・ギタイだった。
ギタイとは東京で開催された彼のフィルムの回顧上映のさいに出会っていた。ユダヤ人とアラブ人の闘いは終わりのない連続アクション劇のようなもので、善玉が翻って悪玉となり、悪玉が善玉になるという具合に、もう半世紀以上も続いている。どちらもが疲労困憊しきっているのだが、解決は不可能に近いと、彼は語った。ギタイのドキュメンタリーのなかでは、パレスチナ人の漁師とルーマニア系ユダヤ人との夫婦が、貧困と孤立のなかで生き抜き、ついに挫折して離婚してしまうまでの過程が、20年以上にわたる追跡を通して描かれていた。大島渚に深い共感を寄せるギタイのなかに、わたしはイスラエルと呼ばれる困難な問題を批判的に背負って生きていこうとする芸術家の姿を見てとったような印象をもった。サイードとギタイという、この2人の人物を導きの糸として、わたしはイスラエルの地に足を踏み入れようと決意したのである。
渡航の前にわたしに一抹の不安がなかったというならば、それは噓になるだろう。なるほどわたしは韓国滞在のときの経験から、死者の数字しか報道しようとしない日本のメディアからははるかにかけ離れたところに、真の現実が横たわっているだろうという見当だけは、直感的につけていた。テルアヴィヴでも、エルサレムでも、人は爆弾の恐怖だけを胸中にしながら生きているわけではないに決まっている。彼らは彼らなりに生活を享受しているであろうし、危険を回避する手立てを体験的に取得しているにちがいない。またパレスチナはパレスチナで、現下の屈辱と恐怖に対し、忍耐強い戦略を抱いているはずだ。それを間近に見据えてみたいという気持ちが、わたしにはあった。しかしわたしの心配は別のところにあった。
わたしがテルアヴィヴの街角を歩いていて、運悪くハマスの仕掛けた爆弾に出くわしてしまうことはありうるだろう。1972年の新宿を知っているわたしは、いつも通っていた映画館街の角の交番があるとき爆破され、無残な残骸を曝している現場に居合わせたことがあった。それは不可抗力である。だがもしわたしが偶然にも被爆して重傷を負ったとしたら、日本のメディアはたちまちわたしを格好の餌食とすることだろう。わたしは無垢な犠牲者の役を宛がわれるか、でなければ周囲の制止を振り切ってわざわざ危険な場所に向かった無謀な人間として、世間を騒がせ迷惑をかけたことを糾弾されるだろう。TVマイクを突きつけられたわたしに許されるのは「テロリスト」を非難し、「平和」を訴えることであり、たとえわたしがイスラエルで見聞した実感を微妙な陰影のもとに話したとしても、それは粗雑な形で要約され、多くの誤解を招くだけだろう。
わたしのこの心配は、4月にヨルダンからイラクに向かった3人の日本人が運悪く人質となり、釈放され帰国した後も、日本のメディアから社会的なリンチを受けたと知ったときにより強くなった。彼らが4月6日の時点でアンマンの安宿に集まり、計画を練っていたとき、わたしは偶然にもそこから200メートルほどしか離れていない、別の安宿にいた。そして人質となった最年少の日本人は、わたしの学生の友人であった。彼らが帰国後に受けた受難を想像すると、眩暈のような感覚に襲われた。イラクとイスラエルの区別もつかない日本のTV視聴者の前で、もし自分が「世間」を騒がせたことの弁明をしなければならないかと考えると、わたしは日本社会に眼に見えない形で横たわっているソフト・ファシズムに、身の毛がよだつ思いがした。
ともあれ気に病んでいても仕方がない。韓国のときもそうであったが、あまりに深刻に思いつめて現実にその土地に行く機会を逸してしまうインテリという人種を、わたしはいたるところで目にしてきた。わたしはもうこれ以上心配などしまいと決意して、飛行機の予約をとった。三月中旬、パリに立ち寄って資料を蒐集した後、イスラエルのベン・グリオン空港にむけて出発することにしたのである。
(つづく)