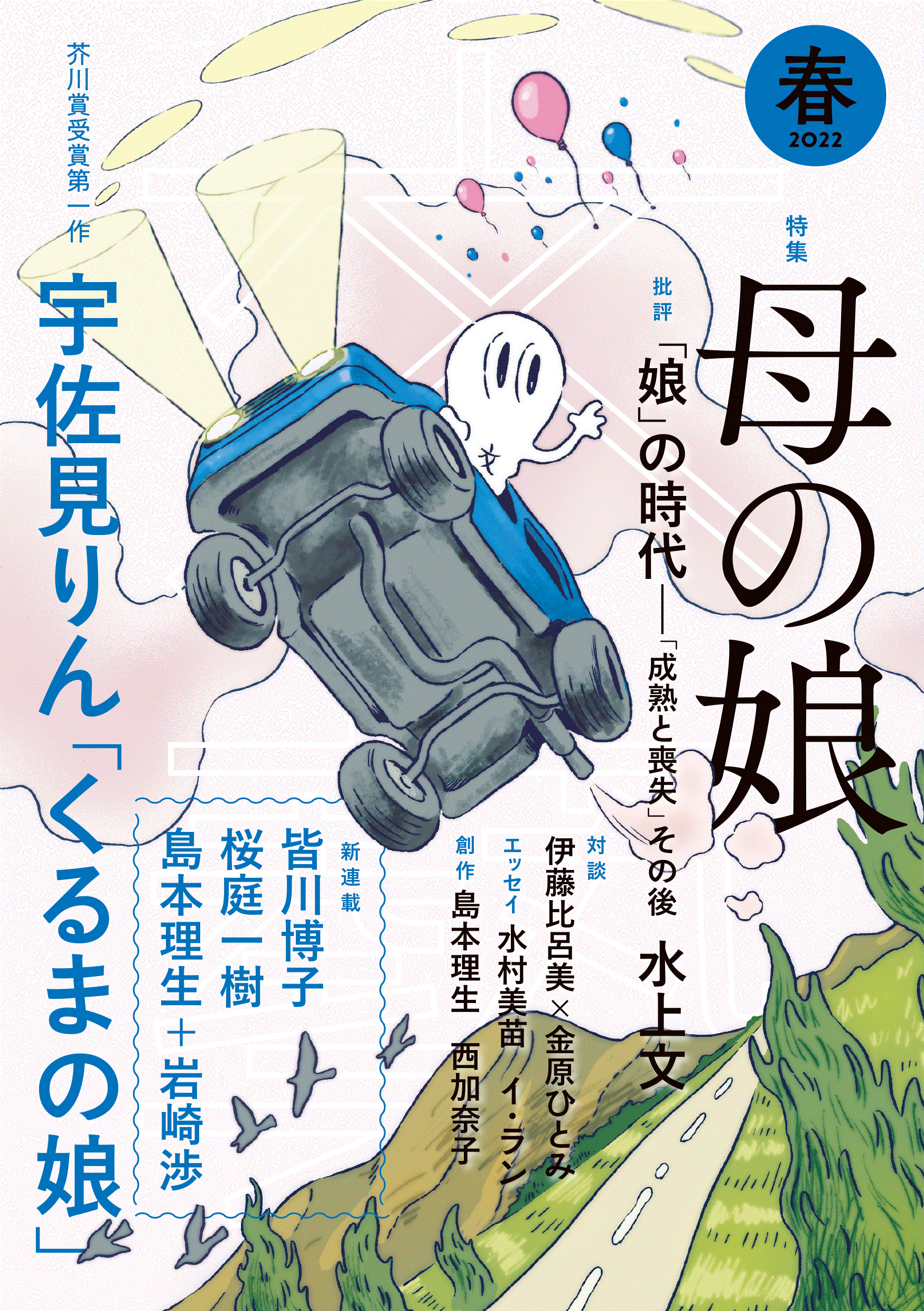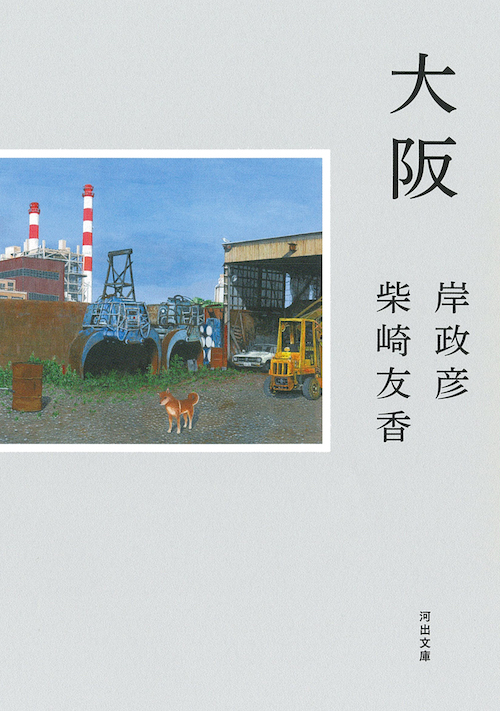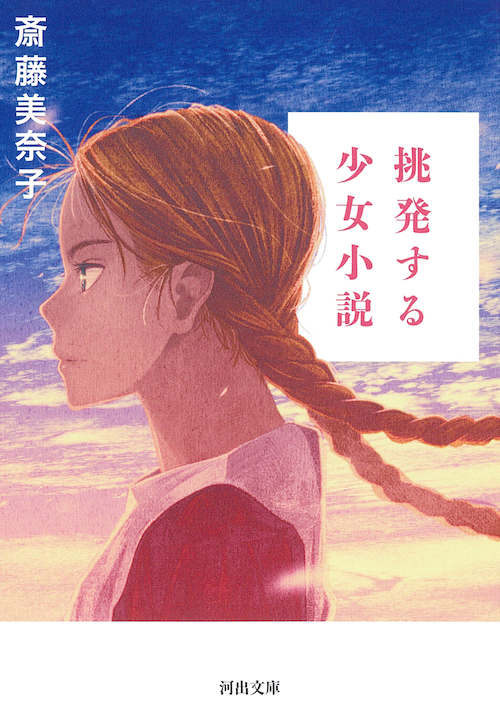単行本 - 文藝
★まるごと1話試し読み★「5分シリーズ」第2弾発売記念!3日連続試し読み公開vol.1『5分後に感動のラスト』収録「ぼくが欲しかったもの。」
エブリスタ
2017.07.24

いよいよ「5分シリーズ」第2弾が発売!
エブリスタと河出書房新社が贈る短編小説シリーズ(特設サイトはこちら)。
投稿作品累計200万作品、コンテスト応募総数25000作品以上から厳選された短編は、すぐ読める短さなのに、衝撃的に面白いものばかりです。
第2弾発売を記念して、3日連続で試し読みを公開します!
あなたも5分で衝撃を受けてください。
『5分後に感動のラスト』(5分シリーズ)より、まるごと1話試し読み!
「あたたかな家庭」を夢見ていたぼく。その夢が叶わないと知った時、見えてきたものとは…。
* * * * *
「ぼくが欲しかったもの。」 川崎かなれ
幼いころから、ずっと家のなかにひとりぼっちだった。
両親はつねに忙しく、家族でどこかに出かけた記憶もない。
だから、いつだってやさしい声で「おかえり」って出迎えてもらえる、そんな暮らしを送りたいと思った。
専業主婦の奥さんとのあいだに子どもを授かって、あたたかな家庭をつくる。
そのことだけを夢見て、ぼくは生きてきた。
「こういうことはね、結婚前にきちんとしておくべきなのよ」
母の苦言に、俄(にわか)に眉を顰(ひそ)める。
社会人になって三年目の夏。上司に勧められたお見合いの席で、運よく良縁(りょうえん)に恵まれることができた。専業主婦を希望する彼女とのあいだで話はとんとん拍子(びょうし)に進み、冬には式を挙げることになった。
「いまは昔と違って、結婚前にブライダルチェックをするのが常識なのよ」
頑(かたく)なに主張する母を疎(うと)ましく思いながらも、根負けして検査を受けることを決めた。彼女だけに受けさせるのは失礼に当たる。そう思い、自分もいっしょに受診した。
軽い気持ちで受けた検査だったけれど、『問題ありませんよ』といわれた彼女が心底ホッとした顔をするのを見たとき、無性に愛しさが込みあげてきた。
彼女とともにあたたかな家庭をつくれるのだと思うと、うれしくてたまらなかった。
だから、その次の瞬間いわれた言葉に、ぼくはしばらくのあいだ、なんの反応も示すことができなかった。
『非閉塞(へいそく)性無精子症』
生まれてはじめて聞くその病名が、彼女との婚約を一瞬にして白紙に戻してしまった。
あれから一週間。睡眠不足がつづき、仕事でミスを連発しつづけた。
これ以上、周囲に迷惑をかけるわけにはいかない。就職以来はじめて、ぼくは有給休暇をとった。
休みをとったものの、することなんか何もない。いままでのぼくの人生は、『あたたかな家庭』を手に入れるためだけに存在していたのだ。
高校入試も、大学入試も、公務員試験も。そのためだけに、ひたすら頑張りつづけてきた。
それなのに──。
母に気遣われるのがいたたまれなくて、とりあえず家の外に出てみた。
出たところで、行く場所なんてない。気づけば出勤時と同じように最寄り駅に向かっていた。
通勤時にはシャッターの下りている商店街が、どの店も営業をしている。八百屋に花屋、肉屋にパン屋、なんだかすこし新鮮だ。
クリーニング屋の脇に、ちいさな煙草屋がある。ぼくが子どものころから、ずっとやっている店だ。
「煙草なんて、吸おうと思ったこともないけどな」
よい父親になるには、いつかやめなくてはならない日がくる。それなら最初から吸わないほうがいいと、ずっとそう思っていた。
もう、そんなふうに思う必要もないのだ。そう思うと、自然と足がその店に向かった。
父が吸っているのと同じ銘柄(めいがら)の煙草とライターを買って、パッケージから一本取りだして咥(くわ)えてみる。
火のつけ方がわからずしばらく苦戦して、ようやく点いたと思ったら、思いっきりむせた。
「っ──」
苦しさに涙目になりながら、煙草を店の前の灰皿に押しつける。
慣れないことはするもんじゃない。そう思い、残りの煙草をスーパーの隣の公園で眠るホームレスの足元にそっと置いた。
ふたたび駅へと向かう道を歩く。家を出て三つ目の信号で、いつも引っかかる。きょうも同じように引っかかって、『あの店』から香ばしい匂いが漂ってきた。
自家焙煎(ばいせん)の看板を掲げた、ちいさな珈琲(コーヒー)店。喫茶店でもカフェでもない、すこし入りづらそうな店構えの店だ。
いつもすこしだけ気になって、けれども立ち寄る余裕なんてなかった。
誰よりもはやく結婚したかったし、子どもを持ちたかった。マイホームの頭金をつくるため、できるかぎり無駄なお金は使いたくなかったのだ。
「高いんだろうな」
コンビニのペットボトルのお茶すら買うのをためらい、水筒にお茶を詰めて持ち歩くぼくには、一杯の珈琲に何百円もかけるひとの気持ちが、正直よくわからない。
よくわからない、けれど……。たぶん、ずっと気になっていたのだ。そんな対価を支払ってもいいと思えるほどおいしい飲み物が世の中にはあるのだろうかと。
香りにつられるように、その店の引き戸を開ける。
珍しいつくりの店だ。古い民家を改築したのだろう。すりガラスに覆われた引き戸の先に、カウンター席だけのちいさな店が広がっている。
「いらっしゃい」
ちいさく流れるジャズピアノの音色。カウンターのなかの店主がしわがれた声でいう。
白髪頭に無精ひげを蓄えた六十代半ばと思しき男性だ。着古したダンガリーシャツに、ゆったりとしたシルエットのペインターパンツ。老眼鏡だろうか。セルフレームの眼鏡をずらし気味にかけている。
店内には、ほかに誰もお客さんがいなかった。モーニングにはすこし遅いし、ランチにはまだ早い。中途半端な時間のせいだろう。
「いい香りですね」
店内を満たす、深みのある珈琲の薫り。店の外で香ったとき以上に、こっくりした甘さを感じる。
「珈琲が好きかい」
「いえ、ゆっくり味わう暇もなくて。いつか余裕ができたら、嗜(たしな)みたいと思っていました」
どんなものを飲んだらいいのかわからないのだと、ぼくは正直に告げた。
「いくつか淹(い)れてあげよう。飲みくらべてみるといい」
店主はそういって、わざわざ三種類の豆を挽(ひ)き、一杯ずつ丁寧にドリップしてくれた。
彼の淹れてくれた珈琲は、とてもやわらかな香りがした。
どう表現したらいいのだろう。いままでに嗅いだことのない香りだ。香ばしくて、なめらかで、包み込むようなやさしさに溢れている。
ネルのなかで、ハンバーグのようにまぁるく膨らむ珈琲粉。琥珀(こはく)色の澄んだ珈琲液が落とされるさまは、まるで手品でも眺めているようで胸が躍る。
「珈琲って、こんなふうに淹れるんですね」
「ああ、ネルは手入れが面倒だし、最近は減ってきているみたいだがね」
ペーパーフィルターやプレスで淹れるより、まろやかな味わいに仕上がるのだという。
「注文が入るたびに、毎回豆を挽くんですか」
「挽いたそばから劣化しちまうからね。その都度挽いたほうが、香りも味もずっといいんだ。胡椒(こしょう)だってそうだろう。瓶詰(びんづめ)のパウダーより、自分でガリガリやる粗挽きのホールタイプのほうが、ずっと旨い」
カウンターの上の胡椒ミルを指さし、店主はいった。
費用対効果、とか。お客さんが重なったときはどうするのか、とか。こういった店でそういうことを口にするのは、野暮なことなのだろう。
「いただきます」
カップにすこしずつ淹れられた珈琲。深々と頭を下げ、そのうちのひとつを口に運ぶ。ひとつめのカップは、驚くほどさらっとした味がした。
「ん……」
珈琲といえば、苦くてどっしりとした味わいのものだと思っていた。そんなぼくの予想を裏切る軽やかな味だ。すっきりしていて、爽やかささえ感じさせる。
「珈琲豆ってのは、もともとは『果実の種』だからね。フルーティな味わいのものもあるんだよ」
豆の種類や精製方法、焙煎の加減、淹れ方によって、さまざまな味わいが生まれるのだという。
「飲みやすくて、とてもおいしいです」
語彙(ごい)の少なさが申し訳ないが、正直に思った通りの言葉を告げた。
「ほかのも、飲んでごらん」
促され、今度は真ん中のカップを手にする。とろんとした琥珀色の液体は、さきほどのものより芳醇(ほうじゅん)な香りを漂わせている。ひとくち含むと、マイルドなやさしさが口いっぱいに広がった。
「これは……」
チョコレート。そうだ。チョコレートを食べたときのような、とろりとした舌触りだ。どっしりとした味わいに、かすかな甘みを感じさせる。
「チョコみたい、ですね」
健康にいいといって母が買ってきた、高カカオチョコレートの味わいに似ている。
「後味がね、似ているよ。舌のうえに甘みがかすかに残る感じで」
珈琲のプロも、『チョコレートのような』とか、『ワインのような』とか、味や香りを既存の食品になぞらえて表現することがあるそうだ。
「どっしりとしていて、チョコレートよりずっと後に残るだろう」
彼のいうとおり、飲み終えたあとも、その後味はなかなか消えることがない。さっきのフレッシュな珈琲と、同じ飲み物とは思えないほど違いがあるように感じられた。
「最後のこれは……」
色味からして、すこし濃い焦げ茶色をしている。とろんと濃厚なそれは、かすかな苦みとつよい酸味を感じさせる、三つのなかでいちばん大人っぽい味のする珈琲だった。
ぼくが思い描いていた珈琲の味に、とても近い。
ずしりとくるのに、その苦みや酸味が、けっしていやな感じではなく、じわりと胸に沁みこむような絶妙な重さだ。
ひとくち飲み終えたあと、しばらくその余韻(よいん)を楽しむと、また飲みたいと感じる。苦みがあるとわかっているのに、それでも求めずにはいられないのだ。
「それがいちばん気に入ったようだね」
まだなにもいっていないのに。店主はぼくを見て、やんわりとおだやかな笑みを浮かべた。
「そう……ですね。どれもおいしいですが、いまのぼくには、これですね」
ほろ苦くて、重くて、それなのに飲まずにはいられないなんて。なんだかとても、不思議な感じだ。
あっというまに空っぽになったカップに、ふたたび珈琲が注がれる。
「気に入ってもらえてよかったよ」
彼はそういうと、残りのふたつのサーバーをカウンターから下ろした。
「あの、残りは……」
「ああ、気にする必要はない。珈琲ゼリーにするからね」
ドリップした珈琲でつくったゼリーが、お店の看板メニューなのだという。
「このお店、おひとりでされているのですか」
店の外には『ランチ』という張り紙が貼られていた。たったひとりで、店を切り盛りしているのだろうか。
「ああ、ひとりモンだからね。バイトを雇うほど潤っちゃいないし。──私が死んだら、終(しま)いだ」
「す、すみませんっ……」
余計なことをいってしまった。慌てて頭を下げたぼくに、彼はおだやかな笑みを向ける。
「悪いなんて、思う必要はないよ。みずから望んで、そういう生き方をしてきた。それを、不幸だと思ったことは一度もないんだ」
「一度も、ご結婚されたことがないんですか」
おそるおそる尋ねると、彼はなんでもないことのように頷(うなず)いた。
「ないよ」
「寂しく、ないですか」
思わずそう呟いたぼくに、彼は静かな声音でいう。
「どんな生き方をしたって、最後はひとりだよ。ゲームとは違う。たくさん子どもをつくったから安心、とか、たくさんお金をあつめたから、しあわせ、とか、そんな単純なモンでもないだろう」
子ども。
いま、いちばん耳にしたくない言葉だ。
涙腺(るいせん)が緩んでしまいそうになって、ギュッと唇を噛みしめる。カップを握りしめて俯いたそのとき、引き戸をひらく音が響いた。
「いっやー、もう最悪。マスターの珈琲飲まなくちゃ、やってらんないよ」
短く整えられた髪、浅黒く焼けた肌。いかにも営業職ふうの背広姿の男が入ってくる。
ぼくと同い年くらいだろうか。慣れたようすでカウンターの一角を陣取ると、「おひやちょうだい」と店主に催促する。
「はいよ」
手渡された水を一気に飲み干すと、ぐったりと彼はカウンターに倒れ込んだ。
「なんにする」
「マスターの淹れたモンなら、なんだっていいよ」
なにかいやなことでもあったのだろうか。不機嫌そうな顔をした彼は、愚痴(ぐち)をこぼすでもなく、店主が豆を挽き、珈琲をドリップするようすをじっと眺めている。
「俺さぁ、この、珈琲が膨らむとこ見ると、すっごくしあわせな気分になるんだよね。嫌なモン、全部吹っ飛ぶっていうかさ」
誰にともなく呟く彼の声に、軽やかなピアノの旋律(せんりつ)が重なった。珈琲のふくよかな香りが店内を満たしてゆく。
「はいよ」
「サンキュ」
差し出されたカップを手にし、口に運ぶと、彼の眉間からみるみる皺(しわ)が消えてゆく。
「はぁ……」
満足げなため息を漏らすと、彼はようやくぼくの存在に気づいたかのように、突然話しかけてきた。
「なに、おにいさんもサボり?」
同い年くらいかと思っていたが、もしかしたらすこし年下かもしれない。ニッと笑うその顔だちは、かすかにあどけなさを残している。
「え、ああ、有給です」
「いいねぇ、俺も有給、取ってみてぇわ」
彼はそういうと、自動車メーカーのロゴが記された名刺を差し出してきた。
「営業のお仕事ですか──大変ですね」
ノルマとか、あるのだろうか。ストレスの原因は、そこにあるのかもしれない。
「まあ、でも好きではじめたことだしね」
にっこり微笑むと、彼は自分の所有している車について熱心に語りはじめる。
「お兄さんは、なに乗ってんの」
「え、いや。車は……」
結婚して子どもができたら、ワンボックスカーを買うつもりだった。それまでは一円でも多く貯金をしようと、まだ一度も車を購入したことがない。無言のままうつむいたぼくに、彼は明るい声音でいった。
「欲しくなったら、いつでもいって。いっぱいサービスするからさ。車のある生活ってやっぱりすごくいいよ。ほら、こうやって休みができたときでもさ、ぶらっと海行ったり、いろいろできるしさ」
「ひとりで海に行って、楽しいかな」
「楽しいよ。ま、この町にも海はあるけどさ、ちょっと足を伸ばして逗子(ずし)方面とかね。夏場と違って134も空いてるし。海沿い走るだけで、しあわせな気持ちになれるよ」
海沿いの道を、ひとりでドライブする。
いままでそんなこと、考えたこともなかった。
「夏場はゴミゴミしてるだけでどうしようもないけど、冬に向けて段々きれいになってくるんだ。帰りは富士山も見えるし、晴れた日なんかは特におすすめだよ」
彼の言葉に、店主がぼそりとツッコミを入れる。
「勤務中に抜け出してんな」
「たまにだよ、たまに。そんくらい息抜きないと、やってらんないじゃん」
いい終わるや否や、カウンターの上に置かれた彼のスマートフォンが震えはじめる。くだけた口調から一転、席を立ち、彼はとても丁寧に応対した。
「んじゃ、マスター、ごちそうさん。騒がしくして悪かったね。おにいさんもごゆっくり」
通話を終えると、彼はさっきまでのストレスフルな顔立ちがうそのように、にこやかな笑顔で去ってゆく。その姿を見送る店主の横顔が、なぜだかすこし誇らしげに感じられた。
一杯の珈琲が、誰かをしあわせにする。
ひとりのドライブが、しあわせな気持ちをつくる。
そんなちいさな『しあわせ』も、世の中には存在するのだ。そんなことにすら、ぼくはいままで一度も気づけなかった。
「マスター、訊いてよ。町内会の会長さんがねぇ」
ふたたび引き戸が開き、ご婦人方が連れだって入ってくる。彼女たちがカウンター席にずらりと並ぶと、マスターは注文を受ける前から透明なグラスに載った珈琲ゼリーを差し出した。
琥珀色の澄んだゼリーの上に、たっぷりと純白のミルクがかかっている。思わず見惚れていると、『にいさんも食べるかい』とマスターに声をかけられた。
「ぇ、ぁ……っ、はい、お願いします」
ゼリーを頬張るたびに、彼女たちは満足げなため息を漏らす。
「これがなかったら、今頃、絶対に旦那と離婚してるわ」
「お姑(しゅうとめ)さんになにいわれても、ここに逃げ込んで来ればなんとか我慢できるのよねぇ」
口々にいいあい、頷きあっている。
スプーンですくって口に運ぶと、つるん、と口のなかに入ってゆく。舌の上で蕩(とろ
けるほろ苦い珈琲の味わいと、やさしい甘さのミルク。絶妙に混じり合うそれは、たまらなくしあわせな気持ちにしてくれた。
「おいしいですね、これ」
「でしょう? ここの珈琲ゼリー、絶品なのよ!」
マスターよりも先に、ご婦人たちが誇らしげに胸をそらす。
日々の生活のなかで味わう、ささやかな贅沢(ぜいたく)なのだという。どんなにささくれだった気持ちも、この店の珈琲ゼリーがあれば癒やされるのだと彼女たちは笑った。
「おお、きょうは賑やかだね」
しわがれた声に振りかえると、パジャマ姿の老人が点滴スタンドを手に立っていた。
ちかくの総合病院の入院患者なのだろう。手慣れたようすでカウンターにかけ、老眼鏡をかけてスポーツ新聞を広げる。
ふらっとひとりでやってきて、黙々(もくもく)と珈琲を飲んで帰る気難しそうな初老の男性。先刻の彼のように、外回りの仕事を抜けてきたと思(おぼ)しき会社員。
誰もが珈琲を飲み終え、店を出ていくときには和やかな顔になっている。
マスターに尋ねようと思っていた言葉。訊かなくてもわかる気がした。
きっと彼は、家族がいなくても、ひとりきりでも、この店で皆に感謝されながら、しあわせに暮らしている。
自分にも、そんな居場所をつくることができるのだろうか。
もし仮に、この先の長い人生を、ひとりきりで生きることになるとしても。しあわせだと思える生き方を、することができるのだろうか。
きっと……できるんだろうな、と思う。
だってこんなふうに一杯のおいしい珈琲にさえ、満たされた気持ちになることができるのだ。
「ごちそうさまでした」
ランチ目当ての客で混みあいはじめた店内。ぼくはゆっくりと立ちあがる。
「ああ、またいつでもおいで。珈琲の道は、はまりはじめると、とてつもなく深いよ」
一杯ぶんずつ豆を挽き、ネルドリップで丁寧に淹れられる珈琲。
心の底から珈琲を愛しているのだろう。マスターの横顔は、とても満たされたものに感じられた。
店を出てマナーモードにしてあったスマホを取り出すと、数えきれないくらいたくさんのショートメッセージと着信が残されていた。送り主はすべて母親だ。折りかえし電話をかけると、繋がったそばからヒステリックな声が響く。
「なにか用だった?」
『なにって、あなた、何度かけても電話にでないからっ』
とても心配してくれていたようだ。もしかしたら、自殺でもするんじゃないかって思われていたのかもしれない。
「ごめん、珈琲店に行っていてさ。ほら、スーパーの近くにある。凄くおいしいんだ。よかったら今度、いっしょに行こう」
受話器の向こう側の彼女が、泣き崩れる声がきこえてきた。
ああ、そうだ。──ひとりじゃない。
すくなくともいまの自分には、ちゃんと『家族』がいるのだ。
この先、増えることは、ないかもしれないけれど。それでもたいせつな家族がいる。
「あ、ごめん。父さんからキャッチだ。──すぐにかけ直すよ。ちょっと待ってて」
父から電話がかかってくることなんて、いままで一度だってなかった。わざわざ昼休みに電話をかけてくるなんて、もしかしたら、なにか大変なことがあったのかもしれない。そう思い通話ボタンを押すと、厳(いか)めしい父の声がきこえてきた。
『さっきお前のパソコンにメールを送ったんだが、見たか』
「ごめん。出先だからまだ見てないけど」
『きょうの朝刊にな、非閉塞性無精子症でも人工授精できる手法を確立した医療チームの記事が掲載されているんだ』
従前の方法では精子を採取できない患者の精巣から前期精子細胞を採取し、多数の着床(ちゃくしょう)を成功させているチームがあるのだという。
『その方法なら、お前も自分の子どもを持てる可能性があるかもしれない。それにな、いまは「子どもを望まない者同士の婚活パーティ」だとか、「不妊治療を前提とした婚活パーティ」というのがあるらしくてな。病気を負い目に感じることなく、パートナーを探すことができるらしいんだ』
わざわざそんなことを調べてくれたのだろうか。仕事で忙しく、それこそ普段は一週間以上、口をきかないことだってあるというのに……。
「──ありがとう」
堪(こら)えきれず、涙が溢れてきた。
こんなにも大切に思われていることにさえ、いままで気づくことができなかった。ぼくはいったい、なにをそんなに頑なになっていたんだろう。
珈琲のおいしさとか、家族の想いとか、なんにも気づけないまま、ひたすら前だけを向いて走ってきた。
たまらなく情けないけど。いまからでも間に合うのだろうか。
日々の暮らしのなかにある、ちいさなしあわせや、周囲のやさしさ。それらを掬(すく)い上げながら、生きてゆくことができるだろうか……。
──できるんだろうな、と思う。
まだ人生の折り返し地点にも、たぶん、立ってない。いまならきっと、まだ間に合うはずだ。
「あのさ」
『ん』
「車買おうと思って」
唐突(とうとつ)なぼくの言葉に、父さんは無言のままだ。
そうだろう。だって、あまりにも突飛すぎる。なによりも論理性を重視する父さんには、きっと理解不能な飛躍だ。
「来年は父さんも定年だろ。ずっと忙しそうだったし、旅行とか全然行けなかったし。おっきい車買うから、どこか、みんなでゆっくり温泉でも行こう」
子どものころ、できなかったこと。結婚して子どもができたら、しようと思っていたけれど。だけどいま、それをすることだってできるのだ。
あたらしい家族をつくる前でも、父さんや母さんを、どこかに連れて行ってあげることはできる。
与えてもらうことしか、考えていなかった。
してもらえなかったこと、できなかったことばかり数えていた。
そんな自分が、なんだか無性に恥ずかしくなる。
『──ああ、いいな。行こう、母さんも喜ぶよ』
電話の向こう側。いつも通りのぶっきらぼうな声で、父さんはいった。
「あ、そうだ。母さんと電話してたんだった」
『はやくかけ直してやりなさい』
「──うん」
父に促され、電話を切る。母親と電話が繫がった途端、ふたたびヒステリックな叫び声が耳を劈(つんざ)いた。
口の中には、かすかにまだ、あの店の珈琲のやさしい後味が残っている。普段は疎ましく思うその叫び声さえも、なぜだかとても愛おしく感じられた。
* * * * *
その他の作品は書籍でお楽しみください!
シリーズ詳細はこちらから。
ーー3日連続試し読み公開!ーー
★vol.2 『5分間で心にしみるストーリー』収録「リング」試し読み は7/25(火)公開!
★vol.3 『5分後に後味の悪いラスト』収録「暇つぶし」試し読み は7/26(水)公開!