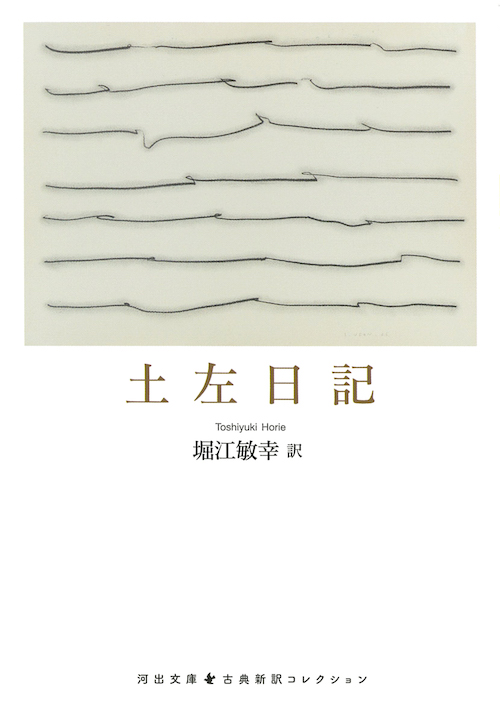単行本 - 日本文学
「文藝」秋季号掲載、長井短「ほどける骨折り球子」試し読み
長井短
2022.07.12
妻の球子(たまこ)は俺を庇って骨折ばかりする。俺も球子を守りたくて夫婦で〝守りバトル〟に没頭するある日、勤め先に俺が会社の金を横領していると電話が入り―。俊才の小説第二作、初中篇。
===↓試し読みはこの↓へ===
ほどける骨折り球子
長井短
球子の骨折が治ったのは結婚記念日の前日で、これで明日はワンピースを着ていけるって球子は喜んでいた。俺としては球子が何を着てたって最高だけど、記念日のディナーはやっぱりおしゃれをしたいもんなんだろう。だったらそもそも俺を庇って骨折なんてやめてほしい。球子の骨折はこれで四回目だった。付き合い始めてから今日までの約二年で四回ってのはいくらなんでも多くないか? と医者に相談したけれど、別に球子の骨自体にはなんの問題もなく、強いて言うなら立て続けに起きた骨折で左肩の骨が他より脆くなっているらしくて「単純に運が悪いと言いますか……」って先生は言いにくそうに球子のっていうか俺たちの不幸に引いていた。そりゃ引くわな。あまりにもすぐ折るもんだから、俺は球子の両親に少し警戒されているし、それを理不尽だとも思わない。だけど本当に、誓って俺は球子を傷つけたりしていない。手を上げるなんて想像しただけで胸糞悪いし、俺は俺なりに球子を守るつもりで結婚している。なのに何故か、俺ばかりが守られる。球子の骨折は全て俺を守ったことによる怪我で、車に轢かれそうになった俺を三回、階段から落ちそうになった俺を一回。俺は呪われているんだろうか。二十七歳で球子と付き合い始めるまで、俺は車に轢かれそうになることなんてなかったし、所謂「危険」みたいなものとは距離をとって生きられていた。なのに、球子と俺の人生が重なり合った途端、俺には危険がつきまとう。不幸もつきまとう。俺の不幸は球子の不幸で、現に俺によってくる危険のせいで球子は何度も骨折しているし、怪我はしなくても例えば、俺が友達と喧嘩して泣いた時、球子も一緒に泣かせてしまったり、俺が頼んだご飯に入ってる虫を見つけて嫌な気持ちにさせたり、とにかく一緒に悲しい思いをさせてしまう。俺は球子を幸せにしたいはずなのに全然そうできなくて、結婚して半年くらいの頃に一度だけ「俺たちって一緒にいない方がいいんじゃないか」と話したことがあった。占いなんて信じないけど、俺と球子はもしかしたらそういうスピリチュアル的な部分での相性が最悪で、一緒にいると破滅してしまうんじゃないかと思ったのだ。半泣きでそれを伝えると、球子は大きく息を吸って俺に言った。
「うるさい! 考えすぎ!!」
だから球子が好きだ。否応なしに俺たちを肯定する球子が好きだ。「幸せにするから」なんてプロポーズをしたけど、幸せにしてくれてるのは俺より球子って感じがする。圧倒的な、球子の光みたいなものが、俺の心も体も守ってくれている。もしかしたら、球子は本当に光っていて、その光に俺は近づきすぎているから危険に巻き込まれるのかもしれない。こんなことを言ったら球子はまた「うるさい!」と俺をるだろうか。
「勇~どっちがいいと思う?」
ギプスが取れたばかりの腕で、黒いワンピースとピンクのワンピースを掲げながら球子がリビングに入ってきた。自由に動けるのが嬉しいのか微妙に揺れていて「こっち、こっち」と呟き続ける少し厚い唇と、ゆったりと繰り返される右、左、って体の傾きは昔おもちゃ屋の店先に置いてあったサンタの人形のようだ。
「うーん、黒かなぁ」
「……ちゃんと考えた?」
「考えたよ」
「ほんとかな?」
探るように俺を見つめてから球子は「じゃあピンクにしよ」と笑った。
記念日だし雰囲気を出そうと、外苑前の路地裏にあるレストランを予約していた。「わんわん物語」が好きな球子のために見つけた店だった。ネットで見た写真の通り、その店は知らないと辿り着けないような住宅街の中にあって「外国みたい!」と球子が笑う。通されたのは庭に面したテーブル席だった。日が沈んだ後に少しだけ残ったオレンジの光が窓から差し込んできて、球子の長い髪を染める。
「今そっくりだよ」
「何に?」
「レディ」
「え、どういうこと? 女みたいってこと?」
「違う違う、ほら。わんわん物語の」
「あ~! あのレディね」
「そう。髪がオレンジで耳みたい」
「ふーん。でも私から見たら、勇の方がレディに似てるよ」
「え、どういうこと?」
「だって私がトランプだもん」
「なんで?」
「勇敢だから」
「おっしゃる通りです……」
「あ、ごめん。勇が弱いとかじゃないよ」
「わかってるわかってる」
わかってる。俺が車に轢かれそうになるのは俺が弱いからじゃないし、球子が道路に飛び出すのも球子が強いからじゃない。ただたまたま、俺たちにそういう局面が訪れているだけだ。そしてたまたま、俺が轢かれそうになる側で、球子が助ける側なだけ。立場が逆になったらいつでも俺は飛び出すけど、どうかこのまま、俺が飛び出す日なんて来ないでくれと思う。それはもちろん、俺は骨折したくねーよなんて最低な理由じゃなくて、単純に球子に不幸が訪れないでほしいから。でも、俺に不幸が訪れることで球子の骨が折れるなら、結局不幸が訪れているのは球子ってことになるんだろうか。
大袈裟にグラスを掲げて、にひゃあっと溶けたみたいに球子は笑う。俺の頭もつられて溶けて、ただひたすらに今が嬉しい。俺たちはまた一年よろしくねって、契約を延長するみたいに挨拶を交わし合う。
「二年目の目標決める?」
「なんだよそれ、新年じゃないんだから」
「え~いいじゃん! 決めよ!」
「そんなん言ったら、俺的には一つしかないよもう」
「なに?」
「球子の骨を折らせない」
「えーまたその話ー」
「いやそりゃそうだろ、逆で考えてみ?」
「あー確かに、そりゃそうだわ」
「な」
「うーん、なるほどねぇ」
「……球子的にはあんの?」
「私は……やっぱ勇を守るになるな」
「いやだからそれがダメなんだって!」
「……逆で考えてみ?」
「……あぁ……まぁそうか……」
「ね?」
「でもこれだとさ、俺らの目標同時に叶わなくない?」
「なんで?」
「だってさ、俺は球子に怪我させたくないじゃん。でも球子もさ、俺に怪我させたくないじゃん。お互いがお互いを守ろうとしてるからさ、これ。守りバトルじゃん」
俺は球子が笑うと思った。だって、今俺が言ってることは変だ。「守りバトル」とか言って、完全に茶化している。球子はそのバトルの中で骨を折ってるのに。でも、球子はそういう不道徳さが好きだし、怪我のことを真剣に扱わないでほしがるから、だから言ったんだけど、球子は笑わない。目を閉じてるみたいに視線を斜め下に送ったまま黙っている。これじゃまるで、俺が球子の骨折を軽く扱ったみたいだ。違う。そうじゃなくて、俺は、俺が重たく受け止めるせいで球子に変な罪悪感を感じさせたくなくて、だから軽やかにしてみたわけで、でもそれは、折らせた俺がやっていいことじゃないんだろうか。血管が透けてしまいそうな球子の薄い瞼を見つめていると、そこは微かに動くから、目を閉じているわけじゃないようだ。付き合い始めてすぐの頃、球子が怒ったふりをして、でも実は寝てましたー! とかいう複雑な嘘をついてきたことがあって、今回もそうだったらなって思ったのに。今回はなんだろう。どっちだろう。探るように見つめていると、そこにちょうど「食後にかけてください」と頼んでおいた「ベラ・ノッテ」が流れてきて、デザートがテーブルの上に置かれる。
「結婚記念日だそうで、おめでとうございます」
「あ、そうなんです。ありがとうございます」
「お食事はいかがでしたか?」
「すごく美味しかったです」
ニコニコと喋る球子を見て、もしかしたらこういうタイミングのことを「助かった」なんて言うのかもしれないと思った。でも俺は全然そう思えなくて、むしろタイミングは最悪で、球子の大好きな「ベラ・ノッテ」に、こんな空気を孕ませたくない。「ベラ・ノッテ」の中で愛想笑いもさせたくない。目の前に置かれたなんだかわからない、緑のブツブツが乗った食べ物はなんという名前だろう。
「こちら、食後のデザートのカンノーロでございます。ごゆっくりどうぞ」
と言って店員が立ち去った瞬間に、俺は笑ってみせた。
「初めて聞いたわ。なんだろうねこれ」
球子は俺のカンノーロを見つめたまま返事をしなくて、さらに俺は焦る。ていうかそれ以前に「ベラ・ノッテ」がかかってるのに「ベラ・ノッテだ!」って言わない球子なんて初めてだ。やっぱり俺は間違えたんだろうか。
「球子ごめん」
「これ、勇が頼んでかけてくれたの?」
「え? あ、うん」
「すごい! そんなことできるんだ! すごい! 嬉しい!!」
「あ、ほんと? よかったぁ」
「ねぇもう一杯飲みたいから頼んできてくれない?」
「あ、すいませ」
「待って待って! 大きい声出すとベラ・ノッテ聞こえなくなっちゃうから! 行って呼んできて!」
「なにそれ」
「ちゃんと聞きたいの。ベラ・ノッテ」
「わかったよ」
喜んでくれてるのか? 俺はとりあえず、言われた通り人を呼びに行く。球子の本心はわからないけど、とりあえず今、球子の願いを叶えることを優先する。席に戻ると、俺のカンノーロが球子の方に引き寄せられていた。
「なに、そっちの方がいいの?」
「ううん、違う」
「二つとも食べたいとか?」
「違うよ~」
「え、じゃあどしたの?」
「ん~。今日も私の勝ちかも」
「え?」
「守りバトル」
ニヤリと笑った球子は、俺のカンノーロを皿ごと回転させる。俺には見えていなかった、カンノーロの裏側には短い髪の毛が付いていた。
「……マジかぁ」
「マジよ」
「え~……え~マジかぁまた?」
「あはは、びっくりだね」
「そういうの起きなそうな店選んだのになぁ……いや、てかごめんせっかく記念日なのに。ちょっと言うわ」
「いやいいいいいいいい。私気にならないから。どけて食べるよ」
「いやでもさ! てか、だったら俺が食うよ」
「ダメ」
「なんでよ」
「見つけたの私だもん」
「え? いや、だとしてもさ」
「勇が言ったんじゃん守りバトルって。それめっちゃ面白いからやろ? 今日からスタートで、これも含まれるから。一ポイント目ね!」
「え~なんだよそれ~」
「勇が言ったんじゃん」
「いやまぁそうだけどさ、でも俺食うよ」
「ダメだよ」
「なんでよ」
「見つけたの私だから。これで勇が食べたら守り泥棒だよ」
球子はゲラゲラ笑う。そんな大声で笑ったらもう、ベラ・ノッテは聞こえないだろう。でも、俺と出会う前から彼女が好きだったベラ・ノッテが聞こえなくなるくらい大きな声で笑う理由が、俺であるってことが、すごく嬉しい。また球子に守られてしまったけど、それは少し情けないような気もするけど、でも俺は、球子がトランプならレディでも構わない。トランプが怪我さえしなければ。
記念日から一週間が経って、その間俺たちは守りバトルを続けている。インターホンには俺が出る。一ポイント。揚げ物は俺がやる。一ポイント。こじつけのような気もしたけど、見つけられた方が勝ちだ。俺がポイントを稼ぐ度、球子ははっきり機嫌が悪くなった。身長の割に広い肩が少し持ち上がるのだ。怒り肩を地で行っている。「私の仕事なのに」とでも言いたげな顔で俺を見上げる姿は可愛くて、おかしくて、でもだからって守りの手は抜かない。これは戦いなのだ。球子ももちろん反撃を試みる。「守り」なのに「反撃」って変だけど、隙あらば俺を守ろうとする姿は「反撃」としか言えない。
仕事が同じタイミングで終わる火曜の夜は、いつも待ち合わせて一緒に帰る。最寄り駅のスーパーで買い物したり、時には居酒屋でお酒を飲んだりして帰るこの一日は、俺の楽しみだった。球子はいつもの電車に乗りそびれたらしく、俺はぼーっとベンチに座って球子を待つ。四月といえど夜はまだ結構冷えて、ていうか今日は特別に寒い気がして、到着を待つのが球子じゃなくて俺で良かった。鋭い風が首元を一周する。ワイシャツの下に着ているテロテロのインナーが昼間吸った汗を今更噴き出しているようでじわじわと寒い。俺が今この寒さに耐えているっていうのも、もしかしたら一つの「守る」かもしれない。いや流石にこれはやりすぎか?
「勇ー!」
駅の中に閉じ込められていたみたいな勢いで、球子が改札を飛び出してきた。球子は身長が確か一六〇センチくらいで、そこまで大きいとはいえないけど、俺の目にはものすごく大きく球子が映る。球子を中心に世界を魚眼レンズで見ているみたいで、これも一種の恋は盲目なんだろうか。
「お待たせ! ごめんね寒かったでしょ」
「正直めっちゃ寒い」
「あはは、だよね。そんな勇に良いアイテムがあります。じゃーん!」
そう言って球子はカバンから俺のマフラーを取り出した。地面につかないように目一杯持ち上げているそれは、先月冬物としてクローゼットの奥にしまったはずのものだった。
「え! すごいなんで?」
「ふふ。絶対勇寒がると思ってさ。知ってた? 今日めっちゃ寒いんだよ。天気予報で言ってたから、昨日の夜こっそり出したの」
ありがとうと言いながらモヤモヤする。だったら今朝渡してくれればよかったんじゃないか? そう思う俺は意地悪だろうか。マフラーを巻き付けようと手を伸ばす球子は満足げで、俺は余計な顔色を悟られないために頭を下げる。
「はい完成! 行こ!」
ギュッと締まったマフラーはつい最近まで使っていたもののはずなのに、人の家みたいな匂いがした。前を歩く球子は気づいているだろうか。もっと俺を守れたんじゃない? 別に守りが足りないとか思っているわけでは全然ないんだけどさ。そう言いたいけどせっかくご機嫌な球子に水を差したくなくて、俺は黙って後ろをついていった。
体が冷えた俺のために、球子は今夜鍋にすると言い出して、スーパーで買い物を済ませた。球子が俺の寒かった時間に触れるたびに、ベンチに座っていたあの数分間の温度がどんどん下がっていくようだった。実際は少し肌寒いくらいだったはずなのに、「キムチで温めよう!」とか「すぐお風呂入れようね」とか、球子が俺を入念に労わることで、俺の頭の中に記録されてるあの場所あの時間は極寒と化していく。寒くなればなるほど、首に巻かれたマフラーの存在が、そしてそれを巻いてくれた球子の存在が大きく大きくなっていく。実際の球子よりも。
「いや~また守っちゃったなぁ~一ポイントだ~」
球子がそう言いながら商店街を歩き始めた時、俺はいよいよ無視できなくなる。俺の首筋を覆うマフラーの暖かさは、冷えたからこそ感じる暖かさ。
「これ、朝渡してくれたらよかったんじゃない?」
「なにが?」
「マフラー」
「え?」
真っ黒な球子の両の瞳は、見開かれすぎた瞼のせいでポツンと俺の前に浮いているようだ。
「いやさ、寒いって知ってたなら、朝渡してくれればよかったのにって」
「あ~確かに」
だよなやっぱり。
「でもさ、びっくりしたでしょ?」
「え?」
「家で『明日寒いよ~』って渡されるよりもさ、寒いって思ってる時に急に渡される方が、びっくりだし嬉しくない?」
びっくりだし、嬉しいし、寒いよ。
「サプライズみたいな!」
「そういうこと?」
「そうそう」
「ッハ、ありがとう」
「いいよ~」
そのあと球子が作ってくれた鍋も、入れてくれたお風呂も、凄く暖かくて、確かに球子が作ってくれた暖かさで、でもじゃああの寒さも球子が作った寒さだろうか。シンクに重なる赤く染まった皿に水を掛け、スポンジで擦る。そうしているうちに段々とお湯になる。温かいと感じる。この蛇口も一種のサプライズなのかもしれない。洗い続けるうちにもう水の冷たさなんて忘れているけど、それでもお湯は温かいままだった。
続きは2022年7月7日発売 「文藝」秋季号でお楽しみください。