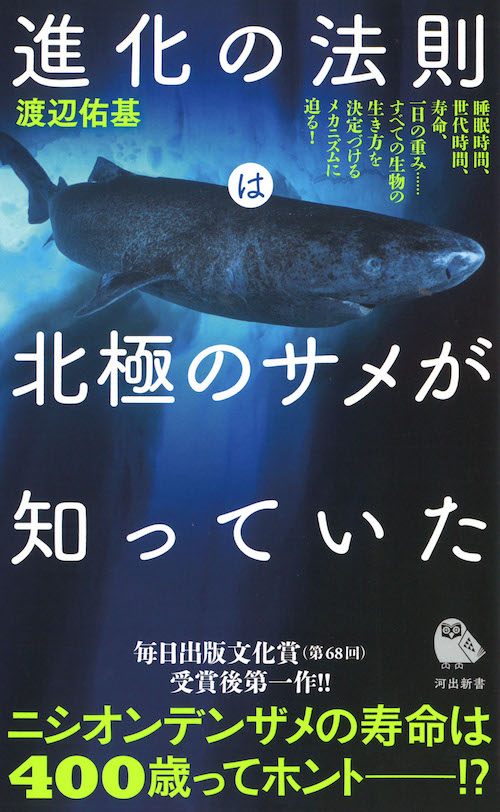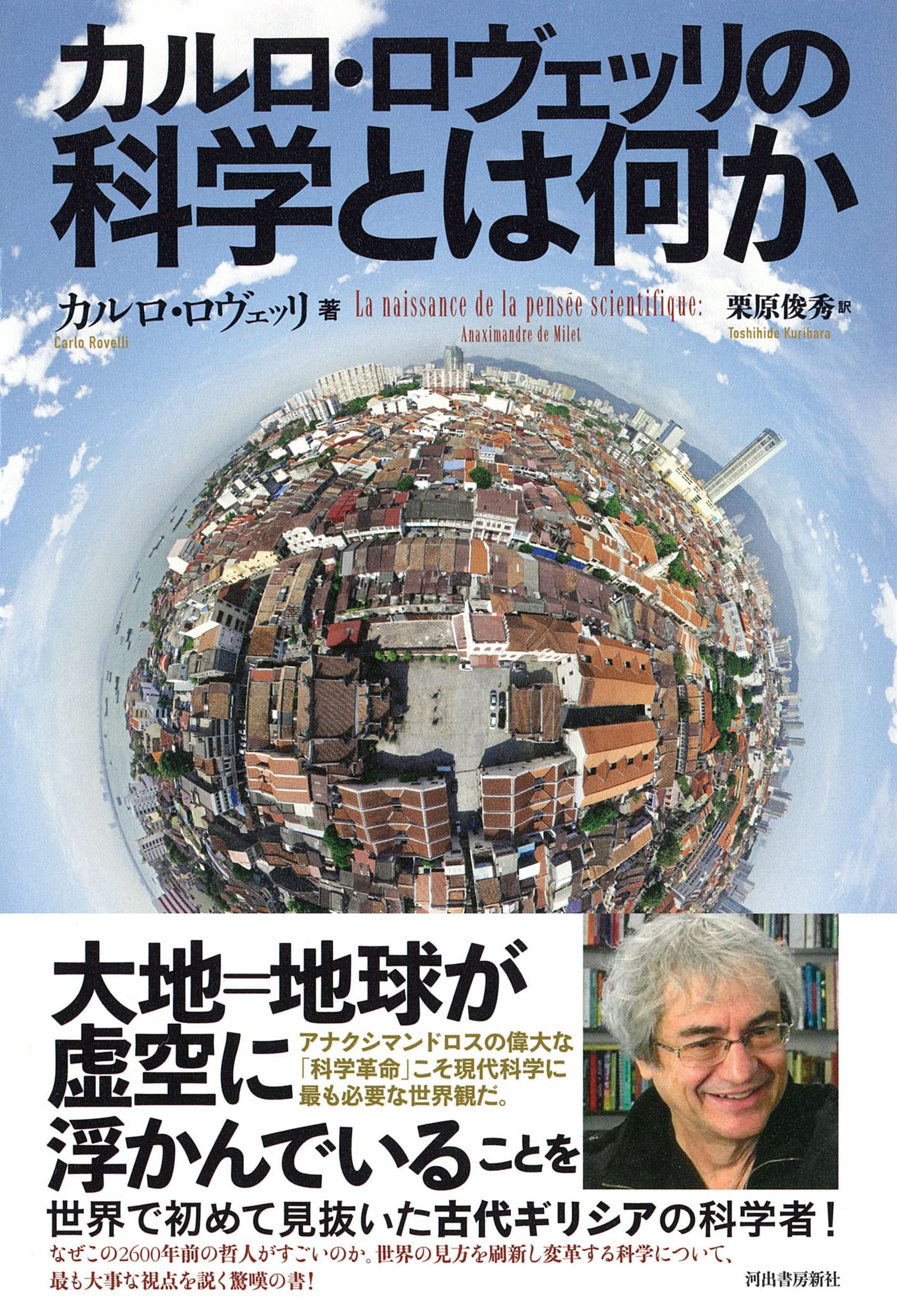単行本 - 自然科学
サメも昆虫も人間も、ゾウリムシも一緒。多様な生物のシンプルな法則に迫る科学冒険ノンフィクション!
渡辺佑基
2019.03.20
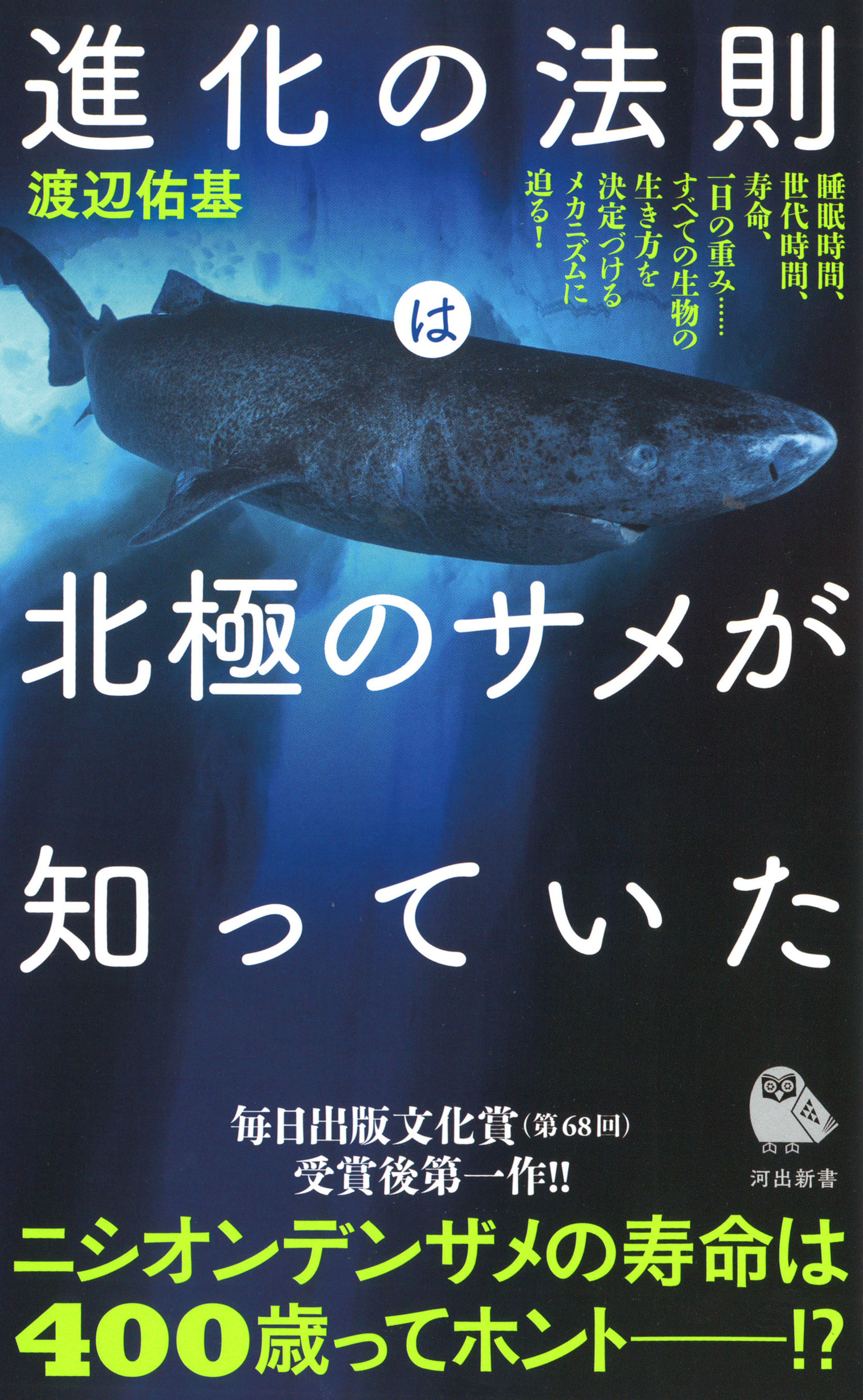
『進化の法則は北極のサメが知っていた』
渡辺佑基
はじめに
冬の寒い日に鼻水が垂れてくるのはなぜか。
それは低温という刺激によって副腎皮質ホルモンが分泌され、鼻腔にあるホルモン受容体と結び付いて鼻水の流出が促進されるから──というのは真っ赤な嘘である。ごめんなさい。
じつは話はすこぶる単純である。冬の空気は冷たくて乾燥しているが、人間の体内は温かくて湿っている。だから鼻から吸い込まれた外気は、気道を通って肺に送り込まれるうちに温められて湿気を含む。そして次に、肺の空気が呼気として体外に送り出される際は、空気は外界に近づくにつれて急激に冷やされる。空気は冷やされるほど水分を保持できなくなるので、空気に含み切れなくなった水分が鼻の内壁に結露する。これが冬のクリーンな鼻水の正体だ(だから鼻水を垂らしたくなければ、鼻ではなく口から息を吐き出せばよく、実際にマラソン選手はそうしている)。
この話を最初に知った十数年前の大学院生の折、私は妙に感激したのを覚えている。なんだ、生物といったって、つまるところ物理なのだ。〇×ホルモンやら神経系やら受容体やらのはたらきも大事なのだろうけれど、生命現象の根幹にあるのは、乾燥した空気は水分をよく含むとか、冷やされると結露するとかいった、ごくシンプルな物理なのだ。
そして私はそれを、心の奥底から面白いと思った。今までとっつきにくいと思っていた生物学が、急にこちら側の身近なものとして感じられるようになった。まるでアマゾンの奥地にいる幻のチョウが、空間を越えてふわりと私の手の中に入ってきたような、そんな気がした。
もう一つ別の例を挙げよう。
オオハシという巨大なくちばしを持つ鳥が南米の熱帯雨林にいる。この鳥のくちばしの大きなことといったら、体の大部分がくちばしでできているといってもいいくらいで、そのためオオハシは実在の鳥というよりは、むしろアニメのキャラクターのように見える。
この巨大なくちばし、いったい何のためにあるのだろう?
それは副腎皮質ホルモンを分泌し、くちばしの内部にあるホルモン受容体を──もちろん嘘である。くどいですね、ごめんなさい。
オオハシのくちばしは、体温の調整に役立っている。くちばしの表面のすぐ下には多数の血管が通っていて、温かい血液が流れている。鳥の体内の血管と違い、くちばしの血管は冷たい外界に近接しているので、そこを流れる血液からは熱が徐々に外に逃げていく。オオハシは体が熱くなると、くちばしを流れる血液の量を増やし、より多くの熱を体外に排出してオーバーヒートを防ぐ。ぎゃくに寒いときには、くちばしを流れる血液の量を減らし、熱の排出量を抑えることによって体温を保持する。
つまりオオハシのくちばしは、エンジンから発生する熱を外に逃がすために車に付いているラジエーター(放熱器)と同じ役割を果たしている。ラジエーターは表面積が大きいほど効率的に熱を排出できるが、それと同じ理由でオオハシのくちばしも表面積が大きいほどいい。別の見方をするならば、オオハシにおいてあれほど巨大なくちばしが進化したのは、天然のラジエーターが厳しい自然を生き抜くための有効な武器になったからに他ならない。
この話を初めて知った折も、私は妙に心が躍った。何のことはない、ラジエーターなのだ。機械なのだ。オオハシの奇妙な姿かたちをいちばんうまく説明するのは、〇〇遺伝子やら××進化論やらといった難しい話ではなく、熱は温かいほうから冷たいほうへ流れるとか、表面積は大きいほうがいいとかいった、シンプルで身近な物理現象なのだ。
冬の鼻水とオオハシのくちばし。このように生物の体温にまつわる現象は面白いものが多い。それは「へえ」という単純な驚きだけではなく、メカニズムが理解できたという一段上の知的な喜びをももたらしてくれる。生命現象と物理現象とが直接ぶつかり合う接面、それが体温なのである。
それに考えてみれば、体温ほどあらゆる生物に当てはまり、なおかつその日々の生活を強く制限しているものはない。池の中をもぞもぞと動くゾウリムシも、草むらを歩くトカゲも、また海上を舞うアホウドリもそれぞれの体温を持ち、それぞれの環境の温度に縛られながら生活を営んでいる。
だから本書では、物理というナイフで自然界をすぱりと切り、体温という切り口からこの地球上に暮らす様々な動物を見渡してみようと思う。そうすることによって、なぜ動物は──あるいは人間は──今ある姿かたちや行動や生活スタイルを取るに至ったのか、その背景にある巨大なからくりみたいなものが理解できるような気がする。
思うのだけれど、生物学者はとかく多様性を強調する。この地球上にはこれほど多様な魚が、鳥が、昆虫が、あるいは植物がいて、これほど見事に環境に適応し、厳しい自然を生き抜いている、という本は数多く出版されている。けれども生命現象を物理的な視点から捉え、メカニズムの理解を促しながら、コガネムシにもマグロにもカモシカにも一様に当てはまる「生物の法則」を探ろうとした本はほとんどない。だから本書を通して、私はそれにチャレンジしてみたい。
断っておきたいのだが、私は生物の多様性の意義を軽んじているわけではない。それどころか、私自身が漁船に乗ったり僻地でキャンプ生活をしたりするフィールド生物学者であるから、世界のあらゆる場所で多様な生物があの手この手の生存競争を繰り広げていることは身に染みて知っている。
むしろ私にとっての最大の謎は、生命活動がシンプルな物理で説明できるということと、地球がこれほど多様な生物に満ち溢れているということ、この二点がなぜ両立しうるのかという問題だ。だって物理的な効率が生物の生存率を決めるのであれば、それをいちばん上手に達成した少数の生物種が世界の資源を独占してしまうはずだろう。まるで人並み外れた活力を持つ英雄、奸雄が戦乱の世を平定し、天下を統一するみたいに。でも不思議なことに、この自然界はそうなってはいない。数百万とも一千万ともいわれる膨大な生物種が絶滅と種分化を繰り返しながら、悠久の時を越えて共存している。シンプルなのに、多様なのである。それがなぜなのか、今のところ私にはわからない。だから本書では、頭の中の斜め上方に「生物はなぜ多様か」と大きく朱書きしたうえで、体温の話を進めていきたい。
というわけで、本書の目的をひとことで言うならば、体温という物理量がどのように生物の姿かたちや生き方を規定しているのか、昆虫にも魚にも哺乳類にも当てはまる大スケールの統一理論を構築することである。そしてその統一理論と、この地球上に見られる信じられないほどの生物多様性がどのように両立するのかを明らかにすることである。さあ、うまくいくかどうか(勝手にドキドキ)。
「ところで一人で興奮しているこの著者は誰?」という声がそろそろ聞こえてきそうなので、ここで簡単に自己紹介をさせていただきたい。私は東京都立川市にある国立極地研究所に所属する生物学者である。現在四〇歳。三島由紀夫によれば、この頃の年齢というのは「経験はかすかに腐臭を放ちだし、新奇な歓びは日ましに乏しくなる年齢」(『奔馬』より)らしいけれども、なんのなんの、まだまだがんばりますよ。趣味はサイクリングとダイビング──とはいえちょっとでも気を許すとロードバイクにもダイビング器材にも埃が積もってしまう典型的な中年である。自慢できるような特技や資格はほとんど持ち合わせていないが、唯一、日本けん玉協会よりけん玉一級の級位を頂戴している。調査で南極を訪れた際、船上での待機時間など暇な時間があまりに多かったので、けん玉を練習した。
生物学者としての私の専門分野は、海洋動物(魚、海鳥、海生哺乳類)の生態である。最近はとりわけ、いろいろなサメ類(映画『ジョーズ』で有名なホホジロザメや北極のニシオンデンザメなど)と南極のアデリーペンギンの調査に力を入れている。
生態学の専門家というと、世界中の動植物の種名に精通したナチュラリストのイメージがあるかもしれない。実際にそういう研究者も多数いるのだが、私はどちらかといえば種名を覚えるのは苦手であり、特に植物の名前はすぐに忘れる。でもその補填なのか何なのか知らないけれど、生命現象の背景にある仕組みを考えるのは比較的得意な気がする。自転車レースの選手の中に坂道の得意なクライマータイプと平地を好むスプリンタータイプがいるように、生態学者の中にもナチュラリストタイプとメカニズムタイプがいる。そして私は典型的なメカニズムタイプだと少なくとも自分では思っている。
サメやペンギンの生態を研究するためのツールとして、私は動物の体に小型の計測機器を取り付ける「バイオロギング」の手法を使っている。バイオロギングについては前著『ペンギンが教えてくれた物理のはなし』(河出書房新社、二〇一四年)に詳しく書いたので、それをここで繰り返すと「渡辺は文章複製でせこく原稿料を稼いでいる」と謗られそうだからやめておこう。でもとにかく大事なことは、近年の電子デバイス技術の進歩によってバイオロギング機器も日進月歩の小型化・高性能化を遂げ、野生動物の行動やまわりの環境を詳細に計測することが可能になったということだ。
そしてバイオロギングの調査手法と、本書のテーマである動物の体温とは太い根っこで繋がっている。というのも、バイオロギングのおかげで動物たちがどれくらいの環境温度を経験し、その環境温度に対してどのように反応しているのかを詳しく計測することが可能になったからだ。また、温度センサーを海を泳ぐ魚や空を飛ぶ鳥の体内に挿入し、動物たちの体温を直接計測する試みも多数行われている。さらに最近、そうしたデータを多数取りまとめて生物全体を貫く法則性を探ろうとする、スケールの大きな研究も行われるようになった。率直に言って、バイオロギングと動物の体温はとても相性のいい組み合わせなのだ。まるでビールと固形フルーツゼリーのように(私の個人的大発見)。
さて、本書は全五章で構成されている。各章では私のフィールドワークの話を織り交ぜながら、動物の体温の話を進めていく。
第一章では、北極の超低温の海に暮らすニシオンデンザメの調査を紹介しながら、そもそも体温とは何なのか、動物にとってどんな意味を持つものなのかを概説する。いわば本論に入る前のウォーミングアップの章である。
第二章では、南極に暮らすアデリーペンギンの調査を紹介しながら、私たち人間を含む哺乳類や鳥類がどのように体温を維持しているのか、そのメカニズムを見ていく。このあたりからペースは上がり、本格的に科学の話になっていく。
第三章では、オーストラリアのホホジロザメの調査を紹介しながら、一部の魚類やウミガメが変温動物としての枠組みから外れ、冷たい海の中で高い体温を維持していることを見ていく。また、その特殊な能力の背景にあるメカニズムや進化的意義について考える。それは必然的に、約六五〇〇万年前に絶滅した恐竜の体温が温かかったのか冷たかったのかという、大変面白い論争にも繋がっていく。
そして第四章では、イタチザメの代謝量を測定する私のフィールドワークを紹介しながら、いよいよ体温が生命活動に与える影響を包括する一つの理論を組み上げていく。結論を先に述べるのならば、生命活動は究極的には化学反応の組み合わせであり、したがって生物の生み出すエネルギーの量は熱力学の法則によって決定される。そしてその視点に立てば、サメも人間も昆虫も、ゾウリムシでさえも同一である。
最後の第五章では、ロシアのバイカル湖に生息するバイカルアザラシの調査を紹介しながら、前章で見つけた理論を応用して生物にとって時間とは何かを考える。興味深いことに、生物にとっての時間の流れるペースは絶対不変の定数ではなく、体温によって、あるいは代謝量によってゴムのように伸び縮みするまぎれもない変数である。私たちが年齢を重ねるにつれて、時間の流れが加速していくことからも想像されるように。さらに締めくくりとして、「生物はなぜ多様か」の朱書きの疑問に立ち返り、その答えを探してみることにしよう。
本書によって、生命現象を物理的な視点から捉えてメカニズムを明らかにすることの面白さを知っていただき、また地球上のすべての生物を包み込む統一理論を探るという知的冒険を楽しんでもらえたなら、筆者としてはとてもうれしい。さらにその現場にいる私のドタバタなフィールドワーク劇をニヤリと笑って読んでもらえたなら、それに勝る喜びはありません。