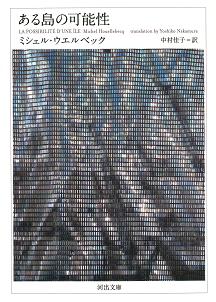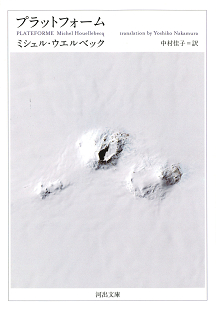文庫 - 外国文学
『服従』の次に読むウエルベック『ある島の可能性』。二千年後に再生された複製人間の物語
ミシェル・ウエルベック
2016.01.20
ミシェル・ウエルベック
【訳者】中村佳子
ミシェル・ウエルベックの最新作『服従』が今秋、日本で刊行されました。
近未来SFというにはあまりに生々しい直近のシミュレーションであるこの新作は、予想通り、いや予想以上に時事にシンクロしてしまい、おかげで普段は翻訳小説なんて読まない、もともと小説なんて読まない、もっといえば小説嫌いという層までをも、読者に取り込むことに成功したようです。新聞の政治欄や社会欄の延長として、あるいは風刺や社会情勢分析として、『服従』を興味深く読んだという方もたくさんいらっしゃることでしょう。
そうした新しい読者に、ネクスト・ウエルベックとして、なにをお薦めするか迷いますが、『服従』で描かれた世界はその後どうなるのだろう、という素朴な疑問をお持ちの向きには、力強くこの『ある島の可能性』を推したいと思います。
『服従』では観察対象との距離が短すぎて、虚実の境を見失い、そこで行われる省察に心穏やかに立ち会えない、展開される果敢な思考実験を存分に堪能できない、なんてこともあったかもしれません。『ある島の可能性』ではそういった心配は無用です。なにしろ観察対象からの距離はたっぷり二千年あります。
これは、遥か二千年後の未来からひとりの観察者の目を通して現代社会を眺める、という体裁の小説です。
観察者は人間ではありません。心身ともに欠陥だらけだった人類に替わるべく改良された次世代の人類ネオ・ヒューマンです。正確に言えば二十一世紀に死んだとある男の複製二十四号と、その後継の二十五号です。ネオ・ヒューマンには死がありません。もちろん時が来れば肉体は死にますが、再生が利くのです。ネオ・ヒューマンの社会にはもはや戦争はありません。個人間の諍いさえありません。そもそも他人と物理的にふれあう機会がありません。他者とのコミュニケーションツールは電子通信に限られています。よってネオ・ヒューマンにはわたしたちを苦しめるような人付き合いから生じる悩みも痛みもありません。そして愛が存在しません。彼らはわたしたちの言うところの「解脱」に近い状態にあります。
人類はどうなったかですか? それはぜひご自身で読んで、お確かめください。
ネオ・ヒューマンの日課は、おのれのオリジナルの残した人生の記録の検討、もっぱらこればかりです。ネオ・ヒューマンは永遠に続く日々を、遠い昔に生きた男の一生を繰り返し追体験するために生きています。追体験といったって、ぜんぜん愉快な人生ではありません。表面はひりひりし、内は腸がよじれるような痛ましい人生です。ダニエルという名のその男は、読めばすぐにわかると思いますが、わたしたちの常識からすると、あまり褒められた人間ではありません。お笑いタレントとして、映画監督として、社会的には成功しましたが、その私生活の冴えなさ加減は『服従』の主人公といい勝負です。ともあれそれでも彼は、この物語において全人類を代表する剣闘士、れっきとしたヒーローなのです。なぜならば彼は、鈍感になること、を拒みました。鈍感になって幸せになること、を拒みました。彼自身の言葉を借りれば、「自分たちを破壊しようとするシステムに与すること、同意することを、最後まで拒絶」しました。つまり、彼は「服従」しなかったのです。
『ある島の可能性』は「服従しない」とはどういうことかを大いに語った本だともいえます。その意味で『服従』のあとで、なおさら面白く読める一冊なのです。
ウエルベックはもっともっと読まれていい作家だと、わたしはずっと思ってきました。ですから二〇〇七年に角川書店から刊行されたきり、長らく絶版になっていた『ある島の可能性』を、こうして文庫本の形でふたたび日の当たる場所へ送り出せることは、翻訳者としてなにより嬉しいことです。こうした機会をいただいた河出書房新社編集部のみなさんに心から感謝を申し上げます。かつて角川書店でわたしが携わった三冊のウエルベック︱『闘争領域の拡大』『プラットフォーム』『ある島の可能性』を編集し、このたびの文庫化を本に寄り添って喜んでくださった安田沙絵さんにも、この場を借りて謝辞を述べさせていただきます。
二〇一五年十一月 中村佳子