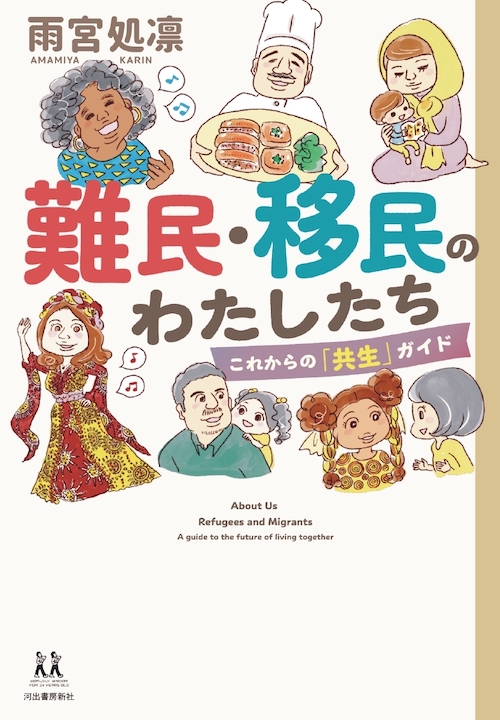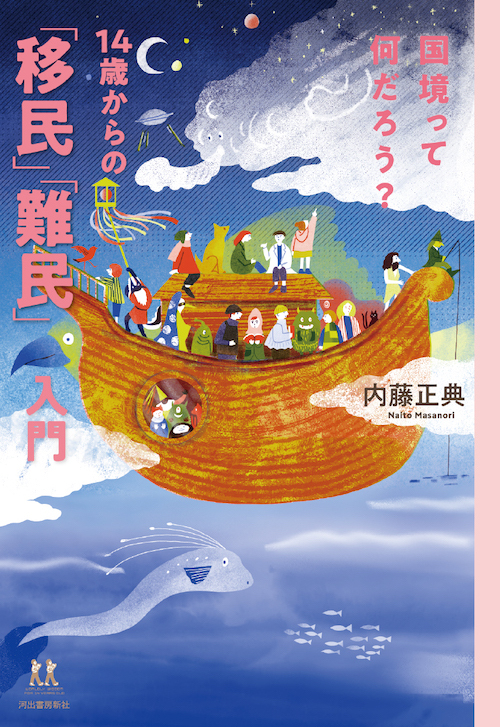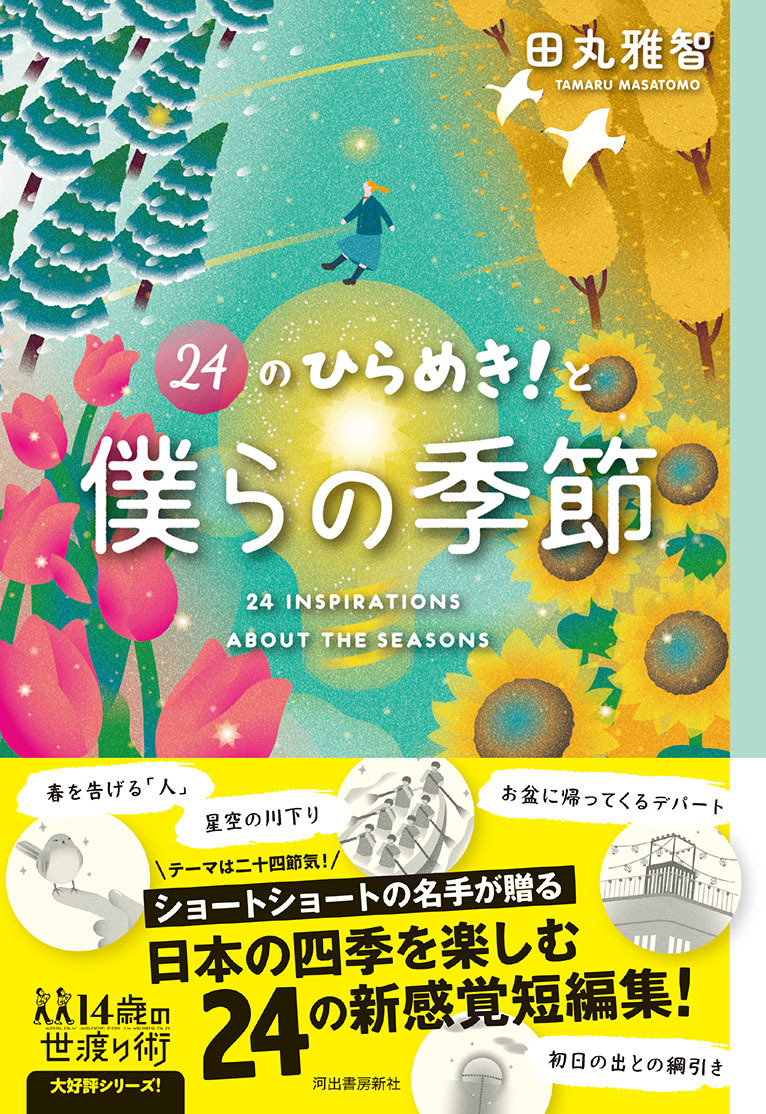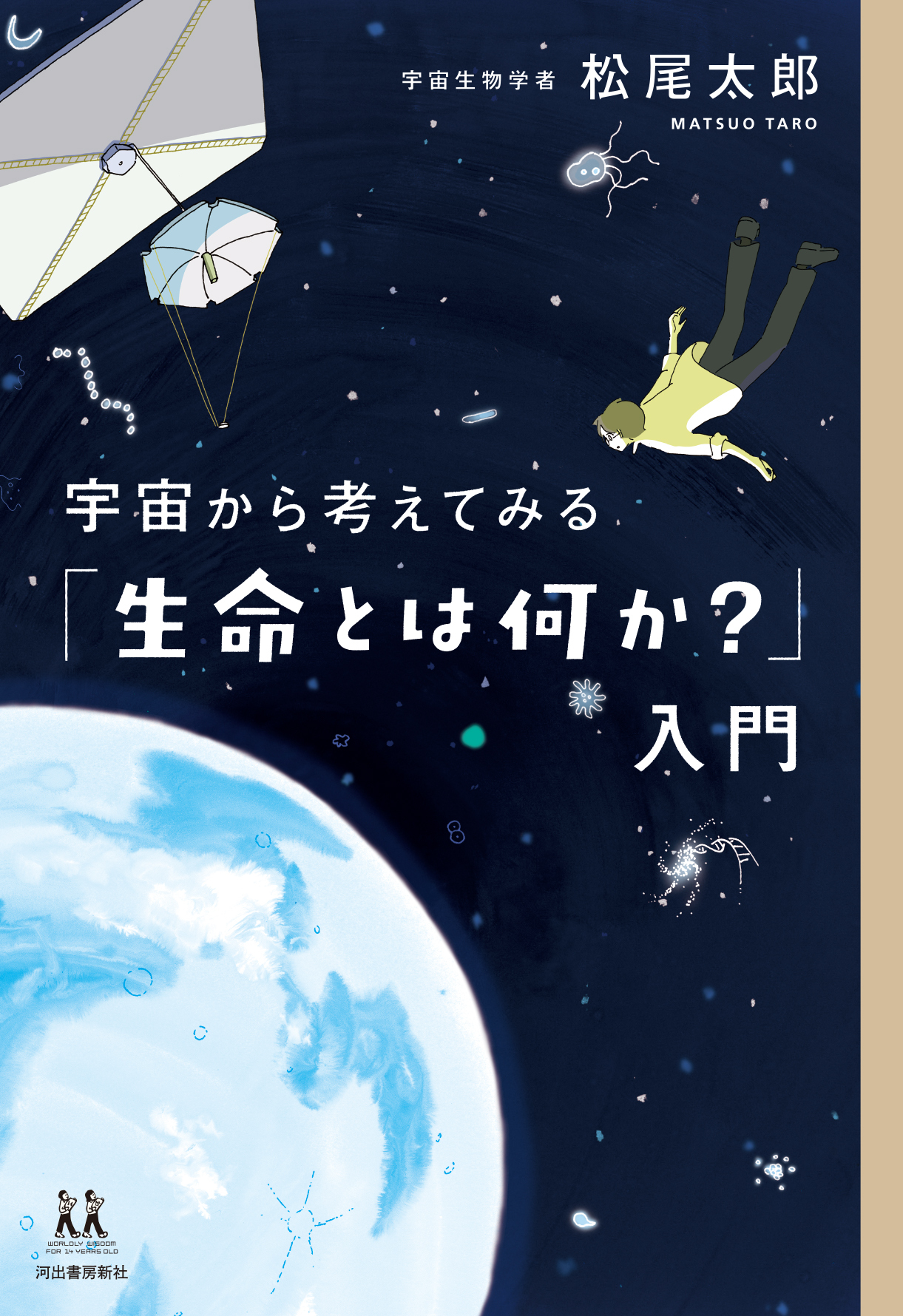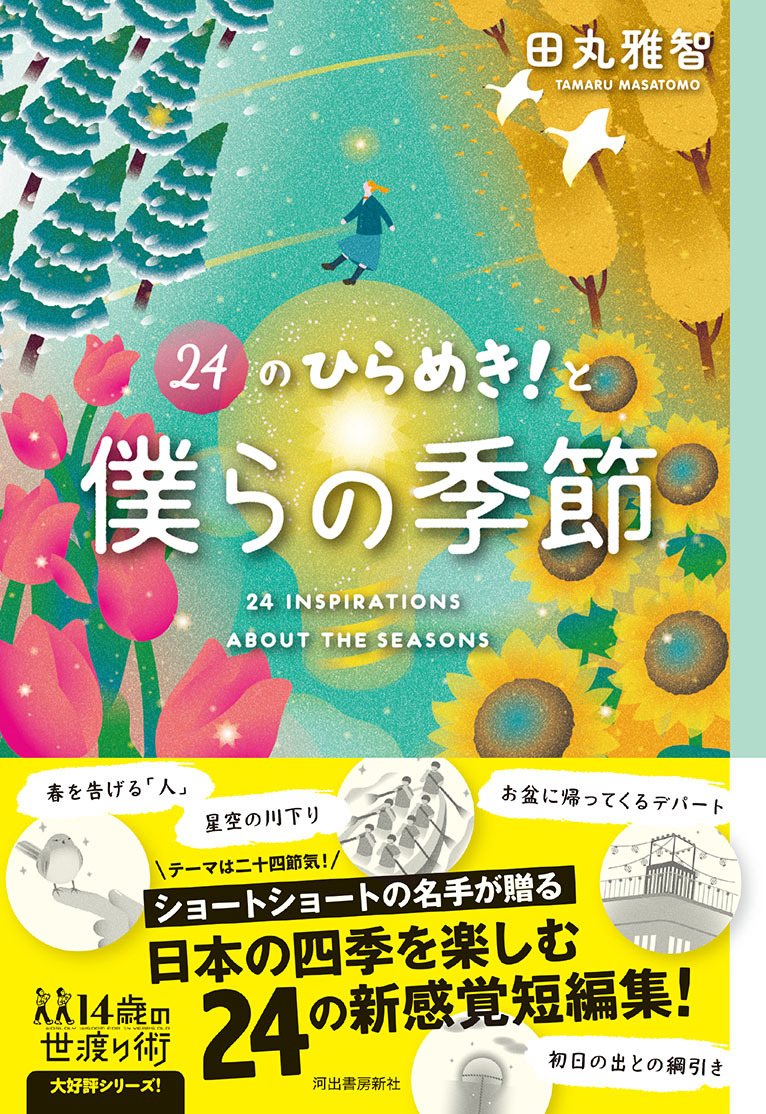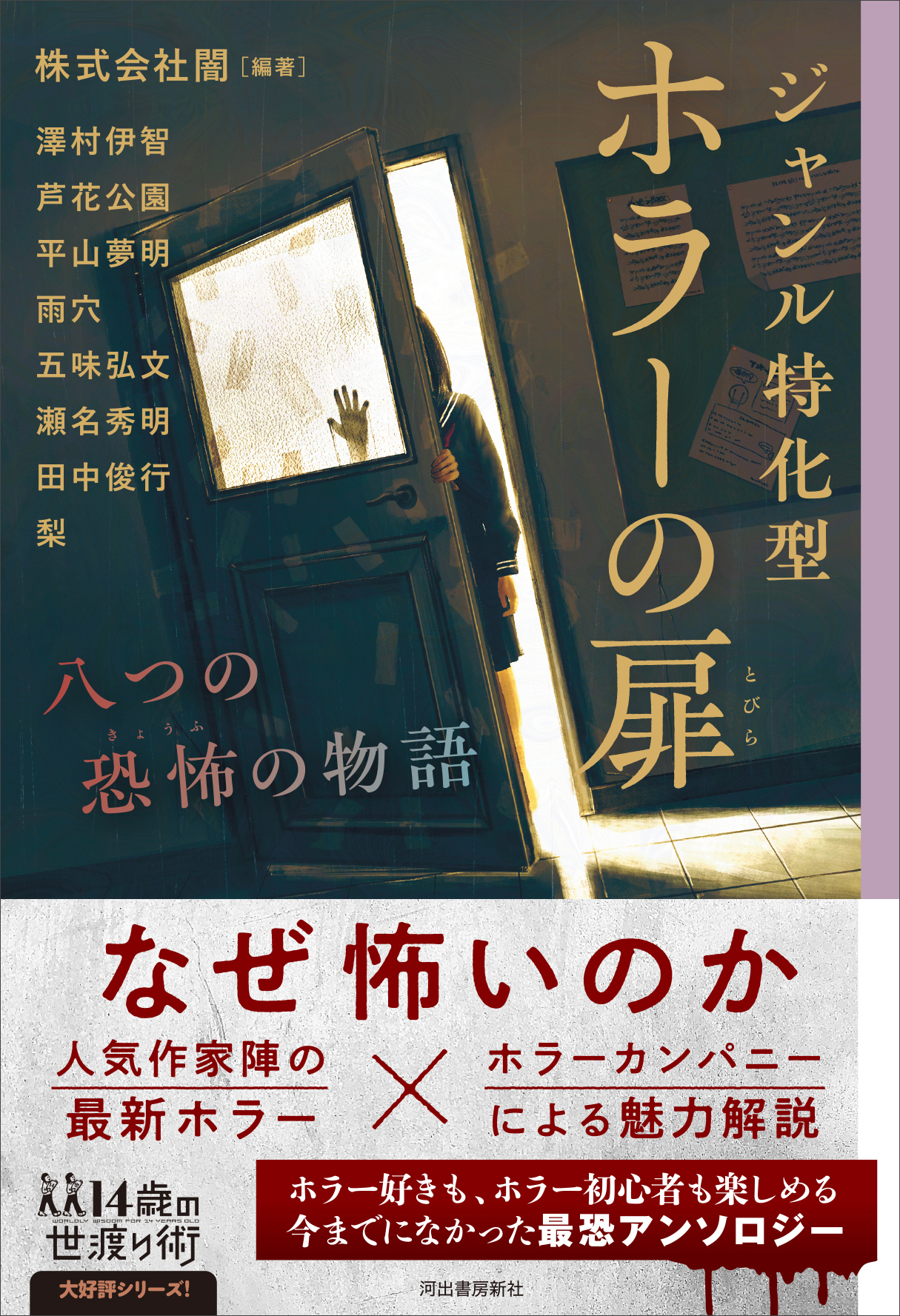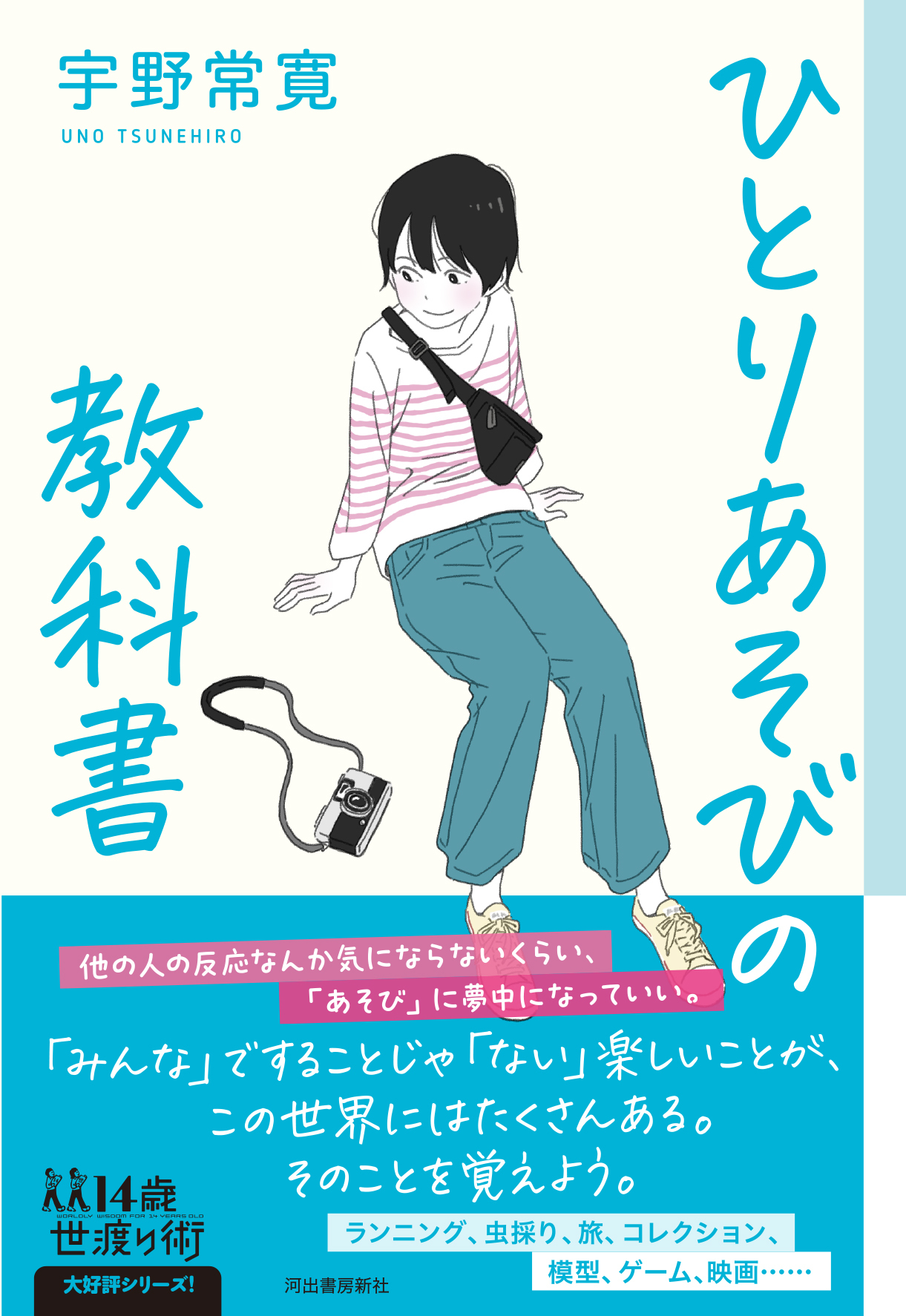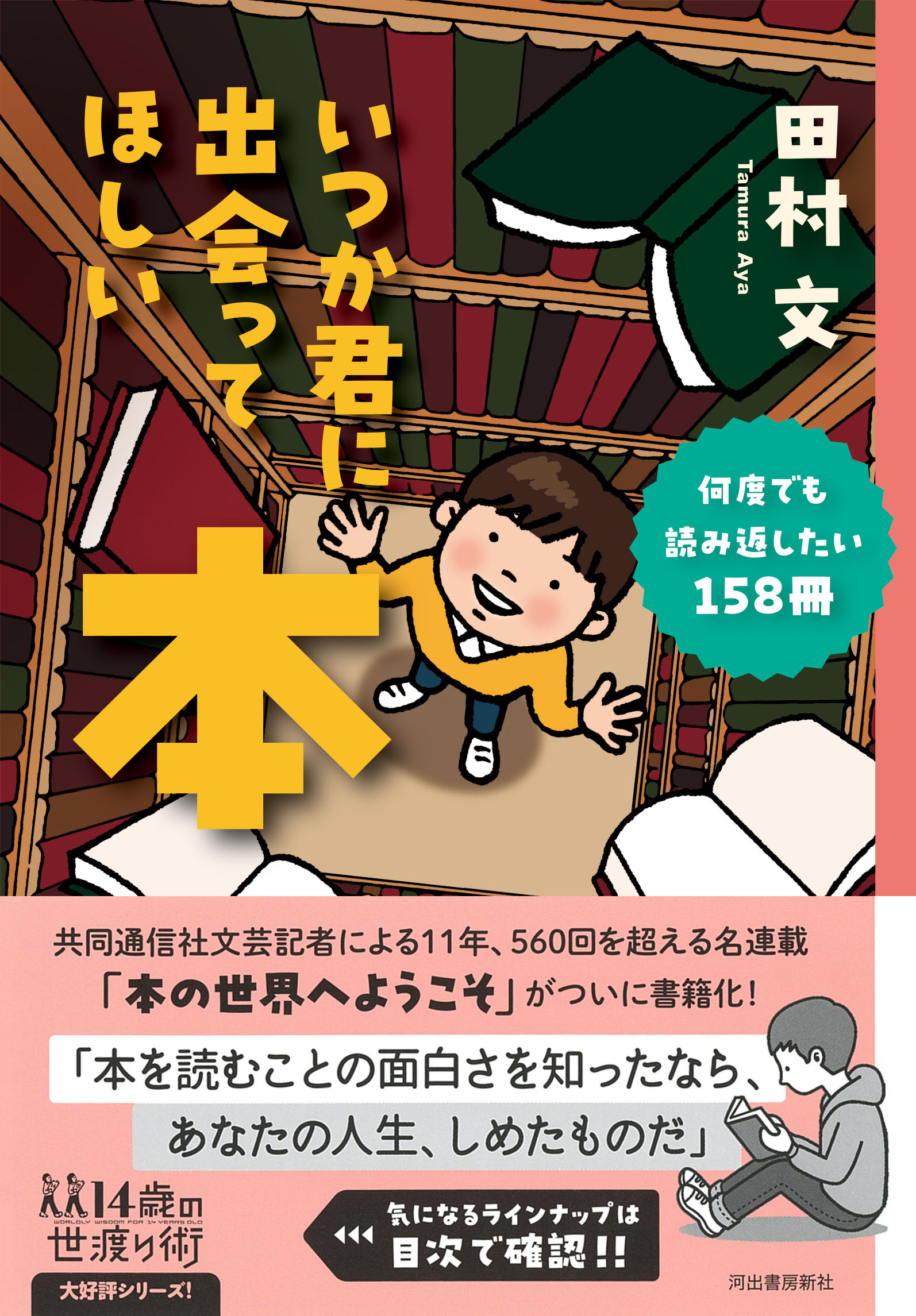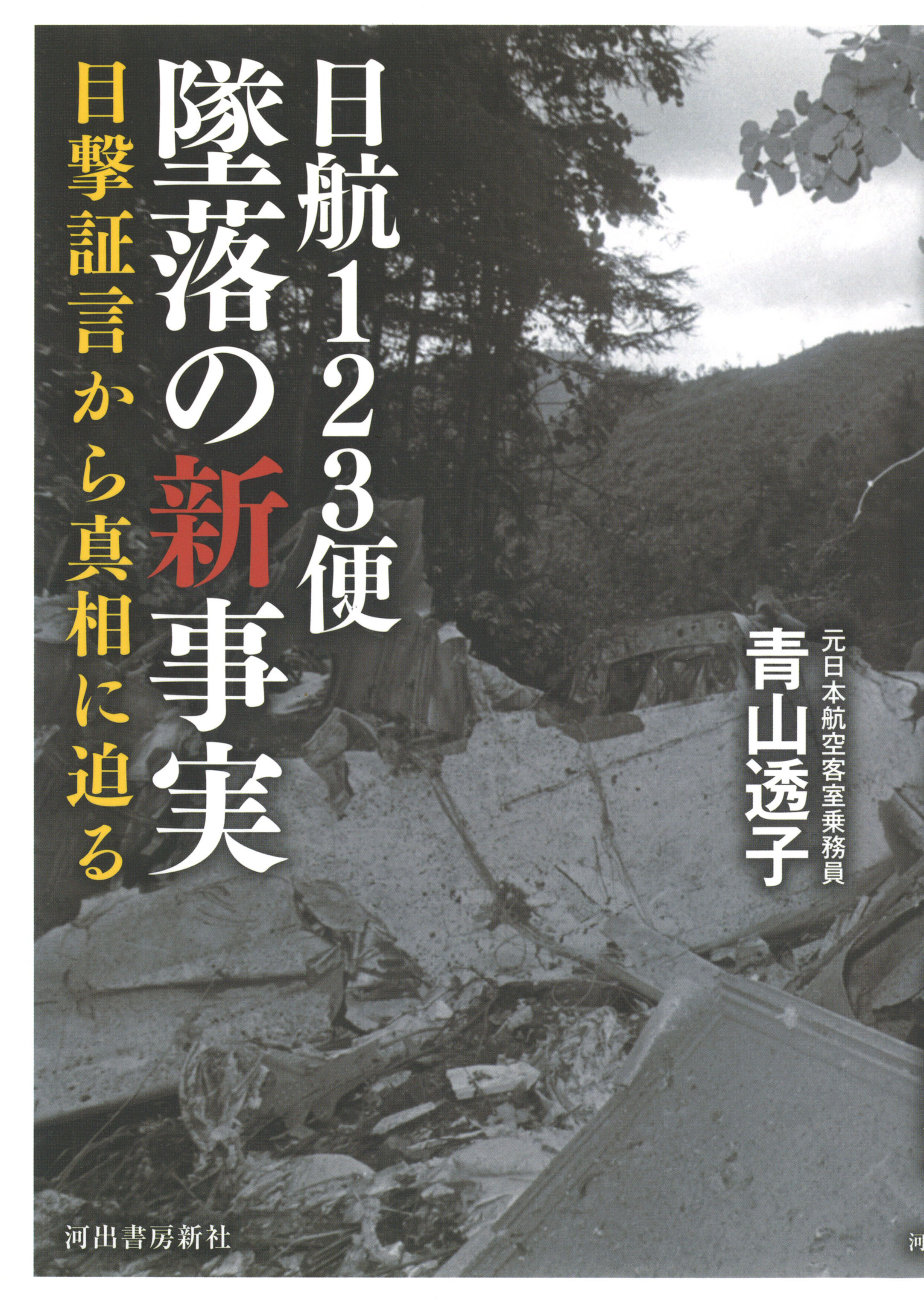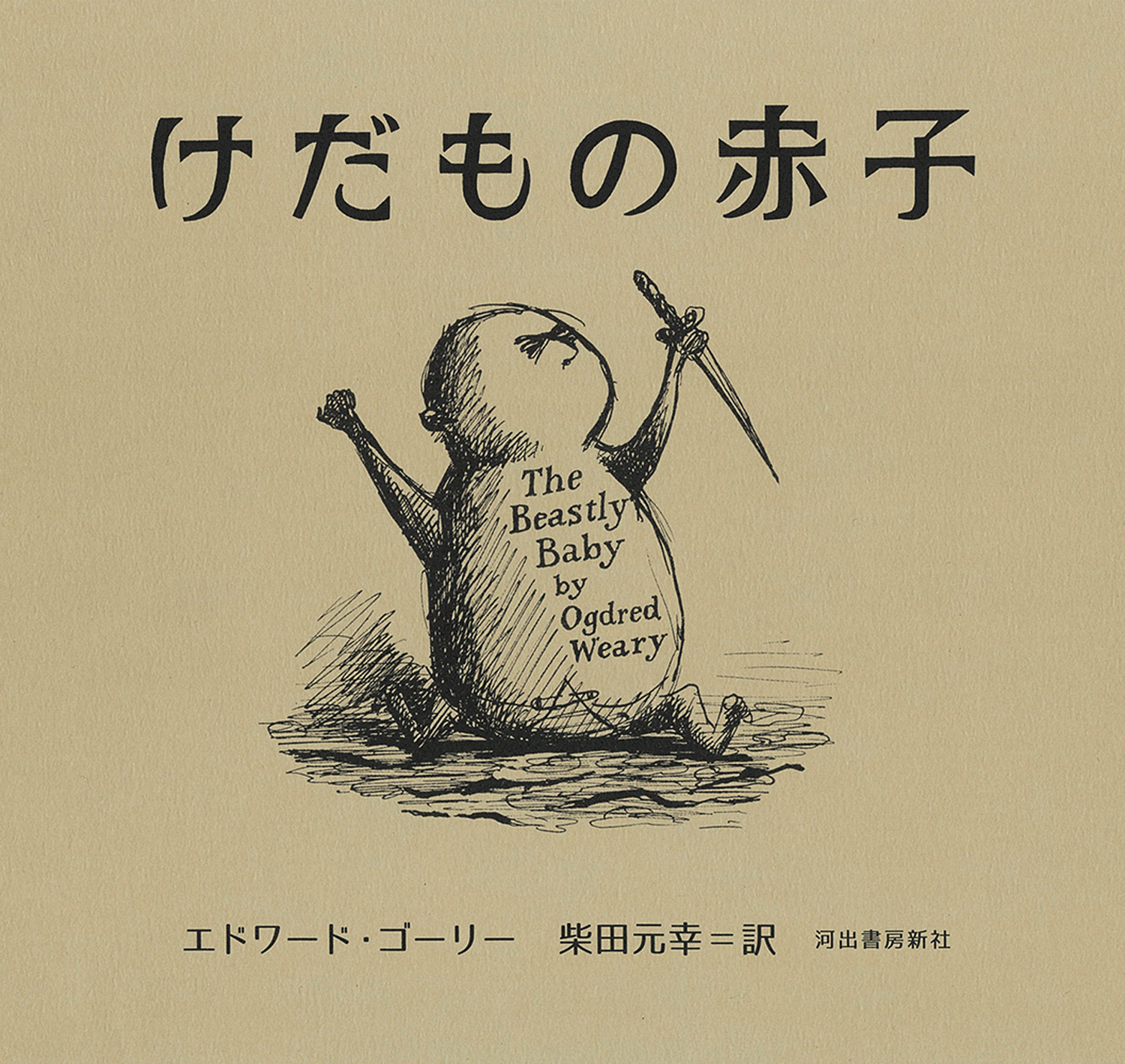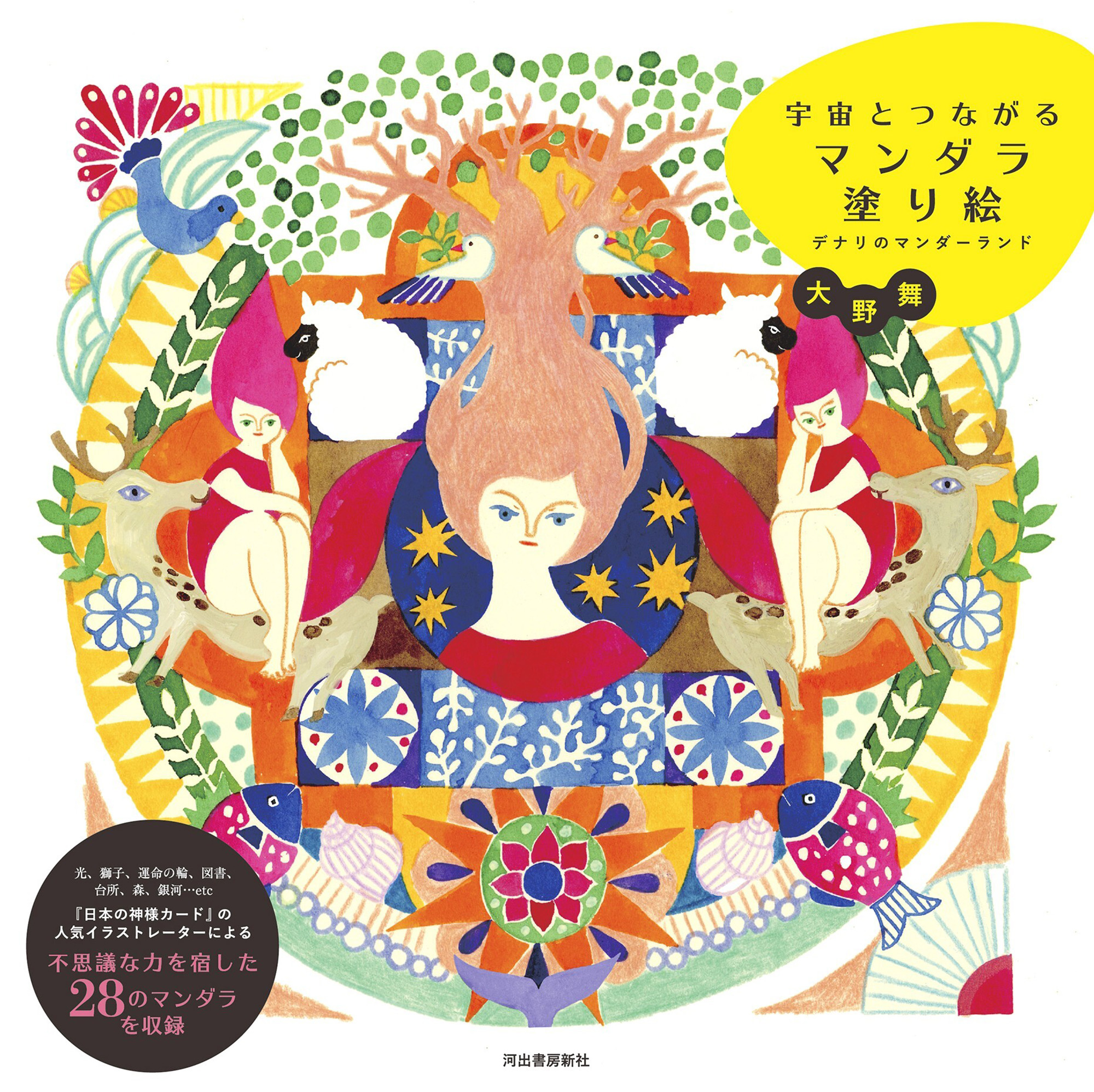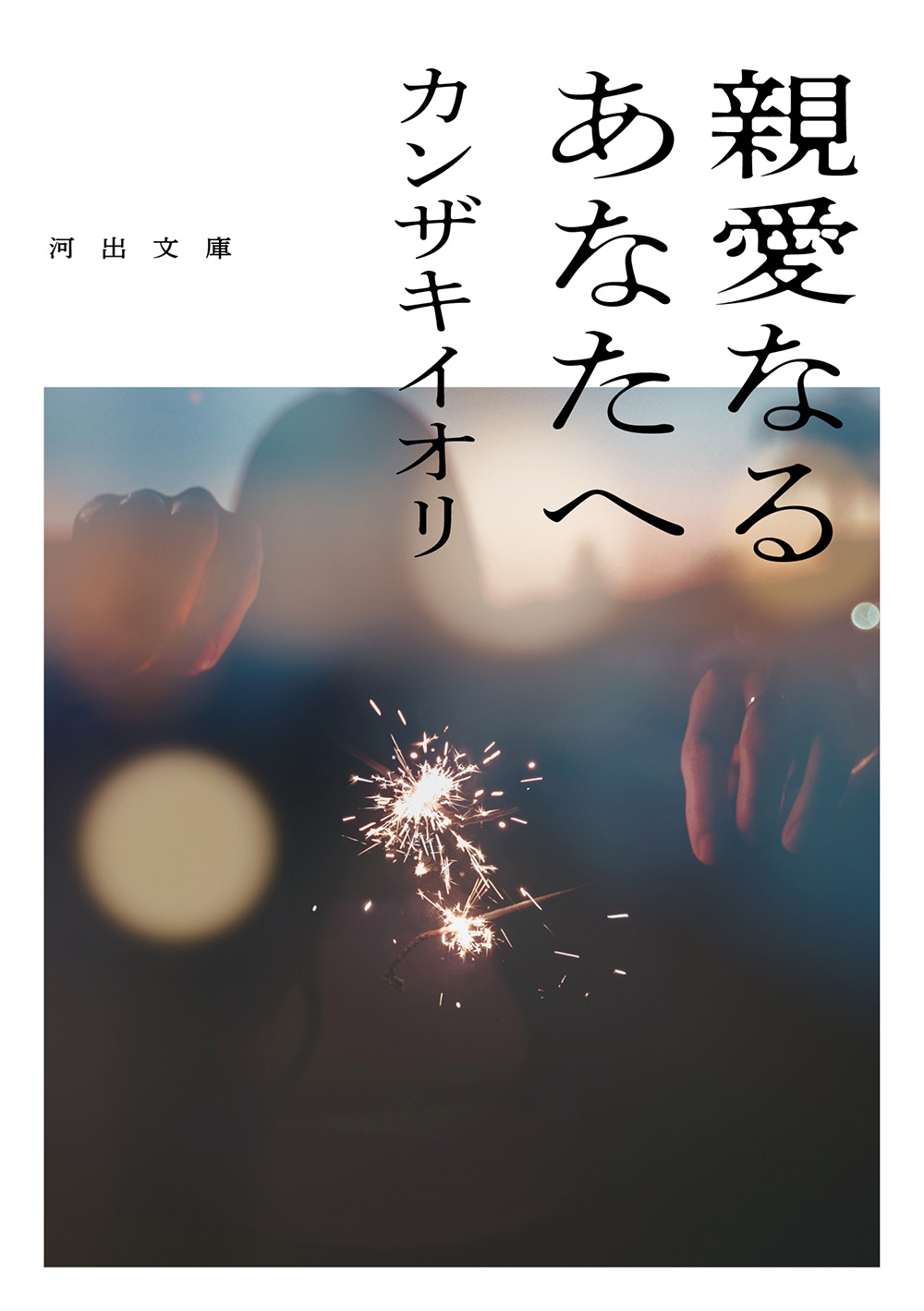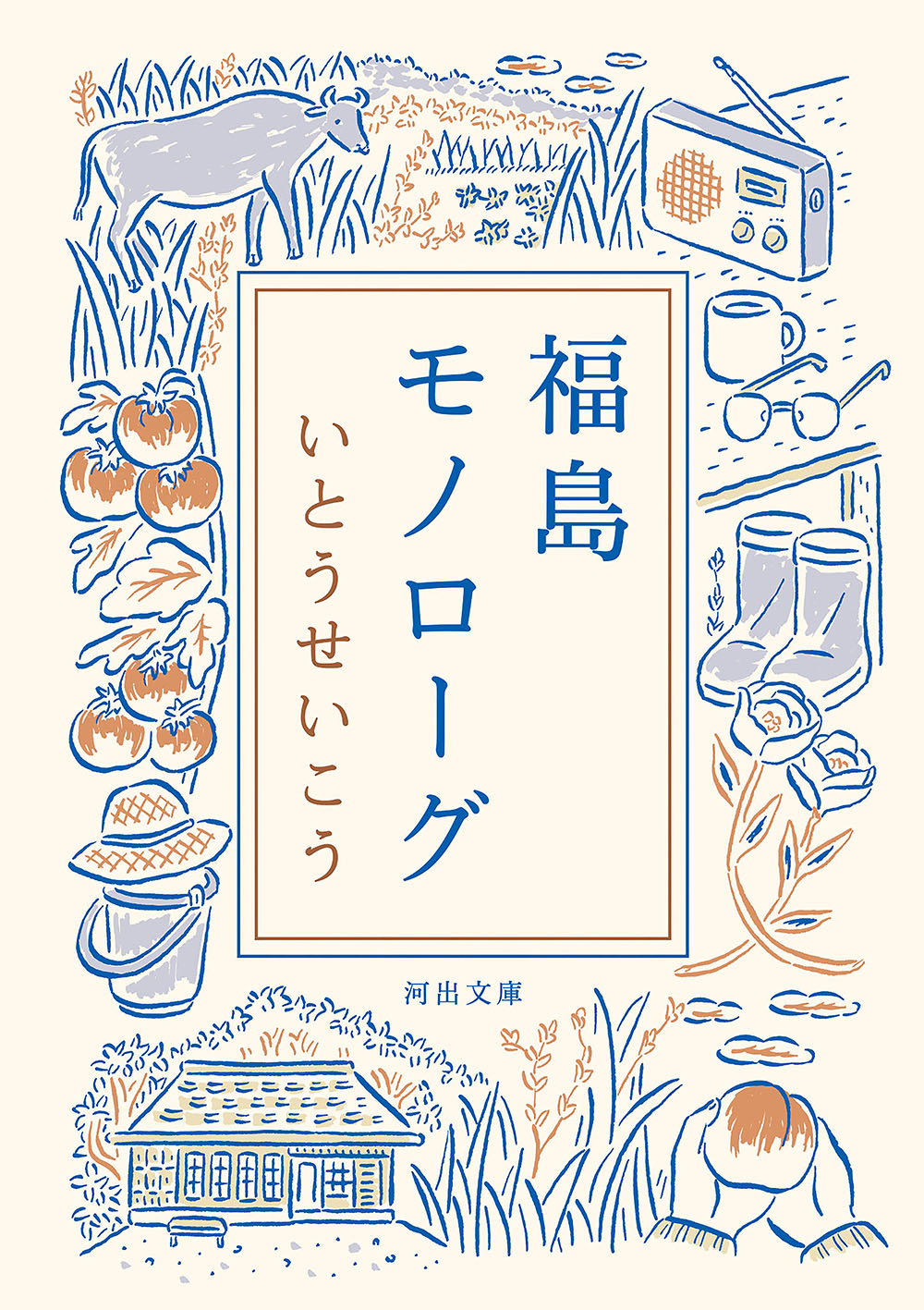ためし読み - 14歳の世渡り術
9歳で日本に来たクルド人の若者の困難とは――。いま知りたい、日本に暮らす難民・移民のリアルな声を集めた入門書から試し読みを公開
雨宮処凛
2025.10.02
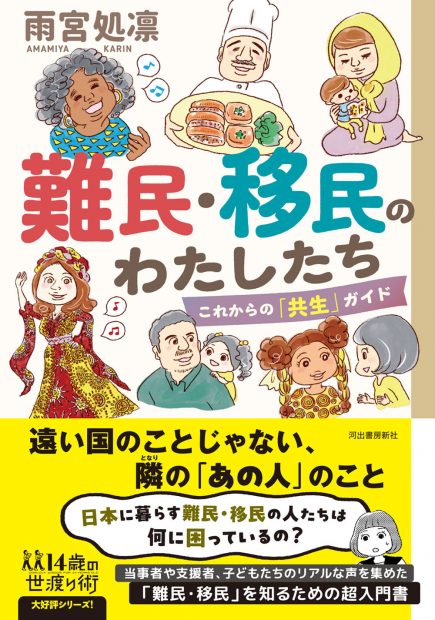
日本に暮らす100人に3人が外国人のいま、基本的な問いに答えながら、今後の共生を考える10代から大人まで学べる入門書『難民・移民のわたしたち――これからの「共生」ガイド』(雨宮処凛著)。
日本に暮らす外国人の数は増え続けていくと予想されており、2070年には10.8%、10人に1人が外国人という時代が推計されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」より)。
長年生きづらさや貧困をテーマとし、日本に住む外国人を支援する現場への取材や活動も続けている雨宮処凛氏だからこそ書けるリアルな実態には、「どこか遠い国の関係ないこと」ではなく、隣に暮らす「あの人」のことを想像し、自分ごととして捉えるためのヒントが詰まっています。
7月の参院選、 自民党総裁選(10月4日投開票)でも争点のひとつとなっている「外国人・移民問題」を考えるにあたり、9歳で日本に来たクルド人の若者を取材した章をまるごと公開します。
==↓ためし読みはこちらから↓==
今、日本に住んでいる外国人の子どもたちは何に困り、困難が多い中でどんな将来を望んでいるのか。そして時に投げかけられる心ない言葉に対し、どんなふうに思っているのか。
話を聞いたのは、幼い頃に来日、今は大学生になった20代前半の男子・アリさん(仮名)。彼はクルド人で、トルコから日本にやってきた。
*クルド人とは
「国を持たない世界最大の民族」と言われ、トルコやイラン、シリア、イラクなどにまたがって居住してきたクルド語を母語とする人々を指す。世界に約3000〜4000万人いるとされているが、独立した統一国家を持たず、各国で少数民族として迫害を受けてきた歴史がある。
■9歳で日本に来たアリさん
アリさんは2010年、9歳の時に母と2人で来日した。
父親はその7年前に、迫害を逃れて一足先に日本に渡っていた。以来、日本とトルコとで離れ離れになった家族は一切連絡を取っていなかった。お互いの安全のためである。
「年に1、2回、トルコのジャンダルマ(トルコの準軍事組織。国家憲兵)が家に来るんですね。それで父親がいないか、洋服を確認したり、私たちの携帯の履歴を見て連絡取っていないか確認したりするんです」
トルコでクルド人のための活動(トルコからの分離独立を求めるクルド人の武装組織・PKK(クルディスタン労働者党)とは無関係)に参加していた父親の行方を、ジャンダルマは追っていたという。このことで、父親は身の危険を感じ日本に渡って難民申請をしていたのだ。
そんなアリさんは9歳までトルコのある村に住んでいたそうだが、そこでの生活は不自由なものだった。
「当時は同化政策が強かったので、もう息苦しくて」
トルコによる、クルド人への同化政策である。ちなみに同化政策とは、同じ国の国民であるという前提のもと、力の強い方の言語や名前、宗教などの文化同化を強いること。
「例えば小学校では、入り口をくぐった途端、クルド語は絶対禁止でした」
通うのは全員クルド人なのにだ。少しでも話してしまうと、体罰が待っている。先生はトルコ人。トルコ語があまりうまく話せなかったアリさんは何度も体罰を受けた。ちなみにクルド語とトルコ語は語族がまったく違うので、習得するのは並大抵のことではないという。
■サッカー少年に立ちはだかる「仮放免」の壁
そんなトルコから9歳で日本にやってきたアリさん。日本の学校に通い始めるが、当然、日本語はまったくわからない。最初は戸惑い、学校にも馴染めなかったという。が、ある日クラスメイトがサッカーに誘ってくれた。身振り手振りで意思疎通し、一緒にゲームをするとたちまち打ち解けたという。それをきっかけにアリさんは人気者になっていく。教室の中では「アリさんに日本語を教える」のがブームとなり、そのおかげでみるみる日本語を身につけたというから、子どもってすごい。
そんな日々の中、彼が夢中になったのはサッカー。学校でもサッカーの上手い子どもとして注目を集めたが、「仮放免」(入管施設への収容を一時的に解かれているという状態を指す。「健康上または人道上の理由により収容を一時的に解除する」措置で、数週間から数ヶ月に1度、入管に「出頭」する必要がある)という立場は彼のサッカー人生にも暗い影を落とした。住んでいる埼玉県外への移動が許可を取らないとできないからだ。
「今は少し緩和されてるらしいんですけど、私の時は、絶対に行かないといけない場合しか許可が出なかったので、県外の大会に出られなかったんです」
どれほどサッカーが上手くても、埼玉県外の試合には出ることができない。それだけではない。簡単に移動できないことは、友人関係にも影響した。
「高校2年生の時、友だちとディズニーランドに行きたいってなって、みんなで集まって予定を決めたんです。けど、入管(出入国在留管理庁。日本人や外国人の入国、出国の審査をするのが主な仕事で、難民認定の審査もしている)の出頭日にそれを言ったら、『いや、遊びには行かなくてもいいでしょ』って。結局行けなかったんですが、友だちにそれを言ってもなかなか信じてくれなくて、ちょっと関係が悪くなってしまったり」
これはつらすぎる……。友だちとのディズニーも大事だけど、これが好きな相手とのディズニーデートだったら……。ちなみに自分が仮放免だとアリさんが知ったのは高校1年生の時。
「お母さんに『県外移動しないで』『入管に捕まる』とか言われてたのでなんとなくわかってたんですけど、それまでは、外国人はみんな同じって認識だったんですよ」
しかし、高校生になり、自ら入管に出頭するようになって初めて、すべての外国人に制限があるわけではないことを知る。一方、入管の職員に心ない言葉を浴びせられるようにもなった。
「入管にはサッカーやってることも話してたんですけど、『すごいチームからスカウトが来ても、君、就職が禁止だからダメだよ』って言われました。『どんなにサッカー上手くてもサッカー選手になるのは不可能、国に帰りな』って」
もし、自分だったらと想像してみてほしい。一番得意で夢中になっていることを、自分の実力とはなんの関係もないところで否定され未来を閉ざされる。私だったら心が折れ、世の中を恨んで自暴自棄になるかもしれない。だが、アリさんは違った。猛勉強を始めたのだ。
「それまで勉強はちょっと苦手だったので、成績を上げて認めてもらおうと思いました。寝不足で倒れるくらい勉強したら成績は上がりました。サッカーは、高校1年生でやめました。今やめて、他のものに興味を向ければ立ち直れるなって気持ちがあったんです」
断腸の思いで諦めたサッカーの道。ちなみにアリさんには日本で生まれた2人の弟がいるのだが、弟たちは兄の影響でサッカーが大好き。1人は選手を目指しているという。
「弟たちはまだ小学生ですけど、私のようにはなってほしくないと思います。全力を出してサッカー選手になれなかったら仕方ないんですけど、在留資格が理由でなれないのは嫌だなって。私はいまだにモヤモヤしていて、今もサッカーをみると悲しくなります」
その言葉を聞いて、なんだか泣きそうになった。アリさんはこれまで、どれほど悔しい思いをしてきただろう。しかも特殊な境遇ゆえ、「わかる」と共感しあえる人もなかなかいないのだ。
■「犯罪者の息子、帰れ」と言われて
入管には他にも嫌な思い出がある。
アリさんが小学生の頃、父親が収容されてしまったのだ。仮放免の人が突然収容されるというのは残念ながらよくあることだ。が、そのことがクラスメイトたちに知られてしまう。その時通っていた学校に、クルド人はアリさんだけ。外国人が捕まる=誰かを殺したと思われ、仲間はずれにされてしまったという。
「私自身もなんでお父さんが捕まったのかわからない。給食の時、同じ班で机を向かい合わせにして食べるんですけど、私だけ追い出されたり、『犯罪者の息子、帰れ』って言われたりしました」
学校に行くのがつらくなり、一時期は朝、家を出て昼過ぎまで公園で過ごしたという。家に先生から電話が来たものの、母親は日本語がわからない。
「なんて言われた?」と聞かれ、「アリさんがとても優秀です」という内容の電話だったと噓を伝えた。のちにバレてられたものの、息子がいじめられていると知ったら母親を悲しませてしまうという一心から隠し通したという。
親が日本語ができないからこそ、いろいろと誤魔化せてしまう。これも外国人の子どもあるあるではないだろうか。しかし、それは時に取り返しのつかない事態を招く危険性も孕んでいる。
■自らの中にあったクルド人への偏見
そんな自らの境遇から、アリさんは自分が置かれた状況――クルド難民についてや、トルコの状況など――について調べるようになったという。
ちなみに中学3年生くらいまで、アリさんは自らを「トルコ人」だと自称していたというから驚いた。同化政策が強いトルコの学校で、「クルド人は悪い」と教えられてきたからだ。
が、いろいろなことを調べる過程で気づいたのは、自分がトルコで受けた教育がナショナリスト(国家主義者)を育てるものだったということ。
「授業でもクルド人は悪いと教えられていたし、トルコでは『唯一のトルコ』というドラマが有名でした。ドラマに出てくるクルド人はテロリストで、そのテロリストに勇敢なトルコ兵が立ち向かい、みんなを助けるという内容です。クルド人のテロリストは、『よし、今日は暇だし、人でも殺すか』と言って子どもや母親を撃つ。そこにトルコ兵がやってきて助ける、みたいな。それを見ていて、『私もトルコ人になりたい』『トルコ兵はカッコいい』という気持ちがありました。だから中学3年生までは、クルド人がたくさんいる蕨にも行かないようにしていたんです。クルド人と関わらないようにしていたし、自分のことを人にはトルコ人だと言っていました」
が、2015年1月に起きたある事件がアリさんに大きな影響を与える。シリアで、イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」に拘束された2人の日本人、後藤健二さんと湯川遥菜さんが殺害された事件だ。
「あの事件を受けて、イスラム教への反発を口にする人が増えました。学校でも『イスラム教、やばいよな』と言う人がいたし、フランスでもイスラム教の女性への暴力がありました。そういうものを見ながら、『一部の人が悪いのに、なんで全員批判されるの?』と思いました」
そうして、自分も同じことをしていると思ったのだという。
「3000〜4000万人以上いるクルド人を、ドラマで見たテロリストのイメージで悪者にしている。それに気づいてから、自分はクルド人だって言うようになりました」
そのことは、家族との関係も変えた。それまでクルド語で話しかけてくる父親にトルコ語で返していたのが、クルド語で話すようになったのだ。クルド人という自覚を持ってからは、父親との関係は劇的に深まったという。
■「牢屋 から解放された気持ち」 約14年間の仮放免生活が終わる
そんなアリさん一家の運命を大きく変える出来事が2023年末、あった。
なんと家族全員に在留資格が出たのである。
この背景には、23年8月の政府の決定がある。日本に生まれ育ったものの在留資格がない18 歳以下の子どもに在留特別許可を与えるというものだ。その数、全国に201人。このうち小学生から高校生までの子どもについて、親に重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば、親子に在留特別許可が与えられることになったのである。ちなみに在留資格がない外国籍の18歳未満は23年9月時点で295人。このうちの201人が日本生まれなのだ(*1)。
以降、そのような境遇の家族に在留資格が与えられているのだが、アリさん一家もその対象となったのだ。
こうして、アリさんの約14年間にわたる仮放免生活にやっと終止符が打たれた。
「最初の1週間は信じられなくて、朝起きて、すぐに在留カード見てました」
アリさんは興奮を抑えきれない様子で話す。すでに難民申請を3回しているので、24年6月の改正入管法施行後はアリさんも強制送還の対象になりえる状態だった。が、これでひと安心だ。県外移動も自由にできるし、アルバイトも就職もできる。健康保険にも入れるし銀行口座だって作ることができる。弟はサッカー選手という夢を、在留資格を理由に諦めずに済むのだ。
「大げさだと思われるかもしれませんが、牢屋から解放された気持ちです。埼玉県自体が、私たちが入れられている収容所みたいな感じでした」
その言葉を聞いて、映画『翔んで埼玉』(2019年)を思い出した。この映画では、埼玉県人が東京都民から迫害を受けており、通行手形がないと東京に出入りすらできず強制送還される。「そんなバカな」とみんなが笑う「通行手形」は、アリさんにとっては実際に存在するものだったのである。
しかし、どんなに理不尽な制限でも、決してルールを破ることはしなかった。
「これまで何度か、賞金が出るサッカー大会に誘われました。友だちから『賞金100万円の大会があるからチームで出よう』とか。でも、仮放免者は報酬を得てはいけない。友だちには『バレないでしょ』って言われたけど、これからも日本に住みたいし、日本の法律や入管のルールを守って在留資格をもらって安定した生活をしたいから、出るわけにはいかない。県外移動も『バレないでしょ』って言われたこともありますけど、警察に職務質問されると『在留カード見せて』って言われるんです。それで仮放免許可書を見せると、入管に確認するんですよ」
そうすれば、許可を得ずに移動したことがバレてしまう。
そうやって日本の法律と入管のルールを守ってきたアリさんに、やっと出た在留資格。
「今は職務質問が楽しみです」と悪戯っぽく笑った。
■やっと頑張れる、やっと未来の計画ができる
それにしても14年間、よく仮放免で耐えてきたものである。
親も仮放免で働けなかったわけだが、生活面に関しては、親戚の援助があった。日本で事業を成功させた親戚がいたのだ。アリさんの大学の学費も払ってくれているという。そんな自らを、「在日クルド人の中でも恵まれている」とアリさんは言う。親戚との繫がりや援助がない人の中には、身体の不調を放置した末に重い病気になった人もいるからだ。
一方、日本人であれば使える奨学金が利用できないなどの不利益もあった。
「条件は全部満たしてたんですけど、住民票がなくて落とされちゃいました」
これまでは保険証もなかったので、医療費は全額自己負担。今も分割で返済している医療費があるという。
「お父さんが耳の病気で、その手術に120万円かかって今も返済しています。お金がかかるから放置してたんですけど、このままじゃ脳に支障をきたすということで手術して」
もともと父親の耳が悪くなった原因は、トルコで軍隊にいた時に受けたいじめだという。耳の鼓膜を破かれるほどの暴力を受けたのだ。以来、耳の不調を抱え、日本に来てからは片耳が聞こえなくなっていたものの、保険証もないため放置していたのが悪化したのだ。
しかし、在留資格が出た今、父親も、そしてアリさんも働くことができる。
「これからはどんどん払える」と嬉しそうなアリさん。
「やっと自由というか、一番大きいのは、日本での未来が安定したことです。これまでは、あんまり夢を持たないようにしてたんです。どうせまた仮放免者だから、で終わっちゃうと思って。だから、今できること、今やりたいことを全力でやるようにしてました。でも、在留資格を持ったらやっと未来の計画ができるんですよ」
在留資格が出たことで、「一気にやる気が出た」という。
「今、1日10時間勉強してます。朝6時に起きて、全部スケジュール決めて、1日14、5時間勉強することもあります。在留資格をもらったことが原動力になって、もう、やっと頑張れる、みたいな」
ちなみにアリさん一家は2023年8月の政府の決定によって在留資格が出たわけだが、在日クルド人を支援する埼玉県の任意団体「在日クルド人と共に」理事の松澤秀延さんによると、成績の良し悪しも在留資格が出る出ないに関わってくるという。
「本当に?」と思うが、アリさんは、入管に言われて在学証明や成績表、賞状などを出頭時に持参していたそうだ。この人は日本にいていい、いちゃダメというのがどういう基準で判断されているかの実態は闇の中だが、人道上の理由だけでなく、子どもの成績が「ここにいられるか否か」に関わるなんて。人生すべてを人質にされているみたいでなんだか怖い。成績が悪いことが、場合によっては強制送還に繫がりかねないのだ。
ちなみに24年3月、入管は非正規滞在外国人に在留特別許可を与える際、可否を判断するための新たなガイドラインを公表したのだが、そこには「子どもが日本で相当期間教育を受けており、親が地域社会に溶け込んでいる」「無国籍で、どこの国にも送還できない」などと並んで「社会、経済、文化の分野で日本に貢献」という項目がある。人道的な面ではなく、「日本に貢献するかどうか」が日本にいられるかどうかの物差しになることには、専門家からも疑問の声が上がっている。役に立つ人間じゃなきゃ存在を許されないなんて、これほど堂々とガイドラインにしちゃっていいのだろうか?
■将来は難民研究や教育に関わる国連職員になりたい
一方、アリさんは根っからの勉強好き。
「今、大学の勉強がすごく楽しいです。気づいたらAプラスをたくさんもらってました」
優秀なのである。もし、もっと前に在留資格が取れていたらもっと優秀だったのではとふと思う。それにしても、9歳まではまったく日本語がわからないというハンディを背負いながら、よくここまで頑張ったものだ。アリさんの通う大学は、難関大学として有名だ。
今、アリさんは大学で平和構築や難民・移民について勉強しているという。特に移民の1・5世について研究しているようだ。
「1・5世って、どんな立場ですか?」
そう聞くと、「子どもの頃に日本に連れてこられた人」という答え。まさにアリさんのような立場を「1・5世」と呼ぶのだと、私はこの日、初めて知った。日本で生まれた弟のような立場だと2世、そして両親のように自分の意思で来た人たちが1世だ。
当事者が、そうして難民・移民問題を研究するとはなんて画期的なことだろう。
そんなアリさんに将来の夢を聞くと、「国連職員」という答え。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)で働き、難民研究や教育に関わりたいという。
「教育を受けることで自分の置かれた立場が理解できますし、自分の状況や権利がわかる。それ以外にも、まず読み書きができると仕事ができる。だけど、今の難民キャンプでは緊急支援が重要視されています。そもそも難民キャンプは一時的なものなのに、永久化して、村になっている。それを国連が放置している」
話しているだけで、彼の知識と熱量に圧倒される思いだ。
国連職員になる前には、海外でボランティアの経験もしたいという。論文も書きたいし、もっともっと勉強したい。目を輝かせて語る彼を見ていると、世界で活躍する人物とはこういう人なのだろうと思えてくる。
在留資格を得られた今、弟たちだってなろうと思えばサッカー選手になれる。
「そうですね。今までは弟たちに自分が仮放免だと気づかせないために、家の中では絶対に話しちゃいけないというルールがありました。気づいてしまうと、自分が他の人と違うと思ってすごく嫌な気持ちになるので」
その言葉を聞いて、「仮放免」という立場がいかにアリさん一家の足枷となっていたかを思い知った。そしてアリさんが兄として、どれほど弟たちを守ってきたのかも。
さて、こうしてアリさん一家に出た在留資格だが、法に反することなどがなければこのまま更新されていくという。そうして10年経てば、永住権が得られる可能性がある。日本で安定して暮らしたいからこそ、父親はルールに従うよう、いつもアリさんたちを諭してきた。
また、在留資格が出たら働くことができるわけだが、そうなると納税義務が発生する。
「ノートを作って、税金の記録もつけています。1回も違反がないように税金を払って、市役所ともいい関係を作って。お父さんの場合は20年くらい在留資格がなかったので、やっと安定した。それを失いたくないって気持ちがすごく強いんです」
■国という「後ろ盾」がないということ
各国の難民事情にも詳しいアリさんだが、そんな彼に、「この国の難民政策はいいという国はありますか?」と聞くと、「オーストラリア」という答えが返ってきた。
オーストラリアに渡った親戚が1年で難民認定され、オーストラリア国籍を得て安定した暮らしをしているのだという。
最近、オーストラリアが自国の国籍を持つ人を守るということを痛感する出来事があった。
それはその親戚がハワイ旅行に行った時のこと。どうやらオーストラリアのトルコ大使館からハワイのトルコ大使館に連絡がいったらしく、家族全員がハワイで拘束されてしまったというのだ。
最悪、そのままトルコに連れていかれることもありえたが、そうはならなかった。オーストラリア政府は彼らを守ってくれたのだ。そうして、無事に帰国。
「他の国ではそうはならなかったかもしれませんが、オーストラリアは後ろ盾になってくれるんだと思いました。そもそも私たちクルド人にはクルドという国がありません。私はトルコで生まれましたが、トルコではクルド人のアイデンティティを主張すると、それだけでテロリストみたいに見られてしまう。それだけでなく、クルド人に対する抑圧と同化政策が強い。それで逃げてきても、日本政府もトルコ寄りなので後ろ盾にはなってくれない」
その言葉を聞いて、生まれながらに日本という国籍がある自分が、どれほど知らずに守られているかを実感した。
ちなみに、「クルド人のアイデンティティを主張する」とテロリストとみなされかねないわけだが、それには「クルドの旗を持つ」「クルドの民族衣装を着る」なども含まれるという。それだけでPKKの支持者とみなされ、捕まった人も多くいるそうだ。
■偏見はやめて一人一人を見てほしい
そんなクルド人への迫害だが、昨今、日本でもネット上でクルド人へのヘイトが散見されるようになっている。
「嫌な気持ちになりますけど、でも、応援してくれる日本人とか仲良くしてる日本人の方が圧倒的に多いので、仕方ないと思って無視してる感じです」
ただ、「決めつけないでほしい」とは切に思う。
「よくSNSでは『クルド人はこうだ』って決めつけることが書いてある。一部のクルド人を見て、『クルド人は悪い』とか、『クルド人死ね』『クルド人ゴミ』とか書いてあるのを見ると、なんで私たち全員がそう言われなきゃいけないのって思います。もちろん、罪を犯したクルド人は罰を受けるべきです。でも、クルド人全員を強制送還しろとかは、どうして一緒にされなくちゃいけないのって」
一方、「クルド人は難民じゃない」などという声に対しても言いたいことがある。
「トルコに帰れないって理由がなかったら帰ってるんですよ。さすがに14年も仮放免で生きるのはつらいです。サッカーだって、トルコに帰れば国籍があるからサッカー選手にもなれるんです。それを諦めてまで日本に残ってるのは帰れないからです。理由があるんです」
今、心配なのは、小学生の弟たちがこの先、ひどい言葉をかけられたらということ。
「私は別にいいんです。もう慣れてるというか、SNSでよく見るので。でも弟たちはまだ子どもだし、気持ち的に頑張れなくなってしまう可能性もあるので本当にやめてほしい」
どこまでも弟思いのアリさんである。でも、アリさんだってまだ20代の若者だ。彼の背負ってきたものの重さは想像することしかできないけれど、厳しい環境がアリさんをここまでのしっかり者にしたのだろう。
そんなアリさんに、日本の一人一人に望むことを聞いてみた。
「集団に対して偏見を持たないでほしいですね。例えば『日系ブラジル人はこうだ』みたいな。頑張ってる日系ブラジル人はたくさんいるのに、1人でも罪を犯すと全員が罪を犯しているみたいに言われてしまう。クルド人においてもそれが言えるんです。だから、偏見はやめて、一人一人を見てほしい。そしてクルド人とか仮放免者とか、そういう視点で見るんじゃなくて、同じ人間という視点から見てほしいですね」
(*1) 「目を輝かせる子、不安を深める子…「在留特別許可」めぐり外国人の子どもたちに明暗 その「線引き」は」東京新聞ウェブ 2023年12月18日掲載
https://www.tokyo-np.co.jp/article/296064
========================
■書籍情報
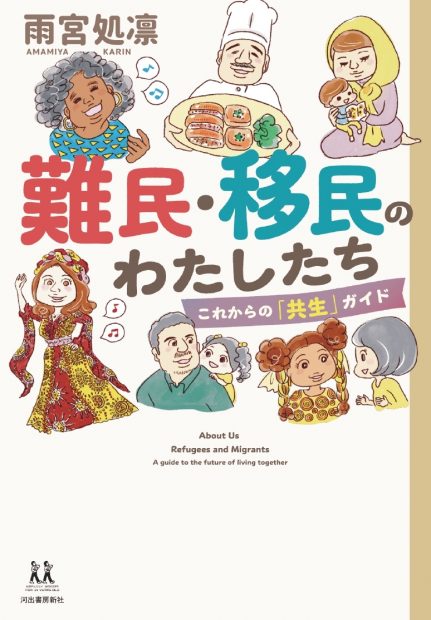
『難民・移民のわたしたち――これからの「共生」ガイド』雨宮処凛
いま、日本に暮らす難民・移民の人たちは何に困っているの? 当事者や支援者、子どもたちのリアルな声を集めた「難民・移民」を知るための超入門書。
*目次より
第1章 どうして難民・移民の人たちは日本にいるの?
〇CASE1 ミョーチョーチョーさん〜ミャンマーから
〇CASE2 アリーヤさん(仮名)〜アフリカのある国から
〇CASE3 クラウディオ・ペニャさん〜チリから
第2章 難民・移民の人たちはどんな生活をしているの?
〇困窮した外国人を支援する大澤優真さんに聞く
〇在日クルド人と共に」理事 松澤秀延さんに聞く
第3章 難民・移民の子どもたちは何に困っているの?
〇CASE1 エリシャさん(仮名・17歳)
〇CASE2 アリさん(仮名・20代前半)
第4章 日本の難民・移民政策って? 入管ってどんなところ?
〇移民問題を研究する高谷幸さんに聞く
〇どうすればウィシュマさんを救えたのか――弁護士・指宿昭一さんに聞く
第5章 難民・移民の人たちに、私たちができることは?
――「難民・移民フェス」の仕掛け人・金井真紀さんに聞く