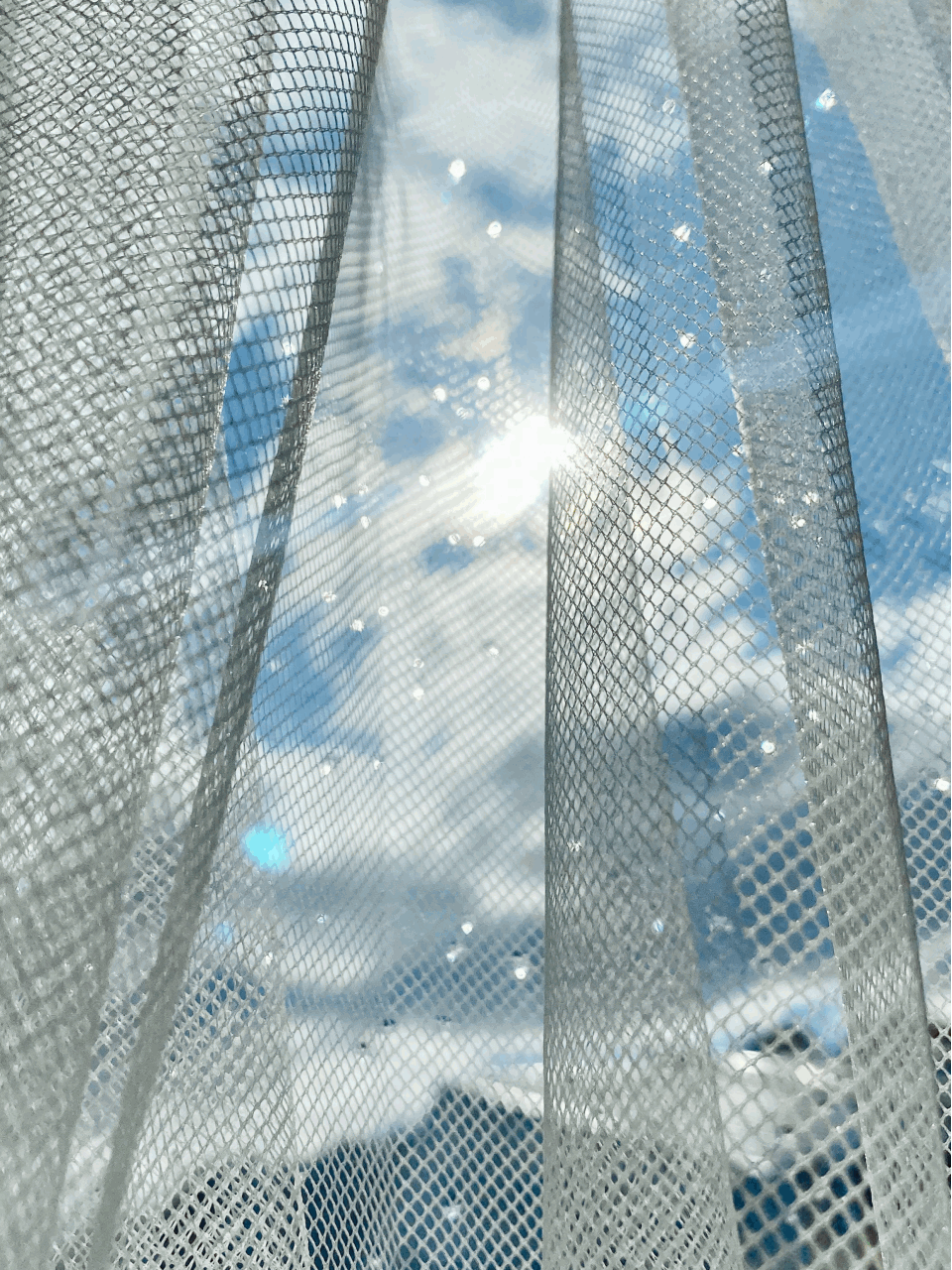ためし読み - 文藝
「文藝」冬季号掲載、水沢なお「うみみたい」試し読み
水沢なお
2022.10.06
卵生生物の生殖をケアする〝孵化コーポ〟でバイトする美大生のうみは、才気煥発な同級生みみが抱える「生まれたくなかった」意志に触れ―。中也賞受賞の気鋭の詩人、初中篇。
===↓試し読みはこの↓へ===
うみみたい
水沢なお
タクシーの中で光る葉っぱ。馬のお腹はいるかみたい。歩道のペールグリーン。にんげんの好きになりかたってわからない。好きなのに、ずっと好きじゃない。
「あ、毛が生えてる」
車窓の外、揺れる光の群れが足元を照らす。ひとつの毛穴から、にょきと二本生えている。わたしの毛。玄関でサンダルに素足を通したときには、気がつかなかった。
「大丈夫、わたしも生えてる」
そう言って、みみはわたしの白いビルケンシュトックに、自分の右足を寄せた。みみが履いているシースルーの靴下、透けた足の指のふもとに、さらさらと毛が生えている。
「まあいっか、四月だもんね」
「うん。四月だから」
頬の少し高いところに流れていく景色を反射させながら、みみはまっすぐにあくびをした。歯に詰まっているのか、さっき一緒に食べた、ブルーベリージャムのにおいがこちらにまで届く。
「やっぱり、みどりにするべきだったなあ」
「なにが?」
「むむの目」
むむは、山と山の子どもだ。手のひらに乗るくらいの、まだちいさな山。くまのような耳の生えたくまむむ。かにのように横歩きのかにむむ。しんしんと降り積もる雪のように真っ白いゆきむむ。むむはその土地の記憶をなぞったかたちでうまれてくるのだった。
家を出る直前まで、みみはむむの目をつくっていた。透明なシリコン型に、レジンを流し込んでつくる。ひとつひとつ、丁寧に。
キャンバスのなかの山に点々を描いた。それを見て、いきものみたい、とみみが言ったのがはじまりだ。油絵だったものを、輪郭のはっきりしたキャラクターとしてデザインしてくれたのは、みみ。Twitterの運営は、わたしがしている。最近、フォロワーが二千人を超えた。月に一度、ネットショップで販売するむむぬいぐるみは、三十個ほどが即完売するようになった。むむ、はいつの間にかむむとしてそこにいて、だれがそう呼びはじめたのか思い出せなかった。
みみの手のひらのうえで、むむは心地よさそうに、淡く燃える木々を見ていた。向かい側に座るお揃いのTシャツを着たふたりが、それを見てくすくすと笑っている。その重なった頭のかたちを見ていると、中学の同級生だったはぎちゃんのことをなぜか思い出す。
駅から五分ほど歩いたところにある河川敷に、レジャーシートを広げる。よく晴れているから、薄くバターが塗布されたように川や芝生がてらてらと艶めいている。弁当が入ったリュックは木陰に置いて、スケッチブックと水彩絵の具を取り出す。みみはマックブックエアー。むむをふたりの間にある日を浴びた石のうえに置くと、わたしはクロッキーを、みみは動画の編集作業をはじめる。
「川には、電波がないのがいい」
「そうだね」
「誘惑されないから」
「みみも誘惑されることあるんだ」
「あるよ」
みみは、ぱちぱちとキーボードを叩いている。ゲームの実況動画に弱いのだと言っていた。倍速で再生すると人間の声が雨音のように聞こえて、より心地が良いのだという。
わたしたちは、一年前まで同じ美術大学に通っていた。みみは、九月が締め切りの岡本太郎賞への公募に向けて、わたしは八月にあるグループ展に向けて、それぞれ制作を続けている。みみは、大学を卒業してからほとんど絵を描いていない。いわゆる、メディアアートとか、インスタレーションと呼ばれる表現方法に興味が傾いている。
「これはなに?」
みみのパソコンを覗き見すると、画面のなかには地球が浮かんでいた。3DCGで表現されているようでかすかにグリッド線が見える。そこに、ちいさなうさぎのような、錠剤のような白い粒がふたつ、宇宙船の軌道にあわせてにゅっと現れ、ぱっと薄紫色の布を広げると、地球をまるごと覆い隠した。
「これは、ありとあらゆる受精を阻止するシーン」
「へえ」
みみがマウスを動かすと、地球はあらゆる衛星と距離を保ちながらくるくると廻った。うつむくみみのまつげ。まぶた。スケッチブックをひらいたままそれを見やると、肉体のかたちがぎゅっとわたしのなかに滑り込んできて、光を混ぜる。人間を描いたらいけないんだ、境目を描写するだけだ。そのかたちを、美しいと思わないための訓練を、わたしは繰り返す。
「うみって、作品には人間を描かないよね」
「人間を描くのってこわいじゃん」
「こわい?」
みみがこちらを見た。額のうえに木漏れ日が落ちると、眩しそうに目を細める。
「うん。こわい」
「でも、こうやって、毎日人間のすがたを描いて、肉体を追いかけ慣れた手で木とか山とか川を描いて、それがわたしと身体の、ちょうどいい距離感だから」
スケッチブックをめくる。水を含んだ筆で撫でた、紺色の影がそっと落ちている。
「まあ、わたしもこわいから。絵を描くこと」
みみは言った。
「そうなの?」
「いいわけができないから」
小鳥の声がきこえる。ちいさな羽とくちばしは草むらに飛び込み、細い茎のうえで尾を震わせる。土をつつく。丸くて茶色い腹をもつひと。橋の下に巣をつくるひと。ひなの世話をするひと。釣りびと。ウクレレを弾いているひと。おそろいの黒いTシャツを着て合気道の練習をしているひと。首の後ろに腕をまわして、ひとに触れる練習をしているみたいだ。
なにも知らない。
みみの頬に止まる緑色に輝く虫、誕生日も、名前も、きょうだいの名前も、どのようにうまれてここにいるのかも知らない。粉っぽい指を伸ばし翅をつまむ、むに、と指に伝わるやわらかな感触に、わたしは黙ってしまう。
「喧嘩したくないからさ」
「うん」
「全部、はんぶんこにするのはどうかな」
みみは川を眺めていた。
「むむは、わたしたちふたりのもので、でも本当はだれのものでもないの」
「いいね、それ」
「むむも、それでいいよね」
むむは、みみの膝のうえで黙っていた。山でうまれたむむは、まだ人間の言葉がわからない。
お山座り、をする。シートの下のやわらかな草の感覚を尻で覚える、抱えた膝下に生えた産毛はモールのような硬度を保ち、枯れ草を落とすように手で払っても、そこに毛はある。当たり前にある。でも時折笑ったりする。
「お腹すいたね」
みみと、むむと、ずっと三人でいたい。透明なくまのヘアクリップに、川の水面がきらきらと反射していた。水色の髪、ぴんぴんと跳ねた枝毛。わたしは、みみの大切にしているすべてになりたい。
「春菊とかがいいのかな」
わさ、と艶のあるビニールのうえから葉の束を撫でたので、うんと頷いた。爪先が泥で汚れていた。クックパッドをひらいたままのスマートフォンを片手に、春菊の重みが増したショッピングカートを押している。みみがすぐ隣にいるのに、意識は発光する画面の奥に吸い込まれていく。【無限ループ確定】レモン鍋、というレシピを見つけてから、はやくそれをつくりたくて仕方がない。料理はそう楽しい作業ではなかったが、ふたりで鍋をつつきながら、互いの好きな映画を見て、その感想をぽつぽつと語り合う時間が待ち遠しい。
「あと、レモンと、豚バラ肉と、白菜と、大根おろしが必要らしい」
「うん」
スーパーマーケットに行くと、あらゆる生活の気配とすれ違うので、わたしはそれをくんくんと嗅ぐ。目の前でみかんを何個買うか悩んでいるふうふ、と思わしきふたり組はきょうだいのようによく似ている、きっと犬を飼っている。生ぬるく赤い腹をした、かしこくてすっぱい犬が、いちじくが植えられた庭のうえを駆け回る。鏡張りの柱の前を同じような背格好のふたりが通り過ぎる、双子の犬みたいで、そのあとをついていくと、駆け回る庭のないわたしたちの家にたどり着く。
去年の五月、みみのアトリエを貸してもらうことになった。香川での滞在制作の間、ビカクシダの水やりをしてくれる人を探しているというので、〈世話したいです〉とLINEを送った。卒業後、自分のアトリエがまだ見つかっておらず、そのくせ公募に向けて100号のでかい絵を描きたくなっていたわたしは、広い作業場を探していた。みみのアトリエは、築五十年近いモルタル木造二階建ての一軒家で、一階は常にブルーシートの敷いてあるアトリエとして、二階は居住スペースとして使用されていた。みみのとなりの部屋はがらんとした空室で、そこにホームセンターで買ってきた薄手のマットレスを敷いて寝た。みみが選んだであろうカーテンや机、皿やマグカップの色合いは薄緑で統一されていて、どれも不思議とわたしの手に馴染んだ。七月になって、お土産を持ったみみが香川から帰ってきた。小豆島そうめんを二人前茹でて一緒に食べた。わたしが世話をしていたビカクシダを見て「つやつやじゃん。うれしい、ありがとう」と礼を述べたきり、特になにも言ってこないので、互いに隣り合う部屋で眠った。さらに一ヶ月ほど経っていた。その日は、汗ばむような蒸し暑い日で、わたしたちは向かい合って鍋を食べていた。暑い日に冷たいものを食べると心地が良いことは知っていたが、熱いものを食べると疲れることにはまだ気がついていなかった。
「わたし、帰らなくてもいい? もちろん、家賃も払うし、家事も分担するし、全部はんぶんになったらすごくいいと思う。そのぶん、美味しいもの食べたり、画材を買ったりできると思うし」
絵が完成したら帰るから、と言い張り、わたしはみみの家に居座っていた。スーパーで買い物をして勝手に料理をふるまうことで、家賃や光熱費を払っていないことの罪悪感はなんとなく紛れていたが、もうそろそろ限界のような気がしていた。
「うん。じゃあ、まだ帰らなくていいよ」
みみは豆腐を箸で割りながらそう言った。
「まだ?」
「うん、しばらくはここにいてもいいよ」
そっか、と言いながらわたしは帰りたくなかった。メリットは提示してきたはずだった。夜勤が多いみみの代わりにゴミ出しができることとか(はじめて家に来た日はゴミ袋で溢れていた)、一般的な同年代の人間よりは恋愛や結婚が理由でこの家を離れていく可能性が低いこととか。
「できれば、ずっとここにいたいんだけど」
みみは、思い悩んでいるのか口を閉ざした。ぐつぐつと鍋が煮える。
「じゃあ、わたしに誓って」
「なにを?」
「人間を愛さないことだけ誓って」
スーパーの冷凍庫のひりついた霜のにおいを浴びながら、わたしはいまでもその言葉の意味を考える。凍った剥きえびを手に取る。ひとはひとを愛するためにうまれてきたのだと、そういういきものになるのだと、疑いもせずこれまで生きてきた。わたしには、その運命を受け入れる覚悟があって、だけど愛のすべてと折り合いがついているわけでもなかった。やがてセックスへと流れ着くのかと思うとほとんどの恋愛は恐ろしかった。だからこそ、そうなり得ない親密さはどこまでも心地が良かった。
みみと一緒にいると、人間であるとか、フリーターであるとか、女であるとか、そういった自分の属性を忘れることができた。よく食べ、よく考えるけものとして、絵を描く愉快な惑星として、窓辺のカーテンに染み込んだ山として存在することができた。でも、みみがそばにいないと、わたしはそれを忘れてしまう。剥き身を持つ指先が冷たくて痛い。わたしはえびが苦手なのに、それではまるで愛みたいだと思って、みみの好物をもとに戻す。
「まだ家に鍋キューブってあったんだっけ」
「どうだったっけ」
調味料が並んでいる細い通路にみみは入っていった。
「鶏白湯(とりぱいたん)しかないよ」
広い通路で待っているわたしに向けて、大きな声が返ってくる。
「うん。それでも良さそう」
親指と人差し指で丸をつくる。みみは鍋キューブをかごに入れ、また先を行く。
「ねえ、うみー。ホンビノス貝、半額だって」
「へー、二百円か」
「良くない? これ」
みみは、パックの内側でゆるやかに呼吸する砂色の貝殻を見ていた。子どもみたい、と子どもの目なんてもう久しく見ていないのにそう思う。
「このスーパーで生きているのって貝だけ?」
「そうかもね」
わたしは言った。
鍋の材料がそろったので、レジ待ちの最後尾にカートをつけた。地域でも激安で有名なスーパーは、休日の夕方頃は特に混み合っている。少しずつ進む列、カートをゆらゆらと前後に動かしながら、レシピサイトの広告のなかで踊っているしろくまをつい眺めていると、ぽん、と通知が降りてきた。
「妹が逃げ出したって」
「また?」
「うん。また」
料金を支払っている間に、みみはかごをサッカー台へと運んだ。豚バラ肉の入ったトレーを薄いポリ袋でくるみながら、いってらっしゃい、とつぶやくので、わたしはなんだか寂しくなった。
「鍋、明日でもいい?」
「うん」
「絶対だよ」
わたしはスーパーの駐輪場に止めた水色の自転車にリュックを乗せると、ライトを灯すために重くなったペダルを二十分ほど漕いで鷹の台へ向かった。
孵化(ふか)コーポ、と切り抜かれたビニールシートが貼り付けられたすりガラスの扉は、横に滑るように開く。玄関でサンダルを脱ぎ、指と指の間に挟まっていた枯れ草を落とす。スリッパに履き替えてから、一目散に106号室へと向かう。
扉を開くと、ぷここここ、とエアーの音が響く。無数の水槽で満たされた、六畳ほどの部屋。目視では、天井や床には張り付いていないみたいだけれど、ちいさな身体の妹は、どこに潜んでいてもおかしくはない。踏み潰すことのないように、ゆっくりと水槽に近づくと、きちんとしまったフタが見えた。そのなかで、イモリの妹は透明な壁にしっぽをこすりつけている。
「よかった、いてくれた」
ほっとしたら、どっと疲労が押し寄せてきた。照明を落とし、リビングへと向かう。冷蔵庫から、だれかがつくり置きしてくれた麦茶のペットボトルを取り出し、二階へと上がる。
仄暗い廊下の突き当たりに、正円の窓がぽっかりと空いている。そこから差し込むかすかな光が、左右に三つずつ並んでいる扉を照らす。わたしは美術館で絵画を眺めているときのように、ゆっくりとゆっくりと、その扉の前を歩く。
〈貝〉
〈うみ〉
〈えび〉
各部屋の前には、自然の家とかで手づくりするような、木製のプレートがぶらさがっていている。わたしはリュックのポケットから鍵を取り出すと、〈う〉の文字からはみ出す透明なボンドを眺めながらドアノブに鍵を差し込み、なかへ入る。
六畳ほどの和室には、ちいさな窓、真っ白くてきれいなエアコン、すのこに載ったニトリのマットレスが置かれている。わたしはペットボトルを床に置くと、マットレスに寝転び、緑化(りょっか)さんにLINEを打った。
〈妹は無事でした〉
ぽっ、と既読が浮き上がってきて、むむがうれし泣きしているスタンプが現れる。
〈わざわざすみませんでした。ありがとうございます!〉
〈明日、朝からシフトだったんで大丈夫ですよ!〉
緑化さんからは、月に一度くらいの頻度でこのようなLINEが届く。孵化コーポの玄関の鍵を閉め忘れてしまったかもしれない。水槽の水を換えたあと、蛇口をひねったままだったかもしれない。電車に乗るよりも先に気がついたときは、引き返して確認をしているけれど、大体は最寄駅に着いた瞬間にふと不安になるのだという。そう語る緑化さんの気持ちが、わたしにはよくわかった。だから仕方がない。
〈妹、無事でした。今日はこのまま孵化コーポに泊まります。おやすみ〉
そうみみに伝えると、目を閉じた。
続きは2022年10月7日発売 「文藝」冬季号でお楽しみください。