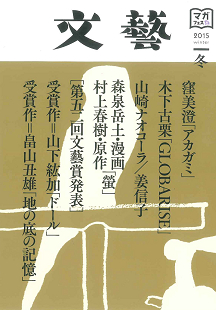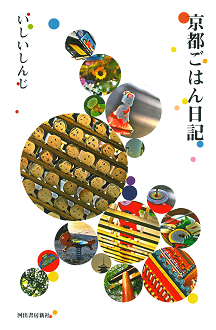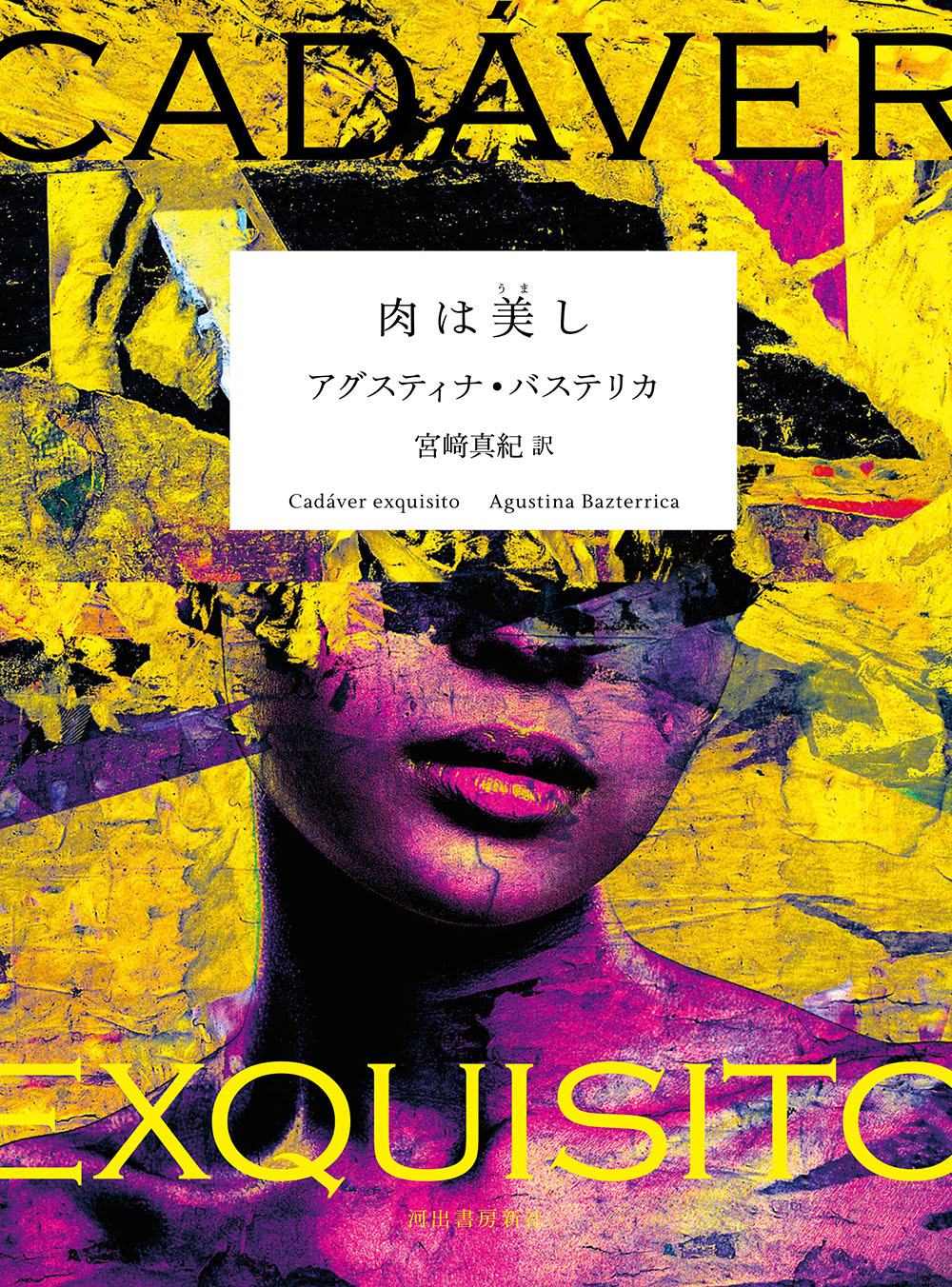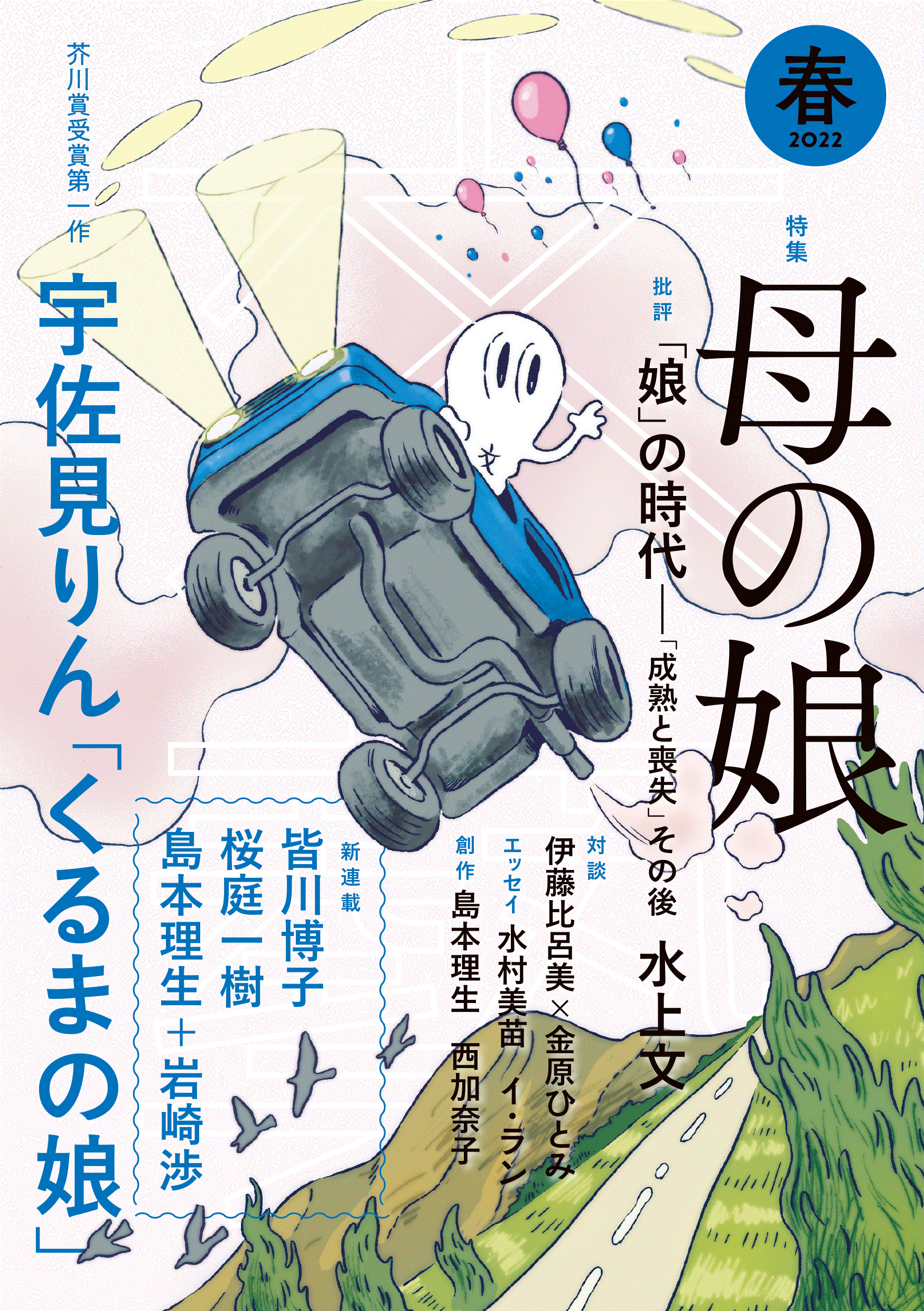単行本 - 文藝
道を照らす海のような小説──『港、モンテビデオ』いしいしんじ
【評者】石井千湖
2015.12.22
いしいしんじ
[評者]石井千湖
──記憶の海を言葉で航る──
いしいしんじは『港、モンテビデオ』の舞台になっている三浦半島の三崎町にいたとき、ヴァージニア・ウルフの『燈台へ』を何度も繰り返し読んだという。本書は三崎と『燈台へ』に描かれたセント・アイヴス、ふたつの港町を言葉によって行き来する。ペリー来航、タイタニック号沈没、第五福竜丸事件といった史実に残る出来事から個人的な体験まで、さまざまな時間と記憶が漂い、生者と死者が出会う海の話でもある。
主な登場人物は三人だ。三崎で魚屋を営む宣之と美智世の夫妻、魚屋に出入りする生業がよくわからない天然パーマの男、慎二。二〇〇七年七月十四日、もうすぐ還暦を迎えようとしている美智世が、慎二にチケットをもらい、観音埼灯台の近くにある横須賀美術館へアルフレッド・ウォリスの展覧会を見に行く場面ではじまる。ほぼ一生をイングランド、コーンウォール地方のセント・アイヴスで暮らした画家の作品を眺めているうちに、美智世は絵のなかの港に入りこんでいく。
一方、三崎の飲食店街では、港町の名前がついたバーやスナックの中身が突然くりぬかれたように消える事件が勃発。宣之は飲みに行った店でチリの詩人パブロ・ネルーダの声を聞き、慎二は汽笛の音と光のかたまりに導かれ〈もんてびでお丸〉という船に乗る。
まず魅了されるのは、現実とは少しずれた三崎の風景だ。例えば、猫っ玉が出てくるくだり。道のところどころに毛の丸い塊が転がっている。もともとは猫だが、住民が食料を大量に与えるから、肥え太って球体になってしまったのだ。〈日中は日陰であまり動かず、なにかのきっかけでポーンポーンと鞠のように跳ね〉る。実際に三崎には猫がたくさんいるから、そんな奇妙で愛らしい光景も見られるような気がしてしまう。
漁港の人々はみんな陽気だ。飲み屋の内側が主人ごと消失するという、よくよく考えると恐ろしい事件が起こっても、どこかのんびりしている。しかし、美智世は夜に熟睡できなくなって二十年以上経つし、宣之は子供のころに被曝したマグロを見た。誰もが不穏な暗がりを抱えているのだ。慎二は三崎に近い浦賀にやってきたペリーの話から、モールス信号の発明を連想し、国際会議で採択されたばかりの〈SOS〉の信号を打ったタイタニック号に思いを馳せる。〈百年経ったいまも闇の海中を流されているからだがあるだろう〉という一節にはっとした。
亡くなった人は時が流れるにつれて遠くなるけれど、完全にいなくなってしまうのではない。闇の海中や港町の暗がり、絵画の風景のなかに潜んでいる。慎二が〈もんてびでお丸〉である人物に邂逅したように、宣之が一九七三年にこの世を去ったネルーダの声を聞いたように、美智世が絵のなかに入って生前の画家を見たように。生と死の境界をはじまりもおわりもない「水」によって溶かすところは、著者の『みずうみ』と響き合う。もう会えないはずの人、見えないはずの世界に、たどりつく道を照らす灯台のような小説だ。