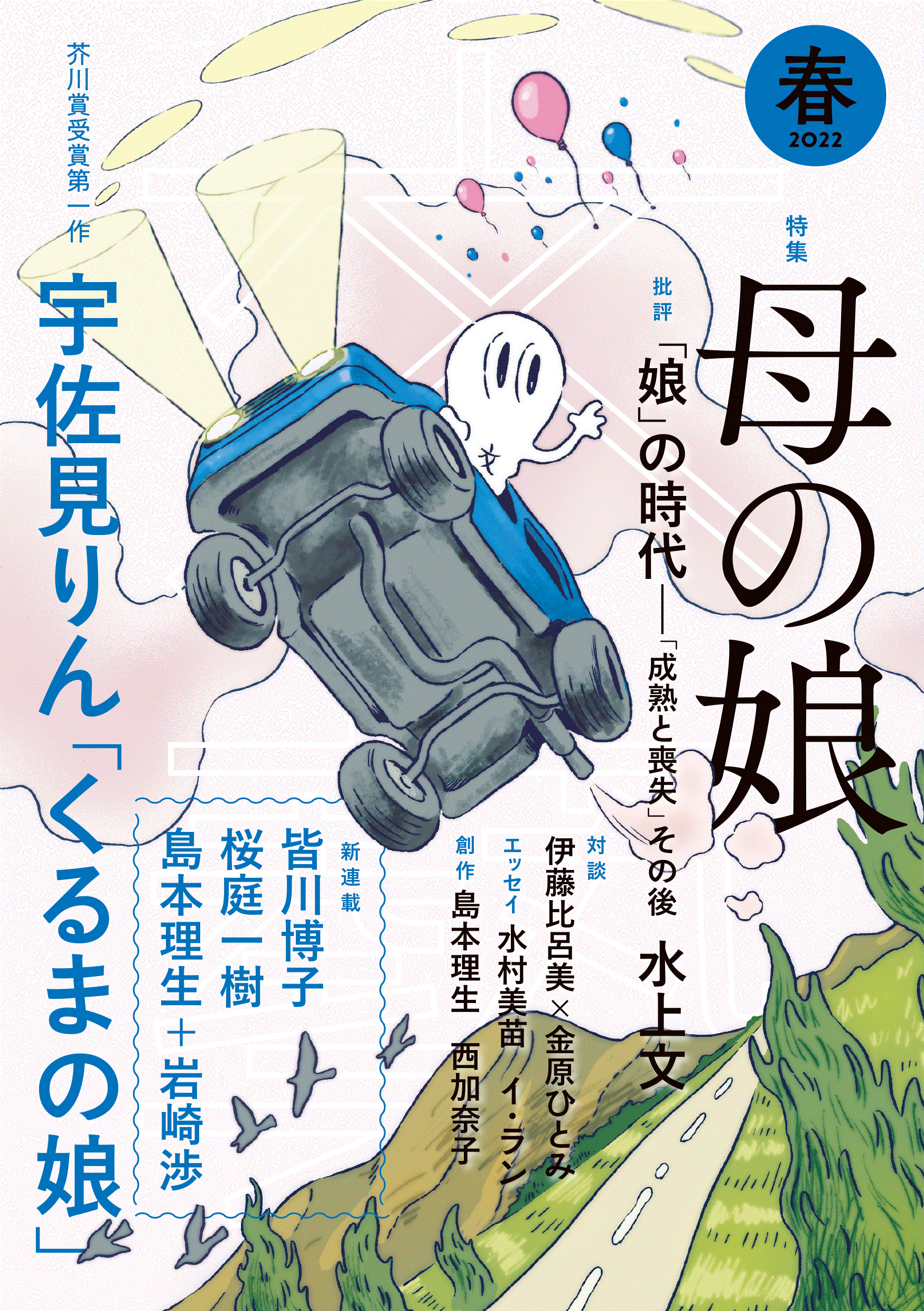単行本 - 文藝
ブーケトス一万、キャンドルサービス十万「これって、つまり、何もないところから金が生まれてるってこと?」【まるごと試し読み】祝!野間文芸新人賞候補記念 古谷田奈月『神前酔狂宴』【第1章】
古谷田奈月
2019.10.09

神社の結婚披露宴会場で働き始めたフリーターの浜野。時給の良さを目当てにバイト先を決めた浜野はある日、結婚式が壮大な“茶番”であることに気づく。「滑稽さが肝の喜劇では、登場人物全員が愚者であるべき」と、働きぶりが一転。そんな中、神社に祀られている神が「もとは人だが、今は神」な、明治日本の実在した軍人であったことを知り……。
以上は結婚、家族、日本という壮大な茶番を鮮やかに切り裂く衝撃作 古谷田奈月『神前酔狂宴』のイントロダクション。本作は、発売直後から多数のメディアで絶賛の声が上がり、SNSでも口コミで評判が広がり続け、注目を集めていますが、このたびめでたく第41回野間文芸新人賞候補に選ばれました。
これを機に、ぜひ、このドライブ感あふれる、スリリングな、まさに「今」を描いたこの作品をお読みいただきたく、第1章をまるごとアップいたします。
結婚式を挙げた人も、挙げてない人も、挙げたい人も、挙げたくない人も、お楽しみください。
神前酔狂宴
古谷田奈月
1
もとは人だが、今は神で、都心の喧噪の及ばない暗がりにそれぞれ祀られている。明治期に偉勲を立てた椚萬蔵と高堂伊太郎は国を愛する人々から深く敬われ、軍神となった現在も、椚大将、高堂元帥、と親しみを込めてそう呼ばれている。明治神宮の東西に社殿を構え、俯瞰するとまるで跪く二人の忠臣のようなので、生前誓った天皇への忠誠を今なお示し続けているのだと言う人もいる。
しかし高堂神社に併設された高堂会館、その中の披露宴会場で働く浜野にとって、一対の神といえばこの二人だ。神前結婚式を終えてきたばかりの二人、片やグレーのタキシード、片や白のドレスを着た二人、この日のためにと繕ってきた神々しさを引きずって、今、もったいぶった足取りでやってくる二人。浜野は両開きの大きな扉の片側に立ち、背筋を伸ばして微笑を浮かべる。こちらももちろん取り繕った体裁だが偽りはない、何せ相手は金を生む神だ。反対側に立った梶もきっと同じ笑みを浮かべ、同じことを考えているはずだった。浜野が営業事務所のゴミ箱から拾った見積書をゆうべ一緒に見たときのこと、そこに書かれた驚愕の金額のこと──会場使用料、控え室使用料、美容代に衣装代に料理代。嘘だろ、おれたちいつもこんな高いメシ出してんの? そう言って笑ったラーメン屋でのこと。ブーケトス一万、キャンドルサービス十万、完全に狂ってる!
しかもそのとき、さらに素晴らしい発見をしたのだ。回転させてなんぼのラーメン屋に長居するのは垢抜けない田舎者だけだと常々言っている梶が、食べ終わっても立とうとせず、見積書をじっと見つめてこう言ったのだった。「これって、つまり、何もないところから金が生まれてるってこと?」
浜野は驚き、すぐには答えられなかった。一点を穿つような力のある梶の細い目に見つめられ、たっぷり三秒もぼんやりしてからやっと頭が追いついた。梶の言うとおりだった。ただローソクに火をつけるだけのことに十万払い、小さな花束を放り投げるだけのことに一万払う。新郎新婦という客は、何もないところに金を出しているのだ。何もないところから金を生み出す神なのだ。
自分の目が輝いていくのを感じながら、「うん、そうだ」と浜野は呟いた。「ゼロから何百万も生まれてるんだ。で、そこからおれたちの給料が出てる」
「てことはおれたち、幻の金で生きてる」
「てことはおれたち、幻のラーメン食ってる」
幻のラーメン食ってる! 浜野と梶は同時に叫び、迷惑そうな、でもどこかまんざらでもなさそうな店主と目を合わせて大笑いした。
その幻の金を生み出す神が、今、浜野と梶の控えた扉の前に横並びになった。「本日は誠におめでとうございます」彼らの正面に立った会場責任者の入江がそう挨拶するのに合わせ、浜野と梶も頭を下げる。わたくしお二人のご披露宴を担当させていただきます、入江と申します、と続けるキャプテンの制服が、新郎新婦の輝く衣装に相反する真っ黒のタキシードであることが浜野には妙にしっくりくる。入江が入場の流れについて説明しているあいだ、浜野は目を伏せ、なるべく新郎新婦を見まいとする。幻の金を生み出す神に顔があっては興醒めだ。
やがて説明を終えた入江が、体ごとくるりとこちらを振り返った。神と直接言葉を交わす権利、それどころか彼らに指示を出す権利さえ持つ者特有の鋭い目で素早く二人の部下をにらみ、低く囁く。「三秒」
浜野と梶は浅く頷き、扉の前に向き合って立った。そして棒形のドアハンドルを握る。では参ります、と最後にそう言い置いて入江が去ると、新郎新婦はたちまち緊張し始める。入江によって整えられた姿勢を崩さぬよう固まったまま、わかりきったことを確認し合ったり、わざとらしい冗談を言い合ったりする。その気になれば二人の会話に加わって、新人らしい陽気さで彼らの緊張を紛らわせてやることもできる。しかし浜野にとって神々のためにすべきことは、キャプテンから下った指示だけだ。三秒。
マイクを通した司会者の声が、やがて厚い扉越しに響いてくる。はっきりとは聞き取れないがおそらくは新郎新婦の名が、結婚披露宴の開幕が、会場全体に告げられているだろう。招待客たちは静まり返り、照明は落ち、スポットライトがそのかわりに狙いをつけているだろう。するとひときわ大きく発せられた声が、今度ははっきり聞こえてくる──新郎、新婦、ご入場です! 音楽が鳴り始め、その瞬間から浜野と梶は数え始める。入場者たちが心構えできるよう、わざと声に出してやる。「いち」「に──」
さあご開帳! 思い切りよく引き開けた扉と壁のあいだ、ぴったり一人ぶんしかないその薄暗い空間で、浜野は拍手喝采の音を聞く。それは三秒前までこの厚い境界線に隔てられていた二つの世界が、とうとう一つになったことを示す音だ──祝福の音、混沌の音、そして何より黄金の音。神々を迎え入れた人々の拍手のひと打ちひと打ちが、浜野には金が生まれる音に聞こえる。祝儀の額と同じだけ鳴り響いているように聞こえる。二百、三百、四百と膨れ上がっていくその音が五臓六腑をあたためてくれ、血を巡らせてくれるのを感じる。
新郎新婦が遠ざかると、それに合わせて浜野はゆっくり扉を閉めていく。同じように反対側を閉める梶と十数秒ぶりに顔を合わせ、どちらからともなく笑みを浮かべる。今日の稼ぎと退勤後のラーメンに思いを馳せながら、左右の扉をぴたりと合わせ、二神をすっかり閉じ込めてしまう。
高堂会館で働いていながら高堂神社の神をさほど身近に感じないのは、結局、神社そのものが身近でないからだった。会館勤務の浜野にとって神社は挙式会場でしかない。その挙式さえ、終日会館内でばたついている配膳スタッフにはほとんど目にする機会がないのだ。
わずかながら神社との繋がりを感じるのは、朝、境内を通り抜けるときだった。出勤時間は日によって違ったが、土日はだいたい八時半から九時のあいだにJR原宿駅を降り、日中の混みようなど想像もできないほどうら寂しい、しかしゴミや嘔吐物やカラスの羽音で彩られた竹下口を抜ける。そこから千駄ヶ谷方面へ向かい、もしイヤホンで音楽を聴いていなければ明治通りの交通の音が遠くから聞こえてくる小道を進んでいく。やがて左手にタトゥースタジオとパンク系のシルバーアクセサリーショップが現れるので、その二軒のあいだの狭い路地に、逃亡者のような心地で潜り込む。十数メートルばかり行き、短い階段を上る。すると急に木々に囲まれ、空気が澄む。たちまち人と街の臭いが消える。音楽が耳障りになる。イヤホンを外し、怖いほどの静けさについ聴き入る。
明治通りに面した表門と違い、この裏門には鳥居も注連縄もないので、どこか冷たい感覚が身を包んだら境内、と浜野は自然とそう覚えた。地元の人々からは高堂の森と呼ばれる、守るように社殿を包むその深い木々のあいだを、息を凝らして進んでいく。
朝陽の中、白袴の見習い神職が掃き掃除をしている姿が目に入ると、別の緊張が生まれはしたがそれでも人心地がついた。おはようございます、と彼らに声をかけ、おはようございます、と返してもらうと、そこでようやく境内での自分の居場所が生まれるような気がするのだ。だから浜野は、住む世界はまるで違うが歳はそう変わらないと思われる、この白袴の青年たちにいつも必ず挨拶した。返ってくる見習い神職たちの声は、よそよそしくも柔らかな響きをもっていた。
挨拶すべき対象はほかにもあり、言うまでもなく、それは御祭神だった。入り口として浜野が使う裏門が境内の南西にあるのに対し、職場の高堂会館は北東にあり、対極に位置するその職場に向かう道のりのちょうど中ほど、境内中央に拝殿はある。正式な参拝が義務づけられているわけではなかったが、お参りの場であり神前式場でもある拝殿前を素通りすることは許されなかった。参道の途中で足を止め、体ごと拝殿のほうを向く。そして深く一礼する。神前と呼べる場所から優に五十メートルは離れているが、それでもそうする。
これは勤務初日、ここで働く上で知っておくべきほかの細かな決まりと一緒に、先輩の汐見から伝えられたことだった。更衣室はここ、通用口はここ、この台帳に入り時間と名前を書いて、この名札を胸につけてという流れの中で、「あ、それから、拝殿の前では必ず一礼」と言われたのだ。二十八歳、常勤の汐見は二〇〇三年のこのときすでに勤続十年のベテランで、ぴったり十歳若い浜野と梶の教育係でもあった。だからその汐見から「神社さんとの付き合いってのが、ここじゃ何より大事だから」と言われればそうかと思う以外になく、浜野はただ単純に従った。出勤前に一礼。退勤後に一礼。これも仕事。
高堂神社と椚神社のおおまかな関係を教えてくれたのも汐見だったが、それはひとえに「椚さんらの前ではくれぐれも行儀良くすること」と言い聞かせるためだった。
椚さん、と高堂会館のスタッフが呼ぶとき、それは椚会館から手伝いとしてやって来る二、三名の給仕を指す。毎週末、彼らは自分たちの職場がある参宮橋から千駄ヶ谷にある高堂会館までてくてく徒歩でやってきて、親族控え室の一つを受け持つのだ。いったいどのような指定をすればそうなるのかと思うような野暮ったい緑色をした、男性はブレザー、女性は丈長のフレアワンピースという制服に身を包み、いつものろのろと不慣れな動作で飲み物や軽食を運んでいた。男女ともにワイシャツに黒ベスト、黒スラックスという高堂会館のギャルソンスタイルに囲まれると椚会館の制服はぎょっとするほど時代遅れに見えたし、二、三名でまかなえる簡単な仕事をわざわざ、お世辞にも有能とはいえない外部者に頼むというのも理解しがたく、初めて仕事に就いた日から浜野は彼らの存在が不可解だった。
しかし汐見に言わせれば、「それもやっぱり付き合いってやつだよ」ということだった。「神社さん同士の、昔からの。おれらがとやかく言うことじゃない。それにうちは一日に八件から十件も婚礼をやるけど、椚さんとこは一日一組限定なんだ。会館の会場もうちみたいに四つもない、一つだけだから、たぶん人が余ってるんだろ。とにかく、椚さんもお客さんだと思って行儀良くすること」
浜野はもちろん、その教えもすんなり素直に飲み込んだ。椚さんや椚神社との関係を気にするどころか、自分のところの神社に祀られている高堂伊太郎のことさえよく知らないのだ。
もしかしたら、日本史の授業で一度くらいはその名を耳にしていたかもしれない。しかし浜野の時の流れにおける興味は常に前方にあったので、五十年後、百年後、三百年後の日本がどんな様相を呈しているか、じき歴史になる何がこれから起きていくかということならば楽しく考えていられたが、過去のことにはどうにも関心が持てないのだった。過去に起きた事柄というのは、たとえどんなに陰惨な史実でも浜野にとっては安全地帯だった。安全で、そのために退屈な世界。自分の力の及ばない世界。
「高堂伊太郎って誰ですか」
そう聞いたのは梶だった。さすがに高堂会館でのことではなく、幡ヶ谷にあるカサギスタッフという派遣事務所でのこと、雑居ビルの中の一室で二人一緒に面接を受けているときのことだった。ブライダルの現場にはなんの興味もなかったが、割のいいアルバイト先を探していた浜野は、求人広告に太字で出ていた「時給一二〇〇円〜」の文字にひょいとつられて応募したのだ。
面接といってもウエイターとしての適性をはかられるようなことはなく、この銀行で口座を作れとかソムリエナイフを買っておけとか、面接を担当した新田という中年男はのっけから採用を前提にした語り口だった。一度に複数の登録希望者を相手にするのも、どうせ同じ話をするだけだからという理由のようだった。
梶とはそこで初めて会った。口調も仕草も荒っぽく、広告に記載されていた身だしなみの規則のほとんどすべてに反していたので、こいつは本当に採用される気があるんだろうかと浜野は内心驚いていたが、新田は梶の細い眉、金色の髪、ピアスだらけの耳を見ても少しも動じなかった。「仕事中、ピアス外せる?」「髪、黒く染められる?」「ジェルでがっちり髪セット、できる?」と慣れた口ぶりで確認しただけで、「はい」「もちろんです」「問題ないです」と頷く梶の素直で真剣な態度には、むしろ好感を持ったようだった。
新田が何より気に入ったのは、二人の若さと自由さだった。十八歳、フリーター、アルバイト経験はあるが飲食業界で働いたことはない──それらは間違いなく不利な要素だろうと浜野は思っていたが、プライドが高い上に経験知を振りかざしてあれこれ意見してくるホテル勤務のベテランウエイターの扱いに日々手を焼いていた新田は、若く、余計な知識がなく、指示されたことに疑問を持たない無垢な新人を求めていた。試験だの留学だのでしょっちゅう穴を空ける学生でないというのもまた、彼の気に入ったところだった。
カサギスタッフは多くの有名ホテルや結婚式場と取り引きがあり、通いやすいところなり憧れがあるところなり自由に職場を選んでいいと新田は言ったが、「でも常勤として長く働くなら、おすすめはここ」と、特別な客にしか教えない裏メニューのように高堂会館の資料を差し出した。「高堂はいいよ。建物はちょっと古いけど、働きやすさはほかの現場の比じゃない。古株たちがみんなすごく雰囲気いいんだ、ざっくばらんで、面倒見良くてさ。それにお客さんに人気のある会場だから、毎回長時間働けるよ。土日だけでも月十三万くらい稼げる、新人でもね。常勤ならその倍は狙えるかな」
「月二十六万!」浜野は思わず色めき立った。一人暮らしを始めたばかりで、頭にはほとんど金の心配しかなかったのだ。「ぼく、常勤で入ります」
しかし隣に座った梶は、「ちゃんとしたとこなんですか?」と意外にも懐疑的だった。「高堂会館なんて聞いたことないし、名前もめちゃくちゃ地味ですけど」
「由緒があるってことでいえば、大手のホテルよりちゃんとしてるよ。神社が母体だから」新田は可笑しそうに答えた。「千駄ヶ谷の高堂神社。会館もその境内にあるんだ。神社と会館は一応別の組織なんだけど、宮司がすべての権限を持ってるから、まあ、親会社と子会社って感じかな」
「高堂神社……」
「高堂伊太郎を祀ってる」
「高堂伊太郎って誰ですか」
「梶くん、ちゃんと歴史の授業出てたか?」
大人相手に物怖じせず話していた梶は、そこで初めてたじろいだ。首から耳がさっと赤らみ、頬には歯噛みの強張りが浮いた。
「ぼくも知らないです」言わねばならない気がして、浜野はすぐにそう言った。「授業は出てましたけど、ほとんど聞いてなかったんで」
「そう? わりと有名な人だけどね」
「有名人とかあんま興味ないんですよね」
「じゃあ地元の長野にいた頃も、その──」新田はそこで浜野の履歴書を確認した。「きみは、脚本ばっかり書いてたのかな。シナリオスクールがあるときは、仕事には入れないって書いてあるけど」
「いえ、脚本はまだ書いたことないです。書き方を教わるためのシナリオスクールかなって……、違うのかな。別になんでもいいんですけど。習いごとくらいに思ってるし」
「ということは、本気で脚本家になろうと思ってるわけじゃない?」
「あの、これからのことなんで……」
「うん」
「だから、自分がどう思うかまだわかんないです」
「でも興味はあるわけだろ」
「いや、別に……」そこでようやく、浜野は新田の怪訝そうな目に気が付いた。隣の梶も、じっとこちらを見ているようだった。「あの、ぼく、あれこれ考える癖があるだけなんです。人と喋ってるときとか、授業中とかに、全然関係ないことがふっと頭に浮かんできてわりとそこにはまっちゃうっていう。子どもの頃からずっとなんで、これを生かすか封じるかしないとぼく、死ぬかな、と思って──社会的にって意味ですけど──それでとりあえず生かしてみようってことになって、親に金出してもらって、東京来て、ためしにシナリオスクール申し込んで、みたいな。実家がある松本はそんな田舎でもないんでどうしても東京ってこともなかったんですけど、一人で暮らしてみたかったから、そこはちょっとわがまま言いました。ていうか全部わがままですけど。だからその、脚本に興味湧くかまだわかんないし、松本にいた頃から何か書いてたわけでもないです。むしろなんにも書いてなかった。日本史のノートも真っ白でした。偉い人なんですか?」
「え?」新田は我に返ったように聞き返した。「誰が?」
「高堂……、太郎」
「伊太郎ね」新田は笑った。「まあ、そりゃあ。偉くなきゃ神様にはなれんだろ」
「ああ……」
「明治時代の軍人だよ。日本を勝利に導いた」
「そのへん詳しく知らないと、高堂会館で働けませんか」
新田はまた笑った。あきれていたが、楽しげでもあった。「いや、いいよ。何も知らないままでいい」
そう言われたからというわけではないが、実際に働き始めてからも浜野は高堂伊太郎について調べたりはしなかった。少しばかり汐見から教わったことを除けば、まったく無知のままだった。
それでも拝殿の前に差し掛かれば、一礼する。誰かにとっての神、あるいは、いつも挨拶を返してくれる見習い神職たちが信じるもの。それがそこにある、ということくらいは、せめて認めたいようにも思った。
それに拝殿を過ぎ、境内の東側に入ってしまえばもうこちらの領域、本物の神のことは考えずに済む気楽な世界だった。まだ高堂の森に覆われてはいるが、裏門から入って以来続いていた緊張はほどけ、雰囲気に張りがなくなる。神事とも崇高さとも無縁な、会館の俗な空気になる。
もっとも、そんなふうに感じるのは関係者だからかもしれない。今日初めてここに足を踏み入れた挙式参列者だったら、都心とは思えないこの静けさ、この深い緑の奥に、突如現れる広大な日本庭園を見て思わず息を呑むかもしれない。錦鯉が泳ぐ二百坪の池やその向こうに見えるどこか古風な会館に、神社由来の緊張をより強く感じるかもしれない。でも浜野にとって、そこはもう仕事場兼遊び場だった。森の木々がいったん退き、日の光がたっぷりと降り注ぐ池沿いの道を、世にも愉快な職場に向けて軽快に進む。
披露宴会場で働きだし、やがてその実態を知った浜野がまず心配したのは梶のことだった。事務所で初めて会ったときから「ちゃんとしたとこで働きたいんだよね」と言っていたからだ。「ちゃんとしたとこ。ばあちゃんが安心する感じのとこ。わかる?」
面接を終え、事務所のビルの外階段を降りながらの会話だった。まともに話をするのはそれが初めてだったが、梶は昔からの知り合いのようになれなれしく話したので、ああ、うん、と浜野も付き合いの長い相手によくするようにいい加減な相槌を打った。
「ちゃんとしたとこって、別に社員として雇ってもらえるとかそういうことじゃなくてさ」うしろの浜野を時折振り返りながら、梶は熱っぽい調子で続けた。「だっておれ中卒だし。でも手に職つけるっつっても友だちとか先輩みたいに、塗装やら土木やら配管やらって気になれなかったんだ。それってなんか、なんていうか、結局またこれまでの自分に似た連中に囲まれる気がして。それでまたばあちゃんに心配かけることになる気がしてさ。ほんと迷惑かけたんだよね、おれ、これまでさんざん。学校とか店とか警察とかにさ、やらかすたんび来てもらって。何回も引っぱたかれて、何回も泣かれて。絶対だめだよね、そういうの。絶対だめだなって思って。だからこれからはもう、ばあちゃんのために生きようって思ってさ。新しい世界に飛び込んで、まっとうな人間になって、ばあちゃんが喜ぶことだけしようって」
初対面の自分に梶があんまりまっすぐ打ち明けるので、おおー、と今度は相槌にも熱が入った。「だけど、それならでかいホテルとかにしてもらったほうがよかったんじゃないの。名前聞けば一発でわかるようなとこ」
「まあでも、さっきのあのおっさんの、由緒があるって言葉をとりあえずは信じるよ」
「そっか」
「神社とか、たぶんばあちゃん好きだと思うし」
「そっか」
「ピアスなし、黒髪、ジェルでがっちり髪セット──」歌うように呟きながら、梶は階段を降りきった。「次会うときは、お互い悲惨な髪型だな」
「梶くんは顔いかついし、たぶんオールバック似合うよ」
そう言うと、歩道に出た梶は振り返って笑った。いかついオールバックって、それチンピラだからと楽しげに肩を揺らし、面接中も思ったけど浜野くん、テキトーだよねと付け加えた。地元の友人たちからもよく言われていたその言葉を、浜野は称賛として受け取り、東京に来て初めて気安く話をした人物の髪を眺めた。笑い声と一緒に揺れながら、金色の髪はまるで日の光のように輝いていた。
その輝きを漆黒に塗り込めてしまうことを梶は少しもためらわなかった。高堂会館という職場が「ちゃんとしたとこ」だと祖母に認められたと浜野に報告するときも、心の底から嬉しそうだった。
「事務所のおっさんは正しかった」初出勤日、梶はピアスなし、黒髪、オールバックの制服姿を更衣室の鏡に映し、目を輝かせてそう言った。「うちのばあちゃん、高堂神社を知ってたよ。高堂伊太郎も知ってたし。立派な人だって。敵軍からも一目置かれた英雄で、近代日本の父の一人だって。そんなすごいところで働くのかって、ここ十年で一番喜んでたよ」
梶の誇りは、しばらくのあいだは純粋な状態で守られた。何しろウエイターの基本として習うことのすべてがあまりに「ちゃんとして」いて、疑いを差し挟む余地などなかったのだ。柔らかい笑顔、完璧な敬語、恭しい動作──これまでいっさい縁のなかったそれらの作法を梶はたちどころに身につけ、みるみるいっぱしのサービスマンに育っていった。
浜野も新人として同じ教育を受けたが、最初のうちは仕事の質におおいに差が出た。たとえば、客のために椅子を引くよう指示されれば梶はホールの果てまでだって飛んでいったが、浜野の場合、健康な人間の着席や起立にアシストなどいるわけがないという個人の価値観がつい勝って、よほど目の前の客でもなければ決して椅子など引かなかった。梶は客に頼まれる前にワインのおかわりを注ぐことにプライドをかけたが、浜野はボトルごとテーブルに置いて勝手にやらせた。梶は客の嘔吐物を始末するべくおしぼり片手にダイブしたが、浜野は、絨毯の上に吐くような奴は死んでしまえばいいと思いながら遠ざかった。
「ちゃんとした」職場はどうも合わない、そう思ったがしばらく辛抱して働いた。英雄の威光も会館の由緒もいっさい労働へのモチベーションに繋がらなかったが、金のためと思えば頑張れた。
ところが、半年ほど経ったある日のことだった。職場の印象が突然に変わった。そのとき浜野は客入れ前のホールにいて、いつものように担当テーブルの最終チェックをしていただけだった。ナプキンの折り目は逆になっていないか。ナイフとフォークは三本ずつ並んでいるか。それらの柄の先を結ぶときちんと直線になるか。パン皿の向きは統一されているか。グラス類に曇りはないか。席札は曲がっていないか──そうしたことを一つ一つ、テーブルの外縁に沿い、ゆっくり弧を描きながら確認していく。毎度の作業だったが、だからこそだったのか、ある席のシャンパングラスをシャンデリアの光に透かしてみたとき浜野はふと、このグラスはさっきも見たんじゃないかという疑念にとらわれた。自分でも気付かないうちに、おれはもうこのテーブルを何周もしてるんじゃないか、忘れ去られた衛星みたいに、意思も目的もないままひたすらぐるぐる回ってるんじゃないか──
それでふうっと気が遠くなったが、手にしたグラスを落としそうになる類の遠のき方ではなかった。知覚はむしろ鋭くなり、グラスも実際そっと戻した。ただ思考だけが遠ざかり、その後はもう、目の前の光景をそれまでと同じには見られなくなった。
浜野はまず、自分でテーブルに置いたばかりのシャンパングラスに奇異の目を向けた。細長すぎる。それから、ナイフやフォークなどのシルバー類。ピカピカすぎる。ナプキン、席札、装花にクロス──すべてが整いすぎている!
しかもそんなテーブルが、顔を上げればいくつも並んでいるのだった。八名掛けの円形テーブルが全部で十五、だだっ広い会場に並び、規則どおりに身なりを整えたウエイターやウエイトレスたちが取り澄ましてそのそばに控えている。彼らの頭上ではナイフよりピカピカなシャンデリアがぶら下がり、壁には金色の糸が織り込まれたカーテンが掛かり、サンルームには子どもじみた犬のぬいぐるみが雌雄セットで飾られ──雄犬は白いタキシードを、雌犬は白いドレスを着ているのが近くまで寄るとわかる──そのサンルームの窓の向こうには高堂の森が、さらに遠くには神宮の空が見える。ここはいったいなんなんだ? 目に映るものすべての仰々しさに、浜野はすっかり愉快な気分になっていた。おれはいったいどこにいる? 今からここで何が始まる?
今から何が始まるのかは、ほかの円形テーブルより数段華やかに飾られた四角いテーブル、王座の如き佇まいの一対の椅子が示していた。結婚披露宴が始まるのだ。そんなことはもちろん知っていたが、すでに何度も立ち会っていながら、浜野はこのとき初めてそれを意識した。
結婚披露宴って何? なんでみんな──ねえ、ほんとに──なんでみんな、結婚を披露するの?
ひと組やふた組の、風変わりなカップルによる思い付きなら理解できた。しかし挙式に披露宴という組み合わせが一般的な婚礼の流れであるのは間違いなかった。高堂会館に入っている水鞠の間、朝凪の間、千重波の間、そして浜野と梶が働く海神の間という四つの宴会場も、休日はたいてい二件ずつ、多いときでは三件の披露宴が開かれていた上にずっと先まで予約でいっぱいだった。「次から次へと、いったいどこから湧いて出るんだろう」際限なく現れる新郎新婦たちについて、梶とそんなふうに話したこともある。「せっかくの週末だってのに、結婚以外にみんなすることないのかな?」
このときようやく十九になろうとしていた浜野には、結婚式や披露宴をしようと考える大人たちの現実はわからなかった。しかし結婚というものが仮に祝うべき節目だとしても──松本で毎日見て育った、絶えず小言を並べる父となるべく家にいまいとする母、という結婚の一つの実態も、この際わきに置いておくとしても──当事者以外の人々にそれを披露するという行為には、人間の何か救いがたいような性質が絡んでいることは本能的にわかった。
何しろすべてが不自然で、目を見張るほど滑稽なのだ。どの新郎新婦も自分たちが決めた曲で大勢の前に登場し、自分たちで用意した一番立派な席に座り、自分たちで計画したとおりの形式で祝福され、そして、そのことに疑問を抱かないのだ。彼らは自分たちがほかの新郎新婦と判で押したように同じことをしているとおそらく気付いていたが、それでも引出物袋に重いカタログを仕込んでわざわざ招待客の荷物を重くしたし、使い回されてぼろぼろになったイミテーションケーキに大喜びで入刀した。彼らはまた、自分たちの選んだ海神の間が高堂会館でもっとも広くて格式高い会場であり、スタッフも精鋭が揃っているというプランナーたちの言葉も信じて疑わなかったが、このことは特に、浜野には胸が痛むほど可笑しく思えた。何しろスタッフの面々は実際のところ、そのほとんどが仕事に誇りを持っているわけでもなければいかなる新郎新婦の幸せも特に願っていない、その日暮らしの非正規雇用者なのだから。
虚飾の限りを尽くすこと──慣れない仕事に振り回されてこれまでは気付かずにいたが、それが結婚披露宴の本質なのだと確信した瞬間、入退場口のほうから先輩ウエイトレスの声が響いた。「お客様、お見えです」
客入れを開始するという合図だった。隣の卓のウエイターが、もう磨く必要もないだろうに磨いていたグラスを置き、背筋を伸ばして入退場口のほうを向いた。その隣のウエイターも、さらに向こうのウエイトレスも同じようにした。浜野はいつの間にか茶番劇の役者たちに取り囲まれていたことに気付いてはっとしたが、主賓卓を担当する梶がトーションで念入りに椅子を払っていた手を止め、やはり彼らに倣ったのを見て、自分もそのうちの一人なのだと出し抜けに認識した。驚きの勢いに乗り、浜野はみんなと同じように背筋を伸ばした。これまで何度もやってきたその動作には、しかしこれまではなかった力が漲り、やがて現れた客に向けた笑みは完全な作り笑いであると同時に心からのものでもあった。そして、梶やほかの同僚たちより少し遅れて、しかしたっぷりと歓迎の意を込めて挨拶したのだ。「いらっしゃいませ……」
その日を境に、浜野の働きぶりは百八十度変わった。新郎新婦の愚かしさ、披露宴の滑稽さを限界まで高めることこそ我が使命と考えるようになり、全力で働くようになった。接客マナーはもちろん、婚礼における禁忌もしっかり頭に入れ、常に六曜を意識し、テーブルが正しくセッティングされているか目を光らせた。テーブルクロスは山折りの面が高砂のほうを向くようにかける、という類の規則を、浜野はもうくだらないとは思わなくなった。というより、心の底からくだらないと思うからこそ尊ぶようになった。これまでのように一歩も二歩も引いた態度でいては、せっかくの茶番が台無しになる。滑稽さが肝の喜劇では、登場人物全員が愚者であるべきなのだ。
やがて梶もこの喜劇に加わるようになった。やる気はゼロだがクビにならない程度にはやる、という人物像をすでに浜野に見出していた梶は、率先して椅子を引いたり数々の余興を手拍子で盛り上げたりするようになった浜野の豹変ぶりをおおいにおもしろがり、いったい何が起きたんだと興味津々だった。働き始めて半年、新しい仕事にも新しい環境にも慣れ、当初の緊張も失われつつある頃だった。
浜野が営業事務所のゴミ箱から婚礼見積書を拾ってきて、行きつけのラーメン屋でかわるがわるそれを見たのもちょうどこの頃のことだった。夜の賄いを食べたあとさらに表参道沿いにあるその店の豚骨ラーメンを食べる、というのは、会館で丸一日働いてごっそり失われた塩分とカロリーを取り戻すために二人が見つけた生存策だったが、見積書に記された数字の並びにもまた似たような効果があった。会場使用料、控え室使用料、美容代に衣装代に料理代──常識外れの金額を見ているだけで元気が出た。力が湧いた。これはただの喜劇じゃない、最大出力の喜劇だ。しかもそこから生まれるのは、幻由来の金なのだ。
茶番の演出という業務内容だけでもじゅうぶん愉快だったのに、そのうえ賃金が幻から支払われるとくれば、手を抜く理由は本当になくなった。昇給は勤務年数ではなく働きぶりを見て随時検討すると新田に言われていたので、浜野はなんとしても最高額の一六〇〇円まで時給を上げてやろうと決めた。梶もおもしろがってその方針に乗り、自然と競争の恰好になった。
二人の野心を誰よりも喜んだのは、裏方の司令塔としてデシャップ業務についていた汐見だった。披露宴の進行とタイミングを合わせつつ時間内にコース料理を出し切るというのがその仕事で、経験と自信と決断力、そして何より統率力が求められた。本来の汐見は穏やかな人物だったが、披露宴が始まると火がついたようになり、さっさと肉を持って来いとランナースタッフを追い立て、とっとと魚を食わせてこいとホールスタッフをせっつき、必要があれば役職付きの社員だろうと他部署のチーフだろうと内線越しにきっちり苦情を申し入れ、デシャップ台の前から一歩も動かずして披露宴の裏舞台を切り回した。誰もが彼に一目置き、全幅の信頼を寄せていたが、一つ、大きな問題は、その仕事をその水準でこなせるのが彼しかいないことだった。
そこで浜野と梶に白羽の矢が立った。二人が時給競争をしていると知った汐見はすぐさまキャプテンの入江にかけ合い、彼らを自分の後継として教育する許可を得た。入江は上にも下にも厳しい人物だったが、汐見だけは完全に信頼されていたので──二人は同期の友人同士で、長年阿吽の呼吸で大会場を仕切ってきた仲でもあった──話は早かった。
「客席で愛想振りまいてるうちは、どんなに頑張っても一三〇〇止まりだ。こっちの仕事を覚えてようやくその先へ行ける」汐見にそう吹き込まれ、浜野と梶も乗り気になった。
デシャップ台から的確な指示を飛ばせるようになるためには会館の深部を知る必要がある、ということで、二人は早速薄暗い裏舞台へ放り込まれた。そこはいつ訪れても修羅場じみている厨房や、水音とベトナム語しか聞こえてこない洗い場など、外部から完全に遮断された世界だった。それらの場所で働く人々は孤島で暮らす住民よろしく独自の文化を作り上げていたため、接客とはまた別のコミュニケーション法を身につけることも新たな仕事に加わったが、付き合いという点で苦労したのは意外にも同じ制服を着た連中との関係だった。カサギスタッフ仲間、配膳の裏方仲間、しかし所属する会場は異なる。そういう場合が一番揉め事が起きやすかった。基本的に皆時間に追われてピリピリしている上、同じ仕事をしているせいで相手の粗が見えやすいのだ。そっちの料理が捌けないせいでうちの料理が出てこないとか、あっちの連中は倉庫の使い方が汚いとか、その手の細かな言い争いが絶えなかった。数の少ない備品の取り合いも頻発した。
スタッフの多くが自分の会場に帰属意識を持っていること、と同時にほかの会場を軽視する傾向があることに気付いて浜野はなんとも白々とした気持ちになったが、反対に、梶はカッカと熱くなっていった。そして、一基しかない貴重な運搬用リフトを使う順番を巡ってこれまででもっとも深刻な口論が起きたとき、「そっち何名だ?」と、ついにそう言い出したのだった。
そちらの会場で行われる披露宴の出席者は何名か、つまり規模はどのくらいかという意味の質問だったが、これは、規模が大きくなるほど披露宴を執り行う上での苦労も多くなり、準備も先手先手で取り組まねばならないという共有意識をダシにした、紛れもない脅しだった。何しろ海神の間は高堂会館最大の会場で、ほかが客数で勝てるわけがないのだ。最大収容人数で見ても、水鞠の間五〇名、朝凪の間七〇名、千重波の間九〇名に対し、海神の間は一五〇名と圧倒的だった。
だからこそ梶は、一撃必殺の技としてその数を持ち出したのだった。「そっち何名だ?」と聞かれて八三、六一、とぼそぼそ答えた千重波の西崎と朝凪の本間に、「一四五」と海神の梶は自信たっぷりに差を見せつけた。ちゃんと話し合おうと抗議する水鞠の岸下のことも、「黙れ、二二」とねじ伏せた。「もう一度言うぞ。一四五だ」
浜野はなんとかこらえていたが、耐えきれなくなり、そこでとうとう笑い出してしまった。披露宴が持つせっかくの滑稽さを仲間たちの敵意に冒涜されたような気がしていたが、梶の強弁は披露宴も顔負けの滑稽さだった。それに飲まれて素直に答える西崎と本間、あっさり負けて赤面する岸下、まるで砲台数のように示された数字の並び、そもそもの争いの理由、わざわざ東京まで出てきてこんなことに巻き込まれている自分。何もかもが可笑しくて浜野は一人で笑い転げた。みんなは不審げに浜野を眺めるうちに闘争心をなくし、結局、時間的に切羽詰まっているところを優先するということでその場は手打ちとなった。
そうこうして一日の仕事を終え、疲れて重くなった足で境内を歩き出すとき、高堂会館という世界に飲まれかけていた自分に浜野はしばしば気が付いた。実際のところ、簡単な仕事ではなかった。与えられた任務をこなすと同時にその一つ一つの滑稽さを笑う、などという余裕を保つのはまず無理だった。冷や汗をかく出来事が毎回必ず一度は起きたし、ミスをすれば落ち込んだ。教わることの中に旧弊があればいかにして改めるべきか悩んだ。そういうとき、浜野の心身はすっかり高堂の常識と論理に埋もれ、甚だしいときには勤務中ずっと、つまり一日のうち十二時間ものあいだ、浜野独自の感性や価値観は封じ込まれたままだった。
それがそのとき、たちまち息を吹き返すのだ。高堂の森から来る夜風には、その柔らかさとは裏腹に肌を透過していきなり腹の中を冷やしにくるような無遠慮さがあった。軽く吹かれるだけで目が覚め、息が軽くなる。起き抜けの心が元気いっぱいはずみだし、そうだすべては幻だった、幻のために身を粉にして働いていたんだったと、飲まれかけていたことさえ愉快に思える。ライトアップされた夜の日本庭園では、その日、新郎新婦が宴後の写真撮影をしていた。白いタキシードと赤いドレスは暗い境内でどぎつく光り輝くことで結婚披露宴の虚構性を浜野に完全に思い出させ、週明けはきっといい場面が書けるだろう、今書いているものはきっといい脚本になるだろうという予感が熱い血になり身中を巡った。
浜野は携帯電話をいじるのに夢中で歩調の遅くなっている梶を振り返ると、興奮にまかせて大声を浴びせた。「早くしろよ、ラーメン食いたい!」
梶は目も上げなかったが、口だけはこちらに応えた。「おれ今日、味玉子トッピングする」
「おれ今日、初めて全部のせにしてみる」
「じゃあおれも、やっぱり全部のせにしてみる」
「だったらちんたらすんなよもう」そう返してから、ふと思い付き、「梶、携帯電話をポケットにしまい、早足で歩き出す」とシナリオスクールで習ったト書きふうに言ってみた。するとA4用紙に書き付けるときには感じたことのない、かすかだが確かな万能感をおぼえ、その驚きと楽しさを味わい直すように浜野はもう一度繰り返した。「梶、携帯電話をポケットにしまい、早足で歩き出す」
梶はようやく顔を上げた。たかだか十メートルばかりうしろの顔が、暗さのせいで表情までは読み取れず、ただどうやら笑っているらしいのが肩の揺れと吐息の音でわかった。梶は何か言いたげに吸い込んだ息を飲み込むと、携帯電話をポケットにしまい、早足で歩き出した。万能感がみるみる胸を満たし、浜野は声をたてて笑った。
追いついた梶と並んで歩き出す直前、目が自然と拝殿のほうへ流れ、呼ばれた感じがそのあとで来た。外灯もなく、篝火もとうに消され、そちら一帯はすっかり闇に飲まれている。神社を囲む帳らしく、そこには人の立ち入りを拒む冷ややかささえある。
しかし確かに何かに呼ばれた。拝殿に背を向け歩き出すと、より強くそう感じた。
経験のない感覚で、怯んだが不思議には思わなかったのは、仕事帰りにラーメン屋に寄るようになって以来、退勤後の一礼をしなくなっていたためだった。店に行くには表門から出るのが早く、そうなると拝殿の前を通らない。一礼するためだけにわざわざそこまで行く気にもならない。ただそれだけのことだったが、どこかにずっと後ろめたさがあった。
しかしそんなふうに筋道を立てられることは、この場合、まったくの謎より恐ろしいことに浜野には思えた。呼び声はつまり神社からではなく自分自身から発せられているということだ。でもなぜ、いつの間に、神に義理など感じるようになったのか。あくまで仕事と割り切っていたつもりの一礼が、一年も続けるうちに信心として胸に刻まれ、いつしか深いところまで達していたのか。
観念して引き返そうかとも思った。頭を下げれば楽になる。ちょっと元帥に挨拶していこうと軽く誘えば梶も不審がらないだろう。しかし浜野は腕を組み、怯える胸を押さえ込んで参道を逆行した。恐れは拝殿から離れるほど増したが、足取りはむしろ頼もしくなり、空へと打ち上がる庭園のスポットライト、その光から生まれる新郎新婦の下卑た笑い声に励まされ、浜野はずんずん進んでいった。隣では梶が、「浜野、全部のせが超楽しみ……」とト書きふうの物言いを真似ていた。「全部のせが楽しみすぎて、今にも走り出しちゃいそう」
「違うよ、ト書きはそういうんじゃない」
「何ガキ?」
「トガキ」
渋柿? クソガキ。歯磨き。生牡蠣。悪あがき──と二人は交互に脚韻を踏み、参道の真ん中を踏んで進んだ。庭園から遠ざかると再び闇が濃くなったが、スポットライトの光が薄れながらも伸び、明治通りのきらめきと結びついたので、それを辿って二人は無事に鳥居をくぐった。
会館での仕事、アパートでの家事、そして創作。この三つが互いに刺激し合うかたちで浜野の日常は勢いよく稼働していた。松本にいた頃の自分を思うと、なんだか信じられないようだった。
中学でも高校でも、浜野はたいていぼんやりしていた。面接のとき新田にも話したように、「全然関係ないことがふっと頭に浮かんで」くる。すると授業中でも、人といても、半分そこからいなくなったようになる。友人には笑われ、教師には叱られ、たまにできる恋人には捨てられる原因になったがやめられなかった。身についた癖でどうしようもないというのもあったが、それ以前に、ただそうしていたかったのだ。
目の前で起きていることより、頭の中で起きていることのほうが浜野は好きだった。目の前でなされる会話より、頭の中でなされる会話のほうが楽しかった。浜野にとって現実とは豊かな舞台を組み上げるための広い広い資材置き場、あるいは肉体の置き場所で、精神はいつもその反対側にあった。
こうしたまま生き続けるのは可能だろうか、可能だとして、具体的にどうすればいいだろう──大学受験に一斉に挑みかかっていく同級生たちから目をそらし、そんなふうに悩んでいた高三の自分に、可能だよ、とできることなら言ってやりたい。未来の浜野はそう思う。そうしたまま生きるのは可能だよ、適当な理由をつけて家から出ればいいだけだ。大事なのは一人になること。とにかく一人になるんだよ。大丈夫、親はそこまで騒ぎやしない。なんといってもあの二人がいる。おまえのお姉ちゃんたちがいる。秀才路線を極めてくれたあの国立大生二人のおかげで、おまえのことは諦めてくれるよ、というか、とっくに諦めてくれてるよ。いい家族! 気楽にいこう。
一人の生活がこれほど性に合っているとは、自分でも驚きだった。一年ももたず松本に帰ることになるかもしれないと、実はそう思っていたのだ。何せ家事などしたことがない。光熱費の支払い方も、ゴミの出し方もよく知らない。それでも一人で目覚める朝と、無人の家に帰る夜に浜野はたちまち魅了され、この暮らしを手放すまいと本気になった。
やってみれば、しかも何も苦ではなかった。料理や洗濯は楽しかったし、掃除は気分爽快だった。トイレはいつもピカピカにした。シャツにはきちんとアイロンをかけた。新居となった北赤羽のアパートは日当たりが良かったので、職場で話したら仰天された上になぜか大笑いされたが、月に一度カーテンを洗う習慣がついた。自分の命を自分で維持しているという実感が、何よりも嬉しかった。
シナリオスクールで脚本の書き方を覚えると、その実感はより確かなものになった。学校を選んだのは父親で、評判やら実績やらをずいぶん気にして決めたようだったが、金を出す以上はこちらに主導権があるのだという息子への圧でもあったようだった。住む町を決めるとき、部屋を決めるとき、引っ越し業者を決めるとき、万事がその調子だった。浜野は決して口を挟まなかった。何せ黙って従えば、それですべて整っていくのだ。戻るあてのない大金をまたたく間に失った父親は、そうしてただ静かに佇んでいる息子を見て、おまえは世界一おとなしい居直り強盗だなと半ば感心したふうに言った。
ともあれその父が選んだシナリオスクールというのが、悪くないところだったのだ。そこには浜野がおおいに警戒していた暑苦しい芸術論や精神論は存在せず、講師はごく実際的な基礎技術を教えてくれ、ペラ換算での時間感覚を身につけさせてくれ、様々な課題で実践させてくれた。浜野は書いた。どんどん書いた。楽しくて仕方なかった。この点において自分はほかの受講生たちと違っているだろうと浜野が確信したのは、それまで何も書いた経験がないことだった。シーンやアイデアが浮かんでも、浜野はずっとそのままにしてきた。特に衝動を感じることもなかったから、文章にも絵にもせず、メモ一枚残すことなくただひたすら脳内に溜め込んできたのだ。それがいよいよ出力の段になり、初動はさながら休火山の覚醒だった。書きたかったのだという発見にまず驚き、書くことで自分の存在が確かになっていく、その強烈な実感にさらに驚いた。いたのかおれも、この世界に。そんなふうに思った。
一年のつもりだったスクール通いはもう一年延長し──だめもとで頼んでみると、渋々ではあったが父はそのぶんの学費も出してくれた──上級のクラスまで進んだ。創作はますますおもしろくなり、小さなコンペで賞をもらうところまでいったが、スクールとの関わりはそこまでだった。受賞した途端に担当講師が師匠面するようになり、今後の面倒を見てやるから助手になれと言い出したのだ。その口ぶりからはこれまで感じたことのなかった芸術論と精神論、さらに何やら権威じみた匂いまでもがぷんぷんと漂い始め、浜野はびっくりして一目散に逃げ出した。上演や映像化への興味も、他人の作品への関心もなかったので、そのところで心性の大きく異なるほかの受講生たちとも距離を置きたくなっていた頃だった。そもそも脚本家になりたいわけじゃなかったとそのときに思い出し、あとは好きにやることにした。
二十五過ぎたらあっという間だぞと汐見からはよく言われていたが、出力の技術が身についた上で足枷が外れたこのときから、浜野の時はぐんと速度を上げた。次から次へと執り行われる婚礼と、高堂仲間たちとの行楽──スキーに花見に海水浴、鍋パーティーにバーベキュー、旅行気分での免許合宿。そのすべてが現実という資材置き場に投げ込まれ、分解したり、歪んだりしながら作品に組み込まれていった。文句なしのサイクルで、一年、二年と飛ぶように過ぎたが浜野の生活は変わらなかった。虚構の砦の塀は高く、完全に守られている気がした。
自分だけの部屋に寝転び、陽に透かせた完成稿を眺めていると、幸せに息苦しくさえなった。可能だよ。そう伝えたくなるのはそんなときだ。そのままでいいよ。今にもっと楽しくなるよ。ほかに誰もいないのに、何もかもが揃ってる、そんな場所にもうすぐ辿り着くんだよ。
============================
続きは古谷田奈月『神前酔狂宴』(河出書房新社)で!