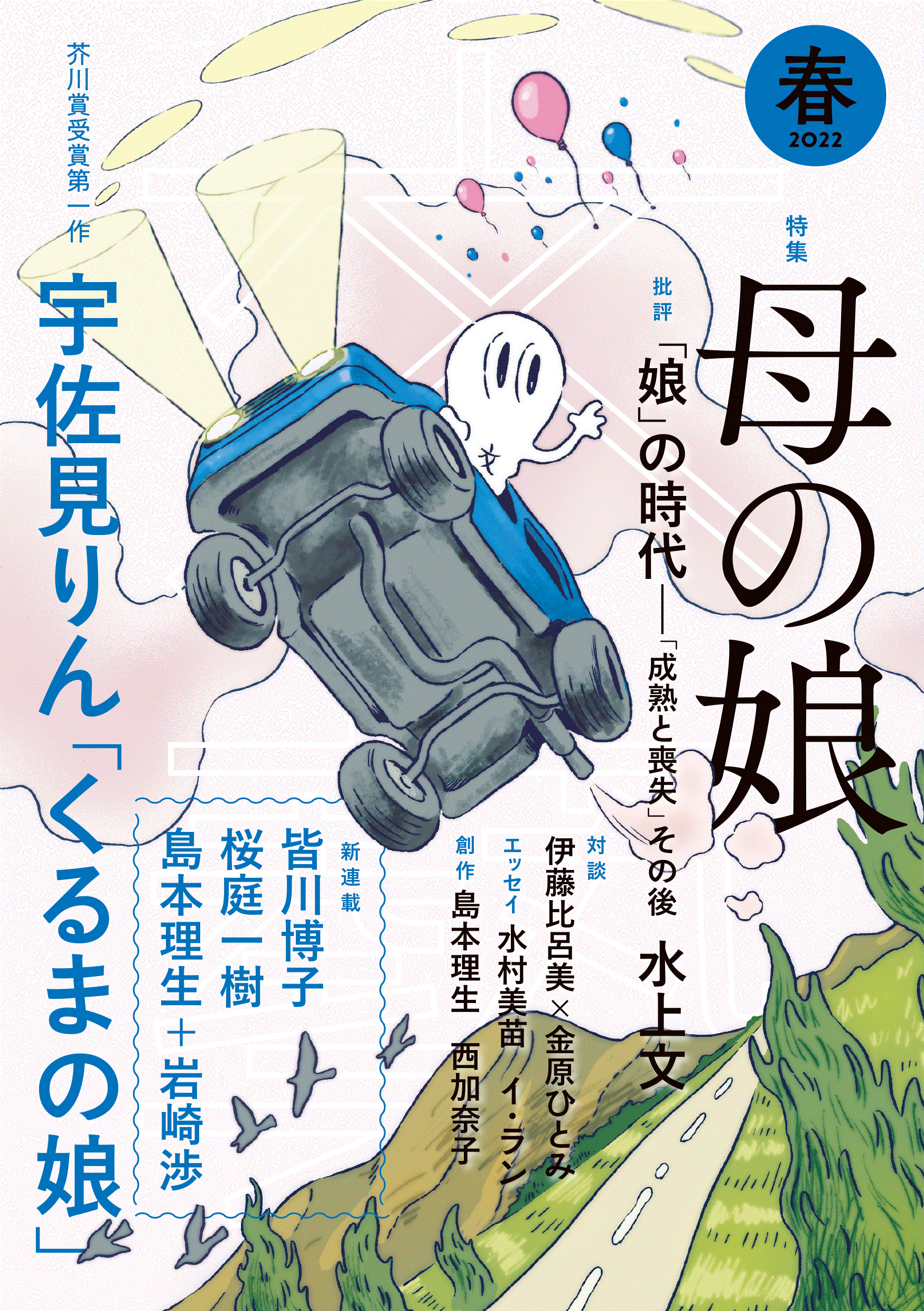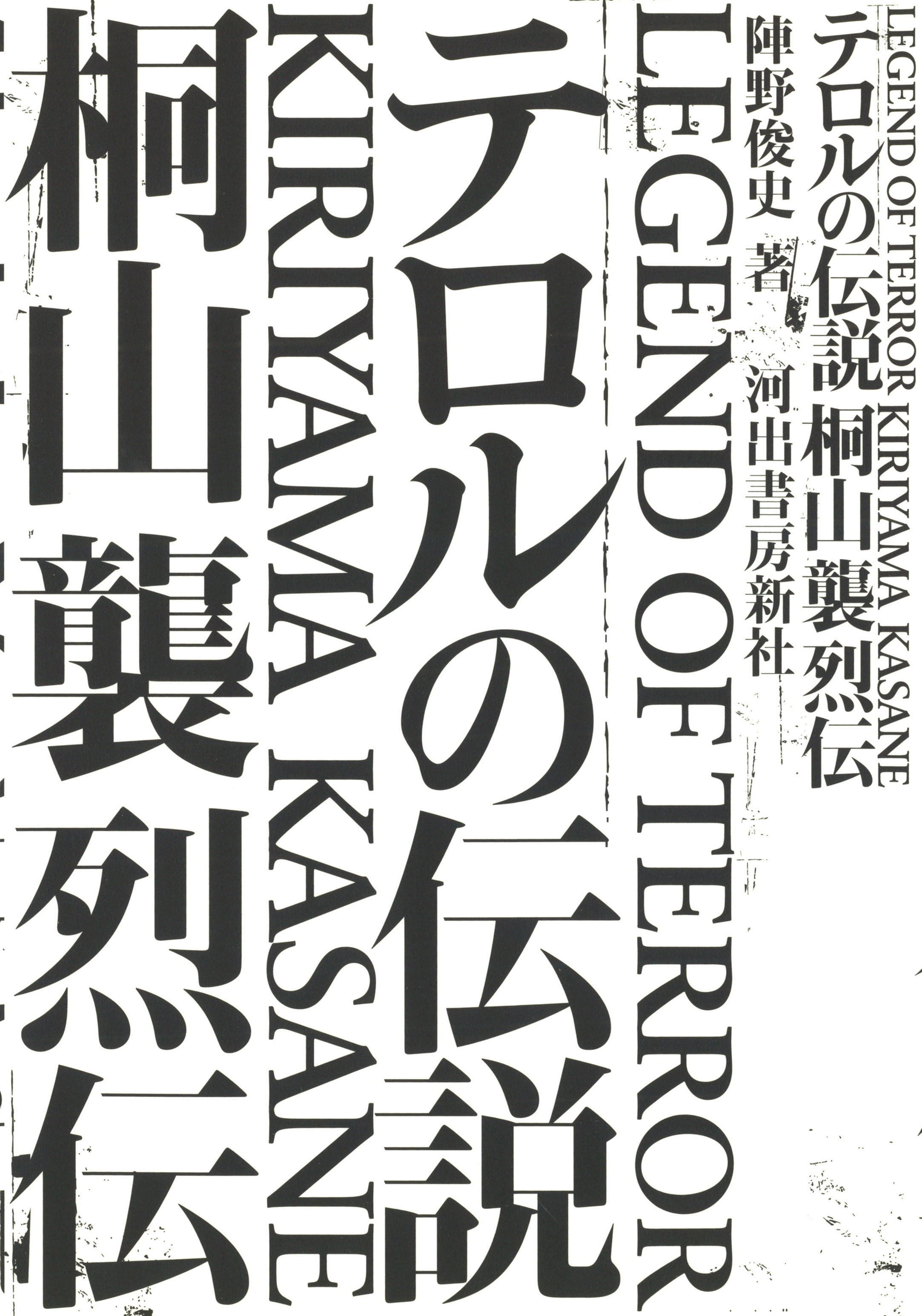
単行本 - 文藝
『テロルの伝説 桐山襲烈伝』[書評]野崎歓
陣野俊史
2016.08.17
『テロルの伝説 桐山襲烈伝』
陣野俊史 著
【評者】野崎歓
テクスト絶対主義にあらがって
なぜこの人の名が忘れられているのか。そのこと自体のうちに、われわれの時代の深い空虚が示されているのではないか。そんな憤りにも近い思いに突き動かされながら、陣野俊史の筆づかいは決して性急に“再評価”を訴えかけるのではなく、ぐっと自らを抑制しつつ、作家・桐山襲のたどった決して長くはないが重い問いかけを含む文学的行程に寄りそおうとする。
それは批評家としての自己に制約を課す姿勢であるともいえる。「暴動」や「人種差別」や「戦争」をめぐってシャープな論考を上梓してきた著者のこと、「天皇制」や「沖縄」や「内ゲバ」を扱う桐山の作品から刺激的なテーマを抽出し問題提起的に立論しようと思えばたやすくできただろう。しかし著者はシンプルな評伝のスタイルを遵守し、作者の人生と作品を切り離すことなく叙述しようと試みた。そうすることが「文学の脆弱化」に抵抗し、テクスト絶対主義にあらがって作者の生と作品を取り戻す手段となるからだ。
その内容自体が吟味されてというよりも、「『天皇暗殺』を扱った小説」云々という「週刊新潮」の「煽情的」な記事ゆえに右翼の攻撃にさらされたデビュー作「パルチザン伝説」(一九八三年「文藝」掲載)以来、闘病のさなかに書かれた『未葬の時』(一九九四年)までの十年と少しの軌跡が示すのは、一貫して自らを枉げることなく書き続けた作家の生の静謐な充実であり、東京都教育庁(教育委員会の事務局に相当)に勤務する日常のただなかでラディカルな作品が結晶していったという事実だ。六〇年代から七〇年代にかけての学生運動の高揚と挫折の意味を問い続け、一見過激な政治事件を主題にしながらも、桐山の表情は実にクールに落ち着き払い、政治と文学の安易な結託などみじんも信じてはいない。彼が貫いたのはひたすら、「現在に対する憎しみありき」と作家自らのいう、現代社会への根源的な違和を研ぎ澄ませることだった。しかもそこに「抒情性への無限の傾斜」が隠しようもなく顔をのぞかせるところが、桐山作品の魅力の秘密でもある。
評者など、実は桐山襲についてほとんど無知だったのだが、著者・陣野俊史は「できるならば、彼の遺した小説をすべて、一字一句削らず」書き写したかったと述べつつ、懇切丁寧に作品を紹介してくれている。そのおかげで触れることを得た桐山の世界は、評者にとっては端的にいって大江健三郎に直結する文体の稠密さと硬質なリリシズムを感じさせるものだった。それは村上春樹以前の文学ということでもある(考えてみれば桐山は村上と同年の生まれなのだが)。時代遅れだというのではない。逆に、そこには明らかにその後抑圧された何かがあるのであり、だからこそいま、桐山の文学が回帰してくる必然性も存在する。古川日出男や目取真俊へと接続しつつ、本書はその回帰への期待を強くかきたててくれるのだ。