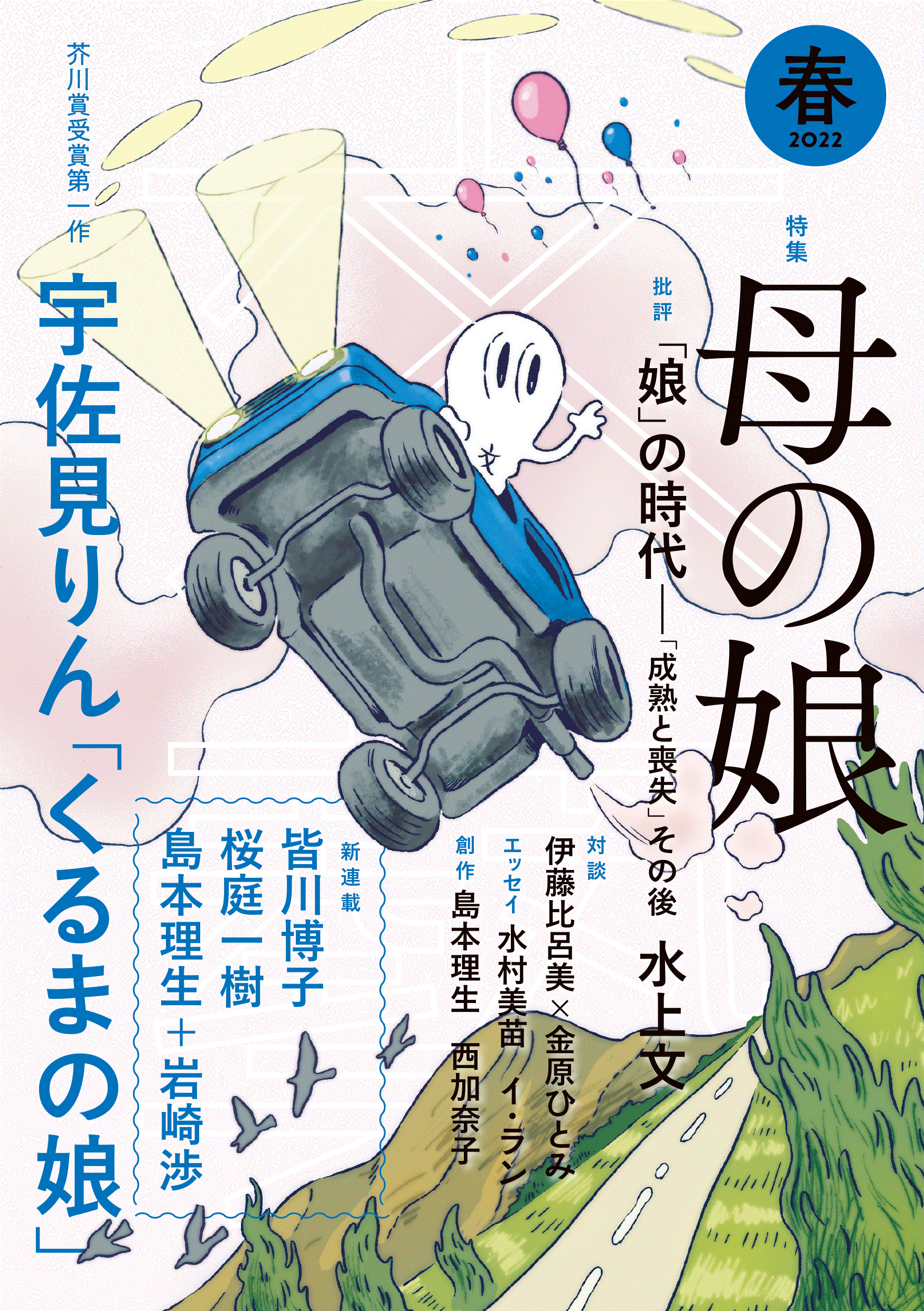単行本 - 文藝
必要悪は単なる悪である/『ねこのおうち』[書評]武田砂鉄
柳美里
2016.08.05
『ねこのおうち』
柳美里 著
【評者】武田砂鉄
必要悪は単なる悪である
読み進めるうちに、ふと、「死」を放置した幼少期の数日間を思い出してしまった。スーパーのレジ付近で「特売」だか「格安」だかの文句とともに五〇〇円で売られていたカブト虫を親にせがみ、これは自分が育てるからと意気込んだものの、買った翌々日にすっかり動かなくなった。「虫かご、絶対に覗かないで」と言いつけると、親は定期的に果物のブツ切りを渡してくれた。中に入れておいた餌は減るはずもないから、土をまぶし、さも手を付けたかのようにカモフラージュし、三角コーナーに捨てた。数日が経ち、さすがに耐えられなくなり、泣きじゃくりながら伝えると、親は「いつ言い出すのかと思っていた」と返した。すっかりひからびて変色してしまったカブト虫を近くの空き地に埋めにいった。
私たちは「死」を放置する。気付いているのに放置する。日本の自殺者数は平成一五年の三四四二七人をピークに、このところは六年連続で減少している。内閣府の「平成二七年中における自殺の概要」は、真っ先に「自殺者の総数は二四〇二五人で、前年に比べ一四〇二人(五・五%)減少した」と自慢げに書く。この数値に基づき、「前年に比べてこれだけ減少しました」との記事が並ぶ。死んだ数を知り、安堵する。それはいかなる安堵だろう。「何とかミクス」の成果で雇用が上向いたから自殺者が減ったと、死の数値を好転の言い分に使う人もいる。一四〇二人も減少したと前向きに語られるだけで報道が閉じられる時、二四〇二五人の自殺者が放置される。
東日本大震災後の福島原発事故を指して、「死亡者が出ている状況でもない」と愚鈍な発言を漏らして再稼働を謳ったのは自民党・高市早苗政調会長(当時)だが、とりわけ3・11以降、死を放置して忘却し、「この道しかない」と勇む動きが散見される。ひからびたカブト虫を隠した自分のような、死を「なかったことにする」態度に、私たちはどういうわけか慣れてしまう。ともすれば親しんでしまう。
命を凝視し続けてきた作家・柳美里が本作で対峙するのは、「死への鈍感」と「生への敏感」だ。蔑ろにされて死に追いやられていく命を、生につなぎとめていく。三匹同時に産まれたものの、一匹だけ「腹に入れ墨みたいな模様があって、ヤクザの親分みたい」な、キジ虎猫のニーコ。公園に捨ててくるように旦那に頼み込んだ妻は「今夜はスキヤキだから早く帰ってきて」と告げ、旦那は、ねこを公園に放る。命を捨てた後で、スキヤキを食らう。
躊躇などない。しかし、悪事は、ねこの所作に刻み込まれる。「ねこは噓をつきません。/どのねこも、ひとになついているということは、初めからノラだったわけではないのです。元は、誰かの飼いねこだった」のだ。ニーコは幸いにもおばあさんに助けられ、一〇日間つきっきりの世話を受け、生きる力を取り戻す。やがて、おばあさんは痴呆となり、生ゴミをあさるなどして飢えをしのぐニーコ。家にやって来た息子たちは「呆けた親なんて、見たくなかったな……」「父さんは立派だったよ。脳卒中でパタッと逝ってくれたから」と、撤収作業と金勘定をテキパキ済ませ、鼻をつまむように出ていく。外へ出ざるを得なくなったニーコは六匹の子供を産んだ後に、草むらに仕掛けてあった殺虫剤入りの肉だんごを食べ、命を絶たれてしまう。
毒だんごを仕掛ける側にも言い分はある。
「ねこの放し飼いは迷惑なんですよ。公園の砂場や家庭菜園にうんこは埋めるわ、ブロック塀におしっこは引っ掛けるわ、ほんとうにサイテーですよ。光町には、ねこアレルギーのお子さんが居るお宅だってあるんですよ」。
残されたニーコの子供六匹(ぼんぼり尾の茶虎、キジ虎、カギ尻尾の茶白、真っ白な長毛、真っ黒な長毛、サビの長毛)に、手を差し伸べる人が現れる。残された命を絶やさぬように、水やりを続けていく。それぞれがそれぞれの「おうち」を見つける。
人間の都合で産まれた命が人間の不都合によって処分されていく。「譲渡会で飼い主を見つけられなかった動物たちは三日以内に命を絶たれます」……小さな命が黙々と踏みつぶされていく。二〇〇〇年度には五〇万匹を超えていた犬猫の殺処分数(動物保護団体『地球生物会議(ALIVE)』調査)は年々減少してきている。個々人の活動や各自治体の努力の賜物だが、これもまた表層的な「減少している」との伝達で済まされ、今日殺されていく命からまだまだ目を背ける人がいる。誰かが捨て、誰かが救い、そのズレが殺処分数となって表出する。数値の増減ばかりが注視され、今そこで途絶えようとする命を直視しようとしない。蓋をする。
「愛玩動物」の「玩」には「おもちゃにする。もてあそぶ。」との意味がある。売れなければ五%引きになり、それでも売れなければ二〇%引きになり、それでも売れなければ殺される。二〇一二年の動物愛護法改正により、相応の理由のない犬猫等販売業者からの引取りを自治体が拒否できるようになるなどの改善が見られたが、その一方で、ペットを有料で引き取り、悪質な環境で放置する業者も増えている。命を軽視した新たなビジネスが生まれている。
柳美里は、命のみならず死をも凝視する。絶対に放置しない。数値ではなく個体を見つめる。「必要悪」という便利な言葉があるけれど、それは単なる「悪」をゴミ箱に捨てやすくするためのラッピングかもしれない。
先日、地方の巨大ショッピングモールに出向くと、建物ごとにテーマが分かれており、その一つが「PET MALL」だった。キーワードは「ソリューション提案型ペットモール」とある。意味が分からない。「日本最大級の規模で、すべてが揃うペットパーク。ペットとの絆が深まり、〝夢中〟が広がる」とあった。漂白されたペット空間が、訪れる者を癒す。どんな命でも、断片的にかわいい部分だけを知ることはできる。でも、ひっくり返したグロテスクな断片を塞いではいけない。朽ちる命よりも「スキヤキだから早く帰ってきて」を優先してはいけない。愛玩から愛が抜け落ちれば玩具であり、オモチャ箱の底に置かれたまま蓋が閉められてしまう。柳美里は育まれる命と途絶える命を描写し、その狭間に蠢く叫び声を掬いとる。「生」の輪郭を保つために「死」を直視する。〝夢中〟が広がるだけでは、「おうち」は見つからない。変色したカブト虫を持ち上げ、すっかり脆くなった身体の感触に黙り込んだ日を思い出しながら、命を背負う責務を柔らかに問う柳の筆致に身を任せる。命と命が仄かに照らし合う帰結に救われた。