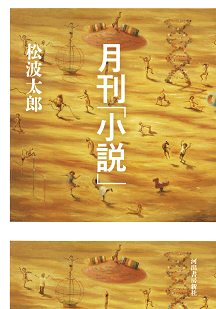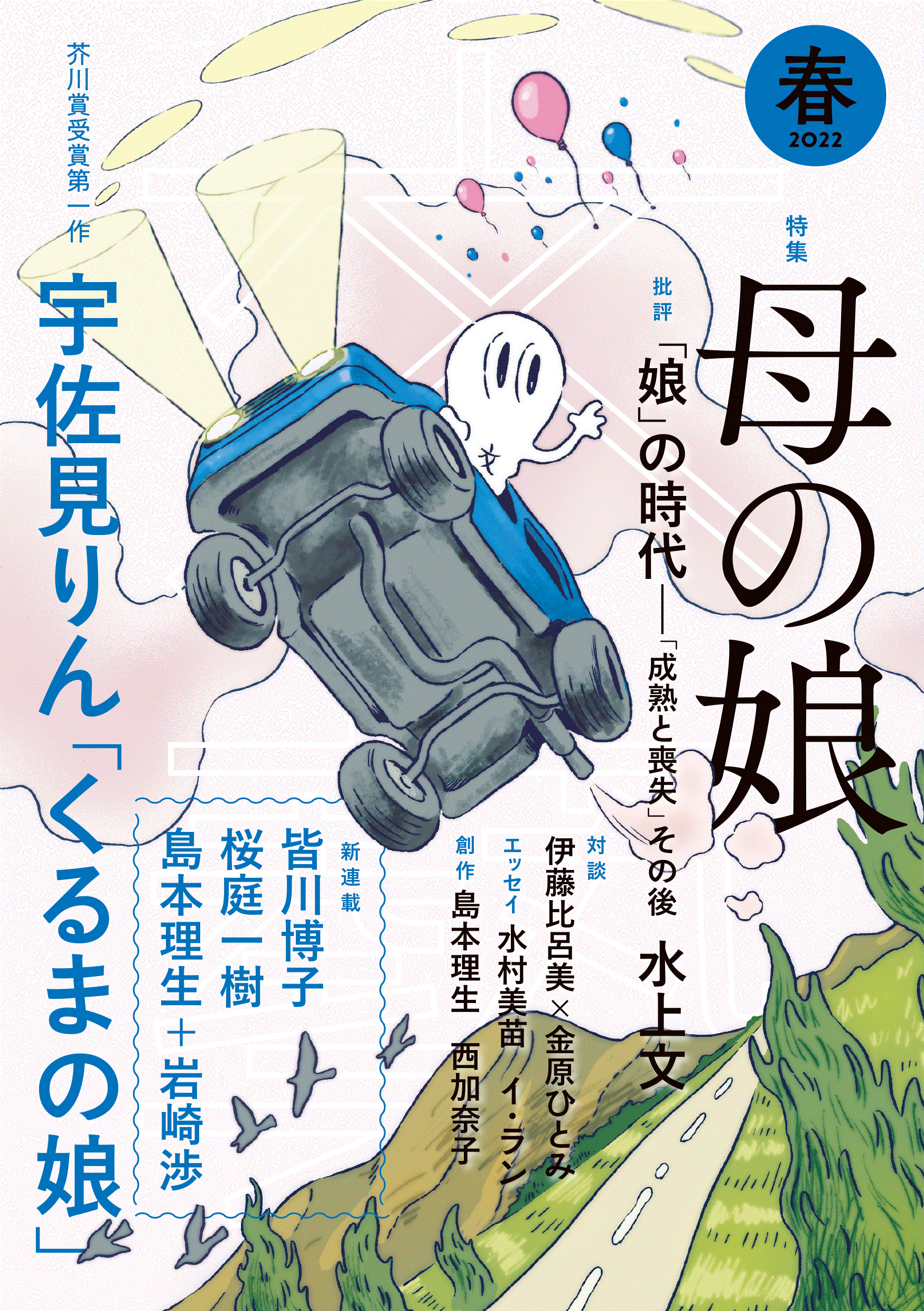単行本 - 文藝
「文学」VS「小説」/松波太郎 著『月刊「小説」』
松波太郎
2016.08.16
『月刊「小説」』
松波太郎
【評者】佐々木敦
「文学」VS「小説」
「文藝」前号の目次に「月刊「小説」」という題名を見つけた時の狐につままれたような感覚は今も覚えている。なんですかそれ? 文芸誌内文芸誌ということらしい。で、雑誌名が「小説」だと。読んでみると、確かに雑誌の体裁を取ってはいる。短編(松波太郎以外の書き手によるものも含まれる)が幾つか掲載されており、あちこちに写真も挟まっているし、なんと広告さえあり、作者紹介もある。だが当然ながら、本気でこの「小説」を雑誌だと思い込む読者など居る筈はないし、そもそも季刊「文藝」に月刊「小説」が載っていることのおかしさはあからさまである(次号はどうするんだ?)。だからもちろんこの「月刊「小説」」はそういう題名の「小説」であるわけだが、ではこれはどういう小説なのか? もちろん「小説」をテーマとする小説なのである。メタフィクション? 確かにメタ的な趣向が満載ではある。だがしかし、その読み味はいわゆる数多のメタものとは、どこかで大いに違ってしまっている。そう思える。ではこれは一体何なのか?
松波太郎は変な小説ばかり書く。題材はさほど変ではないのに、結果として彼の作品は、どれもこれも奇怪な仕上がりになっている。本書に併録された他の三短編「アーノルド」「関誠」「五臓文体論」のどれか一つを読んでみればその変さはすぐにわかる。「アーノルド」はアーノルドという善良なアメリカ人の話。「関誠」は関誠というサヴァンとしか思えない人物とその職場の後輩の話。「五臓文体論」は題名通りの話。会話が多用された文体はすっきりとして淀みなく読みやすいし、特に非現実的な出来事が描かれるわけでもない。にもかかわらず、なんとも言えない不気味さが後味として残る。厭な感じというわけではない。イヤミスならぬイヤ文=イヤな文学流行りの昨今ではあるが、松波小説はそれとも異なる。難解というわけでもない。だが変なのだ。つまりこういうことである。普段われわれが「文学」と呼んでいるものは、こういうものではない。松波の書く小説は「文学」とは相容れない。だから彼が過去何度も芥川賞候補に挙げられているのは、それ自体相当に変なことなのだ。
「月刊「小説」」にこんな一節がある。「紙しかないことに慢心して、小説自身をどんどん限定していき、〝文学〟という名の大説の側に立ち、本来の〝小説〟から離れていったのかもしれません」。すぐ次のように言い換えられる。「紙の一人勝ちであったようなメディアの時代に、紙でできることを追求していった結果、かえって〝小説〟本来から遠ざかっていったということですかね」。つまりこれは一種のメディア論であり、文芸誌論であり、小説論(not文学論)である。だからこういうことだ。松波太郎は「小説」を書こうとしている。それは「〝文学〟という名の大説」に対抗するものとしてある。そして彼は、変なのは、歪なのは、狭いのは、そちらの方だ、と言っている。