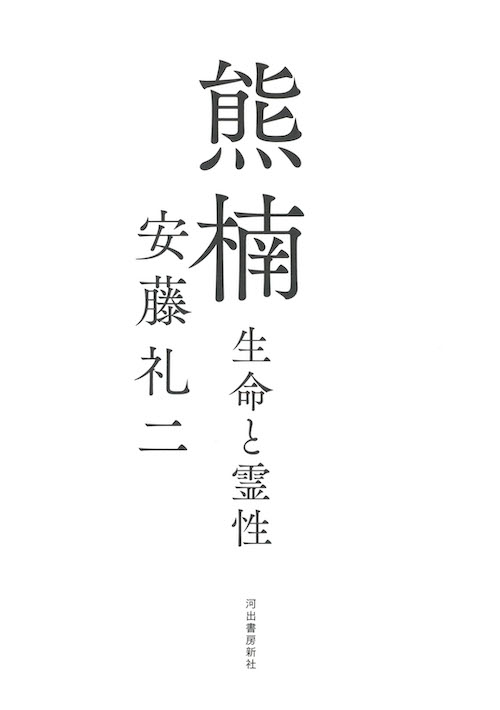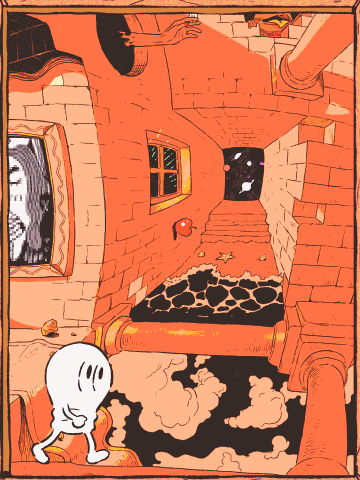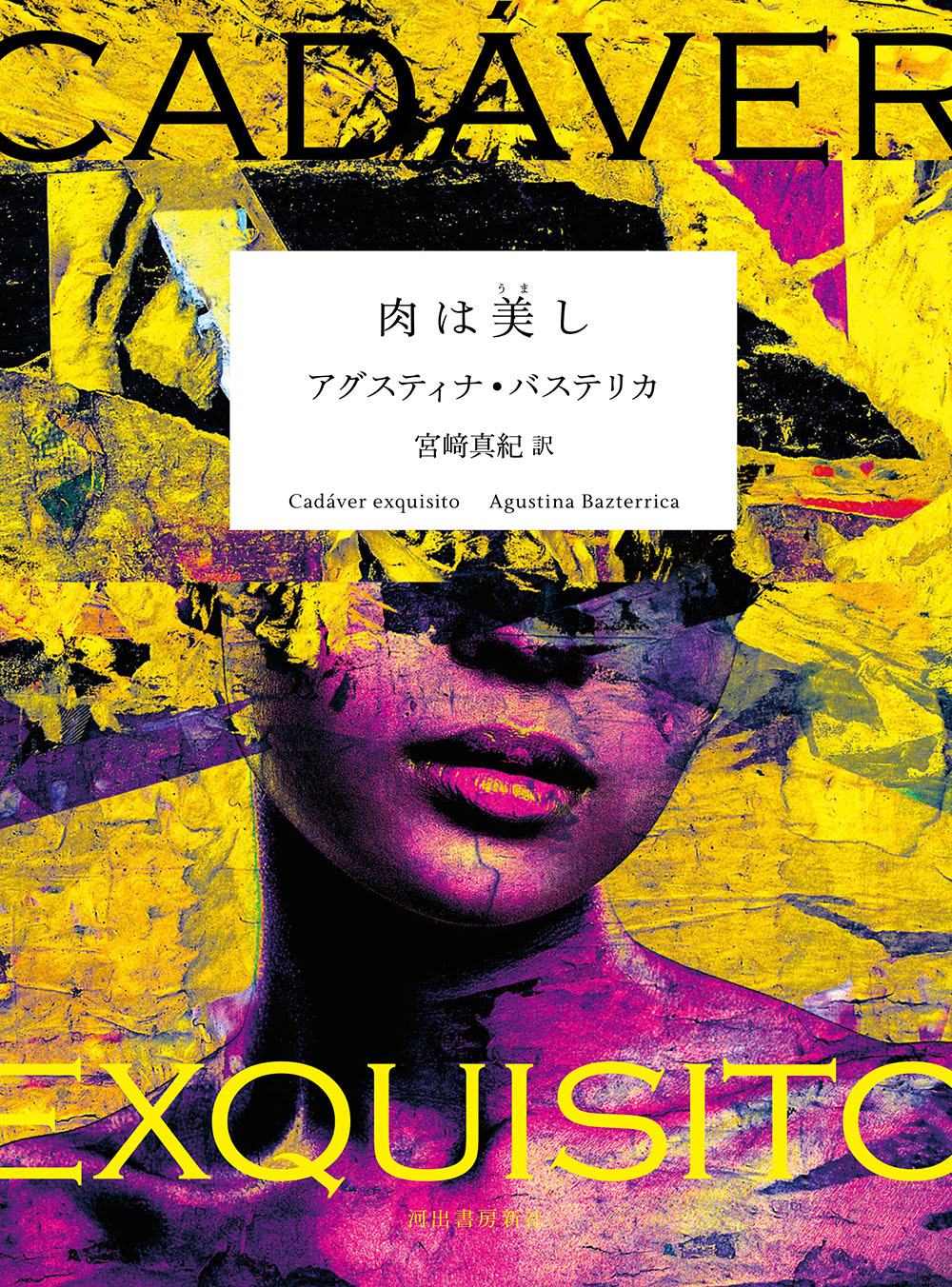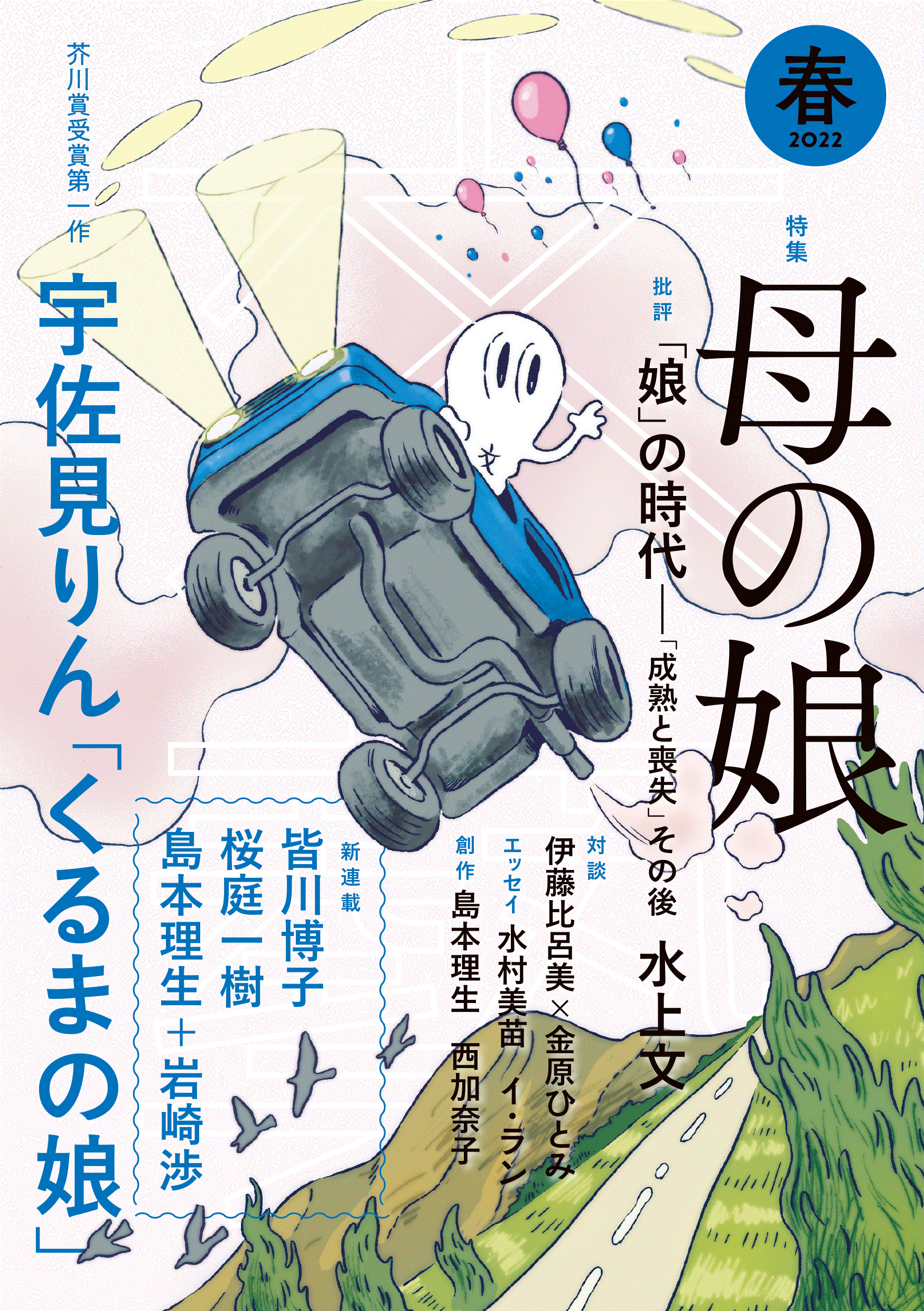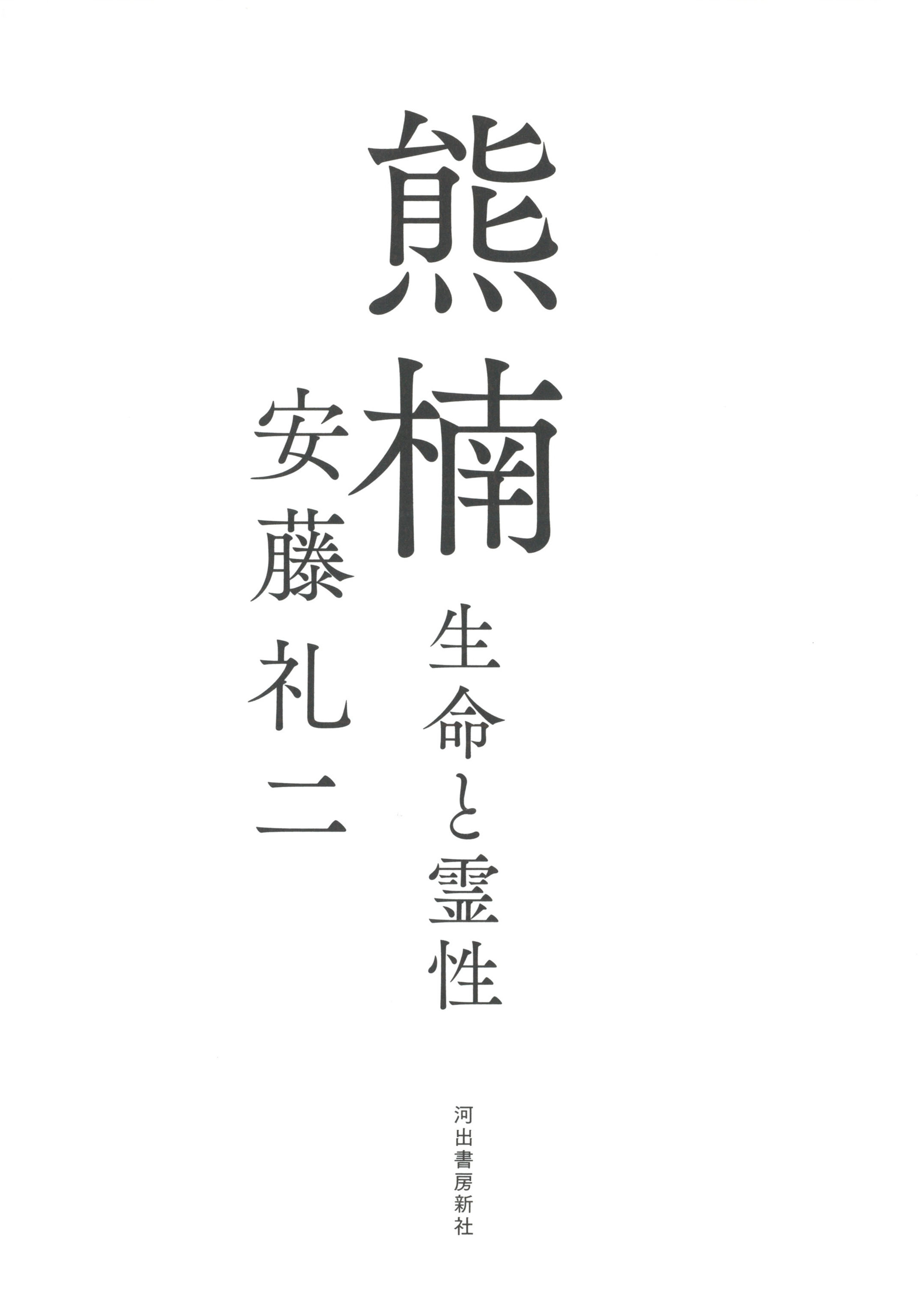
単行本 - 文藝
気鋭の批評家が読む、近代日本哲学の「真の起源」へと迫る傑作『熊楠 生命と霊性』
評者・小田原のどか
2021.02.04
近代日本哲学の「真の起源」へ ――安藤礼二著『熊楠 生命と霊性』
小田原のどか
言葉とは使い、使われるもの、人の道具である。とはいえ、その使用方法は様々だ。この書評はウェブ転載もされるということなので、読者がどのような環境で、メディアで、これを読んでいるかはわからない。いずれにしても、インターネットの普及により、これほど言葉にあふれた時代を人が経験するのは初めてのことだろう。
最近よく思うのだが、道具にもつくられるための時間がある。例えば、打製石器は一時間程度で制作できる。一方で、大きさにもよるが、磨製石器の制作には五百から数千時間かかるとされる。当時の人の寿命を思えば、後者をつくり出すのは制作者の「生命の時間」そのものと言える。
私は、本書『熊楠 生命と霊性』に、石器が磨かれていくように、言葉が磨かれていく過程を見て取る。ここには著者の「生命の時間」がある。どういうことか。編集者として一三年を過ごした著者の、最初の仕事が中沢新一編纂による南方熊楠コレクションだ。そしてまた、折口信夫論で第45回群像新人文学賞評論部門優秀作を受賞したのちに同誌に発表された第一作は、熊楠とアンドレ・ブルトンをめぐる論である。そのように三〇年という時間は尽くされ、熊楠をめぐる言葉は磨かれて、一冊の書物となった。
さて、本書は、南方熊楠の生涯や仕事を、一次資料をもとに詳細にたどらんとする手つきの研究書ではない。「客観的な研究ではなく、主観的で固有の解釈」を「論」として立てること、それが「批評」であると著者は言う。そのような批評の実践として、本書で描き出されるのは、熊楠をめぐる多様な「共振と交響」である。そして、著者が導きの糸とするのが鈴木大拙だ。
本書収録の複数の論考で言及される、一八九三年に米国で開催された「万国宗教会議」で、日本の宗教者は、本邦の仏教の正当性を証明することを強いられる。大拙はここで「東方仏教」なる言葉を創出し、「霊性」について論じた。生命について生涯をかけて問うた熊楠について、著者は、大拙の視点によって「自分なりの熊楠理解が定まった」と言う。
本書の副題「生命と霊性」、すなわち熊楠と大拙は「二つの極」である。本書によれば、前者からは柳田國男の民俗学と折口信夫の古代学が、後者からは西田幾多郎の哲学がそれぞれに生じた。熊楠の「曼陀羅」そして大拙の「霊性」の概念をひもとくことで、著者は近代日本哲学の「真の起源」へと迫る。
磨製石器がおそらくは一人の人の手で仕上げられたものではないように、熊楠をめぐる言葉もまた、複数の者の手で、方法論で、磨かれ続ける。本書所収の「粘菌・曼陀羅・潜在意識」に付記された、「熊楠研究」と「熊楠論」の対立と往還は、まさにその一端であろう。
言葉にあふれた時代に、人の「生命の時間」によって磨かれた言葉を目の当たりにできることは幸いである。そのような幸いが、この書物である。
初出=「文藝」2021年春季号