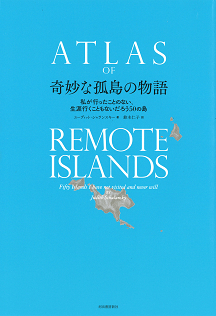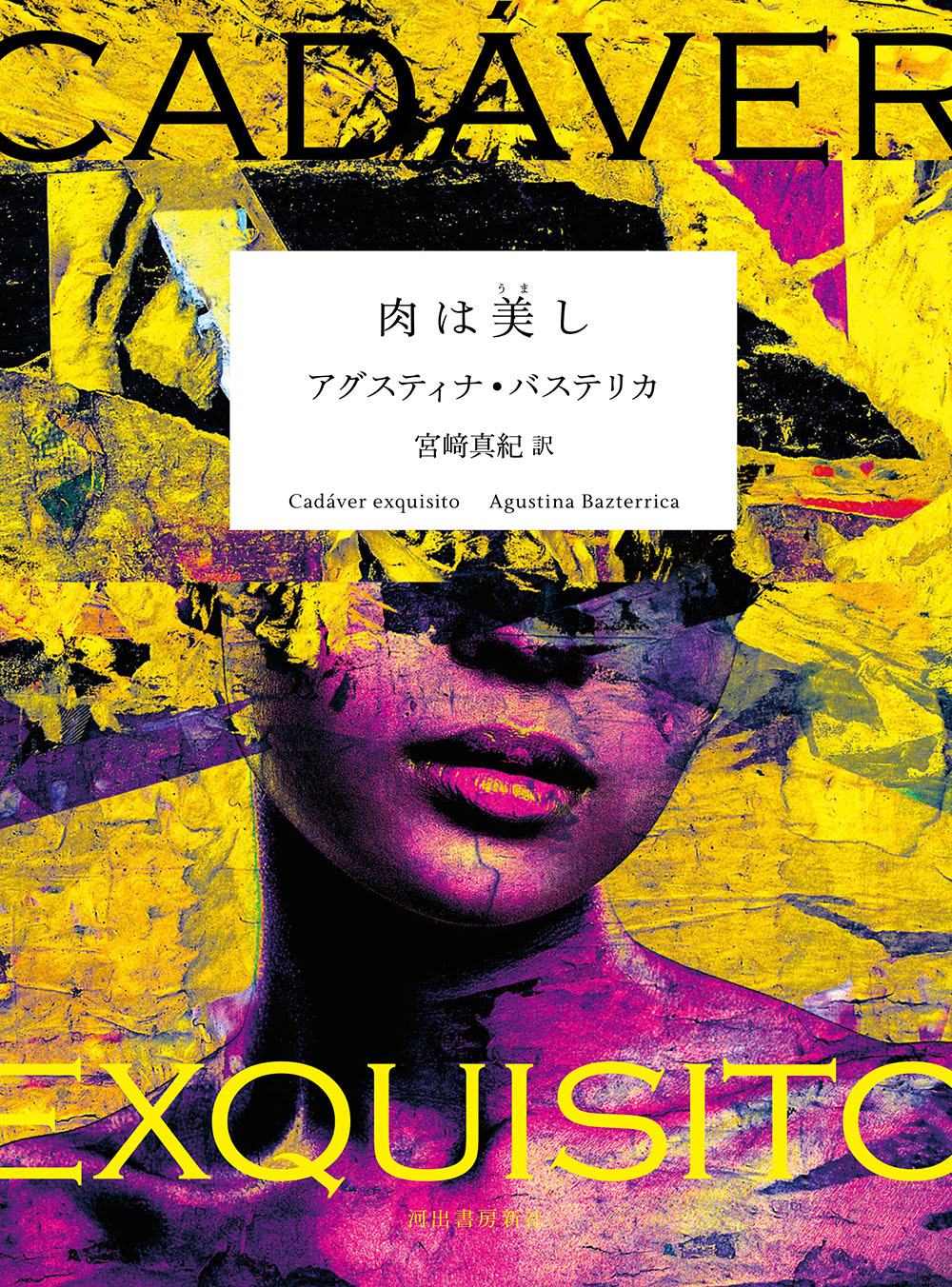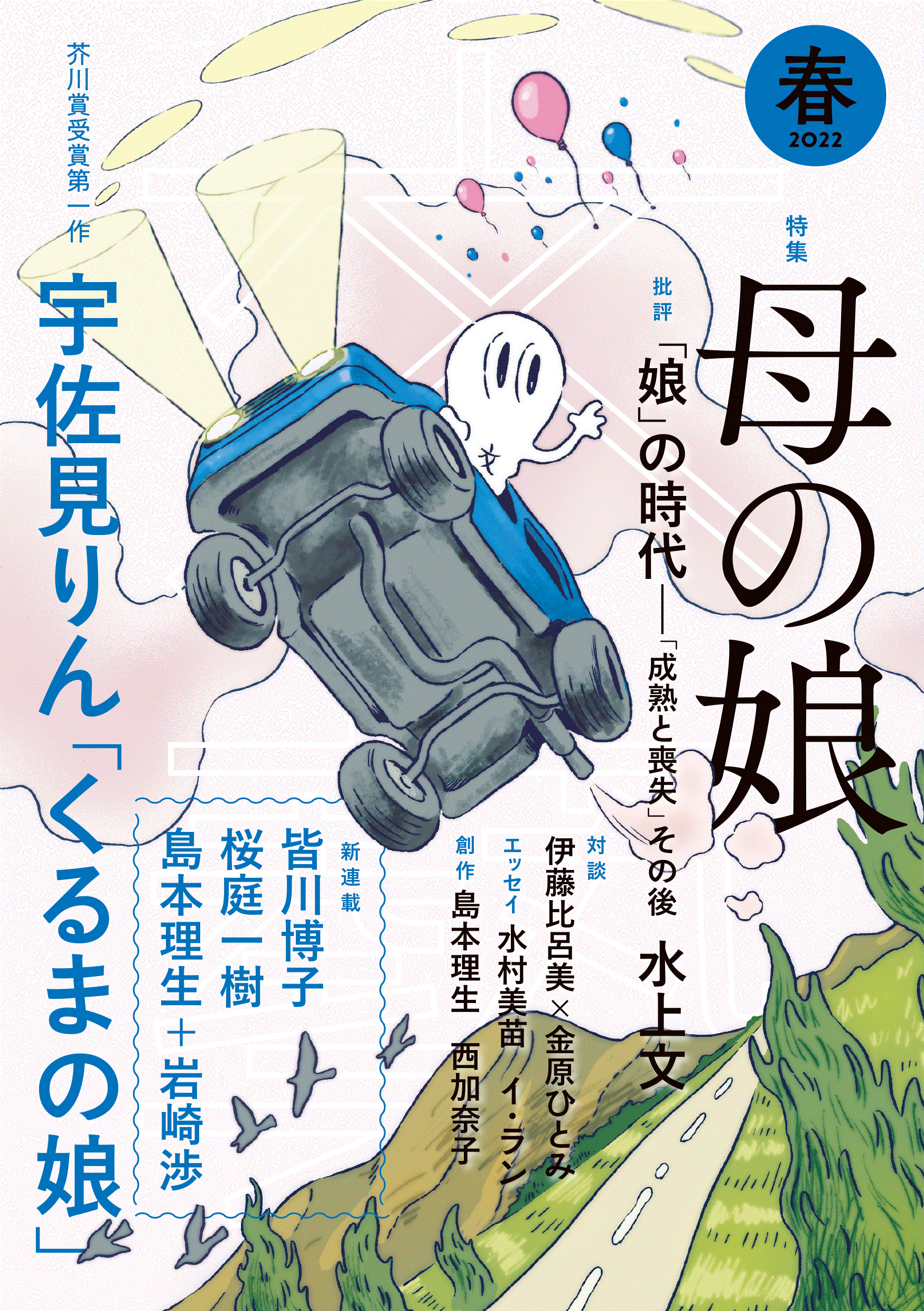単行本 - 文藝
人生ありのままじゃいられない『ゴールドフィンチ』
ドナ・タート
2016.11.28
『ゴールドフィンチ』 (全四巻)
ドナ・タート 著 岡真知子訳
【評者】豊﨑由美
人生ありのままじゃいられない
「風が吹けば桶屋が儲かる」式に、わたしたちは何らかの結果には、さかのぼってみれば必ず原因があるはずだと考えたがる。A→B→C→……Z。しかし、Aが悪しき行為でZが悪しき結果、Aが善き行為でZが善き結果とは、必ずしもならない。善行が最悪の結果を招いたり、悪行が素晴らしい結果を生んだりもする。そればかりか、Z(結果)がまだ出来事の途中にすぎなかったことが、後からわかったりもする。その理不尽さに、世界は、人間は、常に翻弄され続けているのだ。
一九九二年、八年かけて完成させた『シークレット・ヒストリー』でデビューするや、イギリスやフランスをはじめヨーロッパ九カ国で翻訳され、大ベストセラーに。アメリカ文壇を「天才現る!」と騒然とさせたドナ・タート十一年ぶりの新作『ゴールドフィンチ』の語り手テオもまた原因と結果の間で、あっちに転がり、こっちの穴にはまり、さまざまな出来事や感情に振り回される役割を、作者によって担わされている。
〈『ヘラルド・トリビューン』にぼくのことは載っていなくても、オランダのあらゆる新聞にはその記事が出ていた。(略)未解決殺人事件。犯人は不明〉〈前科のあるアメリカ人〉。クリスマスを間近に控えたアムステルダムのホテルに、一週間あまりこもりっぱなしになっている〈ぼく〉ことテオが何らかの事件に関わって、面倒に巻き込まれている様子をうかがわせる場面から、この全四巻の長篇小説は始まる。しかし、詳細は一切語られないまま、物語は十四年前の四月十日、テオが十三歳の時に起こった大きな出来事へとさかのぼっていくのだ。
してもいない喫煙の罪で停学をくらい、母と二人学校の会議に呼び出されることになったテオ。その会議が始まる前、少しでも自分の時間があれば絵画を鑑賞する習慣がある母は、息子を連れて美術館に寄ってしまう。愛する息子に、自分が初めて心から好きになったという、レンブラントの弟子でフェルメールの師匠であるファブリティウスが描いた黄色いフィンチの絵「ゴールドフィンチ(ごしきひわ)」を前に、かの画家を夭折させた火薬の爆発事故について語る母。しかし、テオが気にしていたのは、白髪の老人に付き添われている、古びたフルートケースをぶらさげた鮮やかな赤毛の女の子。彼女に話しかけたい一心のテオは、すでに通過した展示室に戻るという母を見送り、そこに留まるのだが、その直後、爆破テロが起きるのだ。
九死に一生を得ながらも頭を強く打って朦朧となったテオ。必死で母を探そうとする途中で、赤毛の少女に付き添っていた、ウェルティと名乗る瀕死の老人から名画「ごしきひわ」を外に持ち出すよう頼まれ、それを実行に移してしまう。その後何とか自力で美術館から脱出し、歩いて自宅に戻ることができたものの、母は死亡。数ヶ月前に、飲んだくれで賭け事好きな父親が出奔したせいで、孤児という立場になったテオは、いったん裕福な友人宅に預けられることに。やがて、ウェルティが遺した〈ホバート&ブラックウェル〉〈緑色のベルを鳴らしてくれ〉という言葉を頼りにたどり着いた骨董店で、かの老人の共同経営者であるホービーに温かく迎え入れられ、赤毛の少女ピッパが大ケガを負ったものの助かったことを知る。骨董家具の修理名人ホービーのもとに通い、ピッパとも仲良くなっていく中、テオは少しずつ心の平安を取り戻していくのだが、そこに父親と愛人のザンドラが現れ、彼は名画「ごしきひわ」を隠し持ったままラスベガスへ連れていかれることになり─。
と、ここまでが第一巻。自分が学校に呼び出されたりしなければ、母はあの日あの時、美術館にいなかったはずだ。テオの頭からは、大好きな母親が死んだのは自分のせいだという思いが離れない。悪しき原因が生んだ、最悪の結果。しかし、テオにとっての悪しき結果は、その後どこまでも続いていくのだ。賭博師の父親とカジノで働くザンドラのもと強いられる荒んだ生活。やはりろくでもない父親に世界中連れ回されているボリスという少年と出会い、孤独ではなくなるものの、健全とはいいがたい友情を育んでいく中、飲酒や喫煙、ドラッグの味を覚えていく。いいことなど、何ひとつ起こりはしない。
その後、物語は、父親の死をきっかけにラスベガスを脱出してニューヨークに戻ったテオが、ホービーに保護され、ピッパと再会するシークエンスを提示することで、読者に「災い転じて福となる」式の展開を期待させる。もともとの頭の良さから早期大学プログラムを受けるための試験に合格し、自分が修理した素晴らしい骨董家具を売るのがヘタなホービーに代わって、十七歳の頃から店の経営を助けるようになっていくテオの、未来の幸福を読者は祈る。が、それはかなえられない。
大好きな母親が死んだのは自分のせいだという自責の念と、名画を結果的には盗み持っていることになっている状況への深い不安が、彼を少年時代にその味を覚えたドラッグのもとに留め、優れた資質を持っているにもかかわらず「何者かになりたい」という自分に対する期待を封じ、抱えこんでいる大きな秘密を守るために、本当の自分を見失い、ハンサムで人当たりのいい外面だけを整える空虚な男にしていくのだ。
永遠に続いていくかのように思われる悪しき連鎖の結果としてのZ、Z’、Z”……。あと一回こづかれたら立ってはいられないほどの苦境と精神的な圧迫にさらされるに至ったテオのもとに現れるのが、ラスベガスで別れて以来連絡をとってこなかった悪友のボリス。彼によってもたらされた驚愕の事実によって、テオはさらなるドツボにはまっていくことになるのだが、その詳細についてはこれから読む人のために明かさない。
ただ、冒頭にも記したとおり、ここまでは悪しき原因が悪しき結果を招くと思わせてきた物語が、終盤にきて、善行が最悪の結果を招いたり、悪行が素晴らしい結果を生んだりもするという、人の営みにおける自分ではコントロール不能な不可思議な貌を露わにしていくことだけは記しておきたい。そして、枕カバーにぐるぐる巻きにされて長い間隠されてきた名画「ごしきひわ」が、十三年ぶりにおもてに現れた時、そもそもの原因は、テオが考えているように自分が学校に呼び出されるようなハメに陥ったからではないんじゃないのか、という疑問をあからさまにではなく、ごく控えめなトーンで提示する作者の慎重かつ巧妙な語り口に驚かされることも。
ドストエフスキーの『白痴』を愛するボリスは言う。
〈ムイシュキンは親切で、だれのことも愛し、優しくて、いつも人を許し、悪いことは一度もしなかった。だがどんな悪人も信用し、誤った決断ばかりし、まわりのあらゆる人を傷つけた〉〈もしかすると、まちがった道が正しい道ってこともあるのではないか? まちがった道を選択しても、それでも自分が望んでいるところへ出てくるときもあるのでは? あるいは、別の言い方をすると、まちがったことばかりやっても、それでもそれが正しいとわかることもあるのでは?〉
何もかも終わった後、テオは思う。
〈ぼくたちは自分自身の心を選ぶことはできない。ぼくたちは自分たちにとって良いものや、ほかの人々にとって良いものを、自分自身に求めさせることはできない。ぼくたちは自分の人となりを選ぶことはできない〉〈なぜなら──子供時代からずっと、文化の中で異論のない常套句が、常にぼくたちの中にたたき込まれているからではないか?(中略)「ありのままの自分でいなさい」「心のおもむくままにしなさい」〉〈だがここにぜひともだれかに説明してもらいたいことがある。もし人がたまたま信用できないような心を持っていればどうすればいいのか? もしその心がそれ自体の測りがたい理由で、故意に、しかも言葉で表せないほどの輝きに包まれて人を導き、健康、家庭生活、市民としての責任や、強い社会的なつながりや、もろもろのつまらないありきたりの美徳から顔をそむけさせ、その代わりに破滅の美しい炎、焼身、災難へとまっすぐに向かわせたらどうすればいいのか?〉
ボリスとテオの問いかけに正しい答など存在しないことを、しかし、実は二人が語っている予測も制御も不能な何かこそが〈世界の中における偉大さであり、世界の偉大さではなく、世界が理解しない偉大さである。自分とはまったく異なる者を初めて見る偉大さであり、その存在の中に、人は大きく大きく開花するのだ〉ということを、作者のドナ・タートはこの長い長い物語で語っている。
世界に無数に存在するパターンの中の一部にすぎない人間が、大勢の他者との関わりの中で、こづき回され、右往左往し、A……ZZ’ Z”と続く予測不能な因果にふりまわされ、とても「ありのまま」ではいられない人生の真実を描く文学作品であり、『オリヴァー・ツイスト』や『デイヴィッド・コパフィールド』といったディケンズの孤児小説を、二十一世紀版にバージョンアップしたピカレスク・ロマンであり、テオに持ち出された名画をめぐるサスペンス小説であり、コン・ゲーム小説でもある、たくさんの読みどころを備えた傑作。と、同時に、第二巻の帯で山崎まどか氏が看破しているとおり、これは美をめぐる物語でもある。テオの母が美術館で息子に伝える美、ホービーが骨董家具を修理する過程でテオに教える美、名画「ごしきひわ」自身が物語る美。〈あらゆる種類の異なった角度から、独特の非常に特殊な方法で、融通無碍に頭や心の中に入り込〉み、〈自分の運命が引っかかってしまう釘〉となってしまう美。そう、これは偉大な芸術小説でもあるのだ。
わたしは、これからこの豊かにも豊かすぎる小説を読むあなたが羨ましくてならない。