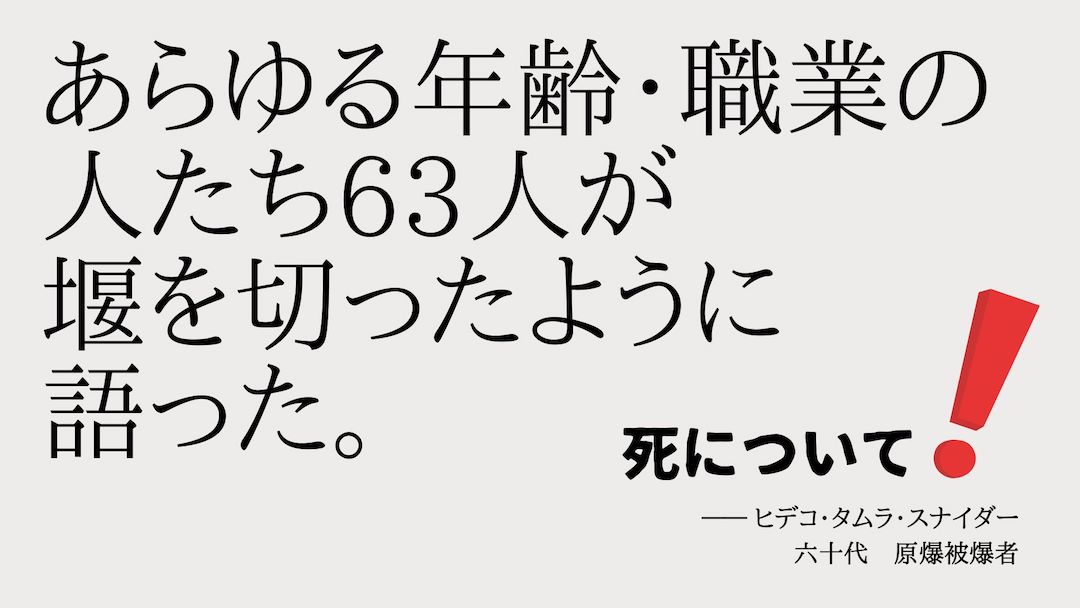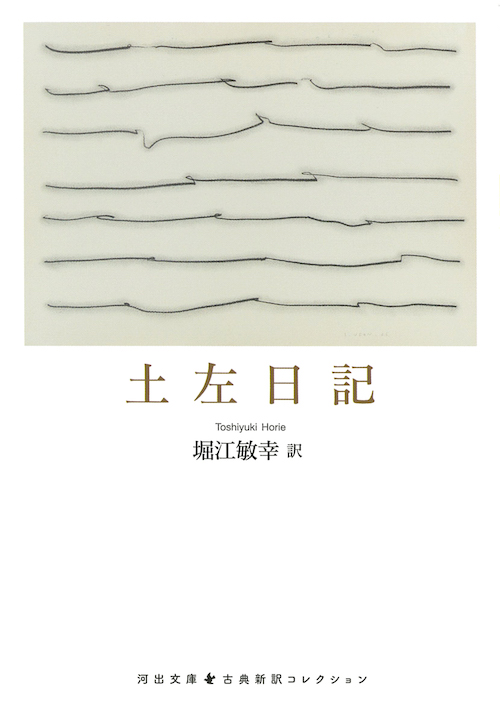文庫 - 人文書
世の中の本の(たぶん)9割以上はクズなので──本とのつきあいかた超・入門『本を読むということ』永江朗
【解説】鷲田清一
2015.12.16
自分が変わる読書術
永江朗著
本書は「14歳の世渡り術」シリーズの一冊として好評だった『本を味方につける本』の改題文庫化ですが、10代だけのものにしておくのはもったいない読書入門です。永江さんご自身も「ぼくとしては若い読者だけを意識して書いたわけではありません。むしろ10歳以上100歳まで、いやいや、7歳でも6歳でも、105歳でも110歳でも読んでいただけるといいなと思って書きました」とのこと(「文庫版あとがき」より)。
まさにその意を汲んだような解説を鷲田清一さんが寄せてくださいました。ここにその前半を特別掲載します。
おとなのための「解説」
鷲田清一(哲学者)
この本に書かれていることはとにかく明快、丁寧、そして長年本や書店を渉猟してきた人だけあって説得力がある。激励されもする。解説など無用だ。だから蛇足にならないよう、そしてこれを読みはじめた中学生たちの学びのリズムを毀さないよう、ひょっとしたらこれを手に取るかもしれないおとな向きに、「解説」とは別の文章として草したいとおもう。
ブックガイド、ジャンル別ベスト、書店案内……となると、いちばんに思い浮かぶのが永江朗さんである。アール・ヴィヴァンの書店員から始めた人生、じつはこの人、バリバリの哲学科出身である。バリバリというのは研究生活を貫いたという意味ではない。ひそかな〝愛人〟としてこれほど哲学に淫してきた人はないという意味で、だ。ちなみに〝愛人〟(amant)とは「愛好者・通」(amateur)という意味でのアマチュアであり、「知を愛する人」(philosophe)という意味での哲人でもある。そういう血筋がこの本の行間に横溢している。哲学を生業にしてきた者、「哲学屋」はそういう気配をすぐ感知する。永江さんにあっては、それを生業にしていないからこそそれがよけいピュアに現われている。「哲学屋」はそのことを、ちょっと嫉妬の思いも交えて確認せざるをえないのだ。
「問題を探すこと、それが読書の喜びだ」。この本で綴られていることはほとんどこの言葉に尽くされていると言ってよい。ひとはふつう、何か直面している問題を解決するために本を開く。だからわかりにくい書き方をしていると腹が立つ。書いてあることが少ししかわからないと、この本はひどいということになる。しかしほんとうの読書とはそういうものではない。わかるということは現在のじぶんの理解の範囲に収まるということだ。それでは世界は広がらないし、めくれもしない。そう、読書は視点を変えるため、もっと別な見方をするためにある。視点を思いもよらない地点に引っ越しさせて、世界のもっと別な現われに触れるためにある。そしてその別の視点を体現しているものとして、他者が綴った書き物があるのだ。だから永江さんは一貫して、本を読む喜びは問題の解決ではなく問題の発見にこそあると言う。となると、逆説的にも、不明になることこそが本を読む悦びだということになる。じっさい、解けない問題がどんどん出てくると、哲学マニアは独り、にたにたしだす。
さて、そういうふうに世界を開いてゆくのは想像力だ。そして想像力をもっともよく飛翔させるのはアナロジーだ。「あれっ、これ似てない?」という感覚である。「哲学屋」は論理的な連関というものに拘泥しすぎるので、投げる網が意外に小さい。永江さんと話していると、その投網がどの方向に向くか、まったく予断を許さない。
たとえば、彼との共著、哲学の殺し文句をめぐる問答集『哲学個人授業』で最初の会話をしたとき、わたしはまず、若いころ意味はぜんぜんわからないのに心を鷲掴みにされた哲学の殺し文句の代表例として、キェルケゴールのこんな言葉を引いた。――「精神とは何であるか? 自己である。自己とは何であるか? 自己とは自己自身に関係するところの関係である、すなわち関係ということには関係が自己自身に関係するものなることが含まれている」(『死に至る病』)。
わたしがこれについて縷々説明しているあいだ、永江さんはずっと別のことを考えていた(らしい)。「関係が関係に関係する」なんて、「すっげえやらしいですね」と返してきた。「密かに情を通じ」というあれである。「関係の関係」ということで、わたしは、関係にはそれに先だって関係項が存在するはず、つまり関係する人がいなかったらそもそも関係も起こらないという考えを覆すとんでもない視点を、それこそ目から鱗という思いでそこに見ていたのだったが、永江さんの反応にその落とし穴にも気づかされたのだった。つまり、「関係」がそのように「やらしい」こと(セックス)をも意味するなら、「関係の関係」である「自己」も「やらしい」もの、つまりは他者との交通・交感だということになってもよさそうなのに、「関係の関係」というあり方は、他者に向けてではなくて内へ、内へとみずからを閉じてゆくことになるのでは、という不穏な成り行きである。
はぐらかしというよりもむしろ、難儀な反論を仕掛けられたな、という思いだった。別の問答でも、それは起こった。〈後略〉
※全文は本書にてお楽しみください。