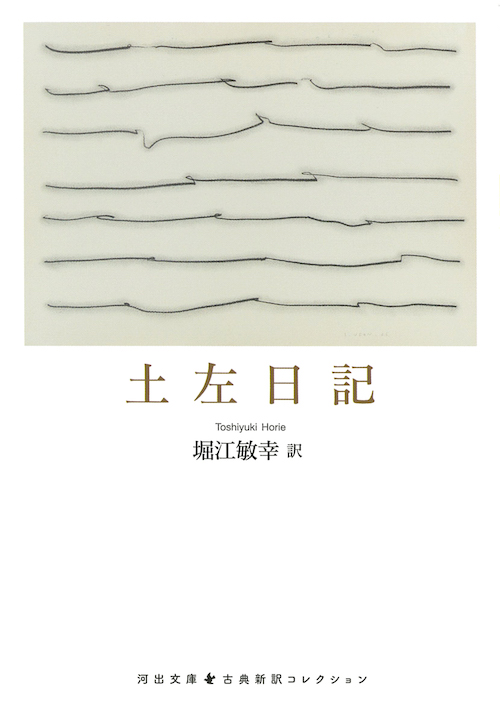枕女王
「枕女王」樹里亜 3
新堂冬樹(しんどう・ふゆき)
2015.08.07

樹里亜 3
黒革のソファに居心地悪そうに座った樹里亜は、パーティションの壁に囲まれたこぢんまりとした室内に首を巡らせた。
壁沿いに設置されたスチール書庫には、ファイルがびっしりと並んでいた。
背表紙には、「浮気調査」「素行調査」「結婚調査」「失踪調査」「借金調査」「盗聴器・盗撮器調査」「ストーカー調査」「いじめ調査」「裁判調査」「不動産調査」「その他」と印刷されたラベルが貼ってあった。
「ハウンド探偵事務所」を訪れたのは、今日で二度目だった。
一度目は二週間前に、依頼にきたときだ。
樹里亜は、この独特な空気が苦手だった。
できるなら、足を踏み入れるのは今日で最後にしたかった。
だが、〈証拠〉を掴むまでは何度でも足を運ぶつもりだ。
「お待たせしました」
ドアが開き、グレイのスーツ姿の中年男性――乾(いぬい)が書類封筒を手に現れた。
依頼のときも、対応したのは乾だった。
キャップとマスクをつけたまま、樹里亜は頭を下げた。
樹里亜にとって、探偵事務所は胡散臭く怖いイメージしかなかった。
変装しているのは、顔を覚えられるのを警戒してのことだ。
「早速、ご依頼の件のご報告をします」
乾が、書類封筒から数枚の写真を取り出しテーブルに置いた。
「とりあえず、ご確認ください」
乾に促され写真を手にした樹里亜は、マスクの下で口角を吊り上げた。
腕を組みラブホテルに入る中年男性と少女、車の中でキスをする中年男性と少女、ラブホテルの前で抱擁する中年男性と少女――三枚の写真は、それぞれ別の日付になっていた。
「ターゲットの未瑠さん、十日間で三回も逢瀬を重ねてました。男性は中林健太郎さんといって、『桜テレビ』のプロデューサーです。これまでに数々の高視聴率のドラマを作ってきたヒットメーカーで、業界では敏腕プロデューサーとして通っています。年齢は四十三歳で、二回の離婚を経験し現在は独身です。因みに、中林さんは、現在、未瑠さんが出演している『嗚呼! 白蘭学園』のチーフ・プロデューサーを務めています」
「やっぱり……」
樹里亜は、写真を睨みつけながら呟いた。
想像通りだった。
「嗚呼! 白蘭学園」は現在四話までオンエアされているが、一話と二話まではセリフもないような脇役だった未瑠が、三話から急にヒロインと同等のセリフ貰うようになった。
セリフだけではなく、役柄も視聴者の感情移入ができるような好感度の高い人物設定になったので、未瑠の人気もうなぎ上りになっていた。
いまでは、ヒロインの松井すずに負けない注目度を集めていた。
未瑠が中林に枕営業し、大役を手にしたのだろうことは明らかだった。
それにしても、とんでもない女だ。ファンの前では清純無垢なアイドルを演じておきながら、裏でやっていることは売春婦となにも変わらない。
「これは単なる好奇心ですが、どうして彼女の素行調査を?」
乾が訊ねてきた。
「彼女の偽善を暴いてやるんですよ」
樹里亜は、吐き捨てるように言った。
「もしかして、写真週刊誌に売るつもりですか?」
樹里亜は頷いた。このスキャンダル写真が世に出回れば、未瑠はかなりのイメージダウンになり、ドラマを途中降板ということもあり得る。
ドラマの降板どころか、最悪、芸能界を引退に追い込まれるかもしれなかった。罪の意識など微塵もない。
彼女は、憧れられる存在になってはならない〈人種〉だ。
スポットライトを浴びるほどに、未瑠の闇は深くなる。
笑顔を振り撒くほどに、未瑠の素顔は醜悪になる。
〈欲〉しかない女が、人々に〈夢〉を与えられるはずがないのだ。
闇の中で太陽をみることができないように……。
「出版社に、知り合いとかいるんですか?」
「いいえ。ネットで調べようと思ってます」
「それは、やめたほうがいいですね」
「え? なんで?」
思わず、タメ語になっていた。
「あなたのような若い女性が編集者に持ち込んでも、足もとをみられて買い叩かれるのが落ちです。それに、持ち込むタイミングも重要ですよ」
「持ち込むタイミング?」
「ええ。いま、未瑠さんは連ドラでヒロインクラスの役を貰っていますが、世間の認
知度はまだまだです。買い取り金額を吊り上げるために、しばらく〈寝かせる〉ことも必要です。もしよかったら、一割の手数料を頂ければ僕が代理人に……」
「あ、大丈夫です。それより、調査料金はいくらになりますか?」
乾を遮り、樹里亜は「サマンサ・タバサ」のエナメルピンクの長財布を取り出した。
探偵を雇って未瑠のスキャンダルを暴いているのは、金儲けのためではない。
買い取り金額を吊り上げるために写真を〈寝かせる〉など、樹里亜の頭にはなかった。
樹里亜の目的は、一日でも早く未瑠を芸能界から抹殺することだった。
「こちらの金額になります」
乾が、請求書をテーブルに置いた。
「ハウンド探偵事務所」の基本料金は、探偵ひとりが一時間につき一万五千円となっている。
未瑠の尾行に十日間で合計三十時間を費やしたので、請求額は四十五万円と消費税の三万六千円だ。
未瑠は、四十八万六千円をトレイに載せた。
「若いのに、お金持ちですね」
冗談めかす乾の言葉に、樹里亜は笑えなかった。
これだけの金を作るのに、二十人以上の男に抱かれた。
そこらの親の脛を齧っているギャルとはわけが違うのだ。
「いま、領収書をお持ちしますので」
席を立つ乾の背中を、樹里亜は虚ろな瞳で見送った。
――お……お前……ど……どうして……?
指名したデリヘル嬢が娘だとと知った英輝は、滑稽なほどに動転していた。
――どうしてって、デリで働いてるからに決まってんじゃん。あんたこそ、なにデリ呼んでんだよ?
樹里亜は、冷めた眼で英輝を見据えた。
――私は、その……。
英輝が、言葉に詰まった。
七三分けの髪、ノーフレイムの眼鏡、レンズの奥の細く鋭い眼――樹里亜は、父の顔立ちが嫌いだった。
陰湿で、なにを考えているかわからない性格が顔に出ているのだ。
大手都市銀行の支店長という仕事柄なのか、家での英輝はあまり感情を表に出さず、いつも合理的で、冷たい雰囲気を漂わせていた。
だが、酒が入ると別人のようになり、娘のような年のキャバクラ嬢と浮気しているのを母にみつかり離婚問題に発展するほどの大喧嘩になったのは、一度や二度ではなかった。
英輝は、若くして都市銀行の支店長に就任したように仕事はできる男だったが、とにかく酒癖と女癖が悪く、しかも、ロリコンの癖があった。
――へぇ、あんたにも慌てたり答えられないことがあるんだね?
樹里亜は、嫌味を言うとベッドの端に腰を下ろしメンソール煙草に火をつけた。
――未成年が煙草吸っても、注意しないんだ? 未成年の女とエッチしようとしてラブホで娘と会っちゃったんだから、注意なんてできるわけないか?
紫煙を天井に向かって勢いよく吐き出し、樹里亜は英輝を嘲笑った。
――わ、私のことは一旦、おいといてだな……お前、家を出てこんなことをやってるのか? いいか? 十八でこんな仕事をしていると病気やらなんやら……。
――あんたにそんなこと言われたくねーし。それって、痴漢が下着泥棒に説教してるみたいなもんじゃん? ロリコン変態親父がさ、偉そうに言ってんじゃねーよ。
英輝を遮り、樹里亜は口汚く罵倒した。
――父親に向かって、その口の利きかたはなんだ!
テーブルを掌で叩き声を荒げる英輝に、樹里亜は珍種の生物をみるような眼を向けた。
――ある意味、あんたって凄いね。デリで未成年とやろうとしていた親父をさ、尊敬しろって?
――言い訳がましくなるが、親というものは、どんなときでも子供の将来を案じる生き物なんだ。
――何万も出して十代の少女とセックスしようとするおっさんを、親なんて思ってな
いから。
樹里亜は、鼻で笑った。
――わかった。私の非は認めよう。たしかに、娘と同年代の女性といかがわしい行為をしている父親を軽蔑したい気持ちはわかる。ただ、だからといって、誤った道に足を踏み入れている娘を見て見ぬふりはできない。わかりやすく説明しよう。私が誤って人を殺したとする。数年後に娘が人を殺そうとしているのを知っていながら、自分には止める権利はないと黙認するのが正しい父親の姿なのだろうか? 私が魔が差して麻薬をやってしまったとする。数年後に娘が麻薬に手を出そうとしているのを知っていながら、自分には止める権利がないと黙認するのが正しい父親の姿なのかな?
――なにくだらないこと言って……。
――待て、とりあえず最後まで聞いてくれ! こんな説明じゃ納得できない気持はわかる。だけど、これは事実なんだよ。親だって、人間だから失敗もするさ。もちろん、私だってそうだ。子供の頃は親の期待に応えようと必死になって勉強して、いい大学に入って、預金額国内三位の都市銀行に就職した。妻と結婚してからは、家族のために自分の時間を犠牲にして働いてきた。自分で言うのもなんだが、四十代で本店の店長に就任するのは異例の出世らしい。言い訳にするつもりはないが、私だって息抜きしなければストレスで……なっ、なにをする!
煙草を消した樹里亜は立ち上がるなり、英輝の股間を鷲掴みにした。
――早くしないと、時間なくなるよ? あんた、身の上話するんじゃなくてエッチするためにきたんだろ?
――や、やめないか! 私達は父娘(おやこ)なんだぞ!?
血相を変えた英輝が、樹里亜の手を払った。
――人の娘なら十七、八でも手を出していいって?
樹里亜は馬鹿にしたように言うと、新しい煙草に火をつけた。
――いい加減にしないと……。
――払えよ。
英輝の鼻先で、樹里亜は掌を上下に揺らした。
――なにをだ?
――基本料金の五万三千円って言ってんじゃん?
――馬鹿なっ、なにもしてないだろ?
――なにもしてなくてもデリヘルは金払うんだよ。ほらっ、早く!
樹里亜が急かすと、英輝は渋々と財布から一万円札を二枚と五千円札を一枚抜いた。
――なにそれ? 二万五千円しかないじゃん。
英輝の差し出す金に、樹里亜は冷ややかな視線を落とした。
――なにもしてないんだから、それで充分だろう?
涼しい顔で、英輝が言った。
――あんた、そういうセコイとこなんにも変ってないね。母さんが肉を焦がしたら罰金、私が寝坊したら罰金……なんでもかんでも金、金、金!
――私は銀行家だ。不利益を与えた人間に責任を問うのはあたりまえだ。利益を出し
た人間には、それに見合った報酬を与えている。
――私は、あんたの部下じゃないし。
――とにかく、二万五千円しか払わないからな。私のためにかかった経費は、ここにくるまでのガソリン代くらいなもんだろうが? それに、どうせほかの客が同じホテルで順番を待ってるんじゃないのか? そうなれば、私にかかった経費は皆無に等しい。二万五千円でも、十分に利益が出てるはずだ。
――あんた、私が思っていたより数百倍もサイテーの親父だね。
樹里亜は言いながら、衣服を脱ぎ始めた。
――おい、なにしてる!?
――私はデリ嬢、あんたは客。やることは決まってんじゃん。やることやったら、五万三千円払えよ。
躊躇わずブラジャーを取った樹里亜は、パンティ一枚で英輝と向き合った。
――もう、やめなさい。
――なに父親ヅラしてんの? 本当は私のおっぱいみたいんだろ? 美乳だと思わね?
樹里亜は、挑発するように両手で乳房を寄せて上げた。
――馬鹿なことをするんじゃない……。
――ほら? 興奮するっしょ? 触っていいよ。
――親をからかうんじゃないよ!
顔を朱に染めた英輝が声を荒らげた。
――からかってねえよ。あんた、私がガキの頃、おっぱい揉んだりまんこ触ったりしてたじゃん。忘れたなんて言わせねえからな。
――なっ……それは……。
軽い口調とは裏腹に、樹里亜は憎悪に燃え立つ瞳で蒼褪める英輝を睨みつけた。
――ガキの頃と違って、テクを磨いたからさ。
樹里亜は、パンティに手をかけた。
――わかったよっ、わかったから……やめてくれ!
英輝が、三万円をテーブルに叩きつけるように置いた。
――ありがとうございます。
慇懃に頭を下げると、樹里亜はブラジャーを手早くつけ五万五千円を財布にしまった。
――早く。
英輝が、手を出した。
――なに?
――釣りだよ、釣り。二千円、多く渡しただろう?
樹里亜はため息を吐きながら、スマートフォンのリダイヤルボタンを押した。
――樹里亜ですっ! 助けてください!
英輝の顔が凍てついた。
――嫌だって言ってるのに無理矢理やろうとして……はい、すぐにきてください!
――おい、お前、なにを言ってるんだ!?
スマートフォンを切った樹里亜に、血相を変えた英輝が訊ねてきた。
――あんたが私に与えた苦しみに比べたら、たいしたことないから。
「お待たせしました」
乾の声が、回想の中の樹里亜の冷笑を打ち消した。
「じゃ、これで」
「あ、もしかしてなんですけど……」
領収書を受け取り腰を上げた樹里亜を、乾が呼び止めた。
「え?」
「あ、いや、なんでもありません。また、なにかの機会があればよろしくお願いします」
乾が思い直したように立ち上がり、頭を下げた。
釈然としない思いを胸に、樹里亜はドアを出た。
☆ ☆
印刷物や原稿が山のように積み上げられたデスクで電話をする者、パソコンを打つ者、雑誌をチェックする者……写真週刊誌「CHANCE」の雑然とした編集部で、編集者達は忙しなく働いていた。
樹里亜は、フロアの片隅の丸椅子で待たされていた。
「持ち込みの連絡してきたのは君?」
くたびれたワイシャツを腕まくりした中年男性が、声をかけてきた。
腋の下には汗染みができ、襟は汚れで黒ずんでいた。
禿げ上がった頭頂の分まで取り戻すとでもいうように、眉毛はふさふさとしていた。
頭は薄いが、肌の張りや声の感じから意外と若いのかもしれない。
「はい」
「編集長の瀬山です。早速だけど、写真みせてよ。雑誌の締切で忙しいからさ」
言い終わらないうちに瀬山は、鳴っていたスマートフォンを耳に当てた。
「どうした? 篠村エミリはまだ出てこないのか!? 気を抜くなよ! 明日もロケだから泊まりはないはずだ。男のマンションから出てきたところを、絶対に逃すなよ! スキャンダル処女を奪うのはウチだ!」
篠山エミリは、「日本の妹」というキャッチフレーズでデビューした清純派アイドルで、テレビでみない日はないといっても過言ではないくらいの売れっ子だ。
過去に男性と噂になったことはなく、無責任なスポーツ紙や週刊誌はレズ説を唱えたほどだ。
瀬山がいうように篠山エミリが男のマンションから出てきたところが記事になったら、「CHANCE」はかなりの部数が売れるに違いない。
「ああ、ごめんごめん。で、写真は?」
電話を切った瀬山が、写真を催促した。
樹里亜は「ハウンド探偵事務所」の書類封筒から取り出した写真を瀬山に渡した。
「ん? この女の子、誰だっけ?」
瀬山が写真を凝視しながら首を傾げた。
「未瑠ってアイドル知りませんか?」
「未瑠……未瑠……誰だっけ?」
「『嗚呼! 白蘭学園』に出てる準ヒロインの子です」
「ん? ちょっとわからないな。で、その未瑠ちゃんの相手は誰?」
興味なさそうに話を進める瀬山に、樹里亜は苛立ちを覚えた。
「このドラマのチーフプロデューサーです」
「は~なるほど。売れないタレントが枕営業で大役を掴んだって話ね?」
「大スキャンダルですよね?」
樹里亜は、瞳を輝かせ訊ねた。
「ターゲットが篠村エミリクラスの大物ならね」
「でも、いまやってる人気のドラマに出演している女優がプロデューサーと枕営業してヒロインの次にいい役を貰ってるんですよ!?」
「準ヒロインっていったって、少女漫画が原作の中高生に人気のドラマだろ? ウチの雑誌の読者層は三十代から五十代の中年男性層なんだ。もっと、全国区の人気のタレントじゃなきゃ、所属事務所やテレビ局に恨みだけ買って雑誌は売れないっていう最悪のケースになるからさ」
瀬山が、写真をヒラヒラさせつつ言った。
「じゃあ、ほかの雑誌に持ち込みます」
樹里亜は、駆け引きに出た。
瀬山は、買い取り金額を抑えるためにわざと興味がないようなことを言っているに違いなかった。
「お好きにどうぞ。ひとつだけアドバイスしてあげるけど、どこの編集部も扱わないと思うよ。いま、出版業界は冬の時代と言われてて雑誌の売り上げも落ちる一方なんだ。だから、売り上げに繋がらないような小物の火遊びを記事にする物好きな出版社はいないよ」
瀬山は肩を竦め、写真を樹里亜に返した。
「君、キャップとマスクで変装してるけど、もしかして未瑠って子のライバル? 準ヒロインをゲットした彼女をスキャンダルで潰そうとか? んじゃ、もっと大物の『枕』の現場を抑えたら連絡ちょうだいよ」
からかうような口調で言うと、瀬山はフロアの奥へと消えた。
樹里亜は、奥歯を噛み締め瀬山の背中を睨みつけた。
ライバルではないが、スキャンダルで未瑠を芸能界から抹殺しようとしたのは当たっている。
読みが甘かった。
プロデューサーとのキス写真を持ち込めば、出版社は競い合うように手を挙げ争奪戦を始めると思っていた。
だが、未瑠の世間での認知度は樹里亜が考えているほど高くはなかった。
樹里亜は重い足取りで編集部を出た。
五十万近い大金が、捨て金になってしまうのか?
――ひとつだけアドバイスしてあげるけど、どこの編集部も扱わないと思うよ。
鼓膜に蘇る瀬山の声が、樹里亜を閃かせた。
金が目的ではなく、未瑠の〈裏の顔〉を暴くのならば雑誌に拘る必要はない。
それまでの気怠げな歩調が嘘のように、樹里亜の足は軽やかになっていた。
☆ ☆
自宅マンションに戻ってきた樹里亜は、「ハウンド探偵事務所」の調査報告書の
入った書類封筒からUSBを取り出しノートパソコンに差し込んだ。
ブログの編集欄を開き、三枚の写真を選択する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『衝撃! 「未瑠」の枕営業証拠写真!』
いきなりだけど、「嗚呼! 白蘭学園」で一話と二話はセリフもない脇役だった無名の未瑠が、三話から急に準ヒロインになったこと、みんな、不思議じゃなかった? 読者のみなさんに、私が特別に種明かししてあげるね。
一枚目の写真は、渋谷のラブホテルに入ろうとする未瑠と謎の中年男性。二枚目の写真は、車の中でキスをする未瑠と謎の中年男性。三枚目の写真は、ラブホテルから出てきてキスをする未瑠と中年男性。
あの清純なアイドル……ミルミルこと未瑠ちゃんのこんな姿をみるだけでショックだと思うけど、相手の謎の中年男性の正体を知ったらもっと驚くよ。
謎の中年男性は、「桜テレビ」でオンエア中の「嗚呼! 白蘭学園」のチーフプロデューサーの中林って人。
もう、みんな、気づいたよね?
私の恋人はファンのみなさんでーす、なんて言ってるミルミルは、準ヒロインの役をゲットするために裏で中林チーププロデューサーとラブホテルでニャンニャンしてたんでーす(笑)
ミルミルファンのオタクさん達、樹里亜を恨まないでね(笑)
ミルミルが売れるためなら中年男とニャンニャンするふしだらな少女だってことに、気づかせてあげたんだからね!
感謝してほしいくらい(笑)
みんな、ミルミルの眼を覚ますために、この記事を拡散してねー!
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
樹里亜は、「全員に公開」のアイコンの上でカーソルを止めた。
クリックすれば、未瑠の〈正体〉が世に知れ渡る。
眼を閉じ、深く息を吸った。
樹里亜は息を止め、マウスに置いた右の人差し指に全神経を集中させた。
(つづく)