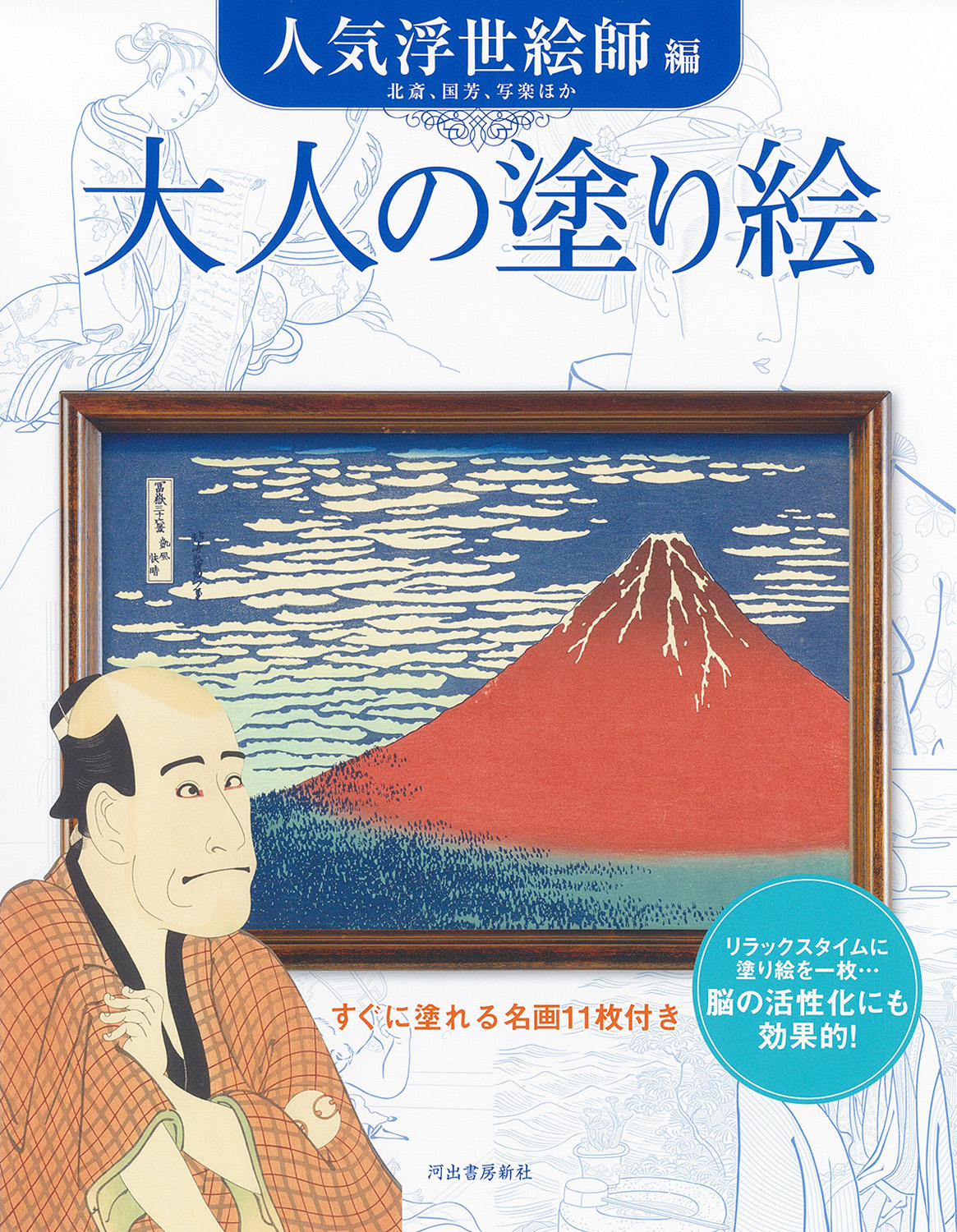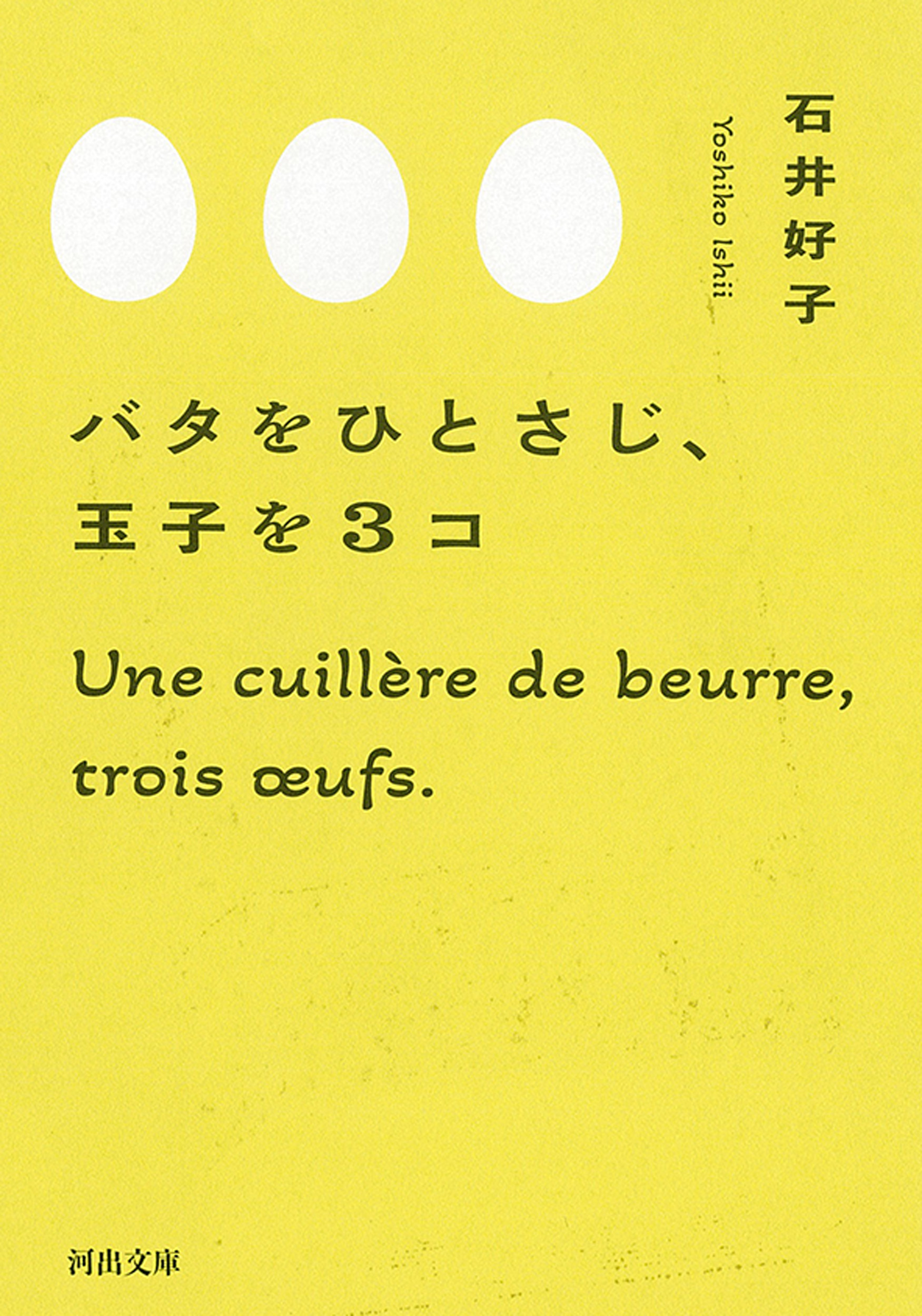枕女王
「枕女王」未瑠 2
新堂冬樹(しんどう・ふゆき)
2015.04.30

「はやく、おいで。さあ、はやく」
未瑠がバスルームから出てくると、既にベッドに仰向けになっている石田が手招きした。
はだけたバスローブから、妊婦のように突き出た腹が醜く波打っていた。
「電気を、暗くしてください……」
ベッドサイドで佇む未瑠は、消え入るような声で言った。
「ん? 恥ずかしいのか? かわいいねぇ~ウブだねぇ~たまらないよ!」
肥満体に似合わぬ俊敏な動きで身を起こした石田が、未瑠に抱きつきベッドに押し倒した。
「電気を……」
「いいのいいの! こんなスベスベピッチピチのアイドルの肉体をみるのに、部屋を暗くするなんてもったいない! 本当はさ、すぐにでも裸をみたいんだけど、まずはバスローブの上から妄想を膨らませるよ」
石田が、興奮気味に声をうわずらせた。
未瑠は、わざと力を入れて身体を強張らせた。
「未瑠ちゃん、もしかして、緊張してる?」
未瑠は、不安そうな眼で石田をみつめ小さく顎を引いた。
「かわいい!」
石田が、頬、鼻、首筋、耳に、闇雲に唇を押しつけてきた。
生ゴミが腐ったような口臭が、未瑠の鼻腔の粘膜を刺激した。
クンニされるよりも、挿入されるよりも、キスは苦痛だった。
「未瑠ちゃん、男性経験は何人くらい?」
「高一の頃、つき合ってた彼氏ひとりだけです……」
未瑠はか細い声で言うと、眼を伏せた。
「え!? 本当にひとりだけ!?」
石田の下膨れ顔が輝いた。
下唇を噛み、未瑠は頷いた。
どういう台詞を言えば……どういう仕草や表情をすれば男が萌えるかを未瑠は計算し尽くしていた。
これまで未瑠の上を通り過ぎた男の数は、両手両足の指ではたりなかった。
「緊張しないでも大丈夫。僕が、調教してあげるから。ねえ、八重歯みせて」
卑猥な笑みを浮かべた石田が、唐突に言った。
未瑠は、唇を少しだけ開いた。
「たまらないねぇ、ライブを観に行ったときから、その八重歯が好きで好きでさ……」
鼻息荒く言うと、石田が未瑠の唇に唇を押し当て、八重歯をしゃぶり始めた。
おぞましさに、鳥肌が立った。
「くすぐったいです……」
未瑠は身体をくねらせ、こそばゆいふりをして逃げた、
「未瑠ちゃんは、敏感なんだ? 全身性感帯なのかな~?」
石田が、腫れた歯茎と痩せ細った歯を剥き出しにした顔で笑った。
吐き気を堪え、未瑠はあひる口を作り石田をみつめた。
さりげなく腕を交差させ、石田にみえるようにバスローブの胸もとから谷間を覗かせた。
セックスという行為自体よりも、だらだらと密着している時間のほうが耐え難かった。
さっさとやることを済ませて、家に帰りたかった。
「もう……たまらん!」
石田が、乱暴にバスローブの胸をはだけた。
露になった豊満な乳房に、石田が息を呑んだ。
それも、無理はない。
未瑠は着やせするタイプなので、衣服の上からはこんなに巨乳とは想像もつかない。
バストは八十六センチ程度だが、ウエストが五十六センチなのでトップとアンダーの差が激しく、まるでエッチなアニメの登場人物のような体型をしていた。
「十八のアイドルがこんなにいやらしい肉体をして……ゆ、夢みたいだ!」
恍惚の叫び――石田が未瑠の乳房を鷲掴みにし、赤子さながらに乳首にむしゃぶりついた。
未瑠は人差し指を噛み、横を向き、必死に声を殺しているふうを装った。
もちろん、感じてなどいない。
よがり声ではなく、罵声ならいくらでも出せそうだった。
石田の汗で湿った頬が乳房に貼りつき、気持ち悪かった。
荒い鼻息を漏らしつつ、石田が胸を揉みしだいた。
胸への愛撫だけで、石田にセックステクニックがないのはわかった。
未瑠の経験では、セックスがへたな人間は仕事もできない。
やはり、しょせんは弱小製作会社のプロデューサーだ。
未瑠は、石田が乳房に夢中になっている隙に、唾液で濡らした人差し指と中指を陰部に当てた。
絶妙のタイミングで、石田の手が下半身をまさぐり始めた。
「濡れてるじゃないか……未瑠ちゃん、感じてるの?」
感激と興奮が入り混じった声で、石田が訊ねてきた。
「いや……恥ずかしい……」
未瑠は、指を唇に当てたまま眼を伏せた。
目論見どおり、石田は唾液を愛液だと勘違いして喜んでいた。
「ねえ、気持ちいい?」
秘部に人差し指を出し入れしながら、石田が未瑠の表情を窺った。
「知りません……」
未瑠は、頬を赤く染め小さく首を振った。
顔を赤くするコツは、息を止め下腹に力を入れることだった。
「しゃぶってくれるかな?」
石田がブリーフを脱ぎ、ベッドに仰向けになった。
勃起していたが、石田のペニスは未瑠の人差し指ほどの長さしかなかった。
未瑠は戸惑った顔で身を起こし、石田の足もとに移動した。
「フェラって、したことある?」
「ないです……」
「初フェラなんだ!」
石田の声が弾んだ。
「僕が仕込んであげるから。まず、先っちょをくわえて」
未瑠は、ぎこちなく亀頭を口に含んだ。
「いいね~、歯を立てないように、頭を前後に動かしてごらん」
言われるがままに……というふうに、未瑠は頭を動かした。
「うまいよ……動かしながら……頬を窄めてみて……吸引するように……そうそうそう……んふぅん……んぁ……うっ……」
気色の悪い呻き声が滑稽で、未瑠は噴き出しそうになった。
未瑠は頬をへこませ唇で亀頭を締めつけ、陰茎の裏筋に舌を這わせた。
「う……うまいね……おぅ……うふぉ……んん……」
石田が身体をくねらせ、よがり声を上げた。
これでも、馴れていると思われないように手加減していた。
本気を出せば、未瑠のフェラチオで五分耐えられる男はいない。
未瑠は淫靡な唾液の音を立て、顔を前後に動かした。
音の効果は、興奮度を何倍にもする。
「ほ、本当に……フェラは初めて?」
石田が首を擡げ、眉間に皺を寄せた表情を未瑠に向けた。
未瑠は、ペニスをくわえたまま石田をみつめ頷いた。
ひとつひとつの仕草が、石田を絶頂へと誘ってく。
吸引を強くし、頭の動きをはやめた。
石田の息が荒くなり、口の中でペニスの硬度が増した。
「未瑠ちゃん……まずい……イキそうだ……とりあえず……出していい?」
未瑠は、ペニスから唇を離した。
「……どうしたの?」
石田が、怪訝な顔になった。
「私、ゴールデン帯のドラマに出るのが夢なんです」
「急に、なんだい?」
急でも唐突でもない。
普通なら、歯牙にもかけないような不恰好な中年男とセックスしてあげている理由は、仕事を貰うためだ。
射精寸前のいまだからこそ、「交渉」を有利に運べる。
なにも言わなければ、衛星放送のキャスティングあたりでお茶を濁されてしまう。
衛星放送ならまだしも、最悪、インターネットの仕事という可能性もあった。
「最近、アイドルでもお芝居をやっているコが多いじゃないですか? 私も、いろんなお仕事をして有名になりたいんです」
「そっか。なら、ウチの会社が製作している『ミスドラ』の担当者に話してみるから。今度、マネージャーさんにでも宣材を持ってこさせてよ。じゃあ、続きやろうか?」
石田が、促すように自分のペニスに視線をやった。
予想通りだった。
「ミスドラ」とは、「ミステリードラマ」の略で衛星第一テレビの午前零時からオンエアされている。
「地上波のドラマに出てみたいです」
未瑠は、無邪気に言った。
「いまは、もう地上波の時代じゃないよ。衛星テレビの加入者も昔と違って格段に増えているし、地上波ほどコンプライアンスが厳しくないから面白い番組作りができるし」
未瑠がなにも知らないと思い、石田は言いくるめにかかった。
たしかに、スポンサーの顔色を窺う地上波はなにかと制約が多い。
それに引き換え、縛りが少ない衛星放送の魅力は攻撃的な番組作りだ。
しかし、それは逆を言えば衛星放送が地上波に比べて影響力が小さいということだ。
視聴者の数が多ければクレームも多くなる。
つまり、衛星放送は地上波に比べて遥かに視聴者の数が少ないのだった。
「だけど、やっぱり、メジャーな感じがするので地上波のドラマがいいです」
言いながらも、未瑠は石田のペニスにさりげなく触れて勃起を維持させた。
快楽を与えている間は、イニシアチブを握ることができる。
「わかった。とりあえず、その話は終わってからにしよう」
「未瑠を地上波のドラマに出してくれなきゃいやです」
駄々をこねるように言いながら、未瑠は石田のペニスを握り上下に扱いては止め、扱いては止めることを繰り返した。
「あ……ちょ……やめないで続けて……」
うわずった声で懇願する石田に、未瑠は十回ほど右手を動かしては止めた。
悪戯っ子が遊んでいる、というふうに。
「み、未瑠ちゃんは……わ、悪い子だね……もう、我慢できないから……入れさせ……あぅ……」
ふたたび、未瑠は石田のペニスをくわえた。
微妙な力加減で亀頭を締めつけ、尿道口を舌先で刺激した。
純情なふりは、そろそろ終わりだ。
未瑠は陰嚢を口の中に吸い込むように含み、睾丸を舌で転がした。
右手ではペニスを扱き、伸ばした左手で乳首を愛撫した。
「き、君……ど、どこで、そんなテクニックを……」
驚いた石田が訊ねてきたが、押し寄せるオルガスムスに眉間に縦皺を刻み言葉を切った。
この「三所攻め」は、持続力に自信がある男も十分と耐えられない。
まだ一分も経っていないのに、石田のペニスは激しく脈打っていた。
その気になれば、あと三十秒以内にイカせることができる。
だが、未瑠は陰嚢から唇を離し、ペニスと乳首を愛撫していた手の動きを止めた。
「いいですよ。入れても」
これまでと一転した妖艶な表情で石田をみつめながら、屹立するペニスの上に跨った。
右手で根もとを押さえ、ゆっくりと腰を沈めた――亀頭が膣に入ったところで、未瑠は和式便所で用を済ませるときの体勢で静止した。
「ちゃんと、入れてほしいですか?」
「た、頼むよ……焦らさないでくれ……」
石田は、射精しないようにすることで必死なのだろう。
十八歳の美少女アイドルが、瑞々しく張りのある裸体をさらして自分の上に跨っているのだ。
ドラマのプロデューサーでなければ、石田のような不細工な中年男が何度生まれ変わっても体験できないシチュエーションだ。
「地上波のゴールデン帯のドラマのキャスティングを、約束してくれたらいいですよ」
未瑠は微笑んだ。
「君って……こういう子だったのか?」
驚きを隠せないといった様子で、石田が言った。
「こういう子じゃなかったら、『枕』なんてしませんよ」
言いながら、未瑠は片目を瞑った。
快楽の寸止めで石田を完全に支配しているいま、「本性」を表しても問題なかった。
むしろ、娘ほどに年の離れた少女にサディスティックに弄ばれている状況が彼の興奮に拍車をかけているに違いない。
「石田さん、ど、う、す、る、ん、で、す、か?」
未瑠は言葉のリズムに合わせて腰を上下させた。
「いい……気持ちいい……」
石田の法悦の声が合図とでもいうように、未瑠は上下運動を止めた。
「もう……ほんと……お願いだよ……」
潤む瞳で懇願する石田の半べそ顔に、少年の顔が重なった。
――やめようよ……なんか、怖いよ……。
十年前――幼馴染の智久の、女の子のような白く滑らかな頬が薄桃色に染まった。
――ねえ、智ちゃん、くすぐったいの? 痛いの?
八歳の少女は、皮を被った細く小さなペニスを揉んだり、摘んだりしながら質問した。
――わからない……けど、変な感じだよ。
――それじゃわからない。どんな感じ?
少女は、手を動かしながら意地悪な気分で質問を重ねた。
――え! なにこれ? 大きくなったよ! なんで!?
少女の掌の中で、智久のペニスが硬くなった。
――わからないって……もう、やめてったら。
智久の泣き出しそうな声が、少女を心地よくさせた。
――やめてほしい?
少女の問いかけに、智久が頷いた。
――やめるなら、なんでも言うこときく?
ふたたび、智久が頷いた。
――じゃあ、私の家来になって。
――家来なんて、やだよ!
――じゃあ、こうしてやる!
少女は、智久のペニスを両手で掴み揉んだりこねくり回したりした。
――やめてったら……苦しいよ……お願いだから……やめてよ……家来になるから!
智久の苦しげな顔をみると、鼓動が高鳴った。
そのとき少女は、幼心にも誰かを従わせる心地好さを知った。
「わかった、約束する……」
石田の声が、記憶の旅から未瑠を連れ戻した。
「なにを、約束してくれるんですか?」
未瑠は、膣の入り口に亀頭を擦りつけつつ訊ねた。
「ドラマだよ……地上波のドラマのキャスティングを約束する……」
頬を上気させ、石田が言った。
「時間帯は?」
「ゴールデン帯だろう?」
「番手は?」
矢継ぎ早に質問し、未瑠は亀頭にクリトリスを強く押しつけた。
「そこまでは、わからないよ。局のプロデューサーの考えもあるだろうし……」
「わかりました」
冷めた声で言うと、未瑠は腰を浮かせた。
「待って! エキストラやちょい役じゃないようにするからさ」
「五番手までなら考えますけど?」
未瑠は、首を傾げて石田をみつめた。
「君は……相当な女の子だな……」
石田が、異星人をみるような眼を未瑠に向けてきた。
いつまでも、オーラのかけらもない素人同然のメンバーと地下アイドルを続けるつもりはない。
みんなが純粋だとかかわいそうだとか書き込んでいるときに、あんたらのミルミルは男に股を開いてるんだから。
不意に、樹莉亜という女が未瑠のブログに寄せた中傷コメントを思い出した。
自分を眼の仇にしている嫌な女だが、書いていることは的を射ていた。
だからといって、非難される覚えはない。
人は、なにかを手に入れたいときにたいていの場合は金を使う。
未瑠は、金の代わりに身体を使ってるだけの話だ。
そして未瑠の身体は、時に、紙幣以上の価値を相手にもたらすのだ。
もし、彼女に会うことがあるのなら訊いてみたい。
なにがいけないの?
「ありがとうございます……でいいんですよね?」
未瑠は、オタク達を虜にしてきた八重歯を覗かす「アイドルスマイル」を石田に向けた。
「負けたよ。ギリギリで五番手なら、なんとかできると思うよ」
「石田さん、大好きです!」
未瑠は、この場の空気にそぐわない溌剌とした声で言うと石田のペニスに手を添えて腰を沈めた。
上体を反らし気味にし、石田の太腿に手をついた未瑠は、ロデオしているカウボーイさながらに腰をグラインドさせた。
快楽の波に溺れながらも、石田がびっくりしたような顔をしていた。
男性経験が豊富と思われても構わない。
「商談」が成立したいま、一秒でもはやくイカせてシャワーを浴びたかった。
太腿に置いていた手を石田の薄い胸板につき、未瑠は高速で腰を振った。
一分も経たないうちに、手足を突っ張らせた石田が呻き声とともに絶頂を迎えた。
☆ ☆
「私、先に帰りますね」
シャワーを浴びた未瑠は手早く衣服を身に着けながら、ベッドで寝煙草をする石田に声をかけた。
「ああ、僕は、もう少し休んでいくから」
石田は、素っ気ない口調で言った。
手に入った「獲物」にたいして、急に態度を変える日本男児の典型のような男だ。
だが、そんなことは織り込み済みだった。
「じゃあ、失礼します」
キャップ、サングラス、マスクを最後につけると、未瑠は頭を下げ、玄関に向かった。
「あ、そうだ。キャスティングの約束、忘れないでくださいね」
未瑠は立ち止まり、振り返った。
「なんの約束だっけ?」
石田が、さっきまでと別人のようなふてぶてしい態度でしらばっくれた。
「やっぱりね」
未瑠は微笑み、トートバッグの中から取り出したマイクロテープを宙に翳した。
「会話は、全部録音してますから。約束を守ってくれなきゃ、局Pや石田さんの上司に送ります」
「な、なんだって!?」
ベッドから跳ね起きた石田が気色ばみ、未瑠に詰め寄ってきた。
「約束を守ってくれれば、このテープの出番もないですから」
未瑠は、涼しい顔で言った。
「そんなことをしたら、君だって困るんだぞ!? 仕事のために『枕』したなんて、アイドル生命は終わりだ! そのくらい、わかるだろう!」
石田が唾を飛ばし、捲くし立てた。
「もちろん、わかってますよ。私は別に、アイドルにこだわっていません。『枕』がバレたらバレたで、スキャンダルをネタに悪女系の女優でブレイクしてもいいですし、バラエティ番組でぶっちゃけ毒舌タレントで露出を増やしてゆくのもいいですし……どんな手段を使っても、有名になれればいいんです。困るのは、石田さんのほうだと思いますよ。私は十八歳ですから、児童買春法に引っかかります」
「俺は金なんて払ってないから……」
未瑠は、石田を遮るように一万円札二枚を宙でひらつかせた。
「私が貰ったと言えば、警察はどっちを信じるでしょうね? それに、石田さんの奥さん、大手広告代理店の役員らしいですね? 奥さんに十八歳のタレントとの浮気がバレたら、石田さんの仕事柄、出世に影響するんじゃないんですか?」
未瑠は、言葉の内容とは裏腹に無邪気に微笑みながら言った。
「坂巻君が知ったら、さすがにまずいんじゃないのか? 所属タレントが、売り込み相手のプロデューサーを脅したってな。この場をセッティングしたのは彼だ。チーフマネージャーを怒らせたら、解雇される可能性もあるだろう?」
一縷の望みに賭けて、石田が反撃してきた。
「クビって言われたら、喜んで辞めます。ブレイクしたら、業界に影響力のある大手の事務所に移籍しようと考えていましたから。正直、製作会社のプロデューサークラスに枕営業させるチーマネの無能さには呆れてましたから」
「き、君って奴は……」
石田が顔面蒼白になり、恐怖なのか屈辱なのか……あるいはその両方なのか、唇を震わせていた。
「もう一度、訊きます。キャスティングの約束、覚えてます?」
ふたたび、未瑠は訊ねた。
「……ああ……覚えてるよ」
拳を握り締めた石田が、吐き捨てるように言った。
「嬉しい!」
未瑠は、石田に抱きついた。
「現場で会いましょう」
背伸びをし耳もとで囁いた未瑠は、ウインクを残して身を翻し玄関を出た。
☆ ☆
ホテルを出た未瑠は、まっすぐ家に帰る気になれず渋谷のファーストフード店に入っていた。
二階のフロアの片隅の席で、抹茶フラペチーノを飲みながらあたりにぼんやりとした視線を漂わせた。
店内は同年代の女子高生が大勢いたが、キャップやマスクなしでも未瑠に気づくものはいない……というより、未瑠の存在が世間に浸透していないので気づく気づかない以前の話だ。
連ドラに出演している人気女優が変装もなしに店に現れれば、大変な騒ぎになる。
近い将来、自分もそうなるために、ついさっきまで、魅力のかけらもない中年男の上で腰を振っていたのだ。
未瑠はため息を吐き、スマートフォンのディスプレイに視線を落とした。
まだ、穂積からの返信はない。
といっても、未瑠がメールしてから十五分くらいしか経っていなかった。
未瑠は、送信メールを開いた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
TO穂積さん
お疲れ様です。
いま、特別営業終わりました。
今回の営業先は、製作会社のプロデューサーさんでした。
強気の営業をかけて、地上波のゴールデン帯のドラマ出演を約束してもらいました。
五番手あたりの役がもらえそうです。
地上波のドラマのメインキャストですよ!
凄いでしょう? 褒めてください(笑)。
こんなメールを送ったからって、心配しないでくださいね。
なにも、裏はありませんから(笑) 。
大きな仕事が決まれば、どんな屈辱も忘れられます。
穂積さんがいてくれたときに比べて、私も精神的に強くなりました。
でも、最近、特別営業のあともなにも感じなくなっている自分が、少しだけ不安です。
変なメールごめんなさい!
マノンちゃんの現場で大変でしょうから、返信はいりません。
頑張ってください!
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
スマートフォンのライトが消えた――漆黒を背景にしたディスプレイのガラスに映る少女が、ハッとするような暗い瞳で未瑠をみつめていた。
(つづく)