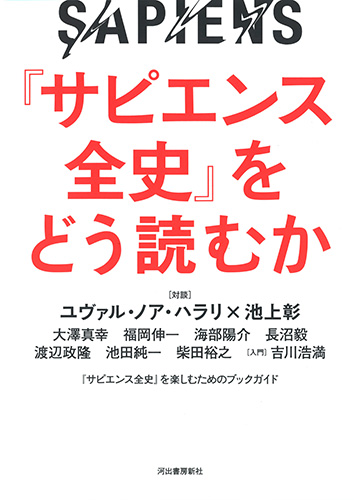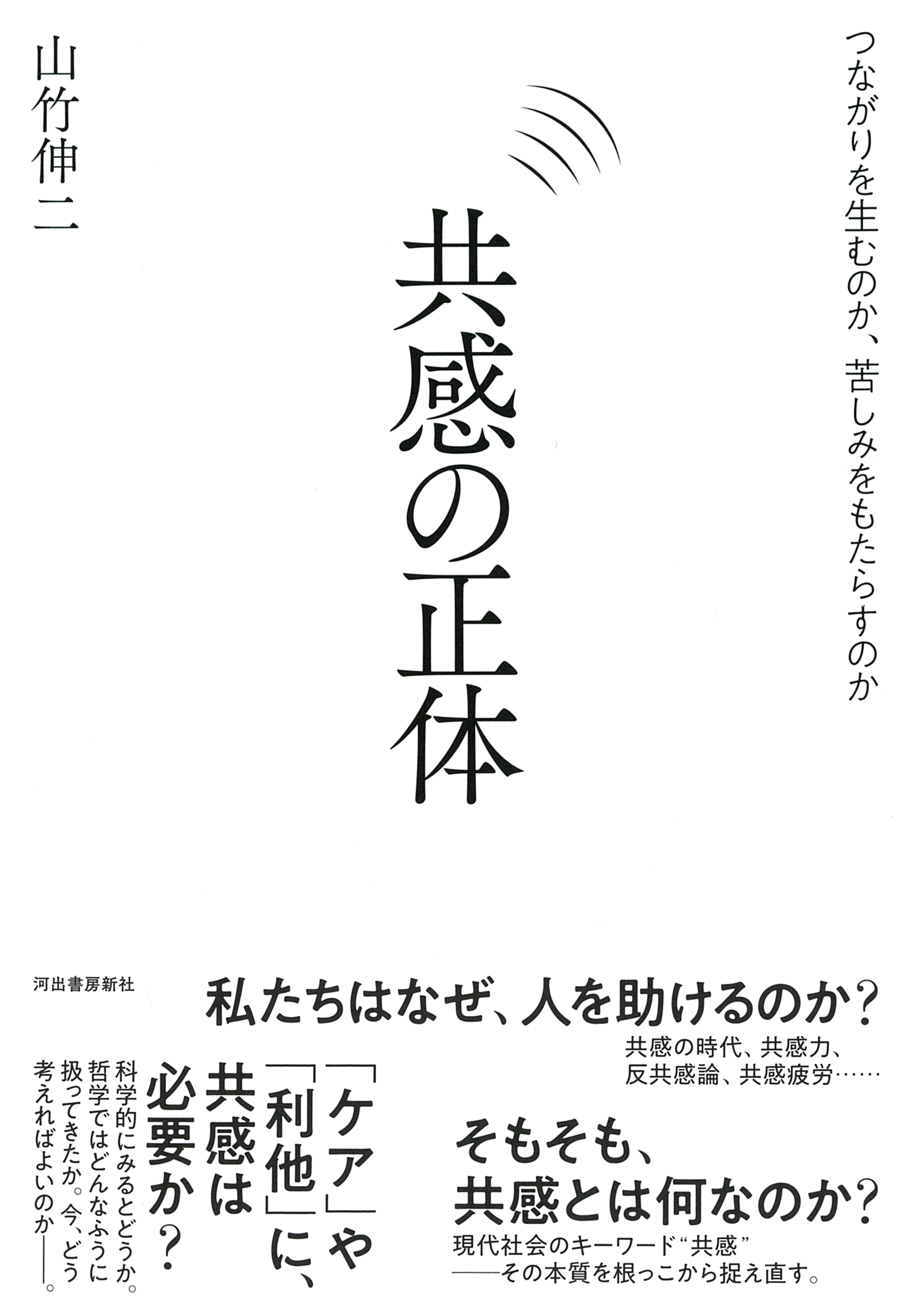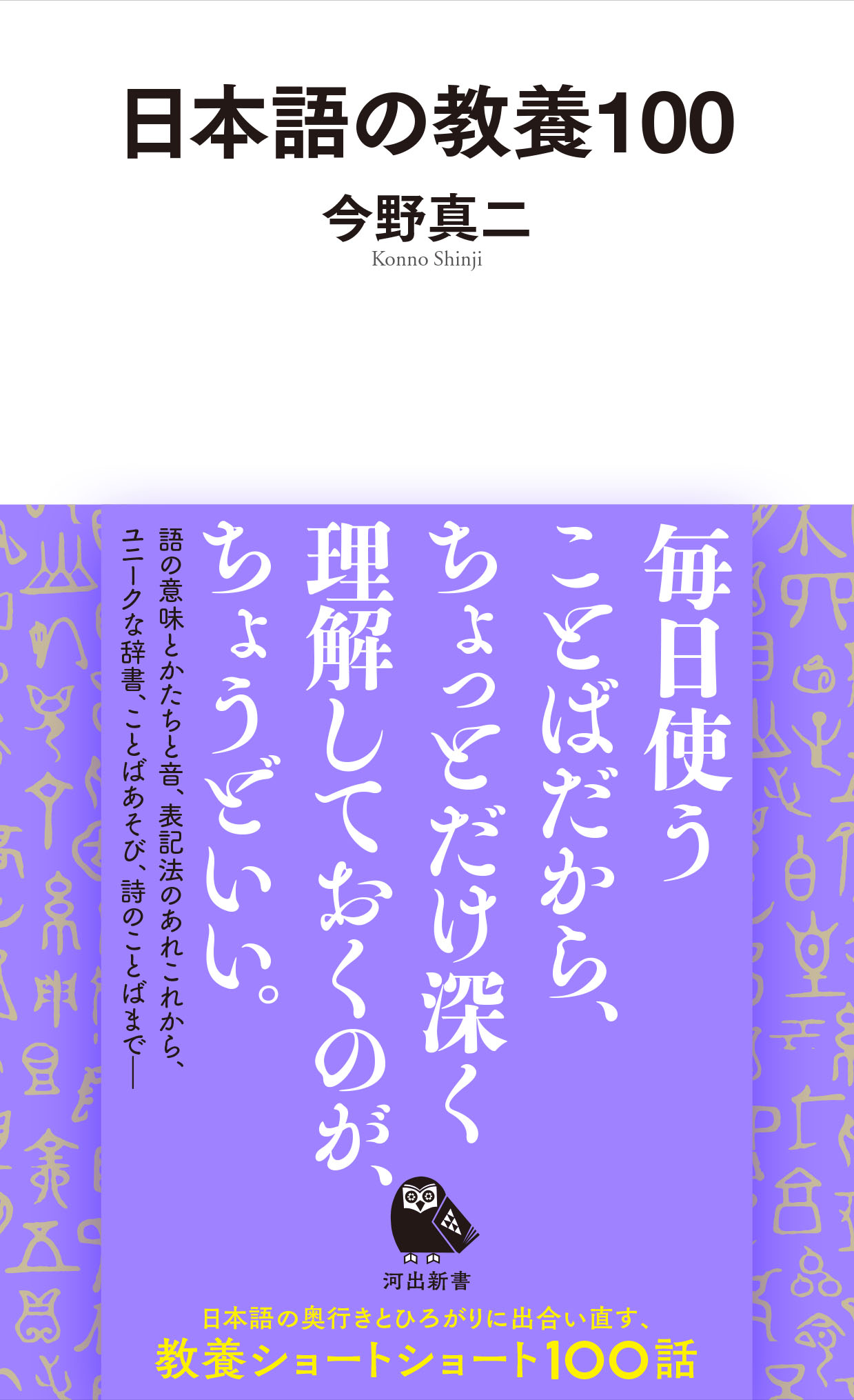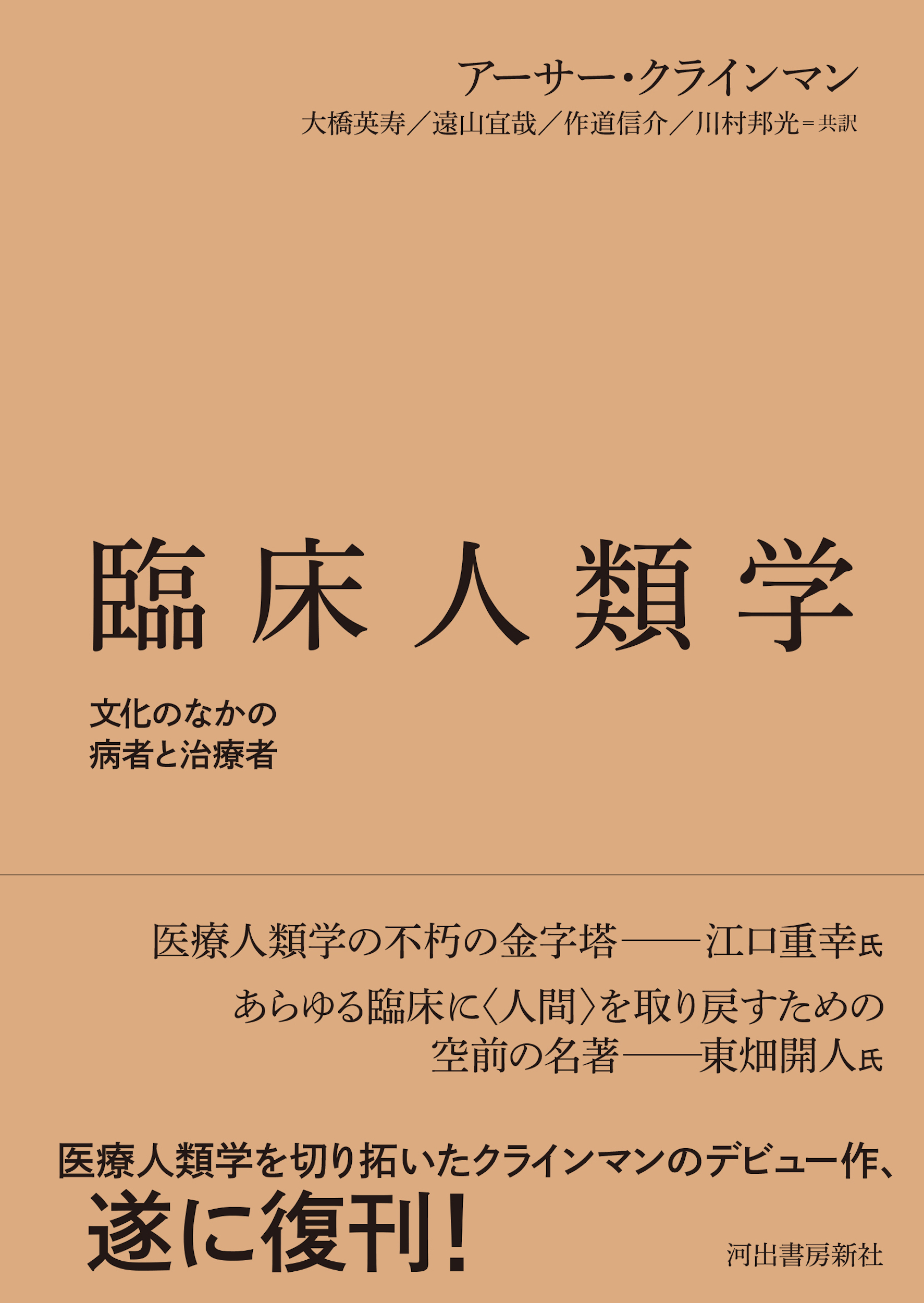単行本 - 人文書
「サピエンスが積む七つの徳」──『ホモ・デウス』書評(評者:長沼毅)
生物学者 長沼 毅
2018.10.26
『超サピエンス前史』
われわれ人間(学名ホモ・サピエンス)と人間界の文明の来し方行く末を俯瞰した前作『サピエンス全史』からちょうど二年で、待望の本作『ホモ・デウス』日本語版が出版された。まずは前作と本作の翻訳に当たられた柴田裕之氏の偉大な訳業に心からの敬意を表したい。そして原書『Homo Deus』だが、前作『Sapiens』から二年足らずで書き上げられたものだ。さらに『Homo Deus』から一年半に満たないうちに最新作『21 Lessons for the 21st Century』を上梓した著者、ユヴァル・ノア・ハラリ教授の「学識力」と「筆力」には唯々感嘆、いや驚嘆するのみである。その学識力と筆力は現在のサピエンス界で最高レベルではないだろうか。『ホモ・デウス』では「力」は「神性」と同一に扱われている。となると、ハラリ教授自身がすでにホモ・デウス(神人)の域に達しているように思える。
われわれ人間を生物分類学的に記述すると動物界-脊索動物門-哺乳綱-サル目-ヒト科-ヒト属ヒト(ホモ属サピエンス)になる。この形式だと、ホモ・デウスはヒト属カミ(ホモ属デウス)とでもなるだろうか。つまり、われわれ人間(ヒト種、サピエンス種)とは異なる新種(カミ種、デウス種)という扱いになる。しかも、その新種は人間humanから進化した「超人」super-humanである。超人についてはすでに前作『サピエンス全史』の最終章(第20章)で「超ホモ・サピエンス」の出現とそのインパクトが予告されていた。その意味で本作は前作の続編と考えられるので、『超サピエンス前史』と銘打ってもよいかもしれない。前史としたのは、いつか未来に書かれるであろう『デウス全史』の前日譚になることを予想したからである。
そのデウス全史だが、超人たるホモ・デウスは果たして“全史”と言えるほどの歴史を作ることができるだろうか。そもそもホモ・デウスは人間(サピエンス)から進化したと言っても、それは自然的な進化、すなわち遺伝子の突然変異と変異体の自然淘汰を経て発生するわけではなく、人間の科学技術力、特にバイオエンジニアリング(生命工学)やサイボーグ化などによって“人間をアップグレード”した産物として出現するものである(上p.59)。
でも、そうは言ったものの、そうして“アップグレードした人間”など、なかなかイメージしにくいだろう。僕はSF漫画・アニメの『攻殻機動隊』(参考URL 1)に出てくる「電脳化」および「義体化」(サイボーグ化)した人間や、もともと生身の人間ではないアンドロイド(人造人間)などをイメージした。ただし、『攻殻機動隊』の英語タイトル『Ghost in the Shell』(殻の中のゴースト)における「ゴースト」とは「魂」を指すのだが、『ホモ・デウス』的には「進化論は魂という存在は受け容れられない」し「魂の存在は進化論と両立しえない」ので(上p.133-134)、せっかく最高級にアップグレードした“草薙素子”(実写版のハリウッド映画では同じイニシャルのMira Killian)も、ハラリ教授のお眼鏡には適わなかったようだ。
人間が人間をアップグレードする理由、いや、しなければならない理由は、今この瞬間にもわれわれ人間が人工知能(AI)をアップグレードし、AIでなければ扱えないほど大きなビッグデータを作っているからである。そう遠くない将来、超ビッグデータを超高効率で処理する超AIが「人間がかつていったことのない場所にまで」自己成長する(下p.241)。いわゆるシンギュラリティ(技術的特異点)のことで、巷間には“2045年問題”として伝わっている。“AIの父”と称されるユルゲン・シュミットフーバー博士(参照URL 2)は2018年2月の時点で「シンギュラリティまであと30年」、すなわち2048年と予想した。いずれにせよ、その時、ついていけるのはアップグレードした超サピエンス、すなわちホモ・デウスしかいないだろう。
そうではあるが、しかし、超AIは「さらには人間がついていけない場所まで行く」(下p.241)。そうなったら、非アップグレードの生身の人間はもちろんのこと、アップグレードした超人たるホモ・デウスといえども「急流に呑まれた土塊のように、データの奔流に溶けて消えかねない」(下p.243)。われわれ人間は出現してから現在に至るまで30万年以上も存続してきたが(参考文献1, 2)、ホモ・デウスは、現れてから消えるまで、いったい何年もつだろう(その頃にはサピエンスはとっくに滅んでいる、あるいは、実質的にいないのと同じになっているだろう)。デウス全史など望むべくもなく、せいぜい小史くらいで終わってしまうのか。原書『Homo Deus』の副題は「A Brief History of Tomorrow」だが、それはあくまでもbrief historyであって、短命な種のshort historyにならないことを願うばかりだ。
意識を持たない超AI
超ビッグデータを超高効率で処理する超AIは、本作ではたとえば「高度な知能を備えたアルゴリズム」と呼ばれている。ただし、その上に「意識は持たない/意識を持たない/非意識的な」non-consciousという形容詞が冠せられている。あくまでも「非意識」なのであり、無意識ではない。無意識は“意識的でないだけで意識そのものはある” のに対し、非意識は“意識そのものがない”のだ。
ホモ・デウスには及びもつかないが、僕にもデータ至上主義のような気が少しあって、何でもカウントしたがる癖がある。無意識や非意識についてもそうで、原書では「無意識」(unconsciousとunconsciously)は本文中に、いずれも第3章に、四ヶ所あって、日本語版ではきちんと「無意識」と訳されている。文脈からみて、これらのunconsciousは著者のハラリ教授が、本来はnon-consciousとすべきところ、うっかり用いてしまった可能性もあるのだが、もしかしたら意図的にunconsciousとしたのかもしれない。そうだとしたら、その意図は何だったのだろうか(ただし上p.149の「無意識状態」のunconsciousは妥当)。
一方、non-consciousは本文中に18ヶ所あった。訳語としては「非意識」、「意識のない」、「意識されない」、「意識を持たない」など、文脈や読みやすさなどから訳し分けられている。ただ一ヶ所、「心を持たないアルゴリズム」(下p.148、原文mindless algorithms)という箇所があった。本作では「心」と「意識」と「主観的経験」が同列に並べられている、つまり、心=意識=主観的経験とイコールで結ばれることになる。したがって、「意識を持たない」=「心を持たない」になる。その上でショッキングなことが語られる。「意識は…生物学的機能は何一つ果たさない…生物学的には無用な副産物…一種の心的汚染物質」と(上p.147)。しかも、「二〇一六年の時点で現代科学が提供できる意識の仮説のうち、これが最高のものである」とも(上p.147)。さように「意識」とは本当に無用の長物なのだろうか。
僕はずっと、AIが高度な知能を備えればAIの中で意識が自然発生してくる、と半ば‘常識’のように思っていた。僕だけでなく、多くの人もそう思っていただろうし、今でもそう思っている人は少なくないだろう。でも、実際のところ、そう思うだけの科学的な根拠はなく、ただ漠然とそう思っていただけだ。そして、その漠然とした思いは、本作のたった一ページ(上p.147)で粉砕されたのである。この時点で上下合わせて全435ページのまだ1/3なのに。
残りの2/3もすごい破壊力を呈している。何がすごいって、たとえば、「人間は分割不可能な個人ではない…分割可能な存在なのだ」(下p.115)。これは英語だともっとインパクトがあって、原文「Humans aren’t individuals. They are ‘dividuals’.」に僕はもうメロメロに溶けてしまった。さらに「意識」に戻ると、残りの2/3でも「知能」と「意識」は別物で、意識なんか要らない、無くても困らない、そもそも意識って何だか分からない、どうせサピエンスには理解できない「意識の大海」云々の論が、これでもか、これでもかと説かれるうちに、「意識高い系」の僕は打ちのめされてしまった。
意識高い系とは、21世紀に入ってからの日本の流行語の一つである、これはもともと良い意味で用いられたらしいが、後に悪い意味になったとのこと。この流行語をめぐる評価の移り変わりはさておき、そもそも「意識」を意識する時点でサピエンス並みということだろうか。来るべき新種のデウスなら、もはや「意識」を意識することさえないだろうから。
なお、僕はこの原稿をある音楽をBGMにして書いている。それは「コンピューターが作曲したクラシックミュージック」だ。そして、コンピューターが詠んだ句入っている俳句集『灼熱の夜が訪れる』からお気に入りも探してみた。日本語版がないので原書「Comes the Fiery Nights」(下p.156)から僕が選んだ一句は、
Ring all the bells!
Never has arrived today,
And may soon be gone.
〔僕の意訳〕
鐘の音に
思い出ずとも
消えるとも
果たしてこれは人間が詠んだのか、意識を持たないアルゴリズム(コンピューター)が詠んだのか、定かではない。
人間と人類 again
『『サピエンス全史』をどう読むか』という本で僕は、「人間と人類」の区別について、それぞれを厳密に定義した上で明確に区別すべきだと述べた。いや、わざわざ厳密に区別しなくても文脈から分かるはずという意見もあろう。しかし、ハラリ教授の文章は、溢れる学識とともに、一読して分かる読みやすさも際立っているので、「人間と人類」の区別についても一読して分かるような工夫がほしかったのである。では、いったい僕は何を欲したのか。ここで今一度、「人間と人類」の区別に対する僕の要求をあげてみよう。
「人間」あるいは「ヒト」は生物学的には哺乳綱サル目ヒト科のホモ属サピエンスであり、和名だとヒト属ヒトになる。そして、ヒト属(ホモ属)に属する現生種・化石種のすべてが「ヒト類」すなわち「人類」になる。つまり、「人類」は、やはり「類」というだけあって、単に人間(ヒト、サピエンス)だけを指すのではなく、「ヒト類」全般を指すと定義しておくべきだろう。世間でよく使う「人類初」という表現はこれから「人間初」あるいは「サピエンス初」に替えてほしい。同様に「人類未踏」も「サピエンス未踏」としてほしい。なぜなら、たとえば、高い山の頂上が仮に「サピエンス未踏」だとしても、ネアンデルタール人(化石人類)がすでに登頂していたかもしれないから。滅んだとはいえ、ネアンデルタール人だって立派な人類だったのだから。
人類(ヒト属=ホモ属)とチンパンジー(パン属)が枝分かれしてから約600万年の間、ヒト属(ホモ属)には少なくとも10数種の同胞種が生まれては消えていった。滅んでしまった同胞種は「化石人類」といい、いまでも生き延びている種は「現生人類」である。と言っても、現在まで生き長らえている現生人類はわれわれ人間(サピエンス)だけだ、と考えるのが一般的なコンセンサスだ。化石人類も、滅びる前は、われわれ人間(サピエンス)と同時代を生きていた種がいた。ネアンデルタール人、デニソワ人、フローレス人などである(『サピエンス全史』上p.18-19、『ホモ・デウス』下p.195)。単に「人類」といった場合、僕の脳裏には彼ら化石人類も浮かんでくる。しかし、ハラリ教授には彼らの姿がすぐには浮かんでこないようだ。でも、読者の方々にはやはり「人類」にはわれわれ人間以外にも複数種いて、「人間」は人類の中の一つの種、しかも、最後の一種であることをいちいち思い出してほしいのである。そうすることで、『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』を通して主張されている「人間至上主義」の意義と重要性もおのずから浮かんでくるだろうから。
『サピエンス全史』でもそうだったが、と『ホモ・デウス』における「人間と人類」は原書でも日本語版でも混乱している。例を挙げると、まず「かつて存在していた全人類種」(下p.195、原文all human species that ever existed)は僕には正しいと思える。これを基準として、その前ページにある「今日、全人類が」(Nowadays all humans)は、「今日、すべての人間は」に替えてサピエンスに限定したら、より分かりやすくなるのではないだろうか。一方、「人類という種全体」(下p.221、the entire human species)は、おそらく「ヒト種(サピエンス)全体」を指していると思われるが、もしかしたら、この2ページ後にでてくるネアンデルタール人も含めて本当にホモ属の全種を指しているかもしれないと思えるほど、曖昧である。
われわれ人間(ヒト、サピエンス)は「物語のおかげで…効果的に協力できた」ので発展した一方、物語を語る能力は「ネアンデルタール人やチンパンジーには望むべくもない」ものだった(上p.194)。遺伝子(ゲノム)の観点から、現生生物でサピエンスにいちばん近いのはチンパンジーであり、化石種まで入れるとネアンデルタール人がいちばん近い。サピエンスとネアンデルタール人の近さは交配可能なほど、つまり、交われば子孫を残せるほどの近さで、古典的な種の定義なら同種と認定されかねないほど近縁である。それでも、ヒトをヒトたらしめる特性、すなわちネアンデルタール人とヒト(サピエンス)との彼我を分ける特性があり、その一つが物語を語る能力だったという重要なメッセージが、より正確、かつ、より容易に日本語版の読者には伝わるように、原書の曖昧さを補ってほしかった次第である。ただし、これが日本語訳の偉業の価値をいささかも損なわないことを、あらためて申し上げておきたい。
認知革命の地はどこか――南アフリカか
僕はこの原稿を南アフリカで書いている。南アフリカといえば、悪名高い人種差別政策「アパルトヘイト」が思い出されるかもしれない。アパルトヘイト博物館に行くと、サピエンスが同じサピエンスを差別した黒歴史の展示がある。そして、屋外にはサピエンスの知的進化に関する展示もあり、そこの「We are story tellers」というコーナーはまさに「物語るサピエンス」発祥のイメージに溢れている。それは『ホモ・デウス』が「すべてが始まったのはおよそ七万年前、認知革命のおかげでサピエンスが自分の想像の中にしか存在しないものについて語りだしたときだ」(上p.194)と述べていることを想起させるに十分だ。
南アフリカには、人類進化史で重要な猿人「アウストラロピテクス」の化石が初めて発見された場所もあり、そこは「人類のゆりかご」として世界遺産に登録されている。ただし、後に、これより古い猿人化石が東アフリカで発見されたので、今では「人類の揺籃」の地位が東アフリカに移ってしまった感もある。が、南アフリカでの初発見は1924年だったので、そろそろ100周年、南アフリカが再び注目されるかもしれない。いや、何百万年前の猿人だけでなく、この数万年におけるわがサピエンス種の知的進化についても、この南アフリカで重要な発見があった。それはつい最近のことである。
南アフリカの「ブロンブス洞窟」は中石器時代、まさに「七万年前、認知革命」前後を含む先史時代のサピエンス種の遺跡である。ここからは1990年代からたくさんの遺物が発見されている。その一つに1 cm×4 cmほどの小さな岩石片があり、それには赤土で“ハッシュタグ”すなわち“#”のような図形が描かれていた。七年にわたる研究の結果、これはサピエンス最古、7万3000年前の抽象画であるとの報告が2018年9月12日にNature誌の電子版で発表されたのである。印刷媒体での発表は同年10月4日、僕の滞在中だった(参考文献3)。
それにしても抽象画とは、そのまま「サピエンスが自分の想像の中にしか存在しないもの」ではないか。そこから物語が始まり、虚構の世界観がつくられたのだ。それが個人にとどまっているうちはまだ良い。「経験する自己」と「物語る自己」が自分の中で分離したり絡み合ったりするだけだからだ(下p.119)。せいぜい「物語る自己」がスリムになった自分を夢みてダイエットを試みるが、現実的な空腹感に苛まされた「経験する自己」がそれを台無しにするだけのこと(下p.124)。ところが、「物語り」が自己の内部から外部に漏れ出したらどうなるだろう。たとえば、神様は太った人間から先に食べる、という物語が語られ、それが洞窟内の仲間うちで受けたとしたら、皆こぞってダイエットに挑戦し、皆こぞって失敗したに違いない。そうやって、洞窟の仲間たちの間で「共同主観」が発生し、育まれたのだろう。
共同主観とは19世紀にカール・マルクスが唱えた「上部構造」(社会的意識)、あるいは20世紀に吉本隆明氏が謳った「共同幻想」とほぼ同じ概念で、これを「大勢で柔軟に協力」して共有できたからこそ、サピエンスは知的大発展を遂げたのだという。それを「認知革命」というのだが、そのことは、僕は『サピエンス全史』で学んでいたし、『ホモ・デウス』でも言及されているので、「七万年前」という時間的(年代的)なところはもう暗記している。しかし、空間(場所)に関する情報は、前作でも本作でも、他書でも、はっきりしたことは分からないままだった。ところが、世界でもまだ一ヶ所――ブロンブス洞窟――だけだが、ついに「七万年前の認知革命」の地が分かったのである。科学的発見における共時性を考えると、これから世界各地で同様な発見が続く予感がする。
なお、共同主観は本作のきちんとした用語でいうと「共同主観的現実」であり、原文ではintersubjective realityである。僕だったら、inter-とあるのでつい「相互主観的」と訳してしまいそうだが、柴田氏は「共同主観的」と訳出された。そのほうがずっと分かりやすいし、ハラリ教授も“我が意を得たり”と納得されるだろう。ここでも柴田氏の訳業に感嘆した次第である。
ヒューマニティのアップグレード
アパルトヘイトの黒歴史に幕を引き、南アフリカ共和国として新たな幕上げをした重要な立役者は、初代大統領のネルソン・マンデラ氏(1918-2013、享年95歳)だった。ややもすると体制派と反体制派の間で武装闘争に明け暮れそうになるところ、マンデラ氏は粘り強く「話し合い」の重要性を説きつづけた。マンデラ氏は自分の短所として「信じやすいこと」を挙げていたが、話し合うことも信じることも、どちらも人間至上主義の大切な要素である。1993年にノーベル平和賞を受賞したのも宜なるかな。
そして、ヒューマニズムといえば、何といっても、あのマハトマ・ガンディー(1869-1948、享年78歳)に触れないわけにはいかないだろう。後にインド独立運動で唱えた真理の主張や非暴力の思想を育んだのは南アフリカだった。ガンディーは23歳から44歳までの21年間を人種差別化が進行していた南アフリカで過ごし、人権回復や非暴力などの思想と方法論を熟成させたのである。ガンディーは母国インドに帰るため南アフリカを去ったが、その思想は後にマンデラ氏らに影響を与えた。南アフリカにいる間、ガンディーは南アフリカで何回か引っ越しをして、後の反アパルトヘイト運動の中心地になったヨハネスブルグにもいた。そこで足掛け2年ほど住んだ家は現在、サティヤーグラハ・ハウスとして公開されている。僕はそこで、1925年に英国国教会の司祭が説教に用いたネタをガンディーが発行していた週報「ヤング・インディア」に転記した「七つの社会的罪」を学んだ。それを以下に挙げる。
理念なき政治 Politics without Principle
労働なき富 Wealth without Work
良心なき快楽 Pleasure without Conscience
人格なき学識 Knowledge without Character
道徳なき商業 Commerce without Morality
人間性なき科学 Science without Humanity
献身なき信仰 Worship without Sacrifice
わざわざ挙げたのには理由がある。それは、この20世紀のサピエンス的な“罪”のリストを21世紀のホモ・デウス的な“徳”のリストに改訂できるのではないかと思ったからである。やることは簡単だ、「なき」(without)を「による」(with)に変えて、その前後を入れ替えるだけのこと。たとえば、僕が生業としている「科学」については「人間性なき科学」を「科学による人間性」にするだけ。英語だと「Science without humanity」を「Humanity with science」にするだけである。これだけで“罪”が、あら不思議、“徳”になる。
本作『ホモ・デウス』では21世紀的な「テクノロジーがすべて」の「テクノ人間至上主義」が朗々と謳われている(下p.189)。テクノロジーは目的ではなく方法だ。そこで方法を示す「with」の出番となる。オリジナルの「人間性なき科学」(Science without humanity)だと“より良い科学をするには人間性が必要ですよ”と目的と方法が混同されている。しかし、「科学による人間性」にすると人間性は目的、科学は方法だとすぐ分かるし、現実性もあって実行可能だ。つまり、「定量化された自己」や「数値を通しての自己認識」(下p.164)によって(自分によってであれ他者によってであれ)人間性を磨くこと――ヒューマニティのアップグレード――を目指すのである。以下に改訂版のリストを挙げよう。
政治による理念 Principle with Politics
富による労働 Work with Wealth
快楽による良心 Conscience with Pleasure
学識による人格 Character with Knowledge
商業による道徳 Morality with Commerce
科学による人間性 Humanity with Science
信仰による献身 Sacrifice with Worship
理念で政治をするのではなく、政治をしているうちに理念が形作られていく。労働で富を得るのではなく、富を元手にして仕事(労働)を作るのである。良心で快楽を正当化するのではなく、快楽によって良心を育むのである(苦痛から良心は生まれない)。人格者に学識が伴うのではなく、学識を積むうちに人格者になるのである。道徳心を持って商売せよというのではなく、商売をしているうちに道徳観念が身につくのである。人間を大事にした科学をするのではなく、科学によって人間性を磨くのである。献身的な信仰をするのではなく、信仰することで献身的な行いをしやすくなるのである。
どうだろう、これで「七つの社会的罪」が「七つの徳」になったのではないだろうか。おそらく異論や反論もあろうかと思うが、とりあえず僕から『ホモ・デウス』への、一つの答案を提出したつもりだ。本作のラスト直前で「単一の明確な筋書きを予測して私たちの視野を狭めるのではなく、地平を広げ、ずっと幅広い、さまざまな選択肢に気づいてもらうことが本書の目的だ」(下p.244)と明言したハラリ教授への、僕の“気づき”の答案として。
追記
日本語版『ホモ・デウス』では本文中に完全に反映しているので敢えて別立てにしていないが、原書には「訂正」(Errata)という項がある(『サピエンス全史』の原書にはなかった)。そこでは、訂正一覧に入る前に、こんな件がある:「それでも人間のすることなので、どうしても間違いはある」Yet as with any human endeavor, mistakes are inevitable. サピエンス界で最高レベルの知性であるハラリ教授もやはり人の子、ミスはあるものだ。しかし、もし、この本を超AI、すなわち「高度な知能を備えたアルゴリズム」が書いたとしたら、このようなミスはなかったのだろう。と思うと、アイロニカルな気がしてくる。もっとも、僕など、もっと頻繁にミスを犯していて、この1万字にも満たない読書感想文の中でさえ、多くのミスがあるはずだ。それに比べれば、ハラリ教授はやはりAI並みにアップグレードされたサピエンスに違いない。
もう一つ。「訳者あとがき」に「日本語版の加筆・訂正」とある(下p.250)。これは、たとえば一例として、「自由民主党…公明党…共産党…自宅…」の件であろう(下p.107)。原書でこれに対応する箇所は「Conservative … Labour … UKIP … home …」(保守党…労働党…イギリス独立党…自宅…)である。ハラリ教授の目配りというか気配りはこんなところまで及んでいた。やはり、アップグレードされているに違いない。
参照URL
1.「攻殻機動隊」インフォメーション・サイト
https://v-storage.bandaivisual.co.jp/sp-site/ghost-in-the-shell-special/
2.“AIの父”ユルゲン・シュミットフーバー博士のホームページ
http://people.idsia.ch/~juergen/
参考文献
1. Hublin JJ et al. (2017) New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens. Nature, 546, 289-292. DOI: 10.1038/nature22336
2. Richter D et al. (2017) The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age. Nature, 546, 293-296. DOI: 10.1038/nature22335.
3. Henshilwood CS et al. (2018) An abstract drawing from the 73,000-year-old levels at Blombos Cave, South Africa. Nature, 562, 115–118. DOI: 10.1038/s41586-018-0514-3. Epub 2018 Sep 12.