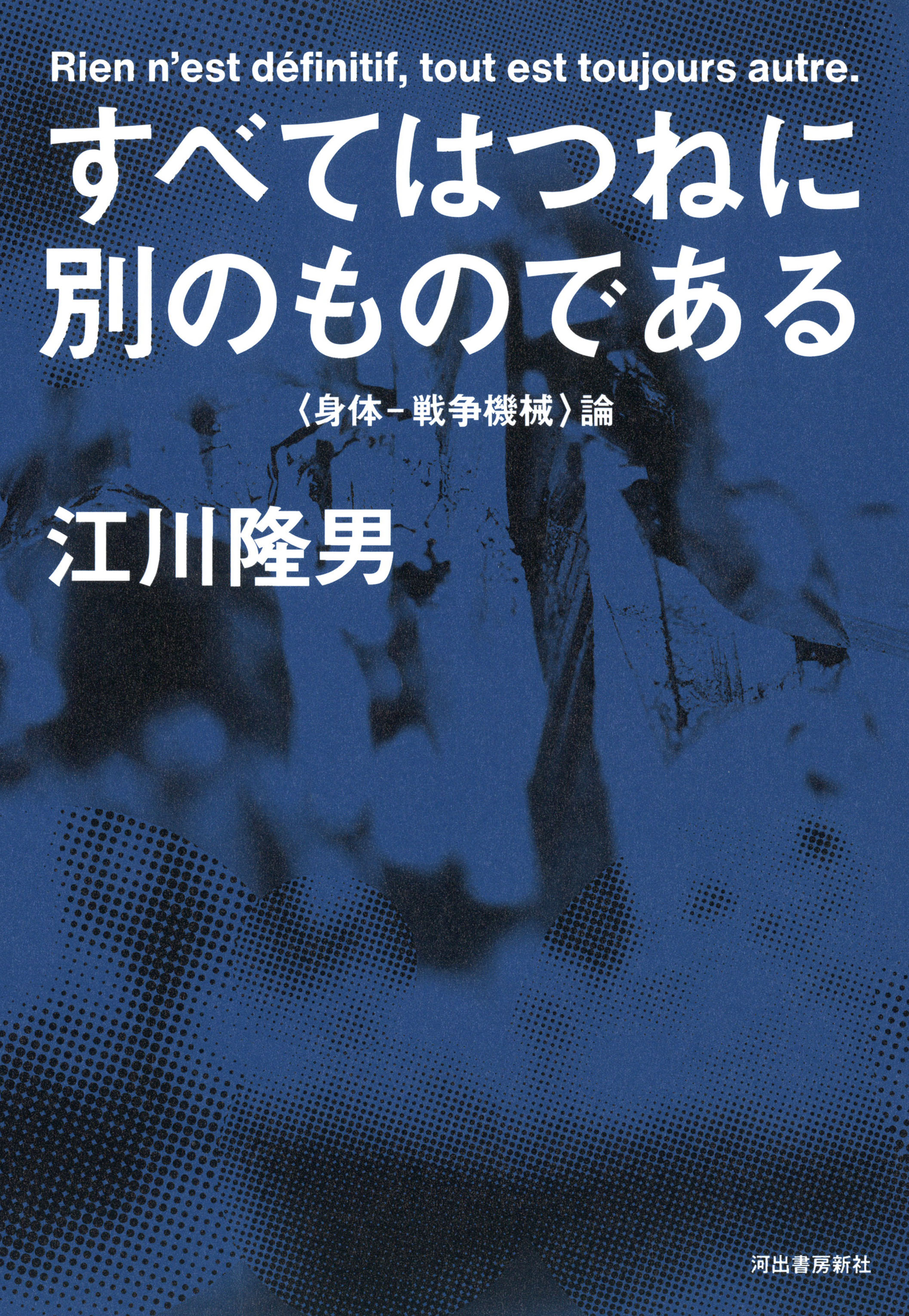
スピノザとドゥルーズ=ガタリをつきぬける孤高の哲学者によるおそるべき触発
評者・福尾匠
われわれはなにかにつけて、これは可能だとか必然だとか偶然だとか蓋然性が高いだとか言う。こうしたボキャブラリーは哲学では「様相」と呼ばれる。日常的にも哲学的にもわれわれはさまざまに様相を割り振るが、言ってしまえば様相とは「納得」の形式であり、何であれあるものをそのものとして、つまり特異なものとして受
2019.11.27人文書
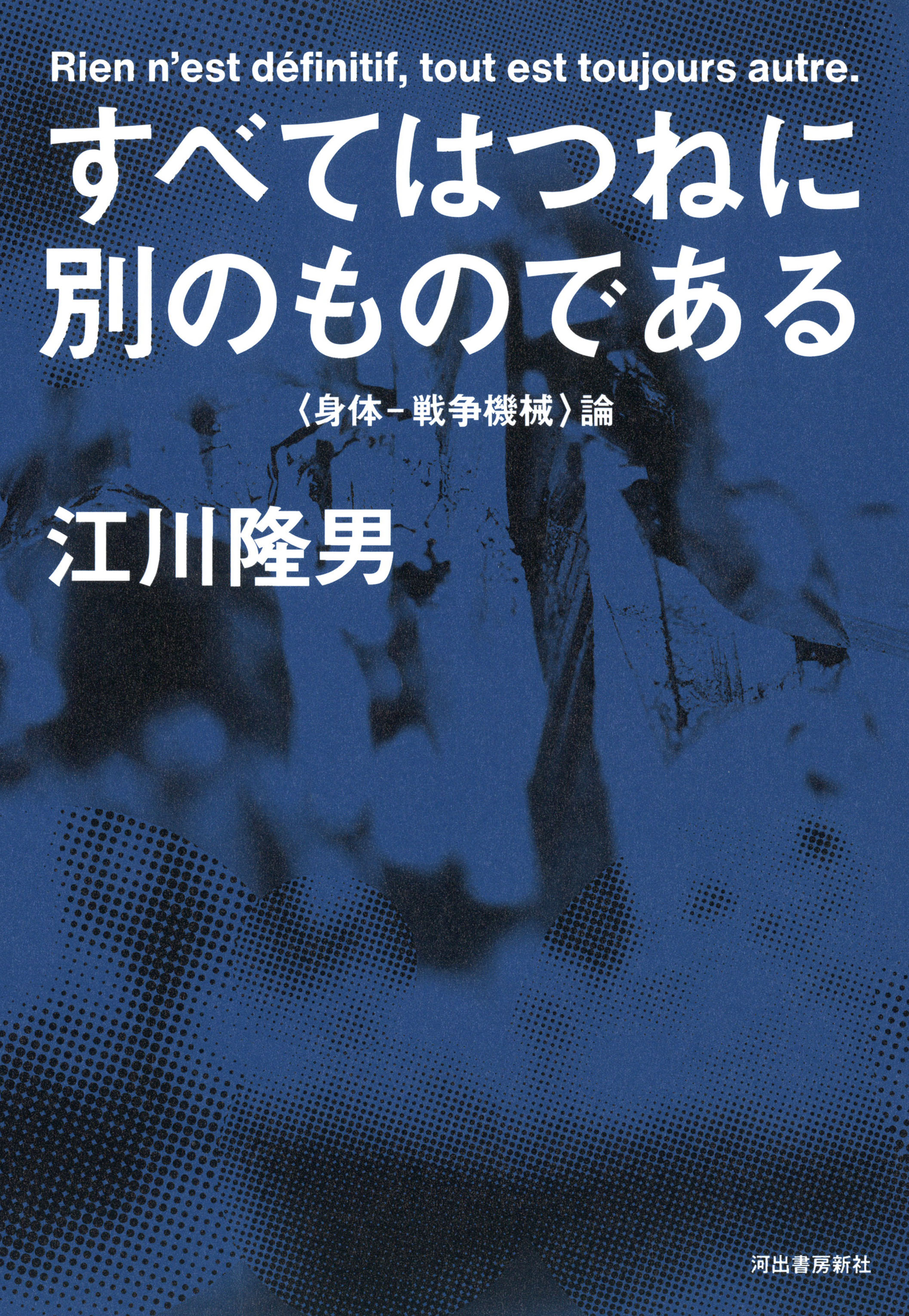
評者・福尾匠
われわれはなにかにつけて、これは可能だとか必然だとか偶然だとか蓋然性が高いだとか言う。こうしたボキャブラリーは哲学では「様相」と呼ばれる。日常的にも哲学的にもわれわれはさまざまに様相を割り振るが、言ってしまえば様相とは「納得」の形式であり、何であれあるものをそのものとして、つまり特異なものとして受
2019.11.27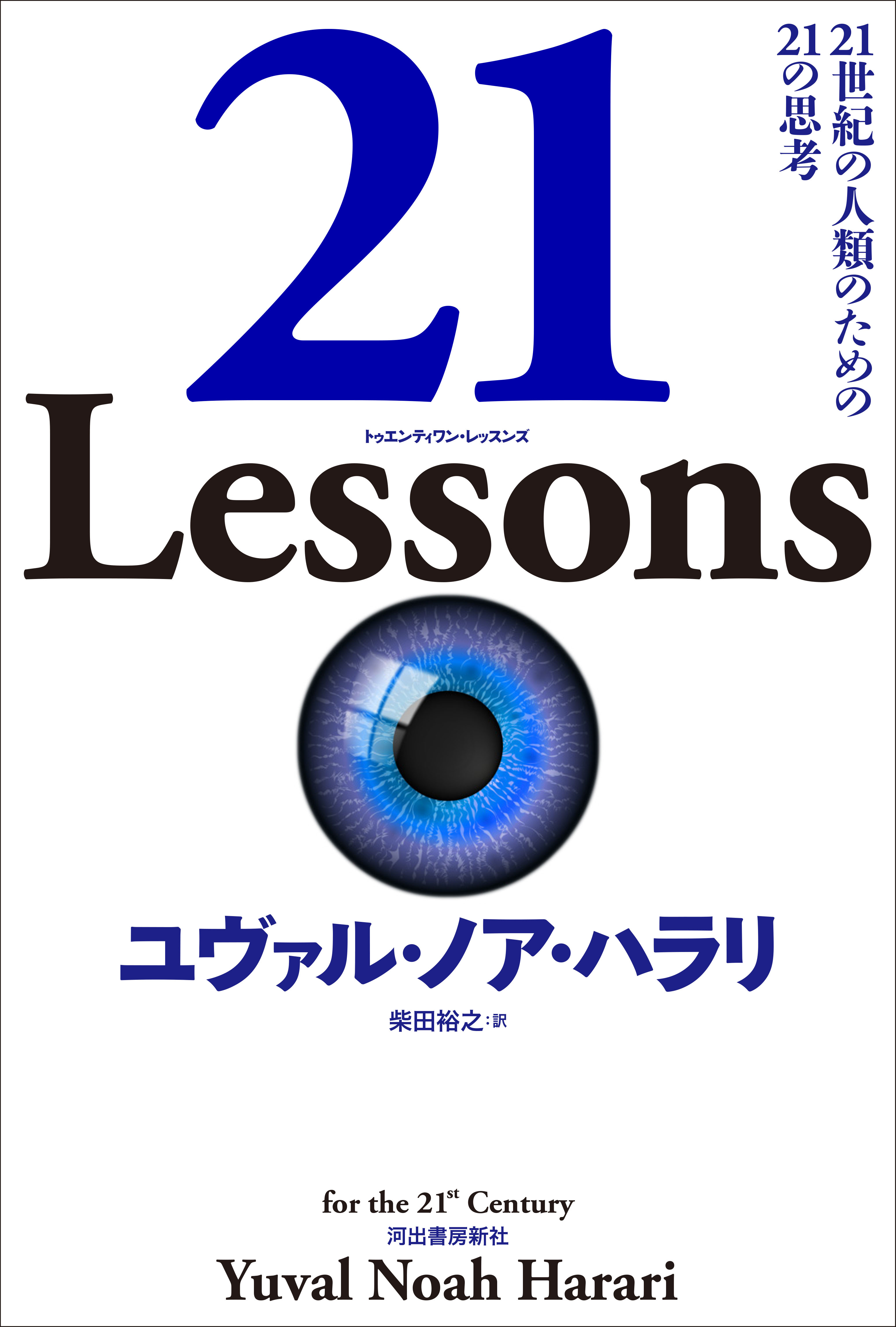
ユヴァル・ノア・ハラリ
『21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考』はじめに 的外れな情報であふれ返る世界にあっては、明確さは力だ。理屈の上では、誰もが人類の将来についての議論に参加できるが、明確なビジョンを維持するのはとても難しい。議論が行なわれていることや、カギを握る問題が何であるかに、私たちは気づきさ
2019.10.21
ユヴァル・ノア・ハラリ
●第1作『サピエンス全史』は世界で1200万部突破『サピエンス全史』は、歴史学のみならず様々な学問の知見を駆使しながら、壮大で斬新な歴史像を提示して世界中の読者を驚嘆させました。第2作『ホモ・デウス』も世界で600万部を突破。生物工学や情報工学といったテクノロジーを手に入れたわれわれ人類の未来を予言
2019.09.12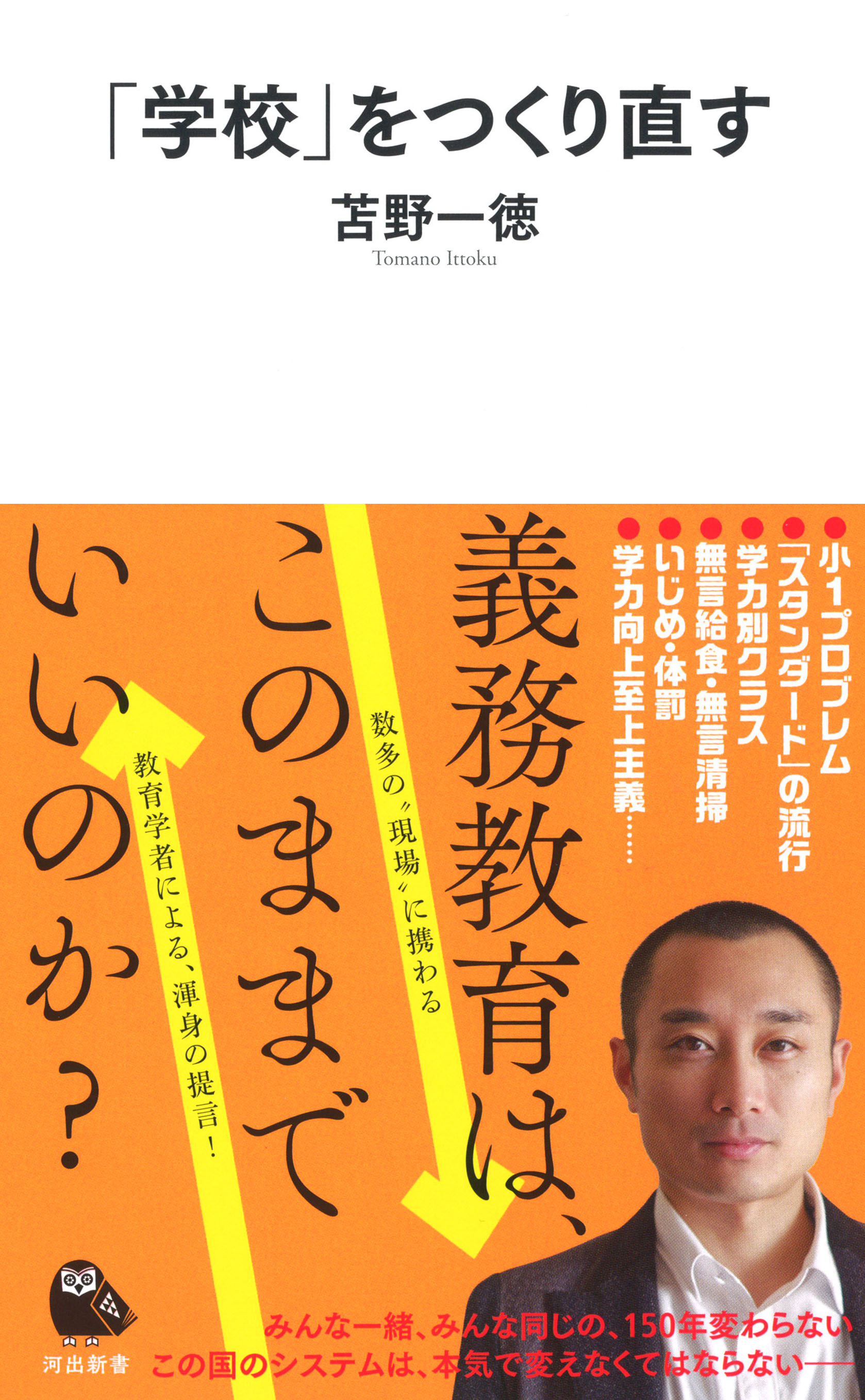
苫野一徳
学校システムの限界 どんな親も先生も、子どもたちには幸せな学校生活を送ってほしいと願っているはずです。 でもどういうわけだか、子どもたちが幸せそうじゃない。そう感じている人は、少なくないんじゃないかと思います。 それは一体、どういうわけなんでしょう? そしてどうすれば、わたしたちはそんな
2019.04.02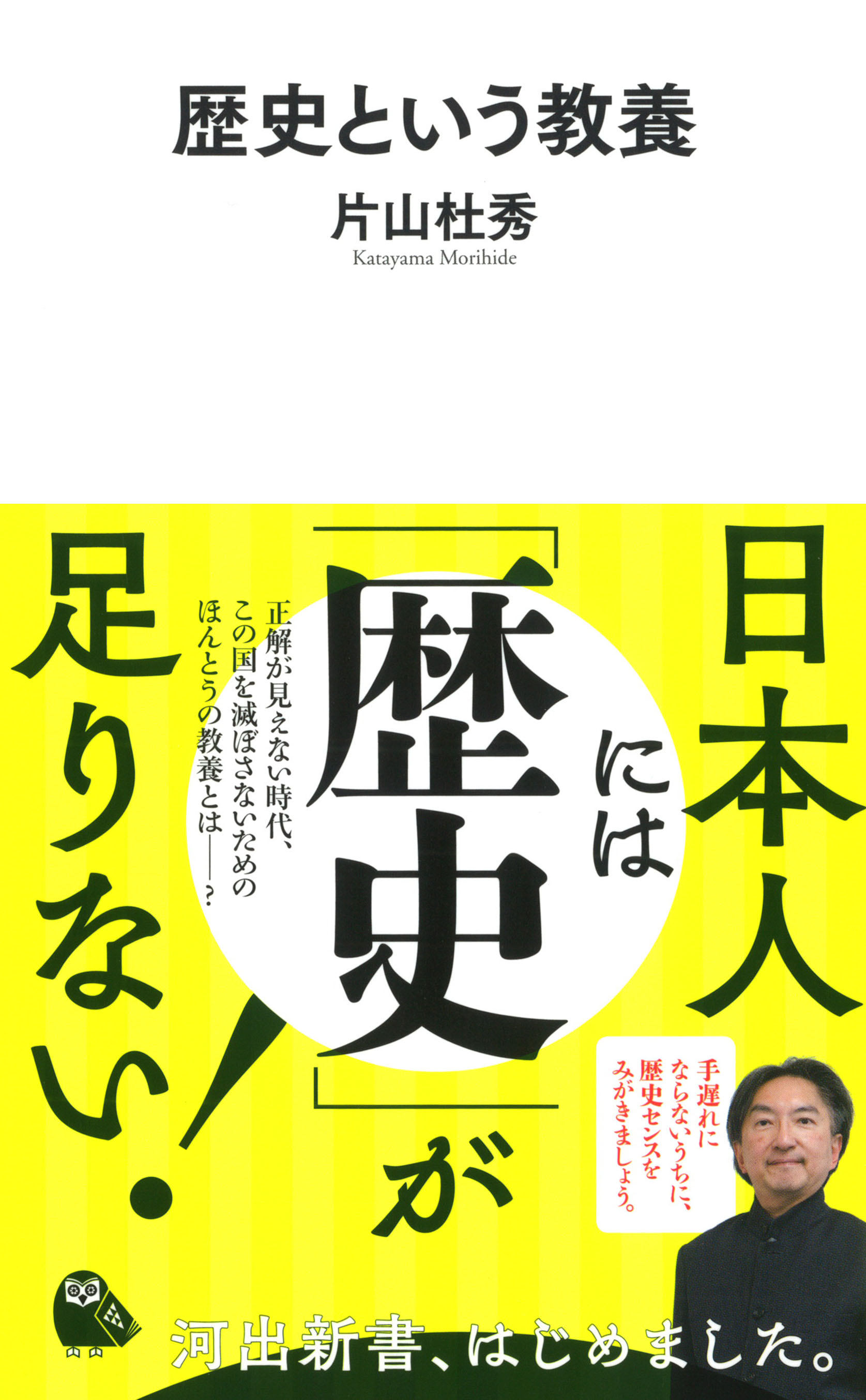
片山杜秀
時事問題から平成史、右翼思想からクラシック音楽まで、幅広い守備範囲を誇る博覧強記の思想史家・片山杜秀さんが、渾身の書き下ろし『歴史という教養』を上梓。なぜいま、改めて歴史とは何かを問う必要があるのか。正解の見えない時代における、ほんとうの教養とは何かーー。この一冊に込めた想いを寄せていただいた。&n
2019.02.15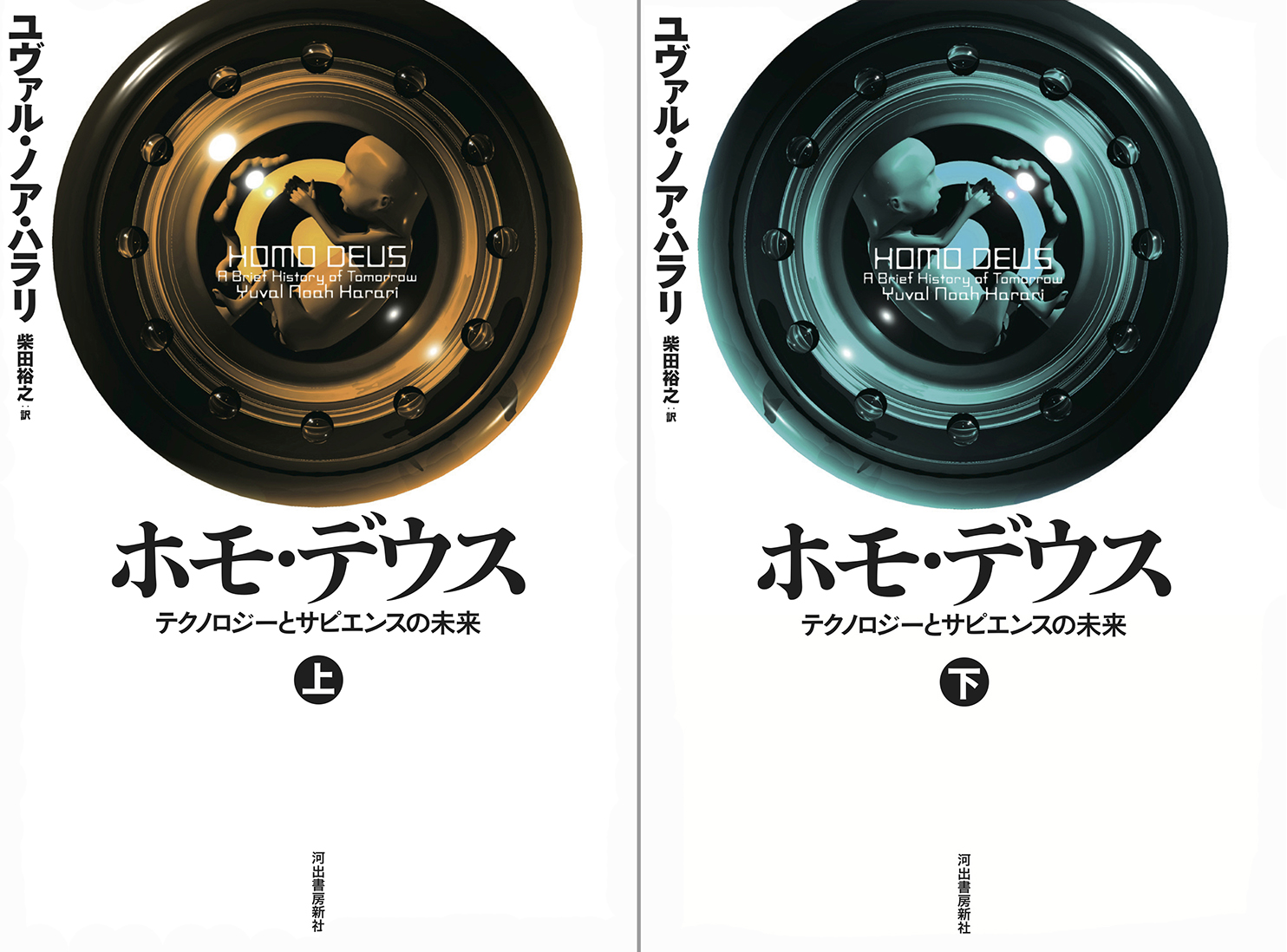
井上智洋
人類史を変えた3つのリンゴ 人類の歴史には、3つのリンゴに象徴される劇的な変革があった。一つ目は「アダムのリンゴ」で、これは紀元前一万年頃に始まった「農耕革命」を象徴している。この革命によって、狩猟・採集社会から農耕社会への転換がなされた。アダムとイブが「知恵の木の実=リンゴ」を食べてエデ
2019.01.07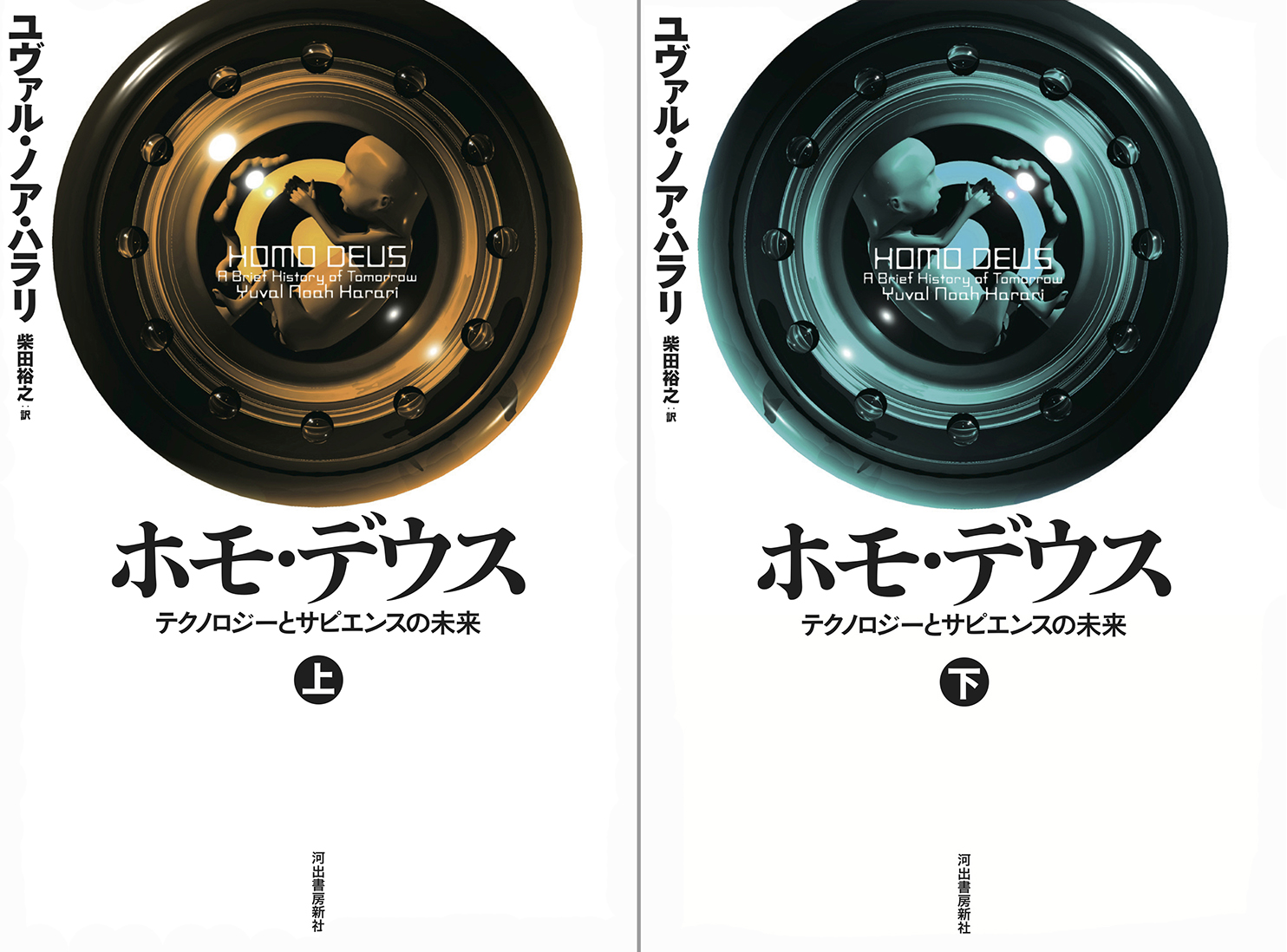
山本貴光
1.私たちはどこから来て、どこへ行くのか 「私たちは何者なのか」とは、古くていつまでも新しい問いである。人類は他の生物とどこが違うのか。なぜ人類だけが地球上でこれほど繁栄したのか。加えて言えば、目下のところ宇宙でも唯一の知的生命体のようである。つい最近も科学雑誌『サイエンティフィック・ア
2018.11.08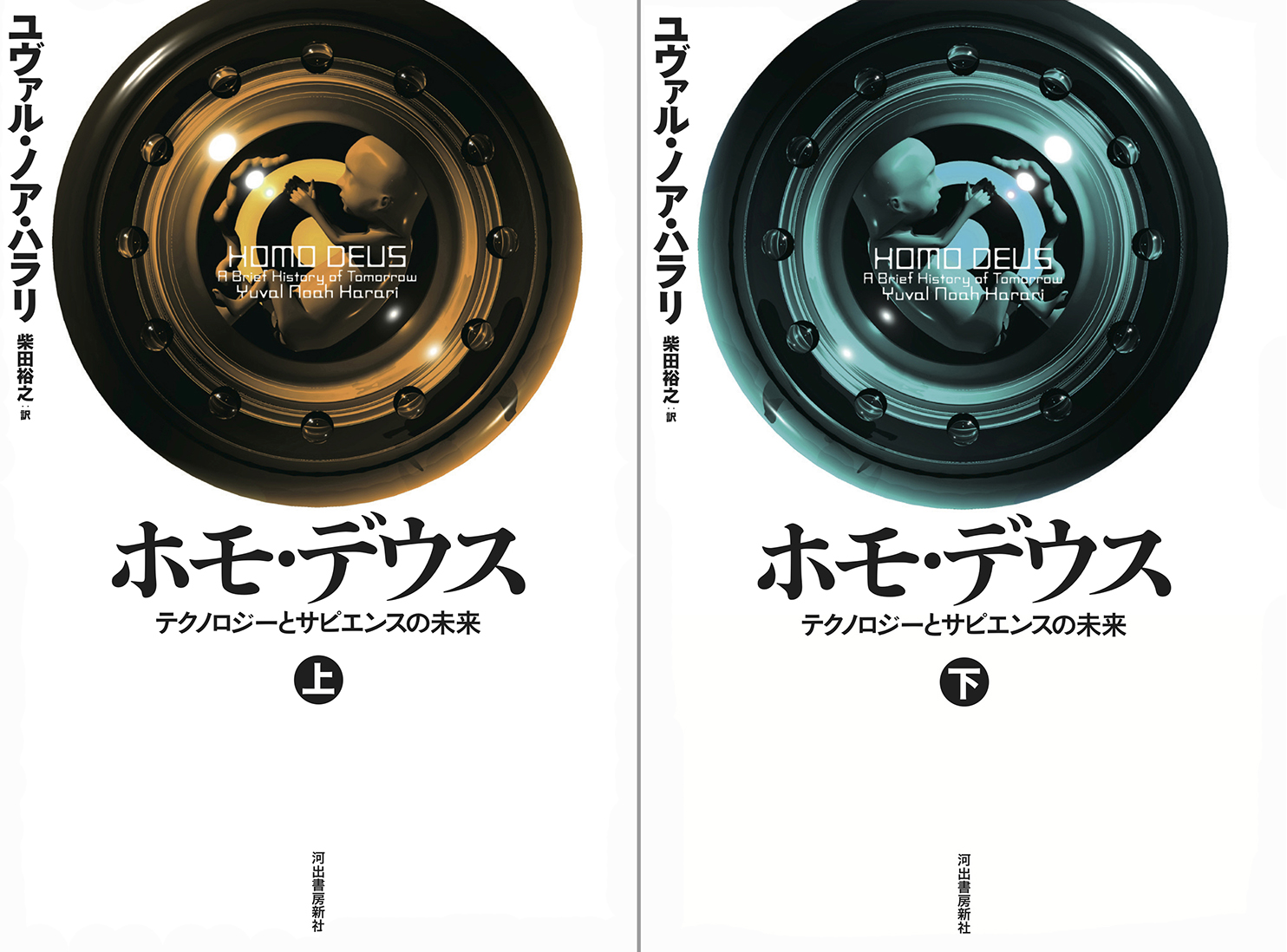
生物学者 長沼 毅
『超サピエンス前史』われわれ人間(学名ホモ・サピエンス)と人間界の文明の来し方行く末を俯瞰した前作『サピエンス全史』からちょうど二年で、待望の本作『ホモ・デウス』日本語版が出版された。まずは前作と本作の翻訳に当たられた柴田裕之氏の偉大な訳業に心からの敬意を表したい。そして原書『Homo Deus』だ
2018.10.26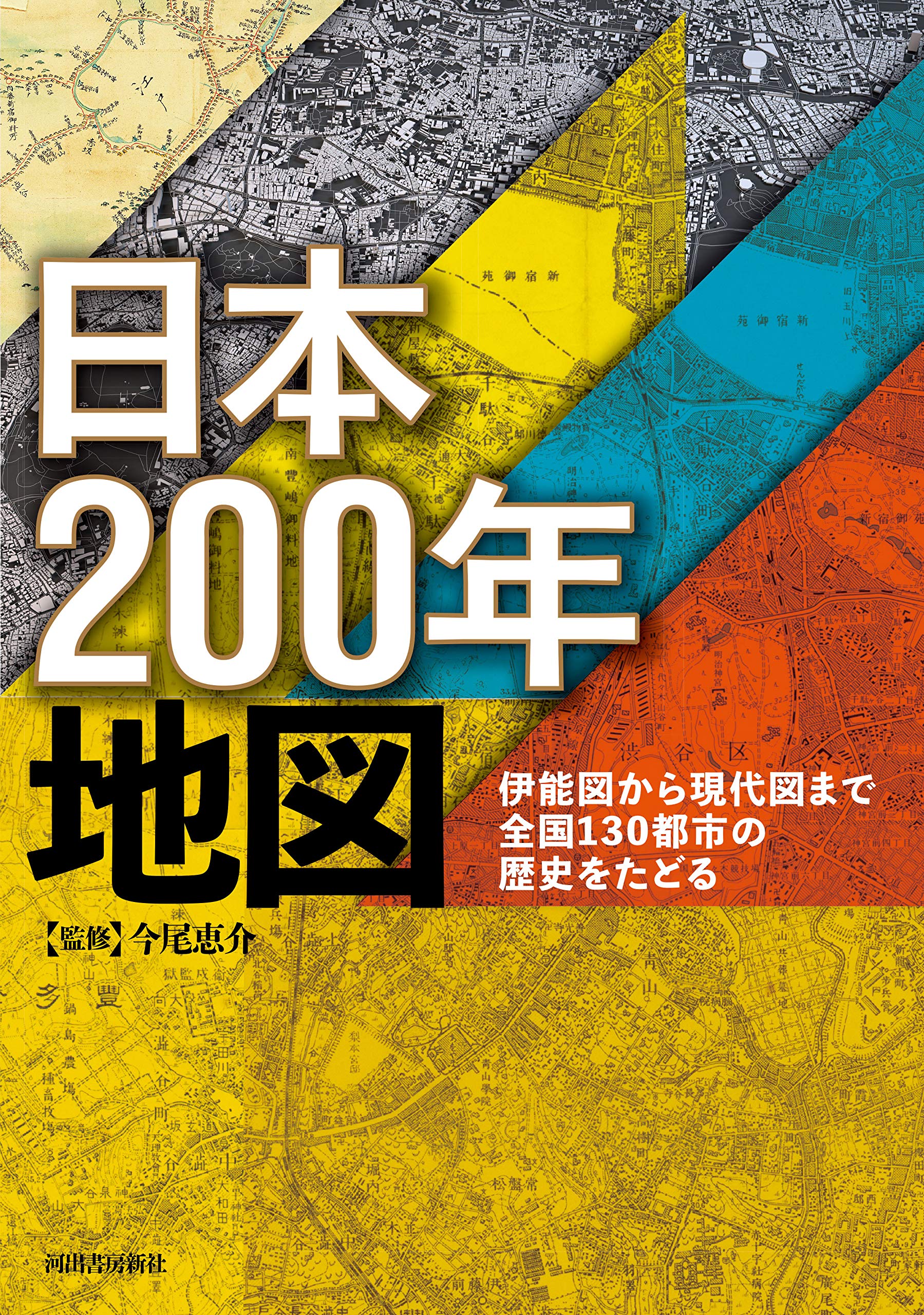
今尾恵介×村山祐司
〈伊能忠敬没後200年企画〉『日本200年地図』刊行記念イベント開催! 地図から読み解く日本200年の変遷~伊能図から現代地図までを比較して~出演:今尾恵介さん、村山祐司さん 今年は伊能忠敬没後200年です。伊能の偉業『大日本沿海輿地図』は日本最古の実測図であり、その正確さは世界
2018.10.26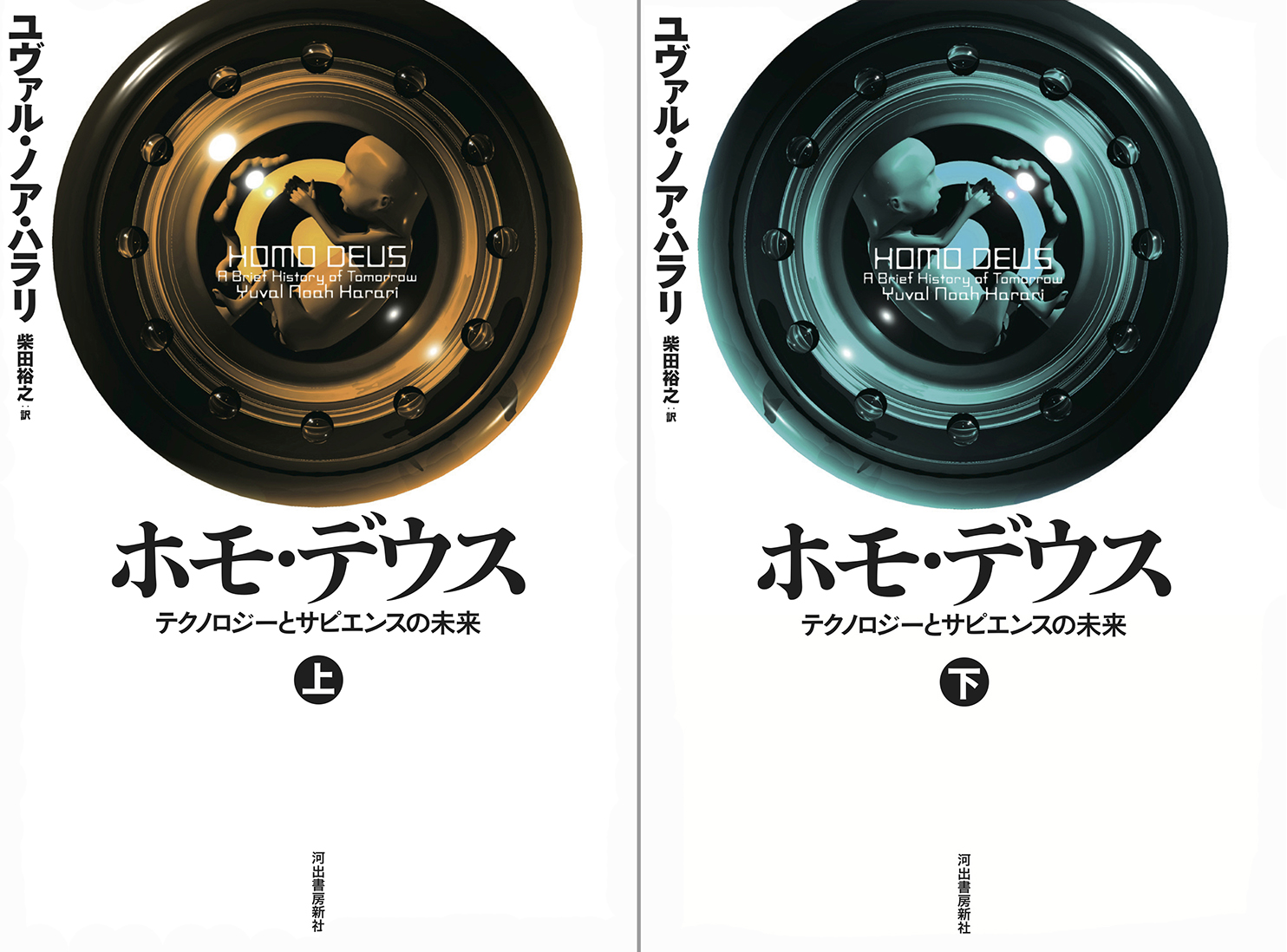
池田純一
『ホモ・デウス』については、すでに長いレビューを2回書いている。だから、ここでは少し絡め手から論じてみたい。それはこの本を手にとった時からずっと疑問に思っていたことなのだが、そもそもどうしてこんな本が書けてしまったのか?という問いだ。「こんな本が」というのは、歴史学者、それも中世軍事史が専門のハラリ
2018.10.25