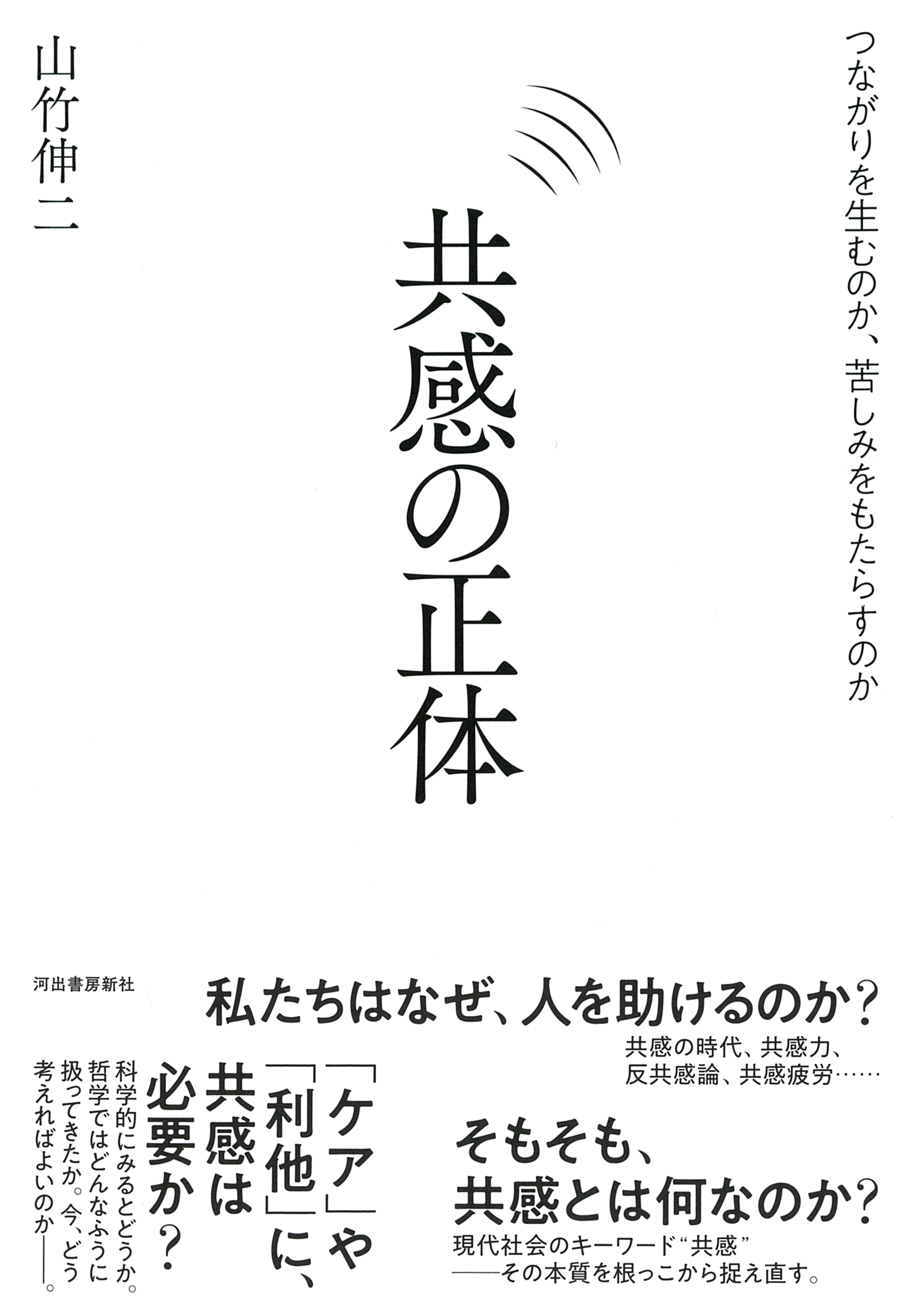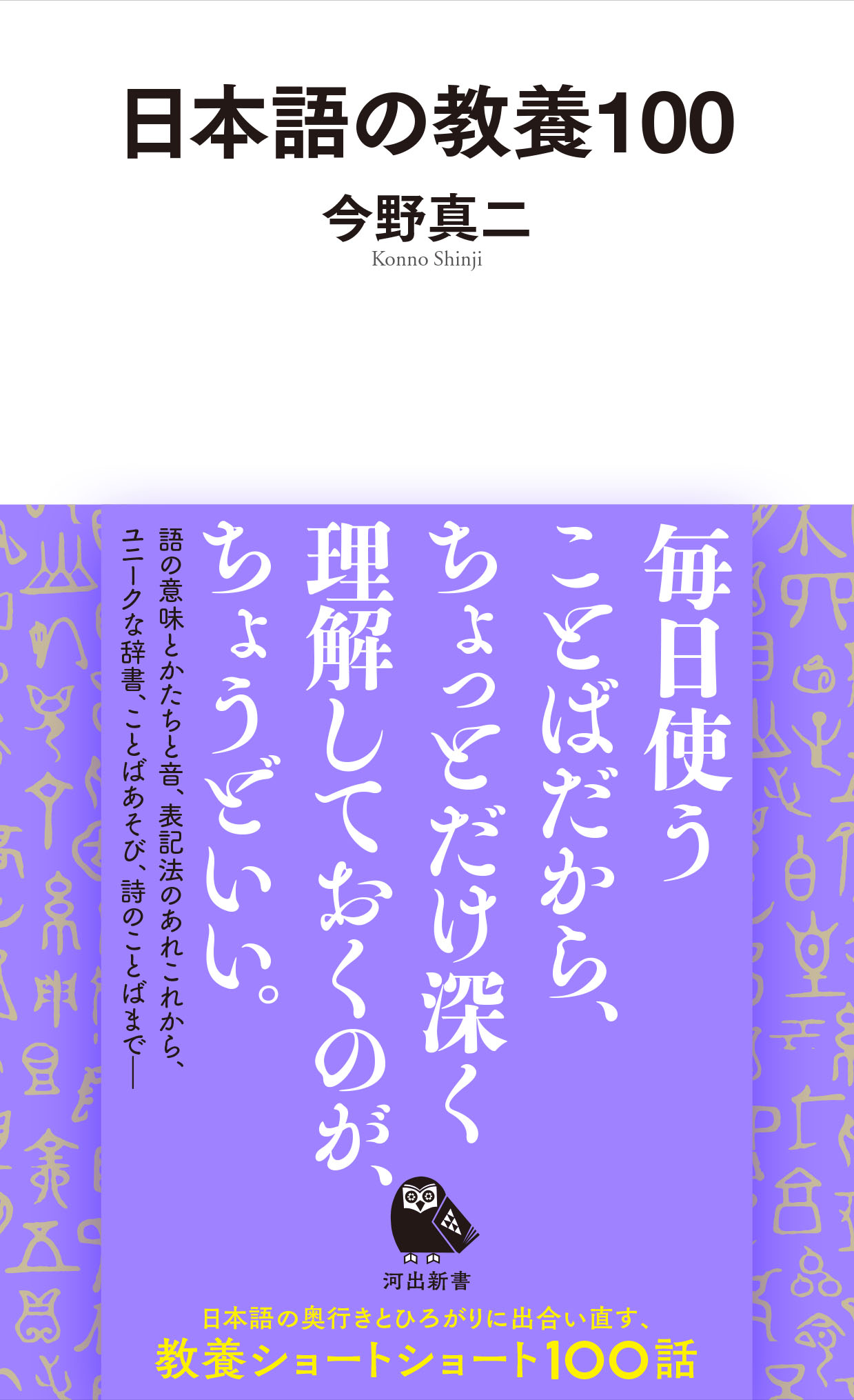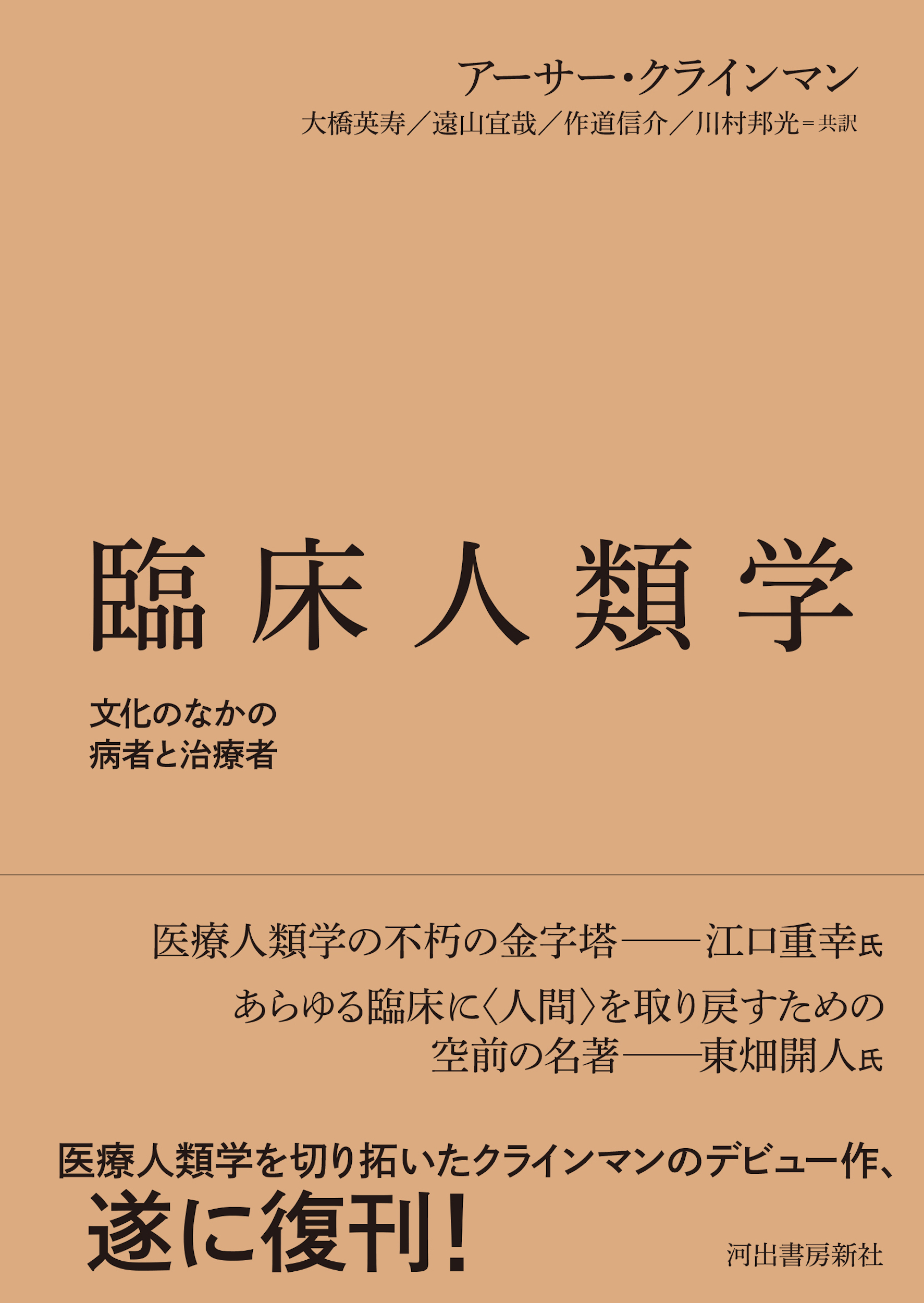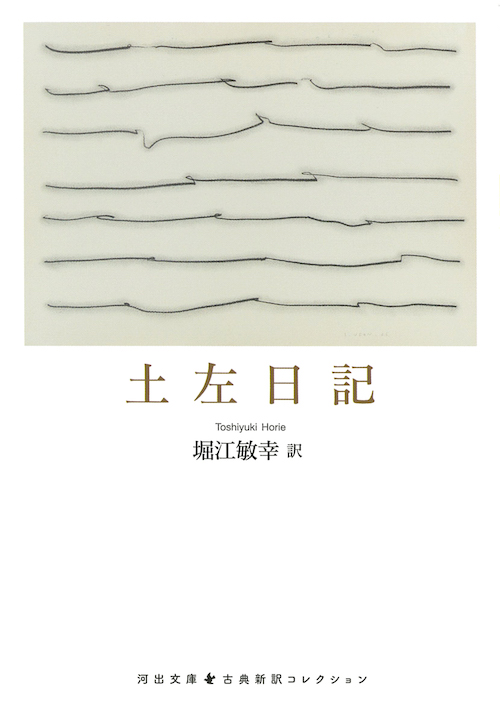単行本 - 人文書
竹内薫氏推薦!イタリア生まれのベストセラー『世の中ががらりと変わって見える物理の本』
【訳者】関口英子
2015.11.23
『世の中ががらりと変わって見える物理の本』
カルロ・ロヴェッリ著
竹内薫監訳
関口英子訳
今年の初め、イタリアの出版界はちょっとした騒動に見舞われていた。昨年(2014年)の10月に出された、100グラムあまりの小さな物理の本が、じわじわとベストセラーのランキングを上昇し、とうとう1位に躍り出たのだ。「科学書」のカテゴリでではない。イタリアが世界に誇る大作家、ウンベルト・エーコの待望の新作小説や、各国で快進撃を続けている近藤麻理恵の片づけ指南書を抑えて、「総合ランキング」での堂々1位だ。
版元は、アデルフィ社という、良質ではあるけれど、いってみれば地味な文学書や哲学書をおもに刊行している、ミラノの小さな出版社。くすんだ青一色の表紙に、タイトル Sette brevi lezioni di fisica〔七つの短い物理の授業〕と著者名・出版社名だけが黒の文字で記された、なんとも素っ気ない装幀の書籍によるこの快挙は、《ロヴェッリ・ミラクル》と称され、各メディアでこぞってとりあげられたため、さらに人気に拍車をかける恰好となった。
この「ミラクル」という言葉には、むろん物理学書であるにもかかわらず、半年あまりで1年もしないうちに30万部近くを売りあげる大ヒットとなった「奇跡」という意味合いもある(現在、世界の二十か国で版権が取得され、順次刊行ふぁ勧められている。だがそれよりも、眉間に皺を寄せながらでないと理解できないほど難解なはずの物理を、誰もがわかる平易な言葉で、公式も用いずに、しかも詩的に語ってみせるという「奇跡」を成し遂げた、著者ロヴェッリに対する称讃がこめられている。
物理学の分野でのベストセラーと聞くと、ファインマンや、ホーキング博士を思い浮かべる人も少なくないだろう。この書は、そうした名著のさらに前段階として、物理とは何かをやさしく説いてくれる「はじめの一歩」と位置づけられる。ロヴェッリは、20世紀における物理の革新的な発見から、現代においてもなお未解決な課題までを、哲学や科学史までをも広く俯瞰したうえで、ひとつの「流れ」として捉えている。たんに個々の知識を羅列するのではなく、物理学が私たち人間の世界観の形成にどのような役割を果たし、私たちという存在にどのような影響を及ぼしてきたのかを語ってくれるのだ。
これまで、物理は自分とは縁がないと思ってきた人、あるいは理解しようとしたものの挫折した人、日常生活のなかで粒子の存在なんて意識したこともないという人……。そんな人たちも、ロヴェッリの全7回の《講義》を読むことによって、どうやら地球はニュートンの発見した万有引力によって太陽のまわりをまわっているわけではないらしいことがわかり、冷凍食品を水に浸けて解凍するとき、冷たい分子とあたたかい分子がランダムに動きまわる様子が想像できるようになる。なにより、私たち人間は宇宙のごく小さな一部であり、宇宙という素晴らしい調和のうえに存在していること、だからこそすべての自然物に対して敬意を抱くべきだということに気づかされる。そして、人間の本来の姿である、より多くのものごとを知りたいと願い、学びつづける気持ちを大切にしたいと思わせてくれるのだ。さもないと、人間は「自らの種に終わりが訪れるのを、自覚とともに見届ける唯一の種になる」というロヴェッリの警告を読んでしまった以上、背を向けるわけにもいくまい。
一方で、この書には、「高校、大学と物理を勉強してもわからなかったことが、3時間で理解できた」、「高校の物理の先生がロヴェッリだったら、僕には別の人生がひらけていただろう」などと、物理を学んだ経験のある若い世代からも共感の声が寄せられている。ロヴェッリは、物理を学ぶことは、ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲を理解できるようになるのと同様、「純粋な美」を理解することであり、「世界に対する新しい視野」を身につけることなのだと情熱的に語り、人間にとって、知るという行為がいかに大切なことなのかを教えてくれる。そこには、文系と理系の垣根など存在しない。
最前線から現在の知のさらに向こうを眺めるとき、科学というものはその美しさを増します。まるで熱せられた溶鉱炉のなかのように、いくつものアイディアや着想が生まれ、新たな試みへとつながっていくのです。そこにはさまざまな歩みがあり、失敗があり、情熱があります。そして、これまで誰も想像さえしなかったことを想像しようという努力があるのです。
という短い文章に凝縮されているとおり、本書全体が科学に対する讃歌となっている。
……
現代の物理学では、特定の問題の解決策としての実験的な研究が重視されるあまり、思想や哲学、概念といった要素が軽視される傾向があると、ロヴェッリは述べている。この数十年というもの、誰もが共有できるような形で根本的な問題を解決できていない現代物理学の停滞は、物理学者の育成や研究活動において、こうした歴史・哲学的な要素が欠けているからではないかと指摘しているのだ。
……
哲学者が疑問を抱かなかったら現代の科学の発展はなかったとロヴェッリも語っているとおり、本来、人文知はいわゆる理系の知識と切り離して考えることのできないもののはずだ。それを完全に切り離してしまうと、アインシュタインが危惧していたように、「何千本もの木を見たけれど、一度も森を見ていない」という状況におちいってしまうのだろう。
日本ではいま、人文知を大学から排除しようという動きがある。だが、果たして本当にそれでいいのだろうか。この書を読むと、思想史も哲学も、最先端の科学技術の発展に貢献しない「無用な学問」などではなく、もっとも革新的な理論のもととなるアイディアを生み出してきたことがわかる。そんな人文知を切り捨てるのではなく、むしろリベラルアーツ的な広い教養に根差した教育に力を入れ、理系と文系の枠を超えた試みがより盛んになるように後押ししていくことこそが、これからの教育に求められているのではないだろうか……。訳しながら、思わずそんなことまで考えてしまった。
(訳者あとがき)