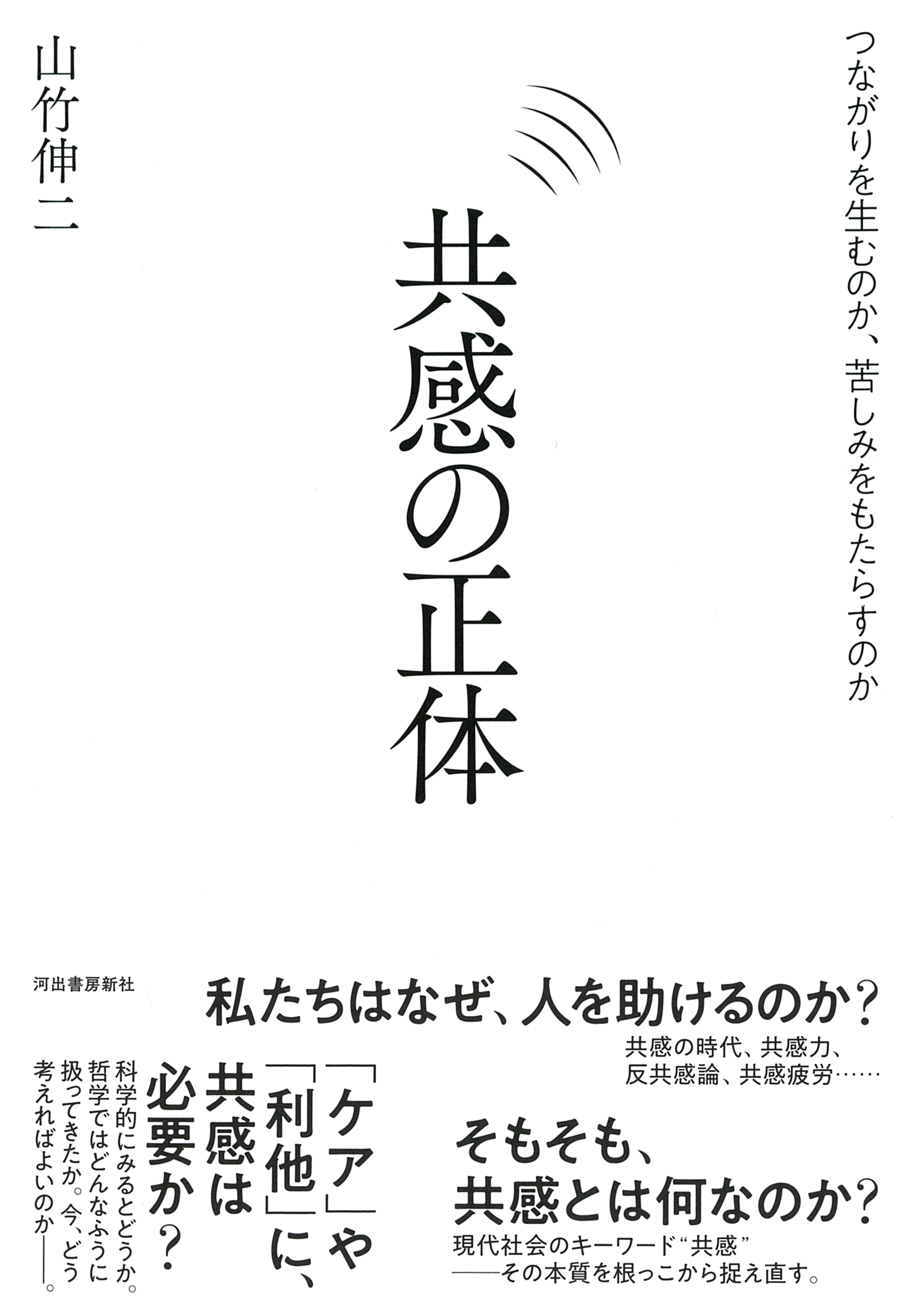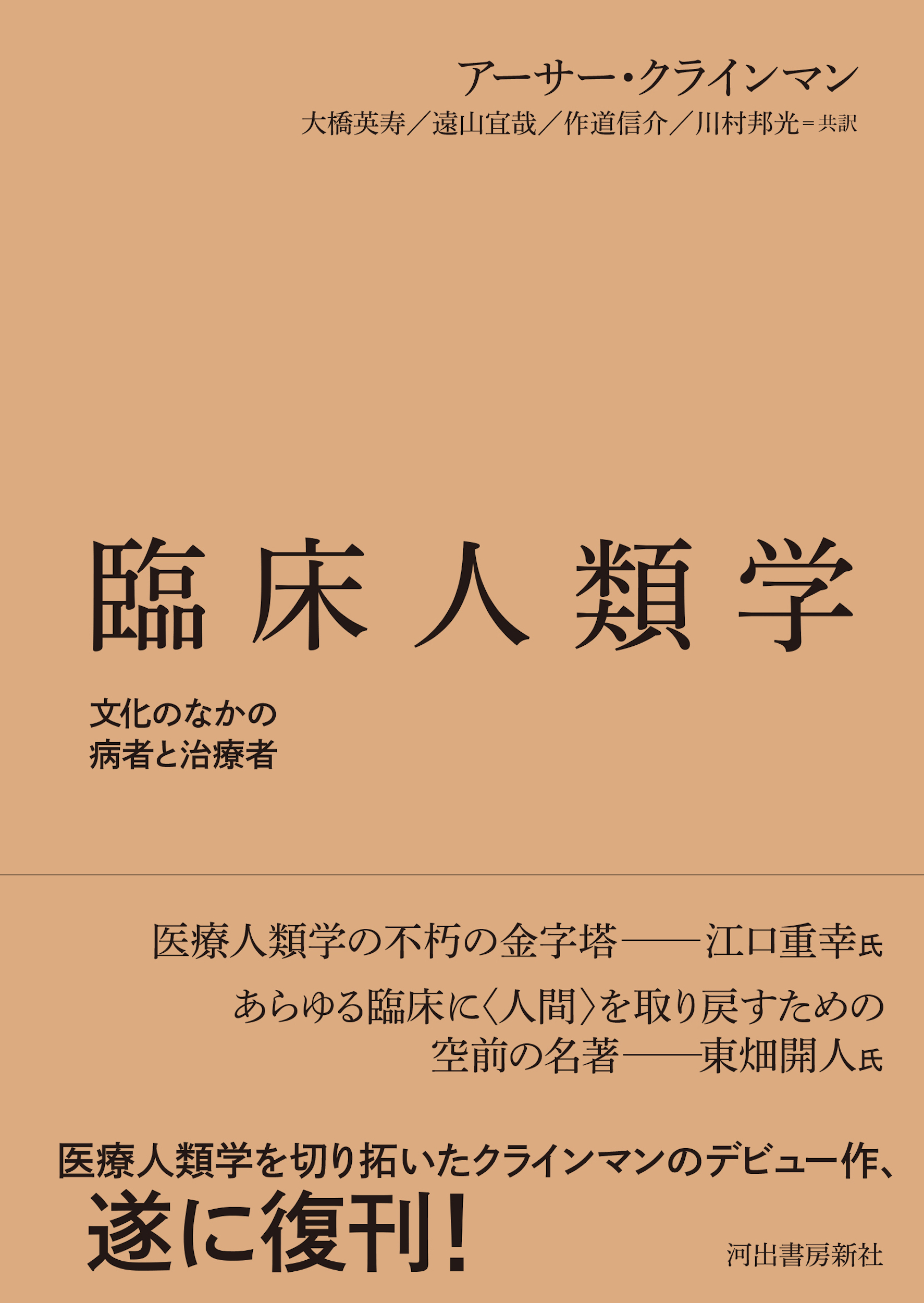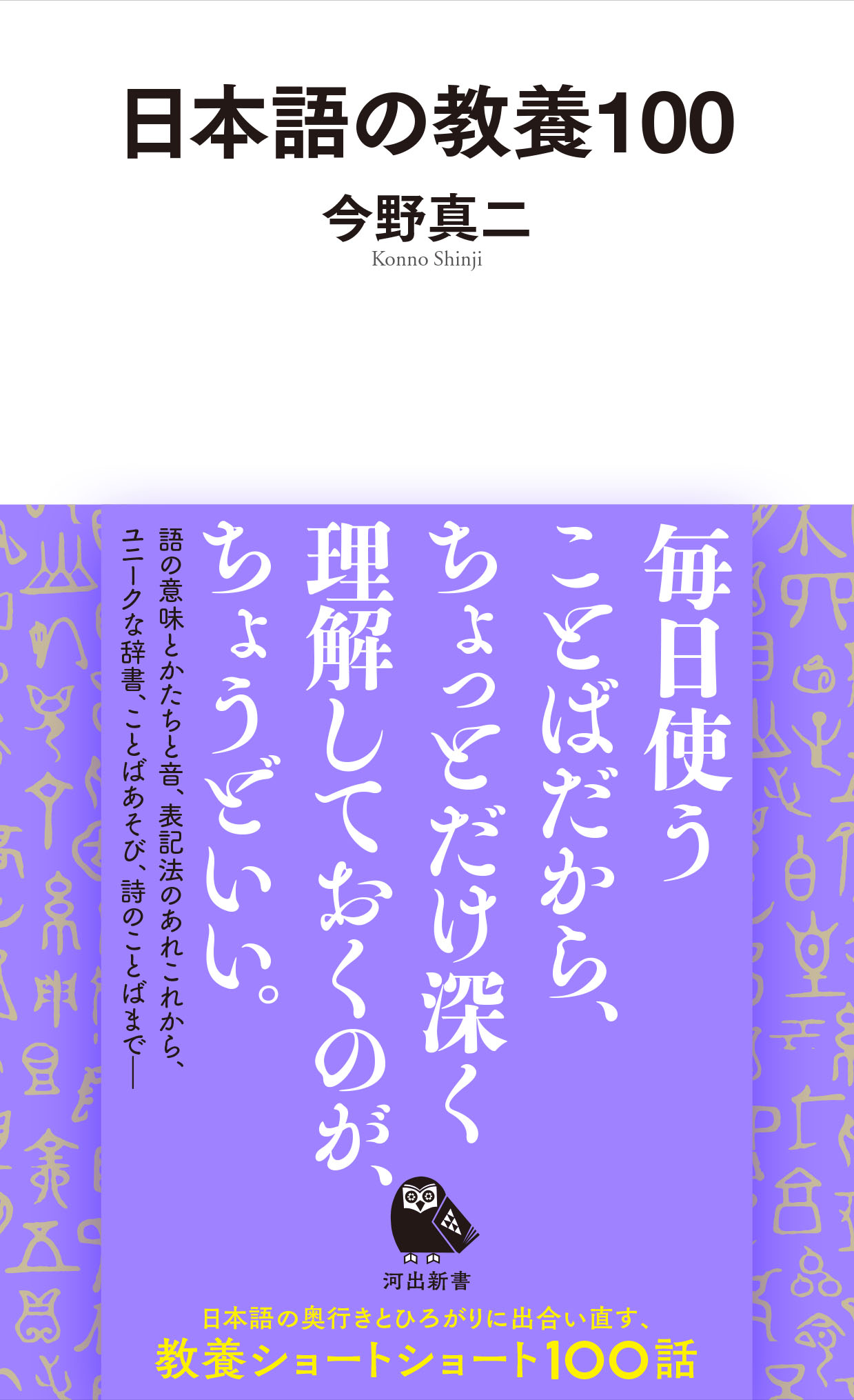
単行本 - 人文書
今野真二『日本語の教養100』(河出新書)刊行記念 往復書簡 「知識の沼――ことばで巨人の肩にのる」第1回 山本貴光→今野真二
山本貴光
2021.04.19
10年以上にわたって多彩な視点から日本語をめぐる著作を発表しつづけてきた今野真二さん。その日本語学のエッセンスを凝縮した一冊とも言える『日本語の教養100』が刊行されました。これを機に、今野日本語学の「年季の入った読者」と自任する山本貴光さんとの往復書簡が実現。日本語についてのみならず、世界をとらえるための知識とことば全般に話題が広がりそうな、ディープかつスリリングな対話をご堪能ください。
* * * * *
今野真二さま
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。このたびは、このような機会をいただきましたことを、とてもうれしく存じます。
それだけに、なにから話し始めたらよいかと、たいへん迷うところですが、下手な工夫をするのはよしにして、素直に筆の向くまま(手の向くまま)、今野さんと話してみたいことを書き始めてみようと思います。
と言いつつ、いざ書こうとすると、どのように書いたらよいだろうと少し迷います。考えてみたら、私はいままでこんなふうにして、公開の書簡という形で誰かと言葉を交わした経験がありませんでした。
例えば、あるテーマについてエッセイ(試論)を書くようなことなら、いくらか経験があるので、それを手がかりに書き始めることもできます。ところが今回、取りかかってみてはじめて感じたことがありました。そもそも人はどうやって公開の往復書簡を書くことができるのだろうか。なんのことはありません。私にとって未知の書きものであることに思い至ったのです。
他方で、書簡を読むのは好きです。作家や哲学者、芸術家たちの全集などにも、しばしば書簡が収められていますね。中には公開を前提としたものもあれば、私的に書き送ったものもあります。特に後者は、誰かが、ある人だけに向けて書いた文章を、宛先ではない人が読むという、なんだか不思議な気分のするものです。
近ごろも、「チャールズ・ディケンズ全集」の第1回配本として刊行された『書簡集I 1820-1839年』(田辺洋子訳、萌書房)という本を手に入れて、これをゆっくり読んでいるところでした。ディケンズは1812年生まれですから、なんと8歳のときの手紙から収録されているわけです(といっても1通のみ)。ディケンズが友人に宛てて、なにかの約束を破ったお詫びを書いているのなどを読んでいると、「これを私が読んでしまってもいいのだろうか」という気もしてきます。
また、そうした手紙では、当事者同士はわざわざ言葉にしなくても通じることは説明されないので、第三者にはちょっと謎めいて読めたりもしますね。例えば、ディケンズが「昨夜約束を守れなかった」という場合、この「約束」は具体的にどんなことだったのかは、文面には書かれていないわけです。
こう考えてみると明確になるように、公開を前提とした往復書簡では、やりとりする者同士が通じているだけではなく、それをお読みになる人たちにも分かるように書かれるものですね。喩えるなら、二人のプレイヤーがみなさんの前で卓球やテニスをしてみせるようなものでしょうか。あ、それだと勝負のようでいけませんね。
そんなわけで、長い独り言のように書く普段の原稿ともちがい、あるいはお互いの他に読み手を想定しない個人間のメールや手紙ともまた勝手がちがうので、こうして書いているいまも、どのように距離をとったらよいだろうと考えているのでした。状態としては、公開対談に近いでしょうか。とはいえ、目の前にいる相手の様子を見ながら適宜交替しつつ話すのともやっぱりちがっているようです。
などと、つい、こうした際に、自分はなにを感じたり考えたり、経験したりしているのだろうと考える癖があるのは、長年ゲームをつくる仕事をしてきたせいかもしれません。というのも、ゲーム制作とは、それで遊ぶ人の経験(心と体に生じる出来事)をつくる仕事で、制作中は絶えずそのことを考え続けるのでした。とはいえゲームに限らず、文章を書く仕事でも、話す仕事でも似たようなものかもしれません。
*
さて、初回ということもありますので、簡単な自己紹介とこのたびの往復書簡でお話ししてみたいことなどを書いてみます。
自分が何者かを手短かに示さなければならないような場合、もっぱら「文筆家・ゲーム作家」と名乗っています。後者は「ゲームクリエイター」のほうが通りもよいように思いつつ、なんとはなしに「クリエイター」という語を自分について使うことにいささかの違和感もあります。そこで、あまり使われていないかもしれない「ゲーム作家」などという言葉を使っています。
私はこれまで、ゲームをつくる仕事から出発して、後にはものを書く仕事、教える仕事をしてきました。大学を出るとき、なにか仕事をするならと、消去法で選んだのがゲーム制作の仕事でした。ときどき、「研究者になろうとは思わなかったのですか」とお尋ねいただきますが、これははじめから選択肢になかったのです。四半世紀前の自分がなにを考えていたかは、もはやよく覚えていませんけれど、たぶん向いていないと感じたのだろうと思います。あるいは、なにも考えていなかったのかもしれません。
10年ほどゲーム会社に勤めたあとは、またどこかよそのゲーム会社で働こうと思いながら、結果的にはそのときどきの成り行き任せで、ものを書いたり教えたりして今日に至ります。「こうなりたい」という目標があってこうなったというよりは、気がついたらこうなっていた、というのが偽らざるところです。
なにか専門はあるかと言われたら、比較的長く続けているゲームに関わることはそうと言えるかもしれません。ただ、これ一筋というわけではないので、それを専門と言ってよいだろうか、などと思ったりもします。それならいっそ、加藤周一のように「非専門家の専門家になろうと志していた」くらいのことを言えたら恰好もつくのですが、もちろんそんなはずもありません。
ただ、この15、6年にわたって書いてきたものを振り返ると、友人の吉川浩満くんとはじめて書いた『心脳問題――「脳の世紀」を生き抜く』(朝日出版社、2004)以来、そのつどの具体的な対象はともかくとして、なにか学術の歴史に関心を向けているような気がしています。
ここで「学術」とは、学問と技芸術、その元になった英語でならsciences and artsを指します。というのは、日本語とその歴史を、それこそご専門とする今野さんには、釈迦に説法ではありますが、それを気にし始めると、そもそも私は一文ごとにそう断ることになってしまいもしますので、以後は逐一断らずに心のなかで「釈迦に説法ではありますが……」とつぶやくに留めます。学術の歴史は、理想的に言えば、人が文字を使った痕跡がどうやら残っているおよそ五千年前から現在まで、地域や言語を問わず営まれたものとなりましょうか。要するに、地球全体でここ五千年のあいだ営まれてきた学術と呼べそうな営み全体を対象とする、というほどの気分で、この頃はそれを「学術史」と称しております。
申すまでもなく、上記は「理想」でありまして、実際にはそれに取り組む私の能力によっておおいに制限されます。例えば、読める言語は、言語全体からすればごくわずかでしかありませんし、目を通せる文献も、現存する史料のほんの一部に過ぎません。それでもなお、無理を承知で大風呂敷を広げてしまうのは、これもまたゲーム制作の経験があるからかもしれない、と書きながら思いました。
どういうことか。ゲームをつくる際、どんなゲームをつくろうかというアイデアから出発します。このとき、最初のアイデアが100だとすれば、最終的にできあがるゲームは、それ以下になることが多いようです。60も実現すれば御の字です。そうだとすれば、最初のアイデア段階で1000を出しておけばどうか。仮にその30%しか実現できなかったとしても300です。これは100のアイデアから出発するのと比べて、かなり大きなものです。
もっとも、いま述べたのは貧しい経験から考えた理屈であって、実際にはいろいろな場合があろうかと思います。ただ、それでもはじめから小さく限定してしまうよりは、大風呂敷を広げておいたほうが、最終的にできあがるものがよくなるような気がするのでした。ハナから「できっこない」と諦め半分で出発するのではなく、「どこまで行けるか試してみよう」という気分です。
そんなわけで、無謀にも程がありそうですけれど、なんとかして学術の五千年史を捉えてみたいと考えながら、そのつど具体的なテーマに向き合っているのでした。このところ取り組んでいることで言えば、文法の歴史や、科学の文体の変化、音楽批評の歴史などは、その一部というつもりです。
*
少し長々と自分のことを書きました。というのは、日本語の歴史という、これまた長くて大きな対象にとりくんでいらっしゃる今野さんのご関心やお話とつながり重なる糸口を探してのことでもありました。
一口に「日本語」といっても、その歴史は長く、古くから残り伝わってきた書き言葉だけでも厖大な史料があって、それこそ簡単には見通し難いようにも見える対象ですね。こういう対象を、どのように眺めたり検討したりできるか。実際、どんなふうになさってきたか、ということを、この機会に伺ってみたいと思っています。
学術の歴史を検討するにあたって、その最重要の手段である言語を避けては通れません。そんなこともあって、私はいつ頃からか、今野さんのご著書や論文を探し読むようになりました。なかなか年季の入った読者です。『消された漱石――明治の日本語の探し方』(笠間書院、2008)や『振仮名の歴史』(集英社新書、2009)あたりからはじまって、『漢語辞書論攷』(港の人、2011)、『百年前の日本語――書きことばが揺れた時代』(岩波新書、2012)を読むころには、「どうも私はこの今野真二先生という人の書くものを、ともかく全部読んだほうがよさそうだ」と考えるようになっていたと思います。
私はしばしば、そんなふうにして、分野ごとの指南役、あるいは脳内ボードメンバーとでも申しましょうか、そういう存在を設定しているのです。そこで、誠に勝手ながら日本語の歴史については、今野さんの仕事を手がかりにして、参照されているものも含めて辿っていこうと考えたのでした。
そういう場合の常として、手元で今野さんの著作リストを作っています。これまで発表された論文やご著書には、どんなものがあるかを一望しようというわけです。手にして読んだものを中心に、ネットで調べたことも含めて、コンピュータでこしらえています。本については、単著をはじめ、その文庫版や、共著、編著を含めて、私が見落としていなければ、先日刊行された『日本語の教養100』(河出新書、2021)まで、64冊が登録されています。最初のご著書、『仮名表記論攷』(清文堂出版)が2001年ですから、本に限ってみても20年でこれだけのお仕事をされているわけです。
こうしてリストにしてみるといっそうよく分かることがあります。一つはそのお仕事のペースです。かねてから、今野さんは三人くらいいるのではないかと睨んでおりました。なにしろご著書だけを見ても、2009年以降は、毎年5、6冊を出しておられます。もっとも少なかった2012年でも3冊で、一等多かった2014年にいたっては9冊。月刊とまではいかないものの、平均するとほとんど隔月で本が出ている勘定。書店で新著を見かけるたび、「月刊今野先生だ」と冗談交じりに言っていたのですが、これには改めて驚きました。
他にも多作な著者がいないわけではありません。ただ、私が見ている範囲でのことではありますが、多くの場合、途中から自著の二番煎じ、三番煎じ、語り下ろしなどが増えてきて、どれがどの本か区別しがたくなるケースもままあります(そのやり方も、年間七万点以上という厖大な本が刊行され、流れ去ってゆく現在の出版環境を考えると、まったく無意味だとは思いません)。それに対して今野さんの本は、毎回新たな材料や見方を提示しておられるので、読者としては飛ばし読みができず、そのつどじっくり読むことになります。
また、著作リストからは、テーマの広がりも目に入ります。文字資料が残っている範囲で見ても、古代から現代まで、それなりの歴史がある日本語について、室町、戦国時代、江戸、明治から近現代と、広い期間とその変遷を扱っておられる。そして漢字や仮名といった表記、文献、辞書、文学、作文、ことばあそびなど、多様な側面をとりあげています。
加えていえば、ご著書にある『文献から読み解く日本語の歴史――鳥瞰虫瞰』(笠間書院、2005)というタイトルの通りというべきか、鳥の眼と虫の眼の双方から日本語の姿とその歴史的変遷を追跡していらっしゃる。つまり、歴史的な変遷という大きな流れと、個別具体的な文献のあくまで具体的な読解と分析という細部への注意がどの本にも共通しているように見えます。こう言葉にしてしまうとなんだか簡単なようにも思えますが、実際にやるとなるとこれは容易なことではありません。
私の素朴な疑問は、こうです。なにをどうしたら、このように日本語を研究できるのか。あるいは、このような幅と多様な視点で日本語を検討してこられた今野さんには、その歴史と現在はどのように見えているのか。
そして、せっかくの機会でもありますから、もう少しわがままを申せば、これを先ほどの学術史という関心と重ね合わせてみたいと思うのです。学術にはさまざまな側面がありますが、大きく捉えれば、この世界を知ろうとする営みと言えそうです。対象はなんであれ、私たち人間は、経験を通じてなにごとかを感じ、思いつき、考え、試すことから、世界についてなにがしかの知識を得る。また、それを人に伝え、検討し、必要に応じて修正したり置き換えたりするわけです。その際、言語はとても重要な役割を果たしています。ものを考えるにしても、人に伝えるにしても不可欠です。
というわけで、いささか粗雑な話で恐縮ですが、学術やその歴史と言語の関係をめぐって今野さんと、ああでもないこうでもないとお話ししてみたいと思うのです。言い換えれば、この往復書簡が、世界と言語と知識の関係について、鳥の眼、虫の眼、互いの眼で考えてみる場になればいいなと願っています。
随分大きな風呂敷を広げてしまったかもしれません。こんなにあれこれ書いておきながら申しあげるのもなんですけれど、今野さんには、ここに記してきたことに関わるか否かを気になさらず書いていただければ幸いです。
これから、どんなお話になるか、とても楽しみにしています。どうぞよろしくお願い申しあげます。
2021.04.19
山本貴光