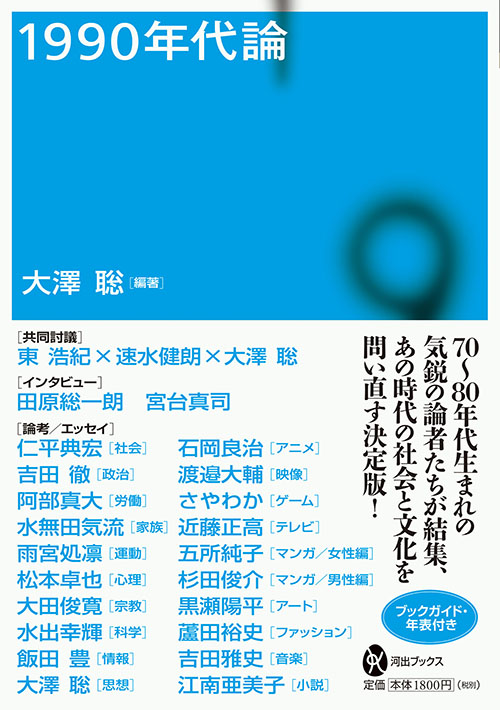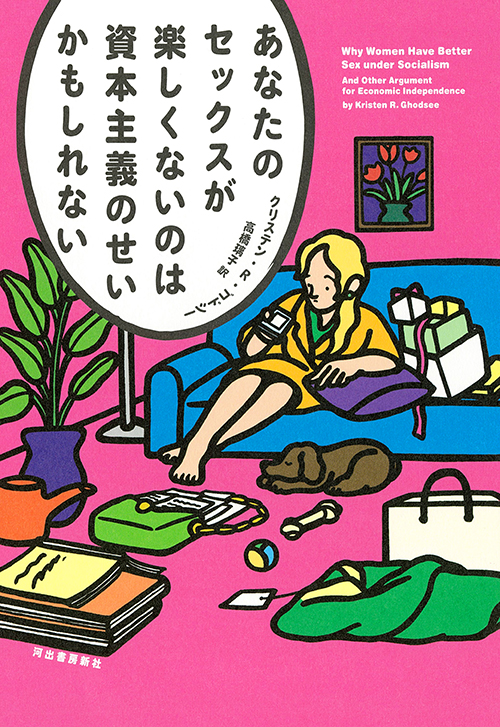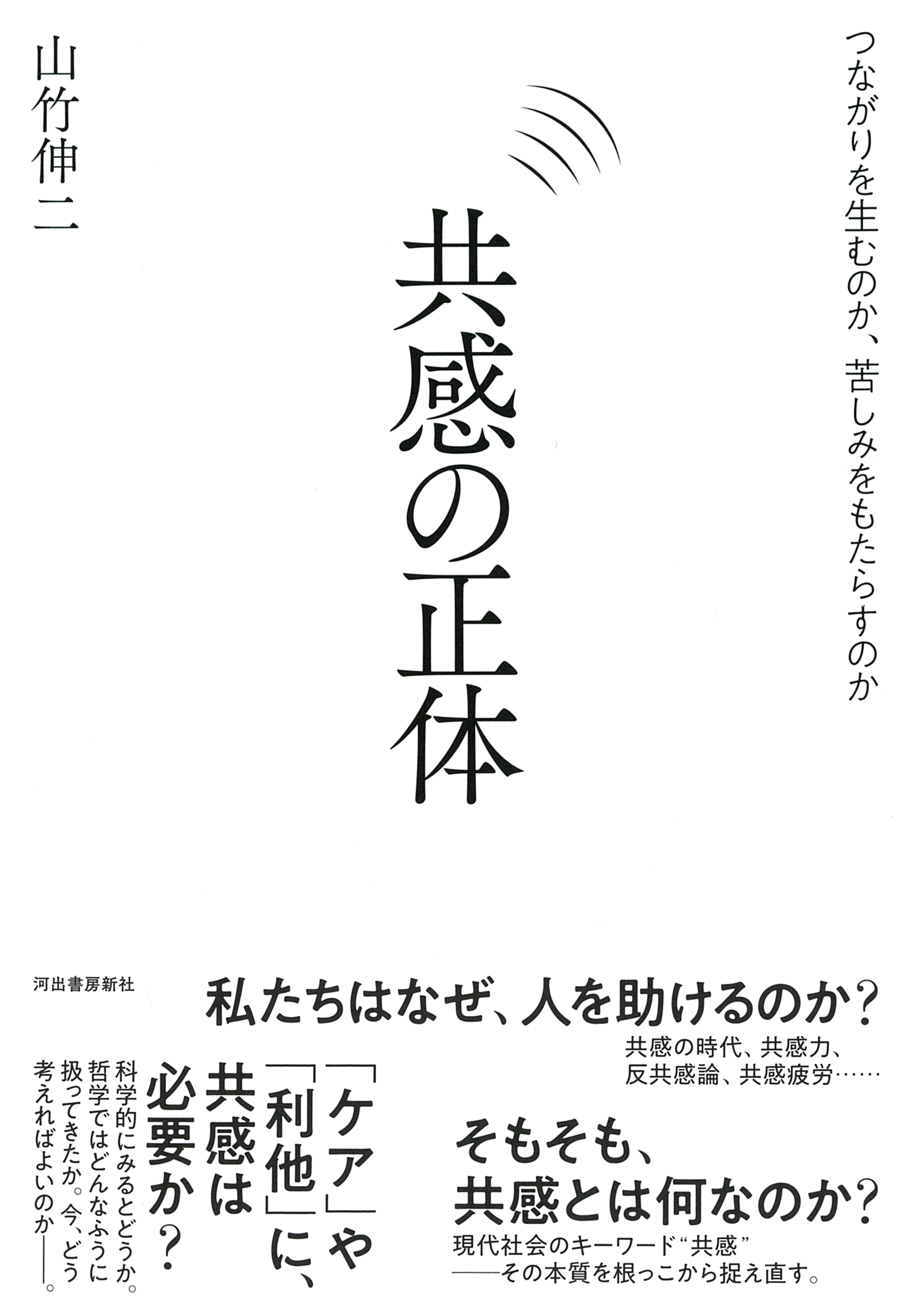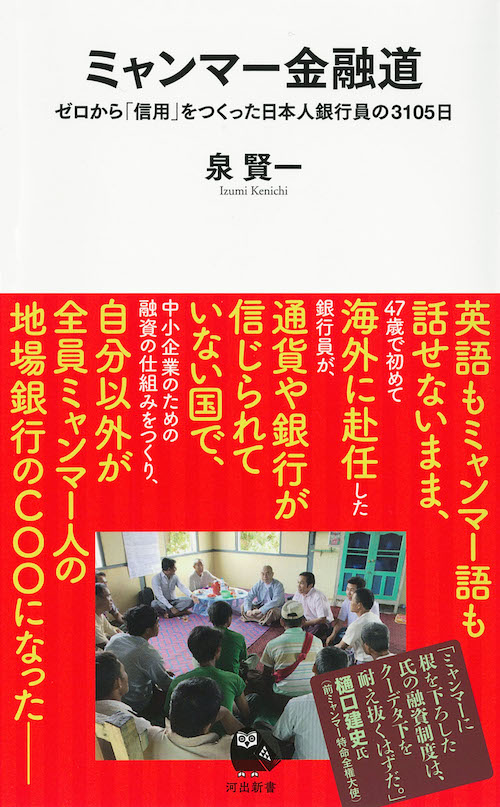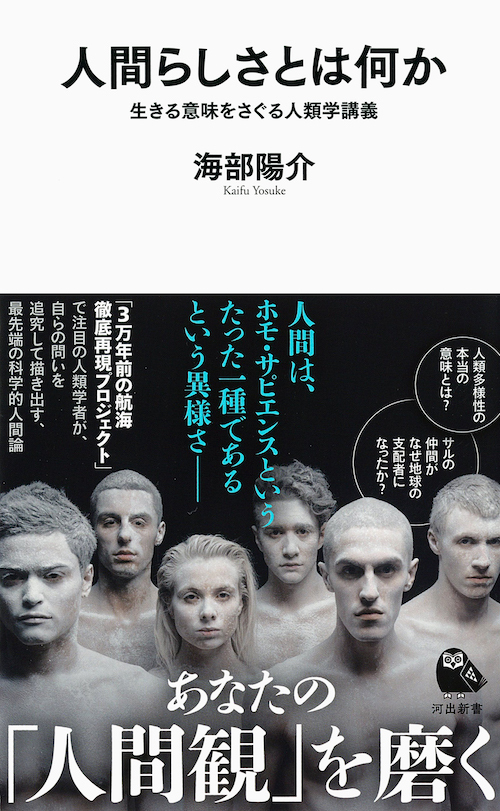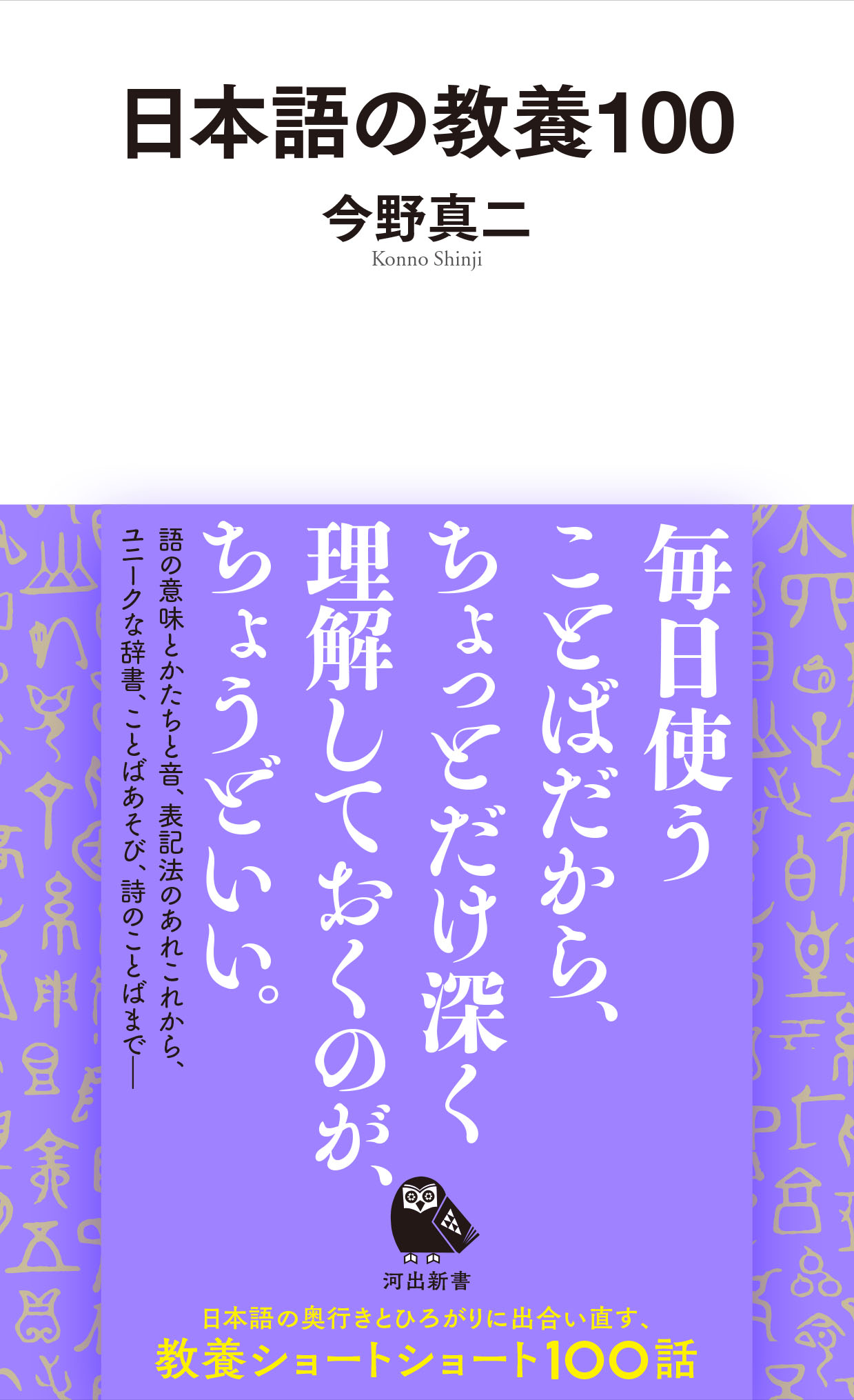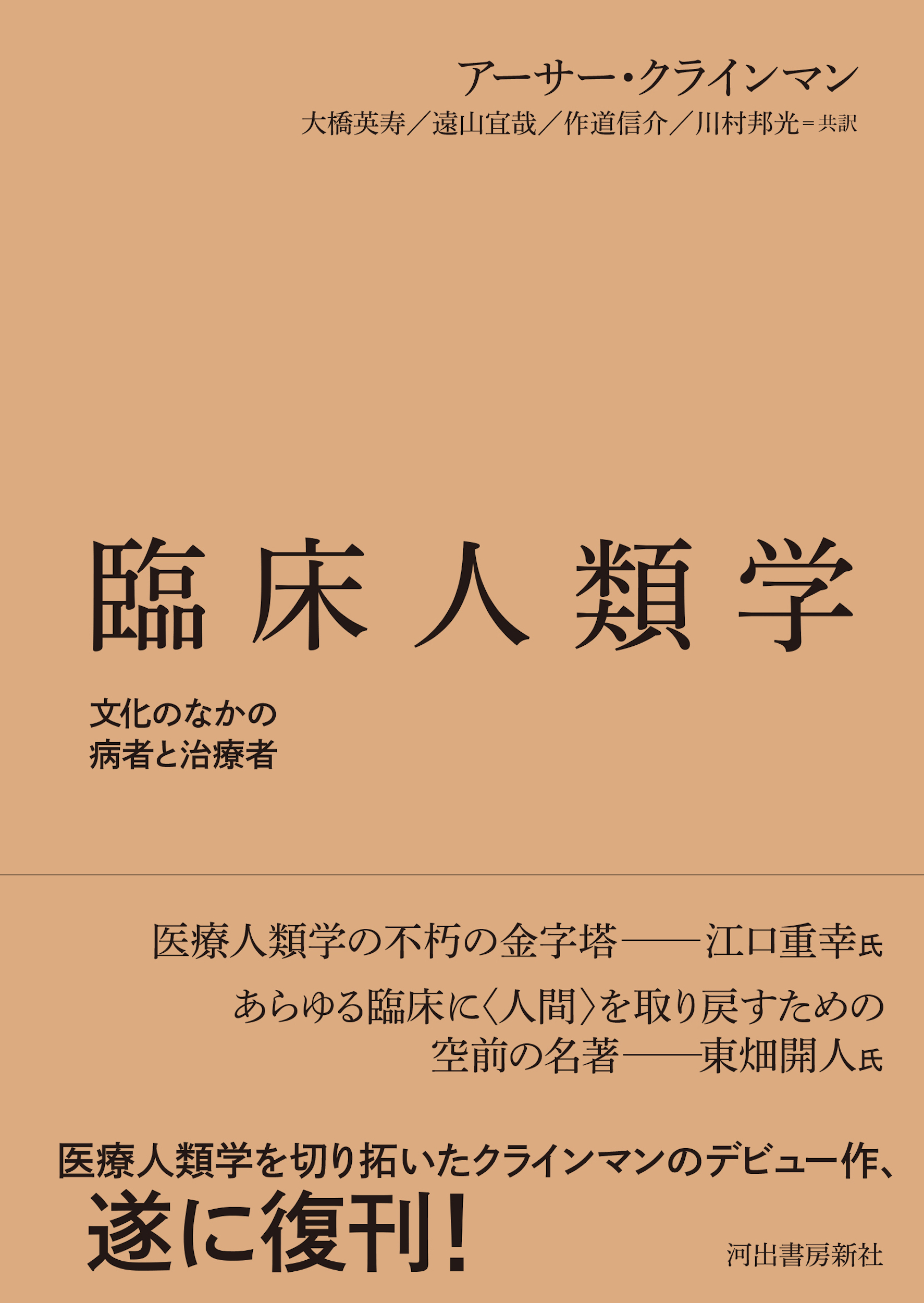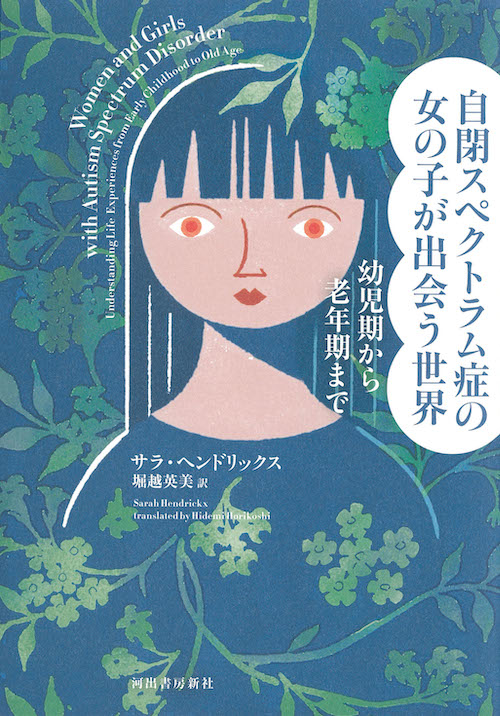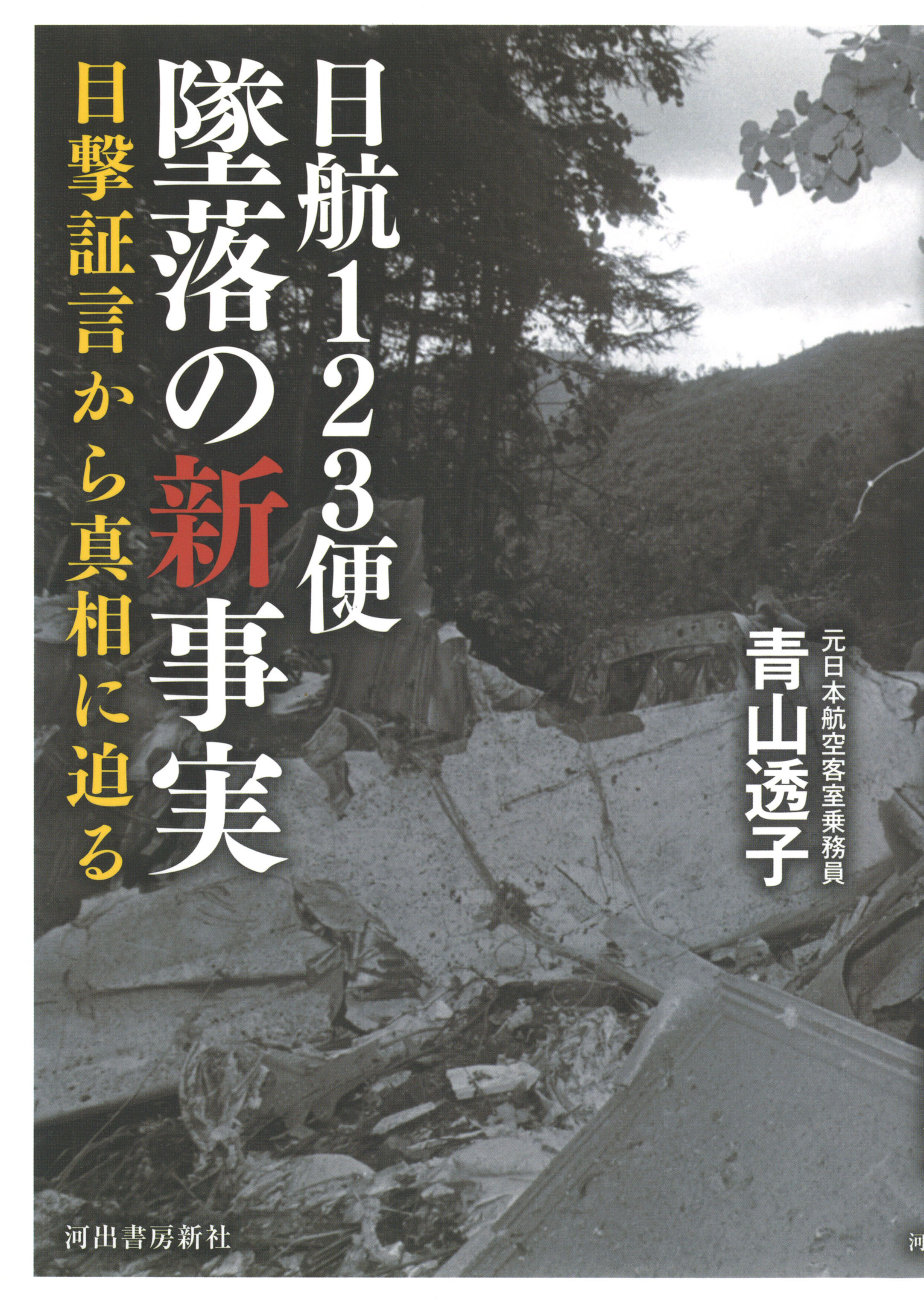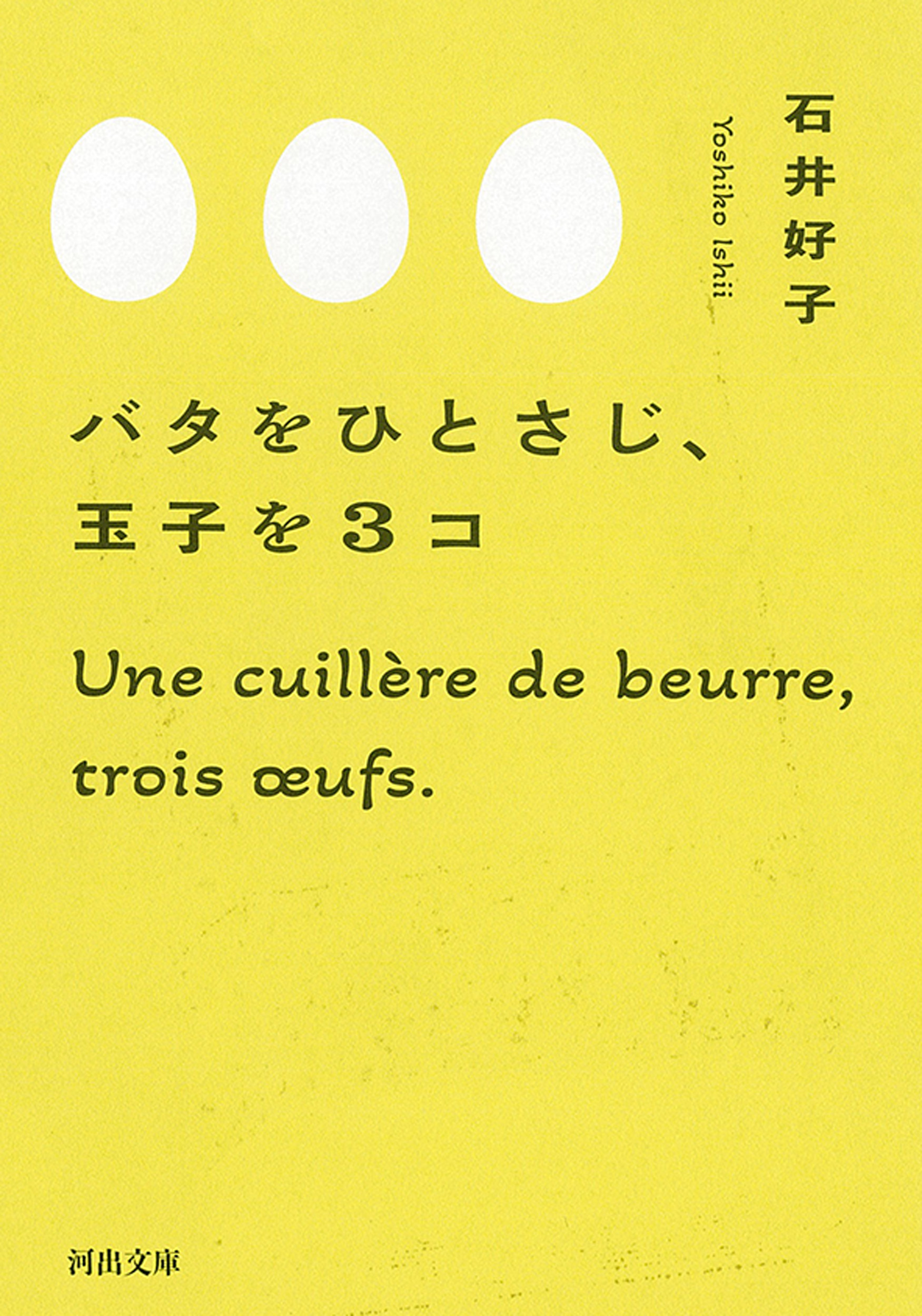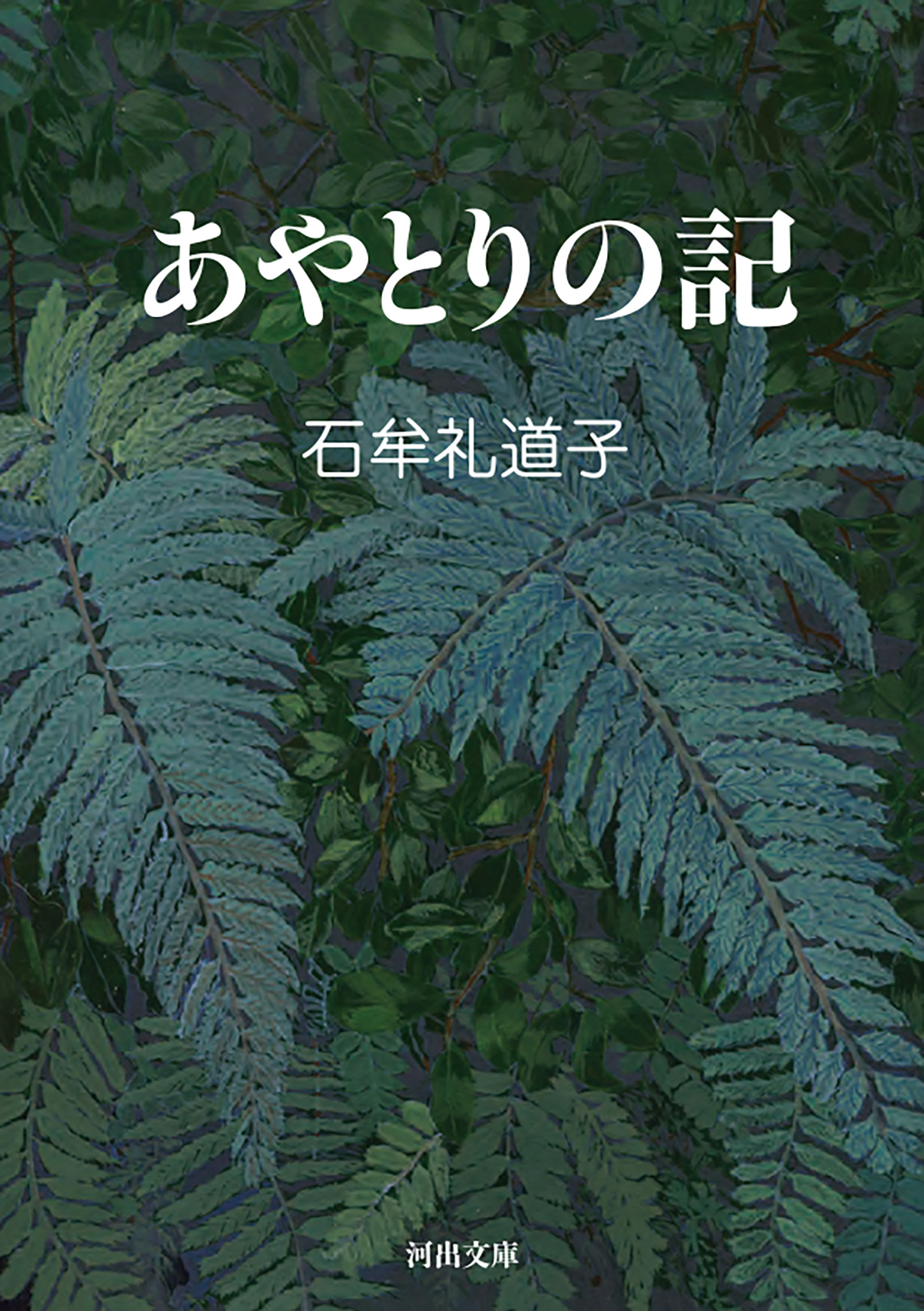単行本 - 人文書
70~80年代生まれの気鋭の論者たちが結集、20のジャンルからあの時代を問い直す――大澤聡[編著]『1990年代論』序文公開!
大澤 聡
2017.08.29
死なない九〇年代の歴史化へ――序文にかえて
大澤 聡
九〇年代の亡霊たちが日本社会を徘徊している。
……どころの話ではない。あの時代に背負わされた社会的なトラウマなり負債なり宿題なりのリストを私たちはいまだに大量にひきずったままだし、なにより当時のキーパーソンのかなりの部分は変わらず現役であり続けている。他方では、あの時代の貯蓄を食いつぶすことでどうにかこうにか延命できているジャンルもあるわけだから、〝九〇年代的なもの〞は私たちの社会や生活のいたるところに塗り込められ、インフラと化したと見るべきなのだろう。
音楽やファッションの世界で言われる「流行の二〇年周期説」を素朴に受け入れるなら、二〇一〇年代は九〇年代リバイバル期に相当していて、リメイクやリサイクルなど、じっさいにその手の事例はことの大小軽重を問わずピックアップしていけばきりがない。親子消費型ビジネスもすっかり定番化した。
けれど、いちどメタとベタとネタの位相の落差がずるずると失効してしまって、それどころか、その無自覚な結託をあられもなく露出して久しいこのコミュニケーション環境からは、個々のリバイバルのポジショニングがもつ意味を正確におさえた批評的な視座は生まれようはずもなく、みんなそれぞれのスケールで思い思いに享受しては安穏なすれちがいを各所で反復している。それが実情だ。九〇年代に起源をもつエビデンス至上主義(〝証拠を出せ!〞)は行くところまで行ったあげく、気づいたときには、自分の信じる(客観的には小さな、けれども脳内では肥大化しきった)物語を補強してくれるデータであればフェイクだろうとなんだろうとかまわず盲信するという壊滅的な事態にまで進展していた。
九〇年代は亡霊化してなどいない。私たちをとりまく条件の大部分はむしろ〝九〇年代的なもの〞によって構成されている……なんて言い出せば、あらゆる年代に適合する汎用的な、つまりおよそ意味をなさない見立てになってしまいそうだけれど、総括されない未決の問題としてこの間、ことあるごとに人びとの脳裡に浮かび続けてきたこともまたたしかなのだ(〝九〇年代とはなんだったのか〞)。九〇年代ノットデッド――二〇〇〇年代半ばに一瞬流通したフレーズを簒奪してそう形容してみてもいい。ただ、そうした問題を問題と識別するためのフレームがどこかに消えてしまった。インフラ化したとはそういうことである。〝九〇年代的なもの〞をあらためて問題として捉えうる視座の奪還。それが本書のミッションだ。
とはいえ、一〇年単位の考察にどれほど正当性があるのかについては見解のわかれるところだろう。じっさい、この国には元号ベースのもうひとつの時期区分が併走していて、そちらも私たちの自画像の変遷を整頓するうえでそれなりの説得力をもつ。しかも、二〇一〇年代に入って(東日本大震災のインパクト以来)、多くの専門領域が一〇〇年単位、一〇〇〇年単位の文明論的な想像力で、世界を捉えかえす必要をうったえてきた。そう考えると、「一九九〇」も誤差含みのただの数字でしかない。しかし、にもかかわらず、というよりもそれゆえに、「予言の自己成就」同様、私たちの行動履歴を確実に規定し続けてきた。では、どのようにして?
本書は一九九〇年代の日本社会を多角的に検討したアンソロジーである。part.A「社会問題編」とpart.B「文化状況編」の二部編成になっている。それぞれに一〇本ずつ批評的な論考/エッセイが配置される。政治や社会、運動、宗教から、マンガやアニメ、ゲーム、音楽にいたるまで、じつに多岐にわたる合計二〇のジャンルの考察を一冊にぎゅっと詰め込み、あたうかぎりのコンパクト化を試みた。巻頭にはノンジャンルの総合的な共同討議を、各パートの締めくくりにはインタビューを掲載してもいる。すべて本書のための書き下ろし&語り下ろしだ。読者の事後の便宜にかんがみ、巻末には年表とブックガイドを付す。
執筆陣の属性は批評家、ライター、研究者、作家とばらばらだ。が、じつは編者を含め一九七〇年代生まれに集中している。厳密には、一九七〇年~八三年生まれ(+九〇年生まれ)で構成される。これは、いわゆる「失われた世代」にそっくり該当する。そして、本書の少なからざる論考は、結果的に、リアルタイムの原体験や感触を陰に陽にそこここに折り挟みながら展開することになるだろう。こうしたシフトそのものが、世代論的な円環のもと、ときとして否定的に解釈されてしまうことは十分に承知している。閉鎖的すぎやしないか、と。けれど、こと今回のミッションに関してはそれでいいという確信が編者のなかにある。サプライヤー(=送り手)側ではなく、ユーザー(=受け手)側にどっぷり身を浸しながら九〇年代を通過したのち社会に出た、そんな人間たちにしかなしえない時代診断と歴史叙述がまちがいなくあるからだ。私たちはまぎれもなく〝九〇年代の子ども〞である。段階的には、「世代論の罠」を過度におそれるべきではないし、おためごかしのバランスをとっても仕方がない。
ただし、世代が近いとはいえ、当然ながら性別から出身地から活動領域からさまざまな分界線が執筆者のあいだには存在する。一枚岩ではありえない。場合によっては、微妙に相反する認識も垣間見えるかもしれない。七〇年代でも前半生まれと後半生まれとでは見てきた光景もまたすこしずつ異なる。にもかかわらず、そして一見無関係に思われる事例を取り扱っていながら、同系の問題をめぐって考察が進んでいることに、はたと気づかされる場面に読者は何度も遭遇するはずだ。
関心のある項目から出発したのち、前後の項目へとページを移動すれば自然とそうしたリンクがたどれるよう配列に仕掛けを施しておいた。もちろん、どんな順にどう読んでもらってもかまわない。本書をとおして、あの時代の総括へと各者の思考がむかうならば、編者としてそれ以上のよろこびはない。近過去を歴史化する作業を経由してはじめて、次の時代のヴィジョンを用意することがようやく可能になる。ただし、その歴史化は対話的に進められることを要求する。願わくは、ここから世代や属性をこえた対話のアリーナが開かれんことを。
(後略)
★『1990年代論』もくじ★
死なない九〇年代の歴史化へ――序文にかえて(大澤 聡)
[共同討議]東 浩紀 × 速水健朗 × 大澤 聡 一九九〇年代日本の諸問題
part.A 社会問題編
A-01[社会] 仁平典宏 終わらざる「社会」の選択――「一九九〇年代」の散乱と回帰
A-02[政治] 吉田 徹 「敵対の政治」と「忖度の政治」の源流――獲得された手段、失われた目的
A-03[労働] 阿部真大 安定からやりがいへ――「やりがい搾取」のタネは九〇年代にまかれた
A-04[家族] 水無田気流 「平凡」と「普通」が乖離した時代
A-05[運動] 雨宮処凛 リスカでバンギャで右翼な青春
A-06[心理] 松本卓也 「ゼロ年代」の序章としての九〇年代の「心理」
A-07[宗教] 大田俊寛 ニューエイジ思想の幻惑と幻滅――私の精神遍歴
A-08[科学] 水出幸輝 震える、あの頃の夢
A-09[情報] 飯田 豊 インターネット前夜――情報化の〈触媒〉としての都市
A-10[思想] 大澤 聡 のっぺりした肯定性――「喪の時代」前夜の理論たち
[インタビューA]田原総一朗 『朝生』の時代 (聞き手 大澤 聡)
part.B 文化状況編
B-01[アニメ] 石岡良治 一九九〇年代アニメ、複数形の記述で
B-02[映像] 渡邉大輔 「ポスト日本映画」の起源としての九〇年代
B-03[ゲーム] さやわか 排除のゲーム史
B-04[テレビ] 近藤正高 フロンティアとしての深夜帯
B-05[マンガ/女性編] 五所純子 「すべての仕事は売春である」に匹敵する一行を思いつかなかった
B-06[マンガ/男性編] 杉田俊介 それから、私たちは「導なき道」を歩いてきたのか
B-07[アート] 黒瀬陽平 九〇年代アートにとって「情報化」とはなんだったのか
B-08[ファッション] 蘆田裕史 情報化するファッションデザイン
B-09[音楽] 吉田雅史 翻訳から仮装へ――「系」をめぐる九〇年代音楽論
B-10[小説] 江南亜美子 九〇年代に花開いた作家たち
[インタビューB]宮台真司 共通前提が崩壊した時代に (聞き手 大澤 聡)
〝90年代特集〟ガイド30――メタ1990年代論(大澤 聡)
年表[1989-2000年]