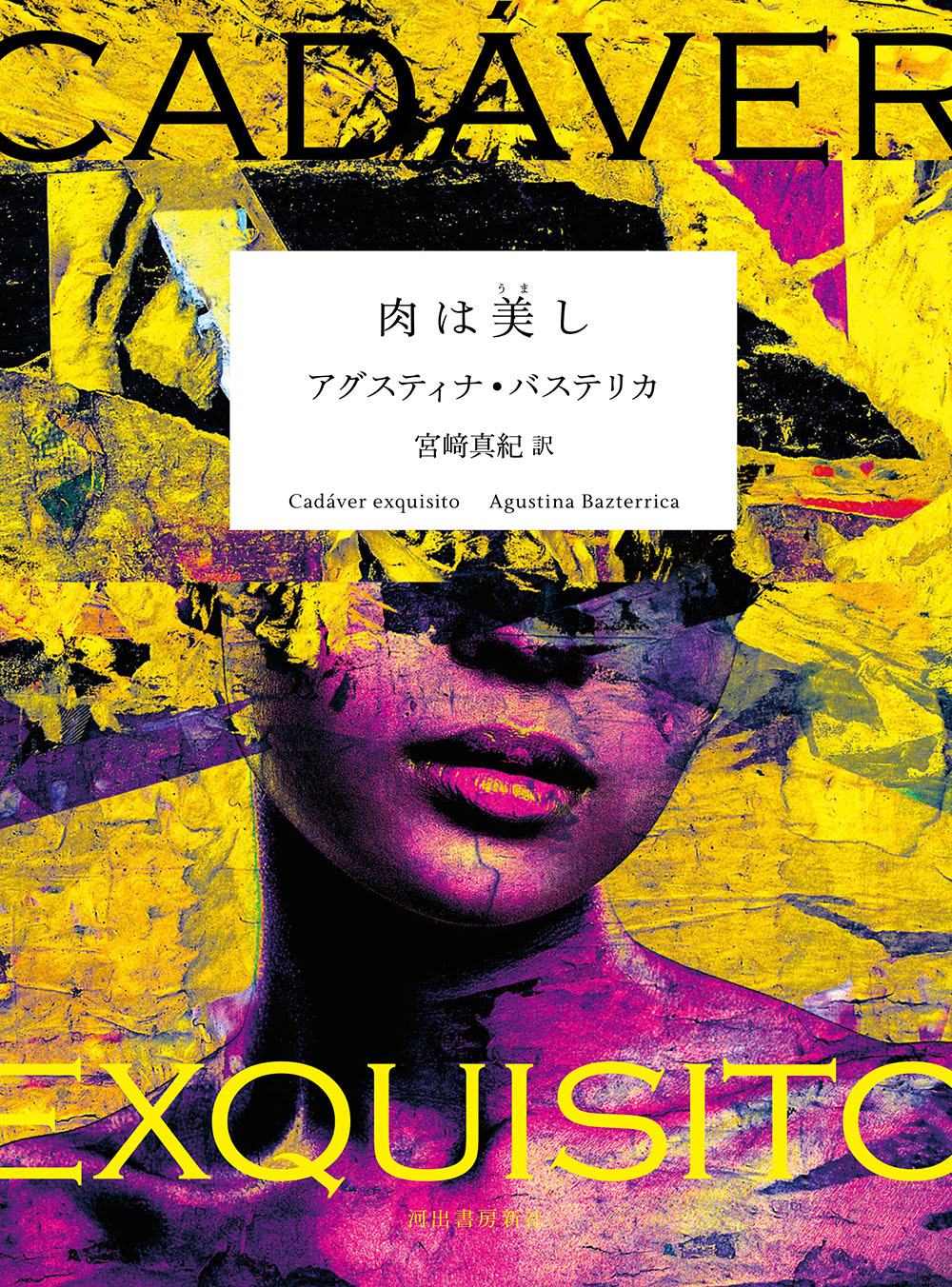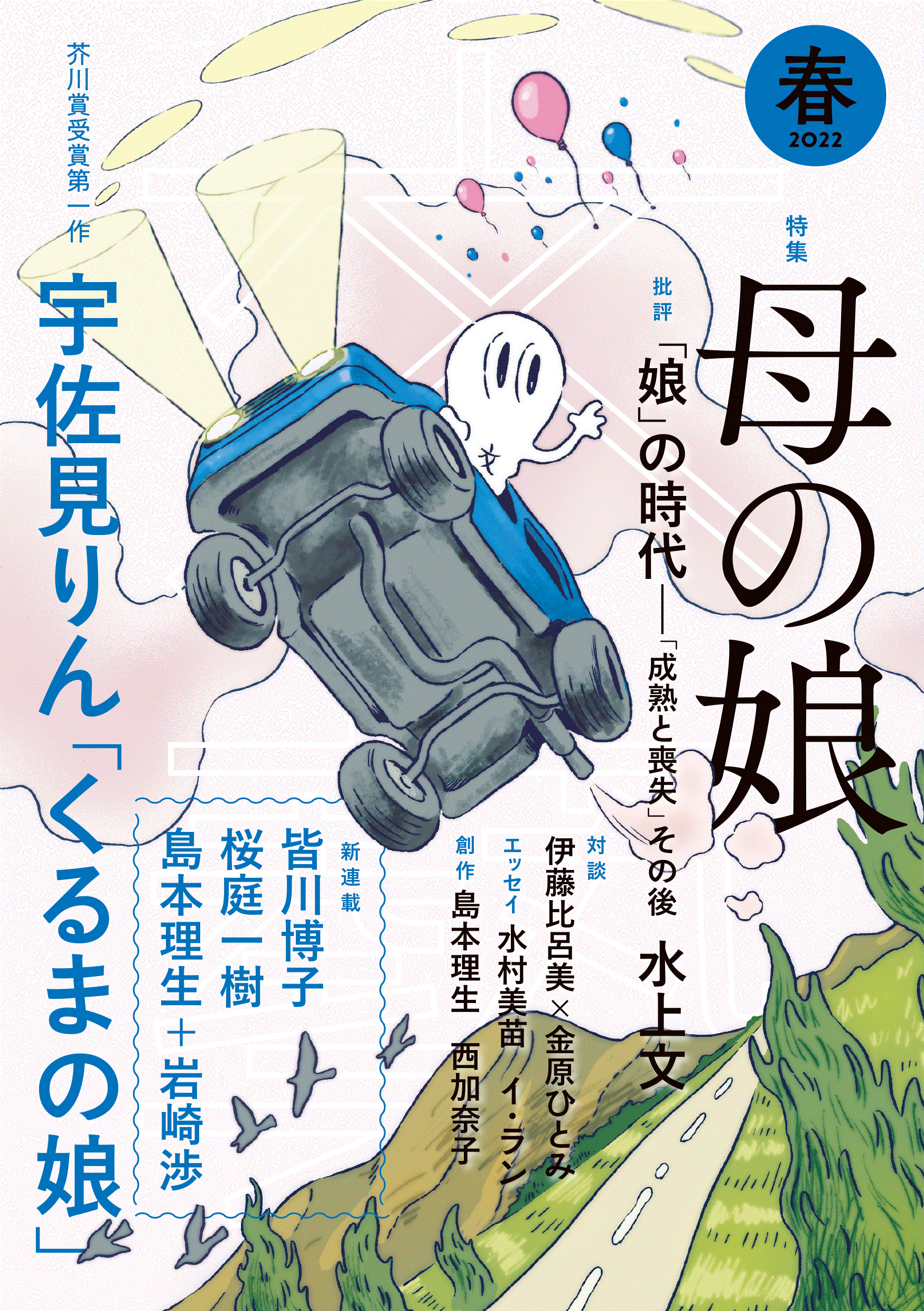単行本 - 文藝
地下鉄サリンから23年──逆さに吊るされた女 田口ランディ『逆さに吊るされた男』書評
レビュアー:吉村萬壱
2018.03.20
逆さに吊るされた女
本作は「私小説」と銘打たれている。地下鉄サリン事件の確定死刑囚Yとの十年を超える交流は、作者である田口ランディに、安全地帯にいて客観的なノンフィクションを書くことも、事実を離れた心地よいフィクションを書くことも許さなかった。それは彼女が田口ランディだったからと言うほかない。それほど本書は徹底した私小説なのである。
オウム真理教とは何の繫がりも持たない作家の羽鳥よう子は、知人の勧めで、彼女の小説のファンだというYに、大島紬を着ていそいそと会いに行く。Yは感じのいい男で、彼女はYと繫がったことで巨大な事件の内側への「通行許可書」を得たことに興奮し、これが運命的な出会いであり、自分には作家としての特別な使命があると感じる。この無邪気さ。しかしこれこそ羽鳥の力でもある。
理屈ではなく感覚で物事を捉える羽鳥は、次第にYと喋ると苛々するようになり、オウム真理教にうさん臭さや恥ずかしさを感じていく。読者は羽鳥のこの感性に期待する。何と言ってもYは八人の犠牲者を出した実行犯なのだ。Yが何を言おうと、彼女は自分の感性を武器に彼の息の根を止めてくれるに違いない。
ところが羽鳥は、期待に反してその後俄然オウム真理教へとのめり込んでいく。そして彼女には全ての事がシンクロし、意味ある出来事として繫がっているように思えてくる。特に元信者の木田智子と知り合ってからの没入度合いは凄い。羽鳥はYが危惧するほどに完全にオウム真理教に取り込まれ、読者の期待は裏切られる。これは一体何なのか。
羽鳥は木田の話を聞きながら「なんてすばらしい。若ければ私も即、入信してしまいそう」と思う。「地獄に落ちてでも、他者を救済しろ 殺してもいい 真に目覚めた者が救済として行うなら それは、救済なのだ」というオウムの教義は、もう殆ど羽鳥の心に食い込みかけているように見える。
ラストで展開するY宛の手紙において、オウムへの接近は「危険なことだとわかっていても、面白いのよ」と羽鳥は告白する。この無防備さは、この作家の性なのだろうか。しかし彼女が「そうなの。私は発病していた」と言う時、読者は、彼女が底の底まで下りて行って全てのオウム信者と同化した後、再びこちら側に戻って来ていたことを知る。その時彼女の手には、一旦オウムに取り込まれて自由を失った人間が口にしてこその、ある言葉が握りしめられていた。
それは実に簡単な言葉だ。
「人間はもっと身勝手でいいのよ」
ここにおいて、オウムという組織、その茶番、その理不尽さに縛られて何一つ身勝手に振る舞えなかったYに対するこの言葉を、他人事として聞ける読者は一人もいないに違いない。我々もまたオウムの信者と変わらないのではないか。そのことを、田口ランディは「発狂」を代償にして摑み取ってきたのである。逆さに吊るされて。私小説でなければ、為しえない技だ。