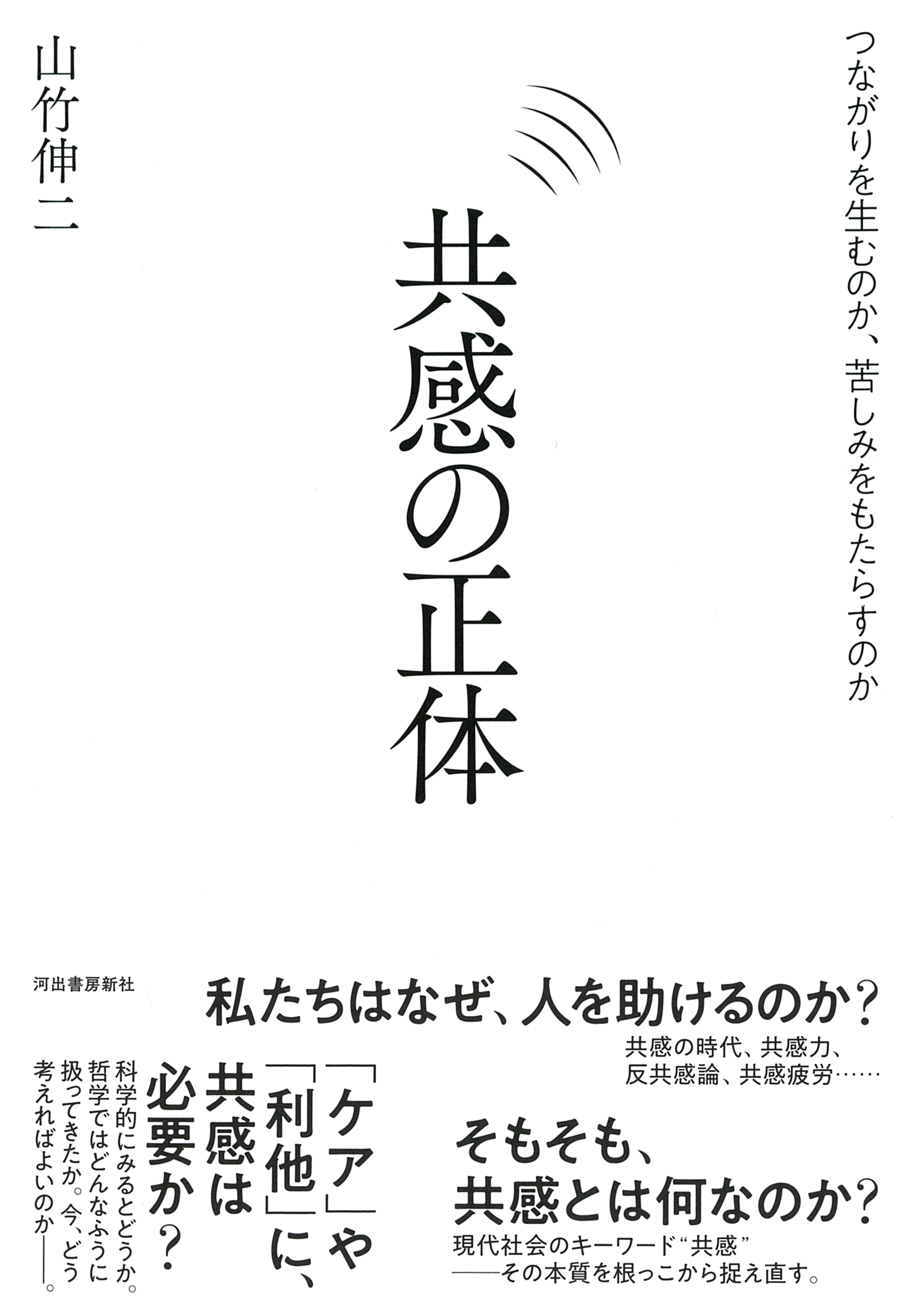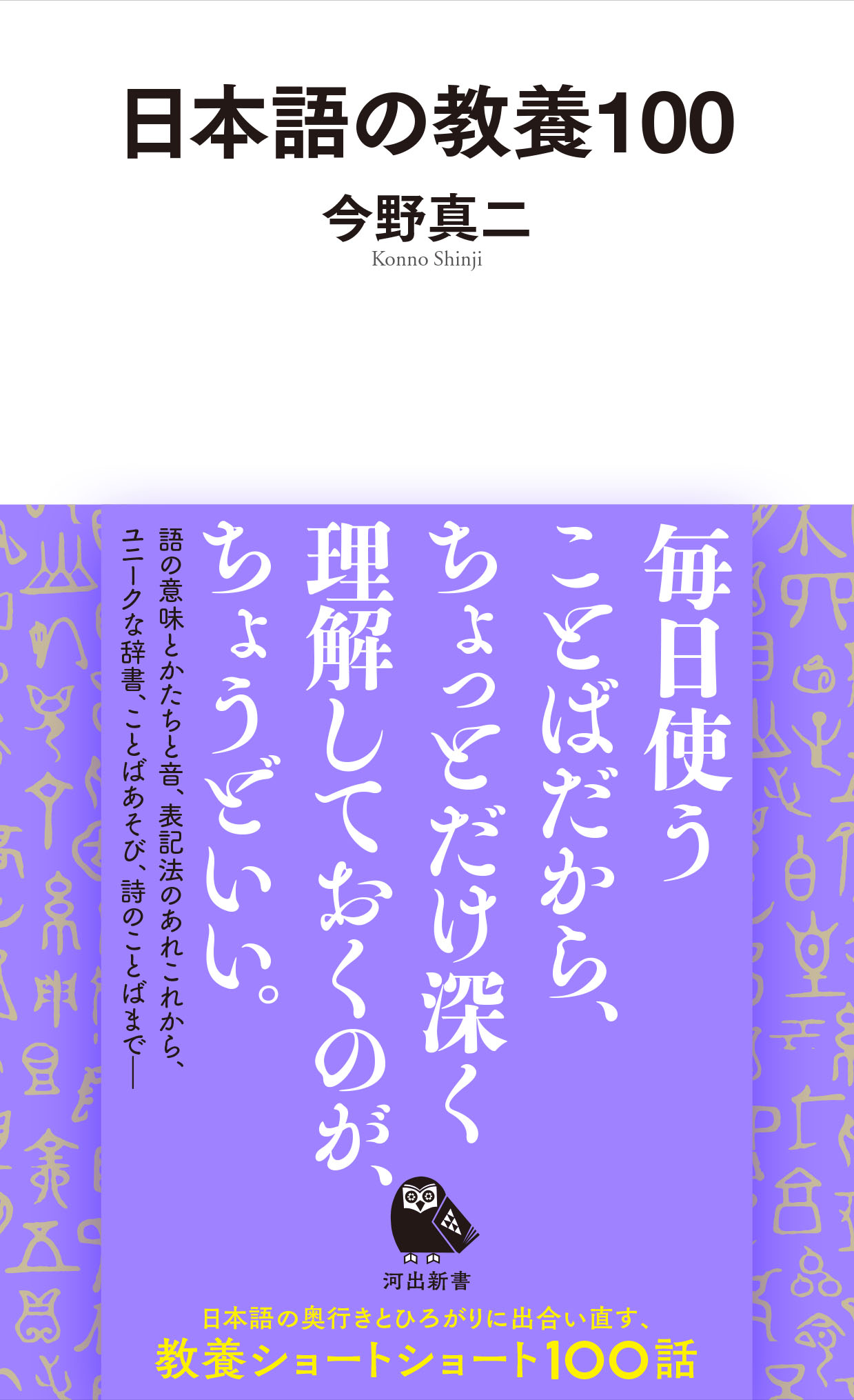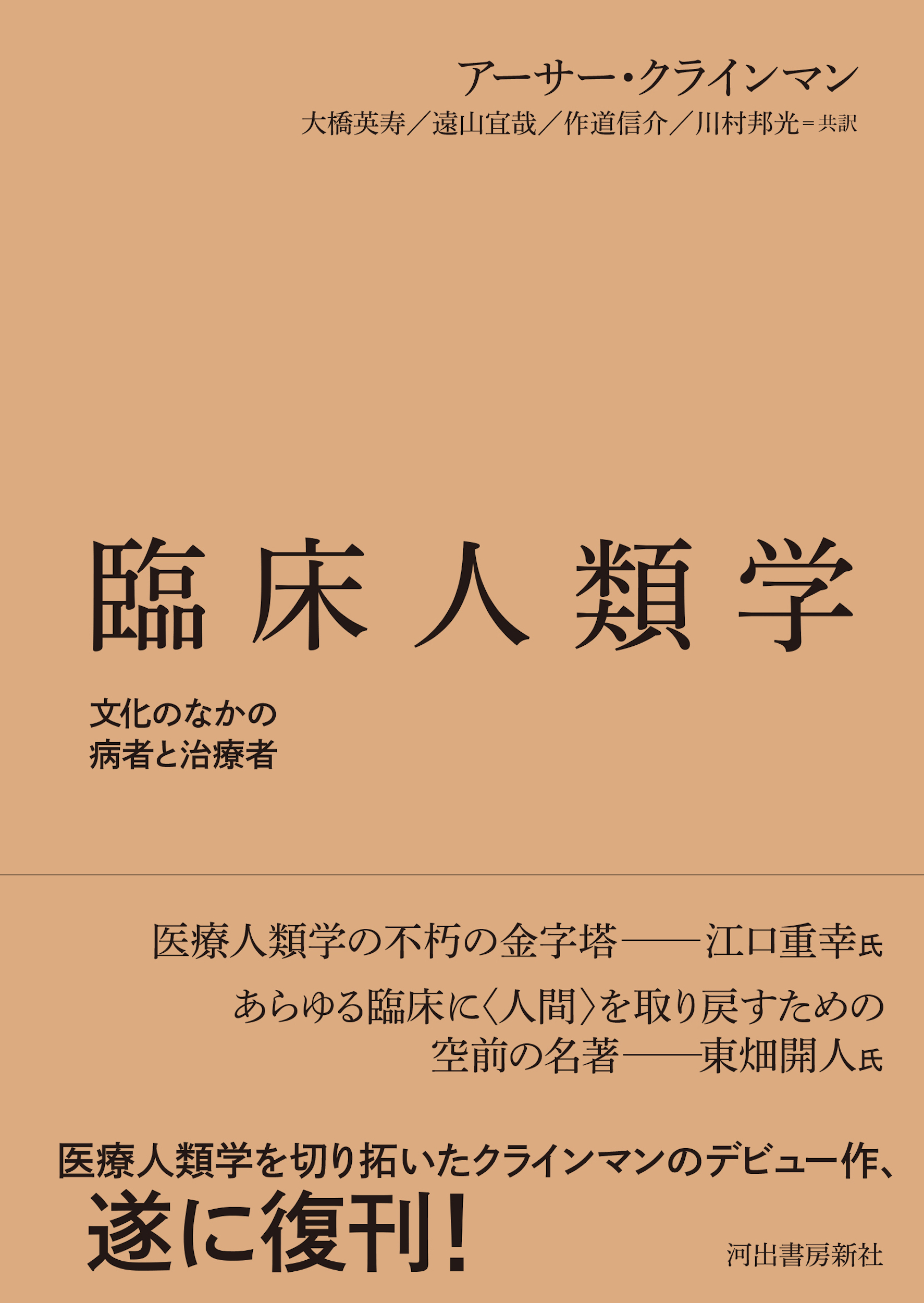単行本 - 人文書
祝重版!河出ブックス『裁判の原点』 著者・大屋雄裕氏インタビュー
2018.07.28

今年1月刊行『裁判の原点』が、発売後6か月で重版となりました。ここで改めて、著者・大屋雄裕氏に、この本の魅力、「裁判について書かれた本」としての新しさについて、お話しいただきます。
—— 発売直後から、新聞・雑誌の書評でも取り上げられ、堅調に売れ続けてきていました。改めて、この本の魅力、「裁判を論じた本」としてどのように新しいものだったのか、伺えればと思います。
大屋: 直接いただく感想もおおむね好評でありがたく思っているのですが、学生からは「なぜ先生が裁判の本を書くのですか」と聞かれたことがあります。どうも法哲学を専門にしている人間が裁判について書くというのには、少々違和感を持つ方もいるようですね。
—— そもそも、「裁判」というのは、どのような分野から論じられることが多いのでしょうか。
大屋: もちろん、裁判法という、まさに裁判を扱う分野の方がまずいらっしゃいます。しかし裁判の本というと多くの方が思い浮かべるのは「裁判というのはこういう手続きを取っているものである」といったことを、民事訴訟法や刑事訴訟法の専門家たちが書いている本ではないでしょうか。
もしくは、法社会学者という人たちが、「社会の中で裁判がどういう機能を占めているか」「日本の裁判制度の特徴は何か」といったことを論じていることを思い浮かべるかもしれない。
あるいは、憲法学者の方たちが論じている、統治機構における司法制度の位置づけ――たとえば政府全体の組織のなかでどう位置付けるかとか、相互関係をどう決めるかなど――について関心を持つ人もいるでしょう。
ただ、これらの分野の研究者たちは、それぞれにそれぞれの思惑というか、前提となる価値観や、興味関心をもっているものです。
—— 一定の前提に立ってしか議論されてこなかったということですか?
大屋: 訴訟法の研究者は、「現状の訴訟手続きは、基本的にそういうものである」というところから始めます。ですから、訴訟を動かしている裁判官のキャリアであるとか、人事統制であるとか、そういう問題には焦点が当たらない。
いっぽう法社会学者は、むしろそういうところを重視します。キャリアパスの数量的分析などをやったり、他の国ではどうなっているかを分析したりはしますが、では「人為的なものとしてどうデザインすべきか」という規範的な議論に、必ずしも関心があるわけではない。
そして、憲法の専門家には統治機構の点から論じることができるはずなのですが、熱心に取り組んでいる方は少ないように見受けられる。というのも、憲法学において多くの関心を集めているのは人権保障なんですね。
ですから、その重要な「人権」を侵害するかもしれない存在として彼らが警戒し重視してきたのは、司法府よりも、立法府と行政府のほうでした。
だからこそ、本書でも言及しましたが憲法訴訟のようなところに関心が向かっており、民事の訴訟において裁判がどういう機能を果たすのかということに強い関心を持ってきた方がたくさんいるわけではない。
裁判をめぐる環境のなかに、こういう意味である種の空白地帯がある。だからこそそれを論じたのが、本書だったと思っています。
—— 空白地帯というのはどういうことでしょうか?
大屋: 野球でいうとポテンヒットが生じる場所というか、いろいろな人の守備範囲を外れているので平凡なフライがアウトにならずに放置されている場所、という感じですね。
裁判に関する「常識」として通用している見解というのがあり、いろいろな人が当たり前のように言及するんだけど本当かどうか実はわからない。あるいは普通の人から見るとなんだかおかしいような気がする。
典型例は、本書第2章でも触れた「日本の裁判所は消極的か?」という問題です。人権訴訟の専門家はたしかにそういう実感を持っていると思うのですが、民法や商法の専門家たちが同意するかは疑問です。あるいは研究者ではない普通の人の方が、素朴に違和感を持っているかもしれません。
なぜそうなるのか? それを考えるには、社会のなかでさまざまな意思決定をしていくという大きな意味での「政治」の機能のなかで、それを分担する司法府・裁判所というものが持つ位置とか、他のシステムとの関係を視野に入れて分析する必要があったと思います。
—— 広い社会のなかにおける裁判の価値については、ほとんど論じられてこなかったということでしょうか?
大屋: 司法政治論といって、広い意味での政治のなかで裁判所という組織が果たしている機能を見ようという研究は登場してきています。
本書でも、政治学の浅羽祐樹先生の研究(「朴正熙時代の法的清算と日韓の新しいゲーム」)や、法社会学・憲法学の見平典先生の研究(『違憲審査制をめぐるポリティクス——現代アメリカ連邦最高裁判所の積極化の背景』)を紹介しました。これはきわめて重要な視点だと思っています。
しかしそれ以外の切り口もある。たとえば従来は政治のエリアだと思われていた国会・議会も、一定の社会的な決定を執行していく組織として広い意味での「行政」の性質を持ちますし、その側面は法的に規律されているわけです。議会法や選挙法という分野が存在するように、政治機構の行政法学的分析も可能でしょう。
同様に司法府も、法によってその意思決定手法や執行手法が規律されている国家機関であるという意味では、広い意味での「行政」的な側面を持ちますし、その考え方に立って分析することができるはずです。
これまでの研究では、国会のことであれば政治学、行政府であれば行政法、裁判所であれば訴訟法といったように切り分けて、問題関心と問題の分析方法を割り当ててきたところがある。
そこから漏れたものがあるのではないか、ということなんですね。全体を通してそれぞれのシステムの相互関係を考えることで、ある程度の見通しを得ることができるのではないか、というのがこの本の主要な動機です。
—— その視点は、実は、研究者ではないけれども、法や裁判に関心を持っている人たちの目線に近かったのかもしれませんね。
大屋: 市民の側から考えると、何かをやっているのが政府のどこかという問題は実はどうでもよくて、全体としての結果が迫ってくるわけですね。
その意味で、その結果に直面している人、たとえば企業で実務を担当している方々の実感と、部分ごとに分析してきた研究とのあいだには、実際にそれなりのズレがあったのではないでしょうか。
そういうズレを感じていた方々にこの本が届いたとすれば嬉しいことだと思います。
—— 先生のご専門である、「法哲学」というジャンルにおいては、この本はどういう位置づけになるのでしょうか。
大屋: これまでも、「訴訟に関するモデル」や、「社会全体の中で法が占める地位について」などのテーマでは、相当の研究がされてきています。
本書でも紹介した田中成明先生は、社会全体が法化するべきだし、そのなかで主要な機能を占めるであろう裁判所を強化するべきだと主張されたわけですね。だから司法制度改革をして、法曹養成の方法も変えることで大量の弁護士を供給して……という考えになられたわけですが、そういった形の先行研究はもちろんあります。
ただ、法哲学者の一人として私がこの本を書いたというのも、少々留保が必要かもしれません。というのも、最近の私の論点が法哲学と一般的にされているものなのかが自分でもよくわからないと言いますか、法的な観点で見ているのかがわからないというか。
—— 社会を分析する際の視点が、法だけではないということでしょうか?
大屋: 法には、社会の内部における人々の動きをコーディネイトする手段という側面があります。しかしこの観点から法を見ると、必ずしも焦点が法に置かれなければならないわけではないし、その手段は法だけではない。
社会全体として見た場合に、ある種の動的なシステムを作っているのか、作ることができるのか? その上で情報化によってどのような変化が起きるのか?
もともと2007年に『自由とは何か』(ちくま新書)を書いた時点から、ローレンス・レッシグを参照していました。法というのは、社会を規制するためのモードの一つであるという彼の立場に非常に親近感を覚えています。
つまり、人々の行動を何らかの意味でコーディネイトしないと、世の中というのはうまくいかない。道路に車を走らせるとして、ある人は右側通行、別の人は左側通行、と勝手に動いていると、もちろん事故が起きるでしょう。何とかしなくてはならない。
しかし、何とかする方法というのは、多様なわけです。道路交通法で取り決めるだけでなく、社会規範としての「常識」として教育することもできるかもしれないし、逆走するとパンクするようなトゲを道路に生やしてもいい。
—— つまり、『裁判の原点』では、社会における法の役割を従来よりも広げて考える視点を投げかけているとも言える。
大屋: レッシグが分析しているのは、法と規範と市場、そしてアーキテクチャです。彼自身も認めているように、重要なのはそれぞれが独立的ではなく、それなりに互換性と相互依存性がある点ですね。
たとえば市場が成り立つためには、所有権というものが保護されていることが普通は必要ですが、これは法的制度でしょう? ここに法と市場の依存関係があると言えます。
もちろん他にもいろいろな関係が考えられる。政治には法を作って人々の動きを変えるという機能がありますが、一定の規範を提示するという役割もある。
訴訟制度を整備したらみんなが使うというものでもないというように、システムに対する人々の反応や別のシステムとの代替関係がありえるという視点を提示した点が、これまでと違うところなのかなとは考えています。
大屋雄裕 (おおや・たけひろ) 1974年生まれ。慶応義塾大学法学部教授。専門は法哲学。著書に『法解釈の言語哲学』(勁草書房)、『自由とは何か』(ちくま新書)、『自由か、さもなくば幸福か』(筑摩選書)、共著に『法哲学と法哲学の対話』『ロボット・AIと法』(ともに有斐閣)など。