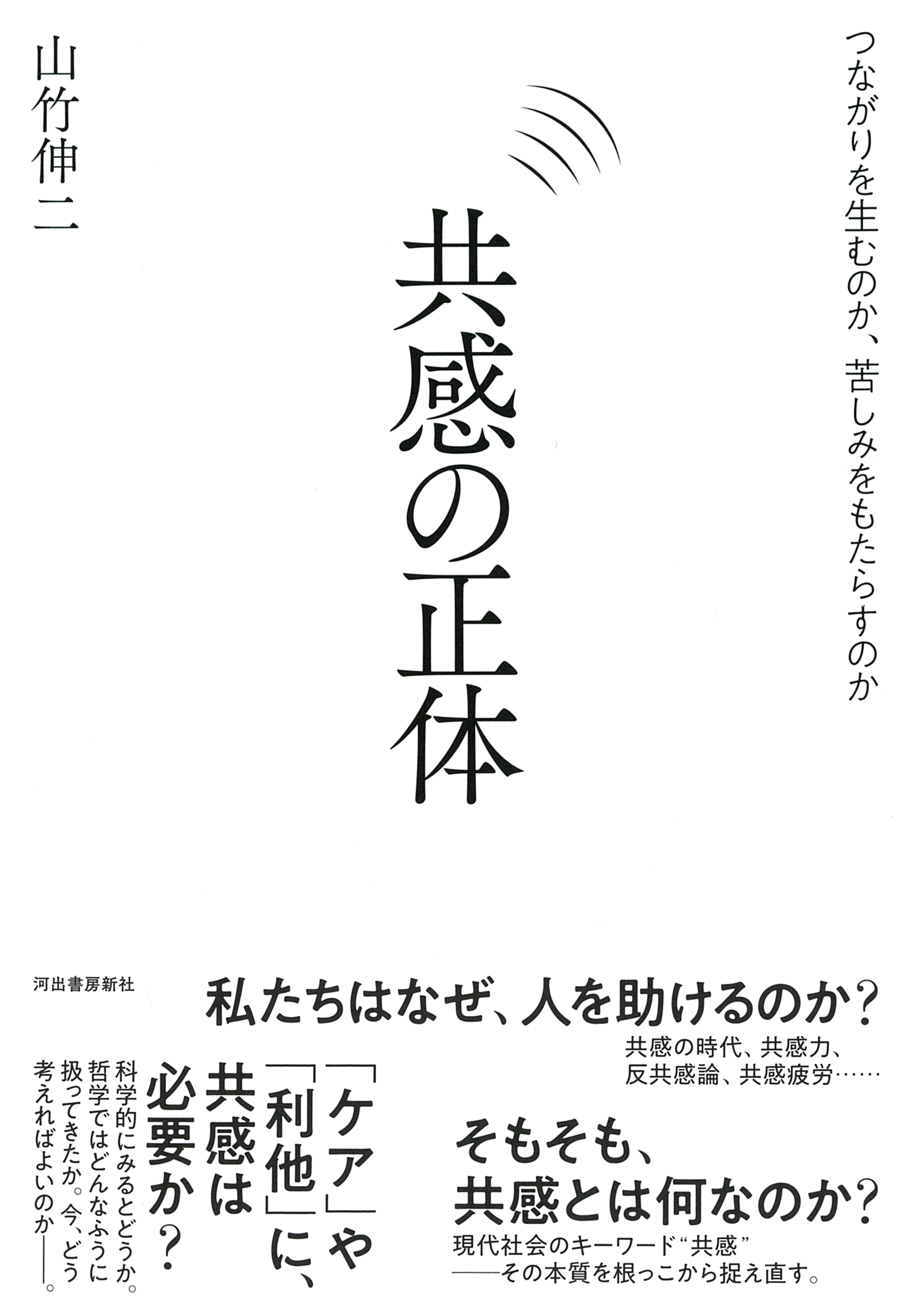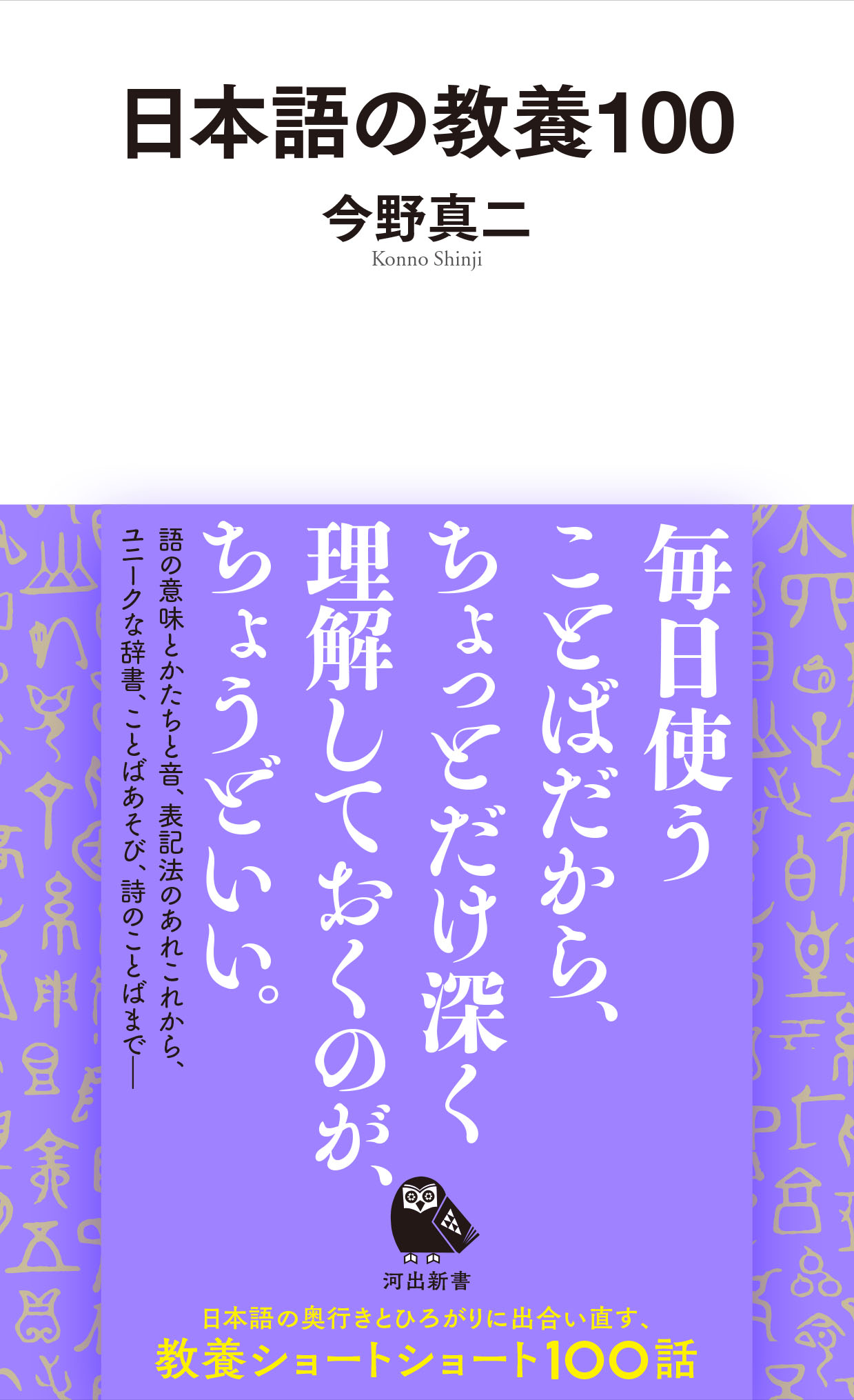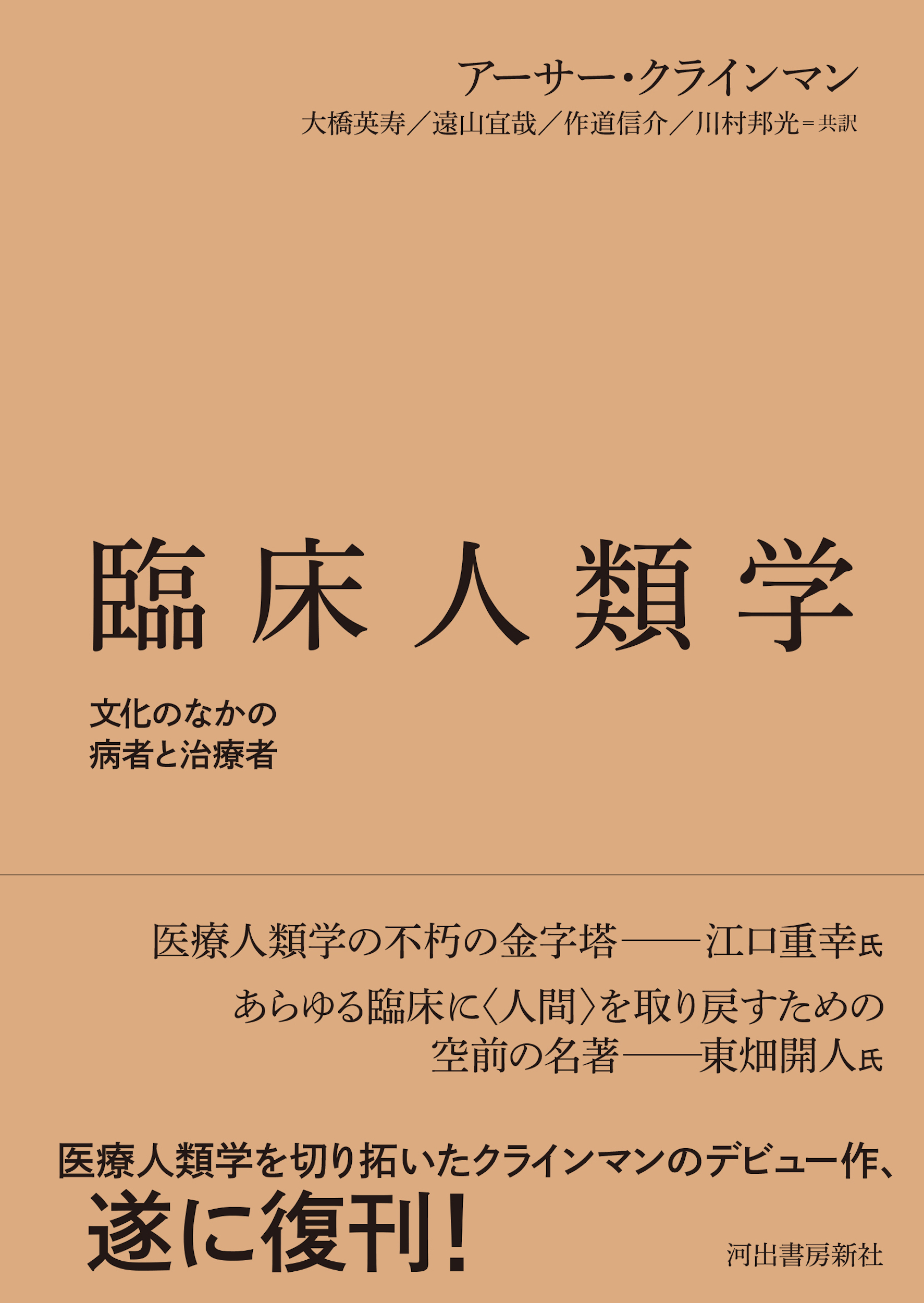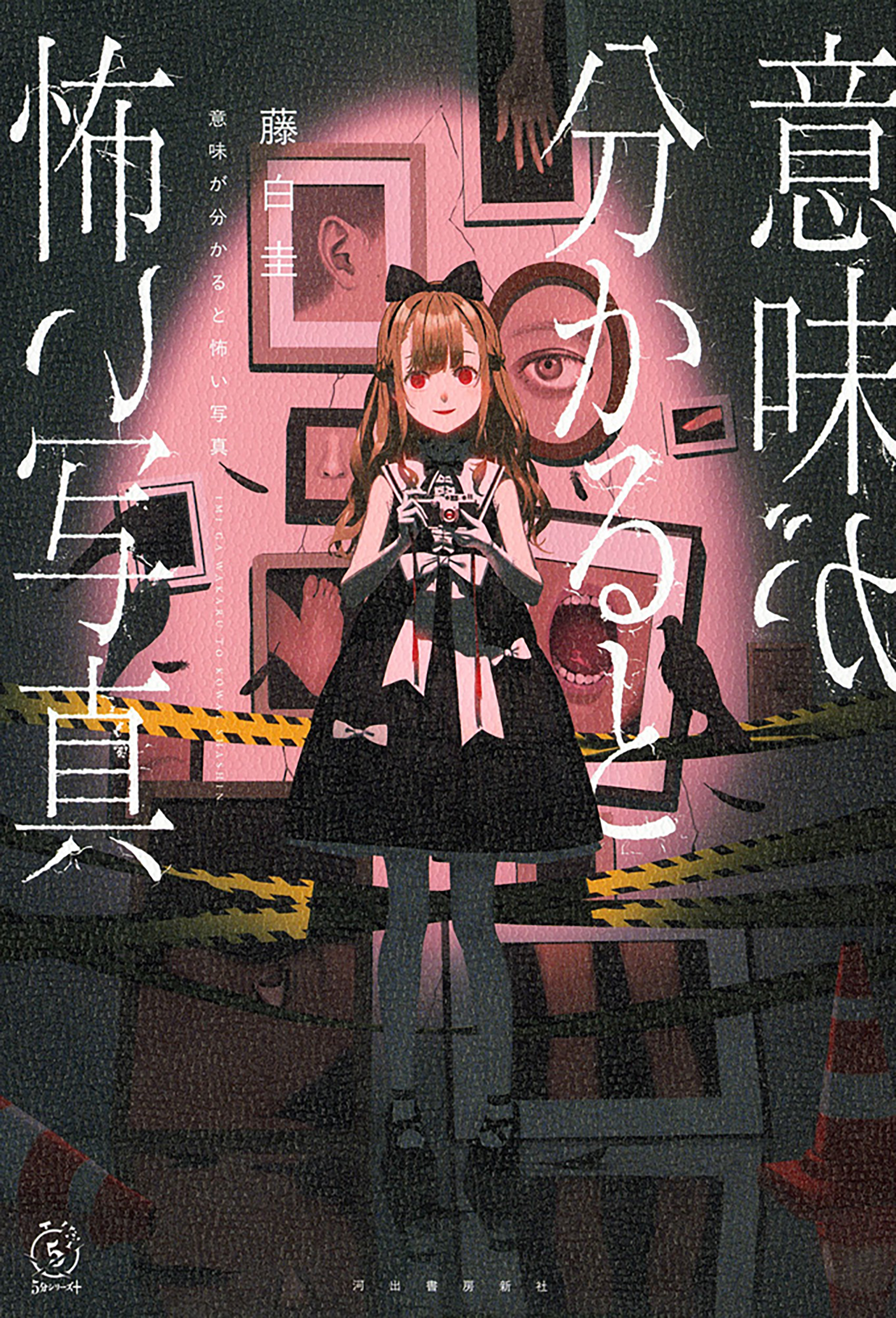単行本 - 人文書
歴史に騙されないための、歴史とのつきあい方――私が『歴史という教養』を書いた理由
片山杜秀
2019.02.15
時事問題から平成史、右翼思想からクラシック音楽まで、幅広い守備範囲を誇る博覧強記の思想史家・片山杜秀さんが、渾身の書き下ろし『歴史という教養』を上梓。なぜいま、改めて歴史とは何かを問う必要があるのか。正解の見えない時代における、ほんとうの教養とは何かーー。この一冊に込めた想いを寄せていただいた。
■日本が沈没するときに……
「何もせん方がええ」。小松左京原作による一九七三年の劇映画『日本沈没』で、新国劇の名優、島田正吾扮する政界の黒幕、渡老人が、丹波哲郎扮する日本国総理大臣に言う台詞です。
渡老人は、日本がごく近々に沈没すると、科学的に確度高く予測されるとき、政府がどのような対応をとるべきか、関西の学者を密かに集めて意見書を作らせ、首相に手渡します。関西の学者とは、イメージとしては、桑原武夫や梅棹忠夫のような人たちでしょう。一九七〇年代前半に、日本の行く末を占う文明論者として大きな影響力を有していた関西の学者というと、そうした方々です。少し経つと、そこにたとえば梅原猛が加わりますけれど。
とにかく、その意見書には「何もしなくていい」という選択肢もありうると述べられている。それを聞いて、丹波哲郎の総理大臣はのけぞってしまう。「何もせん方がええ」という文句をリフレインして絶句する。『日本沈没』の名台詞のひとつであり、役者の芝居としても大きな見せ場です。
「何もせん方がええ」というのは、つまり、下手に考えてもどうしようもないということでしょう。日本が沈むからと、政府が旗を振って日本人を逃がそうとしても、時間的余裕も予算も運搬手段も不足するだろうし、何よりも日本人みんなが安全に移住できる行き先などあろうはずがない。がんばって逃げても、難民化するだけです。
おまけに、日本人は文化的にも言語的にも特殊すぎる。御米を食べて日本列島にかじりついてきた。日本語に近くて学びやすい外国語も無いも同然である。行き場に困る民族なのです。どこに流れても逞しく生きられるタイプではありません。
だから、政府は国民に「日本が沈没する」とは知らせず、対策もせず、外国からそういう報道が出たとしても、「そんなはずはありません、地震や火山噴火や地殻変動が続いても、いつかどこかで収まります」と「日本列島不沈論」の「安全神話」を説いて、国民を騙しておく。それでも心配する人は、勝手に自分の判断で、外国に逃げていくだろう。
もしも日本政府が「沈没する」と宣言したら、国民の安全を守る責任を、民主主義国家として果たさねばいけなくなる。そういう宣言は義務を伴う。しかし、義務は、このケースでは、到底果たされえない。無理筋です。よって「何もせん方がええ」。知ってもどうにもならぬことは、知らない方が身のためだという話ではないでしょうか。
いや、『日本沈没』論をはじめたいわけではありません。「歴史教養書ブーム」をどうとらえたらいいかと考えはじめたら、島田正吾の「何もせん方がええ」という台詞が耳元でなったのです。
■『歴史の終わり』のあとで
歴史は本当に教養になるのだろうか。ここではとりあえず教養を「知識を得ることによって自らの生きる力を養うこと」と定義してみましょう。
だとすると、歴史を知れば知るほど、今の世の中がよく分かり、ひとりひとりが生きやすくなるのなら、「歴史教養書」をどんどん読んだ方がいいとの結論に至るのですが、すんなりそう言えるかというと、私は懐疑の念が先に立ってしまうところがあるのです。もしかして「何も知らん方がええ」のではないか。そんな想念が頭をかすめるのです。
一九九二年、フランシス・フクヤマが『歴史の終わり』という著作を世に問い、日本でもすぐに翻訳され、よく読まれました。フクヤマの言う歴史とは、もちろん、人間の世の日々の積み重ねのことではありません。それがもしもフクヤマの考える歴史だとすれば、歴史が終わるとは、日本沈没ならぬ人類絶滅や地球滅亡を意味することになります。
『歴史の終わり』は『ノストラダムスの大予言』ではないので、そんなことは書いてありません。フクヤマの想定する歴史とは、ヘーゲルやマルクスの用法を前提とした歴史です。「真理をめぐる戦争」が歴史なのだと言えばよいでしょうか。
人間の世の中とは、古代から現代まで、究極の経済的、政治的、社会的な仕組みを求める、大いなる歩みだと考え、その歩みを歴史と呼ぶのが、ヘーゲルやマルクスの流儀でしょう。
その歴史において最後に残ったのは、経済なら、自由競争の資本主義と、結果の平等を求める社会主義。そのどちらが正しいか。政治や言論を巡る空間なら、多様な意見の無限の争いを前提とする議論のある多元的な民主主義と、唯一絶対の真理を認めてみんながそれに従う一元的な民主主義(※ちょっとへんな言い方かもしれませんが、一元化した価値を奉じる党が人民のすべてを代表するといった政治体制は一元的な民主主義としか呼びようがないようにも思います)。そのどちらが正しいか。そういうことになるでしょう。
フクヤマは、一九八〇年代から九〇年代にかけての世界史の過程において、この価値観の闘争についにケリがついたと考えました。特にはソヴィエト連邦の崩壊が社会主義に引導を渡した。資本主義と多元的な民主主義のセットが、社会主義と一元的な民主主義のセットに勝利した。それによって、人類にとっての究極の政治や経済の形態をめぐる闘争史としての歴史は終焉したのだ。そうした理解でしょう。
ケリがまだ付いていない時代には、社会主義と一元的な民主主義のセットの側は、資本主義と多元的な民主主義のセットの側を、歴史の「前史」の段階にとどまっていると主張するのが常でした。
要するに、資本主義や多元的な民主主義は、まだ本当の歴史になっていない。社会主義を実践する正しい歴史としての「本史」に至っていないから、資本主義や多元的な民主主義の歴史は、人間社会にとって「本史未満」の「前史」である。ところが、資本主義の側は「前史」を「前史」として自覚していないで、自分達の今のやり方こそ正解だと思っている。社会主義者の信じる「本史」の側から見れば、無知蒙昧の世界にとどまり、根本的な誤りにすぎない人間観や社会観や世界観にかじりついている。資本主義者は自由主義や相対主義を信じ、それぞれがエゴイステックな立場にこだわって、意見も分裂しっぱなしである。個々人の狭い料簡を丸出しにして倦まない。ああ言えばこう言う。結論なき無限の闘争を繰り広げる。そうして生じる多元的で正解なき民主主義なんて、なんと虚しいものだろうか。「前史」の段階は一刻も早く克服されねばならない。
そういうふうに、究極の進歩を説く社会主義的な側から「前史」と位置付けられた、資本主義や多元的な民主主義の側はというと、人間の歴史には「前史」しかないと思っていたのです。「前史」の矛盾を解決して、ひとつの正解を世の中に徹底して、世界を一元化しおおせて、そこから人類の真の歴史が始まるなんて話は、机上の空論としか感じられなかったのです。
そうした「前史」と「本史」、「一元」と「多元」、二つの立場の緊張関係がさまざまなドラマを作り出していたのが、フクヤマの言う意味で歴史が終わる前の、歴史のありようでした。「歴史の終焉」の前の時代において、歴史を語ることとは、マルクス主義的ないし進歩主義的な枠に歴史をはめて語るか、それとも、その枠を信用しないで、はみだして歴史を語るか、この二つの立場の争いだったのです。
■「正史」が崩壊して自由になった?
ところが、ソ連の崩壊とともに、フクヤマの言う意味で歴史が終焉し、「正史」という大枠が崩れてゆき、「正史」からはみだした語り方がどんどん解放されてゆきました。実は私も、その時代の変化の恩恵を受けてきたひとりであったでしょう。
私は一九八〇年代後半に大学院生でした。日本近代の右翼の思想史をテーマにしていました。すると、そのテーマを批判的に扱うにせよ、幾分肯定的にとらえるにせよ、「正史」の側に立つ人々からは、「前史」の中でも、とりわけ無意味で反動的で百害あって一利なしとも言える右翼の思想などを、なぜにわざわざ積極的に研究する必要があるのかと、あきれ果てられるのが常でした。
ところが、あきれ果てる人たちが、ソ連崩壊を大きな境としていなくなっていきました。あるいは、消えないにしても発言力を弱めてゆきました。
そのおかげで、さまざまな立場から、いろいろな関心から、歴史を掘り下げようという立場の者が大手を振って歩けるようになっていった。自由になった。解放された。時代相は急激に変化した。価値観は多様化した。歴史研究は百花繚乱になった。それはそれでよかった。でも、よいことばかりだったかというと、難しいところです。
資本主義と多元的民主主義の歴史は「前史」に過ぎない。社会主義と一元的民主主義が人類史の本番だ。「正史」だ。この立場は、その善し悪しをとりあえず別にすれば、自分の居場所や羅針盤に間違いは無いという絶対の基準を持っていました。もっと正確に言い直すと、絶対の基準を持っているという自信を有していました。
一方、「正史」の側から「前史」と揶揄されてきた資本主義と多元的民主主義の側はというと、無限の弱肉強食と、ああ言えばこう言う具合の無限の価値対立とに特徴づけられる、相対主義の次元に立って、その居場所を「正史」に対する距離感からだいたい測っていたものでした。要するに絶対の「正史」と相対の「前史」が対立していてこそ、お互いはお互いの、今のポジショニングや力関係を把握できていたのです。
フクヤマが「歴史の終焉」と呼ぶ時代に起きたのは、そうした地勢図の無効化でした。何しろ「正史」が崩壊してしまったのですから。「前史」の側からすると、決してそこに上陸して取り込まれてはならないと警戒し続けていた対岸の大陸が沈没したようなもの。その分、自由気ままにもなったけれど、「正史」という大陸との距離感でしか自らをはかれてこなかったので、アナーキーに漂流するかのようになってしまった。
■それでも歴史と付き合わずにはおれないのだから
そうなっておよそ四半世紀。教養が「知識を得ることによって自らの生きる力を養うこと」だとするならば、「正史」の死の後、パンドラの箱をあけたかのようにひたすら相対主義的に氾濫しまくる歴史知識が、生きるための羅針盤たりうるか、真の教養たりうるかとなると、甚だ心許なく感じられてもくるでしょう。歴史がカオスになっている。そういう言い方をしてもよいかもしれません。
歴史が教養で、教養が「生きる力」だとすれば、歴史は生きるための指針にならなければならない。ところが冷戦構造崩壊後の歴史は、指針というよりはカオスである。「正史」と「前史」の釣り合いがとれなくなって、漂流し続けている。
「正史」が衰弱して、ほとんど死んでしまったので、相対主義だけが生き残り、そういう歴史物語ばかり好き勝手に何十年も享受しているうちに、自分の定位置を、学者も読者も測れなくなってしまう(※相対主義ばかりになれば、座標も流動化するのみですから)。
もっと言うと、歴史知識は漂流しながら断片化し、現実の成り行きに対して機会主義的に、つまみ食い的に、切り貼りされて、現実を合理化するために歴史が捏造される傾向さえ顕著になっている。歴史は、教養というよりも、ついには欺瞞になり詐術になる。
教養を名乗る歴史が実質的には三百代言化してきていないか、ということです。三百代言とは、今日的に言えば、インチキ弁護士であり、御用学者です。目的のためにはわざとウソも言って、依頼人が自らを正当化できる論理を提供する人々です。
もしかして、すっかりそんな時代になっているのではないか。だとすれば、歴史についてなんて「何も知らん方がかえってええ」のかもしれない。しかし、「何もせん方がええ」と聞かされた映画『日本沈没』で、丹波哲郎扮する日本国の首相は、列島の壊滅を前に何もしなかったわけではありませんでした。もしも何もしなかったら、そのあとのストーリーも成り立ちません。日本政府は国民をひとりでも多く海外に逃がすために奮闘するのです。
「何もせん方」がもしかしてよかったのかもしれない。けれど、眼前に日本人が居れば、助けない訳にはゆかない。それが人間なのです。歴史についても同じことです。歴史をどう見るか。われわれはしっかりした物差しを持てない時代に生きている。が、だからといって、「何も知らん方がええ」という訳にはやはりゆかない。人間は時間的存在なのですから。過去を、歴史をふりかえらないわけにはいかないのですから。
どんな困難な時代にも、われわれは歴史と付き合わずにはおれない。ならば、歴史との最低限の付き合い方、せめて歴史を名乗る三百代言の術中にたやすくはまって騙されないようにするような、歴史とのちょっとした交際の手引きが作れないだろうか。『歴史という教養』はそんなつもりから生まれた本です。甚だ至らぬものではありますが。もしもお手に取っていただければ幸甚に存じます。