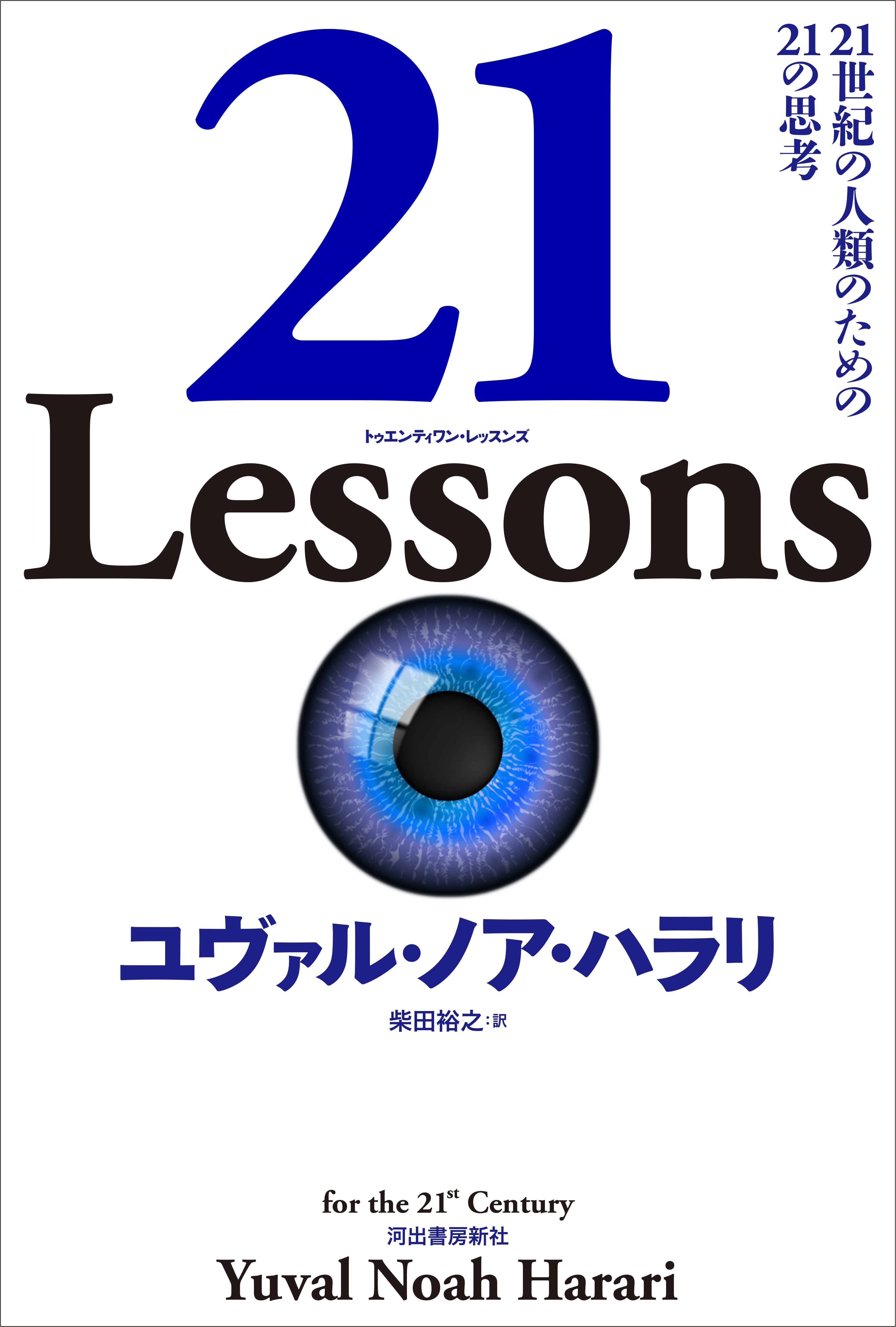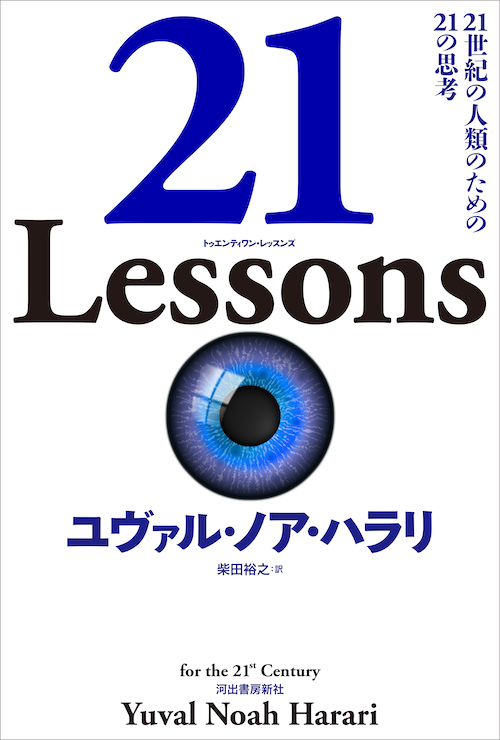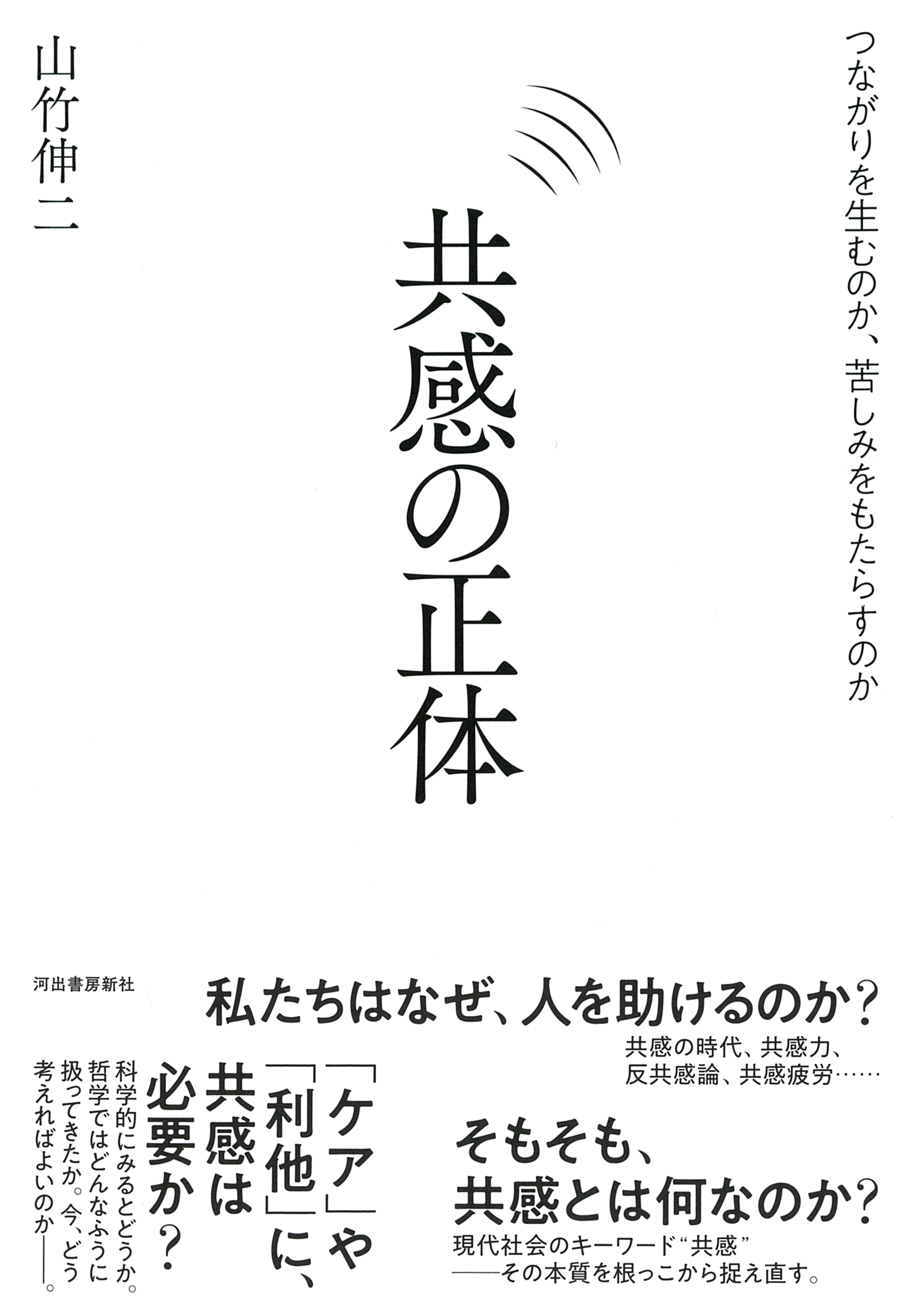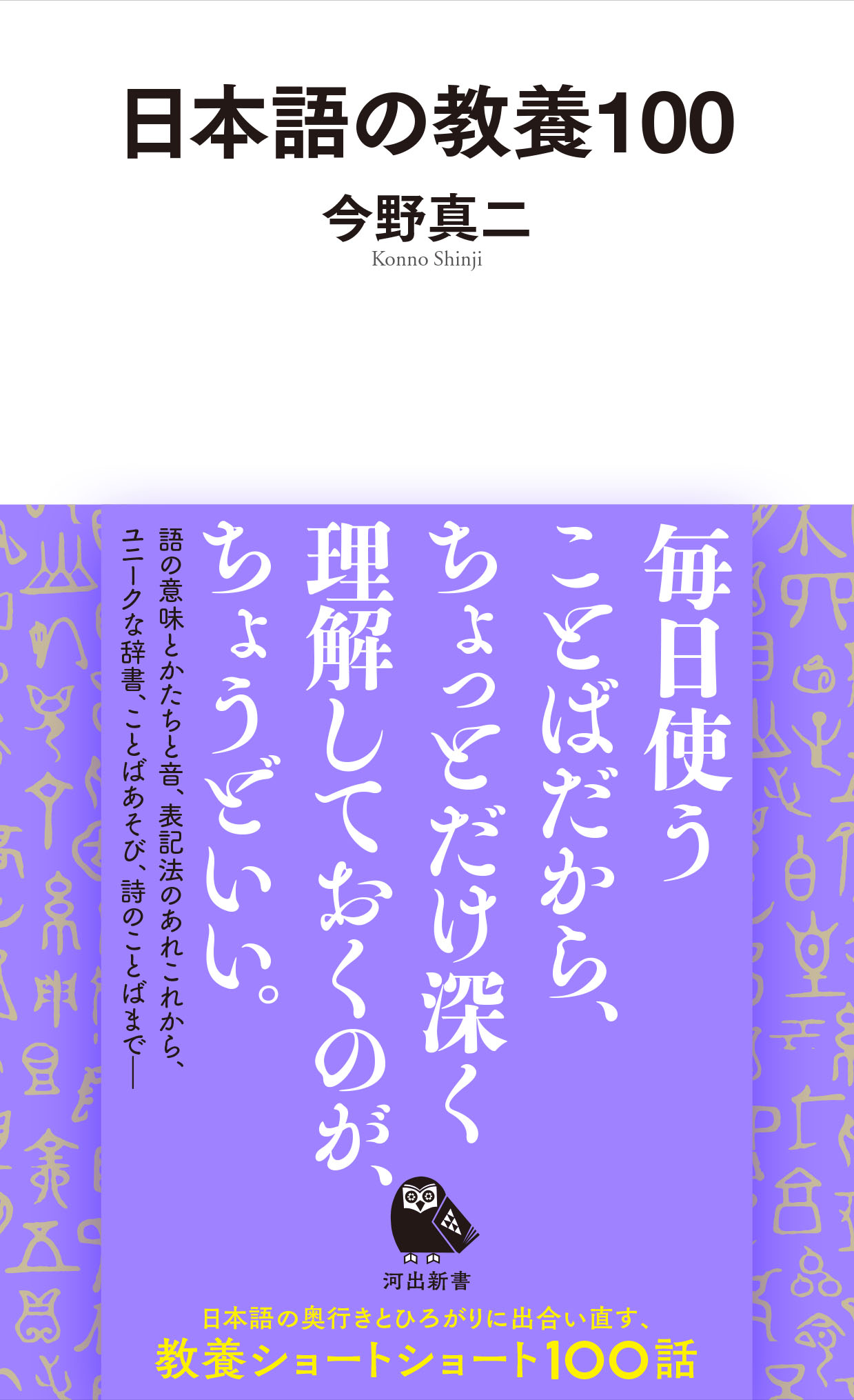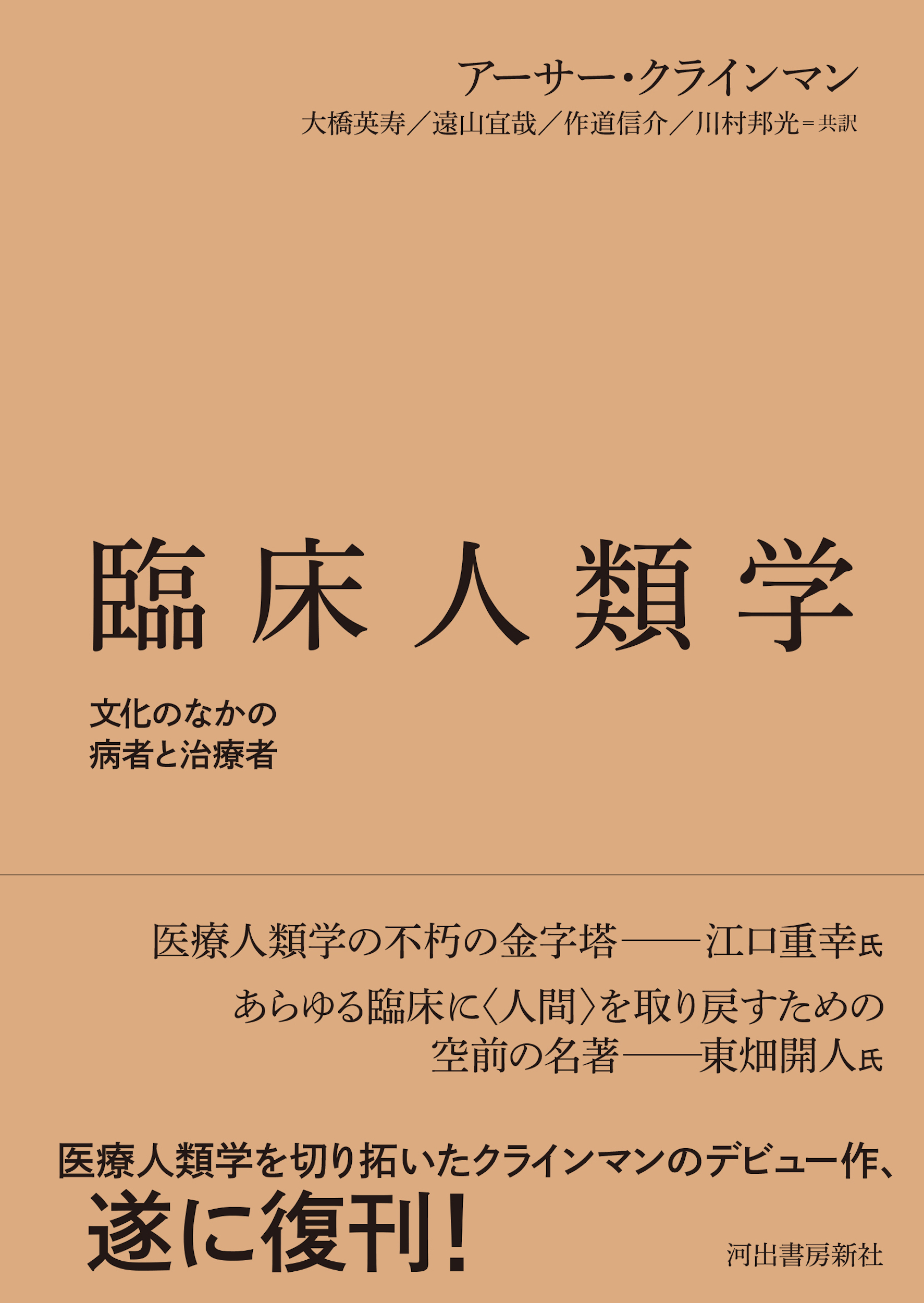単行本 - 人文書
全文公開第三弾! ユヴァル・ノア・ハラリ氏(『サピエンス全史』ほか)が語る、 新型コロナウイルス感染拡大のなかで、 われわれは「死」に対しどう向かい合うべきか。 The Guardian紙記事、全文翻訳を公開。
ユヴァル・ノア・ハラリ
2020.04.28
世界的歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、2020年4月20日付のイギリス有力紙The Guardianに「新型コロナウイルスで、死に対する私たちの態度は変わるだろうか? いや、まったくその逆だ(原題:Will coronavirus change our attitudes to death? Quite the opposite)」と題した記事を寄稿しました。
当社では、ハラリ氏が記した新型コロナウイルスに関する寄稿文「人類はコロナウイルスといかに闘うべきか」(アメリカTIME誌)、「新型コロナウイルス後の世界――この嵐もやがて去る。だが、今行なう選択が、長年に及ぶ変化を私たちの生活にもたらしうる」(イギリスFINANCIAL TIMES紙)に続く、“全文公開第三弾”として、ハラリ氏の著作全てを訳した柴田裕之氏の翻訳による記事全文を特別掲載いたします。
新型コロナウイルスによってあらゆる世界観や価値観が変わろうとしている今、現代における「知の巨人」が“科学・医療の進化による、人間の生と死についての考え方”、“新型コロナウイルス流行後、政府が、そしてわれわれ一人ひとりが取り込むべきこと”を鋭く考察する本稿。是非ご高読下さい。
2020年4月20日「ガーディアン」紙
「新型コロナウイルスで、死に対する私たちの態度は変わるだろうか? 否、じつはその正反対だ」
(原題:Will coronavirus change our attitudes to death? Quite the opposite)
記事全文
ユヴァル・ノア・ハラリ=著
(歴史学者・哲学者。世界的ベストセラー『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』、『21 Lessons』著者)
柴田裕之=訳
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)は、死に対する、より伝統的な態度や、死を受け容れる態度へと私たちを立ち返らせるのか、それとも、寿命を延ばそうとする私たちの試みを後押しするのか?
近代以降の世界を方向づけてきたのは、人間は死を出し抜き、打ち負かせるという信念だ。だがそれは、画期的な態度だった。人間は歴史の大半を通じて、おとなしく死を甘受してきた。近代後期まで、ほとんどの宗教とイデオロギーは、死を避けようのない運命としてばかりか、人生における意味の主要な源泉として捉えてきた。人間の存在にとって最も重要な出来事は、本人が息を引き取った後に起こった。人は死んでから初めて、生にまつわる本当の秘密を知るに至った。そしてようやく永遠の救済を得るか、あるいは果てしない断罪に苦しむことになった。死のない――したがって天国も地獄も生まれ変わりもない――世界では、キリスト教やイスラム教やヒンドゥー教のような宗教は、何の意味もなさなかっただろう。歴史の大半を通じて、最高の頭脳の持ち主たちは、死に意味を与えることにせっせと励み、死を打ち負かそうなどとはしなかった。
ギルガメシュ叙事詩やオルフェウスとエウリュディケの神話、聖書、クルアーン、ヴェーダ、その他無数の聖典や物語は、苦悩する人間たちに辛抱強く説いた。私たちが死ぬのは、神、あるいは宇宙、はたまた母なる自然がそう定めたからであり、その運命を謙虚に潔く受け容れなくてはいけない、と。ことによると、いつの日か神は、キリストを再臨させるといった壮大で超自然的な意思表示の行為を通して、死を廃するかもしれない。だが、そのような大変革を画策することなど、生身の人間の分際ではとうてい望めないのは明らかだった。
ところがそこに、科学革命が起こった。科学者にとって、死は神の定めではなく、たんなる技術的問題にすぎない。人間が死ぬのは神がそう言ったからではなく、何らかの技術的な不具合のせいなのだ。心臓が血液を押し出さなくなったり、癌(がん)が肝臓を冒したり、ウイルスが肺で増殖したりしたためだ。では、こうした技術的問題はみな、何が引き起こすのか? 他の技術的問題だ。心臓が血液を押し出さなくなるのは、心臓の筋肉に十分な酸素が到達しないから。肝臓に癌細胞が拡がるのは、偶然の遺伝子変異が起こったから。ウイルスが私の肺に入り込んだのは、バスで誰かがくしゃみをしたからだ。超自然的なところは何一つない。
そして、どの技術的問題にも技術的解決策があると科学は信じている。死を克服するためにはキリストの再臨を待つ必要はない。科学者たちが研究室でそれをやってのけられる。伝統的には、死は黒い衣をまとった聖職者や神学者の得意分野だったが、今では白衣を着た研究者が彼らに取って代わった。心臓の鼓動が乱れたら、ペースメーカーで刺激を与えられるし、新しい心臓を移植することさえ可能だ。癌が暴れたら、放射線で殺すことができる。ウイルスが肺で急増したら、何か新しい薬で抑え込める。
たしかに現時点では、技術的問題をすべて解決できるわけではない。だが、取り組みは続いている。最高の頭脳の持ち主たちは、もう、死に意味を与えようとして時間を費やすことはない。代わりに、彼らは寿命を延ばすための研究に余念がない。疾患や老化を招く微生物学的・生理学的・遺伝学的システムを詳しく調べ、新薬や革命的な治療法を開発している。
* * *
人間は、寿命を延ばすこの取り組みで、目覚ましい成果をあげてきた。平均寿命は過去200年間に、全世界では40年未満から72年へ、一部の先進国では80年超へと跳ね上がった。とくに、子供たちは死神の魔手から首尾良く逃れた。20世紀までは、彼らの少なくとも3分の1が成人する前に亡くなっていた。赤痢(せきり)や麻疹(ましん)や天然痘(てんねんとう)といった疾患で、彼らは日常的に倒れていた。17世紀のイングランドでは、新生児1000人当たり約150人が最初の1年で亡くなり、15歳まで生き延びられるのはわずか700人ほどだった。今日、誕生後1年以内に亡くなるイギリスの赤ん坊は1000人当たりたった5人で、993人が15歳の誕生日を祝うことができる。世界全体では、小児死亡率は5%を下回るまでになっている。
人間は命を守って寿命を延ばす試みで大成功を収めてきたので、私たちの世界観は根底から変わった。伝統的な宗教が死後の世界こそ意味の主な源泉であると考えていたのに対して、自由主義や社会主義やフェミニズムのように18世紀に生まれたイデオロギーは、死後の世界への関心をすべて失った。共産主義者は死んだらいったいどうなるのか? 資本主義者はどうなるのか? フェミニストはどうなるのか? カール・マルクスやアダム・スミスやシモーヌ・ド・ボーヴォワールの著作の中に答えを探しても無駄だ。
ただし、相変わらず死に対して中心的役割を与えている現代のイデオロギーが一つだけある。ナショナリズムだ。ナショナリズムは情に訴えるときや切羽詰まってきたときには、国のために命を捧げる者は誰でも国民の集合的記憶の中で永遠に生き続けることを約束する。とはいえこの約束はあまりに曖昧なので、ナショナリストでさえその大半が、それをどう捉えればいいのかよくわからない。いったいどうやって記憶の中で「生きる」のか? もし死んでしまったら、人々が自分のことを覚えていてくれるかどうか、どうして知ることができるだろう? かつてウディ・アレンは、映画ファンの記憶の中で永遠に生き続けることを望んでいるかどうか訊かれた。するとアレンは、答えた。「私はむしろ、自分のアパートで生きていたい」と。伝統的な宗教でさえも、その多くが焦点を切り替えた。死んだら天国に行かれると約束する代わりに、現世で信者に対してやれることをはるかに重視するようになったのだ。
今回のパンデミックで、死に対する人間の態度は変わるだろうか? おそらく、変わらない。まったくその逆だ。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のせいで、私たちは人命を守ろうと、なおさら努力するようになる可能性が高い。なぜなら、COVID-19に対して社会が見せる反応として最も目立つのは、諦めではなく、憤慨と期待が入り交じったものだからだ。
中世ヨーロッパのような近代以前の社会で感染症が勃発したときには、人々はもちろん命の危険を感じ、愛する人の死に打ちのめされたが、主な反応は諦めだった。心理学者ならそれを「学習性無力感」と呼ぶかもしれない。人々は、これは神の思(おぼ)し召(め)しだ、あるいは、人類の罪に対する天罰だとでも自分に言い聞かせた。「神はすべて心得ていらっしゃる。私たち邪(よこしま)な人間にはこれが当然の報いなのだ。だから、いずれわかるだろうが、結局は万事最善の結果となる。心配することはない。善良な人々は天国で報われる。それに、薬を探し求めて時間を浪費してはならない。この病は、神が私たちを罰するために見舞われたものなのだ。この伝染を人間が自らの工夫で乗り越えられると考える者は、他の罪にさらに傲慢(ごうまん)の罪を重ねているにすぎない。神の計画を妨げようとは、身の程知らずもはなはだしい」。
今日の受け止め方は正反対だ。列車事故や高層ビルの火災、さらにはハリケーンといった何かの大惨事で大勢の人が亡くなるたびに、私たちはそれを、天罰や避けようのない自然災害ではなく、防ぎえた人災と見る傾向がある。もし鉄道会社が安全対策用の予算を惜しまなければ、また、もし市当局がもっと適切な防火規制を導入していれば、そして、政府がもっと早く救いの手を差し伸べていれば、これらの人は命を落とさずに済んだかもしれないというわけだ。21世紀には、大量死が発生すれば、当然のこととして訴訟と取り調べが後に続くようになった。
疫病(えきびょう)に対しても、私たちは同じ態度を取る。エイズ禍が起こった途端、同性愛者に対する神の罰だとする宗教家もいたが、幸いにも現代社会はそのような見方を狂気の過激思想として斬り捨てたし、昨今ではたいてい、エイズやエボラ出血熱などの近年の感染症の流行を、何らかの組織の失態と考える。そのような疫病を抑え込む知識と手段が人類にはあり、それでも感染症が手に負えなくなるようであれば、私たちはそれを、神の怒りではなく人間の無能のせいと見なす。COVID-19も例外ではない。現在の危機は終息には程遠いが、責任のなすり合いはすでに始まっている。さまざまな国の間で非難の応酬が見られる。政治家は、安全ピンを抜いた手榴弾(しゅりゅうだん)さながら、責任をライバルに放り投げている。
憤慨と並んで、途方もなく大きな期待も見られる。現代のヒーローは、死者を埋葬して惨事の言い訳をする聖職者ではなく、命を救ってくれる医療従事者であり、スーパーヒーローは研究室の科学者だ。映画ファンなら知ってのとおり、スパイダーマンやワンダーウーマンが最後には悪者たちを打ち負かし、世界を救ってくれるのとちょうど同じように、数か月のうちに、いや、1年かかるかもしれないが、研究室の面々がCOVID-19の効果的な治療法ばかりかワクチンさえも生み出してくれると、私たちは信じて疑わない。彼らが成功した暁には、この忌々(いまいま)しい新型コロナウイルスに、この地球上で誰が最強の生き物かを思い知らせてやる! ホワイトハウスからウォール街、さらにははるか彼方のイタリアのバルコニーに至るまで、あらゆる場所で誰もが口にしている疑問は、「いつワクチンができ上がるのか?」だ。いつできるのかであって、できるかどうかではない。
* * *
ワクチンが現に使えるようになり、このパンデミックが終息したときに、人類が引き出すことになる最大の教訓は何だろうか? それは、以下のようなものであることに、ほぼ間違いない。人命を守るためになおさら注力する必要がある。私たちはもっと多くの病院と医師と看護師を必要としている。もっと多くの人工呼吸器や防護服や検査キットの備蓄が欠かせない。未知の病原体を研究し、斬新な治療法を開発するために、もっと多くの資金を投入するべきだ。二度と不意を衝かれることがあってはならない、というわけだ。
これは誤った教訓だ、今回の危機からは謙虚さを学ぶべきだ、と主張する人がいるかもしれない。人間の能力を過信して、自然の力を制圧できるなどと思い上がってはいけない、と。いつも否定的な見方をするこれらの人の多くは、今なお中世の考え方にしがみついており、謙遜を説きながら、自分たちは正しい答えのいっさいを知っていると、絶対の自信を持っている。偏狭な人間のなかには、抑えが利かなくなっている者もいる。たとえば、ドナルド・トランプの閣僚たちのために毎週聖書の勉強会を行なっている牧師は、新型コロナウイルス感染症も同性愛に対する神の罰であると主張した。だが今日では、伝統宗教の権化のような組織や国の大半でさえもが、聖典よりも科学に信頼を置く。カトリック教会は、信徒たちに教会に来ないように指示している。イスラエルは、国内のユダヤ教の会堂を閉鎖した。イラン・イスラム共和国は、国民にモスクを訪れないよう呼びかけている。ありとあらゆる種類の寺院や教派が、公の儀式を中止している。そして、これはすべて、科学者たちが予測を行ない、こうした聖なる場所の閉鎖を推奨したからにほかならない。
当然ながら、人間の傲慢さについて警鐘を鳴らす人がすべて、中世のもののような信仰に戻ることを夢見ているわけではない。私たちは現実的な期待を抱くべきであり、人生におけるどんな災難からも医師の力で守ってもらえるなどと根拠のない思い込みをしてはならないことには、科学者たちでさえ同意するだろう。人類は、全体としては、かつてないほど強力になるだろうが、個々の人間は自らの脆弱(ぜいじゃく)さに向き合う必要があることに変わりはない。1、2世紀のうちに科学のおかげで人間の寿命が無期限に延びないともかぎらないが、それはまだ先のことだ。一握りの億万長者の赤ん坊は例外かもしれないが、今生きている人は全員、いずれ死ぬし、誰もが愛する人を失う。私たちは、自らが束の間の存在であることを認めざるをえない。
人は何世紀にもわたって宗教にすがり、死後も永遠に存在し続けると信じて不安を和らげてきた。今では宗教の代わりに科学を頼り、医師がいつでも救ってくれる、自分のアパートで永遠に生き続けられると信じて不安を軽減しようとすることがある。だが、現在必要とされているのは、バランスの取れたアプローチだ。感染症に対処するにあたっては科学を信頼するべきだが、自分は一時的な存在であり、必ず死ぬという事実に取り組む責務も、依然として担わなくてはならない。
実際、目下の危機のおかげで、人間の命や業績が儚(はかな)いものであるという自覚が深まる人が多いかもしれない。それでもなお、全体として見れば、現代文明がその逆方向に進むことはほぼ確実だ。脆弱さを思い知らされた現代文明は、いっそう守りを固めるという反応を示すだろう。今回の危機が過ぎ去ったとき、大学の哲学科の予算が目立って増えるとは思えない。だが、メディカルスクールや医療制度の予算はきっと大幅に増えるだろう。
そして、それが神ならぬ人間に望みうる最善の展開なのかもしれない。いずれにしても、政府は哲学があまり得意ではない。哲学は政府の任務の埒外(らちがい)だ。だから政府はなんとしても、より良い医療制度を構築することに専念するべきだ。そして、生の意義についてもっと考えるのは、私たち一人ひとりの仕事となる。医師は私たちのために、人間の存在にまつわる哲学的な謎を解き明かすことはできない。だが彼らは、私たちがそれに取り組むための時間を、あと少しばかり稼ぐことはできる。その時間で何をするかは、私たち次第なのだ。
ユヴァル・ノア・ハラリ
1976年イスラエル生まれの歴史学者、哲学者。2014年『サピエンス全史』の世界的ヒットにより一躍時代の寵児となる。2016年の『ホモ・デウス』では衝撃の未来予想図で世界を震撼させた。最新作『21 Lessons』では現代世界を鋭く読み解き、人類を力強く鼓舞する。
出典・初出
Will coronavirus change our attitudes to death? Quite the opposite, First published in English in The Guardian on 20 April 2020.
(https://www.theguardian.com/books/2020/apr/20/yuval-noah-harari-will-coronavirus-change-our-attitudes-to-death-quite-the-opposite)
© Yuval Noah Harari 2020