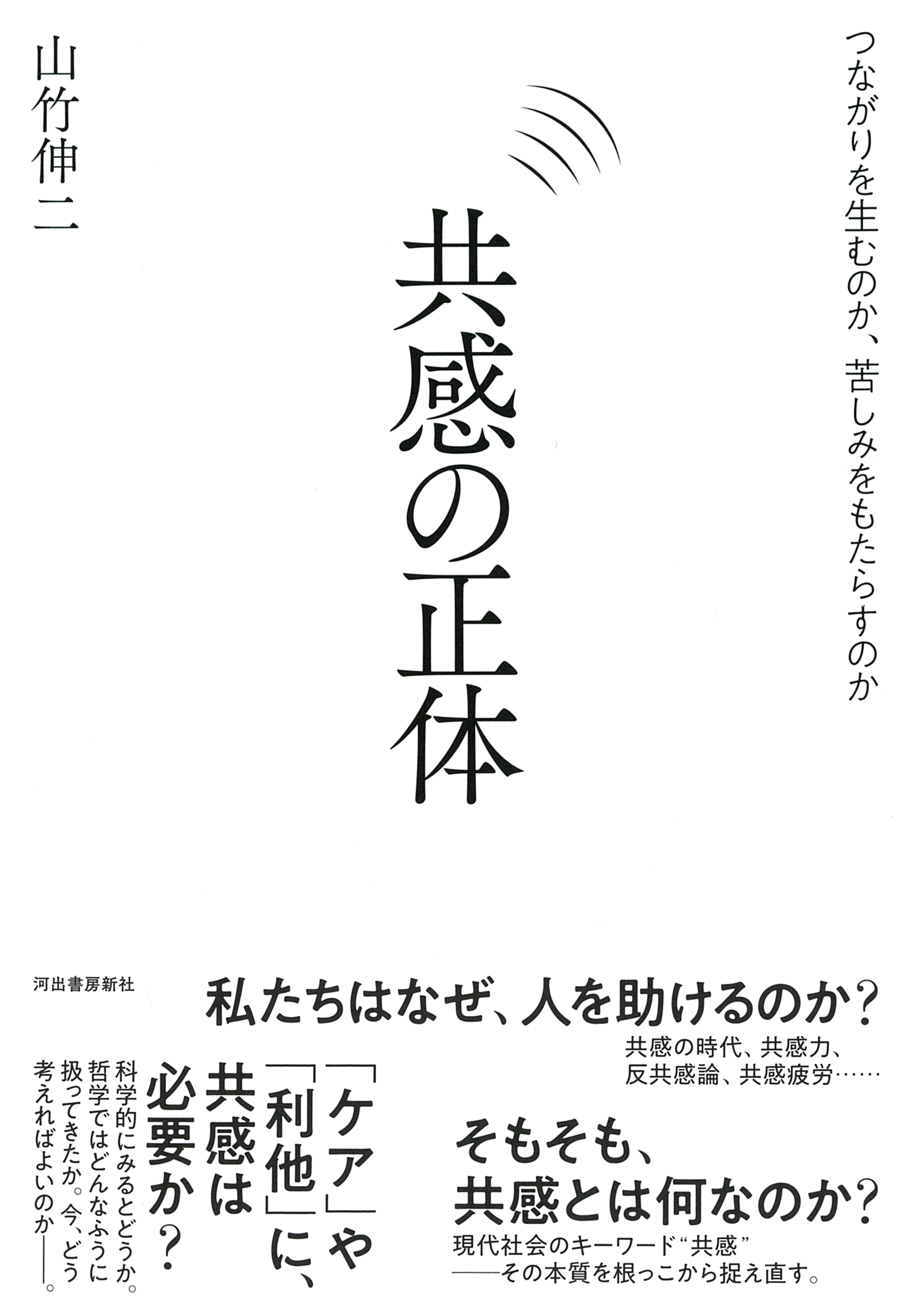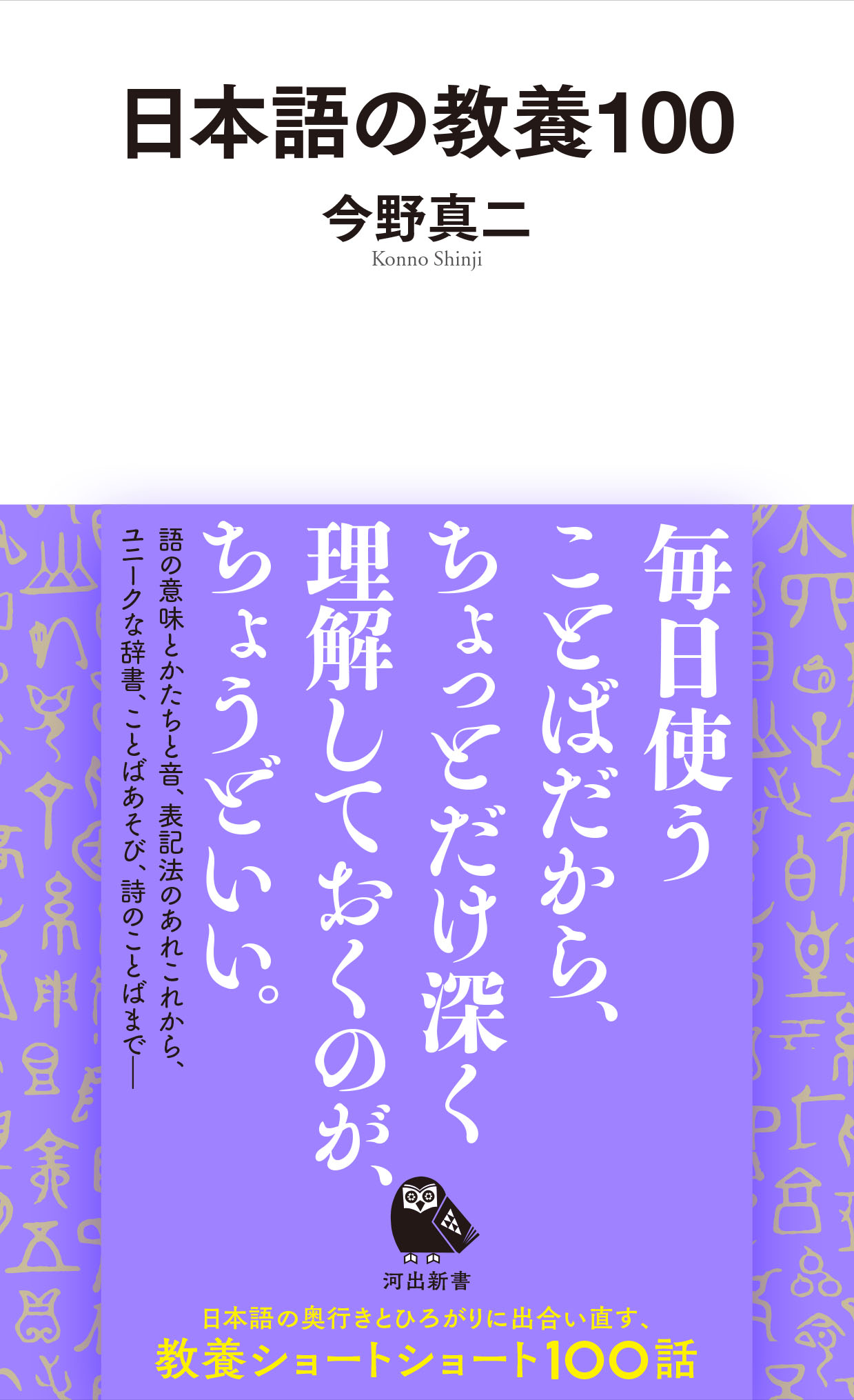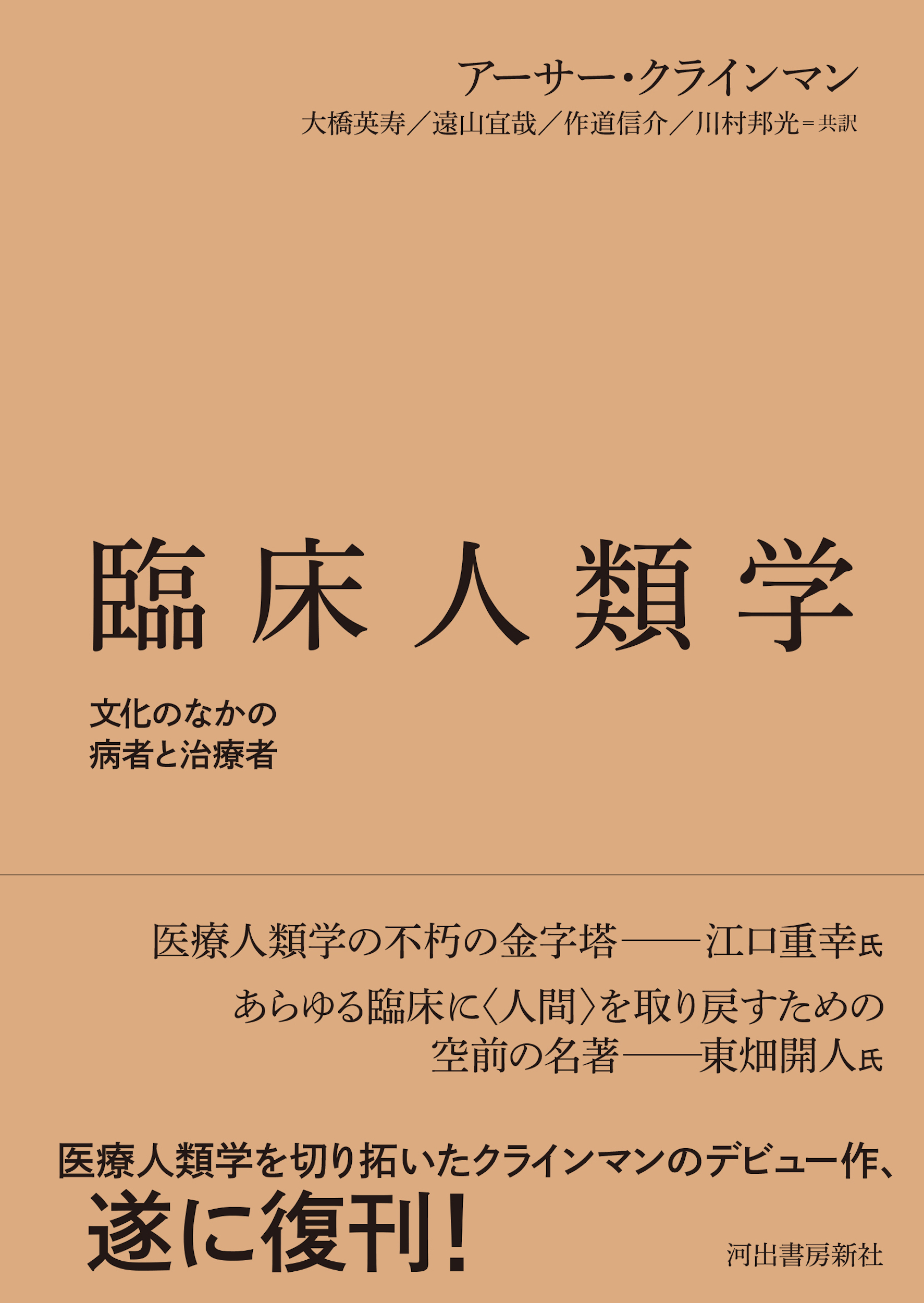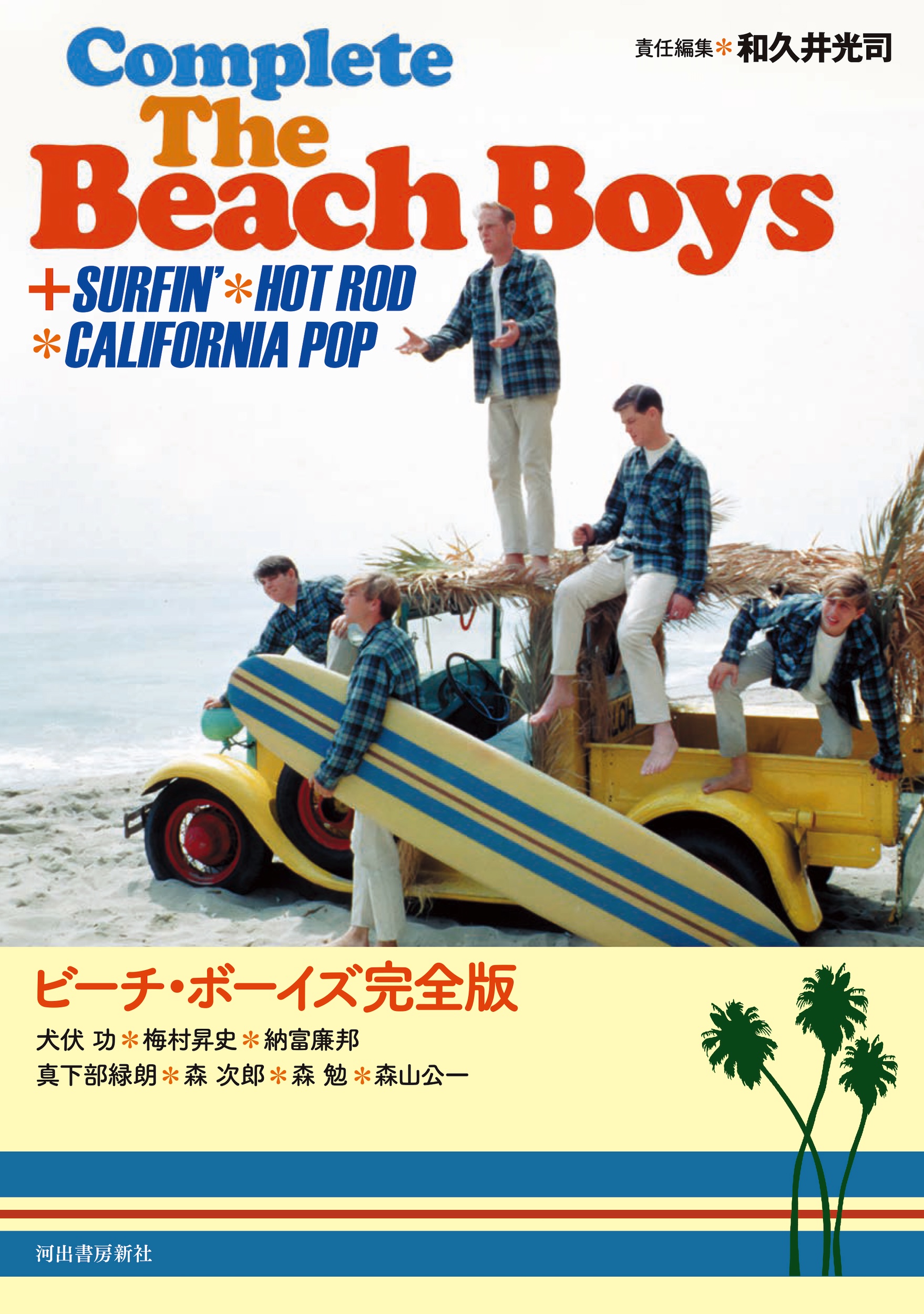単行本 - 人文書
そもそも、この国にとってオリンピックとは何なのか【吉見俊哉『五輪と戦後――上演としての東京オリンピック』刊行記念 著者インタビュー】新型コロナウイルスによって開催延期になったいまこそ改めて考えたい
吉見俊哉
2020.05.14
――本書を脱稿されたあとに、新型コロナウイルスの世界的流行の影響で、東京オリンピックは延期となりました。パンデミックのさなかに、本書を世に問うことになりました。
吉見 この本を脱稿したのは、2月24日、予定されていた開幕日のちょうど5ヶ月前でした。この時点で中国の武漢は封鎖されており、この新型コロナウイルスがオリンピックにとって大きなリスクになることは予想できましたが、それがヨーロッパに飛び火して、イタリアをはじめとして多大な死者を出し、アメリカでも感染者が増え続け、とてもこの夏にオリンピックなど開けないという状況に、たった1ヶ月でなるとまでは予測できていませんでした。この劇的な変化について何か記しておきたいと思いましたが、本はすでに印刷のプロセスに入ろうとしていましたので、わずか2ページ、補記を追加するに留めました。
そのあとも状況は刻々と変化していますので、いま現在、私が考えていることを述べておきたいと思います。
2001年のアメリカ同時多発テロ事件、2008年のリーマンショック、そして2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック――この3つの出来事で、21世紀の人類の歴史は変わってしまったと、私は思っています。あるいは、これらは表れにすぎず、もっと構造的に変わるべくして変わったのかもしれません。
この3つの出来事には共通点があります。どれもが、過剰と言ってよいほどのグローバリゼーションの加速度的進行が、しっぺ返しを食らった出来事なのです。
2001年に、アメリカのグローバルな軍事的覇権に対して捨て身のテロをイスラム過激派が行なった。これはアメリカ中心のグローバリゼーションがブーメランのようにしっぺ返しを食らった現象だと言えます。リーマンショックもまた、新自由主義的なグローバリゼーション、金融資本主義というものが徹底的に進んでいった末に自壊したものです。いまのパンデミックも、もの凄い量とスピードで人が移動するグローバリゼーションの進展がなければ、少なくともこんなに大事にはなっていなかった。21世紀に入って、グローバリゼーションは繰り返ししっぺ返しを食らっているわけです。
ただし、よく言われているように、感染症パンデミックは、人類の歴史では今回が初めてのことではありません。近いところでは、1918年のインフルエンザですね。5000万人とも言われる、凄まじい数の人が命を落とした。しかしこれは第1次世界大戦がなければ、これほど大きな被害にはならなかったのです。最初はアメリカのカンザス州で発生したと言われているわけですが、1917年にアメリカは参戦します。兵士がどんどんヨーロッパに渡る。兵士がウイルスを運んだ結果、ヨーロッパで爆発的に流行してしまう。戦争のときには兵士や物資が世界中を動いていますから、病原菌もばらまいてしまうのです。
もっとさかのぼると、1817年にもパンデミックが起きています。コレラですね。ヨーロッパで感染が劇的に拡大するわけですが、その直前がナポレオン戦争だったことからもわかるように、ヨーロッパ全体が戦場になって兵士が駆け巡るような時代になっていたわけです。いろいろなレベルがありますが、人のグローバルな移動がパンデミックの拡大と切っても切れない。大航海時代のさなか、16世紀にはスペイン人が天然痘をアメリカ大陸に運んでしまう。14世紀のペストの大流行の背景には、モンゴル帝国のユーラシア大陸制覇による交易の拡大があった。ことほどさように、パンデミックはグローバリゼーションと表裏の関係にあり続けてきました。
ひるがえって、2020年現在の世界的な危機は、それがこのように感染症の流行というかたちをとったことにはさまざまな要因があるのだと思いますが、1980年代、90年代と進んできた新自由主義的なグローバリゼーションのひとつの帰結であると思います。
このことは、オリンピックの歴史にとって、特に東京オリンピックにとって重要な意味がある。――それはなぜか。
振り返れば、オリンピックとIOCは、1984年のロサンゼルス大会をきっかけに決定的に変質しているのです。1976年のモントリオール大会までは、コマーシャリズムを極力排除した、国と国とのインターナショナルな競い合いという、いわば古典的なオリンピックだったと言えます。その結果、モントリオール大会は巨額の赤字を抱えてしまい、大失敗だった。次の1980年モスクワは、西側のボイコットもあってうまくいかなかった。1970年代は、近代オリンピックにとって大きな危機の時代でした。
そこでロサンゼルス大会から、オリンピックはコマーシャリズムやグローバルメディアとの一体化を追求する方向へと舵を切ります。この方向転換は、レーガノミクスやサッチャリズムに象徴される新自由主義的な経済政策の拡大とまったく同時的に起こっていたことに注意を払う必要があります。つまり、オリンピックにおけるコマーシャリゼーションと新自由主義的なグローバリゼーションとは、車の両輪なのです。
そして、国際的にはこの先で、2020年の東京オリンピック計画は立てられてきたのです。そうすると、グローバリゼーションが臨界まで達した状況のなかでコロナ・パンデミックが起こり、その結果、すでに変質していた東京オリンピックが延期となったことは、単なる偶然とは言えなくなってくると思います。
1964年の東京大会も含め、ナショナリズムの国際イベントしてのオリンピックが、1976年モントリオール大会で曲がり角を迎え、1984年ロサンゼルス大会からのコマーシャリズムの路線が2020年東京大会で曲がり角にきた。私たちがいま目の前にしている現象は、そうした二重の歴史の曲がり角を示していると、私は思います。
――来年、東京オリンピックが開催されるとすれば、このコロナ禍を乗り越えたあと、という状況が想定されます。どんなオリンピックになるとお考えですか。
吉見 まず、本当に開かれるのかどうかわかりませんね。仮に、先進諸国で今の流行が収まったとしても、アフリカはどうなのか、南米はどうなのか、インドや中東は大丈夫か? それに、1918年の時のように、先進諸国でもこの秋から冬にかけて第二波が来るかもしれません。来年まで続く長期戦になった場合、延期したものが本当に開催できるのか。IOCやJOCは本気で心配しているでしょうね。1940年の東京大会に続き、東京は再びオリンピック中止に追い込まれる可能性が、まだ小さくないのです。しかし、もしもそうなったとき、日本社会は経済的にも精神的にも、ものすごいショックを受けるでしょうね。
だからまず強調したいのは、本書が、そのようになったときですら、そもそも私たちはなぜこのようなオリンピックを始めてしまったのか、日本人にとって東京オリンピックとは何だったのかを根底から検証し直すための視点を提供していることです。万一、この先、パンデミックが収束しないで、東京オリンピックが中止になっても、本書を読むことは決して無駄にならない、むしろそこで茫然となりそうになったら、ぜひ本書を読んで自分たち自身の過去を振り返ってみていただきたいと思います。
しかし、今は仮に開くことができたとしてみましょう。政府やJOC、メディアの演出がどうなるかはすでに予測可能です。つまり、2021年の東京大会は新型コロナウイルスによる世界的な危機を乗り越えた歴史的に記念すべきイベントである、というものです。そういう打ち出し方を必ずしますね。
そもそも、日本政府がこのオリンピックに再挑戦したときのスローガンは、東日本大震災の危機を乗り越えたシンボルとしての東京オリンピックというものでしたね。それに対する世界的な同情を集めたわけです。それと同じパターンを繰り返すに違いありません。
実際、こうした演出は、日本のオリンピックとしてはきわめて常套的な手法です。
実現しませんでしたけれども、1940年の東京オリンピックは1923年の関東大震災から復興し、帝都・東京が大復活したことを宣揚するイベントと考えられていました。
そして、これは言うまでもありませんが、1964年の東京オリンピックは、アジア太平洋戦争に敗戦し、国土が焼け野原になった破滅的な状況を乗り越えて、日本が復活したのだということを示すためのイベントでした。
つまり、オリンピックのような――そして万博もそうですが――世界的なお祭りを行なうことによって自分たちが復活したことを確認するというスタイルが、近代日本人の発想法に繰り返し内挿されていくわけです。日本社会とは、そうやってクライシスをお祭りで乗り越える社会なのです。「日本型危機乗り越えお祭り主義」と呼んでもよいかもしれません。それが私たちに埋め込まれたハビトゥス(習慣)であると言えます。
このようなハビトゥスに慣れ親しんでしまった日本社会が持つ最大のリスクは、自らの失敗に正面から向き合うことをしないで済んでしまうということです。
1964年の東京オリンピックによって、焼け野原から立ち上がった、このまま右肩上がりで成長していくんだと言ってしまうことによって、1945年の敗戦が何だったのかを見ないで済んでしまう。戦前・戦中に起きていた日本の大失敗を記憶せずにやり過ごしてしまう、過去から学ばずにお祭りによってアイデンティティを取り戻してしまう、そういうネガティヴな効果があると思います。
お祭りをやることによって困難な状況を変えたり、お祭りをやることによってなかなか進まない開発を一挙に進めていったりする。1964年だって、それによって米軍施設を返還してもらったり、沖縄返還の足掛かりを作ったりしたわけですね。
いまのコロナに対する政治的対応にまずさも、来年、オリンピックを開くことができたとすれば、すっかり水に流されてしまうに違いありません。政府もメディアもコロナに打ち勝ったという点を大宣伝すると思います。そうやって、新たな忘却のプロセスが始まる。すべて元の木阿弥になってしまう。そういうことがこの国はとても得意なんですね。そうやって何も変わらない日本が繰り返されてきた。日本の病だと思います。
私たちはいまこそ、先ほど言った、新自由主義的なグローバリゼーションが曲がり角に来ていること、私たちの社会システムの問題点を正面から見据えるべきだし、オリンピックで言えば、1984年以来のコマーシャリズムが問い返されなければいけないフェイズに来ていることにフォーカスしなければなりません。
――日本という国では特に、オリンピックは大きな意味を背負わされているように感じます。世界的に見て特殊なことなのでしょうか。
吉見 東アジアでは共通する部分もあるでしょうが、しかし、ここまでお祭りによって危機を乗り越えるということが人々の心性に内面化されているというのは、日本がずば抜けていると思います。
東アジア共通の部分に目を向ければ、1964年の東京のあと、1988年にソウル、2008年に北京でオリンピックが開催されますが、いずれも経済成長を国民全体が実感し祝福するというイデオロギー的効果を持ったという点で、構造的な共通性がありました。この点では、東アジアでは、ヨーロッパやアメリカとは違うフェイズでオリンピックが捉えられていると言えるでしょう。
ただし、韓国では経済成長と相まって、朴正煕の独裁政権が終わり、民主化が進んだ時代と重なっていますし、中国はすでに世界大国としての歩みを進めており、大国としてのナショナリズムがせり出していた時代なので、1964年の日本とは異なる点も大きいです。
いっぽうで日本は、60年代の栄光がメディアを通じて繰り返し繰り返し想起され、実際に経験しているかしていないかを問わず、国民的な記憶として深く埋め込まれている。ここまでウェットにオリンピックの神話的作用が利いているのは、世界的にも相当特異なのではないかと思います。
しかも、オリンピックが終わればその記憶や関心はだんだん減衰していくのが普通ですが、日本では、もちろんいったんは1980年代に下火にはなるものの、平成に入るくらいからマスメディアのなかでの東京オリンピックへの言及は増えていくんですね。一般にノスタルジックに「昭和」を回顧しようという動きが高まっていましたから、その一環とも言えると思いますが、もう一度オリンピックを開けばあの輝ける高度成長の時代が戻ってくるのではないかと、当時を知る高齢層を中心に幻想が広がっていったのではないか。それを目ざとく石原慎太郎が察知して、2005年に五輪招致をぶち上げるのです。
社会状況も変わってしまっているわけですから、1964年が繰り返されることはあり得ないのですが、ちょうど日本経済が下降線をたどっていた時期に、オリンピックというお祭りの神話に頼って、いま一度「おまじない」をするという呪術的なモチベーションが生まれてしまっていたのではないかとすら思えます。
――ところで、吉見さんのご専門の社会学やカルチュラル・スタディーズに限らず、オリンピックについては、これまで膨大な数の研究があります。そうした中で、あえていま、オリンピック論をまとめられました。吉見さんにとってオリンピックとは、どのような研究対象なのでしょうか。
吉見 研究者それぞれにパースペクティブがあるので、あくまで私自身の問題関心ですが、オリンピック、そして私が並行して研究してきた万博というもののエッセンスは、「権力の上演」ということです。
1970年代後半から80年代にかけて学問的な形成を遂げた人間にとっては、構造主義とかポスト構造主義という学問的なパラダイムはとても重要でした。私も若い頃は、フーコーやバルトやレヴィ=ストロース、さらにはカルチュラル・スタディーズの文献を一生懸命読みました。その中で私にとっての最大のテーマは、権力と身体と空間です。
一番有名な議論は、フーコーによるパノプティコン(一望監視システム)ですね。つまり、特定の支配者や権力者が命令しているのではなくて、一人一人の内面に近代的な権力構造が埋め込まれているというわけです。その権力作用は日常化していて、監獄や工場や学校できわめてよく見て取れる。そのような研究は山のようにあったのです。
監獄や工場や学校で作用している権力は、フーコーの言葉で言えば、ディシプリン(規律訓練)型と呼ばれていました。もちろんそうした権力の作動はあるけれど、それと表裏で、祝祭的な権力、スペクタクル的な権力が作動し続けてきたのではないか、そう私には思えてならなかったのです。監獄型の権力と劇場型の権力は表裏一体だということです。
近代という時代は、監獄や工場や学校だけを作ったのではなくて、劇場やデパートや博覧会や動物園やテレビを生んだわけです。そうしたスペクタキュラーな空間を、近代はさまざまなかたちで発明した。そこにはオリンピックや万博も当然入ります。そして、そうした空間の中にもまた近代的な権力は作動している。その分析は、監獄や工場や学校における権力の分析と同様に重要だというのが私の立場であり、だからこそ、盛り場や博覧会やデパートやテーマパークを対象にしてきたのが、吉見俊哉の仕事です。
1992年の『博覧会の政治学』はそうした仕事の初期のものですが、そこでは世界を見る「まなざし」というものが博覧会という空間でどういうふうに編成されていくのかを論じました。さらに戦後日本の万博については、2000年代に入ってからもう少し政治的なプロセスに力点を置いて『万博幻想』を書きました。
博覧会/万博とオリンピックは、近代が権力の上演の場として発明した二大イベントですし、歴史的には19世紀半ばから20世紀初頭に全盛期を迎えた万博が先行していて、オリンピックがその仕組みを継承している要素も多いので、その先にはオリンピックを扱わなければならないというのは明らかだったのですが、最も重要な1964年のオリンピックを万博とはまた違うアプローチでどう扱えばよいかという視座がつい最近まではっきり掴めていませんでした。それがそのほかのさまざまな研究を経ることによって、ようやく見えてきて、今回はじめてオリンピック論を書くことができました。
――そういう意味では『五輪と戦後』は、都市や博覧会の研究、そして、アメリカとは何か、日本の戦後とは何かといった、これまで取り組まれてこられたテーマ系が合流している本とも読めました。
吉見 確かにそのとおりだと思います。1964年の東京オリンピックを考えるということは特別な意味を持っている理由は、これが「ポスト戦争」のオリンピックだということです。それは戦争が終わって新しい時代になったという意味ではなくて、いかにこのオリンピックが戦争の影、アメリカによる占領の影を引きずっているかという意味です。それが調べれば調べるほど、考えれば考えるほど見えてきた。
なぜ「東洋の魔女」はあれほどまでに強かったのか。それは、コーチが良かったわけでもないし、偶然でもなく、きわめて構造的な理由がある。あるいは円谷幸吉はなぜ銅メダルを獲ったのか。聖火リレーはなぜ沖縄から始まったのか。なぜ丹下健三は代々木にオリンピック競技場を建てたのか。それらはすべて、日本近代の殖産興業のプロセスからアメリカの覇権の下でのポスト戦争、つまり冷戦体制の文脈に位置づけないと理解できないし、逆にそう位置づけることによって1964年の意味はいっそうクリアに見えてくる。
1964年の東京オリンピックを輝かしいイベントとして見るのではなくて、そのように輝かしいイベントとして見てしまう我々はどのような戦後を生きているのか、それが見えてくるということです。
舞台の上ではいろいろなドラマが演じられています。そのストーリーの面白さをなぞるのではなくて、そのドラマはどういう劇場で、どのようなシナリオと演出によって演じられ、舞台裏はどうなっていたのか、そうした舞台の構造を解析してみたのが今回の本です。
――今後はどのようなテーマを論じられるおつもりでしょうか。
吉見 私の仕事は螺旋形を描いて、もとの位置に戻ってきているような気がしています。
私の最初の本は1987年の『都市のドラマトゥルギー』ですが、これは今回の『五輪と戦後』と同じように上演論的アプローチによって、東京の盛り場の変遷を捉え直したものです。1920年代の浅草から銀座への盛り場の移行と1970年代の新宿から渋谷への移行とに同型性を認め、盛り場に集まる人々の振舞いの変化から都市化のプロセスを読み解く作業でした。
そうした都市論から出発した私が、メディア論やカルチュラル・スタディーズや大学論を経ながら、これはこれでそれぞれ自分なりに必然性と一貫性があってそうなったのですが、しかし現在は、だんだん再び都市という原点近くに戻ってきています。
私の原点は演劇ですが、それを生かした上演論的アプローチによって社会を捉えることができるという確信から研究に入りました。それが具体的に行なわれている現場として都市に向かっていったわけです。そしていま、こうして積年の宿題だった東京オリンピック論を書いて、東京論・都市論に戻ってきた気がします。このあと、都市論の仕事をいくつかやるでしょう。その先には、上演論的アプローチの学問的価値をもっと深く見定めていく段階に入ると思います。同じところをぐるぐる回っているのではなく螺旋を描いて少しずつ上に上がっていることを祈りながら。もう人生の第四コーナーですからね、先は長くないかもしれません(笑)。
――長年の構想を経て、こうしてオリンピック論を上梓されました。読者はコロナ・パンデミックの中で、本書を手にすることになります。どのように読んでほしいですか。
吉見 私は、実は日本人は東京オリンピックを知らないのではないか、と思います。
1964年の東京オリンピックでどういうドラマがあったかは、テレビで繰り返し接して、よく知っているでしょう。エピソードという意味では。でも、それが東京オリンピックを知っているということになるのか。
あれが歴史的な出来事として何であったのかを考えるためには、それを成り立たせていた権力のパフォーマンスが、一つ一つの場でどのように演じられていたのかを深堀りせねばなりません。そのことによって、まったく違う風景が見えてきます。
私たちが想起する1964年の記憶はメディアによって操作されたものかもしれません。みなでこぞってその神話を演じ続けている循環から脱するためには、まず、どういう循環の中で自分たちが回っているのかを見据えなければなりません。
この本はそういうことをやろうとした本であり、1964年の東京オリンピックが何であったかを知ることによって、いま、2020年もしくは2021年に同時並行で起きていることにただ付和雷同するのではなく、そのプロセスに巻き込まれてしまう自分自身を批判的に捉え返す眼を身に着ける必要があります。
この本が主に焦点にしているのは1964年のオリンピックですが、私たちがその後ずっととらわれ続けている幻想や神話に対して疑問を発するきっかけにしていただければと思っています。