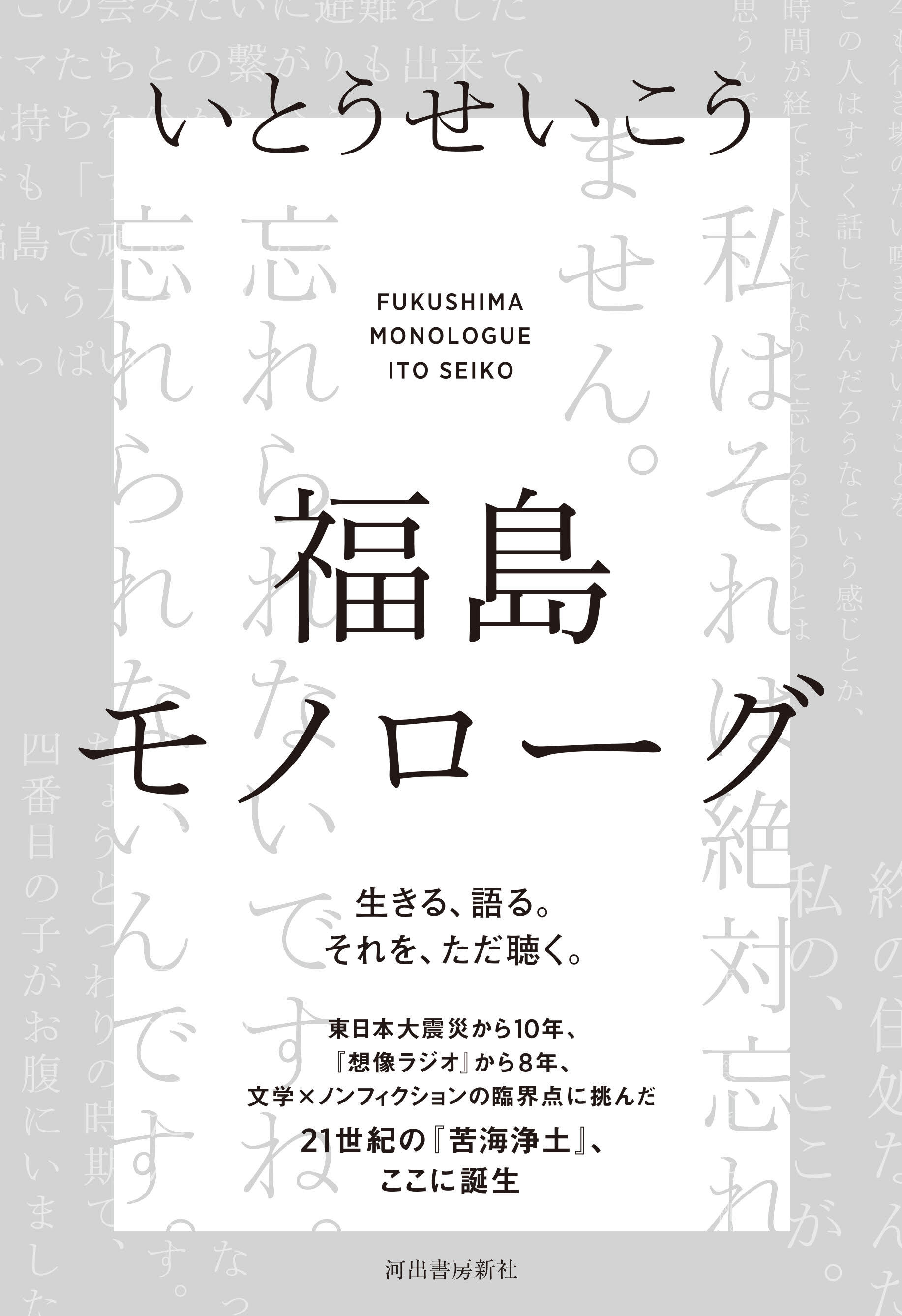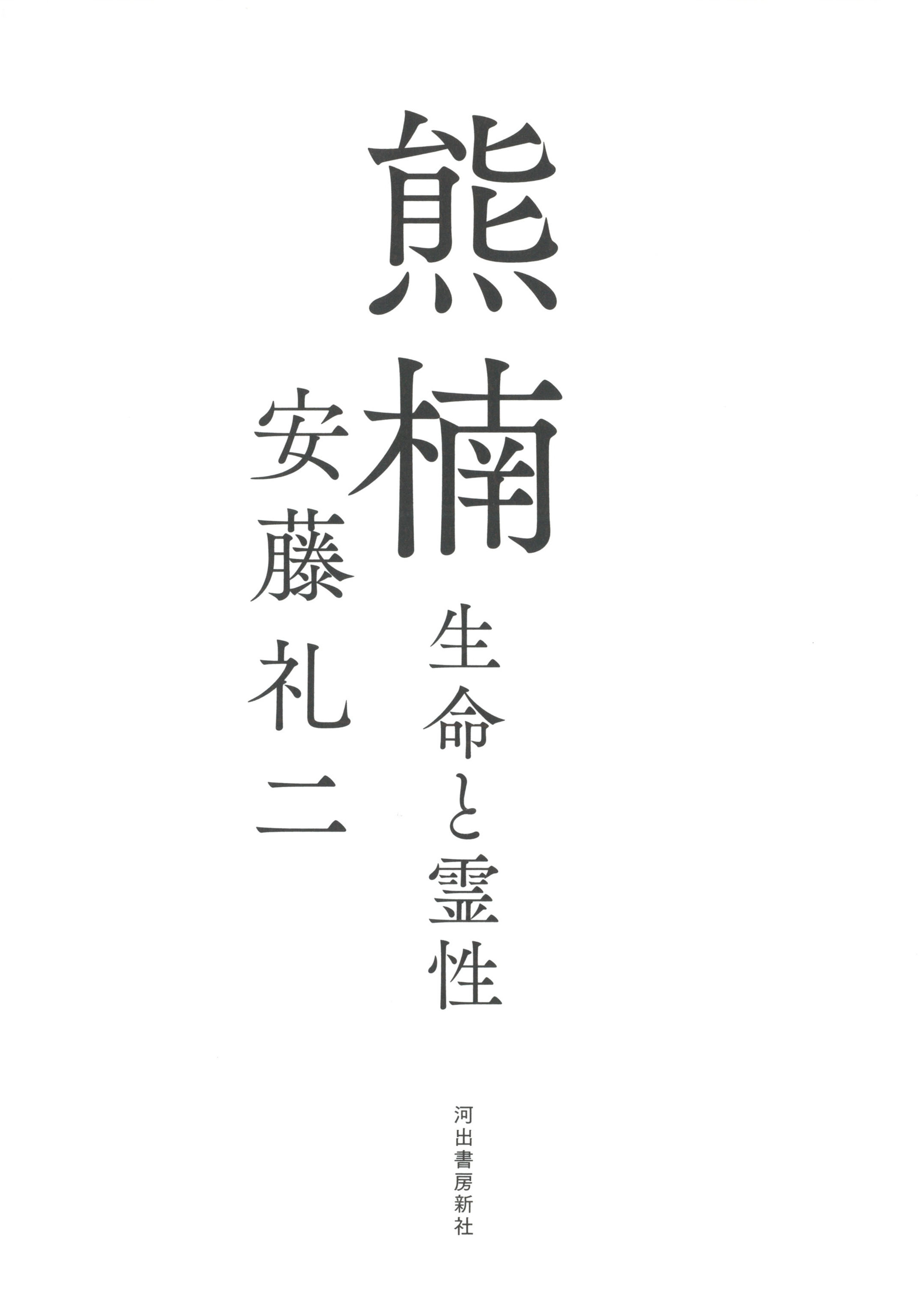単行本 - ノンフィクション
作家・中島京子が読む『武漢日記』|隅々まで息づく小説家の声
評・中島京子
2020.10.16
新型コロナウイルス感染蔓延による中国・武漢の都市封鎖解除から半年あまり――
いまだ世界で猛威をふるうこのコロナ禍を最初に体験した都市から、女性作家・方方(ファンファン)が発信し続けた60日間の記録『武漢日記』は、日本でも発売以降、大きな反響を呼んでいます。いま、この記録を読む意味とは、また、作家はこの災厄にいかに向き合うべきか――
北京や上海を舞台にした作品もあり、中国に造詣が深い作家、中島京子さんによる書評をぜひお読みください。
隅々まで息づく小説家の声――『武漢日記』を読む
中島京子
方方(ファンファン)は、小説家であり、湖北省作家協会の元主席で、二歳から武漢で暮らす、武漢人だ。この日記を読むと、あふれ出る武漢愛に驚かされることもある。文芸雑誌のインタビューの、「作家と都市の関係をあなたはどのように考えていますか?」という質問に、「魚と水の関係、植物と土壌の関係だと思います。」と答えている。武漢は方方という作家にとって生きる場所であり、そこからすべての栄養を取って創作をするホームグラウンドだ。
その武漢が、人類がかつて体験したことのないウイルス禍に見舞われ、都市封鎖という仰天の事態に遭遇する。人口1100万人が暮らす都市といえば、東京に匹敵する規模だ。武漢はかつて「東洋のシカゴ」と呼ばれたという。美しく堅牢な建築の並ぶ武漢は、洗練された都市の魅力に満ちている。
日記は中国最大のポータルサイト新浪網(シンランワン)のブログに、封鎖の二日後からアップされた。武漢封鎖は1月23日から、4月8日まで、七十六日に及んだが、方方のブログは六十日間、封鎖解除が決定された日まで、一日も欠かさず書き綴られた。
とはいえ、このブログは開始後たったの四日で「遮断」の憂き目に遭う。そのとき作家は「予想したよりは長く生きながらえた」と書く。検閲が日常的に存在する国で、作家の率直な筆が封じられるのは想定内だった。「予想外だったのは、多くの人が転送してくれたことだ」。その後、何度「遮断」され、「削除」されても、彼女は書き続けた。夜中の12時の更新を心待ちにし、「削除」に備えてコピーし転送を続けた人々が彼女を支えたのだ。
そんな目に遭っても、方方は、筆鋒をゆるめたりしない。医師の友人や警察官の友人から話を聞き、ネットにもくまなく目を配り、ウイルスとその対策の正確なところをつかもうとする。そうして自ら収集した情報を自分のブログで公開し、間違いがあれば真摯に謝罪して訂正もする。そのかわり、情報の隠ぺいや改ざん、粉飾といった欺瞞は許さない。
ウイルスが蔓延し始めたころ当局は、「ヒト-ヒト感染はない、予防も制御もできる」と喧伝し、真相を隠した。そして、真相を人々に知らせようとした医師たちを処分した。そのことに対する怒りは、日記の中で何度も繰り返される。体制に平気でこびへつらう同業作家が、インタビューで「完勝」という言葉を使って政府の方策を礼賛したことに対し、「勝利がどこにある? 完全がどこにある?」「頭を使って物を言え!」と罵倒する。「この悲しみの日々を胸に刻もう」「職務怠慢、不作為、無責任の連中に対して、私たちは追及の手を緩めてはいけない。一人も見逃しはしない。そうでなければ、遺体運搬用の袋に入れられて運ばれて行ったあの人たち――私たちと一緒に武漢を建設し、武漢の生活を享受した彼らに、私たちは申し開きができない!」という思いが、彼女を突き動かすからだ。
こんなふうに書いていると、『武漢日記』が体制批判のための本のように見えてしまうが、じっさいは、もっと個人の生活に即した日々の記録であることを、強調しておいたほうがいいかもしれない。
コロナ禍といえば、なんといっても「マスク」だ。「マスク」がないのだ。
方方は、あの日のわたしたちそっくりに、「マスク」不足を嘆き、吊り上げられた高値に憤慨し、分けてくれた友人に感謝し、自分もそれを同僚や親戚に分ける。
同じ団地で暮らす人たちは、食料品や日用品の共同購入を始める。
彼女の住む文聯(湖北省文学芸術界聯合会)の宿舎では、しょっちゅう食べ物を交換し合う。そうやって励まし合って、武漢の人たちは封鎖に耐えたのだ。
わたしの好きなエピソードは、突貫工事で建てられた、あの武漢の仮設病院で、中高年の女性たちが広いスペースを利用して踊っているというものだ。方方はそれを「仮設ダンス」と名づけた。感染症と闘い、空きスペースがあれば踊りだす「力強い」武漢の女性たちを、方方は、愛さずにいられない。
不正義を厳しく批判する一方で、方方はこんなユーモアを忘れない。九十九まで生きた祖父の長寿の秘訣は「人を怒鳴りつけること」だったというのだ。「武漢市民はいま家に閉じこもり、何もすることがなくて、イライラしている。発散することが必要だ。会って雑談するのはダメ、感染するから。窓を開けて歌うのもダメ、飛沫がとぶから。李文亮を偲んで号泣するのもダメ、平和を乱すから。できるのは怒鳴ることだけらしい。しかも武漢人は怒鳴るのが好きだし上手だ。怒鳴ってしまえば、体じゅうがさっぱりする。北方人が極寒の日に熱い風呂に入ったような爽快感である」。武漢語にはほんとうに罵語が多いらしい。武漢人らしい怒りのエネルギーが彼女を支えていたことも、こんなふうに突き放したユーモアの中から伝わって来る。
方方の日記には隅々にまで、小説家の声が息づいている。「私の主たる仕事は、小説を書くことだ」「私は小説書きなので、毎日些細なことを日記に書くときも、やはり自分の創作方法に沿って、観察し、思考し、理解してから書き始める」。彼女にとって小説とは、「落伍者、孤独者、寂しがり屋に、いつも寄り添うもの」であって、強者や勝者のものではない。
「歴史に見捨てられた事柄や、社会に冷遇された生命を庇護する」のが小説だ。
そうした意識に貫かれているから、方方の目は、このコロナ禍で、死んでいった者たちに注がれる。そしてその死者たちを、名前で呼ぼうとする。ことに、殉職していく医師たちの名前が挙げられる。李文亮医師。最初に内部告発をし、懲戒処分を受けた眼科医だ。彭銀華、夏思思、黄文軍。
死者たちだけではない、コロナの蔓延する都市で勇敢に自分の仕事をした人たちの名を、方方は書き残す。医療スタッフの送り迎えを請け負った宅配便の配達員汪勇、600人の居住民のために薬を調達した呉悠、武漢病院の医療スタッフのために弁当を作った劉鮮といった、ボランティアの人々。
誰もいなくなった町で、粛々と掃除をする清掃員にも、方方の視線は向く。ふつうの人たち。市民。でも、かけがえのない人たちを、方方は書き留める。
この武漢の記録は、途方もない数の犠牲者を出したウイルスとの闘いの記録だが、それは同じコロナ禍に見舞われた世界中の人々にとって、示唆に満ち満ちている。
この悲しみの記録に接してみて、やはり最初に湧いてくるのは、よくぞここまで実情を書いたという、著者への尊敬の念だ。中国ではいろいろなことが隠されて、正しい情報を取るのは難しいのではないかと、日本に住む我々は漠然と思っているが、やろうと思えばここまでできて、それは日本で漫然と、垂れ流される情報を鵜呑みにしているより、よっぽど正確で深みがあり、批判精神に満ちたものなのだということ。しかもそれを、当局だけではなく、「極左」による、ものすごい攻撃を浴びながら続けていくその意志の強さには圧倒される。
それから、描かれる武漢の人々の強さとやさしさに打たれる。医師の李文亮が亡くなったとき、武漢市民が大声で叫んだという。「李文亮の家族と子供は、我々武漢市民が面倒を見るぞ!」。市民はこれにこたえて李文亮が亡くなった時間に灯りを消し、懐中電灯やスマホで空に向けて光を送って連帯を示した。
同じウイルスに見舞われた日本で、感染した医師や看護師を白い目で見て、その家族や子供に近寄らないでくれという差別的なメッセージを発したのがこの国だったことを思い出すと、なんとも言えない気持ちになる。武漢に比べて死者の数が少ないのは、武漢の経験したことに学び、重症者を出さないように必死で闘った日本の医師の存在があったからではないのだろうか。死者数が少ないからといって、医師や看護師を差別していいなんていう理屈は、どこを叩いたって出てこない。
「二次災害の被害者が中国語になると誰が予想しただろう」という皮肉には、苦い笑いがこみ上げた。感染症が抑え込まれつつあったころ、武漢の指導者が武漢市民に、党と国家の「恩義に感謝する」よう求めたのだそうだ。市民に奉仕するべき党と国家が、その市民に対して「恩義に感謝」しろというのは本末転倒だ。言葉の使い方が間違っている。だから、「中国語が二次災害に遭った」という表現になったわけだ。これなどを読むと、果たして我が日本語は「二次災害」に遭わなかったかなと不安になる。「国民の不安がパッと消える」という理由で、カビの生えたマスクが全国に配られたことがあったが、あれなども日本語の二次災害であるばかりか、二次災害は日本の場合、もっとひどいことになっている気がする。また、方方は「覚えておこう、勝利ではなく終息だということを」と書く。コロナ禍は「終息」するのであって、「勝利」ではない。多くの犠牲者を出し、武漢市民に不自由を強いてようやく「終息」するものを「勝利」と呼ぶべきではないと。これなども、「人類がコロナウイルスに打ち勝った証としての東京オリンピック」という前首相の奇妙な言葉遣いを思い出して、ああ、日本語もだいぶやられたなあと思うのである。
この方方のブログが知られたころによく引用された、「ある国の文明度を測る唯一の基準は、弱者に対して国がどういう態度を取るかだ」というフレーズは、2020年、世界を席捲したコロナ禍が生んだ名言として、世界の文学史に残るだろう。
その言葉を受け止めて、わたしたちは、自分の国の文明度について、いま一度、きちんと考え直すべきだと思えてならない。