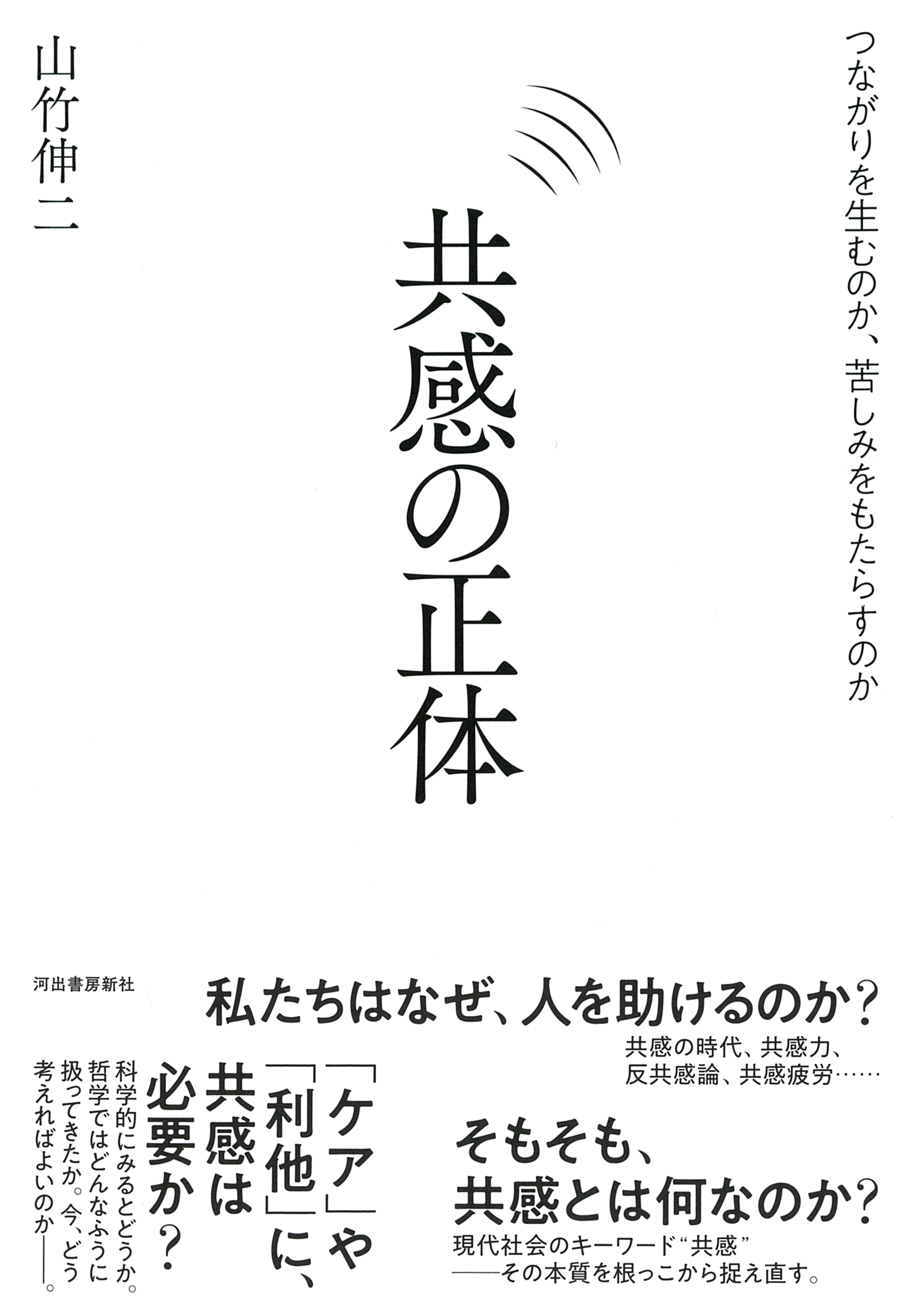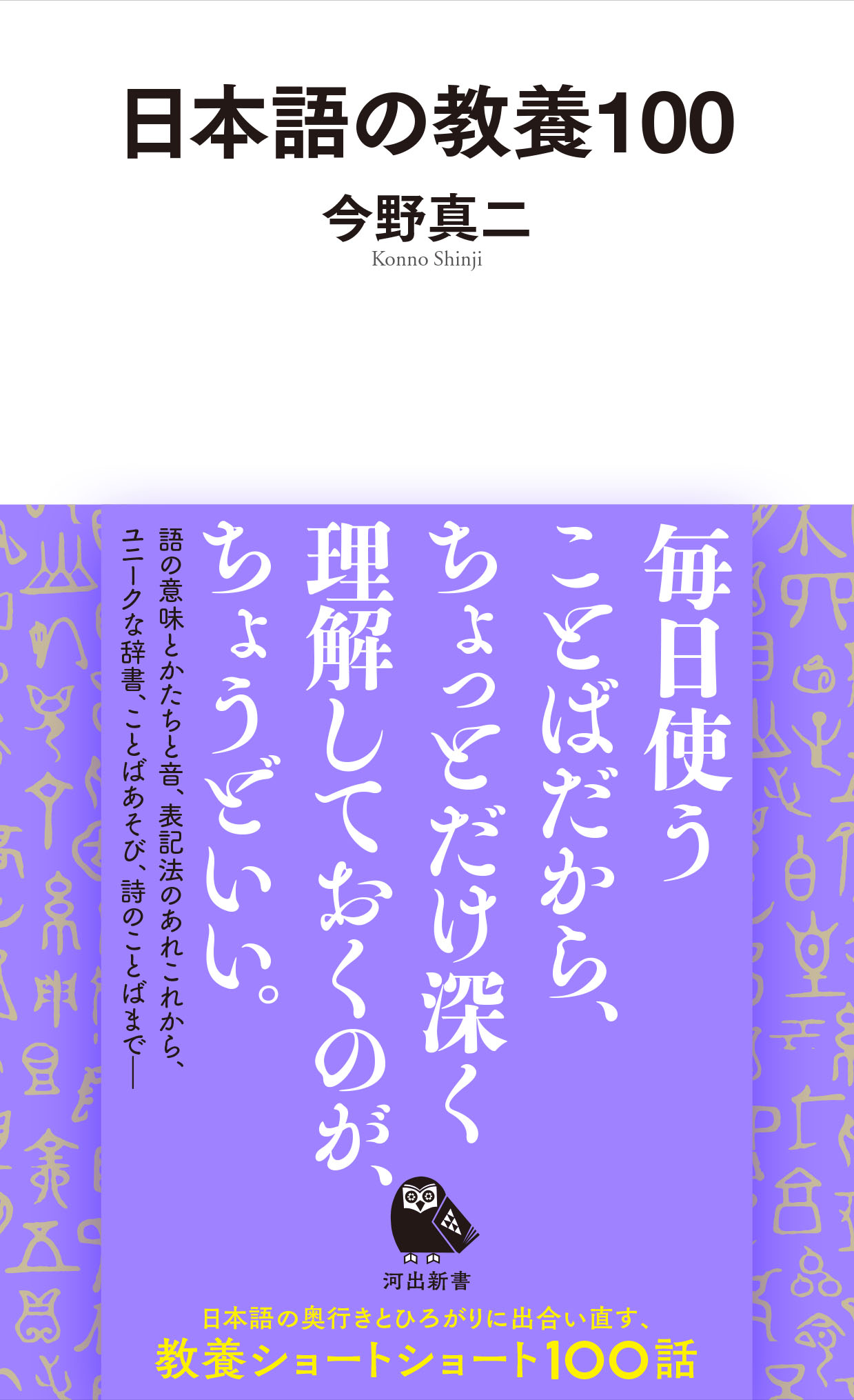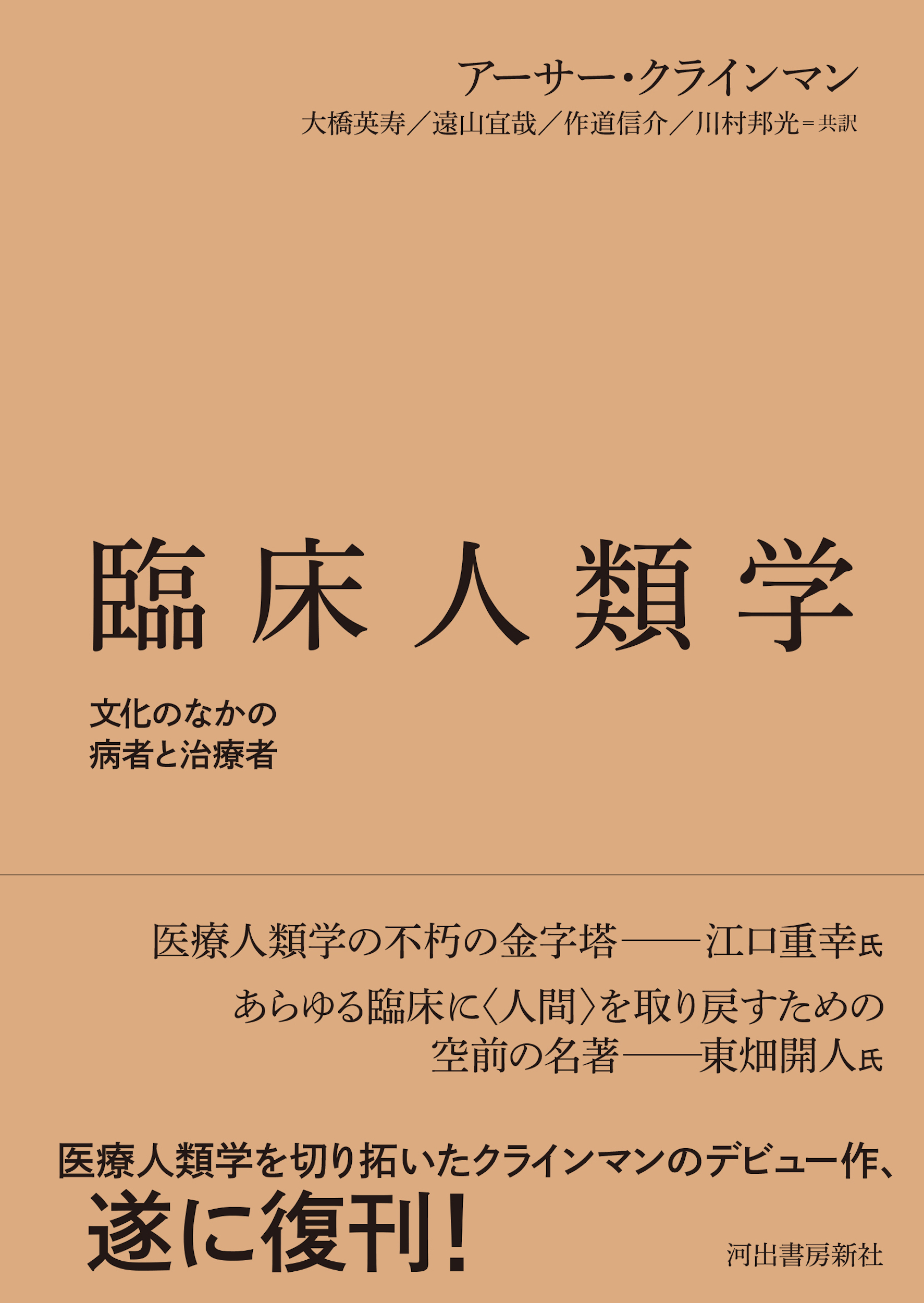単行本 - 人文書
橋本健二『はじまりの戦後日本』序章(抜粋)を公開
橋本健二
2016.05.12
戦後日本はこうして生まれた!――戦後史の盲点をつく画期的な一冊
橋本健二『はじまりの戦後日本』
::::::::::::::::
序 章 「リンゴの唄」と流浪する人々
■小林庸子の戦前・戦中・戦後
小林庸子は一九二一年九月、東京市浅草区象潟、現在の台東区浅草四丁目で生まれた。父は小林濤秀、母親はハマ。二人の兄と一人の姉がいて、四人兄弟の末っ子だった。父親は台湾製糖の台中工場長を務め、一家は台湾の日本人町に住んでいたが、母親は浅草の自宅に帰って庸子を産む。まもなく幼子を連れて台湾の社宅に戻り、約三年をそこで過したが、子どもたちを日本の学校に入れるため、仕事のある父親と台北の学校へ行っていた長兄を残し、帰国する。一九二五年のことである。
庸子は学校嫌いで、よく遅刻をした。唱歌と体育だけは好きだったので、その時間に合わせて登校することが多かったのである。近所に親しい女の子がいてよく一緒に遊んだが、その父親が仕事で映画館に通っていたことから、二人も映画館に自由に出入りできるようになり、「オーケストラの少女」「アヴェ・マリア」など、ディアナ・ダービン主演の映画に親しんだ。
小林家のような中流家庭の娘は、小学校卒業後には高等女学校へ進学するのが普通だったが、勉強嫌いの庸子は父親の反対を振り切り、松竹少女歌劇学校に入学する。一九三六年のことである。二度の選抜を経て卒業できたのは、八〇人いた同期生のうち、わずか一五人だった。そのなかに入ることのできた庸子は、国際劇場のこけら落とし公演で初舞台に立つ。芸名は、次兄がつけてくれた。
しかし次兄は、所属していた歩兵第三連隊が二・二六事件に関わった直後に満州へ送られる。重傷を負っていったん除隊になったものの、日米開戦を前に再度召集、千島列島で乗っていた輸送船が撃沈され、戦死した。父親も、仕事先のパラオから日本へ帰る途中、船が撃沈されて死んだ。庸子の初恋の相手だった立教大学の学生も、学徒動員で航空隊に入ったのち、特攻隊として出撃し帰らなかった。わかったのはいずれも、戦後になってからのことである。
庸子はやがて、主役にも抜擢されるようになり、ファンも増えていった。しかし戦時を迎え、歌劇の演目も「一億の合唱」「銃後の尖兵」など、次第に軍国色を強めていく。そして一九四四年になると、国際劇場は閉鎖、松竹少女歌劇団は解散して松竹芸能本部女子挺身隊へと改組され、工場や鉱山、そして外地への慰問へ出かけるようになる。これを機に少女歌劇をやめる団員も多かったが、庸子は続ける決心をする。
一九四五年三月九日深夜、東京はおよそ三〇〇機のB─29爆撃機の焼夷弾攻撃に襲われる。庸子は母親とともに隅田川へと向かったが、火はすぐ近くまで迫ってくる。川に入ったところで気を失い、人に川から引き上げられて気づいたが、もう母親はいなかった。工場に避難して翌朝、戻ってみると家は跡形もない。母親を捜し回るが、見つからない。四日後になって警察から連絡があり、遺体安置場所の増上寺へ行くと、母親に渡した松竹のマークの入った給料袋が載せられた棺がある。蓋を開けると、生きていたときそのままの姿の母親だった。その後も慰問団として中国へ渡ったり、国内での公演を続けたのち、劇場の地下室で玉音放送を聞く。
九月一日のことだった。会社からの指示で松竹大船撮影所に行き、自分が映画の主役に抜擢されたことを知る。「そよかぜ」と題する映画で、戦時中に企画され台本が作られたが、明るいストーリーの音楽映画だったため、GHQの検閲をいち早くパスしたのだった。その挿入歌のタイトルは「リンゴの唄」(サトウハチロー作詞、万城目正作曲)。この歌の大ヒットで、小林庸子は大スターとなる。その芸名は、並木路子。そのときにはすでに亡くなっていた次兄が、道は人に踏まれ踏まれてしっかり固まっていくが、その周りには並木があって、人の気持ちを和らげるのだといって、付けてくれた名だった。
【中略】
■戦争によって強いられた社会移動
「リンゴの唄」を聞いたとき、多くの人々は流浪のさなかにいた。復員兵たちの一部は、以前の職場に戻って仕事を再開しようとしていたが、他の者は職を失い、生きるすべを探していた。引揚者たちは、帝国の侵略先での職と財産を失い、困難な戦後を生き始めていた。国内にいた人々も多くが職を失い、また住む家を失い、農村の実家や親戚を頼ったり、その日暮らしをするしかなかった。ヤミ商売で生計を立てた人も多かったが、そうでなくてもヤミの食糧を求めて歩き回らねばならなかった。
詳しくは第1章で述べるが、社会学では、人々が社会的地位の間で移動することを「社会移動」と呼ぶ。常態の安定した社会では、人々は就職や昇進、転職、退職などによって社会移動をする。事故や災害、倒産、解雇など、外的な要因によるものも多いけれど、これが主流とはいえない。
しかし戦中から戦後のこの時期、膨大な数の人々が、戦時体制の成立、戦争、そして戦後の混乱という、外的な要因によって社会的地位を失い、新しい社会的地位を求めてさまよわなければならなかった。戦争によって、社会移動を強いられたのである。その過程は、個々人にとっては自らの生活の再建だったが、社会全体としてみれば、日本社会の戦後復興の過程だったということができる。
戦後の混乱から復興に至る過程を描いた、著書や論文、回想録などは数多い。その多くは、政治・経済や社会構造のマクロな動きを全体として論じるか、個人のミクロな経験を記述するものである。この両者が並行して論じられることもあるが、マクロな現象とミクロな現象を、一貫した方法で論じることは難しい。
本書で私は、この両者を結びつけ、ひとつの方法で論じてみたいと考えている。両者を結びつける鍵となるのが、社会移動という概念である。社会は個人から構成されている。個人の側からみれば、個人が社会を作っているということもできるが、逆に社会の側からみれば、社会は個人にそれぞれの社会的地位を与え、社会に組み込んでいる。つまり社会と個人は、社会的地位を通じて結びつくのである。したがって社会の変化は、個人の社会的地位の変化、つまり社会移動の総和として理解することができるはずである。
この方法は、戦中から戦後にかけてのように、社会が劇的に変化する場合には、とりわけ有効性が高いだろう。兵士、軍需産業の労働者、植民者、地主・小作など、戦前・戦中には大量に存在していたものの、戦後になると基本的に消滅してしまった社会的地位は、膨大な数に上る。社会的地位を失った人々は、いかにして社会移動をし、新しい社会的地位を獲得していったのか。これを明らかにすることができれば、社会のマクロな変化と個人のミクロな経験を結びつけながら、戦前から戦後にかけての社会の変化を、つまり戦後社会が成立する過程を描くことができるのではないか。これが、本書の基本的な視点である。
戦後七〇年を過ぎ、いま改めて「戦後史」というものへの関心が高まっている。私の前著『「格差」の戦後史──階級社会 日本の履歴書』(河出ブックス)は、戦争による破壊と戦後改革を経て戦後社会が成立した、その時点から説き起こした「戦後史」だった。しかし、考えてみれば戦後史の記述は、戦後社会がいかにして成立したかというところから説き起こさなければ完結しないはずである。本書はその意味で前著を補完するものであり、併せてお読みいただければ幸いである。