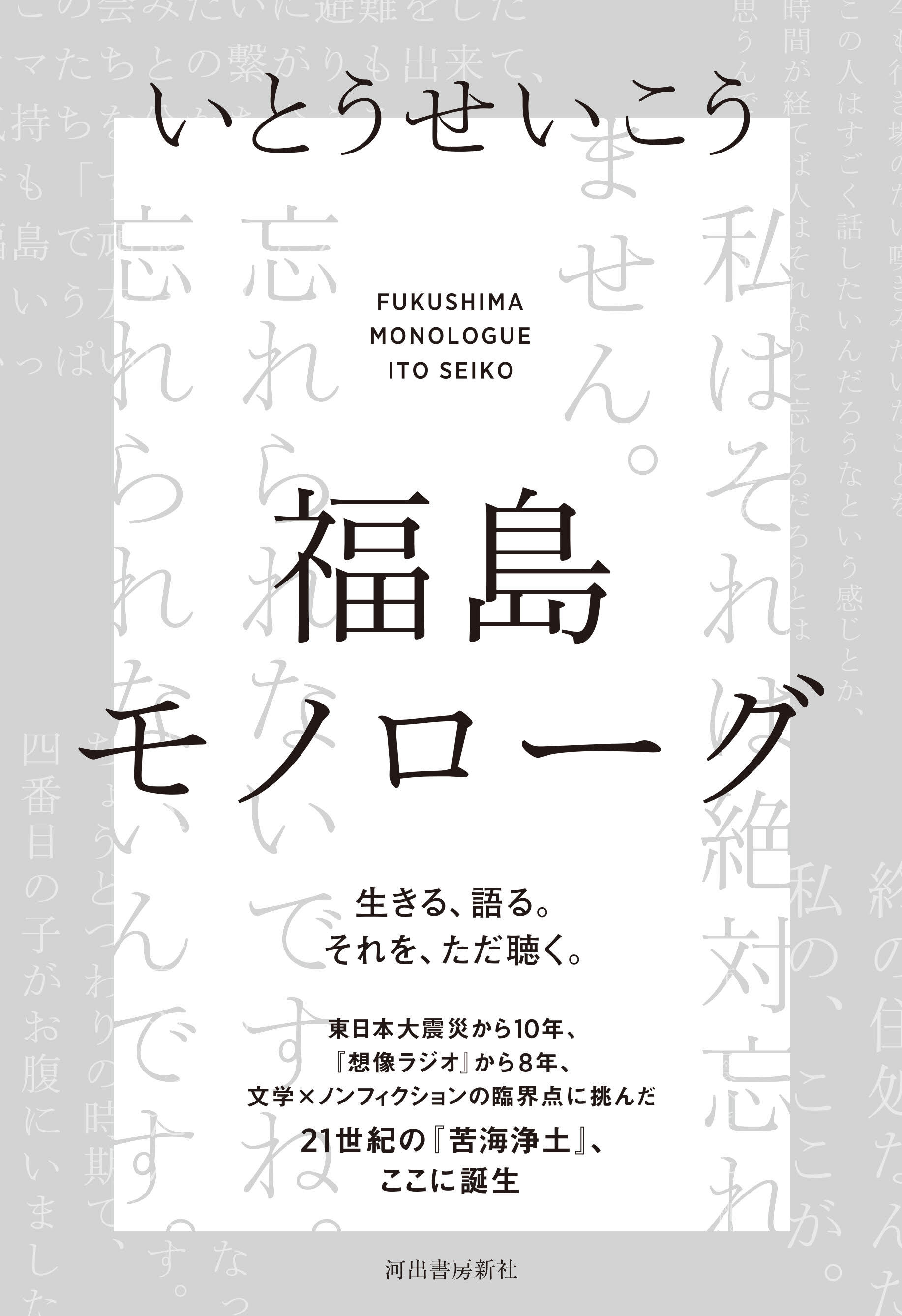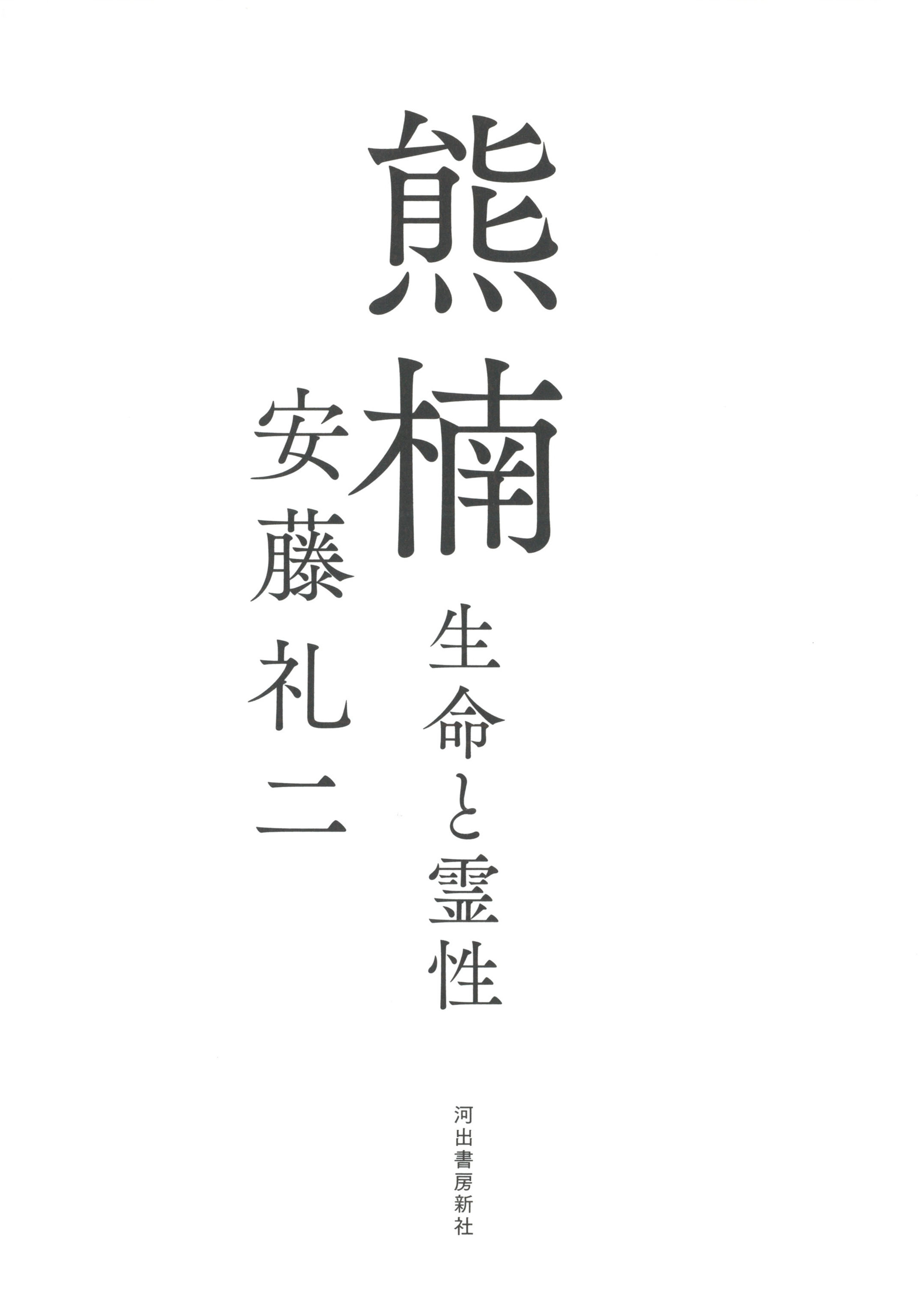単行本 - ノンフィクション
いざ、メダル奪還!「シンクロナイズドスイミングの母」のリオ五輪までの軌跡を描いた渾身のノンフィクション
川名紀美
2016.08.19
『井村雅代 不屈の魂』
波乱のシンクロ人生
川名紀美
生い立ちから中国コーチ時代、更にはリオ五輪に向けた決意まで。周辺への丹念な取材も加えながらシンクロに人生の全てを賭けた日本代表コーチ井村雅代の執念の軌跡を描くノンフィクション。
————————–
あとがき
リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックまであと百日あまりとなった四月半ば、井村雅代さんは心底、憤っていた。
バドミントンの有力選手たちが起こした不祥事の影響もあったのだろう、ナショナルトレーニングセンター長の名前で分厚い文書が五輪代表選手やコーチのもとに送られてきたという。そこには選手として守らなければならない社会的生活規範が事細かに書かれていた。水泳連盟からは、それを読んだうえで誓約書にサインをして提出するように求められた。
誓約書を出すのだから、内容を一字一句もらさず読んで、納得のうえでなければならない。井村さんはこれも教育だと、誓約書にサインをするという行為の重みをシンクロ日本代表チームの選手たちにくどいほど伝え、自身も書類に丁寧に目を通していった。
驚いたことに、そこにはコーチのとるべき行動規範も記されていた。茶髪やピアス、タトゥーなどは禁止。合宿中の喫煙や飲酒も禁じられていた。
「ええトシした人をつかまえて、これはなんや」と怒りがわいたという。
練習中にタバコを吸ったりお酒を飲んだりすることはありえない。しかし、一日の課題をすべて終えたあと、合宿所の外で誰かと食事をする機会があればお酒を飲むかもしれない。
自分の言動については全責任を負う覚悟で選手たちの前に立っている。井村さんは水泳連盟の事務局長にかみついた。「このような誓約書にサインすることはできません」と。
五輪に出場するさまざまな競技のコーチたちは、社会的な経験も指導経験も豊かな人たちが少なくない。彼らは誓約書にサインをしたのだろうか。内心ばかばかしいと思っても、ほとんどの人がサインをしたのではないだろうか。世の中ではそういう振る舞いができる人のことを「おとな」という。
井村さんはちがう。おかしいと思ったら黙っていられないし、おかしいと思いながら「まあ、ええわ」と従うようなことは決してない。そのためにあちらでぶつかり、こちらでつまずき、波風を立てながら生きている。かかわる人たちからすれば「めんどうくさくて」「やりにくい」人である。
でも、私はそんな井村さんが好きだ。言いたいことを言い、おかしいと思うことはしない生き方を貫きたいのに、しがらみにからめとられて思うにまかせない。周囲を慮(おもんぱか)りながら生きている身にとっては、信念に従ってまっすぐに生きる井村さんがまぶしくもあり、敬意もわいてくる。
数年にわたって井村さんにインタビューを重ね、練習や試合の数々を見せてもらった。痛感したのはシンクロナイズドスイミングという、誰もができるわけではないマイナーなスポーツにささげる愛情の深さである。寝ても覚めてもシンクロのことが頭から離れず、「まだ見ぬ」シンクロを生み出すために、時間が取れれば舞台や美術館、動物園などに足を運ぶ。
二〇一五年、ロシアのカザンで開かれた水泳の世界選手権で、女子の競技であったシンクロナイズドスイミングに初めて男女のミックスデュエットが採用され、話題になった。たった十組の出場で、日本からも一組が出た。
実際の競技を見た井村さんに感想を聞くと、「男性と女性で演技するからもっとショー的なものかと思っていたけど全然ちがった」と身を乗り出した。しっかりとしたシンクロのテクニックがベースにあって、そのうえで男性と女性ならではの表現をしているのが素晴らしかったと目を輝かせた。「女性だけなら地球の半分。男女になればシンクロが地球のすべての人のスポーツになる。これからは男の子にもちっちゃいときからやってもらわなあかん」と、シンクロの発展を願う言葉が口を突いて出た。
得意なスポーツなどなく、取材でも新聞記者だったころに真夏の甲子園球場のスタンドを走り回ったことくらいしか思い出せない私が、あろうことかスポーツの世界に足を踏み入れることになった。
きっかけは井村さんが指導者として中国へ赴くことになったときの日本の人々の反応である。「非国民」とか「国賊」などという言葉が飛び交ったのには驚かされた。選手や指導者が国境を越えて行き交うスポーツの世界ほど国際化が進んでいる分野はないと思っていたからだ。
中国へ指導に行くことの何がそんなにいけないのか、井村さんはどんな思いで中国をめざしたのか、中国の選手たちにどんな指導をしているのか、知りたい思いがふくらんだ。
おかげで北京、ロンドンと、二つのオリンピックを現地で見ることになった。ただきれいだなとしか思わなかったシンクロというスポーツの奥深さを少し知ることができた。人間が採点することで得をしたり損をしたりする採点競技のおもしろさにもふれた。
シンクロナイズドスイミングは、その名の通り、複数の選手が心を一つに力を合わせて競う競技である。体格では欧米勢にかなわないにしても、力を合わせることが得意な日本人には案外向いているのかもしれないと思う。
ご本人に、あるいは縁のある人たちに話を聞いて、井村雅代さんが稀有なコーチであると確信を持った。だが、井村さんが偉業を成し遂げられたのは選手をはじめ、さまざまな人たちの支えがあったからだという事実も取材を通じて知ることができた。
選手らの体力づくり、演技を励ます音楽、人々を惹きつける力強く美しい振り付け、選手たちを一段と輝かせる水着……。それぞれの分野の専門家が井村さんの情熱に巻き込まれ、自らの人生をシンクロさせながら力を尽くしている。
なかでも、ちょっぴり風変りな浪花のおっちゃんたちがすてきだった。本文に登場してもらった方たち以外にも、まだまだいる。お好み焼きや、たこ焼など大阪名物「粉もん」の店を全国展開している「たこ八」の代表取締役、曾根光庸さんは、「子どもたちの成長を長く応援したいから」と、二〇一五年四月から毎月一定額を井村シンクロクラブに寄付し続けている。
和菓子の「茜丸」会長、茜太郎さんは、合宿中の選手たちに折にふれては大量のどらやきを届けて喜ばれているし、水泳のパーソナルトレーナー、鳥羽大輔さんは井村シンクロクラブの選手の泳力強化にボランティアで一役買っている。みんな、いつのまにか井村さんのパワーに巻き込まれて気がつくと応援団の一員になっていた。
井村さんをはじめ、取材に応じてくださった方々のおかげで出版にこぎつけることができた。みなさまには、心からの感謝をささげたい。
コーチとは、乗る人を確実に目的地まで運ぶ馬車、と井村さんはよく話す。河出書房新社の野田実希子さんは、優れたコーチのように的確なアドバイスで私を目的地へと導いてくれた。最初に原稿を読み、私を野田さんに引き合わせてくれたのはフリーランスのライター、編集者として活躍している武田砂鉄さんだ。武田さんは河出書房新社の編集者だったとき、前作『アルビノを生きる』を世に出してくれた。お二人にも心からお礼の気持ちを伝えたい。
いまやスポーツがただ公正でさわやかなものだとは誰ひとり信じていないのではないだろうか。国際サッカー連盟(FIFA)の汚職事件、ロシア陸上界の組織ぐるみのドーピング疑惑、選手個人が起こした違法賭博事件など、不祥事は挙げればきりがない。
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック招致をめぐっても、実体のはっきりしないコンサルティング会社に日本が支払った高額の対価が賄賂ではないかと疑惑の目で見られている。大きくなりすぎたオリンピックなどの国際大会は、大量の札束が動く利権の温床にもなっている。
しかし、オリンピックの舞台で戦おうとしている多くの選手やコーチは別だ。黙々と重ねてきた練習を心の杖に、子どものころからの夢を実現するため全力を尽くす。
この本が、美しくも過酷なシンクロナイズドスイミングという競技や、それに献身する人々への関心を高める一助になるなら、こんなうれしいことはない。