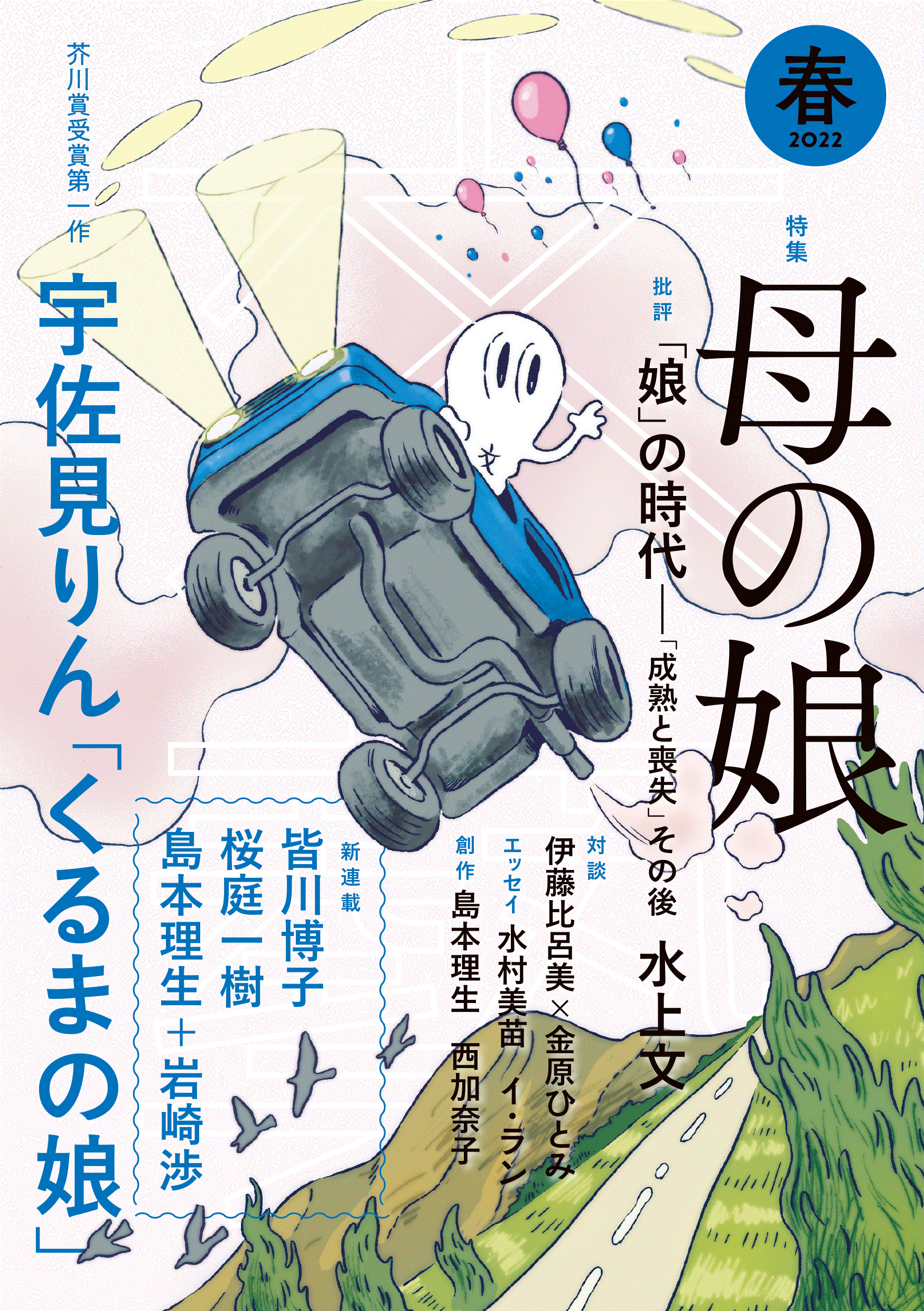単行本 - 文藝
言葉の淵に映るもの『少年聖女』
鹿島田真希
2016.11.17
『少年聖女』 河出書房新社
鹿島田真希 著
【評者】倉本さおり
言葉の淵に映るもの
なにかを「読む」、つまり与えられた言葉を解するとは本来、ひとりきりで昏い淵を覗きこむような行為だ。水面に映るそれはけっきょく、輪郭をあいまいにさせた自分自身の姿にほかならない。「わかった」と思って飛び込んだ瞬間、声の届かない場所に囚われてもがき続けることになる。
かつて「文学」というジャンルが持っていたはずの、禍々しくも健やかな苦しみ─それ自体を「愛」というモチーフに組み替え、見事に昇華させた労作が本書だ。
舞台は熱帯魚が泳ぐ水槽に囲まれたゲイバー。客である〈僕〉を相手に、店員が滔々と昔語りを始める。かつてこの店で働いていた男装の少女のこと。彼女がタマと名乗り、夜ごと下品で過激なショーを演じていたこと。ただひとりだけ彼女の正体を見破った男がいたこと……。いつのまにか語りの位相はなめらかに移行し、タマとその中年男・武史の不器用で荒々しい恋愛の行方がすこしずつ明らかにされていく。
タマは虐待を受けて育った。あえて自虐的なショーに身を委ねるのも、記憶の痛みから目を背けるためだ。そんな彼女に狂おしく恋い焦がれ、結婚にまでこぎつけた武史だが、タマの自棄的な態度は改まらない。おまけに親子ほど歳の離れた二人の関係に、周囲は冷やかな目を向ける。苛立った武史は次第に常軌を逸し始める。
心を麻痺させて生きてきたタマの言葉は、しばしば目の前の現実から遊離し、ひとりきりの世界へと回帰してしまう。ゆえにタマと武史の会話は、読者であるこちらが発狂しそうになるほど嚙み合わない。当初、武史は必死にタマの言葉の解釈に努めるのだが、そのうちに彼自身の言葉も高熱に浮かされたようになり、凄まじい勢いで物語の中に溢れかえっていく。
自分が馬鹿だと信じ込んでいるタマは、武史に向かってことあるごとに「叡智がある」という。それは同居していたベラルーシ人・オリガから自己流で学んだ言葉でもある。チェルノブイリの大事故を経験したせいで危機意識が壊れてしまったオリガは、徹底して自分に都合よく現実を解釈する。一方、武史がタマという異分子に向けるまなざしにだって、幼い頃に見たショッキングな光景に対する自問自答がふんだんに含まれている。要するに、この物語は各人が各人の解釈を─おそらくは夥しい誤謬と共に─重ねることで編まれているのだ。
〈「俺たちは、物語に出会って、夢中で階梯を駆け上がれば上がるほど、うつけと言われるんだ」〉。それぞれに「叡智」を得たうつけどもの物語は、やがて聞き手として外側から見守っていたはずの〈僕〉をも取り込み、実にロジカルな円環を描いて閉じる。そして本作があらかじめ二重構造をなしていた理由に膝を打つことになる。だが読後にゆっくりと立ちのぼるのは、むしろもうすこし小さな輪郭だろう。
混沌とした言葉の淵に飛び込むための肉体。他者と自分を厳然と隔てる、人ひとりぶんの領域。ほんとうの読書の悦びとは、それを確かめるための孤独で愛おしい営みのことなのだ。