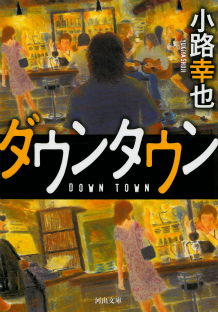花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 10
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2017.02.20

佐々岡睦美 十七歳
ついさっきまで向かい合っていたテーブルに
わたしだけ
遊園地に置き去りにされた子供みたい
楽しかったっていう文字が大きく浮かんで
でもふわふわと漂っていてどこかに消えてしまいそうで
優しさだけの愛は見えない?
傷ついた方が深く残る?
ひとりになるより
憎み合ってふたりで
別れの予感っていうのを感じていた方が淋しくない?
むーん、って唸ってしまった。
花歌の声は、不思議。
いや仮にも音楽をやっている人間が、不思議って言葉だけで片付けちゃマズイって思うけど、本当に不思議。
どうやって声を出しているのかまったくわかんない。
ウィスパーボイスで歌い出したなって思ったら、そこからグリッサンドで急にオペラ歌手みたいに張った声になっていく。その切り替えが、スゴイ。切り替えってわかんないぐらいに自然に急に変わっていって、それがめちゃくちゃ魅力的に聴こえてくる。
身体がブルッ、て震えちゃうぐらいに。
ハルオさんの歌い方とはぜんぜん違う。そもそも歌い方を習ってはいないだろうし、花歌は大好きな歌手とかも特にいないし。
自然に身に付いているんだろうなぁ。
「この歌詞はさぁ」
「はに」
「口に食べ物を入れたまま喋っちゃいけません、っていっつもうたばあちゃんに言われるでしょ」
「はって」
ごくん、ってドーナツを飲み込んだ。
「なに?」
「あれなの? お父さんのことを言ってるの?」
「おとん?」
いや? って花歌はきょとんとした。
「普遍的な男と女の間に横たわる深い川のことを」
「どこで覚えたそんなこと」
「ドラマで」
何のドラマですか。
「これいいねぇ」
「いいでしょ。なんかね、これはするするっとできたね」
「悲しい気持ちで?」
「やー」
ぐるぐると肩を回した。なんでそこで肩を回すの。ストレッチをするの。
「何か、こう、ね? ここんところ何曲も作ってみてわかったんだけどねツボへの入り方が」
「ツボには自分で入るもんじゃないよ」
「そうなの?」
まぁでも言いたいことはわかる。
「どうやってそのツボに入るの」
「プール」
「プール?」
「そう、プールにね、スクール水着を着てそっと潜っていくの」
「潜るとどうなるの。何でスクール水着なの」
「潜って、明るい方へ浮かんでいくと、雨の日だったら淋しくなるんですよ。しかもスクール水着だと」
本当にわからない。小さい頃からずーっと花歌と一緒にいるけど、この子の感覚はほんっとうにわからない。
「花柄のビキニじゃダメなの?」
「ビキニだったらね、浮かび上がるとそこはハワイなんだよ」
「行ったことないじゃん」
「ないけどハワイ」
わかってきた。
「じゃあそこで水着じゃなくてもいいんでしょ。学校の制服着てプールに入ったらどうなるの」
「そこは、天気によるね。天気によって、ケンカしたり泣いたり桜が咲いたりするんだよ。ジャージでも可」
ジャージでもいいのか。
「ジャージだとどうなるの」
「スカだね。ジャージはスカだよ」
わかんなーい。
でも。
「つまり、自分の中のある種の感情を引き出すために、まず形から入って引っ張り出すことを覚えたってことなんだね?」
花歌が眼を丸くした。
「そういうことか!」
「わかってなかったのか!」
花歌が笑った。
「さすがむっちゃんだねぇ。むっちゃんがいなかったらあたしゃ生きていけないよ」
「じゃあ、この曲の歌詞を書くために、まずはスクール水着を着たと。そして雨の日のプールに入っていったというわけですね」
「そういうこと」
きっと花歌の中に、雨の日の何かがあるんだ。自分でも気づいていない何かの感覚。それが、こんなふうな歌詞のイメージを増幅させるんだ。
「入るぞー」
お父さんのオーディオルームのドアがノックされて、同時にドアが開いてリョーチが入ってきたけど、その後ろに知らない女の人がいた。びっくりして思わず二人で立ち上がっちゃった。
「こんにちは」
女の人が、にっこり笑った。
「こんにちはー」
花歌と二人で挨拶したけど、誰?
「紹介する」
リョーチが言った。花歌も誰だろうってまた眼を丸くしてる。
女の人はニコニコしてる。何歳ぐらいかな。三十歳ぐらい? もっと上? すごく年上の女の人。スキニージーンズに白いブラウス。長くて黒いストレートの髪の毛がステキだし、真っ赤なフレームのメガネも似合ってる。
「スタジオミュージシャンのマイカさん。紺野マイカさん」
紺野マイカさん。
スタジオミュージシャン。
「ハルオさんのアルバムにはいつも参加していた人だよ」
「えっ!?」
花歌と二人でびっくりしちゃった。マイカさんは頷いて、中に入ってきて花歌の前に立った。
「花歌ちゃん!」
「はい!」
「おっきくなって! 美人になったね!」
えっ。花歌の眼がどんどん丸くなっていく。
「わたし、会ったことあるんですか?」
マイカさんが、花歌の手を取って握って嬉しそうに笑った。
「もちろん覚えてないだろうけど、私はまだ赤ちゃんのあなたを抱っこしたこともあるのよ。」
そうだったんだ。
「ハルオさんは小さいあなたをいっつもスタジオに連れてきてたから。あなたのオムツを換えたこともこともあるんだからね」
花歌が思いっきり背筋を伸ばした。
「お世話になりました!」
笑っちゃったけど。
「え、でもどうしてここに」
花歌が訊いたら、リョーチが頷いた。
「この間から撮ってる練習風景の動画を、もちろん歌っているところをアニキに送ったんだ。そしたら、アニキがマイカさんを紹介してくれた。もうプロを一人加えて、本格的な曲作りをした方がいいって」
「恭一さんが!」
「アニキはハルオさんといつも一緒にやっていた人、マイカさんもそうだけど、何人かと今も付き合いがあるんだよ」
マイカさんが頷いた。
「恭一くんにはね、私のアルバムのジャケットデザインをやってもらったこともあるんだよ」
「そうなんですか!」
さすが恭一さんだ。でもそうだよね。ハルオさんと一緒に仕事をしたんだから、そのミュージシャン仲間を知っていても当然なんだ。
「曲作りって」
言ったら、マイカさんは私を見て、にっこり笑った。
「あくまでも、私はサポート。恭一くんからも事情を聞いたし、凌一くんとも話した。そして、まだ未完成だけど花歌ちゃんの歌も聞かせてもらったし」
そこで、マイカさんは私の手を取って、ぽんぽんって軽く叩いた。
「睦美ちゃんね」
「はい」
「あなたがアレンジしてる譜面も見せてもらったし、あなたのサックスも凌一くんから聴かせてもらった。スゴイ!」
「え」
本当ですか。
「お世辞じゃないよ。私がここでお世辞言ったって何の得にもならないからね。そりゃあ天才的とは言わないけど、花歌ちゃんと睦美ちゃんは、二人でユニットとしてステージに立つとすっごく映えると思う。睦美ちゃんのアレンジもステキ」
マジですか、って花歌が口を開けて驚いてる。私も驚いてる。
プロのミュージシャンが、私を褒めてくれた。花歌がスゴイ才能を持ってるのはもちろんそうだけど。
「私も一緒に花歌と?」
うん、ってマイカさんが頷いた。
「それは、作戦」
「作戦」
「どんなに花歌ちゃんの歌が良くっても、花歌ちゃんの魅力を最大限に引き上げることを考えたら、睦美ちゃんが隣でサックス吹いて、二人で掛け合いで歌うと良いと思う」
「あくまでも睦美は謎の女ってことで」
「謎の女?」
リョーチがニヤッと笑った。
「ユニットの名前は作らない。表に出るのはあくまでも花歌の名前だけで、でもいっつも隣でサックス吹いてコーラスやってる女がいる。ぼんやりした花歌より顔がハデな睦美の方が目立つから、不思議な雰囲気が出る」
「ハデで悪かったね」
眼が大きくてハデってそれはよく言われるけど。マイカさんがうんうん頷いていた。
「私はね、花歌ちゃん、睦美ちゃん」
「はい」
「録音スタジオでどんなふうにしたらいいかをあなた達に教えるアドバイザー。もちろんサポートミュージシャンとしてキーボードも弾くわ。プロデューサーとディレクターはあくまでも睦美ちゃんと凌一くん」
「え」
凌一と私がプロデューサーとディレクター。
「睦美ちゃんは、花歌ちゃんの音楽を創り上げる。凌一くんは、二人のビジュアルを創り上げる。私は、花歌ちゃんの歌を創り上げる睦美ちゃんを全面的にバックアップする。どんな楽器や機材を使ったらいいとか、今のプロのやり方を教える」
スゴイ。そんなことが。
またリョーチの顔を見た。
「アニキからの指示だよ」
「え、でもね」
花歌が言った。
「マイカさん」
「なぁに」
「すっごく、すっごく嬉しくて倒れそうなんですけど、でも、わたしたち高校生で、スタジオ借りるお金もないし、マイカさんにギャラも払えないんですけど」
そう。その通り。プロはタダで仕事はしない。マイカさんは、またにっこり笑った。
「その通り。だから、後払い」
「後払い」
マイカさんは、小さく息を吐いた。
「私は、ハルオさんにもう一度戻ってきてほしいって心から願ってる。そして、花歌ちゃんの歌に惚れ込んだの。あなたを、〈ハルオ〉の娘であるアーティストとして世に送り出したいって本当に心から思った。それはきっとハルオさんに届いて、彼を呼び戻すきっかけになるかもしれないって思った。同時にね」
悪戯っぽく、笑った。
「ゼッタイに売れるって思った。花歌ちゃんは」
「そうですか?」
大きく、本当に大きくマイカさんは頷いた。
「だから、お金のことも何にも心配しないで。花歌ちゃんは花歌ちゃんの歌をうたえばいい。後は、私たちがやるから」
「私たち?」
そう、ってマイカさんが続けた。
「任せておいて。花歌ちゃんと睦美ちゃんを最大限に輝かせるスタッフを、ハルオさんに今も惚れ込んでいる仲間をすぐに集めるから」
仲間たちってことは、ミューージシャンの皆さんをってこと。
「本当に心配するな」
リョーチが言った。
「皆、花歌がやりたいようにやってくれるってアニキが言ってる。自分たちじゃできないことをサポートしてくれるからって」
今藤恭一 二十九歳
でも、だ。
ハルオさんの言ってることはわかる。
才能の枯渇なんて言葉があるけれど、まだ一応若者ではある俺は経験がないからわからないけど、才能ってものは枯渇するもんじゃないと思うんだ。
そりゃあ、時代の流れってものはある。自分の持っている感性が時代に合わなくなっていくっていうのも、そして自分で時代を作ることもできないっていうのは確かにあると思う。
あの頃、百人いたら百人がスゴイって思ったハルオさんの曲を、今の若い子が聴いたら半分はただ「ふーん」って思うだけかもしれないってのは、確かにあるはずだ。
それでも、その人の感性が劣ったわけじゃない。才能は消えないと思う。ひょっとしたら消えるのかもしれないけど、俺は消えないと思ってる。
だから、もしも、ハルオさんの中から何にも生まれてこなくて、それが恐怖なんだっていうのは何か別の原因があるんじゃないか。
「でも、ハルオさん」
「何だ」
「それと、家族を捨てることが何か関係あるんですか」
ハルオさんが、苦笑いした。
「それを言われると、辛い」
「何が辛いんですか」
ふぅ、と、ハルオさんは溜息をついた。そして一口グラスからメーカーズマークを飲んだ。飲んで、何かを考えながら頭を微かに揺らせる。
思い出した。これもハルオさんの癖だった。
眼を閉じたり、唇を嚙みしめたり、眼を大きくさせたり、とにかく表情を変えながら頭を揺らせて、何かを言おうと考える。
スタジオでよく見ていた光景。
「言葉にしちゃうと、すぐダメになっちまう」
うん? と思った。何かを言おうと思ったけど、ハルオさんはまだ考えている。
「歌詞って、勝手に出てくるんだよ。ムリヤリ引っ張り出した歌詞もそりゃあ今までの歌の中にはあるんだけど、そういうのは大抵すぐに忘れちゃったりするんだ。後から直したくなって皆を困らせたこともある」
ただ、うん、って頷いておいた。俺が何か言うとその表現にハルオさんが過剰に反応するような気がしたから。
「だから、説明するってことが、自分の中から湧き上がってくる何かをきちんとした言葉にしようとすると、ボケボケになっちゃうんだよな。さっきさ」
「はい」
「ある日突然、自分の中から何にも出てこなくなったのを想像してくれ、って言ったよな? オレ」
「言いましたね」
「でも、それもさ、ムリヤリ説明したんだ。そう言いながら、あぁなんか違うって思っちゃったけど、でも何が違うのが自分でもハッキリしなくて、それを考えていくとどんどん言葉が、思考が、ボケていくんだ。ピントがズレていくんだ」
ハルオさんの歌詞は、独特だ。
デビューした頃なんか、言葉は悪いけど頭がおかしい人間が書いてるんじゃないかって言われたこともある。でも、若い俺たちはその言葉の羅列に、リズムに、ものすごい心地よさを感じていた。
これだ! って思った。
そのリズムは、音律が、今なんだって。
それはハルオさんの中から何にも考えないで出てくるもんだっていうのは、知っていた。前に聞いていた。
「小説家、ってスゴイよな」
これは同意を求めていない言い方。自分一人で納得すればいい独り言みたいなもの。
そういう感覚が甦ってきた。
そうだ、ハルオさんと話すときにはこういう感じだったって。
「言葉をさ、自分が思っているのと同じ、ちゃんとした日本語に、言葉にできるんだぜ。だってそうしなきゃ伝わらないもんな。読んでいる人に」
まぁ確かにそうだろうけど。その辺は小説家じゃないからわからないけど、小説家が正しい日本語を、誰にでもわかる言葉を使っているのは確かだ。
「だからさ」
溜息をついた。
「困ってんだ」
「僕に、ですね?」
そう言うと、済まなそうな顔をして頷いた。
「何も説明できないんですよね。何をきっかけにして失踪したのか。何を考えて今ここでこうしているのか。これからどうしたいって思っているのか。言葉にしようとすると、全部が自分の手の平から逃げていくみたいなんでしょう?」
こくん、と、頷いた。
そうなんだ。
この人は、ハルオさんは、うたう人なんだ。
他に何もできない。それ以外に自分を伝える術を持たない人。天才って、そういうものなんだと思う。
そういう人が、うたえなくなっている。
その辛さだけは、説明してもらわなくてもわかるような気がする。
「美紀はさ」
「はい」
美紀さん。今、あの部屋をハルオさんに提供している女性。
「まぁ、夫がひどい男でさ。簡単に言っちまうとDVみたいなもんでさ」
そっちか。
「離婚したんだ。三年前に」
「あの家には、美紀さんと茜ちゃんだけなんですか?」
そうだ、って頷いた。
「美紀の実家だよ。お爺さんが建築家だったらしいぜ」
そうか。あの家はお爺さんが建てたものだったのか。
「じゃあ、もう美紀さんのご両親もいらっしゃらないんですね。お亡くなりになったか何かで」
ハルオさんは、唇を歪めた。
「まぁざっくり言うと、そうだ」
「ざっくりしか言えないんですね。すると、あのプレハブがどうして建っているのかも含めて美紀さんの生い立ちに何かがあるってことですね」
俺を見た。
「やっぱりお前って、鋭いよね。その辺変わんないよな」
それほどでもないと思う。普通に考えればそうなる。
「鋭いって言われたついでに言っちゃいますけど、怒らないでくださいね」
笑った。
「オレはお前に怒ったことなんかないだろ」
「周りの人にはけっこう怒ってましたよ」
そうか、って頷いた。
「そうだろうけど、オレも年を取ったからさ」
丸くなったって自分でも思うって。別に丸くなったハルオさんなんか嬉しくないとは思うけれど。
「美紀さんは、その人は、今までハルオさんみたいな男に出会ったことなかったんでしょう。お爺さんやお父さんも旦那さんも含めて、ある意味で、社会的にもとんでもない男に囲まれて育っちゃったんじゃないですか」
ハルオさんが、眼を丸くした。
「何でわかる」
「わかりますよ」
だって、ハルオさんはそういう人だ。
「自分で言ってたじゃないですか。『オレは女に繋ぎ止められてしまうんだ』って。今、ハルオさんが何年もこの街に住んでいるのは、その美紀さんに繋ぎ止められているんでしょう? 茜ちゃんの手を離せなくなっているんでしょう?」
唇を、歪めた。
「美紀さんは、初めてハルオさんのような、子供みたいに純粋な感性だけで生きている男性に出会ったんですよ。その気持ちがハルオさんはわかったんですよね」
ハルオさんは、下を向いた。それから、小さく頷いた。
「ひどい話さ」
また大きく息を吐いた。
「聞いたこともない、ひどい話。話したくもないから、言わない」
きっと世の中にはそんなのがゴロゴロしているんだ。俺は、自分が平和な世界に生きられて幸せだってわかっている。
「まぁ、あのコンテナみたいな部屋に、ある意味でだぞ? 本当にそうだってわけじゃなくて、あの家の女性たちは閉じこめられていたみたいなもんなんだ。それぐらいは教えないと、オレがどうしてあそこに住んでいるかわかってもらえないかもな」
閉じこめられていた。
「お祓いみたいなことをしてるんですか。俺は全然平気だぞって。あんた方をそのおかしな呪縛から解き放ってやるぞって?」
ハルオさんが、笑った。
「すげぇな。よくそんな言葉がするっと出てくるな」
「若いもんで。そんな設定のマンガやアニメやゲームやラノベなんて、ごまんとこの世にありますよ」
そうか、って頷いた。
「オレは、そういうのに疎いもんな。全然興味なかったから」
たぶん、美紀さんと茜ちゃんの境遇なんて俺が知らなくてもいいことだ。きっと知ってほしくもないだろう。
ただ、ハルオさんがあそこに住んでいることで、普通に暮らしていることで、二人が救われているのは事実なのかもしれない。そうじゃなきゃ何年も一緒に過ごせないだろう。
「セックスしてるんですか」
「ストレートに訊くなぁ。男女の関係とかでごまかせよ」
「男二人で話してるんだからいいでしょ」
まぁそうか、って笑った。
「まるでないとは言わないけど、茜ちゃんがいるからな。あの年頃の女の子ってそういうのに敏感なんだ」
「それは」
花歌ちゃんっていう自分の娘がいるからこそわかることですか、って皮肉を言おうとしてやめた。
「どうするつもりですか」
「何が」
「とぼけないでくださいよ。それを訊かなきゃ、俺は帰れないじゃないですか」
このままこの街でずっと暮らすのか。
それとも、あの家に帰るつもりがあるのか。
でも、きっとその答えをハルオさんは持っていないんだろうと思う。
「そうだよな」
それを訊くために捜したんだもんな、ってハルオさんは言って、大きく息を吸って、吐いた。
「お前の顔を見るまで、何も考えないようにしていた」
そうなんだろうな。
「僕を見て、思い出しましたか? それを考えなきゃならないって」
「たぶんな」
でも、それを考えたって、結論なんか出ないんじゃないか。そんな簡単に結論が出るんなら、何年も失踪なんかしていない。
たぶんだろうけど、ミュージシャンにとってステージには魔力みたいなものがあるんだと思う。
一度でも、ステージに立って喝采を浴びた人間は、いつまでもいつまでも、死ぬまでその魔力に取り憑かれる。それがたとえ小さなライブハウスだったとしてもずっとその素晴らしさを忘れられない。
ましてや、ハルオさんはトップを駆け抜けてきた人だ。
そういう人が、ここまで、そう表現していいなら墜ちている。そのステージにもう一度立つことさえ考えられないぐらいになっている。
溜息が出た。
言わなきゃならないんだろうか。
俺が言うべきことじゃないと思うけど、ここまで来て、ハルオさんに会って、今は戻れないって言われただけで帰ったんじゃあ、俺自身もやりきれないし、うたさんに報告もできない。
傷跡を残さなきゃ、ダメなんだ。
ハルオさんはそういう人だ。
責任とか義務とか社会性とか、ましてや家族の情愛みたいな、そんなもので動く人じゃない。
自分の心に、魂に、何かが残らないと動けない、動かない人だ。
「ハルオさん」
「おう」
「ハルオさんがやったことは、うたさんと、花子さんと、花歌ちゃんの代わりにその人の、美紀さんと茜ちゃんの手を取っただけじゃないんですか? ただ逃げてきたのに、逃げた先で結局女に繋ぎ止められて、自分が離してきた手のことを忘れようとしているだけじゃんじゃないかな?」
ハルオさんが、睨んだ。
睨んだけど、またメーカーズマークを一口飲んだだけだった。
もっと押さなきゃダメか。
「ミュージシャンとして自信を失った。何も浮かんでこなくなった。どうしてかまったくわからなかった。わからないけど、自分には家があった。家族がいた。自分にあるものが自分を腐らせていると思った。ハルオさんの歌の歌詞にありますよね? 『暮らしてると腐るんだ』って。そんなのが頭の中に広がっていってどうしようもなくなって家を出たんでしょ?」
黙って下を向いている。
「出てみた。ふらふらしてみた。でも、何にも出てこなかった。そのうちに今度は自分一人のたった一人の気楽な暮らしがハルオさんを本当に腐らせたんじゃないですか? 自分でもどうしようもならなくなって、たまたまそこにいた人の手を握ってしまったんでしょ。それで、今度はそこから離れられなくなったんだ。要するに」
俺だって、こんな言葉は吐きたくない。
「ハルオさんは、今のあんたは、野良犬にさえなれない、死ぬほどの絶望も戻る勇気も持てない、ただのクズ以下の中年男だ」
(つづく)