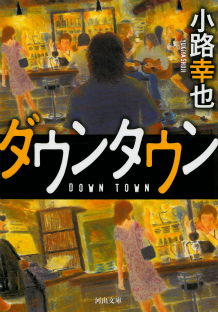花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 4
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.08.24

今藤恭一 二十九歳
〈ハルオ〉は俺たちの世代にとってはマストなアーティストだったよ。
小学校の頃からずっと〈ハルオ〉の歌とパフォーマンスは大好きだったし憧れだったし、日本のアーティストで自分にとってのナンバーワンは誰かって訊かれたら、俺は迷わずに〈ハルオ〉って答える。
別にミュージシャンを目指したわけじゃないけれど、高校時代からデザインに興味を持って、そういうものを見る感覚を高めていけば自然と音楽にだって精通してくる。デザインっていうのは結局人間の感覚で〈気持ちの良いもの〉を追求していくことなんだ。そこに、音楽ってものは欠かせないから。
だから、本当に〈良いデザイン〉って、人を幸せにするんだ。そういうものが〈良いもの〉なんだ。
〈ハルオ〉は、大多数の日本人にはない感性を持って生まれていたんだと思う。
リズム感とか、メロディーラインとか、考え方とか、日本のミュージシャンが持っている〈日本人〉っていう呪縛から全部解き放たれているような感覚。
何だろうな。身体の内から湧き出るものがまるで違うって感じなんだ。アフリカの未だ文明に触れていないような部族の人が伝統的に踊るダンスみたいに、〈ハルオ〉からは〈ハルオ〉しか持っていないものが溢れてくる。
表層的にはあくまでもポップなロックなんだけど、その根っこにあるものはまるで違うように思えるんだ。
その〈ハルオ〉が、自分の弟の同級生のお父さんだったっていうのはマジで衝撃というか、めっちゃ驚いたし喜んだ。まぁもっと言ってしまえばそもそもがご近所さんだったっていうのにも驚いたけどね。
弟の凌一が生まれたのは俺が十二歳、小学校六年生のときで、そりゃあもう嬉しかったよ。兄弟がずっと欲しかったからね。
本当は妹の方がよかったんだけど、弟でもめちゃくちゃ可愛かったし、可愛がった。ずっと僕が面倒見るんだって思っていたけど、すぐに僕が中学生になって部活とかで忙しくなって、遊んであげることはあんまりなくなっていった。それは、しょうがないよな。男ってそういうもんじゃないかと思う。
凌一が小学生になると俺はもう大学生で家を出てしまったから、ますます会わなくなったし話もしなくなった。
でも、〈ハルオ〉の娘である花歌ちゃんの話は、凌一にとっては仲良しの同級生の女の子については、いつも凌一から聞いていたんだ。
俺も気になっていたからね。ああいう父を持つ子供がどんなふうになっていくのかって。
まぁ、そんなのもあって、凌一にとってはすごく面倒見てくれる兄貴じゃなかったかもしれないけど、いろいろ話す機会はあったし、特に仲が悪いわけでもない。めっちゃ良いわけでもないかもしれないけど。
凌一は今、俺が実家に残していったMacでいろんなことを覚えて、映像やデザインや音楽とか写真とか〈表現〉することをいろいろやってるようだけど、そういうのはやっぱり兄としては嬉しいかな。俺も少しはあいつに影響を与えられたのかなって。しかも、けっこうあいつセンスいいからね。感覚的に尖ったものがあるから、ひょっとしたら凌一は俺なんかよりずっとすごい表現者になるかもしれないって思ってる。
そう、大学生のときに、〈ハルオ〉から突然俺に連絡があったときには本当に驚いた。
俺が大学で作っていたポスターやビデオを、たまたま凌一と花歌ちゃんを通じて〈ハルオ〉が見て、そして気に入ってくれたんだ。
それで、〈ハルオ〉のツアーのビジュアル面を全部任せてもらった。
あれは、マジで凄かった。
興奮した。
こんなことって実際に起こるんだなって、奇跡ってあるんだなとまで思ったよ。自分の大好きなアーティストのツアーを、ビジュアル面でプロデュースできるなんて。
ある意味では、最初で最後の、すげぇ体験だったのかもしれない。いやもっともっと上を目指さなきゃならないんだけどさ。
大学を出て、デザイン会社に勤め始めて、大きいのも小さいのもいろんな仕事をさせてもらったけど、まだ大学生のときにやった〈ハルオ〉の仕事以上に興奮させてくれるものはなかった。
いや、過去形にしちゃまずいな。俺だって末端とはいえ現役のデザイナーだ。
まだ、ないんだ。これからきっとやってみせるって思ってる。
そう。
あのツアーから、俺がビジュアル面をプロデュースしたツアーが終わってから、ほんの一ヶ月後だったな。
〈ハルオ〉が失踪したのは。
「マジですか」
恵比寿に住む俺の部屋の近くの、どこにでもあるようなファミレスの喫煙席。
午後十一時。
佐々岡先生が話があるから会ってくれないかって言ってわざわざ来てくれたから、何事が起きたのかって思ったよ。
佐々岡幸一先生。実家の近所の獣医さん。
実家にいる猫のフミもいつもそこで診てもらっているし、先生の娘さんの睦美ちゃんは、花歌ちゃんの親友だ。それこそ生まれたときからいつも一緒にいて、姉妹みたいに育ってきて、そこに俺の弟の凌一も絡んでいる。
あの連中は本当に小さい頃から、高校生になった今もすごい仲良しみたいだ。
俺は割りと、自分でそれを望んだとはいえ、ぼっちの方だったからあいつらの話を聞いているとちょっとだけ羨ましい気持ちも出てくる。二十九歳のアラサーになってから考えると、だけど。中学や高校時代にもっと友達と絡んでおけば、自分の幅ってものももう少し拡がっていたんじゃないかって。
「マジなんだよ恭一くん」
佐々岡先生は顎髭の辺りをゴシゴシと擦りながら言う。俺は、ううん、と唸るしかなかった。
「まぁ、失踪した時点である程度は予想してましたけど」
「していたか」
「だって」
いい大人が失踪する理由なんて女か金じゃないか。だから、〈ハルオ〉の失踪もそうなんだろうなって気はしていた。
「才能の枯渇から来る恐怖から、それまでの人生を捨てて逃げ出した、なんてことは考えなかったか。同じ才能で勝負するグラフィックデザイナーとしては」
佐々岡先生が言うけど。
「や、俺は、あの人に限ってそんなのはないなって思ってたんで」
「そうなのか?」
そんな気がする。あの人は、〈ハルオ〉は、才能なんていう言葉だけで括れるものじゃないと思う。
「もう、全身の細胞のひとつひとつが自分の音楽って感じじゃないですか。だから、あの人が音楽辞めるときはただ死ぬときだなって」
「全身の細胞か」
腕組みをして、佐々岡先生が唸るように言う。
「そうです。細胞のひとつひとつが、それこそ全部〈ハルオ〉」
「確かに。そう言われたらそうかもしれないな」
コーヒーを飲んで、先生が頷く。
「おもしろいな。そんなふうに考えるものなんだな」
「いや、あくまでも僕個人は、ってことですけど」
「いや、確かにそうだ。やっぱり人は資質ってものがあるんだな。ただの獣医には考えもつかない発想だ」
「いや、獣医さんってだけで凄いんですよ?」
そう思う。別に相手を羨むわけじゃなくて、努力しないとなれない職業に就いている人は尊敬する。別にデザイナーが努力していないわけじゃないけれど、僕らみたいなのはそれこそ持って生まれた感性である程度成り立ってしまうところが大きいから。
佐々岡先生が、ポン、と自分の腿の辺りを叩いた。
「そこでだ」
「はい」
「そうまでハルオのことを理解しているであろう、恭一くんにお願いなんだが」
俺を見た。一泊置いたので、こっちから水を向けた。
「まさか、博多まで行って、ハルオさんが今どうしているかを調べてきてほしいってことじゃないですよね」
「わかったか」
ハルオさんが博多にいる。女と一緒でしかも子連れかもしれないって聞かされたときに、そうじゃないかって思った。
あそこの一家に、花歌ちゃんの家族に内緒で会いに行って調べてもらえないかって頼まれるんじゃないかと。
その理由は、俺がハルオさんとたとえ一瞬でも親しく仕事をしたこと。凌一を通じてプライベートでも付き合いがあったこと。
何よりも、俺が独身でしかも今は独立してフリーで仕事をしているから、だ。
「まさか、佐々岡先生が博多まで行けるはずもないですもんね」
「すまんが、行けないなぁ」
獣医さんは大変だ。毎日、生き物の相手をしているんだ。それも治すだけじゃなくて野良猫や野良犬の保護活動もしている。家族旅行なんか一度もしたことがないって聞いているし、そうだと思う。
「もちろん、博多までの交通費や向こうでの宿泊代は私が出す。問題は恭一くんの仕事の状況なんだが」
「まぁ、それは」
何とかはなる。別に今日明日にすぐに博多へ行かなきゃって話でもないだろうから、抱えている仕事が片づけば、一週間ぐらい九州旅行したってどうにかはなる。こういうときに一人でやっていると確かに便利なんだ。今までにもふっと空いた時間に一泊で旅行に行ったことは何度もある。
そして、自分で費用を出してまで、佐々岡先生があの家族のためにしてやろうって思うその理由も、わかる。理解してる。
佐々岡家と岩崎家は大昔からの付き合いなんだ。血は繋がっていないけど、親戚よりも親しいって言っても過言じゃないはず。
花歌ちゃんのお祖母さん、うたさんと、佐々岡先生のお父さん、先代の佐々岡先生は幼馴染みなんだ。それ以前に、うたさんの親と先代の親がもう親友であり、共に出征して帰ってこられた戦友であったってことも知ってる。
二人の間には、血よりも強い結びつきがあったって話だ。
その話をちらっと聞かされたときに、いろいろとうたさんの話を聞いてみたいと思ったこともある。そういう話は、好きなんだ。
じじくさいって思われるけど、昭和の時代には興味があるんだ。もちろん、グラフィックデザインの方面もそうだ。デザインは時代を反映する鏡だ。明治、大正、昭和、そして戦前、戦中、戦後の日本のデザインを俯瞰したいといつも思っているし、いろいろと調べたりもしている。
同時に、デザインは人の生活に密着するものだ。だから、お年寄りの小さい頃の話や若い頃の話を聞くことも楽しい。機会がなくて、今までうたさんと話したことはないんだけど、いろいろおもしろい人生を送ってきたらしいから、ぜひじっくり話を聞かせてほしいんだ。
でも。
「あの、その前にですね」
「うん」
「ハルオさんのご両親のことなんですけどね」
そっちだな、って感じの表情で先生が頷いた。かなり複雑な事情があるとチラッと聞いたことはあるんだけど。
「複雑と言えばそうだが、よくあると言えばよくある話だ。母一人子一人だよ。生まれてすぐに父親はどこかへ逃げちまった」
「逃げたんですか」
うん、って頷く。
「しばらくして死んだことがわかったそうだ。ハルオが小学生の頃だな。何でも暴力団のいざこざに巻き込まれたらしい」
そっちか。
「それで、母親が頑張っていたんだが、夜の商売でな。こちらもそのうちに面倒臭くなって今で言う育児放棄だ。母親らしいことはなにひとつしてこなかった。唯一の救いは、ハルオを殺さなかった、死なせなかったことだな」
「今、そのお母さんは」
先生は、渋面を作る。
「施設に入っている」
「施設」
「ハルオがな。最後まで見捨てなかったのさ」
痴呆症が進んでしまって、もう息子も息子だとわからなくなっていると先生は続けた。
「命を預かるものとして言う言葉ではないが、いつその日が訪れてもおかしくない状況だそうだ。だからまぁ、それもある」
「連絡をつけたいってことですね。いざというときに」
「そうだ」
そうか。ハルオさんは、そこも放棄して逃げているのか。
博多か。
ハルオさんを捜す旅か。
そして、失踪の理由を確認するのか。
「もし、ハルオさんに会えたとして」
「うん」
「その理由も確認できて、本当に別の女性と子供がいたら、どうするんですか? うたさんに伝えるんですか?」
佐々岡先生は、眉間に皺を寄せて、頷いた。
「伝える」
「離婚させるとか?」
「それは、ハルオと花子さんの、夫婦の問題だ。私たちが口出しするところじゃないからな」
「じゃあ」
冷たいような言い方になっちゃうけど。
「放っておいてもいいんじゃないですか? 何がどうなるにしても結論は夫婦間で出すしかないですよね。事情を今知ろうが後で知ろうが、変わんないんじゃないですか」
うん、と、佐々岡先生は頷いた。
「確かにそれはそうなんだがな」
言いながら先生は、俺に向かって指を二本、Vサインのようにして出した。
「すまん、一本貰えるか」
「あ、どうぞ」
煙草をカバンから取り出して、先生に箱ごと渡した。ライターも。先生は普段は吸わないんだけど、ストレスを感じたときにだけ吸うそうだ。俺は我慢できるから喫煙席じゃなくても良かったんだけど、たぶん先生が吸いたかったんだと思う。
「単純に、俺は友達として、ハルオを心配してる」
それはそうだと思うから、頷いておいた。佐々岡先生とハルオさんは小学校と中学校で同級生だったそうだ。
その頃のハルオさんはただの変わり者というか、突拍子もない行動ばかりする男子で、あまり学校からも友達からも良く思われていなかった。そんな中で、佐々岡さんだけはハルオさんの不思議な魅力と才能に魅かれていて、ずっと仲の良い友達で居続けたって聞いている。
「そして、友達の奥さんになった花子さんももちろん、心配している。彼らの行く末がどうなろうとも、二人ともに見続けていくつもりなんだ。もしも、自分が関わることで彼らの関係修復に少しでも力になれるなら、そうしたいと思ってる」
何よりも、って先生は続けた。
「子供を持った親として、ハルオに言いたいことも聞きたいことも多い。あいつは本当に花歌ちゃんを大事に思っていた。眼の中に入れてもいたくないって表現があるが正にそれだった。それは同じ女の子を持った親として私がいちばんよくわかっている。それなのに、何故、花歌ちゃんを置いてあの家族を捨てて失踪しているのか」
話している内に、感情が昂ぶったのかもしれない。先生の頬が紅潮していた。
「誰よりも先に、私がそれを聞きたいと思ってる。だからまぁ」
煙草の煙を吐き出した。
「単純に、私のわがままだ。友人に対する思いだ。それを自分でやらないで君に押し付けてしまうのはどうかと思ってはいるが」
頷いておいた。
気持ちはわかる。
結婚していないし子供もいないけど、男の友人に対する思いとしては理解できる。ぼっちが多かった俺にだって、心を許した友人の一人や二人はいる。もしもあいつらが突然失踪したら、そういう気持ちになるだろう。
「博多には大学時代の親しい友人が何人かいますから、泊まるところは何とかなりますよ。大丈夫です」
「行ってくれるか」
先生が俺を見た。
「あと二日もしたら、今の仕事は片づきます」
考えてみたらフリーになって三年。必死でやってきて長い休みなんか取ったことはない。
それこそ、旧友を訪ねる休暇のついでだと思えばいいし、何よりも。
俺も、ハルオさんに訊きたい。
どうして音楽を捨てているのかって。
「でも、ひとつだけ、いいですか?」
「なんだい」
「博多に行く前に、うたさんに会っていいでしょうか」
「うたさんに?」
岩崎うた 六十七歳
年寄りだからって皆が早寝するわけじゃあない。
特に私は昔から、子供の頃から宵っぱりだった。だから朝も遅いというわけじゃあなくて、朝もそれなりに早く起きられる。
睡眠時間が短くて済む体質なんだろうね。低血圧とも無縁だったし、年を取ってもいまだに高血圧とも無縁。大きな病も怪我もせずに今までやってこられた。丈夫な身体に産んでくれた両親に感謝すべきなのだろうけれど、その親が二人とも早くに死んじまったっていうのは本当に皮肉だね。
むしろ、親が早くに死んで私のために命を使ってくれたって思った方がいいのかねって、考えているよ。
若い男から、会いたいけどできれば人目のつかないところでって話があったのさ。浮いた話ならまぁどうしましょうってなるところだけど、そうじゃないのさね。幸一からも話しがあったから、まぁハルオについてなんだろうって見当はついた。
私の家族には内緒にしたい、と。そして仕事があるからできれば夜に、と。
それならば、口が堅いところで晩ご飯でも食べた方がいいだろうって話になるね。幸いにも、そういうところの伝手だけはたくさんある。こんな年になったって付き合いがあれこれあるから、夜に外出したところで花子も花歌も疑問には思わない。
駅からは少し離れるけれど、〈廉清〉にしましょうかね、と言っておいた。あそこなら離れの和室があるし、亭主の清政は男気のある奴。どんな内緒話をするために客が来ようとも、放っておいてくれる。もっとも古い馴染みに限る話だけれども。
恭一くんね。
今藤恭一くん。
確か、もうすぐ三十ぐらいだったかしらね。
以前に会ったときには、話したときにまだまだ小賢しいところはあると感じていた。もう少し謙虚にならなきゃ男は駄目だと思ってはいるけれども、それはまぁ三十前の男に求めてもしょうがない部分だろう。
花歌と、睦美ちゃん。そして、今藤凌一くんだね。
文字通り、同じ幼稚園、小学校、中学校、そして高校と通ってきた幼馴染みだ。
でも、幼馴染みだからといって、全員が仲良しになるわけでもない。遊んでいるうちに離れる者は離れる。合わない人間が出てくる。
人間ってのは、不思議だね。
この年になっても、友達になるかならないかの差がどこで決まるのかわからない。単に性格の相性の問題だと言っても、じゃあその性格はどこで決まるのかと。
良くない親はいる。どうしても、いる。
その良くない親から生まれた子供もやっぱり良くないかと言えば、そうでもないのさ。親に影響されなくて良かったと思う子供たちもいる。環境が性格を作ると言うが、良くない環境でも良い子が育つこともある。どんなに心が傷だらけになったとしても、その傷を自分で治しちまう子供もいる。
だから、人間はおもしろいんだろうね。生きていても退屈しないのかもしれないね。
花歌と睦美ちゃんと凌一くんは、仲良しになった。
その仲良し同士の、凌一くんの、兄。
今藤恭一くん。
今藤さんとは、単に子供を通した付き合いしかないね。家は確かに近所と言ってもいいところだけど、田んぼに囲まれた田舎じゃあるまいし近所の人間と全部付き合いがあるわけじゃない。
花子の話では、今藤さんの旦那さんは自動車メーカーの営業マンだそうだ。奥さんはパートを持ってはいるが基本的には専業主婦。奥さんと花子はPTAとして付き合いはあったものの、花歌も凌一くんも高校生になった今はほとんど会うこともない。ごくたまに、仲良しでどこかへ出かけたときに連絡し合うぐらいだ。
息子さんが二人。恭一くんと凌一くん。
私も子供は花子しかいないからあれだけれども、男の子二人が家にいると賑やかだったろうね。
我が家との付き合いは、凌一くんが産まれてからになるから、兄の恭一くんがどんな子供時代を過ごしたのかは詳しくはわからない。
凌一くんが家に遊びに来るようになって、お兄ちゃんがいるって話になって、パソコンに詳しくていつでもパソコンの前にいるってね。何度かしか、顔を見たことはなかった。それが、ハルオの眼に留まって、一緒に仕事をすることになった。
あいつは、喜んでいたよね。
こんな身近に凄い才能を持った男が潜んでいたってね。嬉しかったんだろうと思うよ。自分の身内みたいな近いところに、共感できる才能を持っている男がいたってことがね。
「買いかぶりです」
恭一くんが、少し恥ずかしそうに笑う。その言い方に、以前とは違う慎み深さが感じられて、おや、と思ってしまった。
男子たるもの三日会わざれば、かね。
自尊心ばかり強くて、傷つくことも怖くて、ただ愛想笑いで躱すことばかり上手くなっている近頃の若い男の一人なんだと思っていたけれども、少しは成長したのかもしれないね。
経験を重ねて、社会の荒波に揉まれて、いい男になったのかもしれないね。
細面に、黒縁の眼鏡。髪形はまぁ社会人としておかしくはない程度の、若者の髪形。もう少したくさん食べた方がいいんじゃないかっていう体形。
凌一くんとはあまり似ていないんだ。花歌の話じゃあ、凌一くんはお母さん似で、恭一くんはお父さん似らしい。
「僕は、ちょっとだけハルオさんに共感してもらえるところがあって、そこで拾ってもらったようなもんです」
「それでも、あのときは評判になっただろうさ。結果的に今のところ、ハルオの最後のツアーになってしまったんだからね」
「そうですね」
静かに頷く。その頷き方ひとつ取っても、やっぱり以前とは違うね。いろいろあったんだろう。
人はね、仕草ひとつに品性が現れるものだよ。そしてね、品性は生まれつきのものも確かにあるけれども、自分で意識して育てられるものなんだよ。
「でも、そこからもっといろんな仕事に繋げられてこそなのに、僕はまだまだです」
「それはしょうがないよ。あんたはまだ大学生だったんだからね。社会ってのは学生には優しいけれど、同時に自分の分野に土足で踏み込んでくる学生には厳しいもんなんだよ」
「それは、ひしひしと感じました」
「だろうさね。小童が何してくれるんだってものだよ。ハルオが引っ張ってきたから周りは何も言わなかっただろうけど」
出る杭は打たれる。それは、どんな時代になっても変わらない。打たれても気にしない、沈んでいかない人間が金持ちになったり大物になったりするんだろうけれども。
「打たれて、初めて自分に気づくってものもある。まだまだこれからだろうさ」
「はい」
〈廉清〉は小料理屋ではあるけれども、我儘を言えばできるものなら何でも作ってくれる。ばあさんと若い男がコースでゆっくり酒をってのもあれだからね。品数を多くして和定食を二つ作ってもらった。もちろん、恭一くんには肉を多めに。私には、少なめに。
「ビールをもっと頼んでもいいんだよ」
「いや、もうけっこうです。そんなに飲まない方なので」
「最近は増えているよねぇ飲まない若い子が」
恭一くんが頷いた。
「僕の周りでも、飲まない人間が多いですね」
「そういうときの宴会なんかはどうするんだい。盛り上がりに欠けるんじゃないのかい」
「そんなことはないですよ。飲まない人間ほどわりと盛り上げ上手なのが多いですね」
いろいろあるだろうね。時代が変われば人間も変わっていくんだろうから。
「それで?」
一通り、出てきたものを味わったところで訊いた。
「ハルオの話だと思うんだけど、わざわざこんなふうにして会わなきゃならない話ってのは、なんだい」
小さく頷いて、恭一くんが箸を置いた。
「いいよそんなの。食べながら話そうじゃないか。知らない仲でもないんだから」
「すみません」
軽く頭を下げて、また箸を持つ。そうだね、そういうことができるようになったっていうのも、やっぱり成長しているんだね。
その調子なら、きっといい仕事も廻ってくるだろうさ。
「実は、ハルオさんを捜しに博多に行こうと思っているんです」
博多に。
思わず顔を顰めちまった。
「ひょっとして、幸一に頼まれたのかい」
「そうです」
素直に、こくん、と頷いた。
「何だって恭一くんに。赤の他人じゃないか」
「それは、いいんです。赤の他人でも僕は〈ハルオ〉のファンですし、一度は仕事をした人間ですし、何よりも近所の男です。きっと何があっても、冷静な対処ができると思うんです」
真っ直ぐに私を見る。その眼に誤魔化しはないね。本当に捜しに行くことに躊躇はないんだろう。
今度は、私が箸を置いた。背筋を伸ばして、一度頭を下げる。
「申し訳ないね。身内のごたごたに手を煩わせてしまって」
「いえ、とんでもないです」
それにしても、だ。ここであまりに恐縮しても恭一くんが迷惑がるだろうから、また箸を取る。
「幸一がそんなことを頼むってことは、何かがあったってことかい。私が聞いている以上のことが」
「それは、ないです。たまたま博多に大学時代の友人がいるんです。佐々岡先生と話をしたときにそんな話になったら、ハルオさんが博多にいるかもしれないって聞かされたんですよ。それで、じゃあと」
なるほど。
「でも、勝手に捜すというのもなんだし、ここはうたさんに一応確認してから行こう。ついては、もっと踏み込んだ話をしてから覚悟を決めて捜した方がいいんじゃないかと思ったんです」
踏み込んだ話ね。
「そういうことかい」
そうです、と、恭一くんが頷く。
「失踪している理由だね」
「その話です」
男が失踪するのに、大した理由なんかないだろう。誰もが思いつく。金か女だね。恭一くんが続ける。
「仮に、僕がハルオさんを見つけたとします。一人でいるなら僕も声を掛けるのに躊躇しないでしょう。でも、もしも」
「女と暮らしていたら、だね」
「そうです」
「もっと言えば、そこに小さな子供でもいたらどうするんだってことだね」
「はい」
唇を引き締めて、恭一くんが頷く。
「そんな事態になっていたとき、僕は声を掛けて事情を訊いた方がいいのか。それとも黙って観察して、報告だけすればいいのか。それを、うたさんに決めていただいた方がいいと思ったんです」
その通りだね。真っ当な考え方だ。
「ハルオがそれを許したのなら、じっくり訊いておくれ。問い詰めるんじゃなくて、男同士の話としてね。ただし」
「ただし?」
小さく息を吐く。そういう事態はもちろん、想定していた。
「向こうの方に迷惑が掛からないようにね。つまり、子供がいてそれがハルオの子供だっていうんなら、その子が悲しい思いをしないような形で話を聞いてきておくれ」
「どうしてですか?」
「どうしてとは?」
恭一くんが、少し眼を細める。
「こっちには、花歌ちゃんがいるんです。花歌ちゃんは悲しい思いをしているはずです。それなのに、向こうに気を遣うんですか?」
「それは、当たり前のことだよ」
当たり前ですか、って少し驚いたように恭一くんが言う。まぁ、その辺は個人の考え方かもしれないけれどね。
「花歌は、もう高校生だよ。同じ子供とはいえ、年が違う。これはあくまでも向こうに子供がいたとして、そしてその子が花歌よりずっと小さい子供だったら、という前提だけどね」
「はい」
「大きな子供は小さな子供を守る」
どんな状況であろうとも。
「それは、大人が子供に教えなきゃならない、人の道だよ」
恭一くんが、唇を引き締めた。
「男と女のことなんざぁ、当人同士の問題さ。ハルオと花子が離婚しようが何しようが私は文句を言わないよ。でも、自分たちの子供には責任ってものを果たさなきゃならない。そして」
「大きくなった子供にも、その責任は生じるってことですね」
「そういうことさ」
古臭いことを言う婆ぁと思われるだろう。私だってまだ七十も行っていない六十七歳。昭和二十五年生まれの、戦争を知らない世代だよ。その時代がどんなに苦しかったかなんてのは、まったく記憶にない。父母に聞かされた話でしかね。
それでも、小さい頃のこの国の様子はよく覚えている。
「昔は良かったっていう話じゃないよ。むしろ、今の方がずっと良い時代だって私は思っているよ」
「そうですか?」
「そうだよ。こんな便利な世の中は、当たり前だけど今までにないよ。住みやすいったらないじゃないか」
細かいことを言っていくと切りがない。
「私が子供の頃は、もう国中が、新しい言葉で言えばカオスの時代だよ。未だ戦争を引きずる影と、高度成長の光がいっしょくたになっていた。何を頼りにすればいいのかって思えば、とにかく前へ進み続けることだけさ。二度と悲惨な戦争時代にならないようにってね」
「豊かで便利になれば、戦争なんか起こらないって考えていたんですね」
「庶民はね。だから、それぞれが、それぞれにできることをやっていた。子供もそうさ。自分たちの妹や弟、周りにいる小さい子供たちの面倒を、忙しい大人に代わって見ることが当たり前だった」
もちろん、それ以前の時代から、ずっとそうやってきたはずだ。人間ってのはそういうもんだと私は思っているよ。
「もし今の時代に失われているものがあるとするなら、それさ」
小さきものを守る。自分もそうされたから。
そういう正しい連鎖が、失われつつあるから、嫌な時代だと思われているのかもしれない。
(つづく)