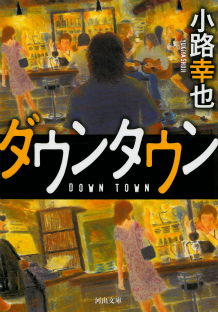花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 3
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.07.25

宮谷花歌 十七歳
お揃いのパジャマがあるんだよ。わたしの家にもむっちゃんの家にも。それはわたしたちが小学校の頃からずっと。
それぞれの家によくお泊まりに行ってたから、どっちの家でもお揃いのパジャマを用意するようになって、それがずーっと今も続いてる。
だから、わたしとむっちゃんはいつでもそれぞれの家で寝られるんだ。
まぁそんなにしょっちゅう泊まったりはしないけどね。一ヶ月に多くて三回とか、そんな感じ。
すっごく仲の良い友達がいるってことがわからないって言ってた子がいるんだ。一年生のときに同じクラスだったCちゃん。仮名じゃなくて志津って名前で皆にCちゃんって呼ばれてる。まぁ正確にはしーちゃんなんだろうけど何故か皆英語のCって雰囲気だよねって言い出して、Cちゃん。
別にそんなに変な子じゃないんだけど、わたしとむっちゃんとえっちゃんの三人がいつもどこでも仲良しだから、それを見ていて不思議に思うんだって。どうしても家に泊まりに行くほどの仲の良さってものが理解できないって、ちょっと悲しそうな感じで言うもんだから、わたしもどう答えていいかわかんなくて。
「Cちゃんねー」
そのことを思い出してむっちゃんに言うと、むっちゃんもそう言ってムズカシイ顔をした。
「でもほら、Cちゃんは頭良いし孤高の人だから」
「そうだねー」
Cちゃんはある意味で有名人だ。成績はいつも学年でトップ。間違いなく大学は東大とかに入っちゃって、将来はスゴイ学者とかになってノーベル賞を取るんじゃないかってぐらいに言われてる人。本当にスゴイんだ。先生なんか、内緒だけどできるものなら飛び級で大学に行かせたいって言ってるぐらいに。
「あんまり頭が良過ぎて回りに理解できる人がいないっていうかさ、同類がいないっていうか」
「同類か」
うん、そうなのかもしれない。
「じゃ、わたしとむっちゃんとえっちゃんは同類なんだ。同じ種類なんだ」
「むぅ。そう言われると何か悩む」
「何でだよー」
二階のわたしの部屋は六畳間で、シングルベッドのすぐ脇にむっちゃんの布団を敷いたらそれでオッケー。ご飯食べてお風呂入ったらもうパジャマに着替えちゃって、あとはだらだら、なんだけど、今夜はもうひとがんばりだ。
ティーコゼーと鍋つかみはあとちょっとで完成。完成したらかわいくラッピングして、明日のえっちゃんの誕生日にプレゼント。
「できたよー」
「え、もうちょっと」
「がんばれ」
「うす」
おばあちゃんが作ってくれた特製レモネードを飲んで、むっちゃんがわたしを見てる。もうちょっとだから待って。
「あのね」
「うん」
「Cちゃんはさ」
「うん」
「頭が良過ぎて私たちとかと、普通に話はできてもお泊まりなんかできないんだよ。それはつまり、同じ哺乳類でも種類が違うと思うんだ。ネズミと猫みたいに」
「ネズミと猫が仲良くしてる動画観たよ」
そういうんじゃなくて、ってむっちゃんが言う。
「同じ人間でも、生きる世界が違う人って確かにいると私は思うんだ」
真面目な話か。
「わかった。だからCちゃんのことは心配するなってことね」
「や、それもそうだけどさ。生きる世界が違う人同士でも繋がれる、同じ感情を共有して同じ感動を味わえるものがこの世にはあるんだよ」
「お?」
それは、ちょっと。
「ムズカシイ話になりますか睦美さん」
「難しくない。それは」
「それは?」
「音楽」
「あー」
なるほど。話をそっちに持ってきたのね。
「ちょっち待って。できた! オッケーだよね?」
針を抜いて、むっちゃんにティーコゼーを見せる。
「うん、できたできた」
完成!
「ラッピングするのは明日にしよう」
「そうだね」
机の上に置いておこう。針とか糸もちゃんと片づけたら、あとはごろごろしながらお話しながら寝るだけ。
「でね?」
「うん」
「音楽だよ」
あぁ、そうね。
「音楽は世界を繋ぐって話?」
「そう」
むっちゃんが大きく頷いた。それは、わかる。言葉がよくわかんない英語の歌でも、わたしたちは良い曲だ! って感動するし。
「言葉がない曲。えーと」
「インストゥルメンタル」
「そう、それ。それでも感動するもんね。それはアメリカ人でもフランス人でもアフリカ人でも中国人でも同じ」
「そう。だからね」
「だから?」
むっちゃんは、布団の上でぴょん、って少しヒザを浮かせてわたしを見た。
「花歌が歌を作ってうたったら、きっとCちゃんも感動してくれるよ。そうしたら、きっとCちゃんも花歌と仲良くなれるって思ってくれると思うよ。つまり、花歌の歌がその人の人生を変えることもできるかもって話」
「マジ?」
マジだ、ってむっちゃんが、ゆっくり頷いた。
「花歌の歌には、そういうパワーがあるの。お父さんのハルオさんがそうなのと同じように」
わたしの、歌に。
「それでね」
「うん」
「もし、花歌がその気になったら、私はもちろん協力するし」
「サックス吹くの?」
「サックスでもペットでも吹けるものなら吹くし、リョーチも協力してくれる」
「リョーチ」
リョーチ。今藤凌一。りょういち、がリョーチになってる。やっぱり小学校からずっと同じ学校で、同じクラスの仲良し。
「なんでリョーチ」
「だってリョーチは、バリMac使いで、デザインでもDTMでもなんでもオッケーなんだよ」
「あー、そっちね」
そうだった。リョーチはお兄さんの恭一さんがグラフィックデザイナーやってて、その影響でパソコンで何でもできるんだった。小学校の頃に自分でCG作っていたもんね。
「じゃあ、リョーチがわたしの歌うところを撮影して、それでミュージックビデオとか作ってくれるんだ」
「そうそう」
でもね、ってむっちゃんがこくん、って首を傾げた。むっちゃんがそういう仕草をするとすっごくカワイイんだ。本人は実はカワイイって言われるのがあんまり好きじゃなくて、むしろカッコいい女になりたいって言うんだけどそれはちょっとムリなんじゃないか。
そのむっちゃんのカワイイところ、実はリョーチは好きなんだよね。
わたしは知ってるよ。むっちゃんは知らないけど。そこはね、ちょっとね、内緒にしてるんだ。
いろいろあるんだ。本当に仲良しでも言えないこともある。
「そうかぁ、歌うかぁ」
「あ、でも」
慌てたようにむっちゃんが言う。
「昼間も言ったけど、別にそうしろって言ってるんじゃないからね? 私に言われたからじゃなくて、あくまでも花歌がそうしたいって思ったらって」
「うん」
それは、わかってる。
「わたしだって、やりたくないことはしないよ」
うたうことは、たぶん好きだ。小さい頃、お父さんが家にいるときにはいつも一緒にうたっていたのは覚えてる。
「お父さんがね」
「うん」
「帰ってこない、蒸発しちゃったことはもちろんちょっと怒ったりしたけど、そんなに困ってもいなかったんだ」
「それは、生活にってことだね」
「そうそう」
住む家はあるし、お母さんは仕事をしてる。お祖母ちゃんだってちょっと前までお習字やお花を教えていた。もともと家にはいない人だったから、寂しいとかそんなことも全然なかった。
「でもね、ひとつだけ困っていたことがあるんだ」
「なに」
「お母さんはね、実はね、ちょっと危険な人になってしまうんだ」
「なにそれ」
お母さんは、さっきも話してたけど真面目な人だ。とってもとっても真面目な人なんだけど。
「でも、お祖母ちゃんに言わせると、我が娘ながら、真面目なクセに突拍子もないことを平気でしてしまう人に変わってしまうことがあるんだ。それが、お父さんのこと」
「わかんない。どういうこと」
「ほら、高校時代に突然プロポーズされたって話したよね」
「聞いたね」
「そして家に連れてきたんだけど、明日さ、むっちゃん全然付き合いのない、たとえばD組の権藤くんにプロポーズされたら家に連れてくる?」
むっちゃんが眼を丸くした。
「何で権藤くん」
「だって、全然付き合いないけど、カッコいいし人気者でしょ」
バスケ部の権藤くん。確かにイケメンだし性格も良いらしいし、バスケ部でもエースっぽいらしい。
「権藤くんなら文句ないしょ」
「文句はないけど、連れて来ないよ。そもそもいきなりプロポーズってアブナイでしょ」
「ほら」
「何がほら」
「お母さんとお父さんの話を聞いただけだと、昔の話だから、スゴイ! 映画みたい! 昔はそんなことあったんだ! ってわたしたちは思っちゃうけど、現実にそんなことやられたら引くでしょ?」
むっちゃんが、口に手を軽く当てて、確かに、って小さい声で言った。
「引くね」
「それは今だからじゃなくて、お母さんの時代でもめっちゃ引くようなことだったんだよ。それをお母さんは平気で受け入れちゃったんだよ」
まぁ最終的にはそれはお父さんのとんでもなく飛び抜けた個性の為せる技ってことで許されたんだけど。
「お母さんは真面目だけど、そういう人なの。それでね」
声を小さくしてむっちゃんの顔に顔を近づけたら、むっちゃんも寄ってきた。
「大きな声じゃ言えないけどね」
「うん」
「前にもね、お父さんを見かけたって情報が入ってきたことがあったの。それをお祖母ちゃんやわたしが聞いてお母さんに伝えるならいいんだけど、お母さんが自分で入手した情報があったらね」
「うん」
「誰にも言わないで仕事も休んで、ぷいっ、て捜しに行っちゃうの」
「黙って?」
「黙って。言えばお祖母ちゃんは「そうかい」で済ますしわたしも「ふーん」って終わっちゃって、何にもできなくなっちゃうから、こっそり黙って行っちゃうの」
それを最初にやられたときには、ちょっとした騒ぎになってしまった。何たって、お母さんは区役所に勤める公務員。
「クビになっちゃうじゃん」
「そうなんだよ」
そのときは、詳しくは知らないけどなんとかなったみたい。
「そもそも、捜しに行くんならちゃんと有給休暇とか取ってわたしとお祖母ちゃんに言って、準備して行けば誰も文句を言わないのに、そういうことも何もかも頭から飛んじゃうみたいで」
むっちゃんが、思いっきり眉間にシワを寄せた。
「信じられない。あのおばさんが」
「でしょでしょ?」
娘のわたしが信じられないんだから、もう本当にびっくりした。
「おばさん、何て言ってたの? その大騒ぎになって帰ってきたときには」
「いや、もう、ただごめんなさいって。つい、って」
「つい、って」
お祖母ちゃんも驚いたけど、そういえば小さい頃にもそんなようなことがあったかもしれないって。
「普段真面目なだけに、まるでバネが外れるみたいにびょーん! ってどっかに飛んじゃうんだね。そしてどこでそのバネが外れるのかがまったくわからないの」
「そうかぁ」
「まぁ実は、そんだけ夫を愛しているってことなんだろうねって、美しい夫婦愛の話になっちゃうんだけどね」
あ、って言ってむっちゃんが手を打った。
「だから、今日はうたおばあちゃんが言ったんだ。晩ご飯のときに」
「そうそうそういうこと。わたしたちが誰かから聞いてお母さんに教えてあげるんだったらね、そのバネは外れないの」
「それね、たぶん、箍が外れるってことわざと勘違いしてると思うよ。そして少し意味が違う」
「たが、ってなに」
「たが、って、ほら樽を締めつけている金属の輪っかみたいなやつ。あれをたが、って言うの。あれが外れて自由に気楽に過ごすことを言うんだけど」
うん、ってむっちゃんは頷いた。
「でもおばさんの場合は、確かにバネが外れるみたいって言った方がぴったり来るみたいだね」
「でしょ?」
さすが花歌、ってむっちゃんがわたしの肩を叩いた。
「その独特の言葉の感覚もね、歌詞を書くときにはすっごくいいと思うんだ。でも、できればおもしろい歌詞よりカッコよかったり可愛かったりする歌詞を書いた方がいいと思う」
歌詞なんて書いたことないからよくわかんないけど、まぁおもしろい歌詞を書いちゃったらそれは芸人になっちゃうよね。
「そうか」
またむっちゃんが何かわかったって顔をした。
「花歌の、ときどきとんでもないことをしちゃうような性格は、てっきりお父さんから受け継いだって思っていたんだけど、お母さんからだったのか!」
や、それは自分ではわかんないけど。
毎日一緒にいるから、こうやってお泊まりしたからってずっと夜通し喋ったりしない。明日は日曜日だけど、むっちゃんは部活がある。
電気を消して、布団に入って、おやすみー、って言って。むっちゃんの寝つきのいいのは知ってる。すぐに、マジか! ってぐらいにすぐに寝息が聞こえてくるんだ。
わたしは、ベッドの上の天井を眺める。寝つきは悪い方じゃないけど、さすがにむっちゃんみたいに早くはない。
(歌か)
うたか、なんて考えちゃうと、お祖母ちゃんの名前みたいで顔が浮かんでくるけど、違う。
みんなに、聞いてほしい歌。
誰かに届く歌。
そんな歌を作って、わたしがうたうのか。
そうしたら、お父さんに届くかもしれないのか。
ミュージシャン。
宮谷ハルオは、自分で歌詞を書いて曲をつけて自分でステージでまるで踊るようにしてうたうミュージシャン。
ギターを弾くしピアノも弾けるし、大抵の楽器はできる。
ものすごい、才能あるミュージシャンだって、みんなが言っていた。そういう人が、わたしのお父さんだった。
いや、今もお父さんだけど。いないけど。
わたしが、お父さんと同じことをするのか。
全然考えたことなかった。
案外、わたしがステージでうたってるのをお父さんが観たら、聴いたら、「真似するんじゃないよ」って笑いながらどっかから出てくるんじゃないかな。
よし。
うたうか。
歌を、作るか。
それは別にお父さんに届けってわけじゃなくて、や、それならそれでもいいんだけど、たくさんの人に届くように。
Cちゃんみたいに、仲良くしたいのになれない人がもっと繋がれるように。
そんな歌を作ってみよう。
うたってみよう。
佐々岡幸一 四十五歳
犬や猫を相手にする獣医なんていう仕事はもちろん、動物たちへの限りない愛情がないとやってられない。
と、いうのは建前だ。
もちろん、動物が好きだというのはその入口にはあるが、限りなく愛情を注ぎ続けていたら獣医などやってられない。何せその愛情を注ぎ続ける動物たちは先にどんどん死んでいくのだ。
しかも、愛情を注がれずに死んでいく動物たちを目の当たりにすることがほとんど毎日のようにあるのだ。
医者は、相手にするのが人間であれ動物であれ、どのようにして死んでいくものたちに接するかを冷静に見極めなければやっていけない。精神を病んでしまう医者が多いのはそのせいだ。
だから、獣医師だって診療時間が終わってからもずっと動物のことを考えているわけじゃない。どんなふうに仕事のストレスを解消できるかによって、いい診療ができるかどうかが決まるんだ。
ただ病気を治すだけじゃない。この地域で人の都合で飼われて死んでいく犬や猫や他の動物たちの将来を考えていかなきゃならない。どうすれば、人間に飼われる動物たちが幸せな一生を送れるかを、啓蒙していかなきゃならない。それと同時に商売でもあるんだから、信頼できる獣医師を目指さなきゃならない。
ましてや二代目となると、初代である父の時代からのお馴染さんからの評判を落とさないようにしなきゃならない。
これでもけっこうツライんだよ。本当に。
だから、ジャズを聴く。今の生活でできる最高の環境で好きなジャズを一日の終りに聴いて、明日への鋭気を養う。むろん、ジャズじゃなくたっていい。ロックだってポップスだって、何だったら歌謡曲だっていい。
良い音楽だったら、それでいいんだ。
「って話、知ってた?」
日曜の夜。
晩ご飯を食べながら、睦美に花子さんのことを訊かれて、頼子と二人で顔を見合わせて頷いてしまった。親父は、おや、という顔をして頷いた。
「知ってたよ」
むしろ睦美が知らなかったのにびっくりだ。
「花歌ちゃんとそういう話はしてなかったのか」
「全然してなかった。お父さんの話はしない方がいいんだってずっと思ってたから」
「まぁ、そうか」
そうだろうな。我が娘ながら睦美は優しくて周囲に気を配る女の子だ。気遣いができる女の子。そういうふうに育ってくれたことは本当に嬉しい。死ぬほど嬉しい。そうでなくても高校生の女の子のあんなことやこんなことが山ほどニュースで流れてくる。ネットに溢れている。
もしも我が娘がそんなことやあんなことをしてたり巻き込まれでもしたら、本当にどうしたらいいかわからなくなる。
そういう意味では、花歌ちゃんが幼馴染みで親友っていうのもものすごくありがたいんだ。
あの子は、他人の大人の私たちから見ても、芯の強い真っ当な心を持った女の子だ。睦美に良い影響や温かい友情を与えてくれたとしても、悪い影響なんかこれっぽっちも与えないとわかる。
本当にわかる。
だからこそ、今の宮谷家の状況を何とかしたいと思ってはいるんだが。
「まぁ、だからお父さんもお母さんも、ハルオの噂をどっかで聞いたりネットで見たりしたら、真っ先にうたさんに報告するようにしてるんだよ」
うん、と、睦美は頷く。
「うたさんに任しときゃアいいんだ。あの人が手綱取っきゃあ、何とかなる」
親父が頷きながら言う。
「むっちゃんもあれだぞ。ハルオの野郎の噂を聞いたら、真っ先にうたさんに言うんだぞ」
睦美が、親父に向かって頷く。
「今度からそうする」
「花子さん、ネットはほとんどやらない人だから助かってるっていうか、幸いしたわよね」
頼子が言う。それは本当だ。もしも花子さんがネットをやっていたら、ハルオの噂を探しまくって仕事にならないんじゃないか。
「今もガラケーだもんね、おばさん」
「そうそう。まぁこれは言わなくてもいいんだが、スマホを持たせない方がいいんじゃないかと思うよ。言うなよ?」
わかった、と、睦美が頷く。
「あ、それでお父さん」
「何だ」
「お父さんのオーディオルームって、防音だよね」
「一応な」
完全なものじゃないが、それなりの音を出しても外に漏れないように作ってある。動物たちが音楽を聴いても騒いだりはしないが、ご近所の手前もある。
「それがどうした」
「そこで、ギターとか弾いても、サックスとか吹いても大丈夫だよね」
「別に問題はないけど、練習をするのか?」
もちろん、睦美が吹奏楽部のための練習をしてもいいようにはしてある。もっとも練習は学校でみっちりやってくるから、家でしたことはないんだが。
「違うんだ」
睦美が、ちょっと笑う。
「花歌と話したんだ。歌をうたってみたらって」
「歌?」
あら、と、頼子が言った。親父が、ほう、と声を上げた。
「あ、カラオケって話じゃないよ。花歌が作詞作曲して、自分でうたうの。そしたら、やってみるかなってその気になったんだけど」
花歌ちゃんが、うたう。
「すごいな」
「え? すごい?」
「すごいよ。ハルオの娘が、うたうんだぞ」
思わず頬が緩んでしまった。
「や、でも、今までそんなの考えたこともなかったからさ」
「それでもだ。あの子の歌が、声が素晴らしいのは知ってたさ」
「知ってたの?」
もちろんだ。ちょっと音楽に詳しいお父さんお母さんだったら、花歌ちゃんが小学校のときにうたったのを絶対に覚えている。
あれは、小学校五年生のときだ。音楽の授業を参観するときがあった。それを見に行っていたんだ。
もちろん、睦美の授業参観だったんだが、花歌ちゃんは同じクラスにいた。合唱をしていたんだが、音楽の先生は、名前は何だったかな、端岡先生だったかな。
きっとあの人は気づいていたのに違いないんだ。
花歌ちゃんの、十歳とは思えない歌唱力に。
その歌声と、センスに。
三人ずつで歌うパートを設けていたんだ。おそらく参観日だからと全員にソロをうたわせていたら時間も無いし、下手な子供が可哀相だ。だから、上手いこと三人組を作って、順番にうたわせてた。
花歌ちゃんは、名前を覚えていないが他の女の子二人とうたった。
図抜けていた。
声量があるとかじゃない。その独特の声質と、正確な音程が。きっとソロでうたわせたらその場にいたお父さんお母さん方は驚いていた。感動して涙を流す人もいたかもしれない。
それぐらい個性的で、図抜けていたんだ。
それから彼女の歌を聞く機会はなかったし、そもそもハルオが失踪してしまった。だから、誰もその話題には触れようとしなかったんだ。子供の心が傷ついているかもしれないんだからと。
「本当にその気になったのか花歌ちゃん」
「本当。でもね、ほら、あの家でギター弾いたりとかは、あんまり」
「そうね」
頼子が頷いた。
「音が響いちゃうし、何よりもうたさんや花子さんが、気にするかもね」
「そうだな」
父親と同じ道を歩くのか、と。いやそれに関してはきっと二人とも花歌ちゃんの人生なんだからと納得はするかもしれないが、積極的に応援するとは思えないし。
「家庭内にさざなみが立つかもしれないな」
「でしょう?」
睦美が大きく頷く。
「だから、お父さんのオーディオルームで、花歌が作詞作曲したり、そこで歌を練習したり、録音したりできないかなって。あ、録音とかはリョーチが全部するから、お父さんには面倒を掛けたりしないから」
そうか。
そういうことか。
「いいぞ」
「やった! ありがと!」
「でも、あなたはどうするの? 部活もあるから一緒にいられないでしょ」
頼子が言うと、睦美は、うん! とまた大きく頷いた。親父はお茶を飲みながら黙って話を聞いている。
「だからね、何曲か、花歌が納得できる歌ができるまでは、花歌一人であそこを使わせてほしいの。それは別にいいでしょ? 今までとおんなじだし」
「そうだな」
花歌ちゃんは帰宅部だ。そして普段からうちに遊びに来て、保護している犬猫の世話をしたりしてくれている。それは我が家としてもものすごく助かっているんだ。アルバイト代をあげたいぐらいだ。
「今までと同じように家に来て、そしてオーディオルームにこもるってわけだな」
「そういうこと。でね?」
睦美が、背筋を伸ばして、私たちを見た。
「もしも曲が完成したら、私は部活を辞めて、花歌と一緒に歌をアレンジしたり、練習したりしたいの。二人で一緒に音楽をやりたいの」
部活を辞めるのか。
「いいのか? 今まで一生懸命やってきたのに」
「いいの」
あれだ、と、親父が口を開いた。
「むっちゃんには、部活よりも花歌ちゃんと一緒に音楽をやることの方が大事なんだろうさ。そうだろう?」
睦美が、はい、と、はっきりと言った。
「それは、大丈夫なの? 今まで一緒にやってきた吹奏楽部の皆に迷惑をかけるんじゃないの?」
「そこは、大丈夫なようにする」
「そういえば、言ってたな。サックスのパートはいるんだって」
「そうなんだ」
自分より上手な後輩がいるから、抜けても平気なような話は前にしていた。
「別に嫌だから辞めるんじゃなくて、他に目的ができたからそっちをやりたいってことを、きちんと皆にも説明して、そして納得してもらって辞めるようにするから」
「あれだ」
親父だ。
「花歌ちゃんだって、自分で歌を作るなんて初めてなんだろう。ああいうもんは、そう簡単に納得できるものができるわけでないだろうし。今すぐにって話でもないだろう」
確かにそれはそうだ。
「じゃあ、まぁそれは睦美に任せるから」
「うん」
「ちゃんと、問題の起こらないようにしなさい。もしも部活の先生が親の話も聞きたいと言ってきたら、一緒に説明してあげるから」
「ありがと!」
嬉しそうに笑う。そもそも、部活は自分が好きだから、必要だと思うからやるものだ。もしも途中で他にやりたいものができたのなら、無理に続けるものでもない。
何よりも。
「睦美」
「はい?」
「お前、ひょっとしたらずっと花歌ちゃんと一緒に音楽をやりたいって思っていたんじゃないのか」
えへへ、と笑った。我が娘ながら、愛嬌だけはたっぷりとある子だ。親の贔屓目を抜きにすると決して美人とは言えないが。
「じゃあ、まぁ頑張りなさい」
頑張るものでもないか。今までと同じように、二人で毎日を楽しく過ごせばそれでいいんだ。
オーディオルームは八畳間だ。壁の棚は全部造り付けだし、オーディオといってもそんなに高価なものが置いてあるわけじゃない。スピーカーの前に置いてあるソファを片づければ、二、三人が並んで演奏するぐらいのスペースは取れる。
その辺は、実際にここで録音するぐらいに話が進んだら相談に乗ってやろう。とりあえずは、花歌ちゃんと睦美が二人でわいわいできるぐらいに、少しおっちょこちょいなところがある花歌ちゃんのために、大事なものはしまっておくぐらいでいいだろう。
ソファに座って、溜息をつく。
「どうするか、な」
頼子にも言ってないことがある。
〈犬狼都市〉のロウさんからの電話の内容だ。頼子に伝えて、うたさんに教えたのはほんの一部で、しかも大幅に改ざんしておいた。
もしも、花歌ちゃんの歌が完成したら。録音するとか言っていたから、きっとYouTubeとかで流すんだろう。
それを、ハルオが聴くことを期待するんだろう。
もしも本当にハルオが聴いたら、そして戻ってきたりしたら。
そのときに、ハルオが一人でないとしたら。
うたさんはどうするだろう。花子さんはどうするだろう。何よりも花歌ちゃんはどう思うだろう。
ロウさんは言っていた。
ハルオらしき男は、女連れだったと。
しかもその女性は、子供を連れていたと。
まるで、親子のように見えたそうだ。
「確かめておいた方がいいか」
こっそりと。
(つづく)