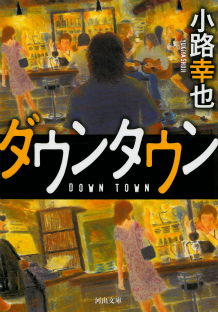花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 6
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.10.17

宮谷花子 四十二歳
仕事から帰ってきて、家に花歌がいないときはすぐにわかる。部屋の電気がついていないから。
あの子は開けっ広げと言うかなんというか、カーテンも閉めないでいることが多いから。庭の桜やカリンの木で道路からは見えないから良いようなものだけど、もう少し女の子らしい慎みとかそういうものを身につけてほしいって思うけど、まぁ今更しょうがないけどね。そういうふうに育っちゃったし、あの人の娘だし。
私の娘でもあるんだけど、性格は向こうに寄っていっちゃったかな。
玄関を開ける。カラカラと音がする。
「ただいま」
花歌がいれば返事があるけど、お母さんだけなら返事はない。音もなく現れて言うだけ。
「お帰り」
「花歌は、睦美ちゃんち?」
「そうだってさ。ギター抱えて行ったよ」
「そう」
「晩ご飯は豚肉の味噌漬けにしたよ」
「ありがと。いいね」
自分の寝室に入って、着替えて、そして廊下を歩いて洗面所に行って化粧を落とす。四十女でもきちんとお化粧をしないと、そして肌の手入れをしないと輪郭がぼやけてくるよ、っていうのはお母さんの口癖。
大人の女の化粧は他人のためじゃない。自分のため。
鏡を見ていると、確かにそうだなぁと思う。よく、男の皺は年輪で、渋みを表すと言うけれど、女の皺は渋みではなくて、甘みを増すためだって。
甘みというのは、歳を取った女にこそ必要なもの。なんですって。甘みなんて全然具体的なものじゃないけど、何となく言っていることはわかる。お母さんを見てるとそう思う。花歌なんかは若いから、おばあちゃんはカッコいい! ってただ言ってるけど、私ぐらいの年齢になってみるとわかる。お母さんは、どんどん輪郭を柔らかくしているんだ。
男の皺は刻まれていくけど、女の皺は面取りをしていく。大根の角を丸くするみたいに、皺の面取りをしていく。そうやって、全体に甘くなっていく。
確かに、お母さんは理想的な年の取り方をしていると思う。そこは見習わなきゃといつも思う。
そうやって、帰ってきて家で過ごすための身支度を整えているうちに、お母さんの晩ご飯の支度がちょうど終わる。
自慢することじゃないけれども、料理はちょっと苦手、というか、手際が悪い。それは、長年お母さんに料理をお任せしているからだ。
家事は嫌いではないしむしろ好きな方だけど、やっぱり働いていてこうやって家に母親がいると任せきっちゃうから。
「はい、できましたよ」
「はーい」
「いただきます」
「いただきます」
豚肉の味噌漬けを焼いたものとキャベツの千切りにトマトが一皿、昨日の残り物のカボチャの煮付けとたくわん、お豆腐にネギと胡麻油と醤油をかけたもの。お味噌汁の具はじゃがいもとたまねぎ。
「納豆もあるんだけど、どうしようかね」
「まだ大丈夫でしょ? 明日にしようか」
「そうかい」
年寄り二人の食卓は、こんなもので充分。お母さんが肉好きなので、わりと肉が食卓に上がることが多いかな。花歌もいるから、ちょうどいい。
もしも私一人だったら、肉よりは魚が中心になるかも。
台所のテーブル。四人座ると少し狭い。テーブルの上に調味料やティッシュケースやリモコンが置いてあるから、三人で食べるとちょうどいい。
花歌と、女三人の生活もそれがあたりまえになると、ちょうどいいんだ。たまに睦美ちゃんが加わっても、まだスペースがある。睦美ちゃんは大きくないから。
男の人が一人加わるだけで、ものすごく食卓が狭くなる。あの人もそんなに大きくはないんだけど、やっぱり存在感が違う。
その存在感がなくなって、もうなくなったことも忘れるぐらいに時が流れて。
壁際に置いた小さなテレビにはNHKのニュース。花歌がいないときには、お母さんはいつもニュースを見る。
「ギターをやってるね」
「花歌?」
お母さんが頷いた。
「ギターは前からやっていたよ」
「曲作りさ。随分と真剣に、睦美ちゃんと二人でやってるようだよ」
「そうみたいね」
うん、と、頷いてお母さんがお味噌汁を飲んだ。お椀を置いて、向かいに座る私を見る。席は、いつも同じ。私の隣が花歌。
「いいのかい?」
「いいって?」
「ろくでなしの父親と同じ道を行くんだよ」
「それは、止められないでしょ」
好きなことをやるのは、それが犯罪でもない限り親に止める権利なんかない。そもそもあの子の才能は、昔から気づいていた。
「心がざわつかないかい。せっかく何年も忘れているのに」
「忘れてなんかないわ」
忘れるはずがない。
「忘れてなくても、近づきはしなかったのに」
「しょうがないでしょう。人生に必要なのは、仕事よ。毎日ご飯を食べるための」
近づけるものなら近づきたいけど、できなかっただけ。
「失踪者は、七年とか経ったら死亡届を出せるとか聞いたけどね」
「残念ながら、本当に生きている可能性がないかどうかを調べなきゃならないのよ。免許の更新をしていないかとか、通帳に動きがないかとかね。そういう四方八方手を尽くしてからじゃないと無理なんですって」
それに、目撃情報だってあるんだから。
でも、わかっててお母さんも言うんだけど。
「お肉、美味しい」
「そうだね。少し高いのを買ったんだけど、やっぱり高いだけあるね」
「柔らかいし」
「これならまた買っても良いね」
お母さんの料理の腕が遺伝していれば良かったんだけどな。
「きっかけ、というものがあるじゃないかい」
「何のきっかけ?」
「花歌が歌をうたうって聞いたときにね、あぁこれもきっかけかなぁと思ってね。そろそろいろんなことに向き合う頃かなぁと思ったのさ」
「あの人のことに?」
そうだよ、ってお母さんは頷いた。
「最悪のことに対する準備をしなきゃね、って思ってさ」
お肉を飲み込んでから、お母さんが言う。
「最悪って?」
「私が死んだら、この土地と家の権利をあんたか花歌に移さなきゃならないんだよ。死ぬ前でもいいんだけど」
「あぁ」
そういう話か。
「まだ六十代でしょうお母さん」
「だから、準備の話だよ。六十代で惚けちまう人だっているんだよ」
「お母さんが惚けるなんて想像できないわ」
「私だって普通の人間だよ。いつ倒れるかわからない」
「それはそうだけど」
そんなことは、考えられない。依存しているって自分で思っちゃうのはあれだけど、確かに私は、四十代の子持ち女のくせに、いまだに自分の母親を頼っている。
何せずっと一緒に暮らしているんだから、それもしょうがないよって考えちゃうんだけど。
「あの男が突然帰ってきたら、迎え入れるだろう?」
一瞬迷ったけど、頷いた。
「たぶんね」
「それはいいさ。あんたたち夫婦の問題なんだからね。でも、もしもそのときに、あの男の隣に女でも子供でもいたらどうするんだい」
「それは」
そのときに考えるけど。
「可能性の話さね。あの男には今でも印税が入ってきているんだ。結構な額のね。そしてあの男が死んでもそれは続く。著作権継承という名目でね。それは、あんたの問題でそして花歌にも続いていくんだ。ここの土地と合わせてね」
思わず唇を尖らせちゃった。子供っぽい仕草。
「そうだね」
そういう問題。
「ややこしいよ、その辺の話は」
「そうだってね」
確かにややこしそう。
「何事もなきゃあ、私だってあと二十年ぐらい生きるかもしれない。あんただって四十年生きる。そんな老人二人を花歌に押し付けるのは不憫だろうさ」
「そういう話ね」
「そういう話さ。どこぞの小説に出てくるようなドロドロのね。その可能性がある以上は、考えておかなきゃねってことだよ」
離婚のことは、考えている。あの人が戻ってきて、離婚したいと言うならそれは受け入れるつもり。あの人の音楽という名前の財産なんかいらない。それは、いい。
でも、もしも、もうあの人が別の女と暮らしていて、それでなんだかんだとあるのなら。
「お母さん」
「なんだい」
「人生って、ややこしいね」
「今更だね。四十女の言うこっちゃないよ」
確かに。
「弁護士さん、いたよね。お母さんの友達に」
「いるね」
「そうなったら、いろいろ相談できるよね」
お母さんがゆっくり頷いた。
「面倒臭いことになる前に、話をするならしておいた方がいいね」
そうね、って頷いたら、お母さんは少し息を吐いた。
「私はね」
「うん」
「親馬鹿ならぬ祖母馬鹿だとは思うけれどね」
「なに?」
「花歌の才能を見抜いているつもりなのさ」
才能。
「あの子には、父親以上の才能のきらめきがある」
「あぁ」
そう思う。
音楽には素人の私だけど、その私でも、感じる。あの子の歌には。
「才能のきらめきが、輝きに変わって世の中を照らすかどうかはこれからのあの子の運次第だろうけどね。でも、あの子はきっと世の中を賑わすよ。〈宮谷ハルオ〉の娘、なんていう看板がない状態でもね」
「それで、〈宮谷ハルオ〉の看板がわかっちゃったら、余計によね」
「そうさ」
簡単に想像できる。どれだけ騒がれるか。
「そうなったらどれだけのハゲタカが寄ってくるかわかったもんじゃない。ましてやあの子は女子高生だよ」
「今の女子高生は最強のブランドよね。良い意味でも悪い意味でも」
「だから、今のうちだよ。花歌が本気になってうたう前に、ミュージシャンになる前に、できることはしておいた方がいい」
「具体的には、離婚ってこと?」
お母さんが、唇を歪めた。
「それも含めて、あいつを見つけなきゃ話にならないけどね」
その言い方に、何か含みがあるのがわかった。
「この間の話? 博多にいるって。何か進展というか、わかったことでもあったの?」
「進展は、別にないよ。ただ、それもきっかけだなって思ったのさ。そういうものはね、どういうわけか一緒に動き出すんだよ。いろんなものがね」
そう言われてみればそうかもしれない。
「睦美ちゃんがいるんだから、きっと花歌がうたいだしたらネットとかに上げるわよね」
「そうだろうね。最近の若者はあたりまえにそういうものを使いこなすんだろう?」
そう。そうなったら、簡単にあの人にも届くかもしれない。
「何か、大変だなぁ」
かぼちゃを口に放り込んだ。味が滲みていて美味しい。
「いつまでも放っておいたツケが回ってきたと思いなさいな」
「そんなつもりはないんだけど。ねぇ、お母さん」
「何だい」
「放っておいたツケで思い出したけどね。そもそもここの土地って本当にお母さんの名義になっているの?」
あら、って顔をする。
「なんだい今更。なっているよ」
「おばあちゃんはシングルマザーだったのに?」
「やめておくれよ今の言葉に直すのは。お妾さんでいいんだよ」
「そっちこそやめてよ。久しぶりに聞いたわお妾さんって」
「事実じゃないかい」
お母さんが苦笑いする。
「まぁ、今更だけど、我が家の女は基本的に男運がないんじゃなくて、男が逃げちまう強い女ばかりができるんだね」
「そうは思っていないんだけど」
思っていないんだけど、確かにそうらしい。
「それで行くと、花歌もいつか女一人になって生きていくのね」
「そうなるんじゃないかね。今のうちに彼氏に言っておいた方がいいね」
「カレシはいないけどね」
それは、本当に。
「あの子って、子供よね」
「まぁ、そういう面ではね」
あの子を好きになる男の子が可哀相になるぐらいに、興味がない。ないというより、そういう感覚を持っていないみたい。
それに関しては心配していないけれど。
今藤恭一 二十九歳
旅行してるな、って感覚を久しぶりに思い出した。
飛行機に乗るのも、随分久しぶりだった。根がインドアだし、自分の部屋にいた方が絶対落ち着くっていう人間だから極端にテンション上がったりはしないけれど。
「たまにはいいもんだよな」
ほとんど知らない土地の、知らない空港。ゲートを出た途端にそこは自分とはまったく関係のない街。
福岡空港ってこんなに街に近いところにあったっけ、って少し驚いた。
福岡は五大都市のひとつで、人口も多いから空港も遠いところにあるんじゃないかって勝手に思い込んでいたから。
それでも、街ってものはどこでもほとんど同じだなって思う。ビルが建ち並ぶ大きな都市はどうしても似たような顔になっていくんだろう。前に仕事で札幌に行ったときも、東京と変わらないじゃんって感じた。
違うんだな、って思うのはむしろ住宅街の方だ。沖縄に行ったときも札幌に行ったときも、建て方や家そのものにけっこう違いがあって、なるほど文化や風土っていうものは人が住むところに現れるんだって考えた。
そういう意味では、福岡、博多の住宅は東京と違いは全然ないように思う。
「そもそも博多って福岡市なんだよな」
東京でたとえば渋谷とか六本木って言ったときに「あぁ」って思うように、博多は福岡市の中の地域の名前だ。それが全国的に誰でも知ってるんだから、よほど古くからある特徴的なところなんだろう。
博多に持っていたイメージはそれぐらいだ。そして、太宰府天満宮は博多じゃなくて太宰府市ってところにあることを今回初めて知った。
今夜だけは博多駅近くのホテルを取った。
ハルオさんが現れたジャズ喫茶は、博多駅からタクシーで十分ぐらいのところある。その気になれば歩いていけないところじゃないらしい。マップでも確認したけど、のんびりと観光がてら歩いてもいい。
明日からは、水野の家に泊めてもらう。
水野はもともとこっちの人間で、東京の大学に進んできて、友達になった。だから、あいつの実家が博多にある。
今は福岡市内でひとり暮らしをしているけれど、話をしたら、もちろん〈ハルオ〉を捜すなんて言ってないけど、身内の問題で人捜しをしなきゃならないんだって相談したら、なら実家の俺の部屋に泊まれと言ってくれた。
部屋は高校時代のそのままになっているから机もベッドも置いてある。実家にはたまに泊まるから、荷物置き場にもなっていない。何よりも大学時代に、今はひとりで暮らしている水野のお母さんは東京に遊びに来たことがあって、そのときにご飯を一緒に食べたので俺のことを知っている。
それでも、友人の家で友人のお母さんと二人きりっていうのは何だと思ったけど、水野も俺がいる間は実家に泊まってくれる。
友人というのは、ありがたいって思う。そんなふうに感じるようになったのはやっぱり社会人になってからだ。
学生の頃は、ただの友達だったと思う。友達は友達で、それ以上でも以下でもない。社会人になって、友達ではない知人ばかりが周囲にいるようになって、それが上司や同僚や仕事先の相手で、友達は普段は周囲にいなくなる。それぞれがそれぞれの場所で、働いて生きる場所を作っている。
お互いに生きる場所を作って、初めて友達が友人になっていく。こいつとはきっと一生友人でいるんだろうなって、気づいていく。
☆
ジャズ喫茶だという〈犬狼都市〉は、三階建ての小さなビルの地下にあった。そういう店には入ったことがなくて、どんなものかと階段を降りて年期の入った木製のドアを開けると、煙草の匂いとコーヒーの香り、それに思っていたよりは大きくはない音楽。
レンガが壁になっているけど、全面じゃなくて床から適当な感じで配置されている。レンガのない壁は木だ。焦茶色の丸テーブルと、木製の椅子がかなり狭い感じで置かれている。ジャズライブもあるって聞いていたけど、たぶんいちばん奥の一段高くなったところでやるんだろう。壁際にアンプがあるし、布が掛けてあるのはたぶん、ドラムセットだ。
「いらっしゃいませ」
カウンターの向こうから、声を掛けてくる。他の店員さんはいないみたいだ。
マスターの名前は市川さん。ロウさんと皆には呼ばれていると先生に訊いてきた。何でもその昔にジャズライブで一緒になって意気投合した古い友人という話だ。
まっすぐにカウンターに向かうと、おや、という表情をこっちを見た。
「ひょっとして、東京からかい?」
「そうです」
「恭一くん?」
「はい、そうです」
黒縁の丸眼鏡。豊かな髭は白くなっているけど、頭はきれいに禿げている。人の良さそうな笑顔。
「ようこそ博多へ」
「お世話になります」
どうぞ、と、カウンターを勧められて、スツールに座った。お客さんはテーブル席に二組。
「お疲れ様だったね」
「いえ」
「コーヒー? 他にもいろいろあるし、もう五時を過ぎてるからお酒も出せるけど」
「いえ、コーヒーを。ブレンドで」
にっこり笑う。コーヒーはドリップで落すみたいだ。ロウさんは、ちらっとテーブル席の方を見た。離れているから、ここで話すことは聞こえないと思う。
「聞いたよ。佐々岡くんから。あの最後のツアーのポスターとかいろいろ作ったのは君だったんだって?」
「あ、そうなんです」
良かったよ、って微笑んでくれた。
「僕は本当に彼のファンだからさ。そんなスタッフの一人に会えて嬉しいよ」
「ありがとうございます。でも、本当にそのときだけだったんで」
「でも、ずっと知っていたんでしょう? 彼を」
「弟が、あの人の娘さんの同級生だったし、そもそも近所のおじさんでしたからね」
聞こえないとは思うけど、ハルオ、という名前は使わないで話す。ロウさんはコーヒーを落としながら、ゆっくり頷いた。
「この間ね、佐々岡くんに電話してからね、彼、もう一回来たんだ」
「来たんですか?」
また、うん、ってゆっくり頷いた。それがロウさんの癖みたいだ。それとも、コーヒーを落としているときには、ブレないようにそうなるのか。
「間違いないよ。じっくり顔を確かめたからね。他人の空似なんかじゃない。午後三時ぐらいだった。そのときは一人だったんだ」
僕の眼を見て言う。
「絶対に、彼だった」
「話したんですか」
いいや、って首を振って、くいっ、とそのまま動かして店の奥の方を示した。
「いちばん奥の、あの壁際のテーブルに座ってね。一人でコーヒーを一杯飲んで、そして帰っていった。ただね」
「ただ?」
「リクエストがあったんだ」
「リクエスト」
「コーヒーを持っていったらね。僕をちらっと見て『ウィリー・ネルソンはあるかい』って言うんだ。実はその声を聞いて確信したんだけど。やっぱり彼だって」
「ウィリー・ネルソン」
知らない名前だ。ミュージシャンの名前なんだろう。
「ジャズの人ですか」
ロウさんは苦笑いした。
「まぁ、ものすごく広い意味ではジャズと言ってもいいかもしれないけど、カントリーの大物だよ。重鎮だね」
カントリー・ソングか。
「あるんですか? カントリーも」
もちろん、ってロウさんは微笑んだ。
「カントリーも守備範囲だからね。何だったらヘビメタだってあるよ。それで『スターダスト』なら、って言ったら、それでいいって。聴きたいんだって、静かに言ってね。こっちを見ないで」
そのLPを掛けてあげると、コーヒーを飲みながら、じっとただ座って聴いていたらしい。
「よほどね、彼でしょう? って訊こうと思ったんだけど、それで二度と店に来なくなっても仕方ないと思ってね。かといって、ご覧の通り一人なんでね。店を出たときに追いかけることもできなくて」
「それでも、また一人で来たってことは」
ロウさんも頷いた。
「確実にこの近くに住んでいるのか、あるいはこの辺によく来る用事があるのか、だと思うんだよ」
「最初は、奥さんと子供みたいな人も一緒に来たんですよね」
「そう」
ただ、ってロウさんは少し顔を顰めた。コーヒーが落ちて、カップに入れて僕の前に置いてくれた。
「まぁ、この通り長い間客商売をしてるんでね」
年期の入ったお店。何年やっているかは聞いてなかったけど、間違いなくそうだと思う。
「その二人が夫婦だとか、恋人同士だとか、あるいは幸せそうだとか、何か問題を抱えていそうだ、なんていうのは、雰囲気が伝わってくるんだよね。見てればわかるって言うか」
「そうでしょうね」
そう思う。
「あの二人、正確には子供を入れて三人だけど」
「子供は、小学生ぐらいだったって聞きましたけど」
頷いた。
「低学年。おそらくは一年生か二年生。六歳とかその辺の子供だね。賢そうな女の子だったよ。大人しく椅子に座ってバナナジュースを美味しそうに飲んで、そこにあるけどケーキもひとつ食べてね」
六歳なら、ハルオさんが失踪してからできた子供でも充分通用するんだ。
「でもねぇ」
うん、って頷きながらロウさんが続けた。
「夫婦の感じがまるでしなかったんだ」
「そうなんですか」
「そう。別に仲が悪そうだとか、そんなんじゃない。話が弾んでいたかっていうとそうでもないけど、笑みを交えながら子供と話してもいた。ただ、どこかよそよそしさみたいなものが感じられてさ。ほら、そもそもさ」
手をぐるっと回した。
「自分で言うのも何だけど、こんな店にさ、子供連れで入ってくるってこと自体、少しばかり奇妙だと思わないかい?」
「そう、ですね」
そう言われてみればそうだ。
「普通は、子供連れの家族ならファミレスかハンバーガーだよ。わざわざこんな店で、煙草も吸えるのに来るっていうのはいまどき少しおかしい。夫婦揃って熱心なジャズファンってならわかるけどさ。そんなふうにも見えなかったし、そもそもハルオはジャズに詳しくはなかったよね?」
「聴いてはいましたけど、凄いファンってわけじゃなかったですね」
少なくとも、僕が知ってるハルオさんはそうだった。
「だからね」
ロウさんが、僕を見た。
「何か事情があって、こんな流行らないジャズ喫茶に来た。一応、人目を忍んだんだって思えば、ここに来たのも納得いく」
確かにそうだ。
「そして、彼と女性もね。少なくとも、親しい知人同士ではあるけれども、夫婦ではない。ドラマみたいに考えれば、シングルマザーの家に転がり込んで居候している中年男、なんていう感じに、僕は思えた」
「本当の家族ではない、と」
「そうだね。あくまでも僕の印象なんで、本当のところはわからないけど」
でも、そう考えれば頷ける話ではある。コーヒーを一口飲んで、それからジャケットから名刺入れを出した。
「僕の名刺です」
ロウさんが、名刺を受け取って少し離す感じで見る。
「この携帯に電話すればいいんだね」
「はい」
営業中は店にずっといてもいいとは聞いているけれど、ずっと張り込んでいるわけにもいかない。
「泊まりは、ずっとホテルかい? なんだったら、実はここには仮眠室みたいなものがあるんだけど」
「そうなんですか?」
微笑んで、頷いた。
「あそこの扉の向こうは、一応楽器置き場なんだけど、ソファベッドが置いてあるんだ。それこそライブに来た貧乏ミュージシャンのためにね。だから、いざというときには泊まるぐらいはできるよ。ちょっと歩くけど、自転車で行ける距離に銭湯もある」
それは、すごく助かるかもしれない。
「今日はホテルなんですけど、明日からしばらくは友人の家に泊まるんです」
「そうなんだ」
「ただ、友人の厚意に甘えるのも一週間ぐらいが限度だろうなぁと考えていたので」
ロウさんは、また微笑んだ。
「ここなら、いつでもいいよ。僕も、彼がどうなってしまったのか、本当に知りたいんだ。そして」
少し息を吐いて、真剣な表情をした。
「もう一度、彼の歌を聴きたいんだ。今の、彼のね」
(つづく)