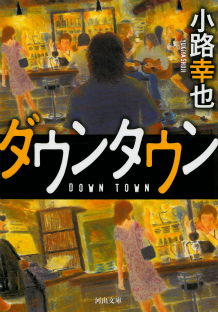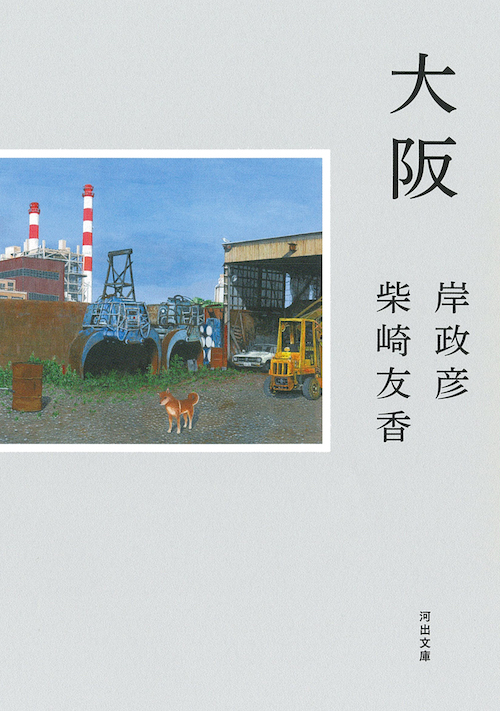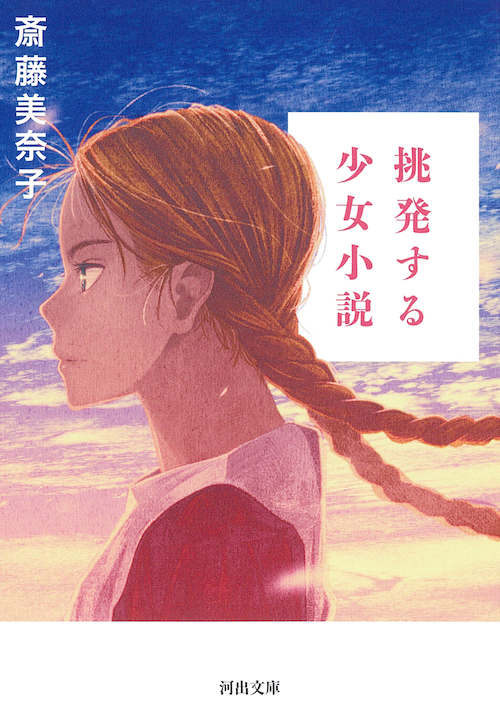花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 7
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.11.18

宮谷花歌 十七歳
信じてるの明日っていう日を
わらえなくても とどかなくても まもらなくても
みかけなくても ありえなくても わらえなくても
でも 信じてるの明日っていう日を
その日が来るっていうのを 眠ってても心臓が覚えているから
ずっとずっと ずっとずっと
リズムを刻んでいるの
明日のハートを ビートを
「どじゅ」
「なに、どじゅ、って」
「いや、どう? って訊こうとして嚙んだ」
嚙んじゃった。真剣にうたったあとに、なにか言おうとすると必ず嚙んじゃうのはどうしてなんだろう。
そう言ったら、うん、ってむっちゃんは頷いた。
「それだけ入り込んでるってことだから、いいと思うよ」
「そっか」
むっちゃんはわたしの書いた歌詞とコード譜を見ながら、うーん、って唸ってる。
「なに? まだヘン?」
「ヘンじゃない。どんどん良くなってる。ここさぁ」
「うん」
「ド頭ね、やっぱり〈でも〉って入れようか」
「わたしもそう思った」
「やっぱ入れよう。それから最後のところもっと言葉ほしいなぁ。音符が余っちゃってる感じがする」
歌い出し、ちょっと間が空いちゃう気がしてたんだ。さすがむっちゃん。
「そうだよね」
「それから、〈ハート〉と〈ビート〉はなんか、弱いかな」
「弱いかー」
「弱いっていうかなんか言葉としてあたりまえっていうか、悪くはないんだけど、もっと印象深い言葉を持ってきた方がメロディにも映えると思う」
「映えるかー」
「すっごくいいメロディラインなんだけど、言葉で損をしてる感じ? さらにそこんところで言葉を増やして、印象的なフレーズがあったらもっともっと届くと思う」
「届くんだよね」
歌詞って、やっぱりムズカシイ。
メロディは本当にいくらでも出てくるけど、そこに歌詞を乗せていくとどんどんメロディが沈んでいっちゃう気がする。
「そこだよね」
むっちゃんも頷いた。
「すっごくわかる。そのメロディが沈んでいく感覚」
「だよねだよね」
メロディラインだけならすっごく良くて、あぁここに歌詞がついたらどうなるんだろうって思って歌詞を書いたら、なんか、あれ? って思っちゃうんだ。
「やっぱりさ」
むっちゃんがマジな顔をした。
「うん」
「スゴイ人ってそこがスゴイんだよ。メロディに歌詞が乗っかっても、全然それこそ沈んでいかないで、メロディと歌詞が一体化しちゃうんだよね」
「そうなんだよねー」
本当にそう思う。歌を真剣に作り始めてから、お父さんがスゴイっていうのがどんどんわかってくる気がしてる。
「なんとなくだけどね」
「うん」
「お父さんが曲作ってるところを、覚えてるんだ」
「そうなんだ」
うっすらとだけど、覚えてる。わたしが遊んでいる横で、急にお父さんがギターを取り出して弾きながら、コード押さえながら歌い出してそれを紙に書いていって、それからそれがどんどん言葉が溢れてきて、歌になっていくところ。
「それ、なんの曲だったか覚えてるの?」
「〈スリック・スラック・スティップ〉だと思う」
「あれかー」
むっちゃんが、むぅ、って声を出した。
「そんな簡単に作ったのか。花歌が遊んでいる横で」
「だと思う」
「あれってものすごく繊細なメロディで、アレンジなんかも高度なことやってるんだよね。変調の嵐で」
「そうなんだ」
その辺はわたしにはわかんない。むっちゃんは吹奏楽やってて、ピアノも弾けるから楽譜も書けてそれこそ曲のアレンジなんかも自分でできちゃう人だからわかるんだろうな。
「天才なんだろうなー、我が親父さんは」
「花歌も天才だよ」
「えへへ」
「えへへじゃなくて、私はそう思ってるよ。そしてね」
「うん」
「なんとなくなんだけど、お父さんの曲調に少し似てる」
「そうなん?」
「そうなんよ。どこがどう、って指摘はできないんだけど、コードの流し方とか、思わぬところで上がっていくメロディの流れとか、なんとなく似てる」
「遺伝なのかな」
「そうなのかもね」
トントン、ってドアがノックされて、はーい、って二人で答えたらドアが開いて、リョーチが入ってきた。
「おう、よく来た」
「お前の家じゃない」
軽く手を上げて、カバンを下ろした。
「何持ってきたの」
重そうなカバン。
「カメラだよ」
「カメラ」
「今のうちに練習風景とかそういうの撮っていく。二人は勝手にやってていいよ。オレのことは無視して」
「ムシしていいの? カンペキに?」
笑いながら言ったら、リョーチが顔を顰めた。
「たまには声を掛けてくれ」
むっちゃんと二人で笑った。優しくないリョーチ。でも、実はすっごく優しいリョーチ。さっさと準備して三脚立ててその上にカメラを付けて、ファインダーを覗いて。
「普通にやってろよ。ただ撮ってるだけだから」
「わかった」
「でも今はちょっと休憩」
言ったら、リョーチはファインダーを覗いたまま頷いた。
「休憩のところを取ってるから」
「リョーチ、そのジャケットカッコいいね。買ったの?」
なんか、ちょっとリョーチらしくない格好してる。
「いや、貰い物。アニキの」
「お兄さんのか」
リョーチのお兄さんは、恭一さん。
「お兄さん、元気?」
むっちゃんが訊いたら、リョーチがこっちを見て、頷いた。
「まぁ、元気だ」
それから、ちょっと首を捻った。
「あのさ、花歌」
「なに」
「これ、完成したらお前のサイトを作ってどんどんアップしていくけどさ」
「うん」
唇を尖らさせた。
「お父さん、〈ハルオ〉の娘だってそこに書いちゃっていいのか?」
そこか。やっぱりリョーチも考えていたか。むっちゃんと顔を見合わせた。
「どうしようかって花歌とも言っていたんだけど、リョーチはどう思う?」
「オレは花歌のしたいようにするだけだよ。でも」
「でも?」
わたしが訊いたら、リョーチが少し考えてから言った。
「これはオレが思ったんじゃなくて、アニキが言ったことだけどさ」
「恭一さん」
うん、ってリョーチが頷いた。
「あいつ、広告のデザイナーだからね。広告って、わかるだろ? 宣伝のプロなんだよ」
「それぐらいわかってるよ。CMとかも作るんでしょ?」
「そう。つまり、広告のプロってことは、音楽だって同じなんだ。ミュージシャンをどうやって売り出すかってことも、あいつはわかってるんだ」
「なるほど」
確かにそうだね。
「だから、そこは〈戦略〉なんだって」
「せんりゃく?」
そうだよ、ってリョーチはわたしを見た。
「お前が、音楽をやることを、本気でやろうとするかどうかを、まず決めさせろってアニキが言ってた」
「本気」
「たとえば、お前がアルバムを作ってCD作ったりダウンロードで販売したりしたら、お金が入ってくるわけだよ。そうだろ?」
「そうだね」
「そのお金って、お前だけのものじゃなくなるんだよ。アレンジをする睦美にだって、お前のサイトを作るオレにだって、ギャランティを払わなきゃならなくなるんだ。それが、〈ミュージシャン〉として本気でやることなんだってアニキは言ってた」
むっちゃんが、唇を真っ直ぐにして、小さく頷いた。この顔は、わかっていた顔だ。
「そんなの、ぜんっぜん考えていなかった」
「だろ? 考えなくてもいいんだ。オレも睦美もお金を貰おうなんて思ってないからさ。でも、もしも、お前が本気でやったらゼッタイにお金が入ってくる。千円でCD売ったら、きっと十万枚も売れる。千円で十万枚売ったら幾らになるか計算してみ?」
「えーと」
計算した。
え。
「いちおく?!」
そうだ、ってリョーチが頷いた。
「冗談でしょ?」
「冗談じゃないんだよ花歌。マジなんだ。オレも睦美も真剣にそれは思ってるぜ。だよな?」
リョーチがむっちゃんに言ったら、むっちゃんも頷いた。
「まだ言わなくていいって思ってたけど、そのとおりなんだよ花歌」
「マジか」
「マジなんだよ。これはね、聞いてね?」
「聞く」
「ただYouTubeにアップして楽しむだけでもいいんだけど、ゼッタイに、ゼッタイに、プロの音楽関係者が騒ぎだすって私も確信してるんだ」
「騒ぐの?」
「騒ぐよ。そして、うちでやらないかって言ってくる芸能事務所や音楽事務所はゼッタイに出てくる。そのときにどうするかは、決めておいた方がいいとは思う」
そんなこと、決めるのか。
「秘密にすることももちろんできるさ。顔は隠して撮影することだってできる。まぁ知り合いにはバレちゃうかもしれないけど、無視してればなんとかなる。そのまま、なんにもしないで消えちゃうって思うんならそれでもいい。それなら〈戦略〉は必要ない」
「でも、わたしがずーっと音楽をやっていくって決めたんなら、最初っから〈戦略〉が必要ってことだね?」
「そういうことだ」
「その〈戦略〉の第一歩が、わたしがお父さんの娘だってことを、言うか言わないか、なんだね?」
「その通り。少しは頭回るようになったじゃん」
「ぶー」
「その〈戦略〉は、リョーチが考えるの?」
むっちゃんが訊いたら、リョーチはまさか、って首を横に振った。
「オレにそんなこと考えられるはずないだろ。アニキだよ」
「恭一さんが?」
リョーチが頷いた。
「もしも、花歌が本気で音楽をずっとやってくって思えたんなら、最初のアドバイスぐらいはできるから言ってこいって。もちろん最初のアドバイスはサービスでやってやるって」
「サービス」
「アニキは一応プロだからね。プロはタダで仕事なんかしない」
そうか、プロはタダで仕事はしないのか。それは、そうだなって思う。考えたこともなかったけど。
「それは、どうしても決めなきゃいけないことなんだね」
言ったら、リョーチは頷いた。
「少なくとも、決めたくないんだったら、〈ハルオ〉の娘だってことはずっと隠さなきゃならない。顔のないシンガーのままだね」
顔のないシンガーか。それはそれでちょっとカッコいい気もするけど、それじゃダメなんだと思うな。
「むっちゃん言ったよね」
「なにを?」
「わたしが歌ったら、ゼッタイにお父さんに届くって」
「言った。それはもうゼッタイに思ってる。間違いなく、お父さんに届く。だって、花歌の歌はそれだけのパワーがあるんだもん」
「わたしが顔を隠していても届く?」
「届くな」
リョーチが言った。
「ハルオさんがわからないはずがないってオレは思う。これは、花歌の歌だってゼッタイにわかる」
「私もそう思う」
「じゃあ」
うん。決めた。
「お父さんに届いたときに、顔を隠していたら恥ずかしいもんね。だから、最初っから〈ハルオ〉の娘だよー、って歌うよ」
そう言ったら、リョーチが思いっきり頷いた。
「よし」
カバンからメモ帳を出してきて、開いた。
「なにそれ」
「アニキから、言われてた。もしも花歌が最初っから〈ハルオ〉の娘だって言ってうたうんだったら、始める前にこれだけはやっておけってことが書いてある」
「恭一さんすごい」
さすがプロだね。
「なにが書いてあるの? なにをするの?」
むっちゃんが訊いた。
「簡単なこと」
リョーチが、なんか適当な方向を指差した。
「花歌の家で、家族会議」
「家族会議?」
「おばあちゃんとお母さんに了解を貰えって。オレらは未成年だし、〈ハルオ〉の娘だってことを言うなら、母親の許可がゼッタイに必要だって」
なるほど。確かにそうだね。
今藤恭一 二十九歳
初日は、外れ。
まぁそんなに期待はしてなかった。これでいきなりハルオさんに出会ったりしたら、なにかの罠かと疑ってしまう。
ロウさんは店の終わる頃にちゃんとメールをくれた。
〈今日はお疲れ様。また明日〉って。
こういうの、もちろん人柄もあるんだろうけど、客商売としては重要なんだろうなって思う。
ホテルで朝ご飯を食べた。
最近のビジネスホテルのモーニングはスゴイって、前にテレビでやってるのを観たけれど、確かにここも凄かった。メニューが充実していた。
滅多に旅行なんかはしないから、ホテルに泊まるっていうのもあまりしないことだけど、こんなに安くて便利で充実したモーニングで儲かるんだろうか、と、心配してしまう。
フリーでやってると、景気の動向っていうのはどうしても気になるんだ。気になるどころか、グラフィックデザインなんていうのは基本〈広告〉だから、世の中の景気に直結する。
僕は知らないけど、バブルっていうのが弾けたときには本当に広告業界は死にそうになったそうだ。冗談抜きに首を括った人がたくさんいたとも。
来年は三十歳だって思うと、自分の将来なんかも考えたりする。
この先もずっと俺はパソコンの前に座って、デザインをやっているのかって。それはもちろん好きでやっていることだからいいんだけど、やりつづけるためには、なにをしたらいいのかって。
営業努力だ。自分のデザインがどれだけ素晴らしいものかを世に訴え続けて、新規クライアントをずっと獲得し続けなきゃならない。そうしないと、生きていけない。実際問題、フリーになった先輩でいつの間にか業界から消えてしまった人なんか、ごまんといるって話だ。
(そういう意味では)
ミュージシャンも、たぶん同じなんだと思う。
売れなきゃ話にならない。ファンをたくさん獲得してアルバムを買ってもらって、それをずっと続けなきゃならない。
でも、そんなことを何十年もできる人なんか、本当にごくごく僅か。ぱっと思いつくのは山下達郎とか桑田佳祐とか松任谷由実とか、本当にそれぐらいじゃないのか。
〈ハルオ〉は消えてしまった。
凌一の話では、まだ事務所とかレーベルとかの契約は切れていなくて、そして印税とかそういうのはしっかり入ってきているそうだ。その辺は花歌ちゃんのお母さんが管理しているらしい。カラオケの印税だけでもバカにならない数字になっているとか。
それは、いいよな。
花歌ちゃんだってまだ高校生だ。ひょっとしたら大学とか行くかもしれない。お母さんも公務員として働いているから、そういう面では心配いらないのかもしれないけど。
心配なのは、ハルオさんだ。
失踪したときには、なにも持っていかなかった。本当に身体ひとつで、行方不明になっている。どうやって生活しているんだろうか。
どう考えてもあの人に生活能力があるとは思えない。まさかコンビニでバイトもできないだろうし、肉体労働も無理だ。
(そうだよな)
なんとなく、明日は我が身、なんて思ってしまう。捜しに来たのに自分の将来のことを考えるなんて思ってもみなかったけど。
☆
昼前にホテルをチェックアウトして、水野の実家に向かった。〈犬狼都市〉のロウさんとはハルオさんが現れたらすぐに連絡が貰えるようになっている。調べたら水野の家からでもタクシーを飛ばせばそんなに時間はかからない。お金はかかるけど、しょうがない。先生がスポンサーになってくれるんだから、そこは甘えておくつもりだ。少なくとも俺よりはたくさん稼いでいるから。
水野のお母さんは、しっかりと俺のことを覚えていてくれた。
「立派になっちゃってねぇ本当に」
「いえ、とんでもないです」
近くに小さな川があって、普通の落ち着いた住宅街の一軒家。猫が二匹いた。スズメとカラスって名前が可笑しかった。確かにそんな色合いなんだ。焦げ茶の猫と黒猫。
水野はもちろんまだ仕事中。終わったら来てくれる。お母さんと二人きりで時間を過ごすのもなんだから、荷物を置かせてもらったらすぐに〈犬狼都市〉に行こうと思っていたんだけど、お母さんは昼ご飯ぐらい食べていけと。
すっかり忘れていたけど、世話好きのお母さんだった。まぁ、話しやすい明るいお母さんだからいいんだけど。
「なんだっけ? グラフィックデザイン?」
「そうです」
「すごいねぇ、そんな才能があったんねぇ」
「才能というほどのものでもないです」
お母さん、美江さんというんだ。水野とは全然似ていないで、水野はお父さん似だそうだ。そのお父さんも、水野が大学卒業してすぐに病で死んでしまったんだ。葬式に行けなかったけど、その他の友人と連名でお花を贈った。
「お母さんは、ずっと家にいるんですか?」
キッチンのテーブルで差し向いで、お茶を飲みながら話していた。お母さんは、とんでもない、って手を振って大きく笑った。
「あたしなんか家にいたらおかしくなっちゃうよぉ。あちこち出回っているわー」
きっと俺が相手だから標準語で話してくれているんだろうけど、ところどころイントネーションが違う。たぶん博多弁なんだな。
「まぁね、幸いあん人が残すもん残してくれたから、贅沢しなきゃやってけるし。雅行もあれでね、気を遣ってくれるのよ。たまにお金を入れてくれたりして」
「そうなんですか」
水野の名前は雅行だ。
「ところでね?」
お母さんがつい、と身を乗りだして声を潜めた。
「はい?」
「なんにも訊くな、って雅行に言われたけどね?」
「はい」
「人捜しだって?」
「そうなんです」
うん、と、頷きながらお母さんは顔を顰めた。
「身内の話ってことやけどぉ」
「はい」
「もしもよ? もしも本当に手助けが必要なら、あたし興信所の所長と同級生よ? タダで捜せって言えるわよ?」
「いや」
苦笑いでごまかす。
「ありがたいですけど、そんなに大袈裟な話にはしたくないんです。本当に身内のことで」
「そうお?」
美江さんの眼がきらりと光ったような気がした。
「あたしね、覚えてるんよ。今藤くんが大学のときに〈ハルオ〉の仕事をしたこと」
「あ、はい」
ちょっと驚いた。確かにそれは覚えているかもしれない。あの頃はさんざん皆の話題になったから。
「それでね? これでも〈ハルオ〉のそれなりのファンなのよ」
「そうだったんですか」
「アルバム全部持ってるもの」
全部。それはそれなりじゃなくて、かなりのファンなんじゃないか。
「あたりまえだけど、彼が失踪してるのも知ってる」
「そう、ですね」
答えながらこれはマズイと思っていた。どこまで追求されるんだ。
「ピンと来たのよね。ひょっとして〈ハルオ〉を捜しに来たんじゃないかって。あ、言わなくてもいい。別にどうしてもってわけじゃないから。おばさんの好奇心だから。そしていつまでだっていたっていいんだからね? そこは心配しないで」
「ありがとうございます」
「でもね、でもね?」
美江さんが、さらにぐっと身を乗りだしてきた。
「今、言ったわよね? 興信所の所長が同級生だって」
「はい」
「もう私も独身だから言っちゃうけど、元カレだったの」
「マジですか」
「マジよマジ。でも雅行には言わないでね。別にまた会ってるわけじゃなくて、クラス会とかで会ってるだけだから。LINEのグループもあるし」
そうなのか。LINEやってるのか。
「その人がね、前に言ってたの」
「なにをですか」
美江さん、にやっと笑った。
「失踪してる〈ハルオ〉は、博多にいるんじゃないかって。見かけたんだって」
これは、びっくりした。
「本当に?」
「本当よ。こんなことで息子の親友を騙してどうすんのよ」
思わず唸ってしまった。
でも、ありえないことじゃない。現にロウさんは店に来た〈ハルオ〉を〈ハルオ〉だと認識した。
もしもハルオさんが長年この街に、博多に住んでいるんだったら、他に見かけた人がいたって不思議じゃない。
ましてや、その相手が人捜しのプロである興信所の所長だとしたら、そういう眼で見てあれは〈ハルオ〉だと確信したのかもしれない。
「その人は、どうしたんですか。ハルオじゃないかって思っただけなんですか」
美江さん、うん、って大きく頷いた。
「興信所の所長だからって、怪しい人じゃないのよ。ちゃんとした男。それは保証する。でもね、本当に好奇心だけで、お得意の尾行とかもしたんだって。徹底的にやったわけじゃないから、ひょっとしたらこの辺に住んでいるのかっていう程度にしか調べていないんだって話なのよ」
もちろん、って美江さんは続けた。
「誰彼区別なくこの話をしてるわけじゃないよ? 昔恋人だった私が〈ハルオ〉のファンだし、信用できるからって話の種に教えてくれての。私だって誰にも言ってないわ」
一度言葉を切って、溜息をついた。
「人生、いろいろあるわよね。踏み込んじゃ行けないところもあるわよ。だから、〈ハルオ〉には復活してほしいけど、本人が望んで今の暮らしをしているんだったらそっとしておこうってのが人情よね。でも」
でもよ、って俺を見る。
「今藤くんみたいな人が捜しに来たってことは、当然〈ハルオ〉にだって家族がいるのよね。その家族の代理みたいな感じじゃないかって思ったのよおばさんは」
頷いてしまった。
そういえば水野はいろんな意味で頭の良い男だった。よく頭の回る人間なんだ。それはこのお母さんから受け継いだものなのかもしれない。
「どう?」
美江さんが言う。
「もしも、このおばさんのおせっかいが当たっているんだったら、その興信所の所長さんにここに来るように言ってもいいんだけど?」
「お願いします」
大丈夫だ。俺は水野を信頼しているし、お母さんもきっと信頼できる人だ。
なによりも、こんなふうに繋がるのって、運命以外のなにものでもないじゃないか。
(つづく)